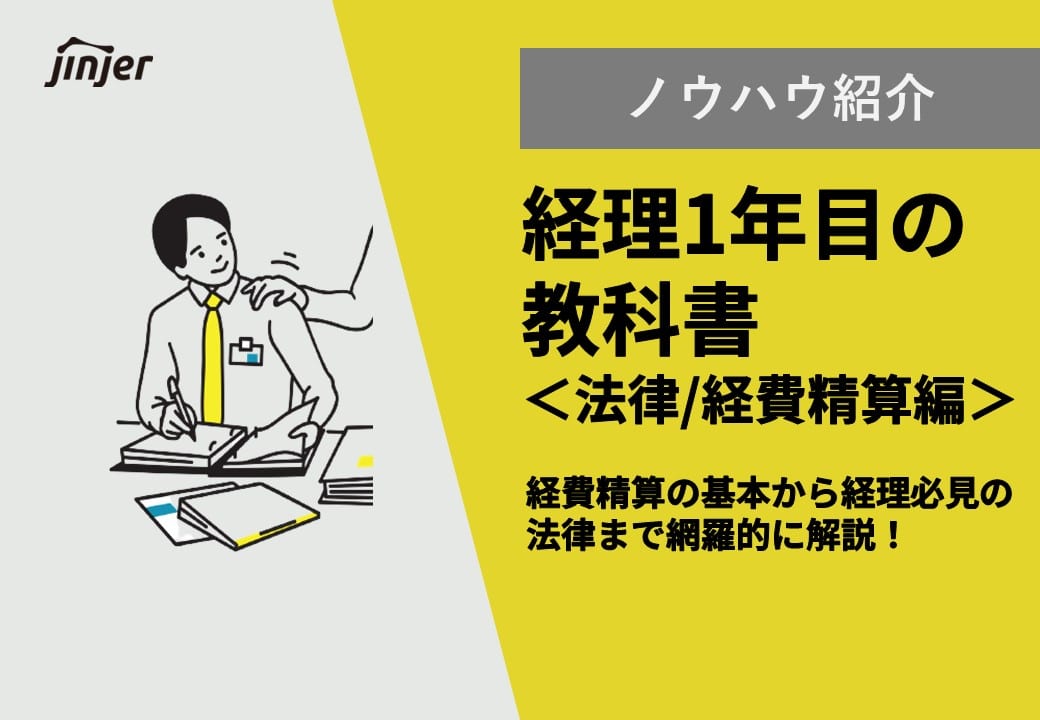法人税の繰越欠損金とは?控除によるメリットや適用要件も解説
更新日: 2024.7.2
公開日: 2022.8.17
OHSUGI

法人税法上の課税所得がマイナス時の金額を欠損金といいます。
繰越欠損金とは赤字を次の事業年度に繰り越すことで、所得が黒字のときに相殺し、当期の課税所得を低く抑えることが可能です。
本記事では、法人税の繰越欠損金の概要や控除を受けるメリット、適用条件、税効果会計について解説します。
関連記事:法人税とは?特徴や対象となる法人、種類や計算方法を紹介
「法改正に関する情報収集が大変で、しっかりと対応できているか不安・・・」
「仕訳や勘定科目など、基本的なこともついうっかり間違えてしまうことがある」
などなど日々の経理業務に関して不安がある方必見の資料です。
経費精算は日々発生するため、流れ作業のように処理することもあるでしょう。しかし、経費精算業務は、社内規程や関連法に対応した細かいルールが存在するため、注意が必要です。
また直近の電子帳簿保存法やインボイス制度など毎年のように行われる法改正に対して、情報を収集し適切に理解する必要があります。
そこで今回は、仕訳や勘定科目などの基礎知識から、経理担当者なら知っておきたい法律知識などを網羅的にまとめた資料をご用意しました。
経理に関する基本情報をいつでも確認できる教科書のような資料になっております。資料は無料でダウンロードができ、毎回Webで調べる時間や、本を買う費用も省けるので、ぜひ有効にご活用ください。
目次
1. 法人税の繰越欠損金とは課税所得が赤字のときの金額のこと

欠損金とは、法人税法上の課税所得(利益)がマイナス(赤字)のときの金額のことです。
青色申告の承認を受けている法人では、この欠損金を一定期間繰越して課税所得が発生(黒字)したときに相殺できます。
上記の仕組みを法人税の繰越欠損金制度といいます。なお、住民税や事業税といった地方税には適用されません。また繰越欠損金が減少した際には修正申告書の提出が必要です。
関連記事:法人で赤字が出た際に免除される税金・されない税金は?赤字決算での法人税の取り扱いも紹介
2. 法人税の繰越欠損金で控除を受けるメリット

赤字を持ち越して、将来課税所得が黒字となったときに相殺できれば、その事業年度の法人税納税額を通常支払うよりも低く抑えることができます。
例えば、繰越欠損金の額が200万円あったとします。
その年度の控除前の課税所得が150万円だった場合、繰越欠損金分の200万円のうち、150万円分を損金に算入できます。結果、その年度の課税所得金額は0円となります。
上記の例で繰越欠損金制度が使えなければ、今まで赤字が積み重なっていたとしても、その年度の所得150万に対して実効税率をかけて求めた法人税の支払いが必要となります。
このように、欠損金を繰り越せるか否かで、企業の法人税負担は大きく異なります。
このように、会計には「知っていることで有利になる制度」が多くあります。そのため、経理担当者は日々、法改正や省庁の発表を確認する必要があるでしょう。また、これらを理解するためにも、現行の制度や法律に関する知識を持っておく必要があります。とはいえ、「どこから手を付けたら良いのかわからない」「条文は堅苦しいので頭に入ってこない」という方も少なくありません。
そのような方には、当サイトで無料配布している「経理1年目の教科書」がおすすめです。本資料では、経理の基本業務である経費精算や仕訳方法、経理担当者が押さえておくべき法律について解説しています。経理初任者の方が必ず持っておきたい1冊となっているので、ぜひこちらから無料でダウンロードしてご覧ください。
3. 法人税の繰越欠損金の適用条件・期間・限度額

法人税の繰越欠損金制度を適用するためにはいくつかの条件があります。
また、繰越できる期間は事業の開始年度によって異なる他、事業規模によって繰り越せる限度額も異なります。
3-1. 適用条件として欠損金発生年度に青色申告が必要
繰越欠損金は売上などの影響により、事業年度単位で変動する法人の税負担を均一にするために導入された制度です。そのため、制度を利用するには複式簿記による記録が必要な青色申告で確定申告をしなければいけません。
会社設立時に青色申告を適用するためには設立から3ヵ月以内に、所管の税務署に「内国普通法人等の設立の届出」と「所得税の青色申告承認申請書」を提出しなければいけません。
すでに設立済みの場合は、青色申告をしようとする事業年度開始日の前日までです。
期日を過ぎてしまうと、翌年度からの適用となる恐れがあるため、早めに手続きしましょう。
3-2. 以降は確定申告の継続が条件となり白色申告も認められる
なお、欠損金が出た年度に青色申告をしていれば、その後の確定申告が白色申告であっても繰越控除規定が適用されます。ただし、損金発生時の青色申告以降、確定申告をしていない法人は繰越欠損金制度の対象とならないため注意しましょう。
また、申告後の帳簿類は保管が必要です。
3-3. 繰越期間は10年までだが事業開始年度により異なる
平成30年4月1日以後に開始する事業年度に生じた欠損金を繰越できる年数は10年間までです。上記以前に開始する事業年度に生じた欠損金の繰越期間は9年までとなります。なお、2年以上連続で繰越欠損金が生じている場合、古い年度のものから順次算入します。
3-4. 控除限度額は資本金により違いがある
繰越欠損金の控除額は資本金により以下の違いがあります。
(1)資本金1億円以下の中小企業
欠損金は全額繰越できます。
また、資本もしくは出資を有しないものや公益法人、協同組合、人格のない社団なども同様の扱いです。
(2)資本金1億円以上の大企業
平成30年4月1日以降を事業開始年度とする大企業では、課税所得(繰越控除前)の50%が控除限度額です。
上記以前に事業を開始している場合、事業開始年度によって以下のように控除限度額が異なります。
- 平成24年4月1日~平成27年3月31日開始事業年度:80%
- 平成27年4月1日~平成28年3月31日開始事業年度:65%
- 平成28年4月1日~平成29年3月31日開始事業年度:60%
- 平成29年4月1日~平成30年3月31日開始事業年度:55%
また、更生手続きを申請した法人や新設法人など、一定の要件を満たす場合は事業年度の考え方が異なります。
詳しくは以下の参照もご確認ください。
参考:No.5762 青色申告書を提出した事業年度の欠損金の繰越控除|国税庁
4. 法人税の繰越欠損金の税効果会計

会計上の利益と税法上の利益は、以下のとおり計算方法に違いがある点に注意が必要です。
- 会計上の利益(税引前当期純利益)=収益-費用
- 税法上の利益(課税所得)=益金-損金
税法上の利益は「課税所得」といい、法人税を計算するベースとなりますが、会計上の利益とは異なるものです。このように、計算上生まれる差を埋めるのが税効果会計です。
繰越欠損金が発生した時点では企業会計上の項目に含まれないものの、将来の税額を増減させる要素となるため、税効果会計での処理が必要です。
4-1. 法人税の繰越欠損金の仕訳方法
仕訳では繰越欠損金額をそのまま記載するのではなく、該当する会計年度の法人税額に直して記載します。
勘定科目は「繰延税金資産」か「繰延税金負債」とし、資産または負債で処理します。(貸借対照表)
相手科目は「法人税調整額」とし、収益または費用として処理します。(損益計算書)
将来の税金負担の軽減額は資産として扱うため、上記の仕訳となります。
4-2. 繰越欠損金が発生するときの仕訳
例えば、法人1期目に赤字を出し、繰越欠損金▲300千円を計上した場合の仕訳は以下となります。なお、実行法人税率は30%とします。
| 借方 | 貸方 | ||
| 繰越税金資産 | 90 | 法人税調整額 | 90 |
※繰越税金資産の期末残高90
このとき、法人税額で計上(300×30%=90)することに注意しましょう。これにより、企業会計上のズレを防止します。
4-3. 繰越欠損金を解消する仕訳
法人2期目に黒字転換したと仮定して、相殺する際の仕訳は以下となります。
なお、課税所得(黒字)は200千円、実行法人税率は30%とします。
| 借方 | 貸方 | ||
| 法人税調整額 | 60 | 繰越税金資産 | 60 |
※繰越税金資産の期末残高30
法人税額は200×30%の60となります。
また、法人1期目の繰越税金資産の期末残高90から60を引いた、30が翌年以降繰り越せる欠損金額(資産)です。
4-4. 繰越欠損金の回収可能性がなくなったとき
なんらかの理由により、法人1期目で計上した繰越税金資産が回収できないと判断されたときは、計上したときとは逆の仕訳を行い取り消します。
| 借方 | 貸方 | ||
| 法人税調整額 | 90 | 繰越税金資産 | 60 |
※繰越税金資産の期末残高0
上記はあくまでも、将来起こりうる税金の動きを記録しているだけのため、途中で状況が変わる可能性もあります。その際は、会計上の仕訳を取り消す作業が必要です。
関連記事:法人税の勘定科目とは?ケースごとの仕訳ルールや注意点を解説
5. 繰越欠損金は適用条件や期間を確認して会計処理をしよう

繰越欠損金制度とは、赤字を次の事業年度に繰越せる仕組みのことです。
赤字を繰越すことで、課税所得が生じた際は相殺し、納税額を低く抑えることができます。
しかし、事業規模や開始時期により適用できる条件や期間が異なる点に注意が必要です。
欠損金が生じた時は、繰越欠損金制度を活用し法人税負担の軽減に役立てましょう。
「法改正に関する情報収集が大変で、しっかりと対応できているか不安・・・」
「仕訳や勘定科目など、基本的なこともついうっかり間違えてしまうことがある」
などなど日々の経理業務に関して不安がある方必見の資料です。
経費精算は日々発生するため、流れ作業のように処理することもあるでしょう。しかし、経費精算業務は、社内規程や関連法に対応した細かいルールが存在するため、注意が必要です。
また直近の電子帳簿保存法やインボイス制度など毎年のように行われる法改正に対して、情報を収集し適切に理解する必要があります。
そこで今回は、仕訳や勘定科目などの基礎知識から、経理担当者なら知っておきたい法律知識などを網羅的にまとめた資料をご用意しました。
経理に関する基本情報をいつでも確認できる教科書のような資料になっております。資料は無料でダウンロードができ、毎回Webで調べる時間や、本を買う費用も省けるので、ぜひ有効にご活用ください。
経費管理のピックアップ
-

電子帳簿保存法に対応した領収書の管理・保存方法や注意点について解説
経費管理公開日:2020.11.09更新日:2024.10.10
-

インボイス制度の登録申請が必要な人や提出期限の手順を解説
経費管理公開日:2022.01.27更新日:2024.01.17
-

インボイス制度は導入延期されるの?明らかになった問題点
経費管理公開日:2021.11.20更新日:2024.01.17
-

小口現金とクレジットカードを併用する方法とメリット
経費管理公開日:2020.12.01更新日:2024.10.07
-

旅費精算や交通費精算を小口現金から振込にする理由
経費管理公開日:2020.10.07更新日:2024.10.07
-

経費精算とは?今さら聞けない経費精算のやり方と注意点を大公開!
経費管理公開日:2020.01.28更新日:2024.10.10
会計 の関連記事
-

レンタカーの経費、ガソリン代、保険料の勘定科目と仕訳方法を解説
経費管理公開日:2023.05.16更新日:2024.05.08
-

接待ゴルフの費用は経費になる?判断基準と仕訳方法を解説
経費管理公開日:2023.05.16更新日:2024.05.08
-

立替精算とは?精算方法や仕訳を解説
経費管理公開日:2023.05.15更新日:2024.05.08