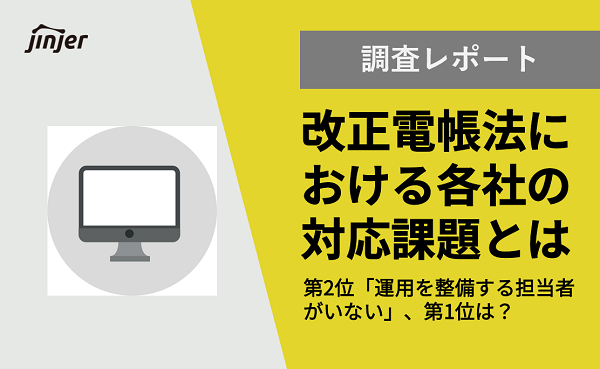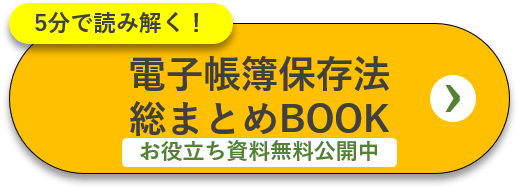電子帳簿保存法で注文書を電子保存するための方法や注意点を解説
更新日: 2024.3.8
公開日: 2020.11.9
jinjer Blog 編集部
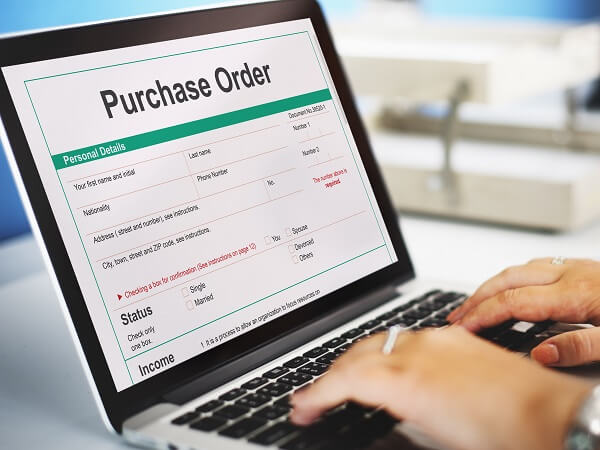
電子帳簿保存法では、注文書や発注書を電子データで保存することが認められています。
注文書・発注書の電子化には、コスト削減や業務の効率化、検索性の向上などさまざまなメリットがあります。
しかし、そうしたメリットを引き出すためには、注意点を理解しておかなくてはいけません。注文書・発注書を電子化する方法を、そのメリットや注意点とともに解説します。
【調査レポート】2022年「改正電子帳簿保存法」に向けた各社の現状とは?
一部猶予が与えられた改正電子帳簿保存法ですが、各社の対応状況はいかがなのでしょうか。
そこで電子帳簿保存法に対応したシステムを提供するjinjer株式会社では「改正電子帳簿保存法対応に向けた課題」に関する実態調査を実施いたしました。
調査レポートには、
・各企業の電帳法対応への危機感
・電帳法に対応できていない理由
・電帳法の対応を予定している時期
・電帳法対応するための予算の有無について
などなど電子帳簿保存法対応に関する各社の現状が示されています。
「各社の電帳法の対応状況が知りたい」「いつから電帳法に対応しようか悩んでいる」というご担当者様はぜひご覧ください。
目次
1. 注文書は電子帳簿保存法によって電子保存できる

電子帳簿保存法によって紙での保管が必要だった書類を電子化して保管することが認められました。そのため、注文書も電子保存が可能です。
しかし、書類の電子化を実現するためには様々な要件をクリアする必要があり、電子化の実現は思っているよりも時間がかかるかもしれません。
事前に要件を確認して途中でつまづくことがないよう、準備を進めましょう。
1-1. 電子取引・電子保存とは
電子取引は電子帳簿保存法で「取引情報の授受を電磁的方式によりおこなう取引」と定められています。
簡単に説明すると、紙の書類を使用せずに電子データのみですべてのやり取りを完結できる取引です。
電子保存は、電子的に作成した書類や帳簿を印刷せずに、そのまま電子データの状態で保存することを指します。会計ソフトやシステムで作成した仕訳帳や賃借対照表、電子的に作成した請求書や注文書などが該当します。
関連記事:【2022年】電子帳簿保存法とは?基礎知識・改正点・対応方法を解説
1-2. 2022年・2023年の法改正で保存要件が緩和された
電子帳簿保存法は1998年に制定されたものですが、繰り返し見直しがされています。近年でも保存要件の大幅な見直しがされ、より電子保存がしやすくなっています。
2022年の改正では電子帳簿保存を始めるための事前承認が不要になったり、タイムスタンプの要件が緩和されたりしています。システムや環境面でも緩和がされ、これによってデータの電子化や電子保存は広まりつつあります。
2023年にも改正があり、ここでは緩和に加えて「宥恕措置」に変わる「猶予措置」が整備されました。
これによって特定の条件を満たしている場合に限り、改ざん防止や検索機能面などの要件を満たしていなくても、電子取引データの保存が可能になっています。
電子保存に切り替えやすくなっているため、この機会にシステムや人材を整備して電子化を進める企業が増えています。
2. 注文書の保存期間


注文書を含む国税関係書類の保存期間は、帳簿や書類の種類、個人と法人などで細かく規定されています。保存期間を守らないとデメリットが発生するおそれもあるため、正確に把握しておきましょう。
2-1. 法人の場合は7年間保存が必要
法人の場合は注文書の保存期間は7年間です。注文書のほかにも取引に関連する書類はすべて7年の保存が義務付けられています。
確定申告書の提出期限の翌日から7年間で計算するため、決算日や企業の年度末など誤ったタイミングで計算しないように注意しましょう。
また、欠損金(赤字)が発生した事業年度の場合は、9年、あるいは10年の保存期間が必要です。2019年4月1日より前に事業を開始している場合は9年、それ以降の場合は10年です。
2-2. 保存しなかった場合の罰則
注文書の保存期間を守らなかった場合でも、法人税法では罰則が定められていません。そのため、法的な罰則は発生しないと考えてよいでしょう。
しかし、税務調査で書類が不十分だと判断された場合は、追加徴税される可能性があります。青色申告をしている場合は、その取り消しも考えられるため、大きなデメリットが発生します。
なお、重要書類に該当する帳簿類の保存期間を守らなかった場合は、会社法違反になり罰則が発生するため、こちらも十分な注意が必要です。
3. 注文書を保存する3つの方法


電子帳簿保存法に則って注文書を保存するには、3つの方法からいずれかを選んでその要件を満たす必要があります。それぞれの保存方法について詳しく解説します。
3-1. 電子データとして保存
電子データで作成した注文書や、電子データで取引先から受け取った注文書は、そのまま電子データとして保存できます。
電子データで受け取った注文書をプリントアウトして紙で保存する方法は、2023年末日までは猶予期間として認められています。しかし、それ以降は電子データはそのまま保存しなければいけません。
これからは電子取引が中心になり、紙媒体の書類は減っていくとされています。そのため、猶予期間中に電子データを保存するシステムを整えておく必要があります。
3-2. スキャナ保存
紙で発行した、または受け取った注文書はスキャナ保存して電子データとして保存することが可能です。
紙の状態のままでも保管が可能ですが、省スペースやコスト削減を考える場合はスキャナ保存をして電子データ化させたほうがよいでしょう。
スキャナ保存をする場合の要件は、少しずつ緩和されているものの保存方法の中で最も厳格に定められています。解像度やカラー、タイムスタンプの要件などさまざまなものがあるため、スキャナ保存をする場合は要件を網羅しておきましょう。
参考:【令和6年1⽉以降用】はじめませんか、書類のスキャナ保存|国税庁
3-3. 紙媒体の保存
電子帳簿保存法が施行され、改正が続いている中でも、従来通り紙媒体での保存は認められています。
紙で作成した注文書の控えや受け取った注文書などは、そのまま保存しておけば問題ありません。
しかし、提出を求められた際は迅速に該当書類を見つけ出し、提示できるようにしておく必要があります。紛失や管理不足と判断されないように、原本を必ずファイリングして管理しましょう。
4. 電子帳簿保存法に沿った注文書の保存要件

今後、電子データで作成された書類は増えていくと想定されています。どのような保存要件があるのか、今のうちに正しく理解しておきましょう。
4-1. 電子データで作成された注文書の保存要件は、契約書や領収書と同じ
電子帳簿保存法では、国税関係帳簿と国税関係書類の電子保存について定めています。この「国税関係書類」には、物やお金のやり取りに直結する書類(領収書や契約書、請求書など)と、物やお金のやり取りに直結しない書類(注文書や見積書、検収書など)があります。
紙で作成した場合はそれぞれ保存要件が異なりますが、電子データで作成・受領した場合はいずれも同じ要件を満たす必要があるので、注意しましょう。
4-2. 電子データで作成された書類の保存要件と注意点
電子データで作成された書類は以下の要件を満たす必要があります。
- システムの操作説明書や手順書の用意
- 見読可能装置の備付け
- 検索機能の確保
- 改ざん防止の措置
それぞれ詳しく解説します。
システムの操作説明書や手順書の用意
スキャナ保存要件と同様に、電子取引においても、説明書や手順書の用意が義務付けられています。この手順書などは税務調査の時に必要となるため、すぐに取り出せる場所に保管しておきましょう。
見読可能装置の備付け
剣毒可能装置とは、モニターやプリンターのことを指しています。電子保存されているデータを映し出せることや印刷することが求められるため、税務調査ですぐに使えるように設定しておきましょう。
検索機能の確保
電子帳簿保存法では、電子データを金額や取引先名などの条件で検索できることが条件に含まれています。複数条件の組み合わせや範囲検索も要件に含まれているため、注意が必要です。ただし、2期前の売上高が1,000万円以下の企業に関しては、調査員の求めに応じて電子データをダウンロードできれば検索機能の確保は不要となっています。
2024年1月以降は、5,000万円以下の企業に範囲が拡大されるため、より対応しやすくなるでしょう。
改ざん防止の措置
真実性を担保するためにも、改ざん防止の措置をとることが義務付けられています。
具体的には以下の要件を満たす必要があるでしょう。
- 受領者・発行者いずれかのタイムスタンプ付与
- データ訂正や削除の履歴が残る、又は訂正削除ができないシステムの利用
- 不正な訂正や削除を防止する事務処理規程
いままではタイムスタンプの付与が必須でしたが、2022年の改正で一定の条件を満たせば不要になりました。
参照:電子取引データの保存方法をご確認ください(令和3年12月改訂)|国税庁
注意:「電子データで作成された書類」とは、電子データで送付した書類のことを指す
PDFデータや電子メールなどで相手に送付した注文書は「電子データで作成した書類」に該当するため、電子保存しなければなりません。
このとき、書類がどのような方法で作成されたかは関係ありません。
注文書をパソコンで作成していても、印刷して郵送された場合は電子データには該当せず紙媒体での保存が可能です。反対に手書きの注文書をPDF化してメールで送付された場合は「電子データ」に該当するため、電子保存する必要があります。
5. 注文書・発注書を電子化する際の注意点

注文書や発注書の電子化や電子保存を始めよう決めても、やみくもに進めてしまえば、コストがかさんだり、電子化後に使いにくくなったりしかねません。
電子化するときに注意すべきポイントを紹介します。
5-1. 電子保存する書類を厳選する
注文書や発注書は単独ではなく、付随する書類があることが多いです。そうした書類には電子保存の義務はありません。
必要のない書類まで電子化すれば、コストがかかるうえに検索性が悪くなってしまいます。
まずは電子化すべき書類を厳選し、後々見返す必要のないものや保存義務がないものは電子化せずに処分するなどの対応を検討しましょう。
5-2. 検索性を高めるファイル名やフォルダ構造を検討する
電子化のメリットのひとつである検索性の向上を最大限に引き出すためには、ファイル名やフォルダ構造を検索しやすいように設計しておかなくてはなりません。
いくらデータが紙にくらべて検索性が高いといっても、大量にあるデータをバラバラに格納していれば、そのなかから1つのデータを探し出すのにかなりの時間を要します。
顧客や商品別などに簡単にソート(並べ替え)できるよう、ファイル名・フォルダ名やフォルダの階層などのルールを事前に決めておきましょう。
さらに、PDFファイルで保管する際は、注文書や発注書の内容も検索できるよう、OCR(光学式文字認識)機能を適用して、テキスト認識のできるPDFファイルを作成しておくことをおすすめします。
5-3. セキュリティ対策をしっかりとおこなう
電子化の際には、不正アクセスや情報漏洩を防ぐためのセキュリティ対策も忘れてはならないポイントです。
「閲覧のみ可能」「データのダウンロードが可能」など、データへの細かなアクセス権限を設定することで、不正アクセスを防ぐと同時に、万一不正アクセスが発生したときにも素早く対応できます。
さらに、定期的なバックアップをルール化しておき、データ消失のリスクを回避することも重要です。
セキュリティ対策を万全にしておけば、電子データの弱点である不正アクセスや情報漏洩、データの消失などのリスクを大幅に改善することができます。
6. 数が増えやすい注文書は電子保存で効率よく管理しよう

注文書・発注書を電子化にはさまざまな準備が必要で、人材やコストの面でも決して容易ではありません。
しかし、そうした問題を踏まえたうえでも、増えやすい注文書や発注書を電子化することにはメリットがあります。今後、電子取引が中心になることも想定し、ぜひ導入を検討しましょう。
電子化を進める際は検索性の保持や電子帳簿保存法の要件を守ることを重視することが大切です。計画を立てて準備をし、スムーズな移行をめざしましょう。
関連サイト:デジタル化の窓口
2020年、2022の電子帳簿保存法改正を
わかりやすく総まとめ!
1998年に制定された電子帳簿保存法ですが、2020年10月や2021年の改正によって企業が電子帳簿保存法に対応するハードルが格段に下がりました。
しかし、電子帳簿保存法に対応すれば業務が効率化されると言っても、要件や法律そのものの内容、対応の手順など理解しなければならないことは多いです。
「どうにか電子帳簿保存法を簡単に理解したいけど、自分で調べてもいまいちポイントがわからない・・・」とお悩みの方は「5分で読み解く!電子帳簿保存法まとめbook」をぜひご覧ください。
資料では
・電子帳簿保存法の内容に関するわかりやすい解説
・2020年10月の改正と2022年の最新内容のポイント
・今後電子帳簿保存法に対応していくための準備や要件
など、電子帳簿保存法に関する内容を総まとめで解説しています。
「電子帳簿保存法への対応を少しずつ考えたいが、何から始めたらいいかわからない」という経理担当者様は「5分で読み解く!電子帳簿保存法まとめbook」をぜひご覧ください。。
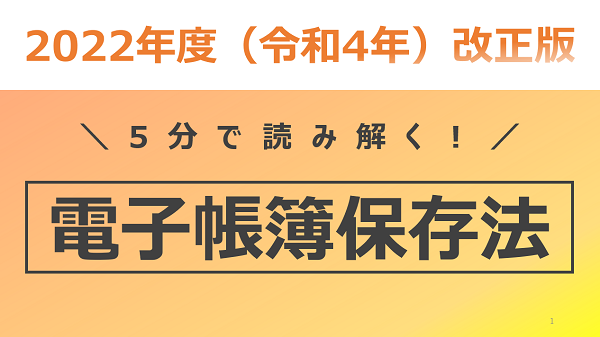
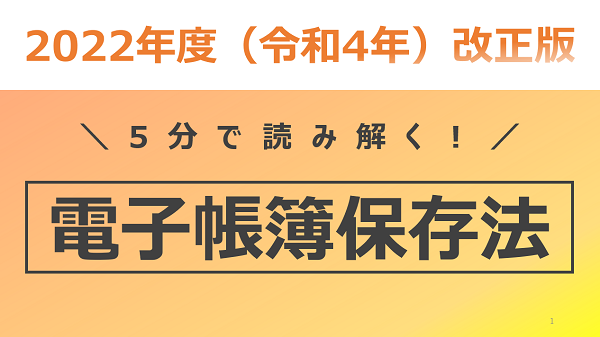
経費管理のピックアップ
-


電子帳簿保存法に対応した領収書の管理・保存方法や注意点について解説
経費管理
公開日:2020.11.09更新日:2024.03.08
-


インボイス制度の登録申請が必要な人や提出期限の手順を解説
経費管理
公開日:2022.01.27更新日:2024.01.17
-


インボイス制度は導入延期されるの?明らかになった問題点
経費管理
公開日:2021.11.20更新日:2024.01.17
-


小口現金とクレジットカードを併用する方法とメリット
経費管理
公開日:2020.12.01更新日:2024.03.08
-

旅費精算や交通費精算を小口現金から振込にする理由
経費管理
公開日:2020.10.07更新日:2024.03.08
-


経費精算とは?今さら聞けない経費精算のやり方と注意点を大公開!
経費管理
公開日:2020.01.28更新日:2024.07.04