棚卸計算法とは何か?具体的な計算方法やメリット・デメリット、継続記録法との違いも紹介
更新日: 2024.7.2
公開日: 2022.8.17
jinjer Blog 編集部

棚卸計算法とは材料の消費数量を把握する方法です。
期中は材料の受け入れ数量のみを記録し、期末に実地棚卸数量を引くことで消費量を求めます。
事務処理がシンプルな一方、期中の消費数量を把握できないことから継続記録法と併用して使うことが多いでしょう。
本記事では、棚卸計算法の概要とやり方、メリット、デメリット、継続記録法との違いについて分かりやすく解説します。
関連記事:棚卸とは?棚卸の目的や実施の時期、方法や流れについて解説
目次
86個の勘定科目と仕訳例をまとめて解説
「経理担当になってまだ日が浅く、会計知識をしっかりつけたい!」
「会計の基礎知識である勘定科目や仕訳がそもそもわからない」
「毎回ネットや本で調べていると時間がかかって困る」
などなど会計の理解を深める際に前提の基礎知識となる勘定科目や仕訳がよくわからない方もいらっしゃるでしょう。
そこで当サイトでは、勘定科目や仕訳に関する基本知識と各科目ごとの仕訳例を網羅的にまとめた資料を無料で配布しております。 会計の理解を深めたい方には必須の知識となりますので、ぜひ資料をダウンロードしてご覧ください。
1. 棚卸計算法とは材料の消費数量を把握する方法の1つ


商品販売業では、仕入価格=仕入原価としてそのまま会計上の処理が可能です。
一方、製造業では商品を自ら作り販売するため、材料費・労務費・経費などに分けて原価計算をしなければ製品原価を求めることができません。
このうち、材料費は以下の計算により求められます。
- 材料費=消費単価×消費数量
棚卸計算法とは、材料の消費数量を把握する方法の1つです。
材料元帳には受入数量のみを記録します。そのため、払出数量や残高を記録しない点が特徴です。
消費数量は、期中の受入数量から、実際に棚卸して確認した材料の数(実地棚卸数量)を引いて計算します。
材料元帳とは材料別に受払と残高を記録する帳簿で、枚数・単価・金額と合わせて記録するもので、商品有高帳の材料版にあたる帳簿です。
なお、消費数量を把握する方法はもう1つあり、継続記録法といいます。詳細は後ほど解説します。
2. 棚卸計算法の計算方法


棚卸計算法では、材料の購入時のみ材料元帳に受入数量を記録し、そこから期末の実地棚卸分を引いて消費数量を計算します。計算式は以下の通りです。
- 消費数量=期首数量+期中購入数量-期末実地棚卸数量
例えば、ある材料を期首に32個、期中に50個購入し、棚卸後の数量は15個だとします。
- 期首数量(32)+期中購入数量(50)-期末実地棚卸数量(15)=67
消費数量は67個と分かります。
なお、上記は決算時の棚卸計算法であり、実務では毎月末に数量を把握することが多いでしょう。その際は以下の計算式で数量を把握します。
- 消費数量(月)=月初数量+当月購入数量-月末実地棚卸数量
3. 棚卸計算法のメリット


棚卸計算法のメリットは手間がかからないという点です。払出のたびにどれくらい払い出したかを払出欄に記載する継続記録法は工数がかかります。一方、棚卸計算法は払出のたびに記載する必要がないため、工数の削減が期待できるでしょう。
材料類の中でも重要度の低いものは、棚卸計算法による記録が認められているため、活用すれば事務処理の効率化も期待できます。事務処理が効率化すれば、棚卸以外の業務に時間を割けます。
なお、材料の中でも後述する継続記録法による計算が困難なものも、棚卸計算法を適用してかまいません。
また、継続記録法を実施するには在庫管理システムのように専用のシステムを導入するのが一般的ですが、棚卸計算法のであれば専用システム導入費用を抑えられます。
4. 棚卸計算法のデメリット
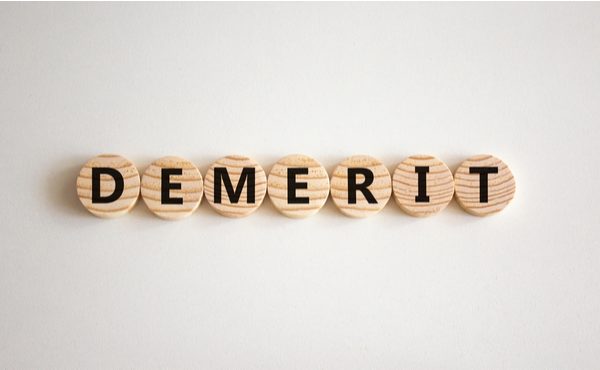
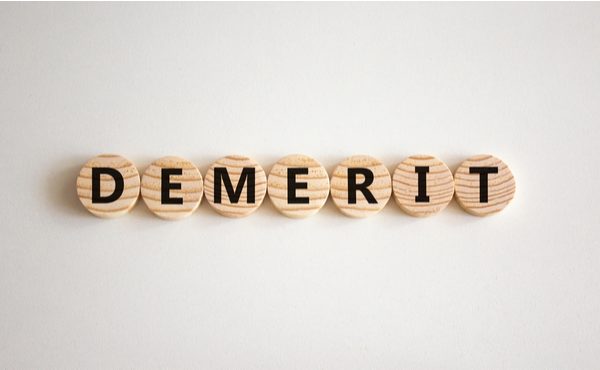
受入数量のみを記録するため、棚卸をしないと正確な在庫数量や消費量が把握できません。
破損などで棚卸減耗があっても消費数量として処理するため、正確な原価計算が難しくなります。
棚卸減耗を把握できないということは、盗難などが続いていても対策が遅れる可能性も否めません。
以上の理由から原価計算では、消費数量の把握は次に紹介する継続記録法の適用が基本とされています。(昭和三十七年十一月八日 原価計算基準による。)
参考:大蔵省企業会計審議会中間報告(昭和37年11月8日)|原価計算基準
5. 棚卸計算法と継続記録法の違い


棚卸計算法と継続記録法では、材料元帳に払い出し数量を記録するか否かに違いがあります。継続記録法の概要を解説します。
5-1. 継続記録法では材料元帳に受払を記録する
継続記録法では、材料の購入だけでなく、消費する都度、材料元帳に記録が必要です。なお、消費数量は払出数量に記録された数量により確認します。
例えば材料元帳に以下のように記録されていた場合の消費数量を考えます。
| 日付 | 摘要 | 数量 |
| 6/1 | 前月繰越 | 20 |
| 6/5 | 入庫 | 30 |
| 6/8 | 出庫 | 10 |
| 6/9 | 出庫 | 20 |
上記の場合、「出庫」分を合計すればよいため、6月9日までの消費数量10+20で30と分かります。
5-2. 継続記録法のメリット
材料の受入数量だけでなく、払い出し数量や残高など全て記録するため、期中のどの時点でも正確な消費数量が把握できます。在庫管理をする上でも役立つでしょう。
材料元帳も記録するので、期末には正確な帳簿棚卸数量も分かることから、棚卸減耗も確認できます。
以上のように、継続記録法は原価管理に優れる方法のため、消費数量記録の基本となります。
5-3. 継続記録法のデメリット
材料元帳に受払と残高を全て記録しなくてはいけないので、棚卸計算法以上に事務処理に手間がかかります。
また、期中は帳簿の払出数量を元に消費数量を確認するので、記録自体が間違っていると消費数量も違ってしまいます。
また、材料数が多い工場では手作業でリアルタイムの記録を取ることは困難です。その際は、在庫管理システムなどを使活用し記録した方が安全でしょう。
6. 棚卸計算法と継続記録法は併用するとより安全性を高められる


棚卸計算法も継続記録法も消費数量を記録する方法のため、理論的には、棚卸をして計算すれば、どちらも同じ数量が求められるはずです。
しかし、実際の材料の動きの中には、破損や紛失、窃盗などにより、帳簿残高と一致しないケースが多くあります。
そのため、棚卸計算法と継続記録法の併用により、より正確な消費数量の把握が可能となります。
6-1. 併用による棚卸減耗の求め方
例えば、材料元帳と月末棚卸の結果が以下のようになったとします。
【材料元帳】
| 日付 | 摘要 | 数量 |
| 6/1 | 前月繰越 | 200 |
| 6/5 | 入庫 | 400 |
| 6/8 | 出庫 | 700 |
| 6/9 | 出庫 | 400 |
【月末棚卸】
| 摘要 | 数量 |
| 前月繰越 | 200 |
| 期中受入 | 800 |
| 帳簿棚卸数量 | 300 |
| 実地棚卸数量 | 200 |
棚卸計算法では、消費数量は800個(200+800-200)となります。
一方、継続記録法を元に材料元帳を確認すると、期中の消費数量は700個となっています。なお、計算上も200+800-300から700個と分かります。
6-2. 棚卸減耗の仕訳方法
結果、実地消費数量800から帳簿消費数量700個を引いた、100個分は破損などにより減耗したものの、帳簿上、記録されていなかったことが分かります。
減耗した100個分は、棚卸減耗費を計算し、以下の方法で仕訳が必要です。
- 借方:製造間接費
- 貸方:材料
なお、上記は通常の生産過程で減耗する程度(破損や紛失など)を想定した仕訳であり、火災などによる大規模な減耗の場合、また別の会計処理が必要です。
以上のように、材料の消費では、棚卸計算法と継続記録法を併用することで正確な原価を計上でき、より精度の高い決算書の作成につながります。
関連記事:棚卸減耗損とは?計算方法や仕訳例、発生原因・対策も紹介
7. 棚卸計算法と継続記録法の違いを知り材料管理に役立てよう!


棚卸計算法は、材料の受入数量のみを記録する方法のため、事務処理が容易な点がメリットです。重要性の低い材料などの管理には認められる方法のため、継続記録法と使い分けることで業務の効率化が期待できます。
また、価値の高い材料では棚卸計算法と継続記録法の併用により、一層確実な消費数量管理が可能です。
材料の管理では、双方の管理方法の違いを知り、適切な方法を選びましょう。
86個の勘定科目と仕訳例をまとめて解説
「経理担当になってまだ日が浅く、会計知識をしっかりつけたい!」
「会計の基礎知識である勘定科目や仕訳がそもそもわからない」
「毎回ネットや本で調べていると時間がかかって困る」
などなど会計の理解を深める際に前提の基礎知識となる勘定科目や仕訳がよくわからない方もいらっしゃるでしょう。
そこで当サイトでは、勘定科目や仕訳に関する基本知識と各科目ごとの仕訳例を網羅的にまとめた資料を無料で配布しております。 会計の理解を深めたい方には必須の知識となりますので、ぜひ資料をダウンロードしてご覧ください。
経費管理のピックアップ
-


電子帳簿保存法に対応した領収書の管理・保存方法や注意点について解説
経費管理
公開日:2020.11.09更新日:2024.03.08
-


インボイス制度の登録申請が必要な人や提出期限の手順を解説
経費管理
公開日:2022.01.27更新日:2024.01.17
-


インボイス制度は導入延期されるの?明らかになった問題点
経費管理
公開日:2021.11.20更新日:2024.01.17
-


小口現金とクレジットカードを併用する方法とメリット
経費管理
公開日:2020.12.01更新日:2024.03.08
-

旅費精算や交通費精算を小口現金から振込にする理由
経費管理
公開日:2020.10.07更新日:2024.03.08
-


経費精算とは?今さら聞けない経費精算のやり方と注意点を大公開!
経費管理
公開日:2020.01.28更新日:2024.07.04





















