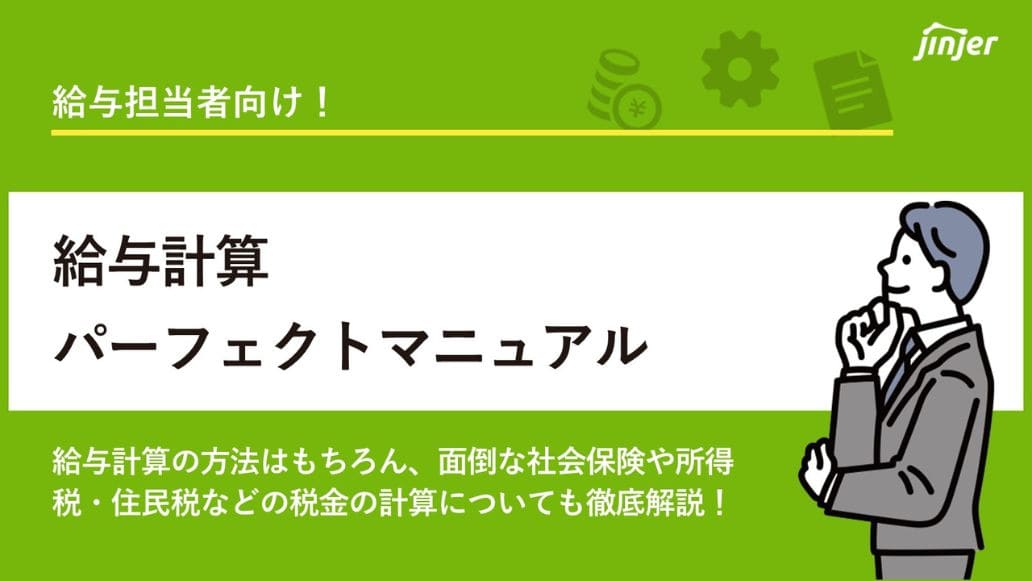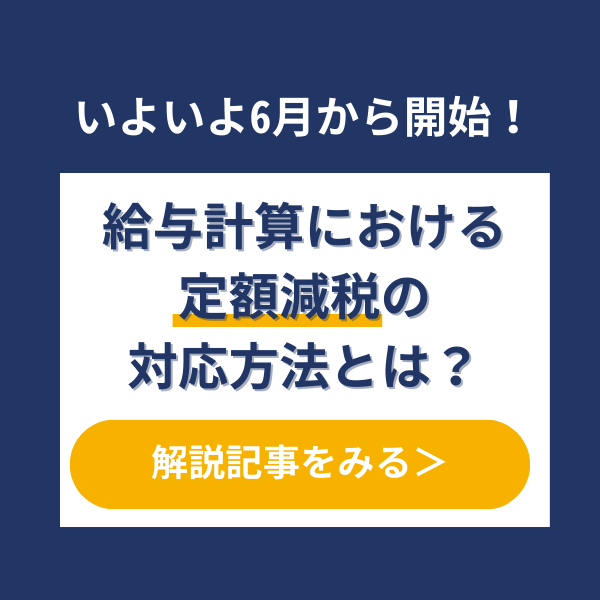扶養手当とは?家族手当との違いや金額・条件を詳しく解説

「扶養手当は聞いたことがあるけど、詳しい内容は知らなくて困っている」
「扶養手当と家族手当の違いは?」
このような疑問にお困りではありませんか。
扶養手当とは、扶養する家族がいる従業員を経済的に支援する目的で、基本給とは別に支給される報酬です。
本記事では扶養手当の概要や支給条件、金額相場や家族手当との違い、導入のメリットやデメリットを解説します。扶養手当の基本知識を身につけたい方はぜひご覧ください。
目次
1. 扶養手当とは


扶養手当とは、主に扶養する家族がいる従業員を経済的に支援する目的で、基本給とは別に支給される報酬です。各企業が自主的に用意する法定外福利厚生の一つで、支給条件や金額は各企業が自由に設定可能です。
扶養する家族に該当するのは、従業員が経済的に支えて生活を維持する次のような親族です。
- 配偶者
- 子ども
- 親
ただし、公務員の場合は扶養手当の支給が法律で定められているため、支給条件や金額が定められています。
福利厚生とは企業が従業員や従業員の家族へ提供するさまざまなサービスのことです。福利厚生には法律で定められる法定福利厚生と、法律とは関係のない法定外福利厚生があります。
| 法定福利厚生 | 法定外福利厚生 |
| 雇用保険
健康保険 介護保険 労災保険 厚生年金保険 |
住宅手当
家族手当 交通費 健康診断及び人間ドックの受診料 退職金 |
社会保険ともよばれる法定福利厚生は、企業が費用負担をして従業員へ必ず提供しなければなりません。一方で法定外福利厚生は社員の労働環境を整える目的で企業が自主的に定めます。
また名称の似ている児童扶養手当は、国による支給制度なので、企業が支給する「扶養手当」とは異なります。
2. 扶養手当の支給条件


扶養手当は、企業の法定外福利厚生なので、支給条件に関する規定はありません。そのため、導入する場合は企業が自由に条件を決めることができます。しかし、条件が厳しすぎると支給対象者が少なく、導入するメリットが得られないので、主な支給条件をチェックしておきましょう。
扶養手当の支給条件の一般的な例は以下のとおりです。
| 扶養対象者 | 扶養の判断 |
| ・扶養する同居家族
・続柄が配偶者子ども親 ・18歳未満の子ども ・60歳以上の親 |
・従業員の社会保険の被扶養者
・従業員と生計をともにする同居家族 ・従業員との続柄(実父母・配偶者・子など) |
また、扶養手当を支給する企業のうち、扶養手当の支給対象者の所得に関して以下のような制限を設けるケースもあります。
| 所得制限 | 支給企業内割合 |
| 103万円 | 5割 |
| 130万円 | 2割 |
参照:配偶者手当を取り巻く現状 3.企業による扶養手当の見直し|厚生労働省
なお育児休業中の支給の有無についても、企業ごとに違いがあります。ただし育児休業期間中が無給の場合には、扶養手当も不支給となるケースが一般的です。
支給条件については、就業規則に明記する必要があるので、条件を定めたら、就業規則に記載しましょう。
3. 扶養手当の金額相場


支給条件と同じく、扶養手当の金額も企業に決定権があります。ここでは、一般的な扶養手当の金額相場(月額)を紹介するので、手当を決める際の参考にしてください。
| 配偶者 | 1万~1万5,000円 |
| 子ども | 3,000~5,000円 |
| その他親族 | 4,000~7,000円 |
子どもを支給対象者とする場合、1人目の子どもの支給額が最も多く、2人目の子どもから支給額が減少するケースも多く見受けられます。
なお国家公務員の扶養手当の支給額は以下のとおりです。
(支給額)
配偶者 6,500円 ※
子 10,000円
子(16歳年度初め~22歳年度末) 加算 5,000円
父母等 6,500円 ※
※ 行政職俸給表(一)8級職員等の場合、支給額は3,500円となり、
行政職俸給表(一)9級以上職員等の場合、支給されない。
ただし、国家公務員であっても、役職や勤続年数などによって金額が変わります。
ここでは、諸手当の平均支給額と扶養手当の現状について解説します。
3-1. 平均支給額
令和2年の厚生労働省の調査において、従業員一人あたりへの扶養手当・家族手当・育児支援手当の平均支給額は約1万8,000円でした。
同調査における企業規模別の平均支給額は以下のとおりです。
| 従業員数 | 平均支給額 |
| 1,000人以上 | 約2万2,000円 |
| 300〜999人 | 約1万6,000円 |
| 100〜299人 | 約1万5,000円 |
| 30〜99人 | 約1万3,000円 |
参照:令和2年就労条件総合調査 結果の概況 賃金制度|厚生労働省
調査結果から、企業規模が大きくなるほど平均支給額も増える傾向にあるといえるでしょう。とくに注目すべき点は、在籍数が1,000人以下と1,000人を超える場合を比べると、支給額に1万円近い差がある点です。
3-2. 扶養手当の金額は減少傾向
近年は扶養手当額を減額したり、扶養手当を廃止したりする企業が増えています。主な理由は、共働き世帯が増えた点や同一労働同一賃金により、正社員のみへの支給が難しくなった点などです。
さまざまな理由から扶養手当を廃止した場合、次のような対応をする企業もあります。
- 子育て手当の支給重点化
- 扶養手当を基本給と1本化
- 能力に応じた手当の新設
なお、見直しや廃止の対象となっているのは家族手当も同様となるため、導入する際にはしっかりと検討することが望ましいでしょう。
4. 扶養手当と家族手当の違い


扶養手当と家族手当の違いは、支給の対象者です。
| 手当 | 支給の対象者 |
| 扶養手当 | 従業員が扶養する親族 |
| 家族手当 | 従業員のすべての家族(扶養の有無は無関係) |
扶養手当の支給対象者は、従業員が扶養する親族のみとなります。一方、家族手当では扶養の有無に関係なく、従業員のすべての家族が支給対象者です。
手当の呼び名が似ているため制度を混同する企業も見受けられますが、「扶養手当」と「家族手当」は同じではありません。
しかし、家族手当も扶養手当と同じく、会社が自由に条件や金額を決められる法定外福利厚生の一つです。そのため、支給対象の条件や金額も企業によって異なります。例えば、「配偶者と子どものみ」「配偶者のみ」「子どものみ」とする企業もあり、支給対象者が扶養手当と同じになってしまうことから、混同しやすい手当といえるでしょう。
5. 扶養手当不支給証明書が必要な場合


扶養手当不支給証明書の提出が必要な場合とは、一般的に夫婦の両方が扶養手当を受給することを認めていない企業から求められたときです。多くの場合、会社は従業員へ問題なく扶養手当を支給するために、提出書類にて従業員の配偶者の不受給を確認します。
扶養手当不支給証明書とは、従業員の扶養手当の対象者について、従業員の配偶者が勤務先から扶養手当を受給していないことを証明する書類です。そのため、書類を受け取り提出するのは従業員ですが、書類の申請者欄には配偶者の住所や氏名を記入します。
また、配偶者の勤務先の名称や所在地などの記入も必要です。加えて、従業員の扶養手当の対象者となる親族についても、氏名・続柄・生年月日・住所などを記入します。
従業員と配偶者のどちらが書類に記入するのかについては、企業の規定に従うことになっているので、扶養手当不支給証明書の発行を求められた場合すぐに対応できるように、どちらが記入するのかを決めておきましょう。
6. 扶養手当のメリット・デメリット


扶養手当の導入にはどのようなメリットとデメリットがあるのでしょうか。ここでは、それぞれを具体的に解説します。
6-1. 扶養手当導入のメリット
扶養手当導入のメリットは、以下を期待できる点です。
- 従業員満足度が向上する
- 愛社精神が向上する
- 企業価値が向上する
- 人材流出を予防できる
- 求職者が増加する
手当のない企業と比較した場合に、手当のある企業は扶養家族のいる従業員の満足度向上につながりやすいです。
また、将来的に結婚を考えている従業員のモチベーションアップにも役立つでしょう。結果、従業員の満足度や愛社精神がアップすることで、退社を検討する従業員も少なくなります。
手当の手厚い企業は、求職者から見ても企業価値が高く魅力的です。そのため、新卒・中途に関係なく求職者の増加も見込めます。
6-2. 扶養手当導入のデメリット
扶養手当導入はメリットだけではありません。導入する場合は、デメリットについても理解した上で検討しましょう。
扶養手当導入のデメリットは、以下の3点です。
- 導入にあたり就業規則の変更手続きや不正受給対策の手間がかかる
- 経理・総務・人事など給与計算を担う部署の負担やコストが増加する
- 扶養家族がいない従業員や扶養手当の条件を満たさない従業員が不満を抱きやすい
このようなデメリットにより、扶養手当不支給の従業員のモチベーションや生産性の低下につながる恐れもあるでしょう。
現在は、扶養手当や家族手当をなくす企業も増加しているため、導入するかどうかについても慎重に検討してください。
導入後に廃止する場合には、不利益変更の強硬による法廷闘争を避けるためにも、従業員の理解や同意を得なければなりません。就業規則の再度変更や代替制度の準備も必要となります。
導入した場合のデメリットや導入後の廃止は難しいことを踏まえ、導入を検討することが大切です。
7. 扶養手当を適切に導入しよう


扶養手当は、企業が従業員や従業員の親族のために提供する法定外福利厚生の一種です。法律による決まりはないため、支給条件や金額は企業が自由に決められます。
ただし、導入は企業の判断に委ねられていますが、「扶養手当の廃止」や「減額」は勝手にできないため注意が必要です。憲法第八条において「労働者及び使用者は、その合意により、労働契約の内容である労働条件を変更することができる。」という規程があるため、手当の廃止や見直しをする場合は従業員の合意を得なければなりません。
しかし、扶養手当の導入は従業員の満足度や企業価値の向上、人材流出の予防や求職者の増加につながるメリットがあります。一方、コストや作業負担の増加、不支給の従業員から不満が出る可能性もあるので、事前に慎重に検討してから扶養手当を適切に導入しましょう。
勤怠・給与計算のピックアップ
-




【図解付き】有給休暇の付与日数とその計算方法とは?金額の計算方法も紹介
勤怠・給与計算
公開日:2020.04.17更新日:2024.03.07
-


36協定における残業時間の上限を基本からわかりやすく解説!
勤怠・給与計算
公開日:2020.06.01更新日:2024.06.04
-


社会保険料の計算方法とは?給与計算や社会保険料率についても解説
勤怠・給与計算
公開日:2020.12.10更新日:2024.07.08
-


在宅勤務における通勤手当の扱いや支給額の目安・計算方法
勤怠・給与計算
公開日:2021.11.12更新日:2024.06.19
-


固定残業代の上限は45時間?超過するリスクを徹底解説
勤怠・給与計算
公開日:2021.09.07更新日:2024.03.07
-


テレワークでしっかりした残業管理に欠かせない3つのポイント
勤怠・給与計算
公開日:2020.07.20更新日:2024.03.25