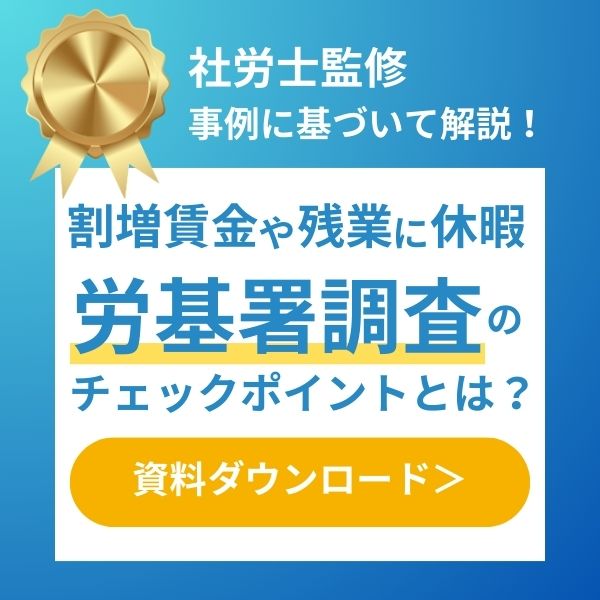半休取得日の残業はどう扱う?残業代の計算方法をわかりやすく解説
更新日: 2025.11.21 公開日: 2025.1.2 jinjer Blog 編集部

半休は、一般的に0.5日分の有給休暇として扱われます。しかしその日に残業したとしたら、残業代はどのように計算したらよいのか戸惑う場合が多いでしょう。
半休取得日における残業代の計算は、残業した時間や業務をおこなった時間帯によって異なるため注意が必要です。
この記事では、半休取得日の残業の取り扱いと残業代の計算方法、残業代に関する注意点、取り決めのポイントを解説しています。制度の導入を検討している方や導入したばかりの方は、ぜひ参考にしてください。
目次
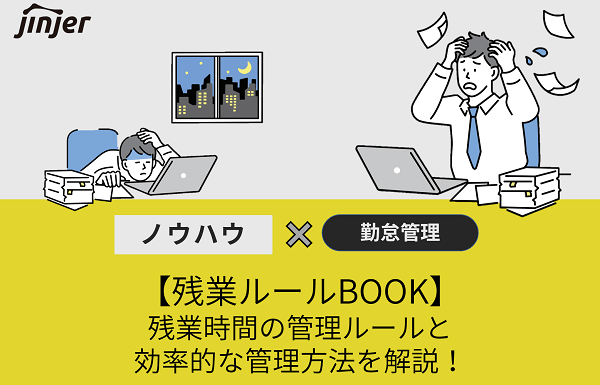
残業時間の管理や残業代の計算では、労働基準法で「時間外労働」と定められている時間を理解し、従業員がどれくらい残業したかを正確に把握する必要があります。
しかし、どの部分が割増にあたるかを正確に理解するのは、意外に難しいものです。
当サイトでは、時間外労働の定義や上限に加え、「法定外残業」と「法定内残業」の違いをわかりやすく図解した資料を無料で配布しております。
資料では効率的な残業管理の方法も解説しているため、法に則った残業管理をしたい方は、ぜひこちらから資料をダウンロードしてご活用ください。
1. そもそも半休制度とは?


まずは半休制度とはなにか、制度の内容や取り扱いのルールを知っておきましょう。
1-1. 企業が独自に取り入れている制度
半休制度は「半日休暇制度」の略称です。有給休暇を半日単位で取得する制度を指すことが一般的で、この制度は企業が独自に導入するものです。
法律による定めはないため、半休制度がない企業とある企業で別れており、制度はあっても企業によって取り扱いが異なります。
半休制度は会社がある平日にどうしても済ませたい用事がある場合や、ライフワークバランスを実現するためなど、さまざまな用途に使われます。半日単位であること以外は有給休暇との違いはありません。
1-2. 半休の取り扱いは就業規則に則る
半休制度がある場合は、適正な取り扱いをするために就業規則が定められています。
申請方法や時間を分けるタイミング、給与の計算など細かい部分もすべて就業規則に則っておこなう必要があります。
また、半休を取得した場合でも残業が発生するケースがあります。「午前中に半休を取ったから午後は残業する」というケースや「午後に半休を取る予定だったが午前の業務が長引いた」というケースなどが考えられます。
このような場合は時間外労働に対する割増賃金が発生することがあるため、こうした部分も就業規則や法律を必ず守って処理しなければなりません。
半休日の残業を禁止していても、実際に残業が生じてしまった際は、残業代の支払いが必要です。残業禁止を理由として残業代が出ないのは、違法であるため注意しましょう。
2. 半休取得日の残業の取り扱い


半休を取得した日にも残業が発生するケースがあります。。
実際に半休の日に残業が発生した場合はどうすればよいのか、午前と午後それぞれのパターンで解説していきます。
2-1. 午前中に半休を取り残業した
午前中に半休を取り、午後から出社して残業したケースでは以下の状況が考えられます。
終業時刻は過ぎたが法定労働時間は超えていない
働いた時間が法定労働時間を超えた
終業時刻とは各企業が定めている時刻であり、17~19時頃に設定されている場合が多いです。半休を取った日に残業し終業時刻を過ぎた場合には、各企業で定める賃金規程に基づいた残業代を残業した時間分支給します。
一般的に時給制で働いている従業員の残業代は、1時間あたりの時給と同じです。月給制の場合は、月給と諸手当を足した額を1ヵ月の平均所定労働時間で割った金額と定めるケースが多くみられます。
しかし、午前中に半休を取得した日に法定労働時間を超えて労働した場合は、計算の仕方が変わるため注意が必要です。1日に8時間を超えて働いた分に対しては、割増賃金を上乗せして支給する必要があります。
2-2. 午後の半休を取ったが午前中の勤務が長引いた
午後に半休を取ったにもかかわらず午前中の勤務が午後まで長引いたケースでは、残業としてでなく早退として扱うのが一般的です。半休は0.5日分の有給休暇として扱われますが、この場合は有給を取らなかったこととして扱われます。
しかし、有給休暇は従業員が希望している日に取得させることが基本です。業務上の都合で有給休暇が取り消しになることは、望ましいことではありません。
管理職の方は、午後の半休を取っている従業員が定刻通りに業務を終えられるよう、適切な対応をする必要があります。
3. 半休取得日の残業代の計算方法


半休取得日の残業代の具体的な計算方法を以下のケースごとに紹介します。
働いた時間が法定労働時間を超えない場合
働いた時間が法定労働時間を超えた場合
それぞれの状況に合った計算方法で残業代を算出しましょう。
3-1. 働いた時間が法定労働時間を超えない場合
午前中に半休をとり午後から勤務して残業したが、働いた時間が法定労働時間を超えない場合には、以下のように算出します。
残業代=1時間あたりの賃金✕残業時間(終業時刻から数える)
終業時間を超過している場合でも働いた時間が法定内の8時間以下なら、残業代に割増賃金を上乗せする必要はありません。
3-2. 働いた時間が法定労働時間を超えた場合
午前中に半休を取り午後から勤務した場合で、1日に働いた時間が法定労働時間である8時間以上となった場合の計算式です。労働基準法に定められているとおり、法定外の労働時間に対して25%の割増率を上乗せして算出します。
残業代=1時間あたりの賃金✕8時間を超えない分の残業時間+1時間あたりの賃金✕割増率(1+0.25以上)✕8時間を超えた分の残業時間
午前半休の場合、残業時間は深夜に及ぶことも想定されます。業務が22時を過ぎた場合には、残業代にさらに25%以上の割増率が加算されるため割増率は50%です。
4. 半休取得日の残業代に関する注意点


半休取得日の残業代に関する注意点は以下のとおりです。
時間の区切りを明確に定義する
休憩時間を考慮して残業代を算出する
それぞれの注意点を詳しく解説します。
4-1. 時間の区切りを明確に定義する
残業代を正しく計算するためには、どの時間で業務を区切るかを明確に決める必要があります。主な分け方は以下のとおりです。
午前休と午後休で分ける
所定労働時間を均等に2分割する
多くの企業では、昼休みを挟んで午前休と午後休とする方法が採用されています。わかりやすく、業務の区切りがよい場合が多いのではないでしょうか。しかし、午前と午後の勤務時間が異なる場合も多く、必ずしも働く時間が均等になりません。
一方で、所定労働時間を均等に2分割する方法なら、1日を均等に分けられます。例えば、「前半の時間が9~13時」「後半の時間が13~17時」と決めることも可能です。
4-2. 休憩時間を考慮して残業代を算出する
残業代を算出する際には、休憩時間も考慮しましょう。労働基準法では、休憩について次のように定めています。
労働時間が6時間を超える場合には45分の休憩を取る
労働時間が8時間を超える場合には1時間の休憩を取る
午後から出社した場合でも、働いた時間が6時間を超えれば休憩を取らなければなりません。残業代を算出する際には、働いた時間から休憩時間を引きましょう。
5. 半休制度に関連する5つのポイント


半休制度の残業に関する取り決めの5つのポイントは以下のとおりです。
制度取得日の割増賃金率について就業規則に記載する
残業の事前許可制の導入を検討する
時間有給制度を取り入れるべきか検討する
有給休暇にカウントすることを忘れない
半休の取得を使用者は強制できない
それぞれのポイントについて、詳しく解説します。
5-1. 半休に関する決まりを就業規則に記載する
半休取得日の割増賃金率は、就業規則に記載しましょう。労働基準法により、労働する時間が1日8時間を超える場合には、賃金に25%以上の割増賃金を上乗せする必要があります。22時以降に業務をおこなう際には、さらに25%以上割り増ししなくてはなりません。
時間外労働についての割増賃金率は、法改正によりたびたび変化します。従業員が割増賃金率を正しく把握できるよう、就業規則に記載しておきましょう。
5-2. 残業の事前許可制の導入を検討する
制度を適切に活用するために、残業の事前許可制の導入を検討するのもおすすめです。半休を取得したにもかかわらず以下のような状況では、うまく活用できているとは言えません。
午後に半休を取っていたが、午前中の業務が午後まで伸びた
リフレッシュのために午前中に半休を取ったが、遅くまで残業をすることになった
制度を取り入れることで従業員のワークライフバランスを整えようと考えても、休んだ分残業が発生するのでは元も子もありません。
残業の事前許可制を導入すれば、従業員は自分の判断で残業できなくなります。時間内に業務を終わらせるよう努めるか、ほかの従業員に業務を割り振ることになり、無駄な残業を削減できるようになるでしょう。
5-3. 時間有給制度を取り入れるべきか検討する
半休制度が活用しづらく従業員が不満を感じている場合には、時間有給制度を取り入れるべきか検討しましょう。
時間有給制度は、1時間単位で有給休暇を取れる制度です。業務時間が8時間の場合には1日の有給休暇を8分割し、必要な時間分だけの有給休暇を取得できます。
半休制度の場合、午後の半休を取得したけれど午後まで残業した場合、半休ではなく早退として扱われるのが一般的です。しかし、時間有給制度を取り入れていれば、時間単位で有給を取得できるでしょう。
多くの業務を抱えている従業員は、半休を取得するのにもためらう場合があります。時間有給制度は、そのような従業員にとっても利用しやすい制度です。
5-4. 有給休暇にカウントすることを忘れない
2019年に労働基準法が改正された際に、年次有給休暇の取得義務が「年5日」と定められました。これは「年10日以上の有給休暇が付与される従業員の場合、最低でも年5日は有給休暇を取得させなければいけない」という法律です。
半休制度では、この有給に半休をカウントすることができます。半休は0.5日として計算するため、2回半休を取った従業員は「1日有給を消化した」と計算してよいわけです。
半休は早退や遅刻として誤って取り扱われてしまうことがあります。半休の申請があったのか、それとも何らかの理由による遅刻や早退なのか、正確に管理して有給休暇にカウントすべきか見極めましょう。
参考:年5日の年次有給休暇の確実な取得 わかりやすい解説|厚生労働省
5-5. 半休の取得を使用者は強制できない
有給休暇は1日単位で与えることが原則ですが、従業員が半日単位での取得を希望し、使用者がそれを認める場合は、半休を与えることができます。
そのため、従業員が1日単位での有給休暇を希望しているにもかかわらず、忙しいなどを理由に使用者が半日単位での取得を強制することはできません。また、半休を1日単位の有給休暇として扱うことも認められないため注意しましょう。
半休を会社の制度として認めているのであれば、原則として使用者は従業員の希望に応じて半休を与えることが求められます。
6. 半休を取得した日の残業時間はケース別に正確に計算しよう


午前中半休を取って残業した場合と、午後から半休をとるはずが午前中の業務が午後まで延びた場合とでは取り扱いが異なります。
また残業代を出す際には、所定労働時間と法定労働時間を理解し、休憩時間や深夜手当を考慮しながら計算しなければなりません。
従業員が半休を適切に活用できるよう、残業の事前許可制を導入するのもよいでしょう。半休が取りづらいようなら、時間有給制度を取り入れるのもおすすめです。
企業側、従業員側の双方が半休制度について理解し、適切に対応できるようにしましょう。
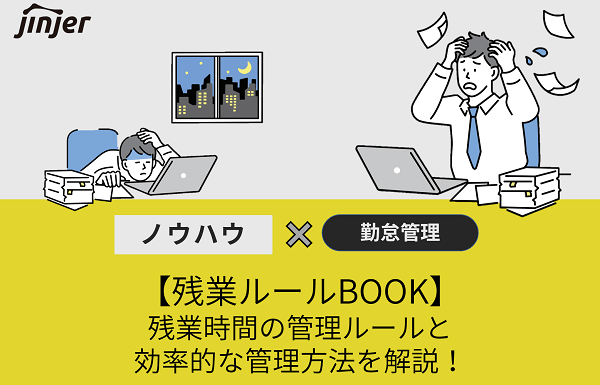
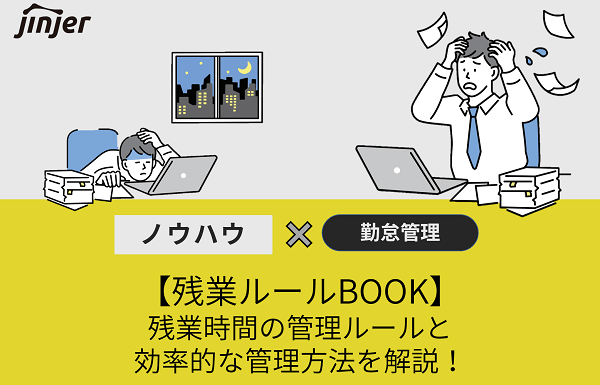
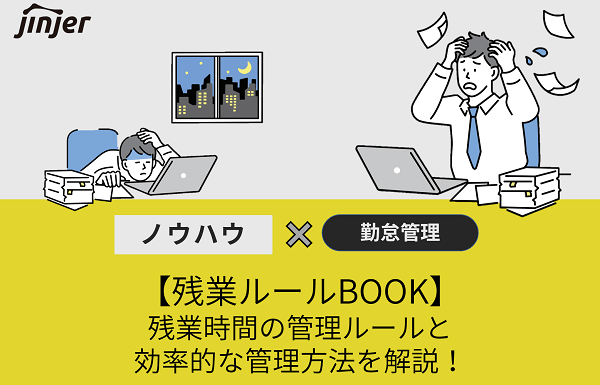
残業時間の管理や残業代の計算では、労働基準法で「時間外労働」と定められている時間を理解し、従業員がどれくらい残業したかを正確に把握する必要があります。
しかし、どの部分が割増にあたるかを正確に理解するのは、意外に難しいものです。
当サイトでは、時間外労働の定義や上限に加え、「法定外残業」と「法定内残業」の違いをわかりやすく図解した資料を無料で配布しております。
資料では効率的な残業管理の方法も解説しているため、法に則った残業管理をしたい方は、ぜひこちらから資料をダウンロードしてご活用ください。
勤怠・給与計算のピックアップ
-



有給休暇の計算方法とは?出勤率や付与日数、取得時の賃金をミスなく算出するポイントを解説
勤怠・給与計算公開日:2020.04.17更新日:2026.01.29
-


36協定における残業時間の上限を基本からわかりやすく解説!
勤怠・給与計算公開日:2020.06.01更新日:2026.01.27
-


社会保険料の計算方法とは?計算例を交えて給与計算の注意点や条件を解説
勤怠・給与計算公開日:2020.12.10更新日:2025.12.16
-


在宅勤務における通勤手当の扱いや支給額の目安・計算方法
勤怠・給与計算公開日:2021.11.12更新日:2025.03.10
-


固定残業代の上限は45時間?超過するリスクを徹底解説
勤怠・給与計算公開日:2021.09.07更新日:2025.11.21
-


テレワークでしっかりした残業管理に欠かせない3つのポイント
勤怠・給与計算公開日:2020.07.20更新日:2025.02.07
残業の関連記事
-

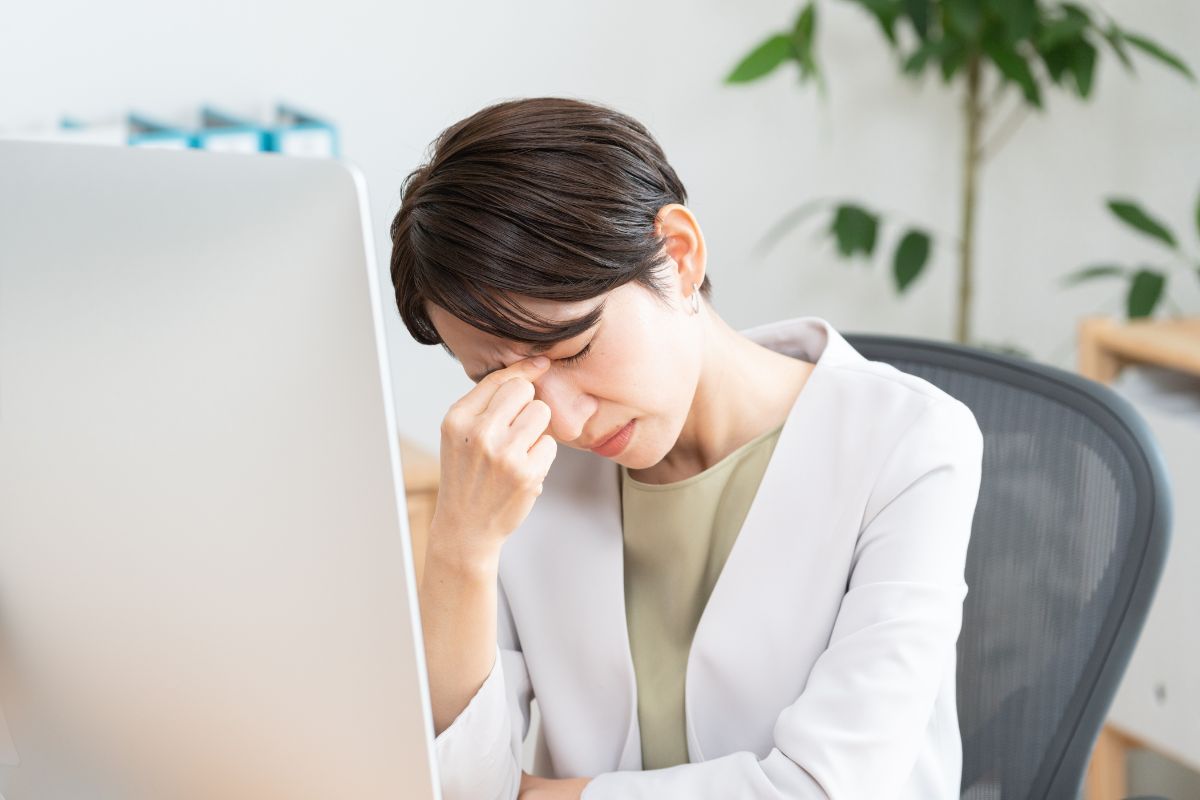
サービス残業の強要が起きていると感じたら?企業が取るべき対策を解説
勤怠・給与計算公開日:2025.08.29更新日:2025.10.07
-

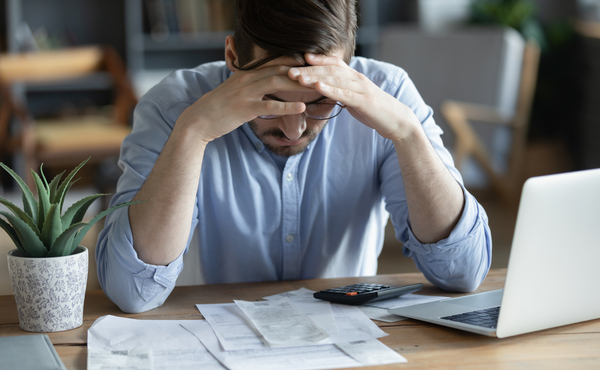
残業手当とは?時間外手当との違い、割増率と計算方法、未払い発生時の対応を解説
勤怠・給与計算公開日:2025.06.02更新日:2025.08.25
-

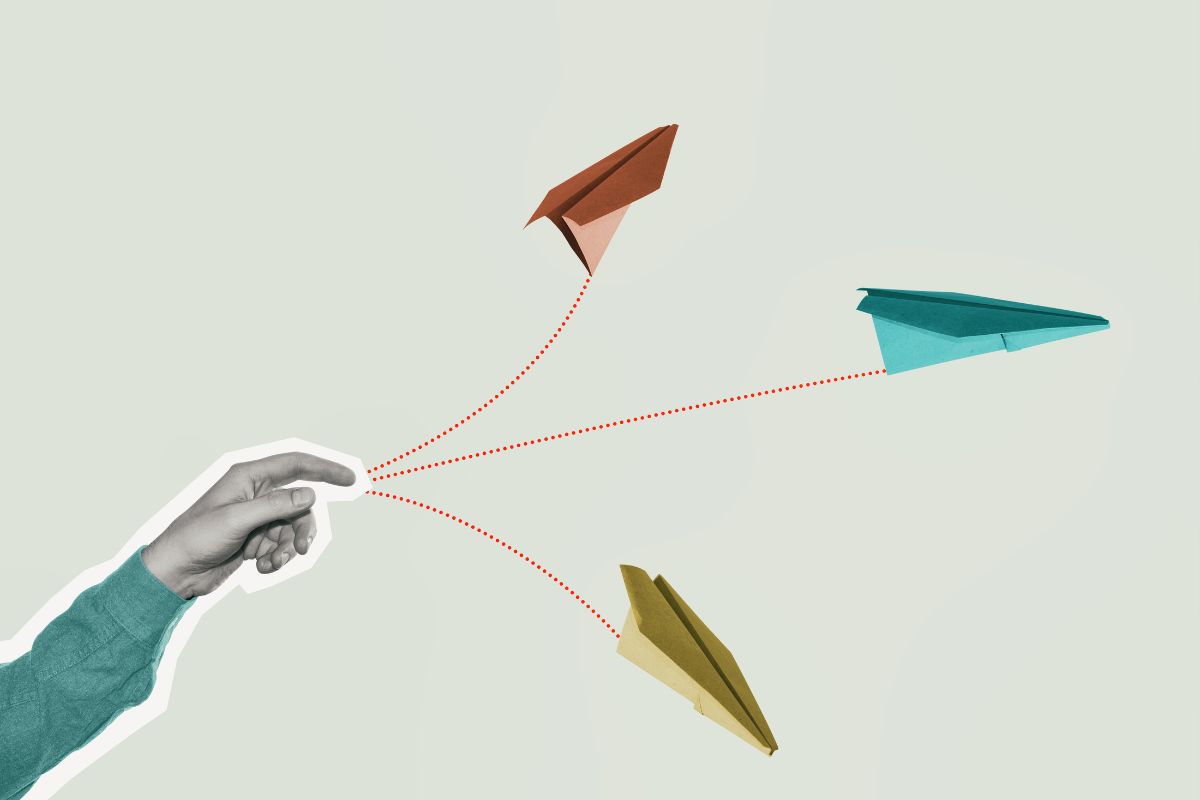
従業員は残業を拒否できる?正当な理由や解雇できる場合を解説
勤怠・給与計算公開日:2025.03.06更新日:2025.09.29