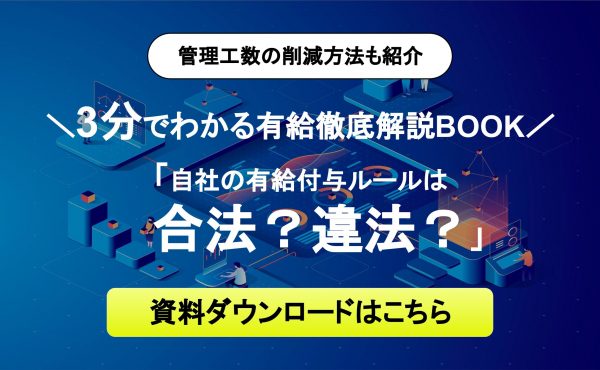時季変更権は退職時まで行使できる?認められないケースとは
更新日: 2024.5.22
公開日: 2021.11.15
MEGURO

時季変更権は、労働者から請求された有給休暇を「事業の正常な運営を妨げる場合」に限り変更できる権利です。そのため、そもそも別日に変更できない退職時などでは行使できません。
この記事では人事担当者向けに、時季変更権は退職時まで行使できるか、また、退職時までに有給休暇を取得させるべき理由、退職時以外に時季変更権が認められないケースを解説します。
「自社の年次有給休暇の付与や管理は正しく行われているのか確認したい」という方に向け、当サイトでは有給休暇の付与ルールから義務化、管理の方法まで年次有給休暇の法律について包括的にまとめた資料を無料で配布しております。
「自社の有休管理が法律的に問題ないか確認したい」「有給管理をもっと楽にしたい」という方は、ぜひこちらから資料をダウンロードしてご覧ください。
目次
1. 時季変更権は退職時まで行使できる?
時季変更権は、「事業の正常な運営を妨げる場合」のみ行使でき、別の時季に有給休暇を変更できる権利です。
そのため、退職時のように、別の時期に有給休暇を変更できないときは、行使できないものと判断されます。
1-1. 退職予定日までの全日数、有給休暇を申請されても認めざるを得ない
時季変更権はあくまでも、会社が従業員の希望とは別の時季に、有給休暇を取得させられる権利です。
そのため、解雇や退職など予定日が既に決定していれば、その日を超えた時季変更権の行使はできません。
さらに、退職予定日までの全期間、有給休暇を取得したいと申し出があれば、法律上は認めざるを得ません。
例えば、退職日まで21日しか残っておらず、21日間全て有給休暇を取得したいと申し出があれば、会社側は認めざるを得ないのが現状といえます。
1-2. 引継ぎが必要な場合であっても、時季変更権は行使できない
退職時に時季変更権を行使したい場面としては、「引継ぎが必要であるケース」が考えられます。
例えば、引継ぎを一切せず、退職までの全期間、有給休暇を取得したいと申し出があった場合。現状では、会社側はこれを拒否できないものと考えられます。
1-3. 引継ぎが必要であることを、就業規則などで定めるしかない
時季変更権では退職時の有給休暇申請日を変更できません。
引継ぎ時のトラブルを防止するためにも、以下のことをおこなう必要あるでしょう。
- 退職時には引継ぎが必要であることを、就業規則に明記する
- 事前に従業員とよく話し合い、引継ぎのスケジュールを立てておく
- 退職日の変更や、有給休暇の買い上げを打診する
なお、有給休暇の買い上げについては基本的に認められていません。
ただし、退職時など日数を消化できない場合のみ、例外的におこなわれていますが、法律上の明記はありません。
そのため、事前に従業員とよく話し合い、引継ぎを終えた後、有給休暇を取得してもらうのが理想的です。
1-4. 会社に重大な損害が発生した場合は、損害賠償請求できる可能性がある
以上のように、退職時の有給休暇取得では、たとえ引継ぎをしないとわかっていても時季変更権の行使はできないものと考えられます。
とはいえ、突然退職を申し出て故意に引継ぎをせず、その結果、会社に重大な損害が発生した場合は、当該従業員に対して損害賠償請求をおこなえる可能性は高くなります。
2. 時季変更権や計画的付与は、退職時までに行使すべき理由
時季変更権は退職予定日が決定し、さらに期間が有給消化日数と同程度では行使できません。そのため、退職時のトラブル防止の観点からも、日頃から従業員の積極的な有給休暇取得を推進するとよいでしょう。
2-1. 時季変更権は、有給休暇日の変更が可能な場合しか行使できない
時季変更権は「事業の正常な運営を妨げる場合」に、有給休暇の時季を変更できる権利です。
そのため、そもそも残りの勤務日が限られている退職時などは利用できません。
もし、時季変更権を行使したい場合は、退職前など使用が認められるときにしましょう。
2-2. 2019年4月法改正により、年5日の有給休暇取得が義務化
2019年4月の法改正により有給休暇取得が10日以上ある従業員は、年5日の有給休暇取得が義務化されました。
「自社が有給取得の義務化にきちんと対応できていないのでは」と心配な方は、当サイトで取得義務化の内容と対応方法をまとめた資料を無料で配布しておりますので、こちらよりダウンロードして義務化の内容をご確認ください。
取得に当たっては、労働者の希望を加味した上で会社が時季を指定して与えられます。(管理監督者を含む)
時季変更権の行使の前に、義務化された制度も活用しましょう。
参考:厚生労働省 | 年5日の年次有給休暇の確実な取得 わかりやすい解説
3. 退職時の有給休暇消化でトラブルにならない方法
退職時の有給休暇の取り扱いはトラブルにつながりかねません。そのため、次のようなポイントを押さえて退職時有給消化におけるトラブルの防止につなげましょう。
- 年次有給休暇の計画的付与を利用する
- 日頃から年次有給休暇を積極的に取得させる
3-1. 年次有給休暇の計画的付与を利用する
年次有給休暇の計画的付与とは、5日を超える日数に対して、会社があらかじめ付与日を決めて有給休暇を取得させられる制度です。
制度の導入には、労使協定の締結や、就業規則への明記が必要です。
計画的付与の活用により、年次有給休暇の消滅を防ぐだけでなく、退職時の一斉取得による引継ぎ拒否など、トラブル防止にも役立ちます。
3-2. 日頃から年次有給休暇を積極的に取得させる
退職時の有給取得トラブルは、日頃から年次有給休暇が取得しづらく、日数が残ってしまうことも原因でしょう。結果として退職の直前でしか消化できず、最後に一気に取得せざるを得ないと考えられます。
そのため、日頃から年次有給休暇の積極的な取得を呼びかけ、管理するとよいでしょう。
4. 退職時以外に時季変更権の行使が認められないケース
時季変更権は退職時以外にも、一定の条件下では行使できませんので注意しましょう。
4-1. 解雇予定日を超えた時季変更権の行使
退職時と同じく従業員を解雇する場合も、解雇予定日を超えた時季変更権の行使は認められていません。
なお、この場合の解雇とは普通解雇や整理解雇を指します。
そのため、会社の倒産などが決定しているときも、年次有給休暇の時季変更はできません。
また、懲戒解雇の場合、年次有給休暇は退職後に使用することができません。そのため時季変更以前に、有給休暇の処理(買い取りなど)自体が不要となります。
4-2. 失効間近の有給休暇の時季変更
年次有給休暇は付与日から2年で失効します。失効直前の年次有給休暇は、時季変更権を行使できないものとされています。
もし、有給休暇消滅後の時季を指定し変更したい場合は、失効期限を伸ばすなど、個別の対応が求められます。
4-3.「年次有給休暇の計画的付与」をしている場合
年次有給休暇の計画的付与により、あらかじめ時季を指定している場合も、時季変更権は行使できません。なお、変更は企業・従業員、どちら側からもできないものとされています。
とはいえ、企業の運営上、急な繁忙などにより正常な運営が困難なことも考えられます。
もし、計画的付与後に時季を変更したい場合は、労使協定で「業務遂行上やむを得ない事由がある場合、計画年休取得日を変更することがある」などと規定する必要があります。
4-4. 産後休業・育児休業・介護休業中の変更
年次有給休暇は厚生労働省が次のように示しているとおり、「労働の義務がある日」のみ請求できる権利です。そのため、労働の義務がない日に時季は変更できません。
6 年次有給休暇
年次有給休暇は、労働義務のある日についてのみ請求できるものであるから、育児休業申出後には、育児休業期間中の日について年次有給休暇を請求する余地はないこと。また、育児休業申出前に育児休業期間中の日について時季指定や労使協力に基づく計画付与が行われた場合には、当該日には年次有給休暇を取得したものと解され、当該日に係る賃金支払日については、使用者に所要の賃金支払の義務が生じるものであること。
例えば、本来労働義務のない育児・産後・介護休暇中に重複する時季変更は認められていません。
5. 時季変更権は退職時には使えない!日頃から有給休暇を積極的に取得させよう
時季変更権は退職時など、別時季に変更ができない状況では行使できません。また、別の休暇と重なるような時季変更もできません。
引継ぎをせず、有給休暇を一斉に消化し退職するなどのトラブル防止のためにも、有給休暇の取得を推進することも対策の一つです。
「自社の年次有給休暇の付与や管理は正しく行われているのか確認したい」という方に向け、当サイトでは有給休暇の付与ルールから義務化、管理の方法まで年次有給休暇の法律について包括的にまとめた資料を無料で配布しております。
「自社の有休管理が法律的に問題ないか確認したい」「有給管理をもっと楽にしたい」という方は、ぜひこちらから資料をダウンロードしてご覧ください。
勤怠・給与計算のピックアップ
-




【図解付き】有給休暇の付与日数とその計算方法とは?金額の計算方法も紹介
勤怠・給与計算
公開日:2020.04.17更新日:2024.03.07
-


36協定における残業時間の上限を基本からわかりやすく解説!
勤怠・給与計算
公開日:2020.06.01更新日:2024.06.04
-


社会保険料の計算方法とは?給与計算や社会保険料率についても解説
勤怠・給与計算
公開日:2020.12.10更新日:2024.07.08
-


在宅勤務における通勤手当の扱いや支給額の目安・計算方法
勤怠・給与計算
公開日:2021.11.12更新日:2024.06.19
-


固定残業代の上限は45時間?超過するリスクを徹底解説
勤怠・給与計算
公開日:2021.09.07更新日:2024.03.07
-


テレワークでしっかりした残業管理に欠かせない3つのポイント
勤怠・給与計算
公開日:2020.07.20更新日:2024.03.25