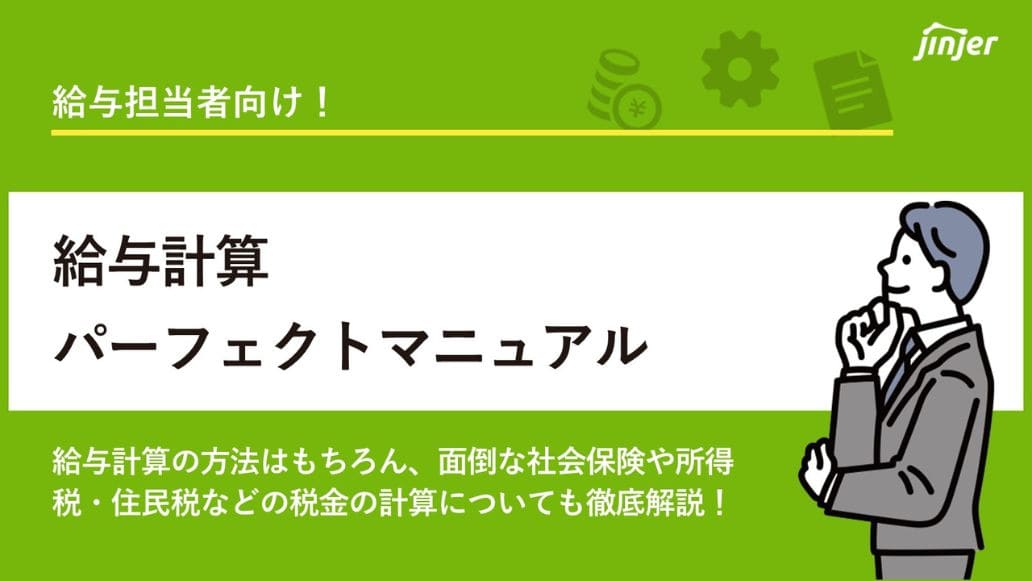退職月の給与計算の方法や仕組みを解説
更新日: 2024.4.22
公開日: 2022.2.16
OHSUGI

退職時に支払われる給与は、退職日などによって通常の給与とは計算方法が異なるケースがあります。単純に退職者が受け取れる金額ばかりでなく、保険料や住民税なども変わってくるため、間違えないように注意が必要です。
本記事では、退職月の給与計算の方法や仕組み、給与計算の注意点、社会保険の資格喪失手続きについて詳しく解説していきます。
「自社の給与計算の方法があっているか不安」
「労働時間の集計や残業代の計算があっているか確認したい」
「社会保険や所得税・住民税などの計算方法があっているか不安」
など給与計算に関して不安な方もいらっしゃるのではないでしょうか。
そのような方に向けて当サイトでは「給与計算パーフェクトマニュアル」という資料を無料配布しています。
本資料では労働時間の集計から給与明細の作成まで給与計算の一連の流れを詳細に解説しており、間違えやすい保険料率や計算方法についてもわかりやすく解説しています。
給与計算の担当者の方にとっては大変参考になる資料となっておりますので興味のある方はぜひご覧ください。
目次
1. 退職月の給与の計算方法


基本的に、給与は以下の方法で算出されます。
総支給額 – 控除額 – 税金 = 差し引き支給額
実際に受け取れるのは、控除額や税金を差し引いたあとの支給額です。この計算方法は、退職の場合でも基本は同じです。ただし、部分的に変わってくるポイントもあります。ここでは、通常の給与計算と退職時の給与計算の異なる点について、細かく見ていきましょう。
1-1. 総支給額の計算方法
まずは、総支給額の計算方法についてです。退職月の給与を計算するためには、先に月の頭から退職する日までの計算方法を定める必要があります。通常であれば、暦日または所定労働日数を基準として算出します。
締め日を月末としている企業を例として、毎月33万円の給与を受け取っている社員がいたとします。この社員が、9月20日付で退社するとした場合、暦日を基準としているのであれば、30日のうち3分の2にあたる20日まで勤務していたと考えられます。よってシンプルに計算すれば、このケースでは22万円となります。
一方、所定労働日数を基準とする場合は、出勤する予定の日数と実際に出勤した日数をベースとして算出します。たとえば先ほどの例と同じく、9月20日まで働く予定だったとして、退職するまでに14日働いていたとします。このケースの給与は、土日祝日などの休日分は含めず、1日あたりの給与を算出して日数で掛け算するので23万1,000円となります。
総支給額の計算方法はどちらが良い、正しいというものはなく、就業規則に則っておこなうため明確に定めておくことが大切です。
1-2. 控除額の計算方法
給与計算における控除額とは、社会保険料が当てはまります。社会保険料は基本的に1ヵ月ごとに発生するものなので、日割り計算はできません。加えて、毎月の給与から控除される金額は前月の分となるため、退職するタイミングによって計算方法が変わるので注意しましょう。
社会保険料の資格喪失日は退職日の翌日になるため、例えば9月30日に退職すると資格喪失日は10月1日になります。基本的には社会保険料は資格喪失日が属する月の前月分まで納めなければなりません。ここでは8月分と9月分の2ヶ月分を納めることになります。
一方、月末以外に退職したのであれば、その月の社会保険料はかからないため、前月分のみの控除となります。
だからといって社会保険料がかからないで済むわけではありません。退職した場合、当人が自ら国民健康保険や国民年金などに入ることが必須です。よって、月末以外で退職すると、退職した月の分の社会保険料は別で支払う必要があります。
当サイトでは、「給与計算パーフェクトマニュアル」という資料を無料配布しています。本資料では給与計算の基礎や手順はもちろん、間違えやすい社会保険や所得税・住民税の保険料率や計算方法についても図解形式でわかりやすく解説しています。給与計算の担当者にとっては、いつでも確認できるマニュアルとして有効に活用できますので、興味のある方はぜひこちらから資料をダウンロードしてご覧ください。
1-3. 住民税の計算方法
その年の前年の所得に対して税額を算出して、翌年の6月からさらにその翌年の5月までに納めるのが住民税です。住民税を納める方法は、普通徴収と特別徴収の2種類があります。
普通徴収の場合は、役所から届いた通知書に従って従業員が自ら納めます。特別徴収の場合は、会社が従業員に代わって納税するため注意しましょう。
2. 退職月の給与の仕組み


退職月の給与の仕組みについて、さらに詳しく見ていきましょう。
退職者の給与を大きく左右するのは社会保険料です。社会保険の資格が喪失するのは、退職日の翌日となります。例えば、5月20日が退職日であれば5月21日、5月31日に退職をするなら6月1日が社会保険資格喪失日になるということです。
つまり、20日なら4月分の社会保険料だけを控除すればいいのですが、31日の場合は4月と5月分、2ヵ月分の社会保険料を控除しなければなりません。
社会保険料は給与から天引きされるので、2ヵ月分かかればそれだけ総支給額が下がるため、社会保険料控除の仕組みを従業員にしっかり説明しておくことをおすすめします。また、退職すると自ら国民健康保険や国民年金に加入する必要があるため、このことも併せて説明しておくと良いでしょう。
3. 退職月の給与計算の注意点


退職月の給与計算方法は前述していますが、通常の給与計算方法とは異なる部分があるため、間違えてしまうこともあるかもしれません。退職する従業員であっても、給与計算は正しくおこなう必要があるので、再度注意点をチェックしておきましょう。
3-1. 退職時期によって住民税の納付方法が変わる
住民税は翌年の所得をもとに、翌月から翌々月にかけて納める必要があります。
1月1日から5月31日までに退職する場合、5月までに納めなければならない税金の残りを、給与から差し引いてまとめて納めます。もし、納税額が給与あるいは退職金を超えてしまうのであれば、納税できなくなるため残りは退職者が自ら普通徴収で納めます。
6月1日から12月31日までに退職する場合、基本的には、退職月の前月の分までを特別徴収で納めます。残りは退職者が自ら普通徴収で支払います。退職者から申し出があれば、翌年5月までに納める必要のある額を、退職金などからまとめて納税することも可能です。
3-2. 所得税は控除する
所得税は、退職月の給与計算であっても通常の計算方法で控除して問題ありません。ただし、月の途中で退職する場合は、給与所得の源泉徴収税額表の「日額表」をもとにして日割で計算するようにしてください。
また、退職する年の1月から支払った源泉徴収額は、源泉徴収票を作成して退職者に渡さなければいけません。退職者が顧問や相談役など法人の役員だった場合は、退職後1ヵ月以内に源泉徴収票を所轄の税務署と市区町村に提出する必要があるため忘れないようにしましょう。
3-3. 退職金は源泉徴収をおこなう
退職金が発生する場合は、源泉徴収をおこなう必要があります。
退職金の源泉徴収票は、退職日から1ヵ月以内に退職者に郵送することが義務づけられているため、忘れないように給与計算と一緒に作成することをおすすめします。
また、退職時に功労金や特別賞与などが発生する場合も源泉徴収が必要となるため、毎月の給与以外に発生する報酬がないかしっかり確認しましょう。
4. 退職後に給与の一部が返金となるケースとは


場合によっては、退職後に給与を一部返金しなければならないことがあります。
例えば、給与を前払いしていたのであれば、退職者に返金を求めなければなりません。前払い分の返金がないまま、月末までに退職してしまうと、余分に給与を支払ったことになります。
また、退職する予定が社内で周知されていないと、返金を求めるケースがあるので注意しましょう。退職者が意思を伝えていたとしても、給与計算をおこなう担当者に伝わっていなければ、通常通りに給与を算出し支払ってしまう場合があります。この場合は、差額の返金が必要になるので、担当者は差額を計算して退職者に返金を求めなければなりません。
5. 社会保険の資格喪失の手続きについて


従業員の退職にあたっては、社会保険の資格喪失や住民税についても速やかに手続きを済ませる必要があります。ここでは、どのような手続きが必要になるのかを紹介します。
5-1. 健康保険や厚生年金保険
健康保険や厚生年金保険に関しては、退職した次の日から5日までに必要な手続きをおこなわなければなりません。
退職者の健康保険被保険者証を回収し、被保険者資格喪失届を作成します。また、退職者に扶養家族がいる場合は、扶養家族分の健康保険被保険者証も提出する必要があります。
その他、各保険ごとに必要な書類を揃えたら、まとめて管轄の年金事務所に提出してください。窓口でも対応してくれますが、郵送による提出も可能なので管轄の年金事務所の所在地をあらかじめ確認しておくと良いでしょう。
5-2. 雇用保険
雇用保険は、退職した次の日から10日以内に手続きをおこなう必要があります。
まずは、雇用保険被保険者資格喪失届と雇用保険被保険者離職証明書を作成します。退職者に雇用保険被保険者離職証明書の内容を確認・署名をしてもらったら、2つの書類と労働者名簿や賃金台帳などの必要書類を添付して管轄のハローワークに提出します。
なお、雇用保険の保険料は毎月の報酬の額に応じて保険料率を掛けた額を徴収しているので、退職月も通常と同じく徴収してください。
5-3. 住民税
住民税は、給与所得者異動届と給与支払報告書を提出しなければなりません。
給与所得者異動届出書は、住民税を納めている役所宛に提出します。この届出書は、退職した次の月の翌月10日までという期限があるので、遅れないようにしましょう。
給与支払報告書は、基本的に他の従業員の分と合わせて年末調整後に提出しても問題ありませんが、役所によって規程が異なる場合があり、給与所得者異動届出書の提出後すぐに提出を求められることもあります。
もし、転職先があらかじめ決定しており、そこで特別徴収をおこなうのであれば、転職先に提出しましょう。
6. 退職月の給与計算の仕組みは正確に覚えておこう


退職月の給与計算は、給与のベースとなる計算方法や退職した日付によって変わってきます。合わせて国民健康保険や国民年金、住民税の異動届など必要な手続きがあることも忘れないようにしましょう。
退職時の給与計算を間違えてしまうと、再計算などの業務負担が増加したり、退職者に返金請求をしたりしなければならなくなるかもしれません。このような手間を省くためにも、退職月の給与計算の仕組みは正確に覚えておくことが重要です。とはいえ、従業員が多い場合はヒューマンエラーが起こるリスクもあるため、必要であれば給与計算システムの導入を検討してみることをおすすめします。
「自社の給与計算の方法があっているか不安」
「労働時間の集計や残業代の計算があっているか確認したい」
「社会保険や所得税・住民税などの計算方法があっているか不安」
など給与計算に関して不安な方もいらっしゃるのではないでしょうか。
そのような方に向けて当サイトでは「給与計算パーフェクトマニュアル」という資料を無料配布しています。
本資料では労働時間の集計から給与明細の作成まで給与計算の一連の流れを詳細に解説しており、間違えやすい保険料率や計算方法についてもわかりやすく解説しています。
給与計算の担当者の方にとっては大変参考になる資料となっておりますので興味のある方はぜひご覧ください。
勤怠・給与計算のピックアップ
-




【図解付き】有給休暇の付与日数とその計算方法とは?金額の計算方法も紹介
勤怠・給与計算
公開日:2020.04.17更新日:2024.03.07
-


36協定における残業時間の上限を基本からわかりやすく解説!
勤怠・給与計算
公開日:2020.06.01更新日:2024.06.04
-


社会保険料の計算方法とは?給与計算や社会保険料率についても解説
勤怠・給与計算
公開日:2020.12.10更新日:2024.07.08
-


在宅勤務における通勤手当の扱いや支給額の目安・計算方法
勤怠・給与計算
公開日:2021.11.12更新日:2024.06.19
-


固定残業代の上限は45時間?超過するリスクを徹底解説
勤怠・給与計算
公開日:2021.09.07更新日:2024.03.07
-


テレワークでしっかりした残業管理に欠かせない3つのポイント
勤怠・給与計算
公開日:2020.07.20更新日:2024.03.25