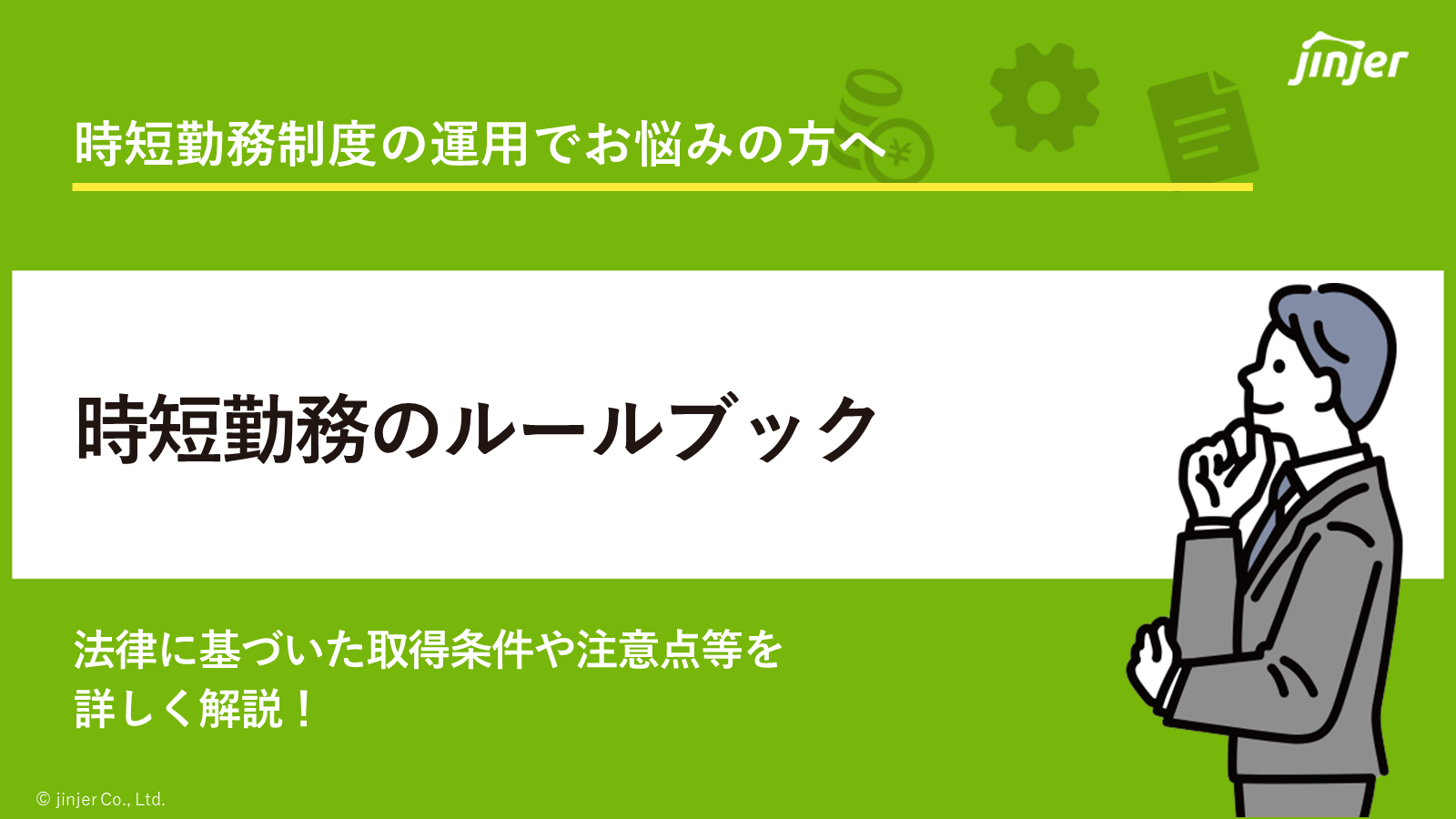時短勤務の残業時間とは?制限や企業の対応方法を解説

2009年の育児・介護休業法の改正により、全ての事業者に「時短勤務制度の実施」が義務付けられています。時短勤務は、所定労働時間を原則6時間に短縮する特殊な勤務形態になるため、残業に関しては管理職や人事担当者も扱い方に悩んでしまうかもしれません。
「時短勤務の残業は違法?」「時短勤務における残業の対応方法は?」など、時短勤務の残業に疑問がある方も多いのではないでしょうか。そこで今回は、管理職・人事担当者向けに時短勤務における残業の考え方や残業代などについて解説していきます。
▼時短勤務についてより詳しく知りたい方はこちら
時短勤務とは?導入するための手順と問題点を解説
目次
「社内で時短勤務をした例が少ないので、勤怠管理や給与計算でどのような対応が必要か理解できていない」とお悩みではありませんか?
当サイトでは、時短勤務の法的なルールから就業規則の整備、日々の勤怠管理や給与計算の方法まで、時短勤務の取り扱いについてまとめた「時短勤務のルールBOOK」を無料で配布しております。
「法律に則って時短勤務制度を運用したい」という方は、ぜひこちらから資料をダウンロードしてご活用ください。
1. 時短勤務の残業時間とは?


時短勤務における残業時間とは、所定労働時間(原則6時間)を超えて勤務した時間を指します。フルタイム勤務との違いは、1日の労働が法定労働時間の8時間を超えていなくても残業が発生する点です。
そもそも残業時間には「所定外労働」と「時間外労働」2つの考え方があります。
【所定外労働】
各企業が就業規則で定める所定労働時間を超過して勤務すること
【時間外労働】
労働基準法で定められる法定労働時間(8時間)を超過して勤務すること
実際には、所定労働時間を法定労働時間と同じ8時間で設定する企業が多く、両者を混同してしまうケースも珍しくありません。例え管理職であっても、「その日の勤務が8時間を超えなければ残業ではない」という誤った認識を持ってしまう可能性があります。
その日の就業時間が法定労働時間内であったとしても、所定労働時間を超えた場合には残業となります。そのため、時短勤務者を誤って残業させないよう、管理者・人事担当者は時短勤務における残業の定義を正しく認識しておきましょう。
2. 時短勤務における残業の可否


結論から言うと、時短勤務の従業員でも残業は可能です。従業員が了承していれば、残業をさせても違法にはなりません。ただし、残業免除を申請した従業員に対して、管理者が残業を強制することは禁止されています。
時短勤務の残業についてはわかりづらいことも多いので、ここでは時短勤務における残業の可否について解説します。
2-1. 時短勤務時の残業は違法ではない
「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」(育児・介護休業法)では、短時間勤務制度を利用している「時短勤務者」の残業に関して、一律禁止という定めは規定していません。つまり、時短勤務者に残業を命じたとしても、それが法律違反に直結するということはないため、違法ではないといえるのです。
また、労働基準法や36協定で定められた範囲内であれば、残業に伴う賃金割増は発生しますが、フルタイムの従業員と同様に法定時間外労働や深夜勤務も可能です。
ただし、「時短勤務」というのは、労働者が仕事と家庭を両立しやすくするために法律で定めている制度なので、頻繁に残業命令を出すというのは望ましくありません。
2-2. 残業免除の申請があれば強制できない
原則として、時短勤務者に残業を命じても違法にはなりませんが、残業免除を申請している従業員に対して残業を強制することはできません。これは育児・介護休業法内で規定されるものであり、免除申請をした従業員に対する残業命令は明確な法令違反となります。
なお、該当従業員が自主的に残業をおこなう場合は合法です。ただし、自主的な残業でも、従業員は育児や介護のために時短申請をしていることを忘れてはいけません。業務内容を整理して、時短勤務に合わせた適切な仕事量を割り振るなど、企業側にも残業をさせない努力が必要です。
2-3. 残業免除の申請方法
従業員が、時短勤務および残業免除を希望する場合は、原則として開始1ヶ月前までに事業主へ申請しなければなりません。申請方法は書面のほか、ファックスや電子メールなど事業主が適当と判断できる方法で、独自に定めることも可能です。
なお、残業免除申請が事業の正常な運営を妨げると判断される場合に限り、事業主が承認を拒否する権利も認められています。また、就業期間が短い従業員や所定労働日数が少ない従業員については、労使協定によって残業免除申請の対象から除外することも可能です。
3. 時短勤務の残業時間における3つの制限


残業免除を申請することで生じる制限には以下の3つがあります。
- 所定外労働の制限
- 時間外労働の制限
- 深夜残業の制限
これらの制限は適用条件が異なる部分もあるため、別々に見る必要があります。各制限のポイントを押さえ、従業員からの申請に適切に対処しましょう。
3-1. 所定外労働の制限
所定外労働の制限により、残業免除を申請した従業員に対する所定外労働の指示は禁止されています。所定外労働とは、各企業が就業規則で定める所定労働時間を超える労働のことです。時短勤務の所定労働時間は原則6時間なので、管理者は6時間以上の労働を指示してはなりません。
所定外労働の制限が適用される従業員は、3歳未満の子供を養育する従業員もしくは要介護状態の家族を抱える従業員です。請求回数に上限はなく、1回の申請につき1ヶ月以上1年未満の期間で所定外労働の制限が適用されます。
【対象となる従業員】
- 3歳に達するまでの子を養育する従業員
- 要介護状態にある対象家族を介護する従業員
【労使協定により対象除外となる従業員】
- 入社1年未満の従業員
- 1週間の所定労働日数が2日以下の従業員
【期間】
1回の請求につき1ヶ月以上1年以内の期間
【請求回数の制限】
請求できる回収に制限なし
3-2. 時間外労働の制限
時間外労働の制限により、残業免除を申請した従業員の法定時間外労働に対して「1ヶ月につき24時間」「1年につき150時間」の上限が設けられています。ただし、制限の適用条件は所定外労働の制限と同様になるため、事業主が上限を超える時間外労働を指示することはできません。
時間外労働というのは、労働基準法で定める法定労働時間(8時間)を超える労働のことです。所定労働時間が6時間の場合、6時間以上8時間以内の労働は時間外労働に含まれません。
【対象となる従業員】
- 小学校就学の始期
歳に達するまでの子を養育する従業員 - 要介護状態にある対象家族を介護する従業員
【以下に該当する労働者は対象外】
- 入社1年未満の従業員
- 1週間の所定労働日数が2日以下の従業員
- 日雇いの従業員
- 配偶者が専業主婦(夫)や育児休業中である場合等の従業員
【期間】
1回の請求につき1ヶ月以上1年以内の期間
【請求回数の制限】
請求できる回収に制限なし
3-3. 深夜残業の制限
深夜残業の制限により、残業免除を申請した従業員の深夜勤務(22時~翌5時までの就業)が禁止されています。所定外の制限と違い小学校就学前の子供を養育する従業員も対象です。免除の申請回数に制限はありませんが、適用期間は1回の請求につき1ヶ月以上6カ月以内です。
【対象となる労働者】
- 小学校就学前の子を養育する従業員
- 要介護状態にある対象家族を介護する従業員
【労使協定により対象除外となる従業員】
- 入社1年未満の従業員
- 1週間の所定労働日数が2日以下の労働者
- 日雇いの従業員
- 所定労働時間の全部が深夜にある労働者
- 以下の条件を満たす16歳以上の同居家族がいる従業員
- 保育または介護ができること
- 深夜に就労していないこと(深夜の就労日数が1か月につき3日以下の者を含む)
- 負傷、疾病又は心身の障害により保育または介護が困難でないこと
- 産前6週間(多胎妊娠の場合は14週間)、産後8週間以内の者でないこと
【期間】
1回の請求につき1ヶ月以上6ヶ月以内の期間
【請求回数の制限】
請求できる回収に制限なし
4. 時短勤務の残業代について


ここでは、時短勤務の残業代について解説していきます。
4-1. 時短勤務でも残業代を払う必要がある
時短勤務でも、法定外残業となった場合には残業代を払う必要があります。
法定外残業というのは、法定労働時間である1日8時間・週40時間を超えて働いた時間です。これは、時短勤務者でも通常勤務者でも同じで、1日8時間を超えて働いた場合は、労働基準法によって通常賃金の25%割増で支払うことが定められています。
ただし、時短勤務は6時間なので、例えば2時間残業して8時間労働となった場合は「法廷内労働」となります。このような場合は割増賃金を支払う必要はなく、通常の残業代で問題ありません。
4-2. 残業代の計算方法
時短勤務中の残業代を計算する場合は、まず「法定内労働」と「法定外労働」をわけて計算しておきましょう。
法定内残業の残業代は割増がないので、残業が2時間発生したとしても法定労働時間となる8時間を超えないため、法定内残業という扱いになります。そのため、法廷内労働の残業代は「通常の時給×法定内残業の時間」で計算します。
法定外残業の場合は、労働基準法で定められている通り25%以上の割増ありで計算しなければなりません。法定外労働時間に対する残業代は「通常の時給×法定外残業の時間×1.25」で算出してください。
時短勤務は6時間労働なので、残業の振り分けを間違えないようにすることが重要です。
5. 時短勤務の残業時間に対する企業の取り組み
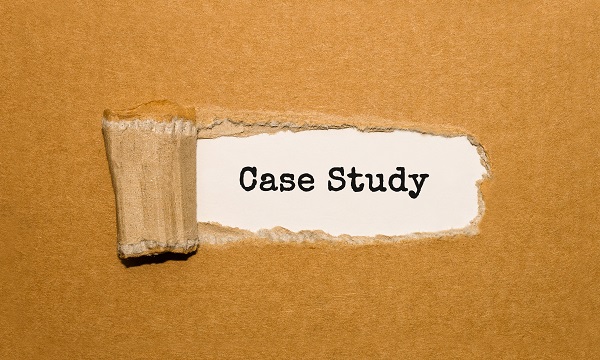
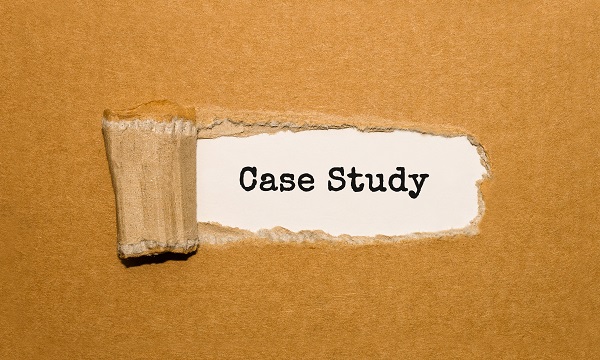
時短勤務における残業時間に対して、企業には以下の取り組みの実施が求められます。
- 管理職に時短勤務制度への理解を深めさせる
- 時短勤務・残業免除の申請手続きを明確にする
これらの取り組みをしていないと、管理者や人事担当者の時短勤務に対する認識がずれてしまい、従業員に適切な対応が取れなくなることもあります。
時短勤務は法律で定められている制度なので、同じ認識で対応できるようにしておきましょう。
5-1. 全従業員の時短勤務制度への理解を深めさせる
時短勤務制度を適切に実施するためには、全従業員が時短勤務制度に対する理解を深めることが重要です。特に管理職においては、時短勤務時の残業が違法とならないよう正しく管理することが求められます。また、従業員の時短勤務を実現するためには、チーム内でお互いフォローする体制の構築が不可欠です。
一方で、制度への理解度が低い職場では時短勤務者へのハラスメント行為(不当な残業指示、嫌がらせ行為等)が発生する可能性もあります。
従業員の妊娠や出産、育児、介護等を理由としたハラスメント行為の防止措置の実施は、男女雇用機会均等法や育児・介護休業法法令で定められた事業主の義務です。
時短勤務希望者が安心して制度を利用できるよう、全従業員に時短勤務制度の趣旨や内容を周知しましょう。
5-2. 時短勤務・残業免除の申請手続き方法を明確にする
事業主には従業員の時短勤務・残業免除申請を促すため、その手続き方法を明確にして周知することが求められます。
時短勤務制度を導入していたとしても、申請方法が不明瞭で制度を利用しにくい状態では育児・介護休業法が禁止する「従業員の不利益」に抵触する恐れがあります。
時短勤務・残業免除は、従業員に働きやすい職場を提供することが目的です。企業にとっても、育児や介護の必要性が生じた従業員の雇用を維持できるというメリットがあります。時短勤務制度はどちらにもメリットがあるので、就業規則に手続き方法を明記するなど、従業員が制度を利用しやすい環境を整えましょう。
6. 時短勤務の残業時間は適切に管理しよう


時短勤務を導入しても、基本的に残業を命令しても法令違反にはならないので、業務や他の従業員への影響を抑えることは可能です。ただし、従業員が残業免除の申請をしており、免除条件を満たしている場合は違法となってしまうため、残業は適切に管理する必要があります。
また、例え本人の同意を得た上での残業であったとしても、「家庭での育児や介護がある従業員が頻繁に残業をする」という状況は好ましくありません。時短勤務はワークライフバランスを保つための制度なので、従業員が安心して時短勤務に取り組めるよう、全従業員に対する制度の周知を徹底しましょう。
「社内で時短勤務をした例が少ないので、勤怠管理や給与計算でどのような対応が必要か理解できていない」とお悩みではありませんか?
当サイトでは、時短勤務の法的なルールから就業規則の整備、日々の勤怠管理や給与計算の方法まで、時短勤務の取り扱いについてまとめた「時短勤務のルールBOOK」を無料で配布しております。
「法律に則って時短勤務制度を運用したい」という方は、ぜひこちらから資料をダウンロードしてご活用ください。
勤怠・給与計算のピックアップ
-




【図解付き】有給休暇の付与日数とその計算方法とは?金額の計算方法も紹介
勤怠・給与計算
公開日:2020.04.17更新日:2024.03.07
-


36協定における残業時間の上限を基本からわかりやすく解説!
勤怠・給与計算
公開日:2020.06.01更新日:2024.06.04
-


社会保険料の計算方法とは?給与計算や社会保険料率についても解説
勤怠・給与計算
公開日:2020.12.10更新日:2024.07.08
-


在宅勤務における通勤手当の扱いや支給額の目安・計算方法
勤怠・給与計算
公開日:2021.11.12更新日:2024.06.19
-


固定残業代の上限は45時間?超過するリスクを徹底解説
勤怠・給与計算
公開日:2021.09.07更新日:2024.03.07
-


テレワークでしっかりした残業管理に欠かせない3つのポイント
勤怠・給与計算
公開日:2020.07.20更新日:2024.03.25