従業員が休職する場合の給与や必要な手続きをわかりやすく解説
更新日: 2025.9.29 公開日: 2024.12.29 jinjer Blog 編集部

「休職中の社員の給与や賞与は、どうなるのだろうか?」
「休職中に社員が受け取れる手当や制度には何があるのだろうか?」
上記のような悩みを抱えている社内担当者は、多いのではないでしょうか。
近年、メンタルヘルスなどに伴い、休職する人は増加傾向にあります。自社の社員が休職した際に、適切な対応をおこなえるよう正しい知識を身につけておくことが重要です。
そこで本記事では、社員が休職した際の給与・賞与の取り扱いや、休職中の社員が受け取れる手当や制度について詳しく解説します。最後まで本記事をご覧いただくことで、社員が休職した際に適切な処理を迅速におこなえるようになるでしょう。
目次
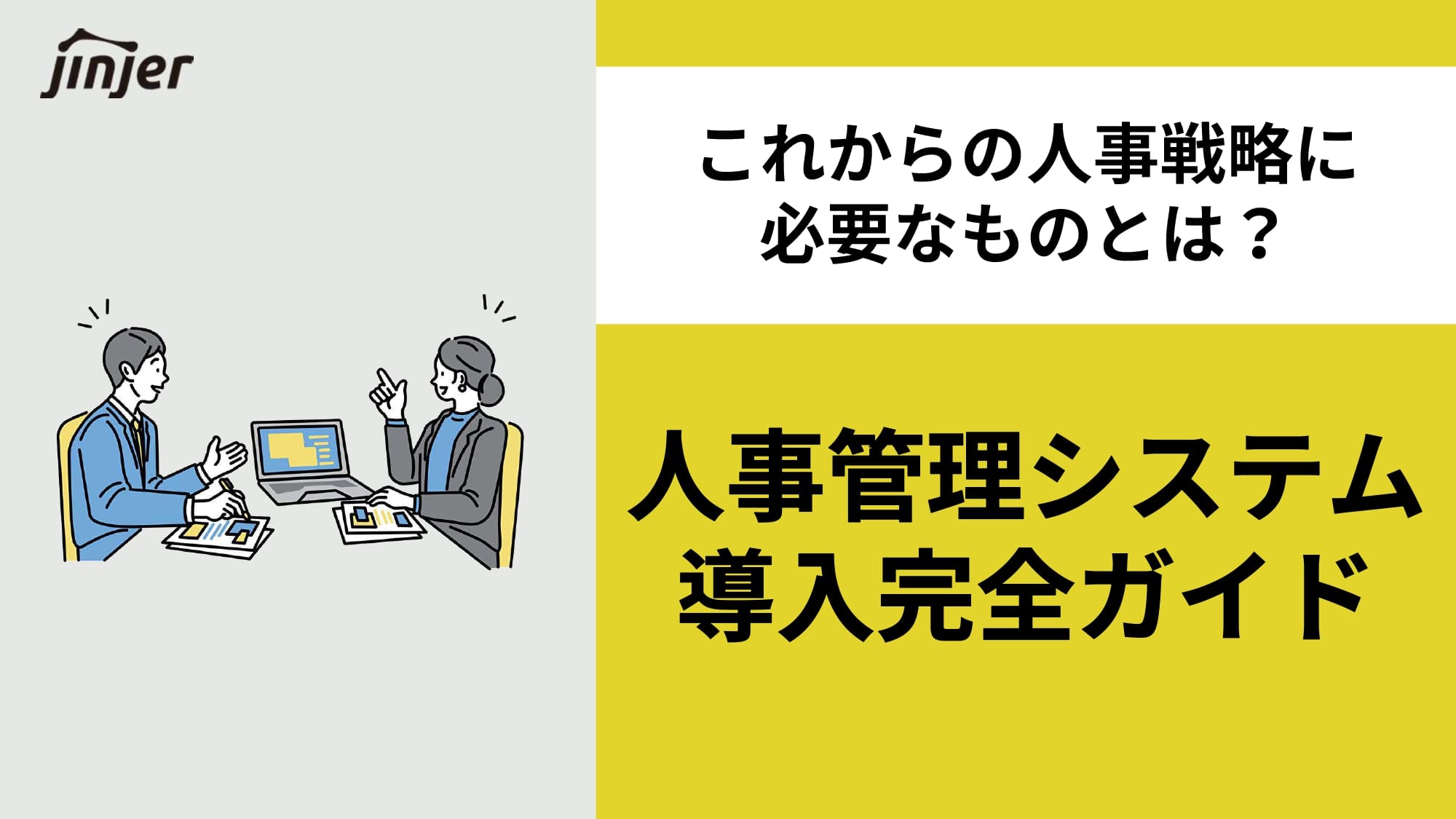
その人事データ、ただ入力するだけで終わっていませんか?
勤怠、給与、評価…それぞれのシステムに散在する従業員データを一つに集約し、「戦略人事」に活用する企業が増えています。
「これからの人事は、経営戦略と人材マネジメントを連携させることが重要だ」「従業員の力を100%以上引き出すには、データを活用した適切な人員配置や育成が必要だ」そう言われても、具体的に何から始めれば良いか分からない担当者様は多いでしょう。
そのような方に向けて、当サイトでは「人事管理システム導入完全ガイド」という資料を配布しています。
◆この資料でわかること
- 人事管理システムを活用した業務効率化の方法
- 人事データにはどのような活用価値があり、活用することで会社が得られるメリットは何か
- 正しい人事データを効率的に管理するためにはどんな機能が必要なのか
人事業務の電子化を検討している方は、ぜひこちらから資料をダウンロードしてご活用ください。
1. 休職中の給与と賞与はどうなる?


従業員が休職をした場合、その期間の給与や賞与はどうなるのか、まずは基本的な部分を確認しておきましょう。
1-1. そもそも休職とは
休職とは、企業に雇用されている労働者が何らかの事情で就業ができなくなり、その期間の労働が免除されている状態を指します。雇用契約を維持したまま、労働だけが免除されると考えておきましょう。
休職の理由はさまざまで、病気や怪我が理由の傷病休職や自己都合による休職、刑事事件で起訴された場合の起訴休職などもあります。また、他社に出向する場合に元の企業での処理を休職にする出向休職などもあります。
休職の取り扱いは企業で異なり、休職の理由によって対応が変わることもあります。
1-2. 給与と賞与は基本的に発生しない
休職にはいろいろな種類がありますが、基本的には従業員が休職中の場合、給与や賞与(ボーナス)は発生しません。給与はあくまでも労働の対価であるためです。このことは、労働基準法の第二十四条(ノーワーク・ノーペイの原則)によって明記されています。
ただし、就業規則に定められている賞与の評価期間や一定の基準を満たしている場合は、賞与が発生します。その際は、自社の賞与の評価基準と照らし合わせて適切な賞与額の支払いを忘れずにおこないましょう。
2. 休職中でも給与が発生するケース
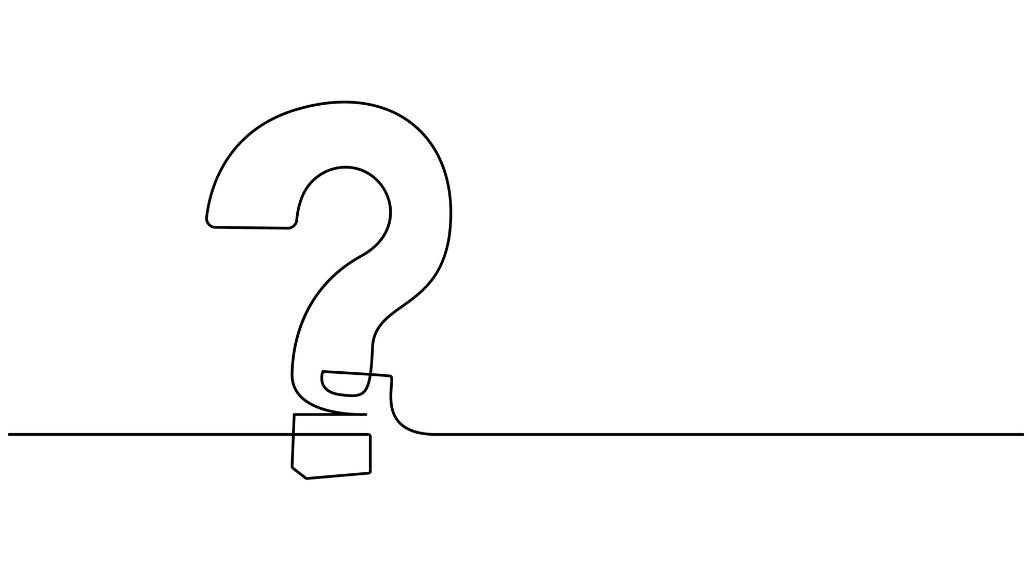
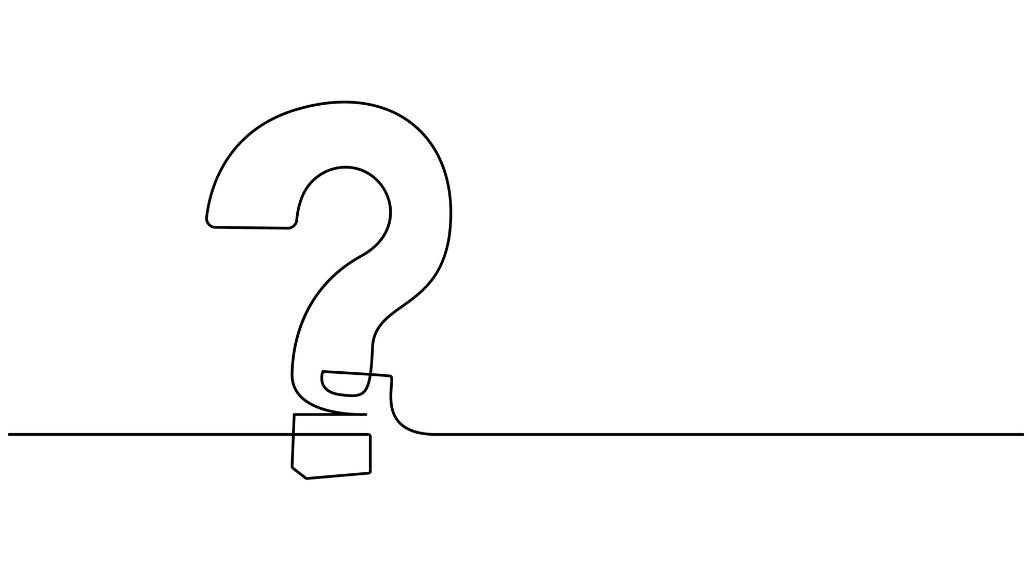
従業員が休職をした場合は、基本的に給与は発生しないとお話をしました。しかし、会社独自の制度を導入している場合や会社都合による休業となった場合は給与が発生することがあります。
2-1. 給与補償制度がある場合
企業によっては「給与保障制度」がある場合があります。給与補償制度とは、福利厚生のひとつとして企業が導入するもので、休職中でも給与の一部や全額を補償するものです。病気やプライベートな事情で「働きたくても働けない」という状況の従業員をサポートする目的で導入されるものです。
この給与補償制度がある場合はノーワーク・ノーペイの原則から外れ、休職中でも給与が支給されます。自社がどのような制度を導入しているのかを確認し、給与補償制度がある場合はその内容に沿った支給をする必要があります。
2-2. 会社都合の休業の場合は給与の6割を支給する
従業員が個人的に休職するのではなく、会社が何らかの理由で休業をする場合は給与の6割以上を「休業手当」として支給しなければなりません。これは法律で定められているものであり、企業が導入している制度や就業規則とは関係なく支給する必要があります。
企業が休業する理由は業績不振をはじめさまざまですが、いずれの場合も労働者が企業の都合によって生活が成り立たなくなる状況を回避することが目的です。
3. 休職中でも発生する社会保険料の取り扱い


休職中の給与支給に関する注意点として、社会保険料の支払い義務が挙げられます。例え社員が休職中であっても、社会保険料を支払わなくてはなりません。
社会保険料の金額は、社員が休職する前の一定期間における所得額をもとに、すでに決められているものであるためです。
また社員の休職中は、その社員自らに自己負担分の社会保険料を支払ってもらう必要があります。本来、社会保険料は毎月の給与から天引きされますが、休職中はその給与が発生しなくなるためです。
もし休職中に、社員が自ら社会保険料を支払うのが難しいときは、復帰後の給与と相殺する手段もあります。どの形が休職中の社員にとってベストなのか、話し合うことが大切です。
4. 休職中の社員が給与の代わりに受けられる手当・制度


休職中の社員が、給与の代わりに受けられる手当・制度は以下の3つです。
- 傷病手当金
- 労災保険
- 障害年金
各手当・制度について順に解説します。
4-1. 傷病手当金
傷病手当金は、病気や怪我のために会社を休職せざるを得なくなった際に支給される制度です。会社を休んでから4日目以降に、最長1年6ヵ月の間、傷病手当金が支給されます。
傷病手当金の1日あたりの支給金額の計算方法は、以下のとおりです。
支給開始日以前12ヵ月間の平均給与額÷30日×2/3=1日あたりの金額
仮に休職前の月給の平均が20万円の場合、1日あたり約4,400円(20万円÷30日×2/3)が傷病手当金として支給されます。
4-2. 労災保険
労災保険は、業務中あるいは通勤中の事故などが原因の傷病に対して、必要な給付を受けられる制度です。労災保険にかかる費用は原則、事業主が負担する保険料によってまかなわれます。
労災保険給付金には「休業補償給付」と「休業特別支給金」の2種類があります。それぞれ給与の60%、20%が受け取れるため、合計で給与の80%の補償を受けることが可能です。
また、労災保険はすべての労働者が受けられる制度です。そのため、アルバイトやパートタイマーの従業員も労災保険の対象になります。
参考:労災補償|厚生労働省
4-3. 障害年金
障害年金は、病気や怪我が原因で仕事や生活に影響を及ぼす場合に、給付を受けられる制度です。
また、障害年金は「障害基礎年金」と「障害厚生年金」の2つにわけられます。障害基礎年金と障害厚生年金の詳細は、下記に示すとおりです。
| 障害基礎年金 | 国民年金の加入者で、20歳未満もしくは60歳以上65歳未満の人が、障害等級1級または2級に該当する際に支給される。 |
| 障害厚生年金 | 厚生年金の加入者で、障害等級1級・2級・3級に該当する際に支給される。 |
障害年金は高齢の方のみならず、現役世代の方も受けられる年金であるため、これを機に要点をしっかりと押さえておきましょう。
参考:障害年金|日本年金機構
4-4. 出産や育児に関連する手当
健康保険に加入している従業員に限り、「出産手当金」と「育児休業給付金」を受け取ることができます。
出産手当金は出産前42日(多胎妊娠の場合は98日)から出産日翌日以降56日までの範囲で、給与の支払いがなかった期間に受け取れます。支給額は給与額の約3分の2です。
育児休業給付金は、出産から子どもが1歳になるまで受け取れるものです。支給額は育児休業に入ってから180日までは給与の3分の2、それ以降は給与の半分ほどです。
保育園に預けることができず職場復帰ができない場合は、子どもが2歳になる前日まで育児休業給付金の対象になります。
4-5. 介護に関連する手当
介護のために休職する場合は、「介護休業給付金」を受け取ることができます。従業員本人が雇用保険に加入していなければなりません。
介護休業給付金は、本人の配偶者・両親・子ども・祖父母・兄弟姉妹・孫・配偶者の両親の範囲内で、2週間以上介護のために休業する場合に支給されるものです。
支給額は給与の3分の2ほどで、対象になる家族1人につき93日までとされています。
5. 従業員が休職期間に入るまでの流れ


従業員が休職期間に入る場合は、事前に企業側がしなくてはならない手続きがあります。従業員からの書類提出も必要であるため、余裕をもって準備に入りましょう。
5-1. 就業規則で休職できる期間や申請方法を確認する
始めに就業規則で休職できる期間や申請方法について確認しましょう。休職に関するルールや取り扱いは、法律などで定められているわけではありません。そのため、会社の就業規則に沿って休職してもらう必要があります。
就業規則で確認するポイントは、以下の5つです。
- 休職の申請方法
- 休職できる期間
- 休職中の給料の有無
- 社会保険料の取り扱いについて
- 復帰時期
従業員が休職している間の予期せぬトラブルを防ぐためにも、就業規則は必ず確認しましょう。
5-2. 必要書類を従業員から提出してもらう
次に休職するための必要書類を従業員から提出してもらいます。必要となるのは「診断書」と「休職届」の2点です。
診断書は従業員が病気や怪我で働けない状態を客観的に理解するために必要となり、受診している医療機関から発行されます。
休職届は従業員が働けなくなった際に、雇用関係は維持したまま、業務から離れることを申請するための書類です。休職届の具体的な記載項目としては、以下のものが挙げられます。
- 氏名
- 所属部署
- 申請年月日
- 休職理由
- 休職期間
- 休職中の連絡先
もし休職届がない場合は、テンプレートなどを参考にあらかじめ作成しておきましょう。
5-3. 傷病手当金の申請をしてもらう
最後に従業員から傷病手当金の申請をしてもらいましょう。
傷病手当金の申請は従業員自ら提出してもらうことも可能ですが、会社経由で提出するのが一般的です。
傷病手当金の申請をするために必要となる書類は「全国健康保険協会」のホームページよりダウンロードできます。
5-4. 社会保険や税金の支払いについて確認する
休職中であっても社会保険料や住民税は発生します。これらの支払いが必要であることを確認し、どのように取り扱うか決めておきましょう。
休職中は各種手当を受け取れる場合でも、収入が減ってしまう人が多いです。そのため、支払いができない場合も出てくることを想定しておくとよいです。
また、休職中はすべての支払いが免除されると勘違いしているケースも少なくありません。
どのような支払いが発生するのか、なぜ発生するのかなど、従業員が納得できるように説明しましょう。
5-5. 休職中の給与や手当を決定する
会社が給与補償制度を導入している場合や、休職中でも発生する手当がある場合は就業規則を確認した上で決定します。
従業員にも伝えておけば休職したあとにトラブルになることは少ないでしょう。
担当者は休職中の人への支払いを正確に計算し、処理しなくてはなりません。休職は頻繁に発生するものではないため、対応する場合は間違いのないように進めましょう。
6. 従業員が休職中の注意点


従業員が休職中の注意点は以下の4つです。
- 連絡先を複数把握しておく
- メールやチャットで連絡する際は言葉遣いに気をつける
- 休職中の従業員の進捗確認を怠らない
- 万が一連絡を取れなかった際は証拠を残しておく
各注意点について順に解説します。
6-1. 連絡先を複数把握しておく
連絡先は念のため、複数把握しておきましょう。何かしらの理由で、教えてもらった連絡先が使えなくなる可能性がゼロとはいいきれないからです。
休職期間中であっても会社と従業員の間には雇用契約があり、雇用関係は維持されています。業務の関係上、休職中でもどうしても確認や連絡が必要な場合に対応できるようにしておくと安心です。
不測の事態に備えて、社員の家族や友人、療養先など複数の連絡先を把握しておくとよいでしょう。
6-2. メールやチャットで連絡する際は言葉遣いに気をつける
メールやチャットで連絡する際は、言葉遣いにも気をつけましょう。文章だけの場合、抑揚や声色が届かず、相手に冷たい印象を与えやすいためです。
病気や怪我で休んでいる従業員は、上司や同僚などに迷惑をかけているという後ろめたさを感じていることがあります。そんなとき、冷たい印象のメールやチャットが届くと、精神的な負担が増えてしまう可能性もあります。
必要に応じて、感嘆符や絵文字、柔らかい表現を用いるなど、言葉遣いに関しては十分に気をつけましょう。
6-3. 休職中の従業員の状況確認を怠らない
休職中の従業員の状況確認も怠らないようにしましょう。従業員の現在の状態を確認しておくことで、復職した際の適切な人員配置をおこないやすくなるためです。
また、従業員の状況を確認する際に、ヒアリングなどのメンタルケアをおこなうことで、早期復職の可能性も高まるでしょう。
ただし、頻繁な状況確認は「早く復帰してほしい」という圧力に感じられてしまうことがあります。休職中の従業員が罪悪感や焦燥感を持たないように適度な頻度を維持しましょう。
6-4. 万が一連絡を取れなかった際は証拠を残しておく
万が一、休職中の従業員と連絡を取れなかった際は、会社側がきちんと対応している証拠を残すようにしましょう。具体的には、留守番電話やメールの活用が挙げられます。
従業員に万が一のことがあった際のトラブルを防ぐためにも、証拠を残しておくことが大切です。
また、もしも連絡が取れなくなった場合はどのように対応するか社内の規定を確認しておくとよいでしょう。自然退職や解雇などの結論がありますが、処理をした後にトラブルになった場合も連絡をしていた証拠があれば有利に対応できます。
7. 休職中の給与の取り扱いを理解して適切に従業員をフォローしよう


これまでお伝えしてきたように、休職中の社員に給与は発生しません。ただし賞与については、就業規則に定められている賞与の評価期間や一定の基準を満たしている場合に限り、支払う必要があります。
また社員が休職中であっても、社会保険料を支払わなくてはなりません。そのため、社会保険料の支払いを忘れることがないよう注意が必要です。
自社の社員が休職した際は、本記事の内容をしっかりと理解したうえで、適切に処理をおこないましょう。
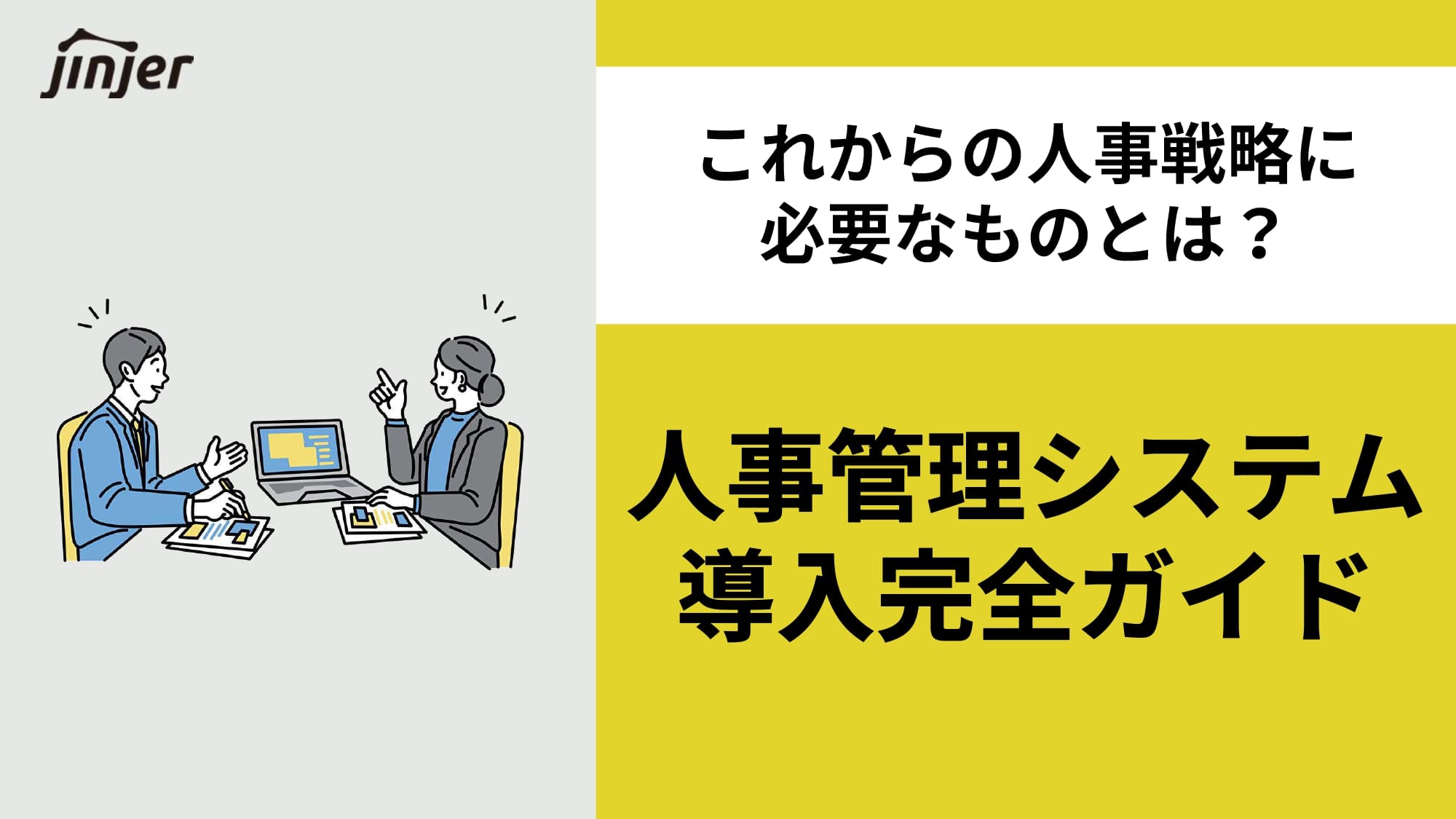
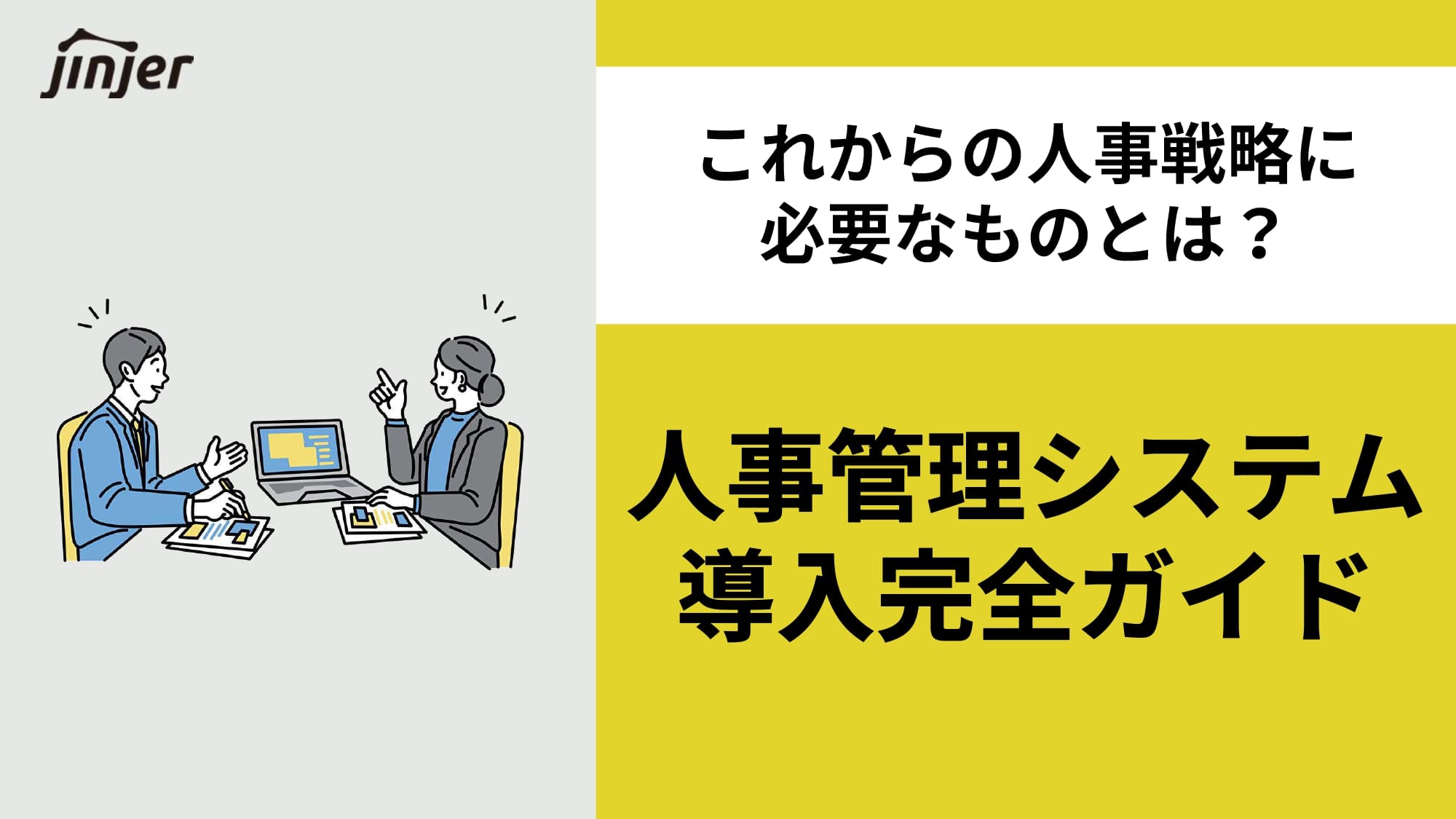
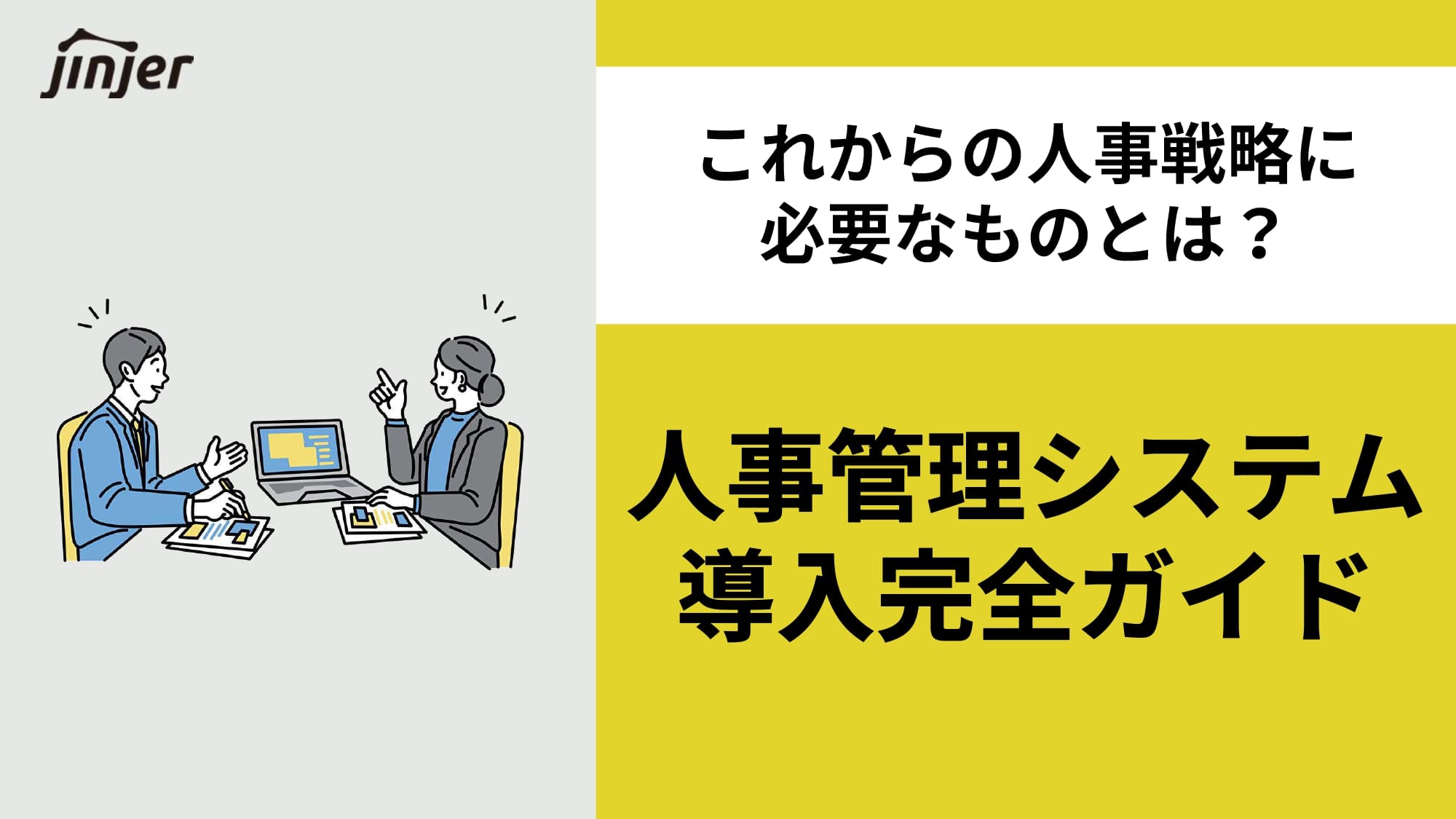
その人事データ、ただ入力するだけで終わっていませんか?
勤怠、給与、評価…それぞれのシステムに散在する従業員データを一つに集約し、「戦略人事」に活用する企業が増えています。
「これからの人事は、経営戦略と人材マネジメントを連携させることが重要だ」「従業員の力を100%以上引き出すには、データを活用した適切な人員配置や育成が必要だ」そう言われても、具体的に何から始めれば良いか分からない担当者様は多いでしょう。
そのような方に向けて、当サイトでは「人事管理システム導入完全ガイド」という資料を配布しています。
◆この資料でわかること
- 人事管理システムを活用した業務効率化の方法
- 人事データにはどのような活用価値があり、活用することで会社が得られるメリットは何か
- 正しい人事データを効率的に管理するためにはどんな機能が必要なのか
人事業務の電子化を検討している方は、ぜひこちらから資料をダウンロードしてご活用ください。
人事・労務管理のピックアップ
-


【採用担当者必読】入社手続きのフロー完全マニュアルを公開
人事・労務管理公開日:2020.12.09更新日:2026.01.30
-


人事総務担当がおこなう退職手続きの流れや注意すべきトラブルとは
人事・労務管理公開日:2022.03.12更新日:2025.09.25
-


雇用契約を更新しない場合の正当な理由とは?伝え方・通知方法も紹介!
人事・労務管理公開日:2020.11.18更新日:2025.10.09
-


社会保険適用拡大とは?2024年10月の法改正や今後の動向、50人以下の企業の対応を解説
人事・労務管理公開日:2022.04.14更新日:2025.10.09
-


健康保険厚生年金保険被保険者資格取得届とは?手続きの流れや注意点
人事・労務管理公開日:2022.01.17更新日:2025.11.21
-


同一労働同一賃金で中小企業が受ける影響や対応しない場合のリスクを解説
人事・労務管理公開日:2022.01.22更新日:2025.08.26
労務の関連記事
-


年収の壁はどうなった?2025年最新動向と人事が押さえるポイント
勤怠・給与計算公開日:2025.11.20更新日:2025.11.17
-


2025年最新・年収の壁を一覧!人事がおさえたい社会保険・税金の基準まとめ
勤怠・給与計算公開日:2025.11.19更新日:2025.12.22
-


人事担当者必見!労働保険の対象・手続き・年度更新と計算方法をわかりやすく解説
人事・労務管理公開日:2025.09.05更新日:2026.01.30






















