健康保険法とは?企業の義務や法改正のポイントをわかりやすく解説
更新日: 2025.6.30 公開日: 2025.1.31 jinjer Blog 編集部

「健康保険法とは?」
「健康保険の法改正の変更点は?」
上記のような疑問をお持ちではないでしょうか。
健康保険法は、従業員が病気やケガをした際に保険給付をおこなう健康保険制度です。企業には、一定の条件を満たす従業員を社会保険に加入させる義務が発生します。
本記事では、健康保険法の概要や目的をわかりやすく解説します。法令を遵守した経営を実現するため、企業の義務や法改正について理解を深めましょう。
目次

人事労務担当者の実務の中で、従業員情報の管理は入退社をはじめスムーズな情報の回収・更新が求められる一方で、管理する書類が多くミスや抜け漏れが発生しやすい業務です。
さらに、人事異動の履歴や評価・査定結果をはじめ、管理すべき従業員情報は多岐に渡り、管理方法とメンテナンスの工数にお困りの担当者の方もいらっしゃるのではないでしょうか。
そんな人事労務担当者の方には、Excel・紙管理から脱却し定型業務を自動化できるシステムの導入がおすすめです。
◆解決できること
- 入社手続きがオンラインで完結し、差し戻し等やりとりにかかる時間を削減できる
- システム上で年末調整の書類提出ができ、提出漏れや確認にかかる工数を削減できる
- 入社から退職まで人事情報がひとつにまとまり、紙やExcel・別システムで複数管理する必要がなくなる
システムを利用したペーパーレス化に興味のある方は、ぜひこちらから資料をダウンロードの上、業務改善にお役立てください。
1. 健康保険法とは


健康保険法の概要や目的、制定の背景は以下のとおりです。
- 健康保険法の概要
- 健康保険法の目的
- 健康保険法の制定の背景
1-1. 健康保険法とは病気やケガに対する健康保険制度
健康保険法とは、業務中以外の病気やケガが発生した場合に、保険給付をおこなう健康保険制度のことです。対象者は従業員とその家族で、亡くなった場合や出産した場合にも適用されます。
健康保険法が適用される事業者は後ほど詳しく解説しますが、企業は一定の条件を満たす従業員を健康保険に加入させなければなりません。
医療費の一部を補償し、従業員が安心して医療機関にかかれる環境を提供することが求められます。
健康保険法にもとづく正しい管理と運営は、従業員の安心感を高めるだけではなく、企業の社会的責任を果たします。
1-2. 健康保険法の目的
健康保険法の目的は、従業員とその家族の生活の安定と福祉の向上を図ることです。日本の医療保険の基盤として重要な役割を担っています。
健康保険法は、高齢化や社会経済の情勢の変化など時代のニーズに対応しなければなりません。そのため、以下のような観点から制度の見直しや改善が定期的におこなわれています。
- 保険制度の運営の効率化
- 給付内容や費用負担の適正化
- 医療の質の向上
企業は法改正に対応しながら、従業員の健康を重視した経営を心がけ、社会的責任を果たすことが求められます。
1-3. 健康保険法の制定の背景
健康保険法は、1922年に制定され1927年に施行されました。かつての日本では、健康保険の加入は任意でおこなわれており、給付額も加入者一人ひとりで異なるものでした。
健康保険法が制定された背景には、以下のような社会的・経済的な理由があります。
- 第一次世界大戦をきっかけに好景気を迎え労働者数が増加
- 第一次世界大戦後の「戦後恐慌」により不況が深刻化
- 賃金引き上げや解雇反対を求める労働運動が激化
- 労使関係の対立緩和や、社会不安の沈静化を図るために政府が社会保険制度の導入を検討
- 1922年に制定・1927年に施行
1883年に世界初の社会保険制度を導入したドイツの成功例を参考に、日本でも健康保険法が制定されました。
参考:時代のニーズに対応した社会保障制度の発展を振り返る|厚生労働省
2. 健康保険法の適用事業所


健康保険法の適用事業所は、以下のとおりです。
- 強制適用事業所
- 任意適用事業所
- 特定適用事務所
2-1. 強制適用事業所
強制適用事業所とは、健康保険法で加入が義務となっている事業所です。以下の事業所が強制適用事業所に該当します。
- すべての法人事業所
- 常時5人以上雇用している個人事業所(士業や法定16業種)
保険の加入は、事業所単位で適用されます。パートやアルバイトでも、労働時間・日数が通常の従業員の4分の3以上であれば、健康保険に加入させる義務が企業に発生します。
2-2. 任意適用事業所
任意適用事業所とは、強制適用事業所ではない事業所のことです。強制適用事業所に該当しない場合でも、以下の条件を満たすことで強制適用事業所として認められることがあります。
- 従業員の2分の1以上が適用事業所となることに同意する
- 厚生労働大臣(日本年金機構)の許諾を得る
適用事業所となった場合、基本的に事業所すべての従業員が社会保険の加入対象になります。なお、適用事業所を脱退したい場合は、被保険者の4分の3以上の同意と、厚生労働大臣の認可が必要です。
2-3. 特定適用事業事務所
特定適用事業所とは、適用事業所の中でも1年のうち6ヵ月以上にわたって厚生年金保険の被保険者が常時51人以上になることが見込まれる事業所のことを指します。「従業員の総数」としてカウントする対象は、以下の条件を満たしている従業員です。
- フルタイムで勤務している従業員
- 週および月の労働日数がフルタイムの従業員の4分の3以上の従業員
条件を満たしていれば、パートやアルバイトなどの短時間労働者も社会保険の加入対象に含まれます。そのため企業は、対象となる従業員を把握しておかなければなりません。
参考:短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用の拡大|日本年金機構
3. 健康保険法における企業の義務


健康保険法において強制適用事業所に該当する企業は、状況に応じて必要な手続きをしなければなりません。以下のケースごとに、それぞれの義務を解説します。
-
- 新たに適用事業所になった場合
- 任意適用事業所の場合
- 従業員の新規雇用や扶養家族に変更があった場合
- 特定適用事業所の場合
3-1. 新たに適用事業所になった場合
新たに適用事業所になった場合、「健康保険・厚生年金保険新規適用届」を、管轄の年金事務所に届出なければなりません。詳細は以下のとおりです。
| 項目 | 詳細 |
| 提出書類 | 健康保険・厚生年金保険 新規適用届 |
| 添付書類 | 法人事業の場合:法人(商業)登記簿謄本の原本
国や地方公共団体の場合:法人番号指定通知書のコピー 強制適用事業所の場合:事業主の世帯全員の住民票の原本(個人番号の記載なし) |
| 提出期限 | 適用事業所になった日から5日以内 |
| 提出先 | 事業所を管轄する年金事務所 |
| 提出方法 | 郵送・窓口持参・電子申請 |
適用事業所になってから提出期限が短いため、手続きを忘れないように注意しましょう。
3-2. 任意適用事業所の場合
任意適用事業所の場合、「任意適用申請書」を企業の管轄の年金事務所に提出し、厚生労働大臣に認可してもらわなければなりません。詳細は以下のとおりです。
| 項目 | 詳細 |
| 提出書類 | 健康保険・厚生年金保険 新規適用届 |
| 添付書類 | ・任意適用同意書
・事業主の世帯全員の住民票の原本(コピー不可・個人番号の記載なし) ・事業主が納めた1年分の公租公課の領収書 |
| 提出期限 | 従業員の半数以上の同意後すみやかに |
| 提出先 | 事業所を管轄する年金事務所 |
| 提出方法 | 郵送・窓口持参・電子申請 |
認可後は、強制適用事業所と同様に保険料を計算し、納付を適切におこなう義務が発生します。
3-3. 従業員の新規雇用や扶養家族に変更があった場合
従業員の新規雇用や、その扶養家族に変更があった場合も日本年金機構への届け出が必要です。詳細は以下のとおりです。
| 提出が必要なケース | 従業員を新規雇用した場合 | 被保険者の扶養家族に変更があった場合 |
| 提出書類 | 健康保険・厚生年金保険者資格取得届 | 健康保険被扶養者異動 |
| 提出期限 | 入社日から5日以内 | 事実発生から5日以内 |
それぞれ提出書類が異なるため注意しましょう。
3-4. 特定適用事業所の場合
特定適用事業所となった場合も、日本年金機構への届け出が必要です。対象となった事業所には、日本年金機構から「特定適用事業所に関する重要なお知らせ」が届きます。詳細は以下のとおりです。
| 項目 | 詳細 |
| 提出書類 | 特定適用事業所該当届 |
| 添付書類 | 新たに被保険者資格を取得する短時間労働者がいる場合:被保険者資格取得届 |
| 提出期限 | 事実発生から5日以内 |
| 提出先 | 事業所を管轄する年金事務所 |
| 提出方法 | 郵送・窓口持参 |
なお、被保険者の総数が50人以下となった場合、「特定適用事業所不該当届」を提出すれば特定適用事業所から外されます。要件を満たさなくなった時点で提出可能ですが、被保険者の4分の3以上の同意が必要です。
4. 法改正の影響


健康保険法は定期的に法改正されているため、常に最新の情報を把握しておきましょう。
ここでは2020年、2024年の法改正による影響について解説します。
4-1. 【2020年】年金制度改正による社会保険加入の対象者の拡大
2020年に年金制度が改正されたことで、2024年10月より、社会保険の加入対象者が以下のように拡大されました。
| 社会保険の適用対象者 | |
| 改正前 | 従業員数が常時101人以上の企業 |
| 改正後 | 従業員数が常時51人以上の企業 |
さらに、短時間労働者への適用も拡大されました。1週間の所定労働時間、もしくは1ヵ月の所定労働日数が通常の従業員の労働者の4分の3未満であっても、以下の条件に該当する従業員は適用対象者に該当します。
- 週の所定労働時間が20時間以上
- 所定内賃金が月額8万8,000円以上
- 学生ではない
パートやアルバイトなど雇用形態にかかわらず、条件を満たしている場合は社会保険に加入させる義務が発生します。
参考:短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用の拡大|日本年金機構
4-2. 【2024年】健康保険法改正による影響
健康保険法は2023年に改正案が可決成立し、2024年4月1日より施行されています。この改正による影響は次のとおりです。
- 出産育児一時金の引き上げ
- 後期高齢者医療制度の保険料上限の段階的な引き上げ見通し
- 医療保険制度の基礎強化
4-2-1. 出産育児一時金の引き上げ
健康保険の被保険者もしくは被扶養者の出産時には出産育児一時金が支給されます。従来は条件に応じて42万円が支給されていました。
しかし、法改正によっては一時金が50万円までに引き上げられています。
4-2-2. 後期高齢者医療制度の保険料上限の段階的な引き上げ見通し
高齢化の進展により医療費が増大する中、後期高齢者医療制度を安定的に運営するために、保険料の上限が段階的に引き上げられる方針が検討・実施されています。引き上げによって生じた税収は出産育児一時金の財源に充てられる予定です。
4-2-3. 医療保険制度の基礎強化
医療保険制度の持続可能性を確保するための基盤強化が進められています。具体的には、都道府県の医療費適正化計画や保険者協議会の導入、国民健康保険を運営する方針の法定化などが予定されています。
4-3. 法改正における企業の注意点
法改正により社会保険加入の対象者が拡大したため、企業は新たな対象者を把握し、加入の手続きをおこなわなければなりません。
正当な理由がなく、加入の手続きをおこなわなければ、ペナルティを課せられる可能性があるため注意が必要です。
とくに、パートやアルバイトの従業員の加入義務が強化されたことを忘れないようにしましょう。企業は、従業員の勤務時間や給与などの条件を正確に確認し、迅速に手続きを進めることが求められます。
さらに、社会保険制度は今後も法改正がおこなわれる可能性があるため、最新の情報を常に確認し、適切に対応することが大切です。
5. 健康保険制度における給付の仕組みと範囲


健康保険を把握するうえでは、給付内容を正しく理解することも重要です。健康保険制度では、被保険者(従業員)やその被扶養者が病気やケガをした際にかかる医療費の一部を給付する仕組みが整えられており、実際にかかった医療費の一部負担や働けない期間の生活を保障する給付が整備されています。
5-1. 保険給付の種類
保険給付の種類として以下が挙げられます。
- 療養の給付
- 傷病手当金
5-1-1. 療養の給付
療養の給付は、被保険者本人やその被扶養者が病気やケガなどの治療で医療機関を受診した際、一定の自己負担割合を差し引いた残りを健康保険が負担してくれる制度です。具体的には、医療機関での診察や検査など治療にかかる費用がカバーされます。自己負担割合は一般的に3割ですが、年齢や所得区分によって2割または1割となる場合もあります。また、医療費が高額になる場合は、高額療養費制度によって自己負担額の上限が設けられており、多額の出費を防ぐことができます。
5-1-2. 傷病手当金
傷病手当金は、業務外の病気やケガによって従業員が仕事を続けられなくなり、給与が支給されない、または減額されている期間の生活を補償するために設けられた給付です。具体的には、休業4日目から最長1年6ヵ月間、健康保険加入時に設定される報酬の基準額である標準報酬日額の3分の2相当額が支給されます。支給を受けるには、医師の診断書などの証明書類が必要となり、休業期間に関しても条件を満たしていることの証明が必要です。
6. 健康保険法に違反した場合の罰則
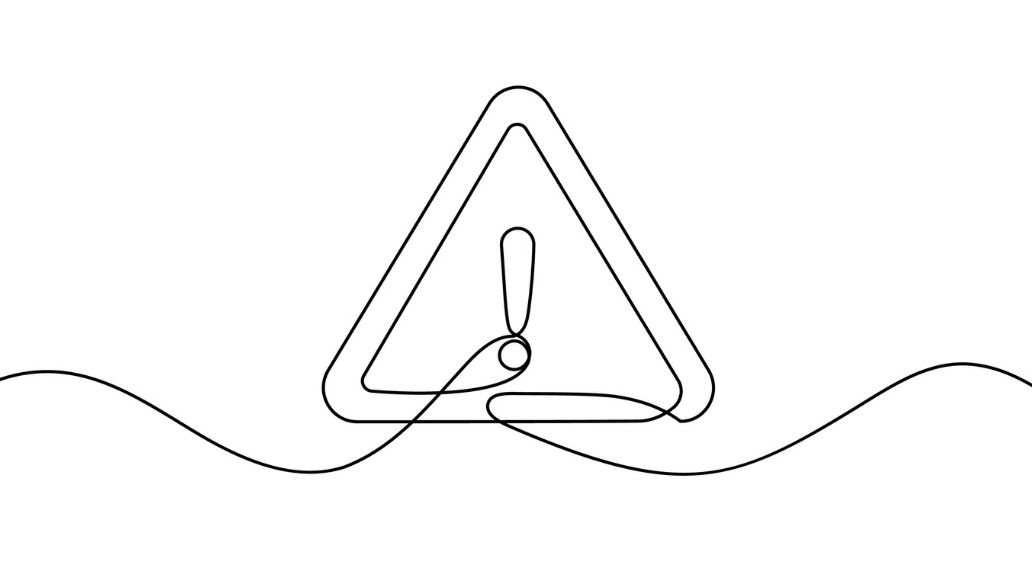
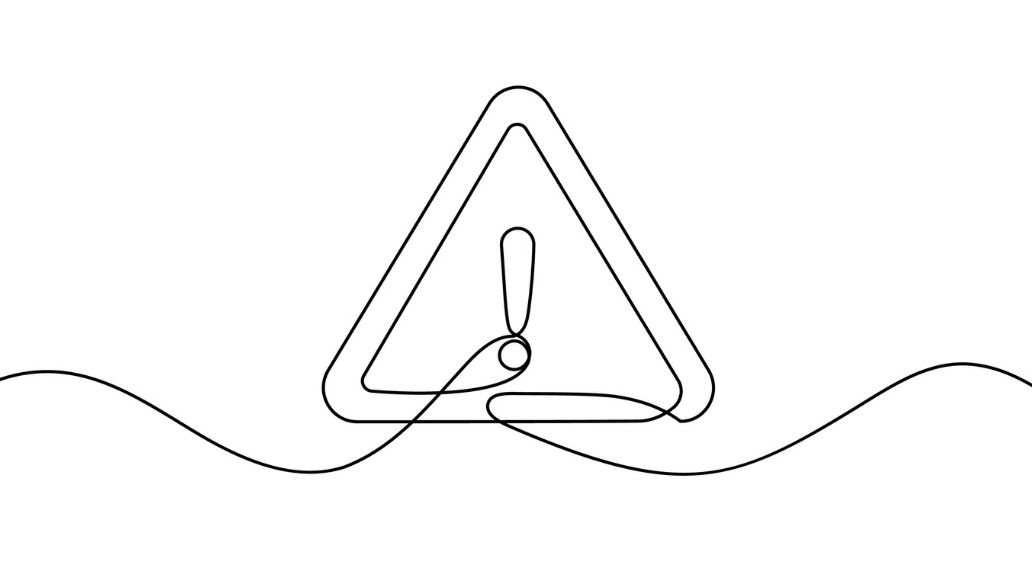
健康保険法に違反してしまうと、罰則が科せられてしまいます。そのため、法令を遵守した運用を心がけましょう。
ここでは健康保険法に違反した場合の罰則について解説します。
6-1. 届出をせず納付しなかった場合
事業主は被保険者の資格の取得および喪失などについて、健康保険事業の運営主体である保険者に届け出る必要があります。届出をしなかった場合、6カ月以下の懲役または50万円以下の罰則が科せられかねません。さらに、保険料を納付しなかった場合も同様の罰則を科せられる恐れがあります。
6-2. 虚偽の報告をした場合
事業主が虚偽の報告や証明によって保険給付を得ていた場合、運営主体である保険者は事業主に給付額の全額もしくは一部の納付を命令可能です。
給付額の全額もしくは一部の納付命令を受けるのは事業主だけではありません。保険給付を受けた者(従業員)も対象です。
7. 社会保険についての業務を改善する方法
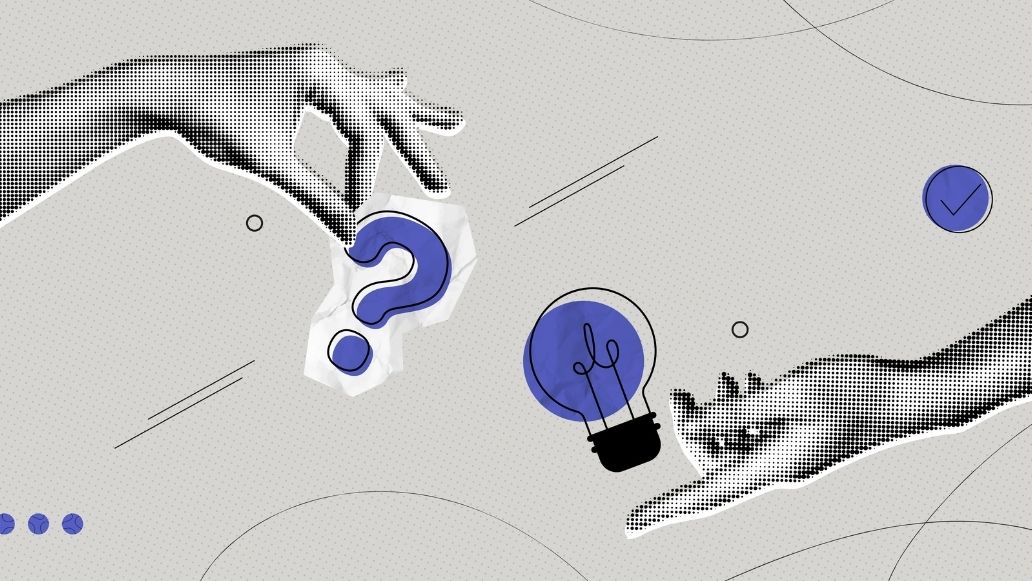
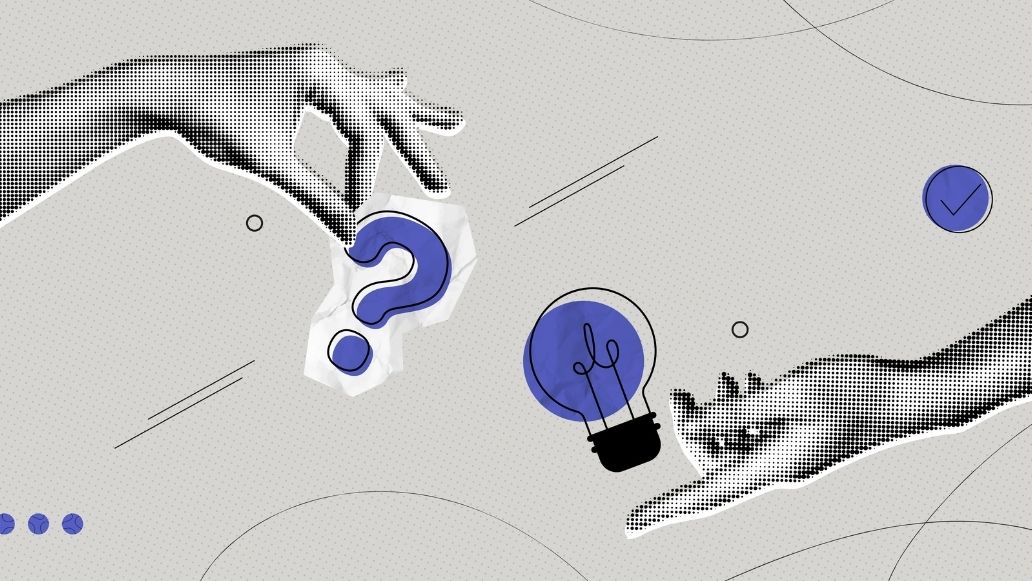
社会保険に関する業務は、被保険者資格の取得・喪失手続きや保険料の納付管理など、正確性とスピードが求められます。自社の社会保険にまつわる業務を改善するのであれば、専用のツール導入を検討しましょう。
専用のツールを導入すれば、自動化によって作業時間の削減とヒューマンエラーの低減が期待できます。また、ツールを活用することで最新の法令にもスムーズに対応可能です。
8. 健康保険法に則った経営を心がけよう


強制適用事業所の企業は、従業員を健康保険に加入させる義務があります。また、2024年からは、社会保険加入対象者が大幅に拡大されました。
アルバイトやパートなどの短時間労働者も対象になる可能性があるため、企業は対象者を把握し、適切な手続きをおこなわなければなりません。違反してしまうと罰則が科せられてしまいます。
社会保険については定期的に法改正がされていて、今後も法改正がおこなわれる可能性は十分に考えられるため、最新情報を確認し、健康保険法に則った経営を心がけましょう。
社会保険に関する業務を効率化するのであれば、専用のツールを導入しましょう。専用ツールを導入すればヒューマンエラーのリスク削減や最新法令にもスムーズに対応可能です。



人事労務担当者の実務の中で、従業員情報の管理は入退社をはじめスムーズな情報の回収・更新が求められる一方で、管理する書類が多くミスや抜け漏れが発生しやすい業務です。
さらに、人事異動の履歴や評価・査定結果をはじめ、管理すべき従業員情報は多岐に渡り、管理方法とメンテナンスの工数にお困りの担当者の方もいらっしゃるのではないでしょうか。
そんな人事労務担当者の方には、Excel・紙管理から脱却し定型業務を自動化できるシステムの導入がおすすめです。
◆解決できること
- 入社手続きがオンラインで完結し、差し戻し等やりとりにかかる時間を削減できる
- システム上で年末調整の書類提出ができ、提出漏れや確認にかかる工数を削減できる
- 入社から退職まで人事情報がひとつにまとまり、紙やExcel・別システムで複数管理する必要がなくなる
システムを利用したペーパーレス化に興味のある方は、ぜひこちらから資料をダウンロードの上、業務改善にお役立てください。
人事・労務管理のピックアップ
-


【採用担当者必読】入社手続きのフロー完全マニュアルを公開
人事・労務管理公開日:2020.12.09更新日:2026.01.30
-


人事総務担当がおこなう退職手続きの流れや注意すべきトラブルとは
人事・労務管理公開日:2022.03.12更新日:2025.09.25
-



雇用契約を更新しない場合の正当な理由とは?伝え方・通知方法も紹介!
人事・労務管理公開日:2020.11.18更新日:2025.10.09
-


社会保険適用拡大とは?2024年10月の法改正や今後の動向、50人以下の企業の対応を解説
人事・労務管理公開日:2022.04.14更新日:2025.10.09
-


健康保険厚生年金保険被保険者資格取得届とは?手続きの流れや注意点
人事・労務管理公開日:2022.01.17更新日:2025.11.21
-


同一労働同一賃金で中小企業が受ける影響や対応しない場合のリスクを解説
人事・労務管理公開日:2022.01.22更新日:2025.08.26
労務の関連記事
-


年収の壁はどうなった?2025年最新動向と人事が押さえるポイント
勤怠・給与計算公開日:2025.11.20更新日:2025.11.17
-


2025年最新・年収の壁を一覧!人事がおさえたい社会保険・税金の基準まとめ
勤怠・給与計算公開日:2025.11.19更新日:2025.12.22
-


人事担当者必見!労働保険の対象・手続き・年度更新と計算方法をわかりやすく解説
人事・労務管理公開日:2025.09.05更新日:2026.01.30





















