厚生年金の44年特例とは?受給要件や手続き方法をわかりやすく解説
更新日: 2025.7.11 公開日: 2025.2.2 jinjer Blog 編集部
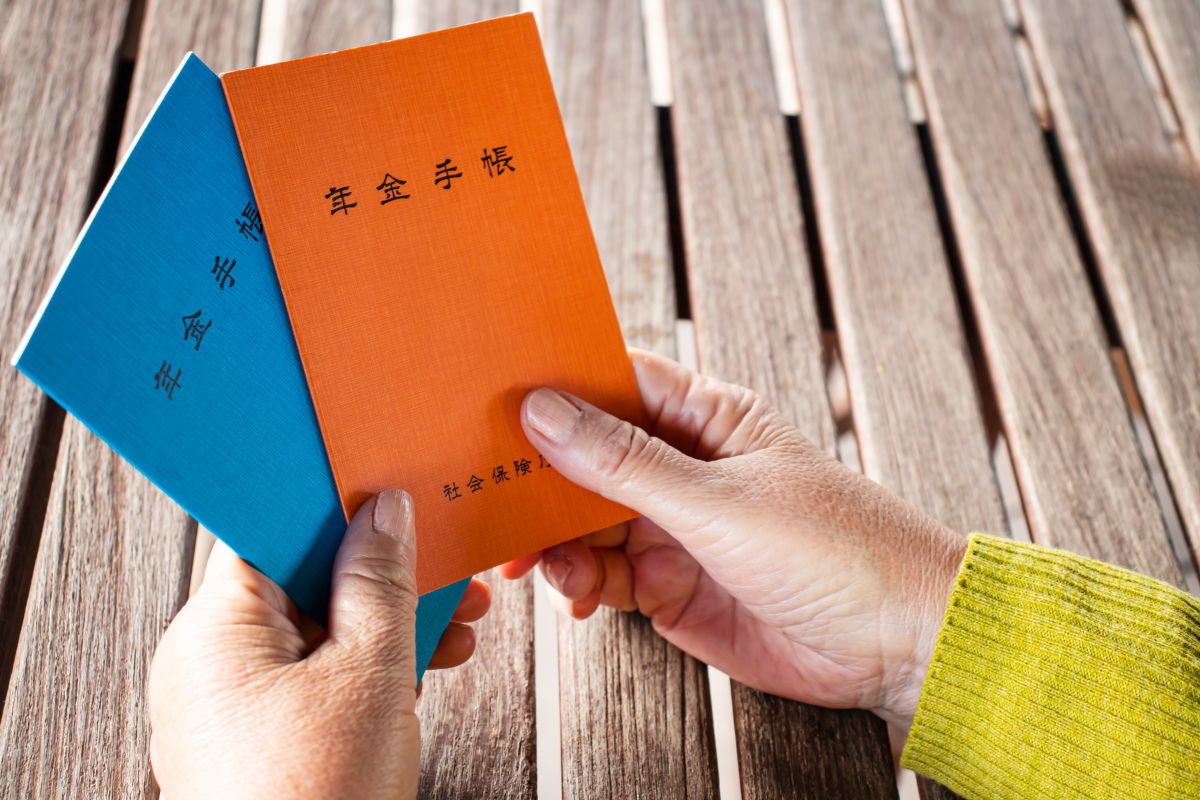
「44年特例とは?」
「対象になるのはどのような人?」
「どれくらい年金が増えるの?」
上記のような疑問をお持ちではありませんか。
44年特例は長きにわたって厚生年金に加入した方を対象に、上乗せして年金を受け取れる制度です。
本記事では44年特例の対象となる方の要件や手続きの方法、メリットなどを解説します。受給金額についても解説しているため、ぜひ最後までご覧ください。
目次

人事労務担当者の実務の中で、従業員情報の管理は入退社をはじめスムーズな情報の回収・更新が求められる一方で、管理する書類が多くミスや抜け漏れが発生しやすい業務です。
さらに、人事異動の履歴や評価・査定結果をはじめ、管理すべき従業員情報は多岐に渡り、管理方法とメンテナンスの工数にお困りの担当者の方もいらっしゃるのではないでしょうか。
そんな人事労務担当者の方には、Excel・紙管理から脱却し定型業務を自動化できるシステムの導入がおすすめです。
◆解決できること
- 入社手続きがオンラインで完結し、差し戻し等やりとりにかかる時間を削減できる
- システム上で年末調整の書類提出ができ、提出漏れや確認にかかる工数を削減できる
- 入社から退職まで人事情報がひとつにまとまり、紙やExcel・別システムで複数管理する必要がなくなる
システムを利用したペーパーレス化に興味のある方は、ぜひこちらから資料をダウンロードの上、業務改善にお役立てください。
1. 厚生年金の44年特例とは?


44年特例とは、厚生年金に44年以上加入した人を対象に、年金を上乗せして支給する制度です。正式名称は長期加入者特例といいます。
2000年の年金制度改正で、年金の支給開始年齢が60歳から65歳に引き上げられました。この変更により、60歳から受け取れる予定だった一部の年金が支給されないケースが生じています。
救済措置として特別支給の老齢厚生年金が設けられましたが、特に加入期間が長い人は不公平感が生じる内容でした。この問題を解消するために設けられたのが44年特例です。
一定の要件を満たすと、特別支給の老齢厚生年金に加えて44年特例部分が支給されます。長く加入者した方への特別な配慮として、老後の生活をより手厚く支える制度です。
2. 44年特例の対象となる人・受給要件


44年特例の対象となる人、受給要件は以下の3つです。
- 特別支給の老齢厚生年金を受給できること
- 厚生年金保険の被保険者期間が44年以上あること
- 厚生年金の被保険者資格を喪失していること
それぞれの内容を詳細に解説していきます。
2-1. 特別支給の老齢厚生年金を受給できること
44年特例は、特別支給の老齢厚生年金を受給できる必要があります。その条件は下記の生年月日の要件を満たしている事です。
| 男性 | 1961年(昭和36年)4月1日以前に生まれた方 |
| 女性 | 1966年(昭和41年)4月1日以前に生まれた方※ただし公務員は除く |
公務員の方を除き、女性は男性より5年遅れで支給開始年齢が設定されているため注意が必要です。
補足として、2024年時点で男性は62歳以下、女性は57歳以下の方は今後も44年特例の対象外となります。特別支給の老齢厚生年金を受給できない世代に該当しているため、歳を重ねても44年特例の支給はありません。
2-2. 厚生年金保険の被保険者期間が44年以上あること
44年以上厚生年金保険に加入していることも、要件の一つです。そのため、個人事業主など厚生年金に加入していない方は対象外となります。
また、以下のように4種類ある厚生年金のうち、どれか一つに44年以上加入していなければなりません。
| 厚生年金の種類 | 対象者例 |
| 第1号厚生年金被保険者 | 会社員 |
| 第2号厚生年金被保険者 | 国家公務員 |
| 第3号厚生年金被保険者 | 地方公務員 |
| 第4号厚生年金被保険者 | 私立学校職員 |
そのため、例えば会社員を20年、転職して地方公務員として24年勤務した方は対象外となります。合計44年厚生年金に加入していますが、同じ種類のものではないからです。ただし、A社で会社員20年、転職してB社で会社員24年の場合、同じ種類の厚生年金に44年加入しているため対象となります。
2-3. 厚生年金の被保険者資格を喪失していること
厚生年金の被保険者資格を喪失していることも44年特例受給要件の一つです。そもそも、厚生年金の被保険者とは以下全てに該当する方を指します。
- 週の勤務時間が20時間以上
- 給与が月額88,000円以上
- 2カ月を超えて働く予定がある
- 学生ではない
上記に該当しない、つまり会社を退職している方が、被保険者資格喪失の要件を満たします。ほかの条件を満たしていても、会社員として働いている方は44年特例の対象外です。
一方、退職後にパートやアルバイトとして働いていても、88,000円以上を超えていない方は44年特例の対象となります。
参考:社会保険加入のメリットや手取りの額の変化について|社会保険適用拡大特設サイト
3. 44年特例の受給金額


44年特例で受け取れる金額は、以下の計算式で求められます。
受給金額 = 1,701円 × 1.000 × 被保険者期間(月数)
※昭和31年4月1日以前生まれの方は、1,701円ではなく1,696円が基準額
ただし、被保険者期間の月数は上限が480月(40年)と定められています。上限で計算すると以下の通りです。
816,480円 = 1,701円 × 1.000 × 480月
この約81万円が、44年特例の受給金額です。
4. 44年特例を受けるメリットとデメリット
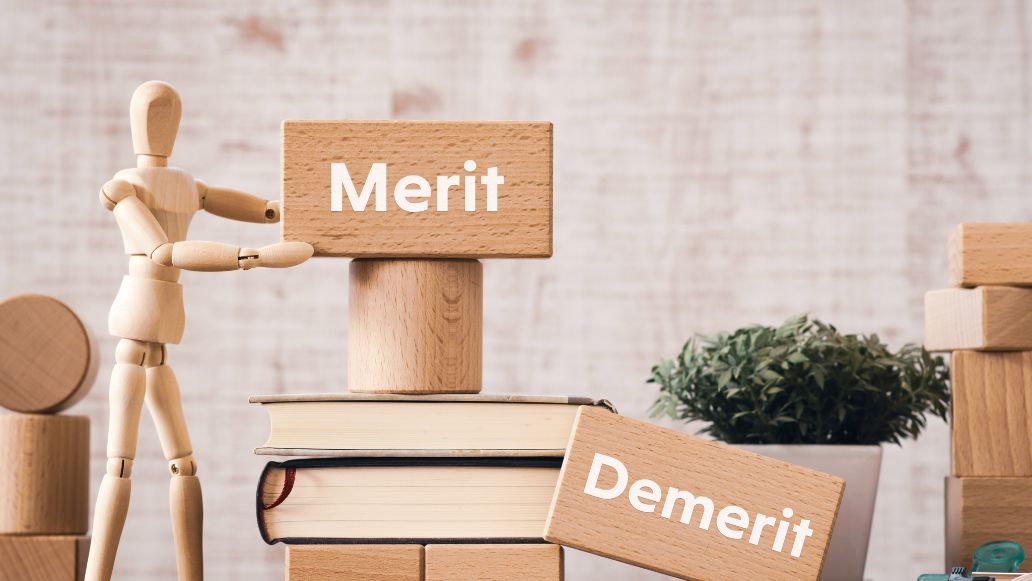
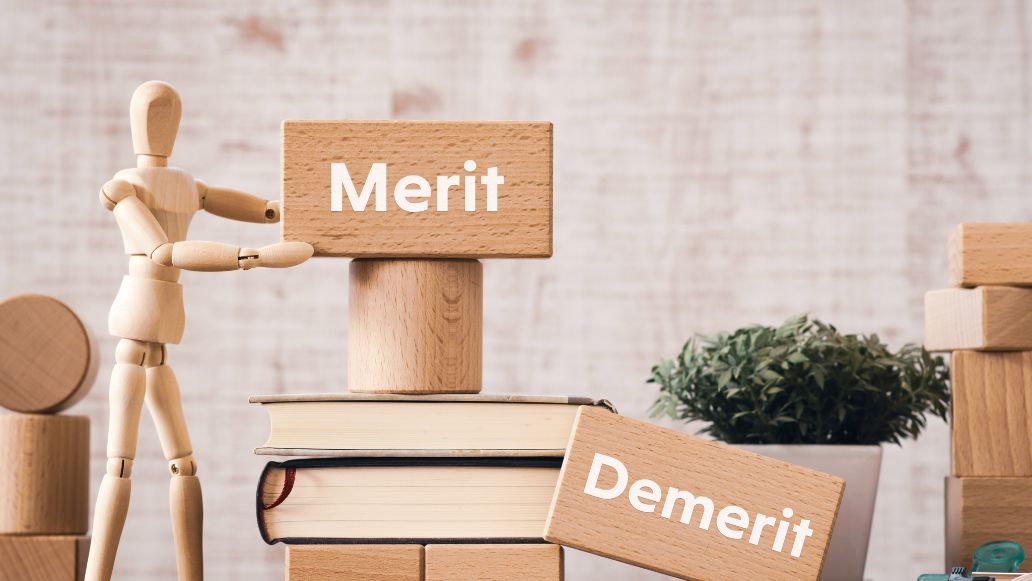
44年特例を受け取ると、収入が増えるという大きなメリットがあります。しかし、将来的にデメリットになるケースもあるため、正しく説明できるようにメリットとデメリットを知っておきましょう。
4-1. 44年特例を受けるメリット
44年特例のメリットは以下の2つです。
- 通常より年金を多く受け取れる
- 早く受給開始できる
44年特例では約81万円の年金が追加され、金銭的な余裕が生まれます。生活費や医療費などに対する不安が軽減され、老後をより安心して過ごせる点が大きな魅力です。
また、年金の受給開始は通常65歳からですが、60歳で退職してすぐに収入を得られます。早期受給により働く必要が減ることで、老後の選択肢を広げ、趣味や家族との時間を充実させる助けになるでしょう。
4-2. 44年特例を受けるデメリット
44年特例を受けると、働き続けることで得られる収入や将来の年金額の増加機会を失う可能性があります。44年特例の制度を利用するには先ほどお伝えした通り、退職または給与を月額88,800円未満にする必要があるためです。
退職せずに働き続ければ厚生年金の加入期間が延び、将来の年金額を増やせる可能性があります。また、正社員として働き続けることで、年金額以上の収入を得る可能性も否定できません。そのため特例を受給すると、結果的に総収入が減少するデメリットがあります。
特例を受け取るタイミングや退職の判断は、人生プランや収入計画を十分に考慮することが大切です。
5. 44年特例を受けるための手続き


44年特例を受けるために特別な手続きは、従業員側も企業側も特に必要ありません。特別支給の老齢厚生年金の手続きが済んでいれば、自動的に加算されます。
ただし前述の通り、一定の要件を満たさないといけません。特例の対象になるのかわからない場合や、被保険者期間が何カ月かを確認したい場合は、年金事務所で確認できます。退職後に対象外とわかると対応が難しいため、事前に確認が必要です。
また、44年特例の受給者が退職した場合は、企業は被保険者資格喪失届を管轄の年金事務所に提出することになります。それを受けて定額部分の受給手続きも開始されるため、44年特例の受給者が退職した場合はこの手続きが必要であることを覚えておきましょう。
6. 44年特例を受ける場合の注意点


44年特例を受け取る場合の注意点は、以下3つが挙げられます。
- 65歳以降受給する年金には上乗せされない
- 失業保険と併用できない
- 加給年金と併用可能だが申請が必要になる
それぞれの内容を確認していきましょう。
6-1. 65歳以降受給する年金には上乗せされない
65歳以降受給する年金には上乗せされないことに注意しましょう。
44年特例は、60歳から65歳までの間に通常支給されない定額部分を受け取れる制度であり、65歳以降の年金額に変動をおよぼすものではありません。
特例の要件を満たしても、65歳以降に受け取る老齢基礎年金や老齢厚生年金に対して加算され続けるものではない点に注意が必要です。勘違いをしているケースがあるため、65歳を迎えた従業員から質問が出るケースがあります。
6-2. 失業保険と併用できない
44年特例と失業保険は同時に受け取れないことに注意が必要です。退職後失業保険を申請すると、44年特例はストップします。
失業保険は、あくまでも働き続けたい人を支援する趣旨の制度です。一方、44年特例は老後の生活を支えるための制度です。両方同時に受け取ることは制度の趣旨にそぐわないため、同時に受け取れない仕組みとなっています。
6-3. 加給年金と併用可能だが申請が必要になる
44年特例を受給している場合でも、加給年金は併用して受け取れますが、別途申請が必要であることに注意しましょう。
加給年金は、一定の要件を満たす配偶者や子どもがいる場合に支給される制度です。65歳の誕生日の前日以降に所定の届出を提出すると支給が開始されます。提出先は最寄りの年金事務所です。
7. 44年特例の対象となる従業員には適切に対応しよう


44年特例は、厚生年金に多くの年数加入してきた方を対象とする制度です。対象者は限られていますが、従業員から質問が寄せられることも考えられます。
適切な対応をおこなうためにも、受給要件や注意点の把握が大切です。従業員が安心して判断できるよう、必要な情報を迅速に提供できるようにしておきましょう。



人事労務担当者の実務の中で、従業員情報の管理は入退社をはじめスムーズな情報の回収・更新が求められる一方で、管理する書類が多くミスや抜け漏れが発生しやすい業務です。
さらに、人事異動の履歴や評価・査定結果をはじめ、管理すべき従業員情報は多岐に渡り、管理方法とメンテナンスの工数にお困りの担当者の方もいらっしゃるのではないでしょうか。
そんな人事労務担当者の方には、Excel・紙管理から脱却し定型業務を自動化できるシステムの導入がおすすめです。
◆解決できること
- 入社手続きがオンラインで完結し、差し戻し等やりとりにかかる時間を削減できる
- システム上で年末調整の書類提出ができ、提出漏れや確認にかかる工数を削減できる
- 入社から退職まで人事情報がひとつにまとまり、紙やExcel・別システムで複数管理する必要がなくなる
システムを利用したペーパーレス化に興味のある方は、ぜひこちらから資料をダウンロードの上、業務改善にお役立てください。
人事・労務管理のピックアップ
-


【採用担当者必読】入社手続きのフロー完全マニュアルを公開
人事・労務管理公開日:2020.12.09更新日:2026.01.30
-


人事総務担当がおこなう退職手続きの流れや注意すべきトラブルとは
人事・労務管理公開日:2022.03.12更新日:2025.09.25
-


雇用契約を更新しない場合の正当な理由とは?伝え方・通知方法も紹介!
人事・労務管理公開日:2020.11.18更新日:2025.10.09
-


社会保険適用拡大とは?2024年10月の法改正や今後の動向、50人以下の企業の対応を解説
人事・労務管理公開日:2022.04.14更新日:2025.10.09
-


健康保険厚生年金保険被保険者資格取得届とは?手続きの流れや注意点
人事・労務管理公開日:2022.01.17更新日:2025.11.21
-


同一労働同一賃金で中小企業が受ける影響や対応しない場合のリスクを解説
人事・労務管理公開日:2022.01.22更新日:2025.08.26
労務の関連記事
-


年収の壁はどうなった?2025年最新動向と人事が押さえるポイント
勤怠・給与計算公開日:2025.11.20更新日:2025.11.17
-


2025年最新・年収の壁を一覧!人事がおさえたい社会保険・税金の基準まとめ
勤怠・給与計算公開日:2025.11.19更新日:2025.12.22
-


人事担当者必見!労働保険の対象・手続き・年度更新と計算方法をわかりやすく解説
人事・労務管理公開日:2025.09.05更新日:2026.01.30






















