従業員のモチベーションを高める報酬制度とは?作り方や導入の注意点を解説
更新日: 2025.2.12 公開日: 2024.6.3 (特定社会保険労務士・中小企業診断士)

報酬制度とは、従業員の給与や昇給・昇進についてのルールを取りまとめたものです。報酬制を導入する際は、従業員のモチベーションを高められるよう、報酬を戦略的に配分する仕組みを整える必要があります。
しかし、なかには自社に合った報酬制度がわからず、困っている方もいるのではないでしょうか。
本記事では、従業員のモチベーションを高めるための報酬制度のメリットや作り方、導入する際の注意点を解説します。報酬制度の導入または見直しを検討中の方は、ぜひ参考にしてください。
目次

人事評価制度は、従業員のモチベーションに直結するため、適切に設計・見直し・改善をおこなわなければ、最悪の場合、従業員の退職に繋がるリスクもあります。
しかし「改善したいが、いまの組織に合わせてどう変えるべきか悩んでいる」「前任者が設計した評価制度が古く、見直したいけど何から始めたらいいのかわからない」という方もいらっしゃるでしょう。
当サイトではそのような企業のご担当者に向けて「人事評価の手引き」を無料配布しています。
資料では、人事評価制度の基本となる種類の解説や、導入手順、注意点まで詳しくご紹介しています。自社の人事評価に課題感をお持ちの方は、ぜひこちらから資料をダウンロードしてご活用ください。
1. 報酬制度とは|報酬を与える基準やルールを定めた制度

報酬制度とは、企業が従業員に報酬を与える際の基準やルールを定めた制度のことをいいます。等級制度や評価制度と並び、人事制度を構成する3本柱の一つとされる、企業が持続的成長を目指すうえで欠かせない重要な要素です。
企業が従業員に支払う報酬には、次のような金銭的報酬と非金銭的報酬の2種類があります。
| 金銭的報酬 | 基本給・賞与(ボーナス)・インセンティブ・手当などのお金で与えるもの |
| 非金銭的報酬 | ポスト・福利厚生・権限などお金以外のもので与えるもの |
金銭的報酬は基本給以外にも賞与、成功報酬、英語いうとボーナスやインセンティブなども含まれます。
報酬制度を導入する際は、上記の金銭的報酬と非金銭的報酬をバランスよく組み合わせることが大切です。こうした総合的な報酬体系を「トータル・リワード」と呼び、従業員の内発的動機付けにつながることが期待されています。
2. 報酬制度の目的|人件費を戦略的に配分すること

報酬制度の目的は、人件費を戦略的に配分することです。
市場競争が激化する中、自社が他社より優位に立つには、経営戦略と結び付けた人事戦略の策定が欠かせません。人件費管理も人事戦略の一つであり、報酬制度を導入することで人件費の適切な管理が可能になるでしょう。
また、報酬制度には、経営戦略において望ましい行動を従業員に促す役割もあります。報酬制度で、従業員が組織に有益な行動を自主的にとる仕組みを作れば、生産性が向上し、経営目標の達成に一歩近づけるでしょう。
3. 報酬制度における主な6種類の報酬

報酬制度における主な6種類の報酬(金銭的報酬)は以下のとおりです。
| 報酬の種類 | 概要 |
| 基本給 | 基本となる給与。残業代・賞与・退職金の計算のベースになる |
| 能力給 | 能力(スキル・知識)に応じて支給される給与 |
| 職務給 | 職務(役職や職種に紐づく仕事内容・役割)に応じて支給される給与 |
| 賞与 | 定期給の労働者に対して、定期給とは別に支給される一時的な給与 |
| インセンティブ | 成果に応じて支給される報酬 |
| 手当 | 基本給とは別に、諸費用として支給する賃金 |
報酬制度を設計する際に基本となる報酬のため、理解しておきましょう。
4. 報酬制度の基盤となる4種類の考え方
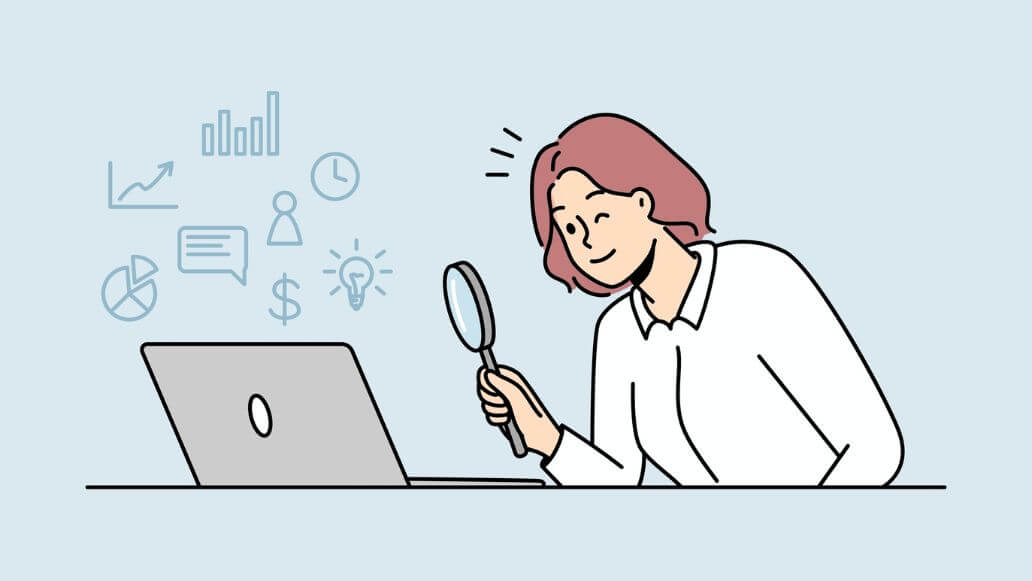
報酬制度は、次の4種類の考え方をもとに制度の設計がおこなわれます。
- 年功序列主義
- 成果主義
- 職務主義
- 職能主義
それぞれ詳しく確認しましょう。
4-1. 年功序列主義
年功序列主義とは、従業員の年齢や勤続年数などを昇給・昇進の基準とする考え方を指します。年齢や勤続年数を重ねるほど報酬や地位が高くなる仕組みです。
従業員にとっては安定した収入や生活が見込めるものの、年長者や従業員数が多い場合は人件費が高騰します。個人の成果や能力を十分に反映できず、従業員のモチベーション低下や離職を招きやすい点にも注意が必要です。
4-2. 成果主義
年齢や勤続年数に関係なく、従業員の成果や実績を人事評価の対象とする考え方を成果主義といいます。組織への貢献度に合わせて報酬を付与するため、人件費を最適化できることがメリットです。
一方で、評価が適切におこなわれない場合は、従業員が企業に対して不信感を抱く恐れがあります。個人の成績が報酬に直結するため、成果を上げられない従業員が離職する可能性も否めません。
成果主義を導入する際は、ほかの評価制度と併用したり成長の機会を与えたりして、いかに人材を育成するかが重要になるでしょう。
4-3. 職務主義
職務主義は、従事する職務の難易度や価値に応じて報酬を配分する考え方です。職務ごとに固定の報酬を与えることで、人件費の管理が容易になり、従業員の納得感を得やすいメリットがあります。
職務主義の報酬制度では、職務記述書(ジョブディスクリプション)の作成が必要です。職務が変われば報酬も変わるため、配置転換がしにくい点に注意しましょう。
4-4. 職能主義
職能主義とは、従業員の職務遂行能力を昇給・昇進の根拠とする考え方です。個々の職務遂行能力をレベル別で評価するため、異動による報酬の変動がなく、従業員エンゲージメントの向上が期待できます。
ただし、職務遂行能力は、勤務年数や経験を重ねていくうちに磨かれるものであることから、年功主義的な運用になりがちです。若年者は年長者に比べて低待遇となる場合が多く、年長者が多い場合は総人件費が増加する可能性もあります。
5. 報酬制度を導入する3つのメリット

報酬制度を導入するメリットは、次の3つです。
- 従業員のモチベーションを高められる
- 人件費の予算が立てやすくなる
- 人材の確保や定着につながる
5-1. 従業員のモチベーションを高められる
報酬制度を導入するメリットは、従業員のモチベーションを高められることです。
従業員にとって昇給や昇進は、働く理由の一つであり、なかには「報酬があるから頑張れる」と思う人もいるでしょう。しかし、報酬制度が整っていない状態では、給与や役職が上がる基準がわからず、なにを目標に頑張ればよいのかわかりません。
従業員一人ひとりがやりがいをもって働くためにも、報酬制度にて報酬の基準や考え方を明確に示すことが大切です。報酬の基準が明確になれば、従業員の仕事に対するモチベーションが高まり、自発的な行動をとることが期待できるでしょう。
5-2. 人件費の予算が立てやすくなる
報酬制度は、人件費の予算を立てる際にも役立ちます。報酬の基準を定義することで、だれに、どのくらいの人件費がかかるのかがわかり、無駄のないコスト管理ができるでしょう。
人件費が利益を圧迫している場合は、報酬制度を見直すことも方法の一つです。とくに年功序列など、年齢や勤続年数に応じて報酬が上がるケースでは、人件費の高騰が予想されます。業務量や働きの割に少ない報酬を与えられている従業員がいることも事実です。
報酬制度を見直せば、優秀な人材に相応の報酬が行き渡るようになり、人件費を適正化できます。今までかかっていた人件費が浮く分、新しい設備や人材への投資が可能です。
働き方や雇用のあり方が多様化している現代において、年功序列のような終身雇用を前提とした考え方は薄れつつあります。人材への投資や評価の公平性が重要視されてきていることからも、時代の流れに合わせた報酬制度の設計が必要になるでしょう。
5-3. 人材の確保や定着につながる
人材の確保や定着にもつながることも、報酬制度を導入するメリットです。
就職活動者の多くは、入社を決める際に、どのような仕事ができて、どのくらいの報酬が受け取れるのかを見ています。報酬制度があれば、就職活動者が将来の年収やキャリアを見通せるようになり、入社後も長く働いてくれる可能性が高いでしょう。
従業員に長く働いてもらうためには、納得感のある報酬制度を確立することが大切です。従業員のニーズや給与水準なども踏まえ、魅力的な報酬体系を編成しましょう。
6. 報酬制度を設計するための6つの手順

報酬制度の設計は、次に挙げる7つの手順でおこないます。
- 現状を把握・分析する
- 人事評価の基準や仕組みを整える
- 報酬体系を編成する
- 報酬水準を設定する
- 報酬テーブルを作成する
- シミュレーションをおこなう
それぞれ詳しく確認していきましょう。
6-1. 現状を把握・分析する
報酬制度を設計する際は、まず自社の現状を把握・分析することが重要です。経営戦略や人事戦略、従業員数、人件費などの実態を調査したうえで、目指す方向性を整理しましょう。
実態調査の方法としては、アンケートが有効です。必要に応じて従業員や人事担当者へのヒアリングもおこない、現場に潜在している問題点や課題を洗い出していきましょう。
6-2. 人事評価の基準や仕組みを整える
次に、報酬制度の基盤となる人事評価の基準や仕組みを決めます。従業員の多様なニーズに応えるため、それぞれに合った評価基準を設けることも検討してみましょう。
すでに報酬制度を導入しており、従業員から不満の声があがっているなら、現状の人事評価制度が合っていない可能性があります。報酬制度を見直す場合も、必ず既存の評価制度との整合性を確認するようにし、必要であれば見直しも検討しましょう。
6-3. 報酬体系を編成する
1、2で決定した方針や人事評価制度をもとに、実際に報酬を与える際の基準となる報酬体系を編成します。報酬体系には、金銭的報酬以外に非金銭的報酬も含めて、だれ(何)に・どのような報酬を与えるのかを明示することが大切です。
具体的には、以下のポイントにしたがって検討するとよいでしょう。
| 基本給 | ・従業員の年齢・勤続年数、成果、能力、職務のどれを重視するのか |
| 賞与 | ・個人、部署、会社全体のどの貢献に対して支払うのか
・支払いの対象となる期間や条件 |
| インセンティブ | |
| 手当 | ・どのような場面、条件で与えるのか |
| 非金銭的報酬 | ・報酬の条件や基準 |
とくに基本給は、残業代や退職金のベースにもなるため、等級で序列化したほうが不公平感が少なく、人件費を管理しやすくなります。賞与やインセンティブに法的な支給義務はないものの、導入することで従業員のモチベーションや生産性の向上が期待できるでしょう。
6-4. 報酬水準を設定する
報酬体系の編成が終わったら、報酬水準を決めます。競合他社や業種、地域の水準とも比較したうえで、適正な報酬水準を設定しましょう。
なお、報酬水準の中でも、各等級における中間値のことを「ポリシーライン」といいます。報酬額を決める際は、ポリシーラインを軸にして等級内の上限額・下限額を検討することが大切です。
6-5. 報酬テーブルを作成する
報酬体系と報酬水準の設計内容から、各報酬の具体的な金額を決め、報酬テーブルを作成しましょう。報酬テーブルとは、それぞれの報酬の金額を等級ごとにまとめた一覧表のことを指します。
報酬制度の設計では、基本給だけでなく賞与やインセンティブ、手当、非金銭的報酬それぞれの報酬テーブルが必要です。報酬テーブルがあることで、報酬金額の変動幅を確認できるようになります。
6-6. シミュレーションをおこなう
自社に合った報酬制度を導入するためにも、報酬制度を設計した後は、シミュレーションをおこなうことが大切です。制度の移行時や組織の年齢構成が変わった場合など、あらゆる場面を想定して人件費への影響を検証しておきましょう。
金額や変動幅を微調整しながら検証と改善を繰り返し、運用に問題がないかを確認するようにしてください。
7. 報酬制度を設計する際の注意点
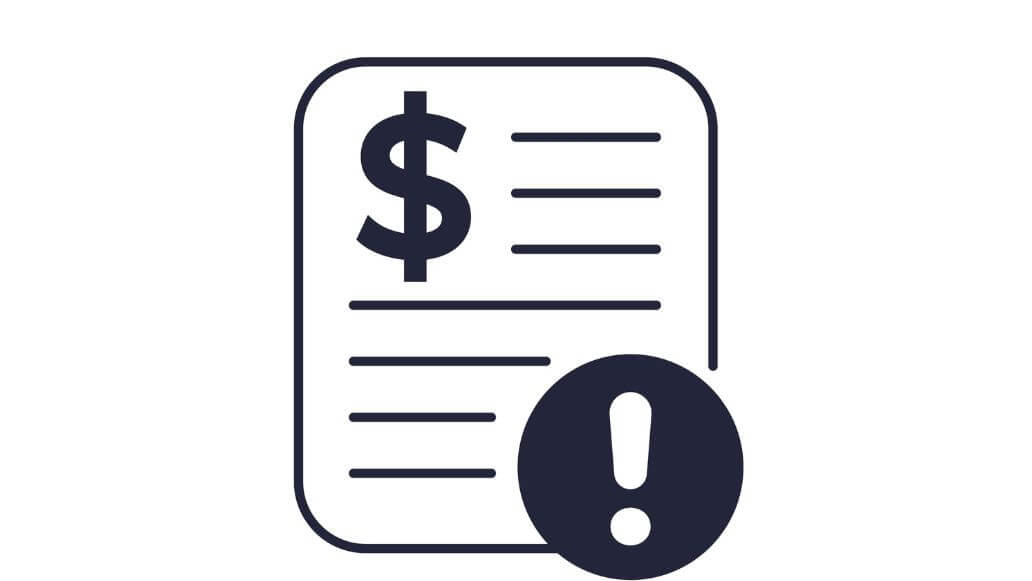
報酬制度を設計する際の注意点は以下の2つです。
- 評価制度とのつじつまを合わせる
- 公平性・平等性を確保する
7-1. 評価制度との整合性をとる
報酬制度を設計する際は、評価制度との整合性をとることが大切です。
評価制度と報酬制度が合っていない場合、従業員が評価に見合った報酬を受け取れず、モチベーションの低下につながりかねません。なかには、離職を選択する従業員もいるでしょう。
従業員のモチベーションを高めて、長く勤めてもらうには、高い評価に対して高い報酬を与える制度の導入が不可欠です。従業員の自発的行動を促すためにも、評価制度と報酬制度は必ず連動させるようにしてください。
7-2. 公平性・透明性を確保する
だれもが納得して報酬を受け取れるよう、報酬制度は公平性・透明性を意識して設計することが重要です。
とくにインセンティブなどの成果主義の報酬は、評価が営業職に偏る傾向があります。しかし、一部の部署・職種のみにインセンティブが与えられている場合は、報酬のない従業員が不満に思う可能性があるでしょう。
8. 報酬制度を導入した企業の事例

最後に、報酬制度を導入した以下2つの企業事例を紹介します。
- 自動車メーカーの最大手であるA社
- 国内最大級のフリーマーケットアプリを運営するB社
8-1. 自動車メーカーの最大手であるA社
世界シェア第1位の自動車メーカーであるA社では、職能主義型の報酬制度を取り入れています。人事評価に応じて基本給が変動する「職能個人給」を採用することで、優秀な人材の活躍を促していることが特徴です。
賞与には、人事評価を点数化し、点数が高いほど支給額が増える仕組みを導入しています。評価は0~3点の4段階で、最高評価の3点の場合、賞与額が標準の1.5倍まで増額する仕組みです。
A社は、自社の報酬制度について、「従業員の就業意欲を高め、厳しい国際競争で勝つ」との考えを示しています。
8-2. 国内最大級のフリーマーケットアプリを運営するB社
フリーマーケットアプリの開発、運営を手がけるB社は、インセンティブにピアボーナス制度を導入しています。
ピアボーナス制度とは、従業員が互いを評価し、報酬額へと反映させる制度です。B社では、チップによって従業員同士が自由に賞賛し合う制度を採用しています。
B社によれば、ピアボーナス制度の導入で従業員の満足度が高まり、社内コミュニケーションが活発になったとのことです。
9. 適正な報酬制度を設計して従業員のエンゲージメントを高めよう

報酬制度があれば、従業員のモチベーションが高まり、生産性の向上や組織の活性化が期待できます。ただし、導入する際は、評価制度との整合性や内容の公平性・透明性に注意して検討することが大切です。
企業が持続的に成長していくためにも、自社に適した制度設計をおこない、従業員エンゲージメントの向上を目指しましょう。

人事評価制度は、従業員のモチベーションに直結するため、適切に設計・見直し・改善をおこなわなければ、最悪の場合、従業員の退職に繋がるリスクもあります。
しかし「改善したいが、いまの組織に合わせてどう変えるべきか悩んでいる」「前任者が設計した評価制度が古く、見直したいけど何から始めたらいいのかわからない」という方もいらっしゃるでしょう。
当サイトではそのような企業のご担当者に向けて「人事評価の手引き」を無料配布しています。
資料では、人事評価制度の基本となる種類の解説や、導入手順、注意点まで詳しくご紹介しています。自社の人事評価に課題感をお持ちの方は、ぜひこちらから資料をダウンロードしてご活用ください。
人事・労務管理のピックアップ
-

【採用担当者必読】入社手続きのフロー完全マニュアルを公開
人事・労務管理公開日:2020.12.09更新日:2026.01.30
-

人事総務担当がおこなう退職手続きの流れや注意すべきトラブルとは
人事・労務管理公開日:2022.03.12更新日:2025.09.25
-

雇用契約を更新しない場合の正当な理由とは?伝え方・通知方法も紹介!
人事・労務管理公開日:2020.11.18更新日:2025.10.09
-

社会保険適用拡大とは?2024年10月の法改正や今後の動向、50人以下の企業の対応を解説
人事・労務管理公開日:2022.04.14更新日:2025.10.09
-

健康保険厚生年金保険被保険者資格取得届とは?手続きの流れや注意点
人事・労務管理公開日:2022.01.17更新日:2025.11.21
-

同一労働同一賃金で中小企業が受ける影響や対応しない場合のリスクを解説
人事・労務管理公開日:2022.01.22更新日:2025.08.26
タレントマネジメントの関連記事
-

プレゼンティーイズムとは?原因と企業に与える損失額・対策をわかりやすく解説
人事・労務管理公開日:2026.01.19更新日:2026.01.19
-



メンタルヘルスサーベイとは?ほかのサーベイとの違い、実施の目的や流れを解説!
人事・労務管理公開日:2026.01.16更新日:2026.01.14
-


企業におけるメンタルヘルスケアとは?4つのケアや事例を紹介
人事・労務管理公開日:2025.11.18更新日:2025.12.19



























