CSFとは?KGI・KPIとの意味の違いや具体例、設定方法を解説
更新日: 2025.1.31 公開日: 2024.7.26 jinjer Blog 編集部

「CSFを活用し、経営目標の達成まで具体的な計画を立てたい」
「CSFやKGI・KPIなど、経営戦略を立てる際に使うビジネス用語について理解したい」
上記のように考えている方もいるのではないでしょうか。
この記事では、CFSの意味やKGI・KPIとの違い、CSFのタイプ、設定方法、具体例などを紹介します。KGI・CSF・KPIのツリー構造や作成方法も解説するので、ぜひ参考にしてください。
目次

人事評価制度は、健全な組織体制を作り上げるうえで必要不可欠なものです。
制度を適切に運用することで、従業員のモチベーションや生産性が向上するため、最終的には企業全体の成長にもつながります。
しかし、「しっかりとした人事評価制度を作りたいが、やり方が分からない…」という方もいらっしゃるでしょう。そのような企業のご担当者にご覧いただきたいのが、「人事評価の手引き」です。
本資料では、制度の種類や導入手順、注意点まで詳しくご紹介しています。
組織マネジメントに課題感をお持ちの方は、ぜひこちらから資料をダウンロードの上、お役立てください。
1. CSFとは

CSFとは、Critical Success Factorの略です。日本語に訳した場合には「重要成功要因」といいます。CSFは企業の目標達成の要素となるものです。
適切なCSFを設定・実行し、望ましい結果が得られれば、企業が掲げる目標達成へより近づけるでしょう。
例えば、経営目標が「売上を10%上げたい」であるとします。業績を上げたいと考えたとき、考えられるCSFは「新規顧客を獲得する」「リピート率を上げる」などです。
CSFを設定すると、目標を達成するために必要な行動を無駄なく実行できます。
1-1. CSFとKGI(重要目標達成指標)の違い
CSFとKGIでは、それぞれ意味が違います。
| 用語 | 意味 |
| CSF | KGI達成のための要素 |
| KGI | 目標のゴールを意味する |
KGIはKey Goal Indicatorの略で、日本語では「重要目標達成指標」です。企業が最終的に達成したい目標がKGIにあたります。
経営戦略を立てる際、まずは最終的な目標を掲げます。目標が「売上を10%上げたい」であるなら、KGIも「売上を10%上げたい」となるでしょう。対して、CSFは成功するための要因なので、業績を上げるために必要だと考えられる事柄を表します。
1-2. CSFとKPI(重要業績評価指標)の違い
CSFとKPIは双方とも目標達成に必要なものですが、やはりそれぞれ意味が違います。
| 用語 | 意味 |
| CSF | KGI達成のための重要な要素 |
| KPI | KGIを達成するための具体的な行動と数値 |
KPIはKey Performance Indicatorの略で、訳すと「重要目標達成指標」となります。KPIは、KGI(重要目標達成指標)を達成するための行動を具体的な数値とともに表したものです。
例えば、KGIが「月間の売上を10%上げたい」であれば、KPIは「1日の売上〇〇円を目指す」「1日の来客数〇〇人を目指す」となります。
1-3. CSFとKSF(重要成功要因)の違い
KSFはKeySuccessFactorの略で、「重要成功要因」と訳されます。つまり、CSFとほぼ同じ意味です。
KSFはKFS(KeyFactorforSuccess)と呼ばれることもあります。
2. CSFのタイプ

CSFには、以下のように5通りのタイプがあります。
| CSFのタイプ | 例 |
| 業界に関連する | ある点で、業界No1になる・業界水準を上回るためのCSFを設定する |
| 競合に関連する | 競合と比べたうえで、自社に取り入れるべきCSFを設定する |
| 一時的なものに関連する | 季節に沿ったCSFを設定する
コロナ禍に対応するためのSCFを設定する |
| 環境的なものに関連する | 円安・少子高齢化・労働者人口の減少などの環境に対応するためのCSFを設定する |
| 管理職に関連する | 管理職のスキルアップをCSFとし、目標達成の要因とする |
CSFを設定する際にはタイプを意識し、自社にとって最適なCSFはどのようなものなのかを考えましょう。
3. CSFの設定方法

CSFの設定方法は、以下の順序でおこないましょう。
- 現状分析する
- 問題解決策を探る
- 複数の候補からCSFを絞り込む
それぞれの過程について、詳しく解説していきます。
3-1. 現状分析する
CSFを決める際には、まず現状を分析します。効果的な分析方法は以下の4つです。
| 分析方法 | 特徴 |
| SWOT分析 | 内部環境や外部環境を「強み」「弱み」「機会」「脅威」に分けて分析する |
| 5フォース分析 | 「新規参入」「業界内の競争」「代替製品やサービス」「買い手」「売り手」などの競争環境を重視して分析を行なう |
| PEST分析 | 「政治」「経済」「社会」「技術」の外部環境を分析する |
| バリューチェーン分析 | 自社と競合他社の「原材料の調達」「製造」「販売」「アフターサービス」までの一連の活動で、どのような付加価値を生み出しているか分析する |
それぞれの企業が置かれている環境によって、実施すべき分析方法は異なります。
3-1-1. SWOT分析
SWOT分析は、企業や組織の戦略的な計画を立てるためのフレームワークです。この分析手法は、内部環境と外部環境を4つの要素に分けて評価することによって、戦略を明確にし、効果的な意思決定を促すものです。SWOTの4つの要素は、強み(Strength)、弱み(Weakness)、機会(Opportunity)、脅威(Threat)です。
まず、強み(Strength)とは、企業が競合他社に対して優位性を持っている点を指します。これには、独自の技術やブランドの知名度、高い顧客満足度といった要素が含まれます。
逆に、弱み(Weakness)は内部の欠点や制約であり、資金力の不足やマーケティング戦略の欠如などが例です。
次に、外部環境における機会(Opportunity)は、企業が成長や改善を図るためのプラスの要素です。市場の成長、新技術の登場、消費者のトレンド変化などがこれに該当します。
一方、脅威(Threat)は、競争の激化や法規制の変更、経済不況など、企業にとってのリスク要因を指します。
SWOT分析を行うことで、内部と外部の両面から企業の現状を把握でき、ポジティブな要素を活かし、ネガティブな要素を克服するための戦略的方向性を見出すことができます。これにより、CSF(重要成功要因)を具体的に設定することが可能となります。
例えば、ある企業が新商品を市場に投入する際、SWOT分析を用いて自社の強みを確認し、競争環境や市場動向を考慮することで、成功のための具体的な活動を明確にすることができます。この流れが、戦略的な意思決定を促進し、企業の競争力を高める一助となります。
3-1-2. 5F(ファイブフォース)分析
5F(ファイブフォース)分析は、業界における競争環境を深く理解するための手法です。この分析を通じて、自社が直面するさまざまな競争要因を洗い出し、正確なCSF(重要成功要因)を策定する際の基盤を構築します。
まず、5フォース分析の対象となる競争要因は5つに分類されます。1つ目は「新規参入の脅威」です。これは、新たな競合が市場に参入する可能性を示しており、参入障壁が低いほど、この脅威は高まります。既存のプレーヤーにとっては、新参者の影響を受けやすくなります。
2つ目は「競合他社の脅威」です。これは、既に市場に存在する競争者との競争の激しさを表しています。競争が激しい場合、自社は価格やサービスの差別化を図る必要があります。
3つ目は「代替品の脅威」です。製品やサービスに対する代替品が存在する場合、顧客は自身のニーズに合った選択肢を持つため、価格競争やブランド力の向上が求められます。
4つ目は「顧客の交渉力」です。この要因は、顧客が価格や取引条件に影響を与える力を指します。顧客の選択肢が多ければ、その交渉力は高まり、企業は柔軟な対応を余儀なくされます。
最後に、5つ目の要因は「供給者の交渉力」です。供給者が価格や供給条件を掌握している場合、企業は原材料費や仕入れ条件の引き上げに苦しむことがあります。
これらの5つの要因を分析することにより、自社の競争優位性をどのように強化するかを見極めることが可能です。業界の環境を理解し、これに基づいてCSFを策定することが、企業の持続的な成長や目標達成につながります。5フォース分析を活用して、より効果的な戦略を形成することが重要です。
3-1-3. PEST分析
PEST分析は、企業が外部環境を理解し、戦略を立てるための強力な手段です。この手法は、「政治(Political)」「経済(Economic)」「社会(Social)」「技術(Technological)」の4つの側面から企業を取り巻く外部要因を分析します。
まず、政治的要因は、法律や税制、政府の政策が企業活動に与える影響を指します。例えば、ある国で消費税が引き上げられると、消費者の購買力が減少し、それによって企業の売上が影響を受けることがあります。
次に、経済的要因では為替レートやインフレーション、雇用率などが考慮されます。最近のデータによると、例えば2023年には円安が進み、それに伴う輸出企業の利益向上とともに、輸入企業はコスト増の圧力を受けるという複雑な背景が見られました。
社会的要因には、人口動態や消費者の嗜好・価値観の変化が含まれます。例えば、健康志向の高まりに伴い、オーガニック製品への需要が増加しました。このようなトレンドを捉えることで、企業は新たな商品やサービスを開発する機会を見出せます。
最後に、技術的要因は、技術革新や新しいテクノロジーの登場がビジネスに与える影響を分析します。例えば、AIの進化により、多くの業界で業務効率化が進んでいる現状では、企業はこれを活用した新たなビジネスモデルの構築を考慮しなければなりません。
このように、PEST分析を通じて、企業は外部環境の変化を敏感に捉え、CSF(重要成功要因)を設定する際に重要な洞察を得ることができます。あらゆる外的要因を把握することで、リスクを最小限に抑え、ビジネスの成長を促進させる道を探ることができます。
3-1-4. バリューチェーン分析
バリューチェーン分析は、企業の活動を「主活動」と「支援活動」に分け、自社がどのように顧客に価値を提供しているかを明確にするための手法です。この分析を通じて、各活動が付加価値を生み出す過程を理解し、最終的には競争優位の確立を目指します。
主活動には、製品の原材料調達、製造、販売、顧客サービスなどが含まれます。例えば、自動車メーカーでは、原材料の調達から生産、販促活動までの全工程が大切です。原材料の調達であれば、品質の良い部品を選定することで製品の品質に直接的に寄与します。また、生産プロセスの改善により、コストの削減や生産効率の向上が可能です。
一方で、支援活動は、技術開発や人事、企業資源の管理など、主活動を支える役割を果たします。たとえば、物流システムの効率化はコスト削減に貢献し、顧客満足度の向上へとつながります。
競合他社との比較を行うことで、自社の強みや弱みが明確になり、戦略的優先順位を設定することができます。この比較に基づいて、例えば製品開発においては革新的な技術を採用することで、市場のニーズに応える新たな価値を生み出すことができるでしょう。また、リソースの最適配分を通じて、特定の活動に集中することができ、これがCSF(重要成功要因)の設定に寄与します。
バリューチェーン分析を通じて、自社の価値提供のメカニズムを深く理解し、その結果を具体的な戦略に落とし込むことで、企業は持続的な競争力を持つことが可能になります。自社の特性に適したバリューチェーンを築くことが、更なる成長の鍵となるのです。
3-2. KJ法を用いて問題解決策を探る
次に、問題解決策を探りましょう。問題解決策を探る際には、KJ法を活用すると効果的です。この発想法は、文化人類学者の川喜田二郎氏が考案したため、氏のイニシャルをとってKJ法と呼ばれています。
KJ法のやり方は以下の通りです。
- 多数のアイデアや情報をカードや付箋に書き込む
- 出されたアイデアや情報をグループ分けする
- グループ同士の関係性を図解化する
- グループ同士の関係性を文章化する
10人以下のグループ、あるいは個人で実施するのが理想です。それぞれのステップを詳しく説明します。
3-2-1. アイデアを書き出す
まず最初のステップは、アイデアを書き出すことです。参加者にはテーマを伝え、それに基づいてブレインストーミングを実施します。この時、他者のアイデアを否定せず、新たな意見を歓迎する環境づくりが重要です。
アイデアは、1枚のカードまたは付箋に1つずつ記入します。この手法を用いることで、後のグルーピング作業が容易になります。
3-2-2. 書き出したアイデアをグルーピングする
次に、書き出したアイデアをグルーピングします。まずは無造作にカードを並べ、内容をよく読みます。その後、印象の似たアイデアや同様の意見を集め、小さなグループを作成して見出を作成します。
見出しを見てグループとしてまとめる作業を何度かおこない、最終的に数個の大きなグループにします。
3-2-3. 各グループの関係性を視覚化する
3番目のステップでは、各アイデアの関係性を見つけ、視覚的に図解します。例えば、関連性があるアイデアを線でつなぐ、対立する意見を矢印などで表すなどです。
3-2-4. 各グループの関係性を文章化する
最後に、グループごとの関係性を文章化し、重要度に応じて優先順位を設定します。この結果を参加者と共有し、文章化しましょう。
ここまでの一連の流れによって、アイデアを可視化でき、情報をわかりやすく整理できます。
3-3. 複数の候補からCSFを絞り込む
最後に、複数の候補から効果的だと考えられるものをCSFとして絞り込みます。
1つに絞りきれない場合には社員や顧客にアンケートを取り、外部からの視点を取り入れるのがおすすめです。問題解決や目標達成に効果的と思われるものを選びましょう。
4. CSFの具体例

CSFの具体例を紹介します。ここでは売上10%アップを目標とした美容院を例に、CSFを設定してみましょう。
| 分析結果(SWOT分析) | 強み:固定客が多い
弱み:認知度が低く、新規顧客が増えない 機会:周囲の住民の高齢化が進んでおり、高齢者向けの美容院のニーズが高まる傾向 脅威:近隣の大手のチェーン店が幅広い年齢を対象に経営している |
| CSF | ・エイジングに特化したサービスを展開する
・紙媒体のわかりやすい広告をポスティングする ・固定客が引き続き満足できるサービスを実施する |
分析結果では、固定客を確保した状態で新規顧客を獲得する必要性がわかります。ターゲットを高齢者に絞るのであれば、適切な広告の出し方も考えなければなりません。
5. KGI・CSF・KPIのツリー構造(階層構造)とは
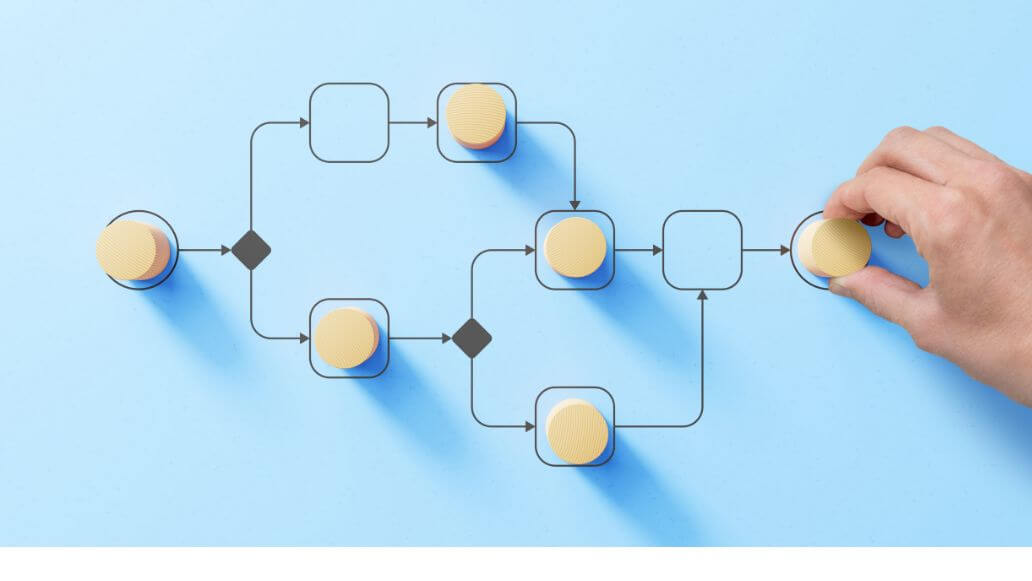
KGI(重要目標達成指標)・CSF(重要成功要因)・KPI(重要目標達成指標)を用いたツリー構造は、企業目標を達成するためのフレームワークです。
3つの階層構造は以下のようになります。
| KGI(重要目標達成指標) | 企業全体の最終目標 |
| CSF(重要成功要因) | 最終目標を達成するために実施する具体的な行動 |
| KPI(重要目標達成指標) | 目標達成度のための具体的な数値目標 |
経営目標を達成するためには、KGI・CSF・KPIのツリー構造を意識して目標達成へのプロセスを明確化することがポイントです。
CSFの位置付けを把握し、ツリーを活用して目標達成を目指すとよいでしょう。
6. KPIツリーの作成方法

KPIツリーの作成方法は以下になります。
| 順序 | 内容・注意点 |
| 1.KGIを設定する | ・目標は数値化する
・目標と現状のギャップを把握する ・目標達成までのプロセスについて考える ・わかりやすい目標にする |
| 2.CSFを設定する | ・目標達成のために現場ですべきことは何か考える
・多くの要素を列挙し、重要な要素のみに絞り込む |
| 3.KPIを設定する | ・目標達成のために、何をいつまで、どれくらい実施すればよいかを具体的な数値に落とし込む |
KGIを設定してから、CSF、KPIと順を追って設定していけば、目標達成のための行動をどれくらい実施すればよいかが自然に把握できます。
7. 適切なCSFを設定して目標達成を促そう

CSFは、企業の最終的な目標であるKGIを成し遂げるための、重要な要因です。適切なCSFを設定し、短期の具体的な数値目標であるKPIに落とし込めば、目標を達成できる可能性が高まるでしょう。
CSFには5通りのタイプがあり、自社の状況に合わせて設定する必要があります。自社の状況を把握するためには、SWOT分析・5フォース分析・PEST分析・バリューチェーン分析などを用いるのがよいでしょう。
自社を取り巻く状況は変化するため、都度CSFも更新しなければなりません。定期的に現状分析をおこない、CSFをブラッシュアップしていきましょう。

人事評価制度は、健全な組織体制を作り上げるうえで必要不可欠なものです。
制度を適切に運用することで、従業員のモチベーションや生産性が向上するため、最終的には企業全体の成長にもつながります。
しかし、「しっかりとした人事評価制度を作りたいが、やり方が分からない…」という方もいらっしゃるでしょう。そのような企業のご担当者にご覧いただきたいのが、「人事評価の手引き」です。
本資料では、制度の種類や導入手順、注意点まで詳しくご紹介しています。
組織マネジメントに課題感をお持ちの方は、ぜひこちらから資料をダウンロードの上、お役立てください。
人事・労務管理のピックアップ
-

【採用担当者必読】入社手続きのフロー完全マニュアルを公開
人事・労務管理公開日:2020.12.09更新日:2026.01.30
-

人事総務担当がおこなう退職手続きの流れや注意すべきトラブルとは
人事・労務管理公開日:2022.03.12更新日:2025.09.25
-

雇用契約を更新しない場合の正当な理由とは?伝え方・通知方法も紹介!
人事・労務管理公開日:2020.11.18更新日:2025.10.09
-

社会保険適用拡大とは?2024年10月の法改正や今後の動向、50人以下の企業の対応を解説
人事・労務管理公開日:2022.04.14更新日:2025.10.09
-

健康保険厚生年金保険被保険者資格取得届とは?手続きの流れや注意点
人事・労務管理公開日:2022.01.17更新日:2025.11.21
-

同一労働同一賃金で中小企業が受ける影響や対応しない場合のリスクを解説
人事・労務管理公開日:2022.01.22更新日:2025.08.26
タレントマネジメントの関連記事
-

プレゼンティーイズムとは?原因と企業に与える損失額・対策をわかりやすく解説
人事・労務管理公開日:2026.01.19更新日:2026.01.19
-



メンタルヘルスサーベイとは?ほかのサーベイとの違い、実施の目的や流れを解説!
人事・労務管理公開日:2026.01.16更新日:2026.01.14
-


企業におけるメンタルヘルスケアとは?4つのケアや事例を紹介
人事・労務管理公開日:2025.11.18更新日:2025.12.19



























