対話型組織開発とは?診断型との違いや心理的安全性の関連性などを徹底解説
更新日: 2025.10.30 公開日: 2025.3.20 jinjer Blog 編集部

対話型組織開発は、従業員が主体となって課題を発見し、解決策を生み出す手法です。
組織開発の手法の中には、診断型組織開発のように課題を特定・分析する手法もあります。しかし、対話型というのは現場の声を引き出しながら、心理的安全性の高い環境を築き、主体的な行動変容を促すことが可能になるので、組織の持続的な成長が期待できます。
ただし、単に「対話」をするだけでは現場のリアルな声を拾うのは難しく、本質的な課題を把握することはできません。対話型組織開発の成果を得るには、心理的安全性の確保が不可欠です。
本記事では、対話型組織開発の概要や診断型との違い、心理的安全性の概要やメリットなどについて詳しく解説します。
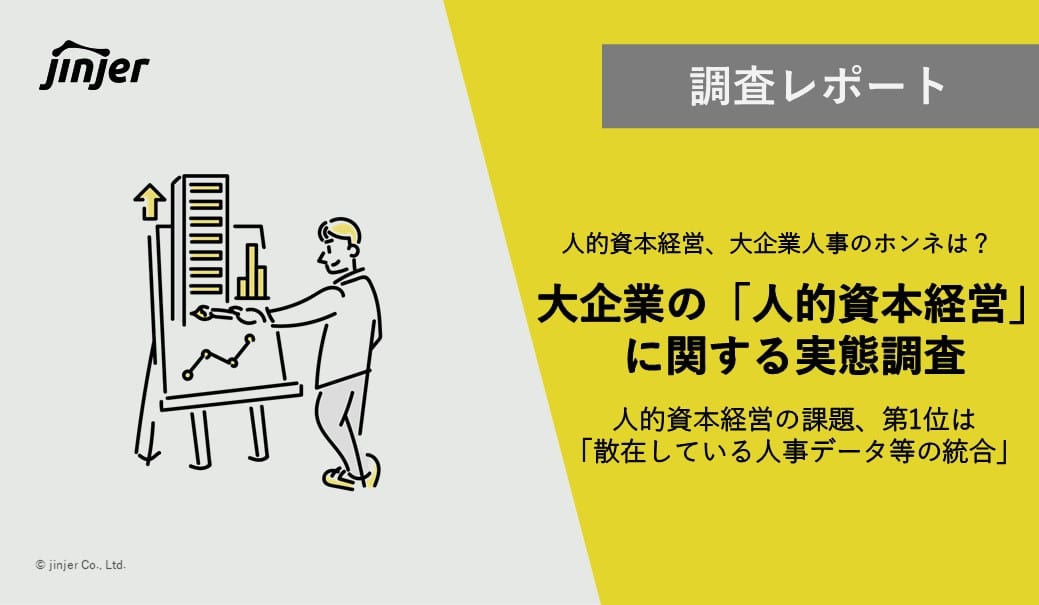
人的資本の情報開示が義務化されたことで人的資本経営への注目が高まっており、今後はより一層、人的資本への投資が必要になるでしょう。
こういった背景の一方で、「人的資本投資にはどんな効果があるのかわからない」「実際に人的資本経営を取り入れるために何をしたらいいの?」とお悩みの方も、多くいらっしゃるのが事実です。
そのような方に向けて、当サイトでは人的資本経営に関する実際調査の調査レポートを無料配布しています。
資料では、実際に人事担当者にインタビューした現状の人的資本経営のための取り組みから、現在抱えている課題までわかりやすくレポートしています。
自社運用の参考にしたいという方は、ぜひこちらから資料をダウンロードの上、お役立てください。
1. 対話型組織開発とは

対話型組織開発とは、対話を通じて組織内の関係性を変革し、持続的な成長を促す手法です。対話を重ねることで組織全体の認識を変え、主体的な変革を生み出します。
対話型組織開発が注目されているのは、現代の変化が激しいビジネス環境のなかで、従来のトップダウン型の指示では迅速な対応が難しいためです。対話型組織開発では、組織内のメンバーが共通の目的を持ち、相互理解を深めることで自律的に課題解決を進められます。
例えば、企業がDX(デジタルトランスフォーメーション)を推進する際、従業員が変化に適応するには、自分ごととして捉えることが重要です。
対話型組織開発では経営層から現場までが意見を交わし、組織全体の納得感を高めながら組織変革を進められます。
1-1. 組織開発には診断型と対話型がある
組織開発には、大きく分けると「診断型」と「対話型」という2つの手法があります。
診断型というのは、外部コンサルタントや人事部門が中心となって、従業員アンケートやデータ分析などで組織の課題を特定し、その解決策を提案・実行していく手法です。この手法の特徴は、効率的で短期間の成果が期待できることですが、現場の納得感や主体性が得られにくいのが課題です。
一方の対話型は、従業員同士で率直な対話をおこない、自分たちで課題を見出し、組織の変革に関わっていくプロセスです。トップダウンではなく、現場レベルで感じる課題の解決策を実施するという手法は、主体が従業員となるので持続可能な変革が可能になります。
このように、診断型と対話型には明確な違いがありますが、実際の組織開発では状況や目的にあわせて使い分けるのが効果的です。
2. なぜ組織の対話は生まれにくいのか?
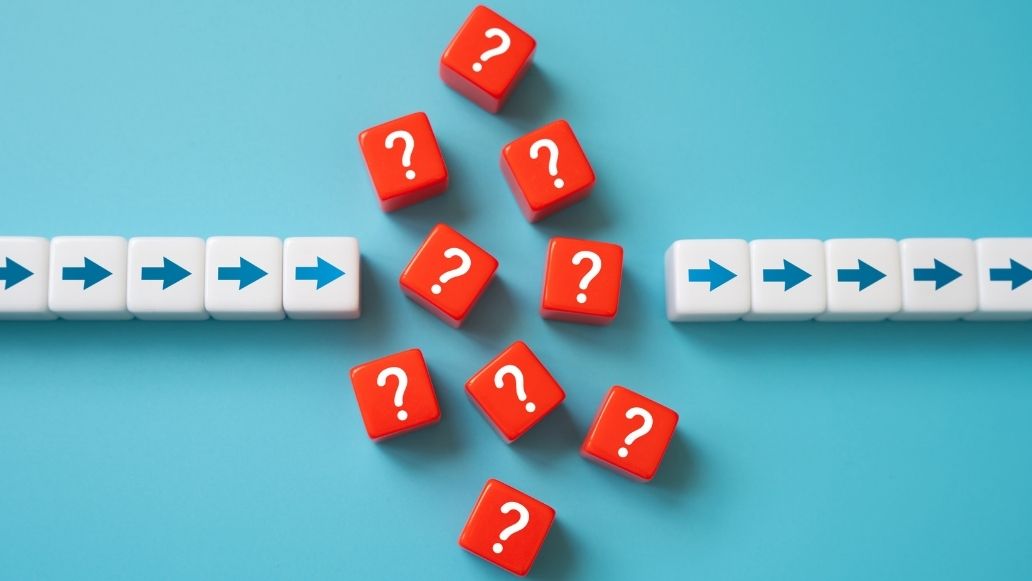
ここまで対話型組織開発の重要性について解説しましたが、現実問題として職場内で対話が活性化されないことに課題感を持っている企業も少なくないでしょう。
ここでは、組織の対話が生まれにくい主な原因について解説します。自社に当てはまる原因がないか、まずはチェックしておきましょう。
2-1. トップダウン型の意思決定
経営層や管理職が一方的に方針を決定するトップダウン型の組織では、現場の意見が反映されにくい傾向があります。
意思決定が上からの指示で完結してしまうため、従業員が議論に関わる機会が少なくなり、組織の意思形成に参加している実感も沸きづらくなってしまうのです。
その結果、現場で感じている課題や改善のアイデアが共有されず、組織の成長機会が失われてしまいます。
こうした状況が続くと、従業員の主体性も低下し、的を射ない施策が繰り返されるなど、組織全体の硬直化を招くことにもつながります。
2-2. 職場環境の変化による対話機会の減少
コロナ禍以降、リモートワークが定着し、自宅やカフェなどオフィス以外の場所で働くスタイルが一般化しました。場所に縛られずに働けることでワークライフバランスを保ちやすくなる一方、面と向かって話す機会が減少しています。
その結果、コミュニケーションは業務連絡やタスク共有といった「必要最小限」にとどまり、何気ない雑談や相談の機会が失われています。
こうした状況では、チームの一体感が弱まってしまい、相互理解や信頼関係の構築が難しくなることも少なくありません。
2-3. 企業風土や文化の問題
企業の風土や文化そのものが、対話を妨げているケースもあります。たとえば、「業務中の私語禁止」や「同調圧力が強い」といった風土が根付いている組織では、活発なコミュニケーションは起こりにくくなります。
また、上司が部下の意見を受け止めず、自分の考えを一方的に押し付けてしまう職場では、従業員の間に「どうせ言っても無駄だ」という諦めムードが広がるでしょう。
このような空気が定着すると、新しい発想や改善の提案は生まれにくくなり、組織の停滞を招いてしまいます。
3. 対話型組織開発に必要な「心理的安全性」とは

対話型組織開発を進めるうえで、欠かせない土台となるのが「心理的安全性」です。
心理的安全性とは、メンバーが自分の意見や感情を安心して表現できる職場の雰囲気や関係性を指します。対話型組織開発では、従業員同士が対話を通じて組織の課題や可能性を探り、共に解決策を見出していくプロセスが重視されます。
もしも、一人だけ違う意見をいう従業員を責めたり頭ごなしに否定したりするような環境では、対話にならず本質的な課題や可能性を見出すことはできません。そのため、たとえ異なる意見であっても否定されることなく受け止められる安心感が不可欠です。
心理的安全性が高い職場では、誰もが自由に発言でき、建設的な意見交換が活発になります。一方で、心理的安全性が低いと、批判を恐れて本音を隠したり、対話自体が形骸化したりしてしまいます。
つまり、対話型組織開発の成果を引き出すためには、心理的安全性の確保が必要となるのです。心理的安全性は、従業員同士が信頼関係を築く、共感的な聴き方を実践する、上下関係を越えた対話の場をつくるなどコミュニケーションから意識的に育てていくことが重要です。
4. 対話型組織開発の利点を活かすにはディベートが必要

対話型組織開発は、組織内の従業員同士が率直に意見を交わし、相互理解を深めることで、変化に強く柔軟な組織を育てる手法の一つです。
その利点を最大限に活かすには、単なる「会話」ではなく、意見が違う者同士でも前向きに議論し合える「ディベート(建設的対話)」が重要になります。従業員が、対立を恐れずに本音を語り合える環境を整えることは、「対話型組織開発」を成功させるポイントです。
ここでは、対話型組織開発の利点を活かすディベートの意義と、それを成立させるための要素を整理していきます。
4-1. 心理的安全性の確保
ディベートを可能にするには、従業員が「安心して本音や意見を述べられる」心理的安全性が不可欠です。前述していますが、心理的安全性とは、自分の考えや疑問を表明しても否定されたり攻撃されたりしない、信頼感のある状態を指します。
対話型組織開発を進めるには、全員が対等な立場で話せる場を設け、発言に対する評価やジャッジを控えなければなりません。心理的安全性が確保されていれば、従業員は積極的に発言しやすくなり、それぞれの多様な視点や価値観をぶつけ合うことで、新たな気づきや学びが生まれやすくなります。
心理的安全性を高めるには、管理者や上司が率先して発言をおこない、失敗を責めない文化を構築することも重要です。
4-2. 双方の意見を尊重しあう文化形成
対話型組織開発において、効果的な意見交換をおこなうには、自分の主張を一方的に押し通すのではなく、相手の意見にも耳を傾ける「尊重の姿勢」が不可欠です。
ディベートと聞くと、勝ち負けを競う印象を持ってしまいがちですが、組織開発におけるディベートは、あくまでも「共通理解を深めるための手段」です。意見が対立したときこそ、「なぜ相手はそう考えるのか」「相手の発言の背景にある価値観は何か」などを探ることが、組織の成熟度を高めます。
このような文化を築くのは簡単ではありませんが、日常的な会話の中で、お互いの意見を肯定的に受け止めるように意識すると少しずつ根づいていきます。双方の意見を尊重しあえる文化を形成すれば、違いを恐れず、多様性を認め合える職場環境へと変化していくでしょう。
4-3. 対話型組織開発を建設的な意見交換の場にできる
対話型組織開発を意味ある取り組みにするためには、「建設的な意見交換の場」として機能させることが重要です。
対話というのは、一歩間違えると単なる雑談や表面的なやり取りで終わってしまいます。これでは、組織変容にはつながりません。建設的な対話とは、意見が異なるとしても、同じ目標や目的に向かって一緒に考えて、より良いアイデアや解決策を見出すプロセスのことを指します。
より良いアイデアや解決策を見つけるためには、話し合いの目的やルールを明確にし、参加者全員が「考えを深める」姿勢で臨む必要があります。また、対話から生まれた解決策を実施し、改善につなげることも不可欠です。「解決策を出す」だけで終わらせるのではなく、実際の行動を伴ってこそ、対話型組織開発を成功に導くポイントとなります。
5. 対話型組織開発のメリット

対話型組織開発のメリットは、以下の3点が挙げられます。
- 成功循環モデルの構築
- 心理的安全性による創造性と生産性の向上
- 現場主導で課題を解決できる
ここでは、それぞれのメリットについて詳しく解説していきます。
5-1. 成功循環モデルの構築
対話型組織開発を導入すると組織内の関係性が深まり、組織全体の成果向上につながる成功循環モデルが生まれるというメリットがあります。
対話型組織開発では、対話を重ねることで関係の質が高まり、それが思考や行動の質を引き上げ、最終的に成果へとつながる「成功循環モデル」の構築が可能になります。これは、ダニエル・キムが提唱した組織変革のフレームワークであり、「関係の質」→「思考の質」→「行動の質」→「結果の質」というポジティブな連鎖を生み出す効果が期待できます。
また、対話を通じて互いの価値観や立場を理解し、信頼関係が深まることで、自然と建設的な意見交換が生まれやすくなります。表面的な課題解決ではなく、根本的な構造や関係性にアプローチすることで、継続的に成果を上げる組織文化が育まれるというのは大きなメリットといえるでしょう。
5-2. 心理的安全性が高まり創造性と生産性が向上する
対話型のアプローチは、従業員の間に「心理的安全性」を生み出しやすく、自由な意見交換ができるようになるという点が大きな特徴です。
心理的安全性とは、発言や提案をしても否定されたり責められたりしないという安心感のある状態のことを指します。対話を通じて一人ひとりの声が尊重される環境が築かれると、人はより自由に意見を出せるようになり、創造性が高まります。
また、認識の違いや思い込みによるミスも減るので、結果として生産性の向上にもつながります。近年の研究でも、心理的安全性が高いチームは成果を出しやすいことが実証されており、対話型組織開発はその土台をつくる有効な手段にもなっています。
5-3. 実際の課題を現場主導で解決できる
対話型組織開発では、現場で働いている従業員が主体的に課題を発見し、解決策を考えていくというプロセスがあります。
外部の専門家による分析やトップダウンの一方的な施策導入ではなく、現場の当事者が中心となるため、実情に即したリアルな解決策が生まれやすくなります。これは、従業員の納得感や実行力にも直結するので、施策の定着率や持続性にも良い影響を与えます。
さらに、対話を通じて得られた気づきは、単なる問題解決にとどまらず、組織風土そのものを変えていく原動力になります。現場主導で課題を解決できるというメリットは、「自分たちの手で変えることができる」という意識を育てる効果があるので、組織全体のパフォーマンス向上も期待できるのです。
6. 対話型組織開発を成功させるポイント

対話型組織開発を効果的に進めるためのポイントは以下のとおりです。
- 多様なメンバーを対話に参加させる
- 安心して意見を出せる環境を整える
- 目指すゴールを明確にする
それぞれのポイントについて、詳しく解説します。
6-1. 多様なメンバーを対話に参加させる
対話型組織開発の真価が発揮されるのは、異なる立場や価値観を持つメンバー同士が率直に意見を交わすときです。そのためには、役職や世代に関わらず、対話の場には、部門や役職を超えた多様なメンバーを参加させることが大切です。
毎回同じメンバーだと意見が偏り、新しい発想が生まれにくくなります。さまざまな立場の人が参加することで、思い込みを排除し、本質的な課題を見つけやすくなるのです。
上司と部下、現場と本部、あるいは中途採用者や派遣社員など、普段対等な会話をする機会の少ない人同士が対話をすることで、組織内に新たな気づきやつながりが生まれます。
重要なのは、「対話の対象者を限定しない」ということです。発言力や立場に差があっても、それぞれの声に価値があると企業が認識することで、対話の質は格段に向上します。意図的に異なる立場のメンバーを集め、固定観念を打破しましょう。
6-2. 安心して意見を出せる「心理的安全性」環境を整える
対話を深めるための土台となるのが、「心理的安全性」です。心理的安全性が確保されていないと、発言は表面的または忖度したものになってしまうので、組織開発の本質的な効果は得られません。発言を批判される雰囲気では、従業員は意見を控えがちになり、対話の意味が薄れます。
また、対話の場を設定する際には、リーダーやファシリテーター(進行役)が積極的に場の雰囲気を整えること、意見の違いを尊重する文化を育むことが求められます。
他にも、発言しやすいルールの明示や共感を示すリアクション、否定的な反応を避けるなど、細かな配慮の積み重ねが心理的安全性を高めます。意見が尊重される環境を作ることで対話が活発になり、組織の成長を促進できます。
6-3. 目指すゴールを明確にする
自由な対話は重要ですが、目的(ゴール)が不明確なまま進めてしまうと、議論が散漫になります。その結果、対話後に「結局、何のための対話だったのか?」という疑問が残る、無駄な時間になりかねません。
対話型組織開発では、事前に「この対話で何を明らかにしたいのか」「何のために議論するのか」など、ゴールを明確に設定することが重要です。ゴールは、必ずしも数値的な成果にする必要はなく、「組織の課題について共通理解を深める」「現場の声を可視化する」など、対話そのものに価値を置くもので構いません。
ゴールが共有されていれば、参加者の意識も揃い、話し合いが建設的な方向に進みやすくなります。対話の自由さと方向性の明確さによって、組織の結束力が強まり、実効性のあるアクションへとつなげられます。
7. 対話型組織開発で活用できるフレームワーク

対話型組織開発で活用できる主なフレームワークは、下記の4つになります。
- AI(アプリシエイティブ・インクワイアリー)
- フューチャーサーチ
- OST(オープンスペース・テクノロジー)
- ワールド・カフェ
ここでは、それぞれの特徴と進め方を詳しく解説します。
7-1. AI(アプリシエイティブ・インクワイアリー)
AI(アプリシエイティブ・インクワイアリー)は「問題を解決する」のではなく、「組織や人の強み・成功体験」に焦点を当てて、前向きな変革を促すフレームワークです。対話を通じて、過去の成功体験やポジティブな側面を引き出しながら、理想の未来像を描くのが目的なので、組織や個人の強みを最大限に活かすためのビジョン共有に役立ちます。
AIの進め方は以下のとおりです。
| 1.発見フェーズ | 過去・現在・未来の成功体験を話し合う |
| 2.夢フェーズ | 「ありたい姿」を明確にする |
| 3.設計フェーズ | 実現に向けた方法を計画する |
| 4.実行フェーズ | 計画を行動に移す |
成功体験をもとに未来を描き、実行に移すことで、組織全体のモチベーションやエンゲージメントを高められます。
7-2. フューチャーサーチ
フューチャーサーチは、異なる立場のメンバーが一堂に会し、組織の未来を話し合うフレームワークです。
多様な視点を取り入れ、組織の方向性を明確にするのに役立ちます。
フューチャーサーチの進め方は以下のとおりです。
| 1.過去を振り返る | 組織の歴史や経験を共有する |
| 2.現在を探る | 組織が抱える課題を明確化する |
| 3.未来を描く | 「ありたい姿」を定義する |
| 4.共通意図の整理する | 組織としての方向性を統一する |
| 5.アクションプランを作成する | 実行可能な計画を策定する |
上記の流れで進めることで、関係者全員が共通の意図を持ち、未来の実現に向けて動き出せます。
7-3. OST(オープンスペース・テクノロジー)
OST(オープンスペース・テクノロジー)は、参加者がテーマを提案し、興味・関心に応じて自主的に対話をおこなう参加型のフレームワークです。雇用形態や勤務年数、上下関係などにとらわれず、現場のリアルな声や創造的なアイデアが引き出されやすいのが特徴です。
参加者が主体的に関わると当事者意識が高まるので、納得感のある意思決定が可能になります。
OSTの進め方は以下のとおりです。
| 1.テーマ設定 | 参加者が議論したいテーマを提案する |
| 2.セッション実施 | 興味のあるテーマについて議論する |
| 3.成果共有 | 対話で生まれた気づきやアクションプランを全体で共有する |
上記の流れに沿って議論することで、組織の課題解決や新たな可能性の発見につながります。
7-4. ワールド・カフェ
ワールド・カフェは、リラックスした雰囲気の中で少人数の対話を繰り返し、アイデアを共有するフレームワークです。自由な発言を促し、新たな気づきを得るのに適しています。
ワールド・カフェの進め方は以下のとおりです。
| 1.テーマ設定 | 全員で共通のテーマを設定する |
| 2.セッション実施 | 4~5人のグループで話し合う |
| 3.成果共有 | 異なるグループのメンバーと意見交換する |
| 4.意見を統合 | 最初のグループに戻り、全体の意見を整理する |
| 5.全体共有 | 話し合いの成果を全員で共有する |
少人数のグループでの話し合いを繰り返しながら、意見を交換・統合することで、参加者の発想が広がり、組織やチームの課題解決にもつながります。
8. 対話型組織開発を活用して組織の成長につなげよう

変化の激しい時代に組織が成長し続けるためには、対話型組織開発の考え方を取り入れ、実践することが不可欠です。
対話型組織開発は、従業員同士の「対話」を通じて現場主導で課題解決を進められるため、納得感のある施策が実行されやすく、組織の持続的な成長につながります。
対話型組織開発を効果的に進めるには、対話の目的を明確にし、従業員が発言しやすい環境を作ることが大切です。AIやフューチャーサーチ、OSTなどのフレームワークを活用すれば、組織に適した方法で変革を進められます。
急速な変化が求められる今、従業員一人ひとりの自律性や創造性を引き出すには、安心して意見を発信できる組織文化が不可欠です。組織の成長を目指す企業にとって、対話型組織開発は有効な手段となるので、自社の組織づくりのファーストステップとして取り入れてみてください。
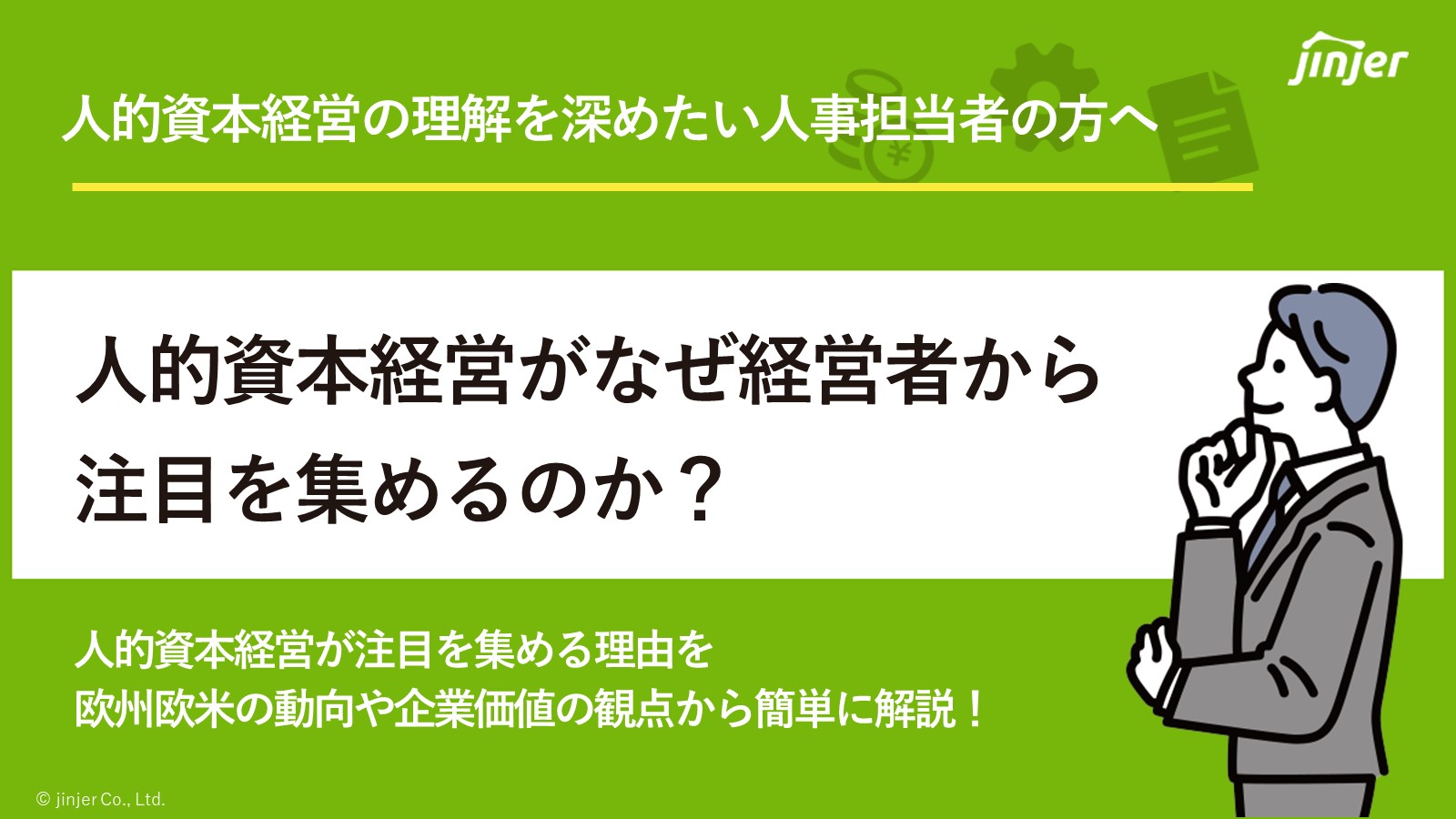
企業価値を持続的に向上させるため、いま経営者はじめ多くの企業から注目されている「人的資本経営」。
今後より一層、人的資本への投資が必要になることが想定される一方で、「そもそもなぜ人的資本経営が注目されているのか、その背景が知りたい」「人的資本投資でどんな効果が得られるのか知りたい」という方もいらっしゃるのではないでしょうか。
そのような方に向けて、当サイトでは「人的資本経営はなぜ経営者から注目を集めるのか?」というテーマで、人的資本経営が注目を集める理由を解説した資料を無料配布しています。
資料では、欧州欧米の動向や企業価値を高める観点から、人的資本経営が注目される理由を簡単に解説しています。「人的資本経営への理解を深めたい」という方は、ぜひこちらから資料をダウンロードの上、お役立てください。
人事・労務管理のピックアップ
-

【採用担当者必読】入社手続きのフロー完全マニュアルを公開
人事・労務管理公開日:2020.12.09更新日:2026.01.30
-

人事総務担当がおこなう退職手続きの流れや注意すべきトラブルとは
人事・労務管理公開日:2022.03.12更新日:2025.09.25
-

雇用契約を更新しない場合の正当な理由とは?伝え方・通知方法も紹介!
人事・労務管理公開日:2020.11.18更新日:2025.10.09
-

社会保険適用拡大とは?2024年10月の法改正や今後の動向、50人以下の企業の対応を解説
人事・労務管理公開日:2022.04.14更新日:2025.10.09
-

健康保険厚生年金保険被保険者資格取得届とは?手続きの流れや注意点
人事・労務管理公開日:2022.01.17更新日:2025.11.21
-

同一労働同一賃金で中小企業が受ける影響や対応しない場合のリスクを解説
人事・労務管理公開日:2022.01.22更新日:2025.08.26
タレントマネジメントの関連記事
-

プレゼンティーイズムとは?原因と企業に与える損失額・対策をわかりやすく解説
人事・労務管理公開日:2026.01.19更新日:2026.01.19
-



メンタルヘルスサーベイとは?ほかのサーベイとの違い、実施の目的や流れを解説!
人事・労務管理公開日:2026.01.16更新日:2026.01.14
-


企業におけるメンタルヘルスケアとは?4つのケアや事例を紹介
人事・労務管理公開日:2025.11.18更新日:2025.12.19



























