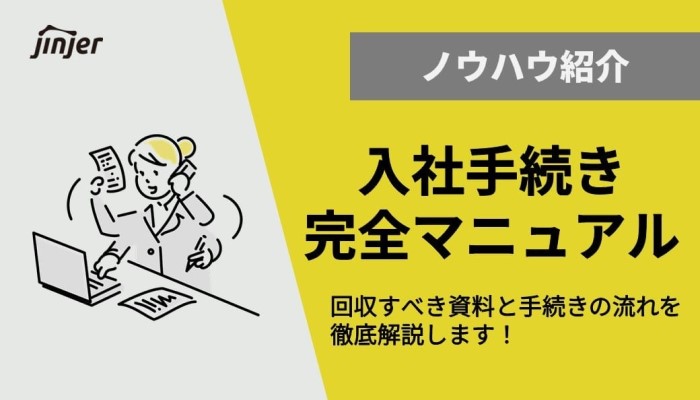入社手続きにかかる時間はどのくらい?準備スケジュールを公開
更新日: 2024.7.9
公開日: 2020.12.9
OHSUGI

新入社員が入社してくるときには、入社手続きが必要です。いろいろな手続きが必要ですが、どのくらいの時間がかかるものなのでしょうか。
こちらの記事では、入社手続きにかかる時間や準備のスケジュールについて見ていきましょう。
入社手続きは確実に対応する必要がありますが、社会保険の資格取得手続きや雇用契約の締結など対応しなくてはならない項目が多く、漏れや遅れが発生してしまうこともあるのではないでしょうか。
当サイトでは、入社手続きに必要な書類や入社手続き業務のフローをまとめた「入社手続き完全マニュアル」を無料配布しております。
「チェックしながら抜け漏れや遅滞なく入社手続きを行いたい」という方は、ぜひこちらから資料をダウンロードしてご覧ください。
目次
1. 入社手続きにかかる時間の目安

内定から入社手続きにはある程度の時間がかかります。しかも在職中で転職活動をしていて新しい会社に入社するのか、離職中もしくは新卒で入社するのかによっても異なります。
では在職中、離職中もしくは新卒で入社手続きにどのくらいの時間がかかるのか考えましょう。
1-1. 在職中の場合
在職中の方の場合、入社手続きには時間がかかることがあります。
前の職場で中核を担っていたような方の場合には、入社手続きに加えて引き継ぎなども必要となります。
重い責任を与えられていたり、役職についていたりする社員の転職では、内定通知への返信から入社手続きを経て初出勤するまでに3ヶ月程度かかるケースもあるでしょう。
1-2. 離職中、新卒の場合
すでに前職を退職してから採用されたり、新卒で入社したりする方の場合には入社手続きにかかる時間は短くなります。
入社手続きには入社諾否や入社日の決定、必要書類に提出や雇用契約の締結などいくつかのステップがあります。
離職中もしくは新卒の内定者の場合、内定通知をもらってからすぐに入社手続きに入ることができるでしょう。
その場合には、内定通知をもらった月末プラス1ヶ月程度が入社にかかる時間の目安となります。おおよそ1ヶ月半から2ヶ月程度を入社手続きに費やすことになるでしょう。
2. 入社手続きで一番時間がかかること

入社手続きにはいろいろなステップがあるので、一つひとつのステップを確認しながら進めていく必要があります。入社手続きの中には時間がかかるものもあり、しっかりとスケジューリングすることが重要です。
では入社手続きで一番時間がかかることについて見ていきましょう。
2-1. 内定者にとって一番時間がかかること
内定者にとって最も時間がかるのは、会社に提出する書類を揃えることでしょう。
特に新卒で入社する場合は、書類作成など不慣れなことが多いため、書類の準備だけで時間を要してしまいがちです。
しかし、提出してもらう必要書類が欠けていると、雇用保険や健康保険、所得税・住民税などの手続きが滞るため、内定者が書類手続きを進めやすいように工夫することが求められます。
入社時には新入社員の氏名や住所を確認するための住民票やマイナンバー、特定の資格を所有していることを証明するための自動車運転免許証や他の資格証明書、合格証明書など提出してもらいます。
また、署名捺印済みの雇用契約書や入社承諾書、厚生年金の手続きのための年金手帳、場合によっては身元保証書が必要になるかもしれません。
このほかにも、健康診断書や給与振込先申請書、給与所得者の扶養控除等(異動)申告書、同じ年内に前職を退職して中途採用で入社するのであれば、雇用保険被保険者証や源泉徴収票が必要書類に入ってくるでしょう。
このように、内定者に提出してもらう書類は多岐にわたるため、提出漏れがないように内定者側でチェックできるリストを作成するなど、事前に対策を講じておくことが重要です。
2-2. 総務担当にとって一番時間がかかること
新入社員にとっても入社手続きには時間がかかりますが、受け入れる総務担当も入社手続きにはかなりの業務が伴います。総務担当にとって一番時間がかかるのは、帳簿作成と保険関係の手続きでしょう。
企業では法定三帳簿と呼ばれる、作成・保管が義務付けられている帳簿があります。労働者名簿、賃金台帳、出勤簿の3つですが、すべての新入社員の情報を記入するのはかなり時間のかかる作業です。
正社員だけでなく、契約社員、パート・アルバイトなどすべての従業員の情報を記入しなければなりません。加えて出勤簿も全社員を対象に記入が必要で、5年間(当分の間は3年間)の保管義務があります。
さらに、入社手続きには各種保険の手続きや税金の手続きが必要です。出勤日数、所定労働時間によっては、健康保険と厚生年金への加入手続きをおこなわなければなりません。
新入社員を雇用してから5日以内に健康保険・厚生年金被保険者資格取得届を年金事務所や健康保険組合に提出します。
雇用保険は、31日以上の雇用契約と週20時間以上の所定労働時間という条件を満たした場合に加入しなければなりません。新入社員を雇用した月の翌月10日までに、雇用保険被保険者資格取得届をハローワークに提出する必要があります。
また、所得税と住民税の手続きもあります。
もし中途採用の社員が住民税を普通徴収から特別徴収に変更したいのであれば、給与支払報告・特別徴収に係る給与所得者異動届出書を担当する市区町村役場の住民税担当課に提出しなければなりません。
このように、総務担当が行う入社手続きは非常に複雑で手間がかかり、社内でフローが整備できていない場合、記載内容や収集の不備は頻繁に起こってしまいます。 当サイトでは、入社手続きに必要な書類や、入社書類を集めた後の業務フローをまとめた資料を無料で配布しております。入社手続きを漏れなく行いたい方は、是非こちらからダウンロードしてご覧ください。
また、上述した「健康保険・厚生年金被保険者資格取得届」と「給与所得者異動届出書」のひな形は以下より確認できます。
3. 入社手続きの一般的なスケジュール
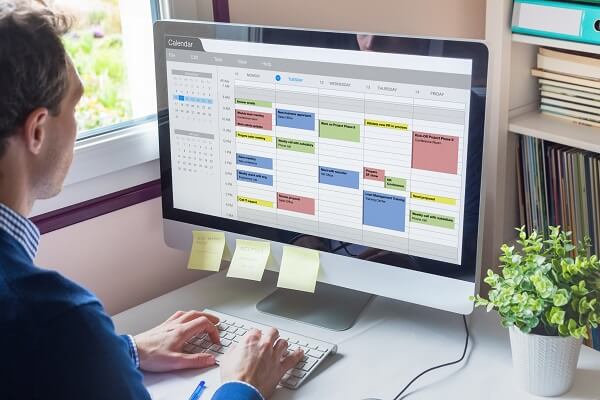
入社手続きにはある程度の時間がかかり、揃えるべきものも多いので、スケジューリングが非常に重要です。
入社手続きの一般的なスケジュールについて知っておくと、いつまでに何をしなければならないかを把握できるでしょう。
3-1. 必要書類の案内
内定通知を送付し、内定者から承諾の連絡を受けたなら入社手続きの最初のステップ、「必要書類の案内」が必要です。入社手続きには非常に多くの書類が必要です。不足しているとスムーズな手続きがおこなえません。
そのため、できるだけ前もって必要書類の案内をしておくことが望ましいでしょう。
内定の受諾後に面接がある場合はその日に、そうでない場合は入社日に提出してもらうことができます。
3-2. 労働条件通知書の作成
必要書類の案内とともに、労働条件通知書の作成もおこないます。
雇用契約書は法律上義務ではありませんが、労働条件通知書は労働者に交付することが義務付けられています。遅くとも入社日には労働条件通知書を手渡せるようにしておくべきです。
3-3. 備品の準備
新入社員が初出勤日からスムーズに業務をおこなうためにはさまざまな備品が必要です。デスクやイスはもちろんのこと、パソコンや事務用品、社員証、名刺などの備品を準備しておきましょう。
こうした備品をしっかり揃えることで、新入社員がスムーズに業務に入れるだけでなく、仕事に対するモチベーションの維持も期待できます。
3-4. 必要書類の受理・確認
入社日に必要書類を受け取ったなら、書類に不備や不足がないかを確認します。書類に不備や不足があった場合には、速やかに本人に知らせましょう。
3-5. 帳簿の作成
企業に作成・保管が義務付けられている法定三帳簿の作成をおこないます。労働者名簿、賃金台帳、出勤簿にはそれぞれ作成時のルールがあるので、それに則って作成を進めましょう。
3-6. 保険・税金の手続き
新入社員から提出してもらった書類を用いて、雇用保険、健康保険、厚生年金、住民税、所得税の手続きをおこないます。場合によっては社員にさらに書類を提出してもらわなければならないこともあります。
雇用保険や健康保険、厚生年金は期限が決められているので、社員の入社後速やかに手続きをおこなうようにしましょう。
4. 入社手続きのスケジュールを組む際の注意点


上述でも解説しましたが、雇用保険や社会保険、各種税金の手続きには提出期限があるので、間に合うようにスケジュールを組まなくてはいけません。特に社会保険に関しては、入社日から5日以内に必要書類を提出しなくてはいけないため、早めの準備が必要です。書類の不備による差し戻しなども想定し、時間に余裕をもたせてスケジュールを組んだほうが良いでしょう。
また、スケジュールと関係ないところではありますが、入社手続きに関する情報も個人情報として扱わなければいけません。万が一外部に流出してしまった場合は、該当の従業員のみならず社会的な信用も失う恐れがあります。
入社手続きのスケジュール管理と合わせて、従業員の情報管理についても同時に対策を講じておきましょう。
5. 入社手続きには時間がかかるので十分前もって準備を始めよう

入社手続きは、新入社員にとっても企業にとっても時間がかかる業務です。スケジュールがしっかり決まっているので、遅れることなく書類を揃えたり手続きをしたりすることが重要です。
もし郵送・受理・修正などの入社手続きの業務を電子化していないのでしたら、システムを導入し電子化することで工数削減が可能です。つまり、入社手続きにかかる時間の短縮が期待できます。入社手続きの電子化について気になる方はこちらの記事をご覧ください。
参考記事▶入社手続きを電子化するメリット・デメリットを徹底解説
電子化するしないにかかわらず前もってスケジューリングし、手続きを済ませることで、余裕のある準備をおこなうようにしましょう。
入社手続きは確実に対応する必要がありますが、社会保険の資格取得手続きや雇用契約の締結など対応しなくてはならない項目が多く、漏れや遅れが発生してしまうこともあるのではないでしょうか。
当サイトでは、入社手続きに必要な書類や入社手続き業務のフローをまとめた「入社手続き完全マニュアル」を無料配布しております。
「チェックしながら抜け漏れや遅滞なく入社手続きを行いたい」という方は、ぜひこちらから資料をダウンロードしてご覧ください。
人事・労務管理のピックアップ
-


【採用担当者必読】入社手続きのフロー完全マニュアルを公開
人事・労務管理
公開日:2020.12.09更新日:2024.03.08
-


人事総務担当が行う退職手続きの流れや注意すべきトラブルとは
人事・労務管理
公開日:2022.03.12更新日:2024.06.11
-


雇用契約を更新しない場合の正当な理由とは?通達方法も解説!
人事・労務管理
公開日:2020.11.18更新日:2024.07.10
-


法改正による社会保険適用拡大とは?対象や対応方法をわかりやすく解説
人事・労務管理
公開日:2022.04.14更新日:2024.06.12
-


健康保険厚生年金保険被保険者資格取得届とは?手続きの流れや注意点
人事・労務管理
公開日:2022.01.17更新日:2024.07.02
-


同一労働同一賃金で中小企業が受ける影響や対応しない場合のリスクを解説
人事・労務管理
公開日:2022.01.22更新日:2024.05.08