完全歩合制の最低賃金は?対象者・違法となるケース・歩合制との違いを解説
更新日: 2025.3.21 公開日: 2025.3.16 jinjer Blog 編集部

「完全歩合制の最低賃金について知りたい」
「完全歩合制の対象者を知りたい」
上記のようにお悩みの方も多いでしょう。
完全歩合制は固定給がなく成果に応じた歩合給のみが支払われる仕組みのため、最低賃金がありません。
本記事の内容は、完全歩合制について最低賃金や対象者、導入が違法となるケースや導入する際の注意点の解説です。
そのほかに、完全歩合制に関わる業務委託契約や、完全歩合制と歩合制の違いについても解説しているため、ぜひ参考にしてください。

人事労務担当者の実務の中で、従業員情報の管理は入退社をはじめスムーズな情報の回収・更新が求められる一方で、管理する書類が多くミスや抜け漏れが発生しやすい業務です。
さらに、人事異動の履歴や評価・査定結果をはじめ、管理すべき従業員情報は多岐に渡り、管理方法とメンテナンスの工数にお困りの担当者の方もいらっしゃるのではないでしょうか。
そんな人事労務担当者の方には、Excel・紙管理から脱却し定型業務を自動化できるシステムの導入がおすすめです。
◆解決できること
- 入社手続きがオンラインで完結し、差し戻し等やりとりにかかる時間を削減できる
- システム上で年末調整の書類提出ができ、提出漏れや確認にかかる工数を削減できる
- 入社から退職まで人事情報がひとつにまとまり、紙やExcel・別システムで複数管理する必要がなくなる
システムを利用したペーパーレス化に興味のある方は、ぜひこちらから資料をダウンロードの上、業務改善にお役立てください。
1. 完全歩合制には最低賃金がない


完全歩合制には、最低賃金がありません。フルコミッション制ともよばれており、成果に応じた歩合給のみが支払われます。
固定給は一切なく、成果がないと歩合給も支払われないため無給です。従って、1日8時間・週40時間働いた場合でも、成果がない場合の給料は0円となります。
なお、最低賃金とは最低賃金法により国が定めた賃金の最低限度のことです。労働基準法では、労働者の賃金は最低賃金額以上にすることや、労働時間に応じた一定額の賃金の保障を定めています。
しかし、合法的に完全歩合制を導入した場合は、上記の法律の対象外です。合法的に導入するためには、対象者を限定する必要があります。
2. 最低賃金がない完全歩合制の対象者


最低賃金がない完全歩合制の対象者は、会社と業務委託契約を結んだ個人事業主のみです。会社と雇用契約を結んでいないため、業務委託契約を締結した個人事業主には法律の賃金の定めが適用されません。
なお、個人事業主とは税務署へ開業届を提出して、法人化せずに個人で事業を営む方を指します。
業務委託契約を結んだ個人事業主とは異なり、会社と雇用契約を結ぶ以下のような方を完全歩合制の対象にはできません。
- 正社員
- 契約社員
- アルバイト
- パート
会社と雇用契約を締結した場合、法律の賃金の定めが適用されるためです。
3. 完全歩合制に関わる業務委託契約とは
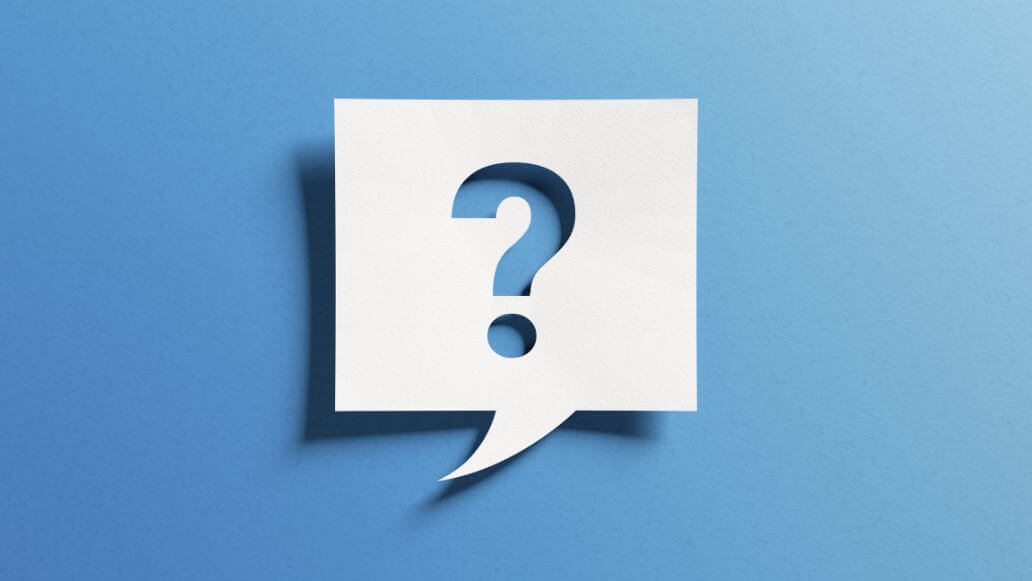
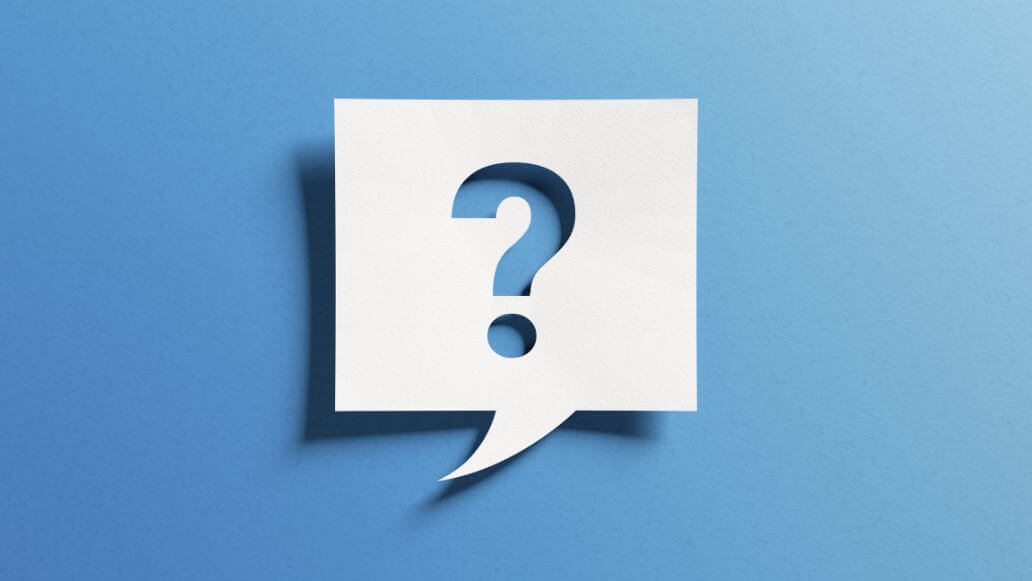
完全歩合制に関わる業務委託契約とは、仕事の発注者と仕事の受注者となる個人事業主の間で、以下のような内容を記した契約書を取り交わすことです。
- 業務内容
- 報酬
- 契約期間
しかしながら、法律に業務委託契約に関する定めはありません。法律上で業務委託契約にあたるのは、以下の2つの契約です。
| 名称 | 請負契約 | 委任契約・準委任契約 |
| 内容 | 一定基準を満たした受注者の成果物に対して発注者が報酬を支払う契約 | 受注者の業務の遂行に対して発注者が報酬を支払う契約 |
| 一般的な受注者の職種 |
|
|
なお、一般的に委任契約を取り交わすケースは弁護士などへ法律行為が伴う業務を依頼する場合のみです。
上記の契約のいずれかを取り交わした個人事業主に限り、完全歩合制の対象者となることを覚えておきましょう。
4. 最低賃金がない完全歩合制の導入が違法となるケース


最低賃金がない完全歩合制の導入が違法となるケースは、雇用契約を結んだ以下のような労働者を対象とした場合です。
- 正社員
- 契約社員
- アルバイト
- パート
雇用契約を結んだ従業員の賃金には、法律による定めがあります。歩合制を導入している場合でも、労働時間に応じた一定額の賃金を保障しなければなりません。
例えば、営業職の従業員と歩合制による雇用契約を結んだ場合です。従業員の成果がまったくない場合でも、法律により会社は従業員に賃金を支払う必要があります。
従って、完全歩合制の導入が違法とならないケースは、法律が適用されない業務委託契約を取り交わした個人事業主を対象とする場合のみです。
5. 最低賃金がない完全歩合制と歩合制の違い
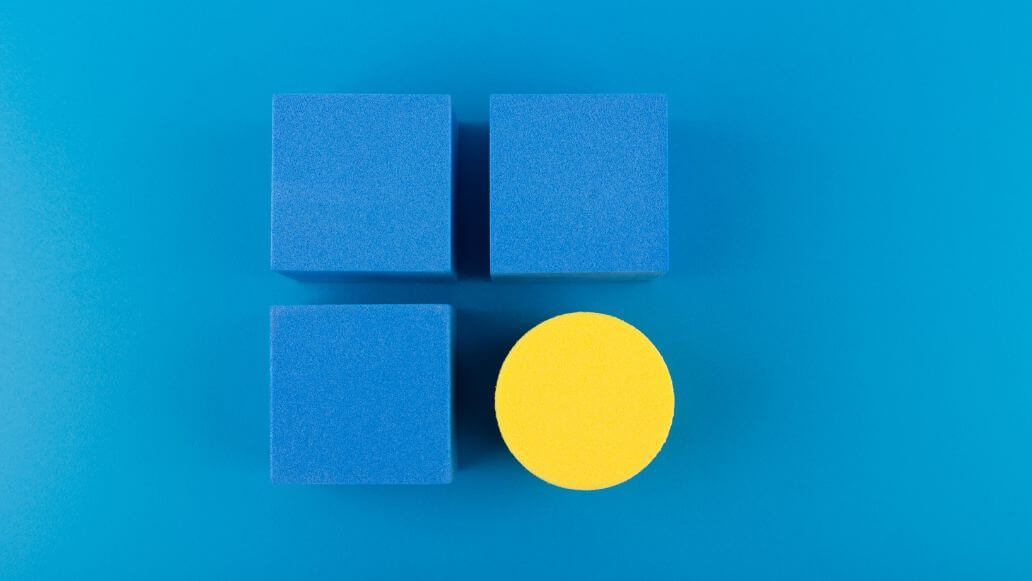
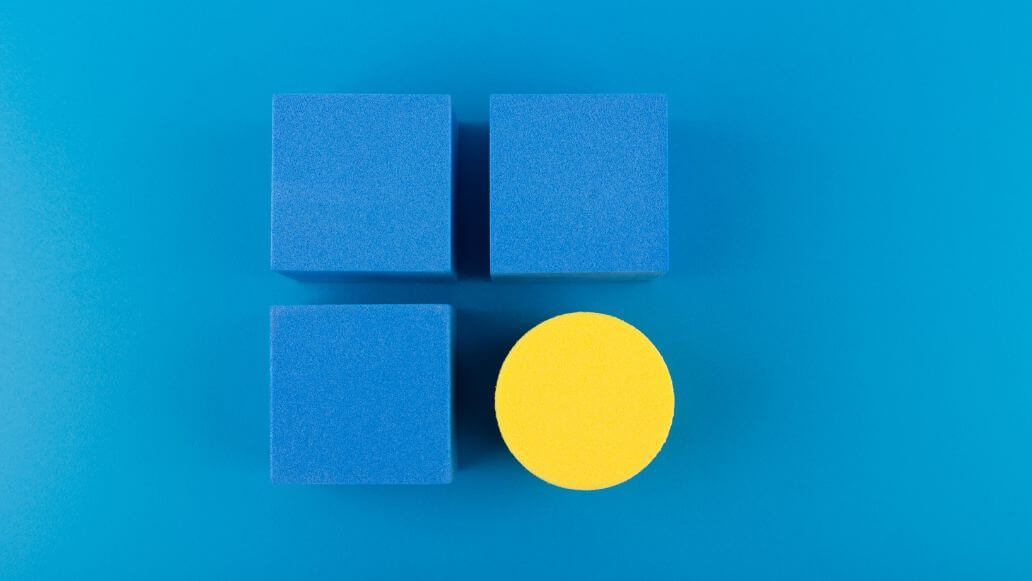
最低賃金がない完全歩合制と歩合制の違いは、以下のとおりです。
| 完全歩合制 | 歩合制 | |
| 違法にならない対象者 | 仕事の発注者(委託者)と業務委託契約を結んだ個人事業主(受託者) | 会社(雇用主)と雇用契約を結んだ従業員(労働者) |
| 労働基準法・最低賃金法の対象となるかどうか | 対象外 | 対象 |
| 報酬・賃金の内訳 | 報酬(歩合給に相当)のみ | 固定給と歩合給 |
上記の歩合制の固定給とは、労働者の成果の有無に関係なく、会社が労働者に支払う一定の給与のことを指します。
成果に応じた報酬や歩合給が支払われる点は、どちらの制度も同様です。しかし、委託者と委託者・雇用主と労働者が結んだ契約の内容により、歩合率はそれぞれ異なります。
例えば、歩合率を売上の10%とする契約を結んだ場合、1ヵ月に100万円売り上げた場合の歩合給や報酬は10万円です。
歩合制では賃金として歩合給の10万円に固定給を加えて支払い、完全歩合制では報酬として10万円のみ支払います。
6. 最低賃金がない完全歩合制を導入する際の3つの注意点


最低賃金がない完全歩合制の導入の注意点は、以下の3つです。
- 個人事業主との業務委託契約により導入する
- 業務委託契約でも雇用契約と判断される場合がある
- 報酬の基準を明確にする
各注意点について見ていきましょう。
6-1. 個人事業主との業務委託契約により導入する
最低賃金がない完全歩合制を導入する際の注意点の一つは、個人事業主との業務委託契約により導入することです。個人事業主と結ぶ業務委託契約には、労働基準法や最低賃金法の定めが適用されません。
雇用契約を結んだ労働者を対象とした導入は、違法です。最低賃金がない完全歩合制を導入する場合は、業務委託契約を結んだ個人事業主のみを対象として導入しましょう。
6-2. 業務委託契約でも雇用契約と判断される場合がある
契約書上は業務委託契約でも雇用契約と判断される場合があることも、最低賃金がない完全歩合制の導入の注意点です。個人事業主が仕事の依頼者の指揮監督下で働き報酬を得ていると判断される場合は、契約書上は業務委託契約でも雇用契約とみなされる場合があります。
例えば、以下のような場合です。
- 会社が業務命令や指示を出す
- 会社が勤務時間や勤務場所を指定する
- 会社の就業規則に従わせようとする
- 個人事業主が自由に仕事を断れない
また、合法的に完全歩合制を導入できる業務委託契約では、仕事の発注者(委託者)と個人事業主(受託者)の関係は対等です。一方、完全歩合制の導入が違法となる雇用契約では、雇用主と労働者の間に主従関係があります。
実態が雇用契約だと判断された場合には、労働基準法や最低賃金の適用対象となるため、完全歩合制の導入は違法です。
6-3. 報酬の基準を明確にする
最低賃金がない完全歩合制の導入の注意点として、報酬の基準を明確にすることも挙げられます。導入前に報酬額や報酬の決め方を明確にし、業務委託契約書に明記することで、業務委託契約を結ぶ個人事業主とのトラブルを避けられるでしょう。
例えば、以下のような報酬の決め方があります。
- 総売上金額に対して一定の%(歩合率)を乗じた金額を支給
- 契約1件あたりの金額を定めて、総契約件数に応じた金額を支給
また、事前に依頼する業務に応じた報酬の相場を調べておきましょう。業務委託契約における報酬額や報酬の決め方は、基本的に会社と個人事業主の双方の合意により決まるためです。
7. 完全歩合制には最低賃金がないことを理解しておこう


完全歩合制には、最低賃金がなく固定給もありません。歩合給に相当する、成果に応じた報酬のみが支払われます。
完全歩合制の対象者となる方は、法律の賃金の定めが適用されない業務委託契約を締結した個人事業主のみです。対象者以外の導入は、違法となるため注意しましょう。
歩合制を導入したい場合には、適切な対象者のみに完全歩合制を導入するか、固定給と歩合給を支払う仕組みを導入します。
本記事の内容も参考にしつつ、最低賃金がなく対象者が限定される完全歩合制について理解を深めましょう。



人事労務担当者の実務の中で、従業員情報の管理は入退社をはじめスムーズな情報の回収・更新が求められる一方で、管理する書類が多くミスや抜け漏れが発生しやすい業務です。
さらに、人事異動の履歴や評価・査定結果をはじめ、管理すべき従業員情報は多岐に渡り、管理方法とメンテナンスの工数にお困りの担当者の方もいらっしゃるのではないでしょうか。
そんな人事労務担当者の方には、Excel・紙管理から脱却し定型業務を自動化できるシステムの導入がおすすめです。
◆解決できること
- 入社手続きがオンラインで完結し、差し戻し等やりとりにかかる時間を削減できる
- システム上で年末調整の書類提出ができ、提出漏れや確認にかかる工数を削減できる
- 入社から退職まで人事情報がひとつにまとまり、紙やExcel・別システムで複数管理する必要がなくなる
システムを利用したペーパーレス化に興味のある方は、ぜひこちらから資料をダウンロードの上、業務改善にお役立てください。
人事・労務管理のピックアップ
-


【採用担当者必読】入社手続きのフロー完全マニュアルを公開
人事・労務管理公開日:2020.12.09更新日:2026.01.30
-


人事総務担当がおこなう退職手続きの流れや注意すべきトラブルとは
人事・労務管理公開日:2022.03.12更新日:2025.09.25
-


雇用契約を更新しない場合の正当な理由とは?伝え方・通知方法も紹介!
人事・労務管理公開日:2020.11.18更新日:2025.10.09
-


社会保険適用拡大とは?2024年10月の法改正や今後の動向、50人以下の企業の対応を解説
人事・労務管理公開日:2022.04.14更新日:2025.10.09
-


健康保険厚生年金保険被保険者資格取得届とは?手続きの流れや注意点
人事・労務管理公開日:2022.01.17更新日:2025.11.21
-


同一労働同一賃金で中小企業が受ける影響や対応しない場合のリスクを解説
人事・労務管理公開日:2022.01.22更新日:2025.08.26
労務の関連記事
-


年収の壁はどうなった?2025年最新動向と人事が押さえるポイント
勤怠・給与計算公開日:2025.11.20更新日:2025.11.17
-


2025年最新・年収の壁を一覧!人事がおさえたい社会保険・税金の基準まとめ
勤怠・給与計算公開日:2025.11.19更新日:2025.12.22
-


人事担当者必見!労働保険の対象・手続き・年度更新と計算方法をわかりやすく解説
人事・労務管理公開日:2025.09.05更新日:2026.01.30






















