目標設定の重要性や設定するときの注意点を詳しく紹介
更新日: 2025.4.17 公開日: 2023.5.30 jinjer Blog 編集部
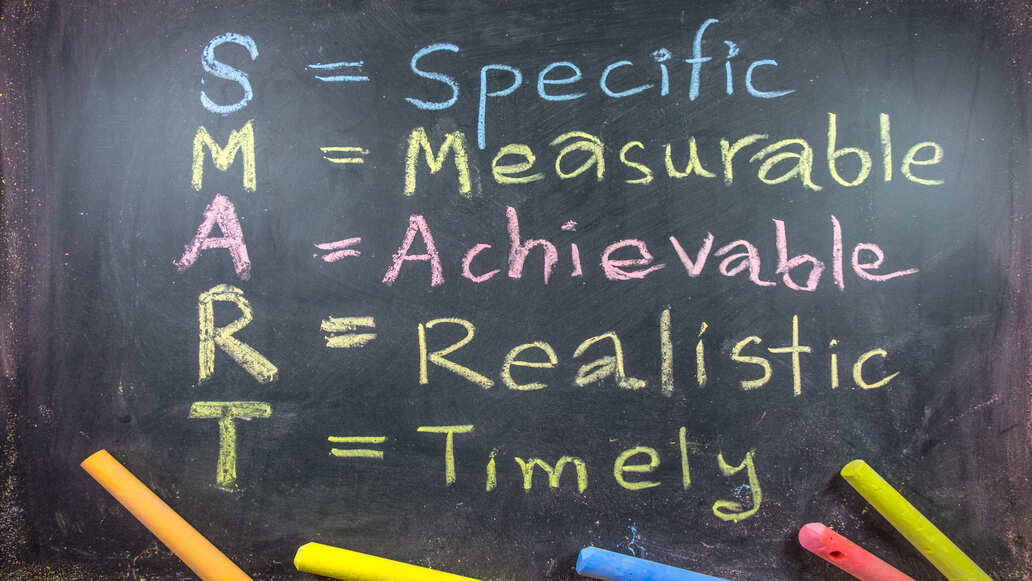
目標設定は、チームを管理する上でなくてはならないプロセスです。具体的かつ明確な目標がないと、進むべき方向や選択すべき手段が見えてきません。目標設定の重要性を理解して、メンバーの士気や業務効率が向上する目標を設定しましょう。
目標設定の重要性や効果的な目標を設定する方法、さらには目標を設定するときの注意点を紹介します。
目次

人事評価制度は、健全な組織体制を作り上げるうえで必要不可欠なものです。
制度を適切に運用することで、従業員のモチベーションや生産性が向上するため、最終的には企業全体の成長にもつながります。
しかし、「しっかりとした人事評価制度を作りたいが、やり方が分からない…」という方もいらっしゃるでしょう。そのような企業のご担当者にご覧いただきたいのが、「人事評価の手引き」です。
本資料では、制度の種類や導入手順、注意点まで詳しくご紹介しています。
組織マネジメントに課題感をお持ちの方は、ぜひこちらから資料をダウンロードの上、お役立てください。
1. 目標設定とは?

チーム管理に目標設定が必要といわれるのは、目標があることでチームが行動を起こしやすくなるためです。目標設定とは何なのか、目的との違いを交えて紹介します。
1-1. ゴールに向けて具体的な指標を設定すること
目標設定とは、最終ゴール(目的)を達成する上で必要となる具体的な指標を決めることです。
最終的な目的の達成に必要な行動・方針・施策・結果などのことで、チームメンバーで目標を共有することで、個々のメンバーが何をすべきかを自分自身で判断しやすくなります。目標設定をしていないと、ゴールは見えていても「何をすればいいかわからない」「どの方向にがんばればよいのか決められない」「ゴールに近づいているのか不安になる」など、行動のぶれやモチベーションの低下を招きやすくなります。
ただし効果的な目標を設定するためには、自社の経営戦略はもちろん、チームメンバーのスキル・実績についても深い理解が必要です。
1-2. 目標と目的との違い
目的とは、最終ゴールです。これに対し目標は、最終ゴールに至るまでに目指すべき指標を指します。目的を達成するために目標があると考えればよいでしょう。
例えば、市場シェア率1位を達成したいというのは目的です。これを達成するためには、営業の件数を増やしたりWebサイトのコンバージョン率を上げたりなどが必要となります。
一方、営業の訪問件数を○件増やす、コンバージョン率○%アップを目指すなどと設定した場合、これらは目的ではありません。目的を達成するために設定される目標です。
企業では、目標は複数階層で設定されるのが一般的です。一例をいうと、大きい方から、企業目標、部署目標、チーム目標、個人目標などがあります。目標を階層別に設定することで、目的達成までのルートがより具体的・現実的になるのがメリットです。
2. 目標設定のメリット

適切な目標を設定することは、目的達成までにかかる時間・ルートの短縮につながります。目標設定をすることで得られるメリットを見ていきましょう。
2-1. 作業効率の向上につながる
目標を設定すれば、社員一人ひとりがすべきことが見えやすくなります。まず何をすべきか、何を優先したほうがいいか、どのくらいの時間でこなすべきかなどの把握が容易になり、余計なプロセスを省略することが可能です。
また、小目標を達成することでチームの士気が上がりやすくなり、モチベーションや団結力も高まりやすくなるでしょう。チームの雰囲気がよければ作業効率も上がります。
そして目標の未達は、社員が自分自身を振り返るチャンスとなります。目標が達成できなかった原因を探すことで、社員は業務のムダや非効率なやり方に気付くはずです。改善点が分かれば、社員の作業効率はより一層向上します。
2-2. 社員のモチベーションを維持できる
次にすべきことや短期間で達成できる小目標が見えていると、モチベーションを維持しやすくなります。
遠いゴールはわかっていても、明確に「今をこれをする必要がある」というものが分からないと、人はどうしても集中できなくなるものです。その結果、作業が進まなくなり、徐々にモチベーションが下がり、さらに作業が進まなくなり…という悪い循環が生まれます。
目標設定をすることで道標ができるため、どこに向かえばいいか、どのように頑張ればいいかが明確になり、チームであれば同じ方向を向いて業務を遂行することができます。そうして小目標を達成していけば達成感も得られ、さらにモチベーションが上がっていきます。
2-3. 進捗管理が容易になる
目標達成のためのマイルストーンを細かく設定すれば、進捗管理もスムーズになります。一つクリアしたらまた次…と順を追ってステップが進むため、社員が次のアクションに迷うこともありません。
また進捗管理表の作成により、チーム全体の状況を可視化・共有できます。達成が遅れている目標は致命的になる前に対策できる上、デッドラインに向けてスパートをかけることも容易です。進捗管理が適切にできていれば、ギリギリになって大慌てで対応するということもなくなるはずです。
加えて、進捗度を従業員がそれぞれ認識することで、業務の効率や質にも大きな影響がでます。予定よりも遅れている場合は、遅れを取り戻すために行動し、余裕があれば再確認やよりよい方法の模索などができるでしょう。
3. 目標設定の方法

目標は、内容、方法、期限などの設定の仕方や内容が重要で、ゴールを目指す効率にも大きく影響します。目標設定をする際に意識したいポイントを解説します。
3-1. 目標の根拠を明確化する
目標の種類には、今ある課題を解決するために設定する発生型目標と、個人の意志で目標を設定する設定型目標があります。目標を設定するときは、どちらのタイプに該当するか考えましょう。
二つの目標の種類の違いは、合意形成のしやすさです。課題解決のための発生型目標は、メンバーの理解を得やすくなります。一方で設定型目標は、なぜこの目標なのかという強い根拠がないと、合意を得るのは困難です。
例えば社員の売上目標について、○%アップするとした場合、なぜ○%アップする必要があるのか、なぜ売上目標のアップが必要なのかという議論が起こる可能性があります。
目標の種類に合わせ、「なぜ」の部分を明確にしてください。
3-2. フレームワークで具体的な目標を設定する
目標に曖昧さがあったり、細かく分けすぎて目標の数が多すぎたりすると、目標達成に向けた意識が分散しやすくなります。
「何をすればいいかわからない」や「あれもこれもやることがある状態」を回避するためには「今何をするべきか」が明確にわかるように、フレームワークを使いましょう。
フレームワークで優先的に取り組むべき目標や、今進めるべき業務などがわかれば、集中して取り組みやすくなります。また、フレームワークを使えばチーム内の共通認識も構築しやすくなり、進捗管理にも役立つためより効率的に目標達成に向かって進めるはずです。
3-3. 目標達成までに必要なタスクを洗い出す
目標を達成するには、さまざまなプロセスを経る必要があります。前述したようにフレームワークを使えば、目標はより具体的になって進め方もわかりやすくなります。
しかし、やるべきことが分かってもそれに具体性がなければ効率的な業務はおこなえません。
たとえば、新商品の売り上げを上げたいときに「もっと宣伝をして多くの人に知ってもらう」という方針は間違っていません。しかし、そのために何をすればよいか具体的には決まっていない状態です。
タスクを洗い出す際は「10代にも知ってもらえるように〇〇でも宣伝をおこなう」「製品の良さを伝えるために動画を作成する」といったように、誰が見ても明確にわかる行動をリストアップすることが大切です。そしてそうした行動に必要な行動をあげていけば、よりはっきりとしたタスクが見えてくるでしょう。
3-4. 目標達成の期限を設定する
目標を設定していても、期限がなければ緊張感がなくなってしまいます。
目標達成までの期限はその内容によってさまざまで、数ヵ月で達成できるものもあれば、数年単位の大きなプロジェクトである場合もあります。目標達成までの期間が長いと、意識が薄れやすいため途中で期限を区切ることが大切です。数ヵ月や半年など、適切な期限を設定しましょう。
小目標や中目標を設定し、それぞれに期限を設ければ最終的な大目標達成の期限も自然と守れるはずです。中間目標を達成することでの達成感や、定期的に来る期限に対する緊張感も得られるため、モチベーションを維持しやすくなります。
4. 【業種別】目標設定の具体例・書き方

目標設定を有用なものにするには、業種や部署に合わせた具体的な内容が欠かせません。ここでは業種別に目標設定の例や書き方を紹介していきます。
4-1. 目標の種類
目標には「発生型目標」と「設定型目標」の2つがあります。この2つの違いを知り、使い分けることでよりわかりやすい目標を設定できます。
①発生型目標
発生型目標は「すでに問題や課題が発生している状態」で設定する目標です。発生している問題・課題を解消することが目標になるもので、マイナスの状態を0に戻すように設定します。
発生型目標で重要なことは「このラインまでくればよい」「ここまで戻してようやく通常の状態になる」といった基準値を目標にすることです。つまり、この基準値が曖昧だったり、チーム内で認識がばらついていたりすると目標の達成が困難になります。
②設定型目標
設定型目標は、設定する時点で明確なゴールが決まっていないタイプの目標です。
発生型目標のように「問題を解決して基準値に戻す」という性質ではなく、現状よりも上を目指したり、新しいものを開発したりする際に使われる目標です。
明確な基準値がない、あるいは基準値を超えている状態でさらに先を目指すストレッチ目標になるため、発生型目標よりも目標を具体的かつ期限を決めて設定しないと達成しにくいです。
4-2. 目標設定の具体例
発生型目標と設定型目標があることがわかったところで、実際に目標設定を考えていきましょう。業種別に具体例を紹介していきます。
営業職
営業職の目的は、営業を成功させて売り上げをよくすることです。そのために必要な目標設定としては、以下のようなものが考えられます。
- 3ヶ月以内に新規顧客を5件以上獲得する
- 部署としての売り上げ目標を達成するために個人の目標を見直し必要な指導をする
- 営業部のメンバーの7割以上が売り上げ目標を達成できるようにサポートをする
営業職は成果が数字に出やすいため、期限や目標をできるだけ数値化して目標設定をすると効果的です。売上目標未達などの課題を抱えているのか、それともより上を目指したいのかによって、発生型目標と設定型目標を使い分けるようにしましょう。
販売職
販売職も営業職と似ている部分があり、売上を上げることを目標にします。
- 店舗の売り上げを前年よりも10%上げる
- 夏物の過剰在庫を5月中までに40%以上減らす
- 問題のある従業員への指導をして接客態度を改善し、クレーム0を目指す
販売職の場合は、接客や在庫に対する目標も設定することで最終的な利益を増やすことにもつながります。店舗全体を見て必要な目標設定をすることが大切です。
事務職
事務職は数字による成果が発生しにくいため、目標設定が曖昧になりやすいです。それを解消するために、目標設定では具体的な数字を出すとよいでしょう。
- 消耗品や備品の在庫管理を徹底し、経費を前年よりも5%削減する
- 電話は3コール以内にとり、メールはできるだけ即日返信をして顧客満足度を上げる
- 業務効率化のために有用なアプリやシステムを検討し3種類以上提案する
事務職は企業によって業務の幅が違い、方針にも差があります。そのため、抱えている問題に対応する発生型目標を中心に設定すると具体的な内容が考えやすいでしょう。
人事・労務
人事や労務は社内の幅広い業務に携わるため、目標もさまざまです。発生型目標と設定型目標それぞれを使い分けて、優先して取り組むべき目標を決めましょう。
- 従業員満足度を改善し、前年の離職率15%から10%まで下げられるようにする
- 採用プロセスの効率化や会社説明会の充実をおこない1年で40人の採用を目指す
- 勤怠管理システムを刷新し、勤怠管理にかかる時間を20%減らしミスをなくす
人事や労務は、部署内のみで決定できる目標だけでなく、他部署の承認や連携が必要なケースがあります。特に設定型目標を作る場合は、必要に応じて合意を得てから決定するようにしましょう。
5. 目標設定に効果的なフレームワーク

ビジネスにおける目標設定では、役立つフレームワークが多数存在します。ここではその中から代表的なものを紹介します。
5-1. SMART
SMART目標設定に必要な五つの要素の頭文字を取ったもので、組織や個人が目標を設定する際に、目標設定の基準を示すフレームワークです。
- 具体的(Specific):具体的かつ曖昧さが排除されている
- 測定可能(Measurable):数値で効果測定できる
- 到達可能(Achievable):現実的な数値が設定されている
- 価値のある(Relevant):取り組む価値があると思える
- 時間制限のある(Time-bound):明確かつ根拠のある期限が設定されている
SMARTはどのような目標設定においても有用な方法で、上記の要素を全て満たせば、納得感がありつつも非現実的ではない目標を設定できるはずです。
ただし、数字による成果がでにくい業種の場合は「測定可能(Measurable)」が満たしにくい場合がありますが、割合や期日を明確にすることでSMARTの効果を損なわずに済むでしょう。
5-2. MBO
MBO(Management by Objectives)は組織マネジメントの概念のひとつで、日本語に直訳すると「目標の管理」になります。
目標管理といっても、上司やリーダーが一方的に管理して支持をするのではなく、従業員個人が自己管理によって個人目標を設定してマネジメントすることを言います。「チームの目標がこれだから、自分はここまでにこうしよう!」というような目標です。
組織や部署、チームなどの目標と個人目標がつながることで、従業員ひとりひとりが企業に貢献しているという意識が生まれ、モチベーションを維持しやすくなるでしょう。
MBOでは目標の達成度によって評価することもできるため、人事評価制度とリンクさせて運用することも可能です。
5-3. OKR
OKR(Objectives and Key Results)は、日本語に直訳すると「目標と主要な結果」です。目標設定や管理方法の考え方のひとつで、Googleをはじめとした大手IT企業で導入されました。
OKRでは目標の達成に必要な主要な成果を決め、その成果を上げるために課題に取り組んだり、業務を進めたりします。「何をすべきか」「どんな成果を上げるべきか」が非常に明確になるため、効率的に目標に向かって進みやすくなります。
また、上げるべき成果が明確になることでチームが団結力を高めて高い士気で必要な取り組みを推進することもできるようになるでしょう。目標達成に向けた力を高めたい際にOKRは有用な手法です。
5-4. KGI・KPI・KDI法
KGI・KPI・KDIは成果の指標を定量的に定め、設定した目標をどれくらい達成できたか判断する指標です。いずれも日本語にすると「重要〇〇指標」という言葉になります。
| KGI(Key Goal Indicator) | 「重要目標達成指標」を意味し、最終的なゴール地点が指標になっています。企業レベルのゴールとして設定されることが多く、売上高や粗利益、経常利益などを目標として設定することが多いです。 |
| KPI(Key Performance Indicator) | 「重要業績評価指標」を意味し、目的を達成するために必要な要素を指標にしたものです。中間数値指標と呼ばれることもあり、いわゆる中間目標や中目標のように扱われます。顧客獲得数や来場者数、契約成立数などが設定されます。 |
| KDI(Key Do Indicator) | 「重要行動指標」を意味するもので、KPIを達成するために必要な要素を指標にしたものです。KPIを達成するためにどのような行動をするか、どのような成果を上げるかを数値によって表すことが多いです。営業電話を〇回する、メールマガジンを〇通以上送るなど、具体的な指標になります。 |
KGI・KPI・KDIはつながっており、KGIを達成するために必要な要素がKPIで、KPIを達成するために必要な要素がKDIです。KDIを丁寧に遂行し、KPIを達成していけばKGIの達成にもつながることになり、従業員ひとりひとりの目標設定が企業としてのゴールに向かっています。
大きな目標ではぼやけてしまう指標を細かく分け、従業員が明確な目標をもって業務をおこなえるようにするのがKGI・KPI・KDI法です。
関連記事:目標を数値化するメリット・デメリットや方法を詳しく解説
6. 目標設定の注意点
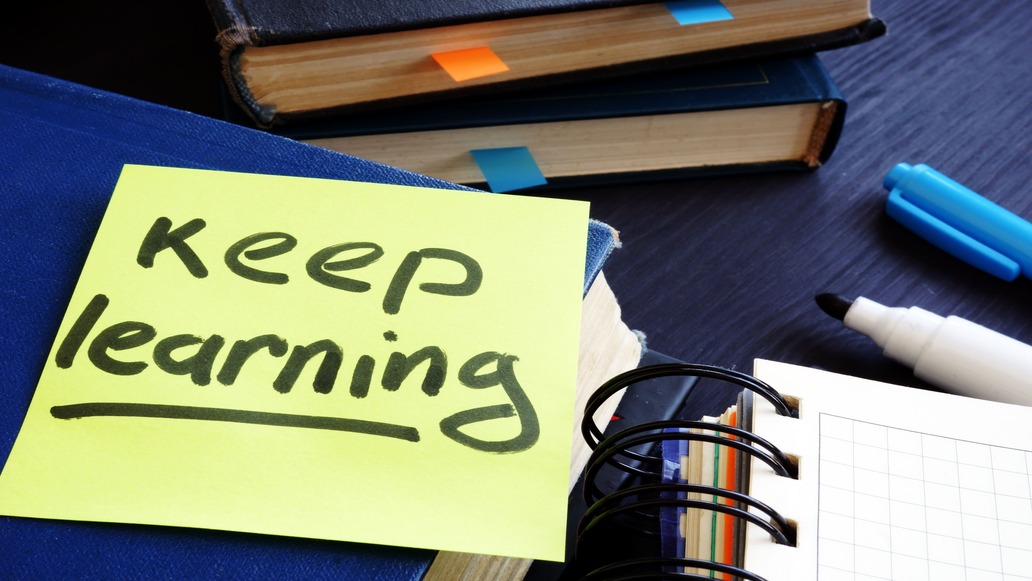
目標設定は必要ですが、思いつきで作ったような目標は社員のモチベーション低下につながります。目標を設定するときの注意点を見ていきましょう。注意点を押さえれば目標設定におけるコツにつながります。
6-1. 目標に固執しすぎない
目標は、あくまでも現時点の状況に即したものです。将来状況が変わったときは、柔軟に対応しなければなりません。状況の変化を読み取れずに古い数値・目標に固執すると、目標設定の意味がなくなってしまいます。例えば、さまざまな要因によって目標設定シートに記載した進捗に変化があった場合は、軌道修正が求められます。
環境の変化に柔軟に対応するためには、目標設定の時点で状況が変化する可能性を組み込んでおくことが重要です。最初から別のブランも想定しておくことで、いざというとき柔軟に目標数値や方向性を変えられます。
6-2. 公平さを維持する
チームや社員に目標を課すときは、負担の大きさが偏らないよう注意します。目標の難易度に差があると合意を得にくい上、社員のモチベーションも下がるかもしれません。全員が同じ目標に向かって邁進するためには、個々の負担に差が出ることは控えるべきです。
チーム全体で同じ負担を共有すれば、メンバー同士のつながりが強まったりチームの一体感が高まったりといったメリットがあります。
コミュニケーションの密度は、業務効率や業務成績はもちろん、職場の雰囲気にも直結するものです。目標設定を誤って、職場がギスギスしないよう注意しましょう。
6-3. 期限は短めに設定する
目標は中長期的なものと短期的なものを設定します。数年単位の長期目標でも、数ヶ月単位の中目標や小目標を設定し、目標達成までの期間が空きすぎないよう注意しましょう。
目標未達の状態が長すぎると、社員のモチベーションを保てません。短期目標で成功体験を積み重ねていくことが、中長期のより大きな目標達成につながります。ゴールまでの道筋を逆算し、細かく目標を設定しましょう。
また、短い期限を設定することで適度な緊張感も生まれるため、メリハリのある業務がしやすくなるでしょう。
6-4. 少し難しい目標を設定する
設定する目標は少し難しいものにしましょう。簡単な目標では従業員のスキルアップやモチベーションアップにつながりません。
少し難しい目標であれば、それを達成するために足りないものを補おうとしたり、より効率的な方法を模索したりするでしょう。その結果従業員のスキル、モチベーションのアップが期待できます。
目標の達成を目指す中でスキルアップをしてければ、従業員もやる気が出やすく、さらに上を目指せるようになるはずです。
ただし、達成が難しすぎる現実的ではない目標にすると反対にモチベーションが下がってしまいます。達成可能な範囲を慎重に見極めましょう。
6-5. 過去の目標を参考にする
過去の目標を参考にするのも効果的です。例えば評価者である上司が過去に設定した目標を共有して参考にしてみましょう。目標の参考があれば、設定の際の精度向上が期待でき、実際の経験があるためより的確で具体的なアドバイスもしやすくなります。
しかし、過去に達成した目標であることを押し付けてはいけません。「自分たちはできたのだからできるはず」「過去に達成できているのだからできないのはおかしい」というように、結果だけを見た強引な方法は反感を招きます。
過去の目標だけでなく、達成した際の環境や人員、従業員の経験やスキルなども考慮し、あくまでも参考程度にするようにしましょう。
6-6. 目標について相談できる環境を作る
従業員が目標を設定したとしても、適切な目標かどうかを本人が判断できない可能性もあります。適切な目標を設定できているかどうか、相談しやすい雰囲気を作り出しましょう。
相談ができれば高すぎる目標を設定して自分自身を追い詰めてしまうケースや、目標が低すぎて成長につながらないといったケースを回避しやすくなります。
相談しやすい環境は、目標が未達になりそうな場合の相談や、反対にモチベーションが下がっていそうなメンバーへの面談などもしやすくなるはずです。チーム内のコミュニケーションを活性化するためにも、相談しやすい環境づくりは非常に大切です。
6-7. 定期的な振り返りをする
目標は一度設定して終わり、達成できたから終わり、というものではありません。
設定している目標は定期的に見直し、本当に適正なのか、最新の状況にも適しているかなど、常に新しい情報と照らし合わせて確認しましょう。
そして過去の目標も、達成できているのならばそのプロセスや環境を参考にし、未達の場合は課題や問題点の改善に取り組むために活用できます。定期的に自分たちが積み上げてきたものを振り返り、よい点を引き継ぎ、悪い点は改善しましょう。
7. 適切な目標設定をして企業全体の活性化につなげよう

目標を設定することは、作業効率の向上や社員のモチベーションアップに有効です。進捗管理もしやすく、社員が目的意識を持って働きやすくなります。
ただし曖昧かつ具体性のない目標は、社員にとって負担です。どこを目指せばよいか分からない目標は避け、数値を伴った具体的な目標を設定しましょう。
業務効率化が声高にいわれる昨今、目標なしに働くことは時代の流れに逆行しています。「どのような」「何のために」「いつまでに」という要素をしっかり抑えて、有益な目標設定をおこなってください。
関連記事:目標とは?目的との違いや設定するためのポイントを紹介

人事評価制度は、健全な組織体制を作り上げるうえで必要不可欠なものです。
制度を適切に運用することで、従業員のモチベーションや生産性が向上するため、最終的には企業全体の成長にもつながります。
しかし、「しっかりとした人事評価制度を作りたいが、やり方が分からない…」という方もいらっしゃるでしょう。そのような企業のご担当者にご覧いただきたいのが、「人事評価の手引き」です。
本資料では、制度の種類や導入手順、注意点まで詳しくご紹介しています。
組織マネジメントに課題感をお持ちの方は、ぜひこちらから資料をダウンロードの上、お役立てください。
人事・労務管理のピックアップ
-

【採用担当者必読】入社手続きのフロー完全マニュアルを公開
人事・労務管理公開日:2020.12.09更新日:2026.01.30
-

人事総務担当がおこなう退職手続きの流れや注意すべきトラブルとは
人事・労務管理公開日:2022.03.12更新日:2025.09.25
-

雇用契約を更新しない場合の正当な理由とは?伝え方・通知方法も紹介!
人事・労務管理公開日:2020.11.18更新日:2025.10.09
-

社会保険適用拡大とは?2024年10月の法改正や今後の動向、50人以下の企業の対応を解説
人事・労務管理公開日:2022.04.14更新日:2025.10.09
-

健康保険厚生年金保険被保険者資格取得届とは?手続きの流れや注意点
人事・労務管理公開日:2022.01.17更新日:2025.11.21
-

同一労働同一賃金で中小企業が受ける影響や対応しない場合のリスクを解説
人事・労務管理公開日:2022.01.22更新日:2025.08.26
人事評価の関連記事
-

派遣でも部署異動はさせられる?人事が知っておくべき条件・注意点・手順を解説
人事・労務管理公開日:2025.06.03更新日:2025.12.18
-

賞与の決め方とは?種類と支給基準・計算方法・留意すべきポイントを解説
人事・労務管理公開日:2025.05.26更新日:2025.05.27
-

賞与の査定期間とは?算定期間との違いや設定する際の注意点を解説
人事・労務管理公開日:2025.05.25更新日:2025.12.18































