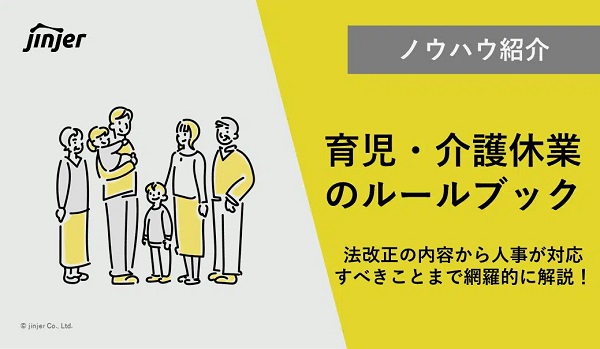育児休業期間はいつからいつまで?延長できる?給付金についても解説

育児休業を取得している従業員は、育児休業給付金の支給など手厚い支援を受けることができます。上手に活用することで仕事と育児の両立が実現できる制度ですが、期間はどのくらいあるのでしょうか。
この記事では、育児休業期間がいつからいつまであるのか詳しく解説しています。従業員から休業の延長依頼をされたときの手続き方法についても紹介していますので、ぜひ最後までご覧ください。
目次
「育児・介護休業のルールブック」を無料配布中!
会社として、育休や介護休業の制度導入には対応はしてはいるものの 「取得できる期間は?」「取得中の給与の正しい支給方法は?」このようなより具体的な内容を正しく理解できていますか?
働く環境に関する法律は改正も多く、最新情報をキャッチアップすることは人事労務担当者によって業務負担になりがちです。
そんな方に向けて、当サイトでは今更聞けない人事がおこなうべき手続きや、そもそもの育児・介護休業法の内容をわかりやすくまとめた資料を無料で配布しております。
また、2022年4月より段階的におこなわれている法改正の内容と対応方法も解説しているため、法律に則って適切に従業員の育児・介護休業に対応したい方は、こちらから資料をダウンロードしてご活用ください。
1. 育児休業期間はいつからいつまで?

育児休業とは、1歳未満の子どもを養育するために法律で定められた制度です。休業期間は、原則として子どもが1歳になる前日までとしています。なお公務員の場合、育児休業期間は最大3年間まで認められています。
女性の場合、出産直後の8週間は産休になるため、育児休業の開始日は子どもが生まれて57日目以降からになるのです。
育児休業は子ども1人につき1回まで取得できます。しかし、法改正により2022年10月以降は休業期間の分割が認められるようになるため、今後は期間中であれば分割して2回の取得も可能です。
1-1. 男性の育児休業期間は女性と異なる?
男性の育児休業期間は、配偶者の出産予定日から1歳になる前日までです。女性は出産後、産後休業を挟むため、男女で育休期間は異なります。
男性の育休取得率は、2021年の調査で13.97%であり、女性の85.1%と比較すると非常に低い数値です。しかし、それでも年々上昇傾向にあるため、以前よりは取得しやすくなってきています。
ですが、取得期間は2週間未満が50%以上を占めており、子どもが1歳になるまで取得できている人はほとんどいません。
予定日より早く生まれた場合
育休開始日は出産予定日としていますが、実際予定日通りに出産できるとは限りません。予定より早く生まれた場合は、会社に申し出ることで育児休業開始日の繰り上げが可能です。
予定日より遅く生まれた場合
予定日より早く生まれた場合とは異なり、遅く生まれた場合は元々の予定日から育児休業がスタートします。なお男性の場合も申請することで、育児休業給付金の受給が可能です。出産が遅れた場合でも、出産予定日から支給対象となります。
1-2. 多胎妊娠の場合でも育児休業期間は同じ
双子など2人以上の赤ちゃんを同時に妊娠する多胎妊娠であっても、子ども1人の場合と育児休業期間は変わりません。
多胎妊娠によって期間が変わるのは、産前休業のみです。通常、産前休業は6週間としていますが、多胎妊娠は14週間前からの取得ができます。
なお、育児休業給付金の額も、子どもの人数に関係なく額は同じです。
2. 育児休業期間は延長できる?

育児休業期間は、子どもが1歳を迎えるまでが基本の期間ですが、状況によっては延長も可能です。近年では待機児童問題があるため、「保育所に入園できなかった」など事情もあるでしょう。
このようなやむを得ない理由がある場合、子どもが1歳6ヵ月になるまで延長できます。さらに延長が必要になった場合は、最長2歳まで可能です。
なお、育児休業期間を当初の予定から変更する際は育児休業期間変更申出書が必要です。育児休業期間変更申出書はいくつもテンプレートがあるため、記入例を確認可能です。
2-1. 育児休業期間延長の条件
育児休業期間を延長するための条件は、延長をしないと子どもを養育する人がいない場合です。具体的には、主に以下のような理由が挙げられます。
- 保育所へ入園申込みをしたが入れなかった
- 配偶者の怪我、病気、死亡により養育が困難になった
- 配偶者と別居した
子どもが1歳の時点で、2歳までの延長希望を出されたとしても認められません。1歳6ヵ月まで延長するときと、2歳まで延長するときそれぞれで、条件に当てはまっている必要があります。
また、保育所への入園申し込みと入所希望日は、1歳の誕生日より前であることも条件です。
1歳の誕生日から1歳6カ月になるまで延長条件
1歳の誕生日から1歳6カ月になるまで育児休業期間を延長するためには、以下の条件を満たす必要があります。
まず、1歳の誕生日の前日に保護者またはその配偶者が育児休業中であることが前提です。その上で、次の①または②のどちらかに該当する場合に延長が可能です。
- 保育施設への入所を希望しているが、空きがないために入所できなかった場合
- は育児を担当する予定だった配偶者が、死亡、けが、病気、離婚などの事情で育児をすることが困難になった場合
保護者は、この育児休業延長を申請する際に、保育施設の入所が困難であることや配偶者の状況を証明するための書類を提出する必要があります。これにより、1歳6カ月になるまでの追加の育児休業を取得することができます。
1歳6カ月になった次の日から2歳の誕生日前日まで延長条件
1歳6カ月の誕生日を迎えた後でも、保育施設の入所が決まらない場合は、育児休業期間をさらに延長することが可能です。この期間中も保育施設への入所を試みていることを示す書類の提出が必要です。1歳6カ月になった次の日から2歳の誕生日前日まで延長が許可される条件として、まず、1歳6カ月になる日に本人またはその配偶者が育児休業中である必要があります。その上で、以下の①または②のいずれかに該当する場合、延長が適用されます。
- 保育施設への入所を希望しているが入れない状況
- 子どもを育てる予定であった配偶者が、死亡やけが、病気、離婚によって育児を行うことが難しくなった状況
これらの条件を満たしている家庭は、子どもが2歳の誕生日を迎える前日まで追加の育児休業を利用できます。
2-2. パパ・ママ育休プラスで2ヵ月の延長が可能
夫婦ともに育児休業を取得する場合は、「パパ・ママ育休プラス」という制度を利用することで、1年2ヵ月まで取得が可能になります。
パパ・ママ育休プラスは、夫婦が一緒に取得する方法や、育休を交代する形で取得する方法など、パターンはさまざまです。
この制度の利用条件は、以下のようになります。
- 夫婦ともに育児休業を取得していること
- 配偶者は子どもの1歳の誕生日までに育児休業を取得していること
- 本人の育休開始予定日が子どもの1歳の誕生日前であること
- パパ・ママ育休プラスの取得者の休業開始日が、配偶者の開始日以降であること
夫婦どちらが先に育休を取得しても問題ありませんが、先に取得した方は、制度の対象とはならず、通常通り子どもが1歳になるまでの期間となります。
パパ・ママ育休プラスは、特別な事情がなくても利用できる制度です。
3. 育児休業期間を延長するための手続き

育児休業期間を延長する場合は、従業員からの申し出を受けて、会社側が手続きをおこなう必要があります。
延長手続きをおこなわなかった場合、育児休業給付金が支給されなくなってしまうため、速やかに申請することが望ましいでしょう。延長するために必要な書類はハローワークへ提出しますが、休業終了の2週間前までに申請しなければなりません。そのため、育児休業期間を延長するための手続きの流れを正しく把握しておく必要があります。順番に説明します。
3-1. 延長申請に必要な書類を用意する
以下は、延長の理由によって異なる必要書類です。
- 保育所に入園できなかった場合:市区町村が発行する入所不承諾通知書
- 配偶者の怪我、病気、死亡により養育が困難になった場合:住民票、母子健康手帳、医師の診断書など
- 配偶者と別居した場合:住民票と母子健康手帳
これらを従業員に提出してもらう必要があります。なお、保育園に入れなかった証明となる「入所不承諾通知書」は、1歳の誕生日時点の入所状況が確認できるものに限るので、注意が必要です。
会社側は、以下の2つの書類を用意しましょう。
- 育児休業給付金支給申請書
- 賃金台帳や出勤簿など、支払い状況を証明できる書類
上記2つの書類は、初回の給付金申請手続きで使用したものと同じなので、用意は難しくありませんが、従業員に提出してもらう書類はできる限り早めに回収しましょう。
3つの書類がそろったら、管轄のハローワークへ提出して、延長手続きを完了させます。
3-2. 管轄のハローワークへ書類を提出する
延長申請に必要な書類を整えたら、次に管轄のハローワークへ提出します。提出手続きが完了すると、申請内容が審査されます。書類に不備や問題がなければ、延長の可否が判断され、結果が通知されます。提出期限や手続きの流れは事前に確認し、計画的に進めることが重要です。また、申請書類の正確性が求められるため、記載漏れや記載内容に誤りがないかを慎重にチェックしてください。育児休業期間の延長手続きにおいて、特に期限を守ることが重要であり、期限を過ぎると申請が受理されない可能性があるため注意が必要です。
4. 育児休業期間に受け取ることができる給付金

育児休業期間中には、多くの場合、育児休業給付金を受け取ることができます。この給付金は、労働者が育児休業を取る際の経済的な負担を軽減する目的で、健康保険や雇用保険から支給されます。育児・介護休業法では休業中の収入は保証されていませんが、この給付金が代わりにサポートを提供します。支給額は休業前の賃金に基づきますが、所得税や社会保険料の控除はありません。これにより、育児に専念する期間中の家計の安定が図られます。
4-1. 育児休業給付金
育児休業給付金は、原則1歳未満の子を養育するために育児休業を取得した場合、一部の要件を満たすと支給されます。育児休業開始から6カ月目までの支給額は、育児休業開始日前の6カ月間の賃金を180日で割った金額に支給日数を掛け、それに67%を掛けた金額です。7カ月目以降の支給額は、同様に計算された金額に対して50%を掛けた金額です。また、育児休業を延長した場合も、7カ月目以降と同じ計算式で支給額が算出され、子どもが1歳6カ月または2歳になるまで、賃金月額の50%を受け取ることができます。
さらに、育児休業を2回まで分割取得できるようになったことにより、1歳未満の子については、原則として2回まで育児休業給付金を受けることが可能です。具体的な支給額や手続きについては、雇用保険の加入状況や各個人の労働条件によって異なるため、事前に詳細を確認しておくことが推奨されます。
4-2. 出生時育児休業給付金
出生時育児休業給付金は、育児休業を取得する親に対して支給される特別な給付金です。産後の高額な育児費用に対処するため、この給付金は出産直後に主に提供されます。特に、産後パパ育休を取得した場合、一定の要件を満たすことで「出生時育児休業給付金」を受け取ることが可能です。
支給額は「休業開始時賃金日額×出生時育児休業を取得した日数×67%」という計算式に基づいて計算されます。基本的な考え方は一般的な育児休業給付金と同じですが、その支給日数は育児休業給付金の支給率67%の上限日数(180日)に含まれます。例えば、28日分の出生時育児休業給付金を受け取った場合、支給率67%の育児休業給付金を受け取れるのは残り152日分となります。
支給要件は以下のとおりです:
1. 休業開始日前の2年間に、賃金の支払い基礎日数が11日以上の完全月が12カ月以上あること。
2. 休業期間中の就業日数が、最大10日以下(10日を超える場合は80時間以内)であること。
申請期間は、子どもの出生日から8週間経過した翌日から2カ月後の月末までです。なお、2回に分割して取得した場合でも、給付金の申請は1回にまとめて行います。
以上の条件を満たすことで、出産後の育児負担を軽減し、安心して育児に専念できる環境を提供します。
5. 育児・介護休業法の改正内容

育児休業期間が関わる育児・介護休業法は2021年に改正されました。育児・介護休業法が2021年に改正されたことによって、育児休業について次のような変化が生まれました。
- 産後パパ育休(出生時育児休業)がスタート
- 育児休業の分割取得が認められる
- 雇用環境の整備や個別の周知・意向確認の措置が義務化される
- 有期雇用労働者が育児・介護休業を取得しやすくなる
- 育児休業取得状況の公表が義務化される
5-1. 産後パパ育休(出生時育児休業)がスタート
法改正により、産後パパ育休(出生時育児休業)がスタートしました。産後パパ育休は男性が育休とは別に最長4週間取得できる制度です。産後パパ育休がスタートしたことにより、男性の子育てへの積極的な参加を後押ししています。
5-2. 育児休業の分割取得が認められる
従来の育児休業は分割して取得はできませんでした。しかし、法改正により育児休業の分割2回で取得が可能になっています。育児休業を分割して取得することで、臨機応変な育児休暇を計画立てられます。
5-3. 育児休業が取りやすい環境の整備が義務化される
法改正によって育児休業が取りやすい環境の整備が義務付けられています。例えば育児休業期間とはどのような期間なのか、休業取得の事例提供といったように、従業員が育児休業を取りやすい環境を整えましょう。また、自社の育児休業についてルールや社会保険料免除などについて、従業員に周知する必要があります。
5-4. 有期雇用労働者が育児・介護休業を取得しやすくなる
法改正によって無期雇用、有期雇用など雇用形態に関わらず、育児休暇が取得しやすくなりました。例えば従来は、引き続き雇用された期間が1年以上であることが取得条件でした。しかし、法改正によって雇用期間による取得条件は撤廃されています。
5-5. 育児休業取得状況の公表が義務化される
法改正により、常時雇用する労働者が1,000人を超える事業所の場合、育児休業取得状況が公表されるようになっています。自社のホームページや厚生労働省が運営しているサイトなどで、育児休業取得の状況が公表されます。
6. 育児休業期間に関するよくある質問

また育児休業期間に関する質問でよくあるケースをまとめます。ケースごとにどのように対応すべきか説明しますので、参考にしましょう。
6-1. 育児休業期間の短縮は可能?
育児休業期間は、一般的に延長する人の方が多いかもしれませんが、中には短縮して早く復職したいと考えている方もいます。
そのような場合、予定よりも育児休業期間を短くすることは可能です。子どもが1歳になるより前に保育所が見つかった場合や、従業員が復職を希望している場合などは、育児休業期間の変更をおこなう必要があります。
ただし、終了予定日の変更を認めるかどうかは会社の判断に任されているため、トラブル防止のためにも、育児休業期間変更に関する内容は就業規則に規定しておいた方が良いでしょう。
休業期間を終了させるためには、従業員から「育児休業終了届」を提出してもらいます。また、休業期間中は社会保険料が免除されているため、「育児休業等取得者申出書・終了届」を日本年金機構に提出することも忘れずにおこないましょう。
6-2. 育児休業期間に退職することはできる?
育児休業期間中に退職することも可能です。ただし、退職の時期や条件により、育児休業給付金の支給に影響が出ることがあります。例えば、退職後すぐに別の仕事に就く場合や、自営業を始める場合などは、給付金の受給資格を失う可能性があります。退職を検討する際には、給付金の支給条件や手続きを確認することが重要です。また、本人の意思による退職は可能ですが、事業主が退職に追い込むような働きかけをすることは違法です。退職を考える際には、事前に十分な情報収集と準備を行い、自分自身の意向が尊重されるよう努めることが重要です。
6-3. 育児休業給付金は退職後に受け取れる?
育児休業給付金は、育児休業期間中の生活を支えるためのものであり、雇用保険の加入者であることが給付条件です。そのため、退職日を含む月以降は受け取ることができません。給付金の支給は雇用継続が前提となっているため、育児休業中に退職する場合、その時点で給付金の支給が終了します。ただし、育児休業中に退職したとしても、それまでに受け取った育児休業給付金の返還義務はありません。ただし、退職する予定を隠して受給していた場合や、育児休業終了時に退職した場合でも意図的に退職の予定を隠していた場合は返還義務が生じることがあります。退職のタイミングや給付金支給条件については、事前に詳細を確認しておくことが重要です。
7. 育児休業期間のルールや手当を理解して正しい労務管理を

育児休業期間は、産後休業終了の翌日から子どもが1歳になるまでを原則としています。しかし、預け先の保育園が見つからなかったなど、やむを得ない理由がある場合は、最長2歳まで延長可能です。
延長手続きをおこなうとき、企業担当者は育児休業に関する要件や内容を理解した上で、進めていく必要があるでしょう。
従業員が安心して子育てができるよう、夫婦ともに育児休業が取得できる職場環境を作っていくことが大切です。待機児童問題で保育所に入れないケースも多々あるので、延長依頼があった際は、適切に対処できるようにしておきましょう。
「育児・介護休業のルールブック」を無料配布中!
「育休や介護休業を従業員が取得する際、何をすればいよいかわからない」「対応しているが、抜け漏れがないか不安」というお悩みをおもちではありませんか?
当サイトでは、そのような方に向け、従業員が育児・介護休業を取得する際に人事がおこなうべき手続きや、そもそもの育児・介護休業法の内容をわかりやすくまとめた資料を無料で配布しております。
また、2022年4月より段階的におこなわれている法改正の内容と対応方法も解説しているため、法律に則って適切に従業員の育児・介護休業に対応したい方は、こちらから資料をダウンロードしてご活用ください。
人事・労務管理のピックアップ
-

【採用担当者必読】入社手続きのフロー完全マニュアルを公開
人事・労務管理公開日:2020.12.09更新日:2024.03.08
-

人事総務担当が行う退職手続きの流れや注意すべきトラブルとは
人事・労務管理公開日:2022.03.12更新日:2024.07.31
-

雇用契約を更新しない場合の正当な理由とは?通達方法も解説!
人事・労務管理公開日:2020.11.18更新日:2024.08.05
-

法改正による社会保険適用拡大とは?対象や対応方法をわかりやすく解説
人事・労務管理公開日:2022.04.14更新日:2024.08.22
-

健康保険厚生年金保険被保険者資格取得届とは?手続きの流れや注意点
人事・労務管理公開日:2022.01.17更新日:2024.07.02
-

同一労働同一賃金で中小企業が受ける影響や対応しない場合のリスクを解説
人事・労務管理公開日:2022.01.22更新日:2024.10.16
労務管理の関連記事
-

【2024年最新】労務管理システムとは?自社に最も適した選び方や導入するメリットを解説!
人事・労務管理公開日:2024.08.22更新日:2024.08.22
-

【2024年4月】労働条件明示のルール改正の内容は?企業の対応や注意点を解説
人事・労務管理公開日:2023.10.27更新日:2024.10.18
-

社員の離職防止の施策とは?原因や成功事例を詳しく解説
人事・労務管理公開日:2023.10.27更新日:2024.09.03