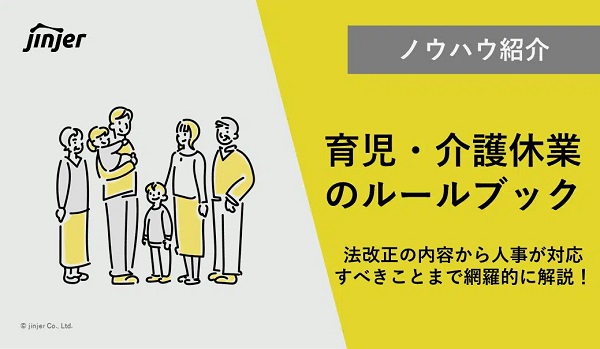出産手当金の申請方法とは?支給額やもらうための条件についても解説
更新日: 2024.7.5
公開日: 2022.3.29
OHSUGI

産前・産後休業中は会社から給料が支給されないため、生活費の保障として出産手当金を保険者に申請できます。
この記事では、出産手当金とは何か、支給条件や支給額の計算方法、会社が女性従業員に代わり申請する方法を解説します。
目次
「育児・介護休業のルールブック」を無料配布中!
会社として、育休や介護休業の制度導入には対応はしてはいるものの 「取得できる期間は?」「取得中の給与の正しい支給方法は?」このようなより具体的な内容を正しく理解できていますか?
働く環境に関する法律は改正も多く、最新情報をキャッチアップすることは人事労務担当者によって業務負担になりがちです。
そんな方に向けて、当サイトでは今更聞けない人事がおこなうべき手続きや、そもそもの育児・介護休業法の内容をわかりやすくまとめた資料を無料で配布しております。
また、2022年4月より段階的におこなわれている法改正の内容と対応方法も解説しているため、法律に則って適切に従業員の育児・介護休業に対応したい方は、こちらから資料をダウンロードしてご活用ください。
1. 産休中の生活費を一部保障する出産手当金とは?

出産手当金とは、健康保険の被保険者である女性従業員が、出産のため会社を休んでいた期間に支払われる給付金のことです。
産前・産後休業中は賃金が支払われないため、その分の生活費や出産・育児にかかる費用を補う目的で制度が導入されました。
1-1. 出産手当金の基本の計算式
1日に受け取れる出産手当金の額は下記により計算できます。
支給開始日以前の12カ月間の標準報酬月額の平均額÷30日×2/3
注意したいのは、支給額は額面や手取り金額ではなく、社会保険料の標準報酬月額がベースとなる点です。
なお、支給開始日以前に被保険者期間が12カ月未満である場合は、計算方法が上記とは異なります。この場合、次の2つを比較して低い額の方で計算しなくてはいけません。
- 支給開始月以前で直近かつ継続した月の標準報酬月額の平均額
- 加入する健康保険組合の前年9月30日時点での標準報酬月額の平均額
1-2. 申請者は従業員本人か会社のどちらでも可能
手続きは申請する従業員本人か、会社側のどちらがおこなっても問題ありません。
ただし、賃金の支払期間や計算方法などを記載する「事業主証明」という申請書があるため、従業員がおこなった場合も、会社側でも所定の手続きが必要となります。
1-3. 出産育児一時金との違い
出産時に申請できる給付金に「出産育児一時金」がありますが、これは出産にかかる費用の軽減を目的として導入された制度です。
そのため、会社の健康保険に加入している女性はもちろん、国民健康保険に加入する女性や、配偶者の扶養に入っている女性も申請できます。
令和5年より支給額が1児につき42万円から50万円に引き上げられました。多産出産であっても金額は変わりません。例えば、双子を出産すると100万円が支給されます。また、妊娠週数が22週に満たないなど産科医療補償制度の対象外の場合は、支給額が48.8万円に変わります。
なお、出産育児一時金を受けるには、妊娠4カ月以上の出産であることが条件です。
2. 出産手当金はいつもらえる?申請の必要条件
 女性従業員が出産手当金を受け取るためには、いくつかの条件があります。
女性従業員が出産手当金を受け取るためには、いくつかの条件があります。
条件を満たしていない場合は出産手当金を申請がすることができないため、会社側も事前に把握して申請漏れのないようにしましょう。
2-1. 会社の健康保険に加入している女性が対象
出産手当金の支給対象者は、会社の健康保険(協会けんぽ、健康保険組合を問わない)に加入している女性従業員です。なお、正社員ではなく、パートやアルバイトの女性も対象になっています。
ただし、会社の保険ではなく、国民健康保険や、配偶者の扶養などに入っている女性従業員は対象とならないため注意しましょう。
2022年10月に実施される法改正にて、健康保険の適用範囲が拡大されるため、出産手当金の対象者も増加することが考えられます。
当サイトでは、社会保険(健康保険・国民年金保険)の法改正についてまとめた資料を無料で配布しております。2022年10月以降の出産手当金の対象者に誰があたるのか不安なご担当者様は、こちらから資料をダウンロードしてご確認ください。
2-2. 妊娠4カ月以上経過した出産であること
対象の出産は、妊娠4カ月(85日)以上経過した後の出産に限ります。
出産とは、流産・死産・人工妊娠中絶を含みます。
なお、84日までの出産は支給対象とはなりません。
2-3. 産前産後休業を取得していること
産前・産後に取得できる休業期間は、出産する子の人数によっても異なるため、申請を受ける際は、予定日と合わせて確認しましょう。
産前休業:出産予定日前42日間。双子以上の出産の場合98日。従業員の希望により取得できる。
産後休業:出産予定日後56日間。産後6週間の取得は義務。それ以降は医師の許可があれば就労が可能。
ただし、産前産後休業を取得していても会社から給与の支払いを受けた場合は、支給の対象外とされます。給与の支払い日額が出産手当金の日額より下回る場合は、その差額分のみを受け取ることが可能です。
2-4. 退職した場合の出産手当金の扱い
次の条件を満たす女性従業員は、退職後も出産手当金の申請が可能です。
- 退職日までに1年以上継続して被保険者だった(任意継続の被保険者期間は除く)
- 退職日に出産手当金を受けている、または、受ける条件を満たしている
ただし、退職日に出勤してしまうと出産手当金の支給条件から外れてしまい、以降の支給が打ち切られてしまうため注意が必要です。
2-5. 出産手当金はいつから申請可能?
休業期間中の給与の支払い状況を確認する必要もあるため、申請期間を含む給料の締日を過ぎてから申請が可能となります。
ただし、実際に休業を取得していない分の申請はできません。取得予定日がすべて決まっていたとしても、申請できるのは休業を取得した分のみです。申請の際にその都度会社の証明が必要になることから、一般的には全休業日分をまとめて申請するパターンが多いようです。
この場合は、出産後56日経過後、給料の締日を過ぎてから一括して申請ができます。ほかにも、産前分・産後分など分割して申請することも可能です。
3. 出産手当金の対象期間と支給額の計算方法
 出産手当金の対象期間は、産前・産後休業期間のうち、従業員が申請している期間と、実際の出産日です。
出産手当金の対象期間は、産前・産後休業期間のうち、従業員が申請している期間と、実際の出産日です。
ただし、出産予定日と実際の出産日は変動するケースが多いため、その際は実際の期間に応じ、支給額が変動します。
ここでは、具体例をもとに支給額の計算方法を確認します。
3-1. 出産が予定日より10日早まったケース
【標準報酬月額の平均が280,000円の場合の計算例】
280,000÷30=9,330円(10円未満は四捨五入)
9330円×2/3=6,220円(1円未満は四捨五入)
(42日-10日)×6,220円(日額)=199,040円
上記が産前休業分の出産手当金となります。
3-2. 出産が予定日より5日遅かったケース
【標準報酬月額の平均が280,000円の場合の計算例】
280,000÷30=9,330円(10円未満は四捨五入)
9330円×2/3=6,220円(1円未満は四捨五入)
(42日+5日)×6,220円(日額)=323,440円
なお、出産日当日は産前休業に含み計算します。
3-3. 産前休業を取らなかった場合の出産手当金の扱い
妊娠中の従業員が産前休業を取得せず、仕事を続けたときは、出産手当金は支給されません。
そのため、給与も通常どおり計算し、支払います。
4. 出産手当金の申請方法

出産手当金の申請方法は、産前・産後休業分に分けて申請する方法と、産後に休業分を一括して申請する方法があります。ここでは、一括して申請する方法を解説します。
4-1. 従業員から産前・産後休業の申請を受ける
従業員から妊娠の報告を受けたら、産前・産後休暇を取得するか確認しましょう。
取得する場合、出産予定日に応じて所定の日数を付与します。
なお、日数に誤りがないように「産休申請書」などを準備しておくとよいでしょう。
4-2. 出産手当金の申請書類を準備する
協会けんぽや各健康保険組合のホームページから、出産手当金の申請書類をダウンロードし、添付が必要な書類を確認します。
なお、申請書には以下の記入が必要です。
- 被保険者情報
- 振込み口座
- 申請内容
- 医師・助産師記入欄
医師や助産師に記入してもらう箇所もあるため、産休に入る前に従業員に申請書を渡し、産休明けに医師・助産師の意見書と一緒に持参してもらうとよいでしょう。
▼申請書類は下記からダウンロードできます。
健康保険出産手当金支給申請書 | 全国健康保険協会
4-3. 事業主証明書類を作成する
申請書の「事業主証明」では、従業員の賃金や出勤状況を記載します。書き方については、後述で詳しくポイントをお伝えします。
なお、健康保険法施行規則の改正に伴い2020年12月25日より、出産手当金の証明に必要であった事業主の押印が不要となっています。
参照:各種申請書の記名・押印が必要なくなりました|全国健康保険協会
4-4. 従業員から申請書や添付書類を受け取る
従業員の産休が終わった後は、申請書や添付書類を受け取り、「事業主証明」書類と合わせて所定の窓口(協会けんぽまたは、各健康保険組合)に送付します。
なお、出産手当の申請は産休を開始した翌日から2年以内となります。
給付金は直接従業員の口座に支払われる他、支払いまで1~2カ月ほど時間がかかります。
5. 出産手当金申請書の書き方のポイント

出産手当金の申請用紙は全部で3枚あります。そのうち2枚を従業員側で記入し、残りの1枚を事業主側で記入しなくてはいけません。
ここでは、各用紙ごとに書き方のポイントをまとめてましたので、これから申請をおこなう方はぜひ参考にして下さい。
参照:健康保険出産手当金支給申請書(手書き用記入例)|全国健康保険協会
5-1. 被保険者記入用
被保険者記入用には、被保険者番号や氏名、住所、電話番号、生年月日といった被保険者情報を記入します。漏れの無いよう、全ての記載項目を埋めましょう。
また、出産手当金の振込先を記入する欄もあります。ここには、被保険者の口座を記入します。
万が一、書き間違ってしまった場合は、訂正箇所を二重線で消し正しい内容を記入しましょう。
5-2. 被保険者・医師・助産師記入用
申請期間(出産のために休んだ期間)、出産予定日、医師・助産師の証明などを記入するための用紙です。
書き方のポイントとしては、申請期間には公休日や土日も含めて記入します。また、申請期間を経過する前に用紙を提出することができない点にも注意しましょう。
医師・助産師の証明は、1回目の申請が出産後で出産の証明が確認できた場合に限り、2回目以降の証明を省略することが可能です。
5-3. 事業主記入用
被保険者の勤務状況や賃金の支払状況、事業主の証明を記入する用紙です。
勤務状況に関しては月別に記入欄があるので、申請期間中の出勤日を〇印で囲みます。この欄に有給休暇の取得日を記入する必要はありませんが、賃金の支払状況を記入する欄には取得した日の賃金額を記入しなくてはいけません。
賃金の支払状況を記入する欄には、出勤日以外で支払った報酬や手当等を記入します。有給休暇のほか、通勤手当や住宅手当など支給したものがあれば、ここに記入しましょう。
事業主の証明は申請の都度必要です。2回目以降の申請の際にも省略はできないので注意しましょう。
6. 出産手当金の申請方法を理解して従業員の働きやすい環境を整えよう

出産手当金は、産休中の女性の生活を支える保障制度です。
申請条件を満たせば、正社員だけでなくパートやアルバイト、契約社員であっても受給できます。
申請は本人だけでなく、会社からおこなこともできるため、女性従業員の労働環境を整えるためにも、条件や手順を把握しておきましょう。
「育児・介護休業のルールブック」を無料配布中!
「育休や介護休業を従業員が取得する際、何をすればいよいかわからない」「対応しているが、抜け漏れがないか不安」というお悩みをおもちではありませんか?
当サイトでは、そのような方に向け、従業員が育児・介護休業を取得する際に人事がおこなうべき手続きや、そもそもの育児・介護休業法の内容をわかりやすくまとめた資料を無料で配布しております。
また、2022年4月より段階的におこなわれている法改正の内容と対応方法も解説しているため、法律に則って適切に従業員の育児・介護休業に対応したい方は、こちらから資料をダウンロードしてご活用ください。
人事・労務管理のピックアップ
-

【採用担当者必読】入社手続きのフロー完全マニュアルを公開
人事・労務管理
公開日:2020.12.09更新日:2024.03.08
-

人事総務担当が行う退職手続きの流れや注意すべきトラブルとは
人事・労務管理
公開日:2022.03.12更新日:2024.06.11
-

雇用契約を更新しない場合の正当な理由とは?通達方法も解説!
人事・労務管理
公開日:2020.11.18更新日:2024.07.10
-

法改正による社会保険適用拡大とは?対象や対応方法をわかりやすく解説
人事・労務管理
公開日:2022.04.14更新日:2024.06.12
-

健康保険厚生年金保険被保険者資格取得届とは?手続きの流れや注意点
人事・労務管理
公開日:2022.01.17更新日:2024.07.02
-

同一労働同一賃金で中小企業が受ける影響や対応しない場合のリスクを解説
人事・労務管理
公開日:2022.01.22更新日:2024.05.08