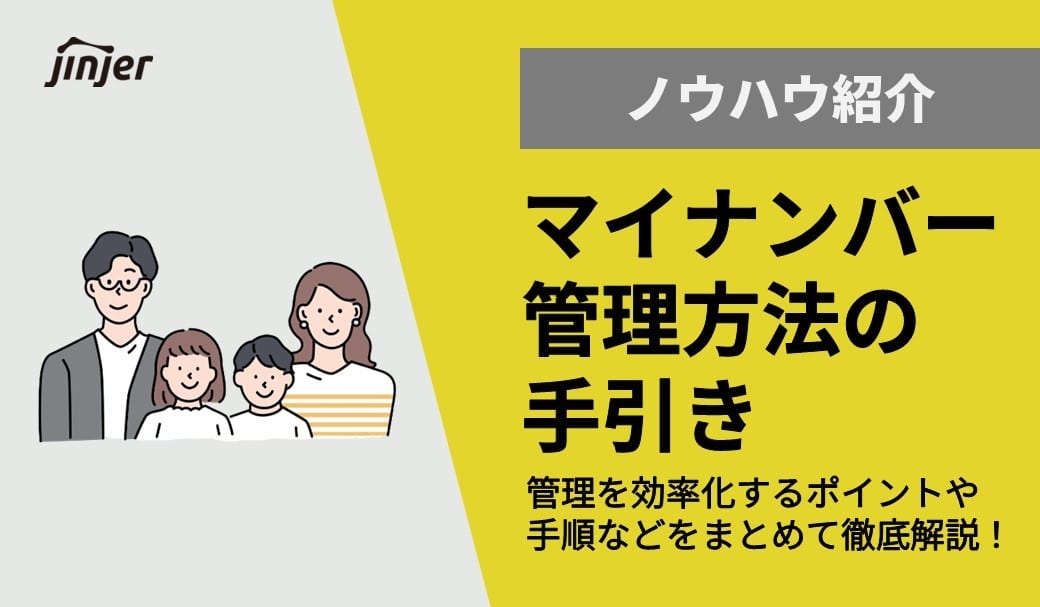マイナンバーの廃棄方法や注意すべき3つのポイント
 マイナンバーの利用が済んだら、できるだけ速やかに破棄または削除しなければいけません。
マイナンバーの利用が済んだら、できるだけ速やかに破棄または削除しなければいけません。
廃棄方法も紙書類ならシュレッダーにかける、データなら完全に削除するなど、復元できない方法が求められます。
この記事では、マイナンバーの廃棄方法や注意点、廃棄の効率を上げる方法について解説します。
1. マイナンバーの破棄方法について
 マイナンバーは、社会保障・税・災害対策にかかる事務作業のみに利用でき、利用後は速やかな廃棄または削除が求められます。
マイナンバーは、社会保障・税・災害対策にかかる事務作業のみに利用でき、利用後は速やかな廃棄または削除が求められます。
また、廃棄する際は、情報が復元できないようにすることが大切です。
1-1. マイナンバーは不要になったら速やかに廃棄する
マイナンバーには具体的な廃棄時期などは定められていないものの、従業員の退職などで関連手続きが終わり次第、必要な範囲を超えて保管してはならないことがマイナンバー法により定められています。[注1]
企業が取得したマイナンバーは、従業員の行政手続きをする際にのみ利用可能となるため、退職した後は事務処理保管が認められていません。
そのため、社会保障などの手続きが終わり次第、できるだけ速やかに廃棄しましょう。
[注1]行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律|e-Gov 法令検索
1-2. 退職者のマイナンバー書類の保管期間は7年
マイナンバーは速やかに廃棄することが定められていますが、マイナンバーが記載されている書類は、すぐに廃棄する必要はありません。その理由は、人事関連書類にはそれぞれ保管期間が決められているからです。
保管期間は書類ごとに異なりますが、扶養控除等申告書などの保管期間が7年となっているため、マイナンバーが記載されている書類の保管期間は7年となります。
保管期間が経過した後は、マイナンバー記載の書類だけでなく保存しているデータも削除することを忘れないようにしましょう。
1-3. 保管期限が過ぎた書類・データの廃棄方法
会社で扱う書類は、それぞれに保管期限が法律で定められています。
それらの書類にマイナンバーが記載されている場合は、7年の保管期限が過ぎ次第、速やかに廃棄しなければなりません。
ここでは、書類とデータの具体的な廃棄方法を解説していきます。
書類(紙)は焼却処分またはシュレッダーにかける
紙ベースでマイナンバーを取り扱っていた場合は、それらの書類が復元不可能な方法で廃棄する必要があります。
具体的には以下の方法で処分しましょう。
- シュレッダーにかけて粉砕する
- 焼却処分する
- 溶解処理する
データ情報は復元できないようにする
パソコンのデータ内にある退職者のマイナンバー情報などは、保存期間が過ぎ次第、該当のデータを削除しましょう。その際は、データが復元できないようにする必要があります。
マイナンバーを取り扱っていたパソコン自体を破棄する際は下記の方法データを完全に削除しましょう。
- データ削除専用ソフトを使う
- パソコン自体を物理的に破壊する
ただし、これらの方法は専門的知識がないとデータの復元ができてしまう可能性もあります。そのため、専門の処理業者に依頼する方が安全です。
保存が必要な書類はマスキングし判別できるようにする
マイナンバーが書かれた書類は破棄が基本です。
しかし、実務的に保存が必要な書類は、マイナンバーが書かれた箇所にマスキングをしたり、切り抜いたりすることで、継続して保管ができます。
2. マイナンバーを廃棄する際の3つの注意点
 マイナンバーは、取得や利用する際にも細かい決まりがありますが、廃棄にも細かい決まり事が定められています。単に「不要になったらすぐに廃棄する」というだけでは、規程に違反してしまう可能性もあるので注意してください。
マイナンバーは、取得や利用する際にも細かい決まりがありますが、廃棄にも細かい決まり事が定められています。単に「不要になったらすぐに廃棄する」というだけでは、規程に違反してしまう可能性もあるので注意してください。
ここでは、マイナンバーを廃棄する際の注意点を解説していきます。
2-1. 自社廃棄は廃棄年月日・担当者・方法を記録に残す
書類で管理しているマイナンバーなどを自社で廃棄した場合は、廃棄した書類の名称・年月日・担当者・廃棄方法などを記録として残す必要があります。
なお、書式などに決まりはないため、紙やエクセルなどで記録して問題ありません。
書式の名称としては、「マイナンバー取扱記録簿」「マイナンバー管理台帳」などが一般的です。
また、デジタルデータの場合は削除した操作のログが残るようにしましょう。
2-2. 外部委託する際は業務委託契約を締結する
マイナンバーの廃棄を外部に委託する際は、安全管理措置を講じているか、どのような方法で廃棄しているかなどを確認し、適切な業者を選ぶ必要があります。
その理由は、企業はマイナンバーの破棄などを外部に委託した場合、監督責任が生じるからです。
監督を十分におこなわずにマイナンバーが漏洩した場合、委託業者だけでなく委託した企業も責任を問われます。
そのため、業者に委託する際は、秘密保持義務やマイナンバーの取り扱いについて定めた業務委託契約書を締結する必要があります。
2-3. 外部委託により廃棄した場合は証明書をもらう
外部委託先でマイナンバー書類やデータを廃棄したときは、機密文書廃棄業者の発行する「廃棄証明書」(溶解証明書)が必要です。
発行方法は業者により異なり、紙または電子発行のどちらかです。発行にかかる時間は処理方法によっても違いがあるため、どのような方法で発行するか、いつ頃届くか確認しましょう。
また、廃棄証明書自体も5年または7年の保管が必要なため、無くさないように注意しましょう。
3. マイナンバーの廃棄を効率化する方法
 マイナンバーは管理だけでなく、破棄する際も多くの手間とコストがかかります。
マイナンバーは管理だけでなく、破棄する際も多くの手間とコストがかかります。
そのため、破棄を前提とした仕組みをあらかじめ構築し、業務が効率化できるように整えましょう。
3-1. マイナンバー管理システムを導入する
マイナンバー管理システムとは、マイナンバーの収集から破棄まで、データ上で一元管理できるシステムです。
システムを導入することで、マイナンバーをデータベースで管理できるため、書類のように場所を取らないほか、情報漏洩や廃棄漏れのリスクを軽減できます。
また、操作の度にログが残るため、いつ誰がどのような操作をしたか、逐次記録する必要もなく、「安全管理措置」に準拠した運用がしやすくなります。
収集や管理が容易になるだけでなく、廃棄が必要なマイナンバーをリマインドする機能もあるため、人為的ミスによる廃棄漏れ防止にも役立ちます。
外部機能と連携できるサービスもあるため、マイナンバー管理の手間を削減し、効率的な事務運用をしたい場合は検討してもよいでしょう。
3-2. 書類別・年度別に保管する
マイナンバーを紙ベースで管理しているなら、書類別・年度別・保管期限別に分けて管理するとよいでしょう。
特に、保管期限は以下の期間に分かれています。
7年:源泉徴収票、扶養控除等(異動)申告書など
4年:雇用保険関係書類
3年:労災保険関係書類
2年:健康保険、社会保険(厚生年金)関係書類
これらの書類は混ざらないように別々に保管しておきましょう。
また、マイナンバーの保管の際は鍵付きの金庫などに入れ、外部に流出することの無いように厳重に保管する必要がある点も忘れてはいけません。年度別にまとめ、年度の終わりには適切な方法で廃棄できるように整えましょう。
3-3. 必要のない書類にマイナンバーを記載しない
最後に、マイナンバーは必要のない書類やデータベースに書き込まないように注意しましょう。
例えばメモのつもりで「マイナンバー取扱記録簿」などに廃棄したマイナンバーを記録してしまうと、それ自体も適切な方法で廃棄しなくてはいけなくなります。
そのため、閲覧は原本やデータベースを基本とし、コピーやデータの出力は最低限度に留めることも、破棄を効率化するためには大切です。
4. マイナンバー管理システムを導入して廃棄を効率化しよう

マイナンバーは取得や利用だけでなく、廃棄方法も厳格に定められています。そのため、管理実務では廃棄まで見越して、効率よく処理できるシステムの構築が求められます。
マイナンバー管理システムを活用すれば、紙ベースのように場所を取ることなく、マイナンバーをデータ上で一元管理できるので、効率よく廃棄できるのはもちろん安全管理措置対策にも有効です。
また、必要に応じて廃棄時期をリマインドしてくれるため、人為的な処理漏れを防止することも可能なので、導入を検討してみることをおすすめします。
人事・労務管理のピックアップ
-

【採用担当者必読】入社手続きのフロー完全マニュアルを公開
人事・労務管理
公開日:2020.12.09更新日:2024.03.08
-

人事総務担当が行う退職手続きの流れや注意すべきトラブルとは
人事・労務管理
公開日:2022.03.12更新日:2024.06.11
-

雇用契約を更新しない場合の正当な理由とは?通達方法も解説!
人事・労務管理
公開日:2020.11.18更新日:2024.07.10
-

法改正による社会保険適用拡大とは?対象や対応方法をわかりやすく解説
人事・労務管理
公開日:2022.04.14更新日:2024.06.12
-

健康保険厚生年金保険被保険者資格取得届とは?手続きの流れや注意点
人事・労務管理
公開日:2022.01.17更新日:2024.07.02
-

同一労働同一賃金で中小企業が受ける影響や対応しない場合のリスクを解説
人事・労務管理
公開日:2022.01.22更新日:2024.05.08