心理的安全性とは?ぬるま湯組織との違いや高めるメリットを解説
更新日: 2025.7.11 公開日: 2025.4.1 jinjer Blog 編集部
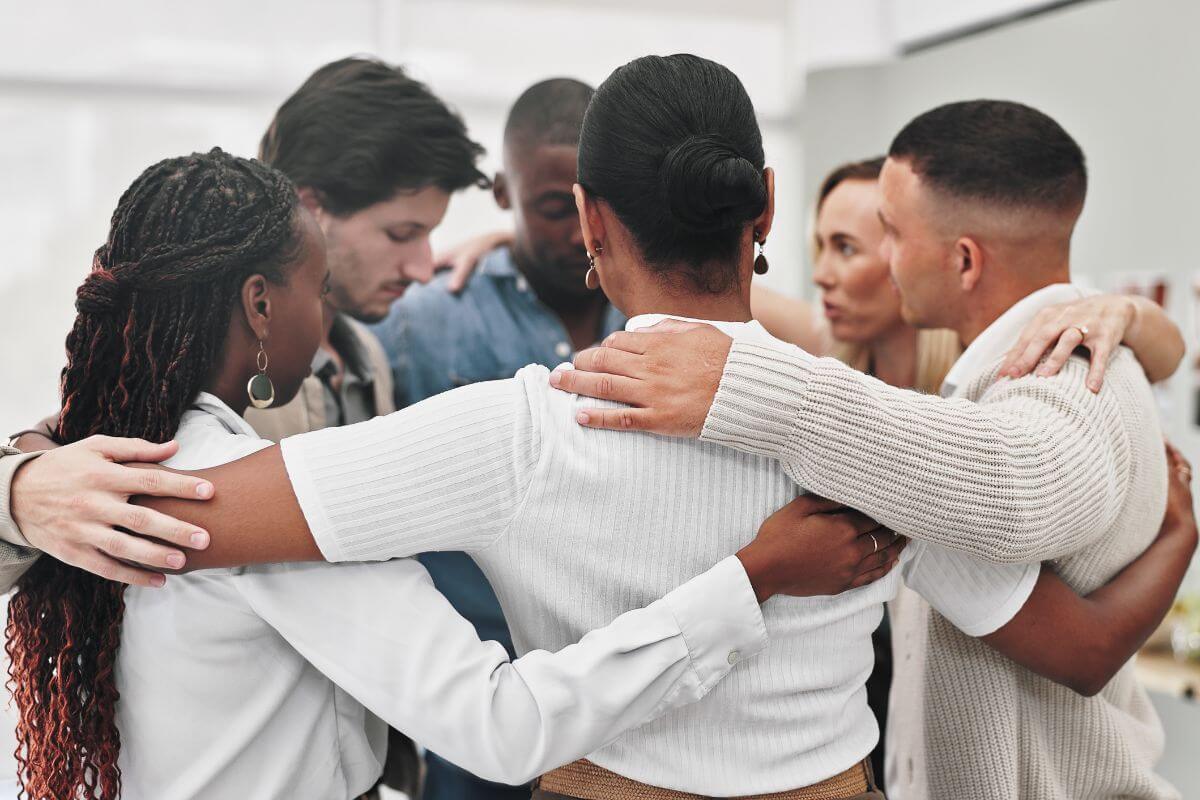
心理的安全性(psychological safety)とは、組職や職場で自分の意見や気持ちを、誰に対しても臆することなく安心して発言できる状態を指します。
心理的安全性というのは心理学用語で、組織行動学の専門家の定義では、「チームの他のメンバーが自分の発言を拒絶したり、罰したりしないと確信できる状態」とされていて、近年日本でも注目が集まっている概念です。
心理的安全性が確保されている職場は、従業員からさまざまなな意見を引き出すことができるので、イノベーションや新しいアイデアの創出が可能になります。
本記事では、企業の成長・発展につながる心理的安全性の概要や構成要素、ぬるま湯組織との違いについて解説します。

従業員の定着率の低さが課題の企業の場合、考えられる要因のひとつに従業員満足度の低さがあげられます。
従業員満足度を向上させることで、従業員の定着率向上や働くモチベーションを上げることにもつながります。
しかし、従業員満足度をどのように測定すれば良いのか、従業員満足度を知った後どのような活用をすべきなのかわからないという人事担当者様もいらっしゃるのではないでしょうか。
そのような方に向けて当サイトでは、「従業員満足度のハンドブック」を無料でお配りしています。
従業員満足度調査の方法や調査ツール、調査結果の活用方法まで解説しているので、従業員のモチベーション向上や社内制度の改善を図りたい方は、ぜひこちらから資料をダウンロードしてご活用ください。
1. 心理的安全性とは
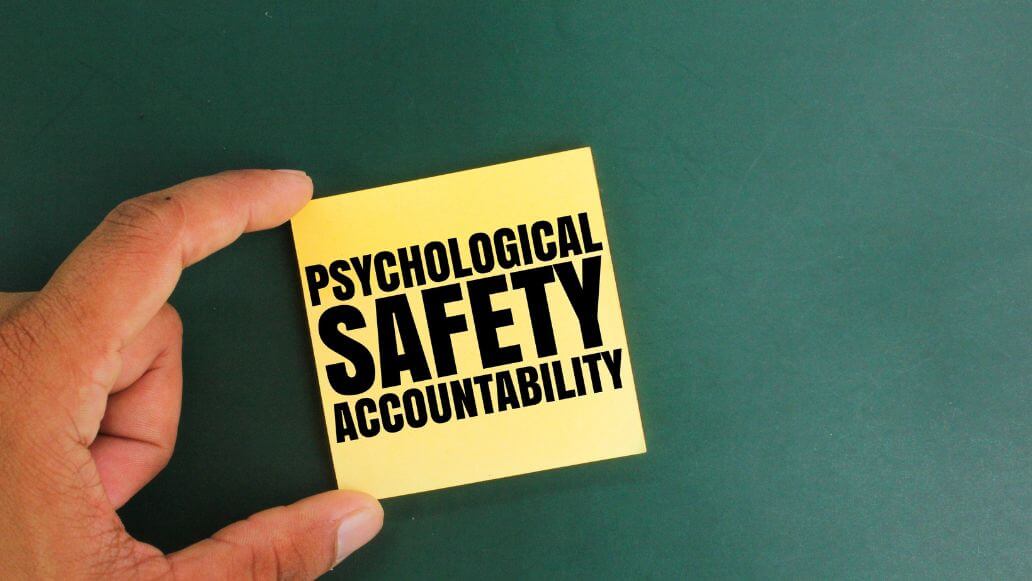
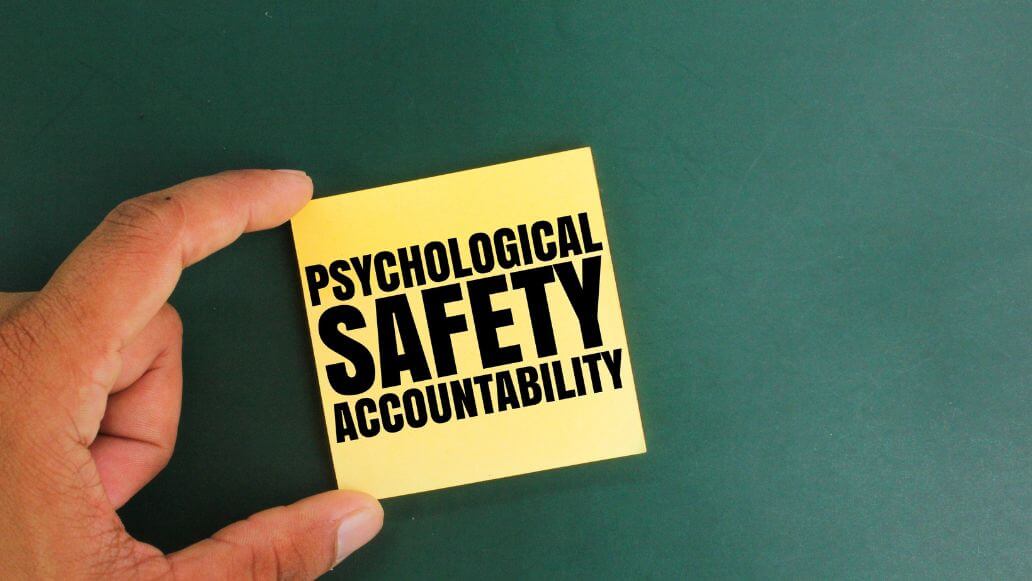
心理的安全性とは、自分の意見やアイデアを組織・チームのだれもが率直に意見を言える状態を指します。
ハーバード大学のエイミー・エドモンドソン教授が1999年に提唱しましたが、近年注目されるようになったのはGoogleの研究がきっかけです。
Googleの分析では、成功するチームの共通点として、心理的安全性の高い職場では意見が交わしやすいことがわかりました。
発言のしやすさがチームのパフォーマンス向上につながることも明らかになり、多くの企業がこの考えを取り入れています。
1-1. 心理的安全性の高さとぬるま湯組織は違う
心理的安全性の高い組織とぬるま湯組織の違いは、改善や成長につながる議論が交わされているかどうかです。
心理的安全性が高いこととぬるま湯組織は、どちらも話しやすく助け合う環境があるというのは共通していますが、このような環境を作る目的はチームの成長です。
単に仲が良いだけで、現状維持を続ける組織はぬるま湯組織にあたります。心理的安全性の高いチームとはむしろ、意見を積極的に交わし議論を深める組織です。
健全な議論を通じてチームや会社を成長させ、充実感を得られる環境こそが、本来の意味での心理的安全性の高い組織と言えます。
1-2. 心理的安全性を高める重要性
心理的安全性を高める重要性は、企業の利益や成長に大きく関係するからです。
心理的安全性がここまで注目されたのは、最大手のグローバル企業であるGoogleが「生産性が高いチームは心理的安全性が高い」という社内調査結果を出したことが始まりです。
Googleは、成功を収めるチームに必要な条件を探るため「プロジェクト・アリストテレス」という調査をおこないました。対象となるチームは数百という規模で、この中から生産性の高いチームの特徴を徹底的に分析したところ、心理的安全性が高いという答えにたどり着きました。
常に業績を上げ続けているチームは、心理的安全性が高く活発な議論がおこなわれるだけでなく、アイデアを活用して結果を出し、人事評価も高いという結果が出ています。
つまり、心理的安全性を高めることは企業の利益や成長に大きく寄与するので、業種に関係なく重要だということなのです。
2. 心理的安全性が低い職場の従業員の特徴


心理的安全性を提唱したエイミー・エドモンドソン氏は、心理的安全性が低い職場の従業員の特徴として、下記の「4つの不安」を抱えていると説いています。
- 無能だと思われることに対する不安
- 無知だと思われることに対する不安
- ネガティブだと思われることに対する不安
- 邪魔だと思われることに対する不安
ここでは、これらの不安について解説します。
2-1. 無能だと思われることに対する不安
「無能だと思われる」というのは、単純に「仕事ができない人」と思われることに対する不安です。
この不安は自分で勝手に思い込んでしまうこともありますが、心理的安全性が低い職場の場合、上司が頻繁に「使えないやつだ」などの暴言を使ったりすることも原因となります。
無能だと思われることに不安があると、ミスを隠したり、指導を受けても素直に聞き入れなかったりという態度になります。
ミスを隠蔽してしまうと、後に発覚したときにトラブルに発展する可能性もあり、会社が信用を損ねることになるかもしれません。また、指導やアドバイスを素直に聞き入れないとチーム内に軋轢が生まれるため、プロジェクトの進行が妨げられることもあります。
2-2. 無知だと思われることに対する不安
無知だと思われることに対する不安というのは、同僚や上司に質問をしたいときに感じやすい不安です。
無知と思われることへの不安があると、例えば仕事でわからない単語あった場合、質問をしたくても「こんなこともわからないの?」と思われるのではないかと不安になり、結局わからないままにしてしまいます。
わからないことはネットで調べればいい、と思うのが一般的ですが、業種によってはネット情報と意味が異なるケースはゼロではありません。わからないままにしてしまうと、ミスが起こりやすくなりますし、業務への反応が遅くなることから業務が停滞するリスクが高まります。
2-3. ネガティブだと思われることに対する不安
ネガティブだと思われる不安というのは、否定的なことを言うと嫌われるのではないか、非協力的と思われるのではないかという心理があります。例え正しい意見でも、「そのやり方は間違っている」「その方法は効率的ではない」ということが言えず、対立を避けるようになります。
そのため、本当なら違うやり方が良くても、効率的な方法があるとしても、指摘をすることができません。
この不安は、本人にとって大きなデメリットはないとしても、プロジェクトの改善や業務の進行を妨げることになり、結果的に企業にとって損失を与える可能性があります。
2-4. 邪魔だと思われることに対する不安
邪魔だと思われることに対する不安というのは、自分のアイデアや意見が業務の妨げになってしまうかもしれない、という不安です。この不安は、自分に自信がない人に多く見られます。
邪魔だと思われる不安を持っている人は、仕事に対して消極的になったり、ミーティングでも発言をしなかったりするのが特徴です。アイデアを思い付いたとしても、それをチーム内で発信することがないので、逆に業務を妨げる可能性があるということに気が付いていない状態といえるでしょう。
受動的な状態ではチームは活性化せず、従業員自身も成長できない環境になってしまいます。
3. 心理的安全性は4つの因子で構成される
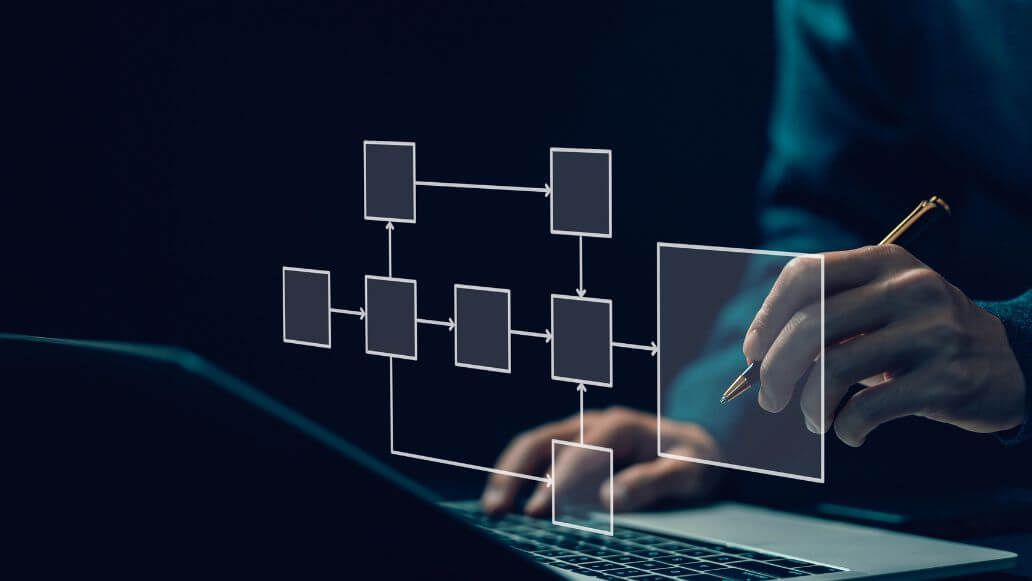
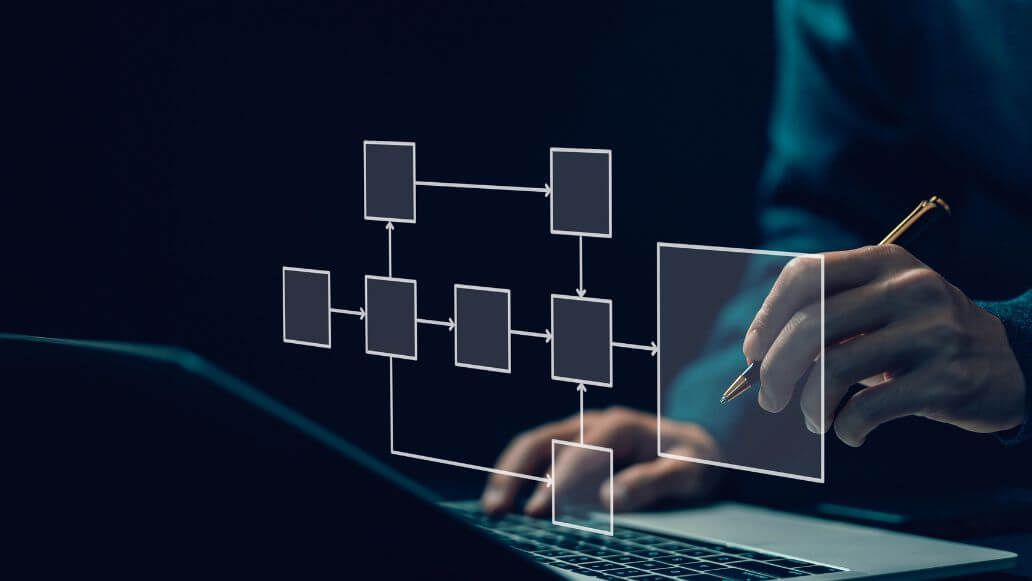
心理的安全性を構成する因子は以下の通りです。
- 話しやすさ
- 助け合い
- 挑戦
- 新奇歓迎
ここでは、各因子について詳しくみていきます。
3-1. 話しやすさ
話しやすさ因子とは、意見や考えを気兼ねなく発言できる環境があるかどうかをいいます。話しやすさ因子があるチームは、「こんなことを言ったら怒られるかも」「仕事ができないと思われるかも」など否定的な感情を持つことなく、自分が思ったことをどんどん発言できます。
話しやすさ因子を作るには、発言のハードルを下げることが重要です。
例えば、初歩的な質問でも「恥ずかしい」と思わず質問できる環境や指摘や異なる意見を述べても「場を乱すかもしれない」と萎縮せずに発言できる雰囲気を作ることが求められます。
どんな意見でも耳を傾けてもらえる、という安心感は、心理的安全性に必要不可欠です。
3-2. 助け合い
助け合い因子とは、困ったときに遠慮せず助けを求められる、互いに支え合える状態です。
心理的安全性の高いチームは、従業員同士がお互いに協力しあうことを当たり前と思っています。できないことがあるとしても、それを他の誰かが補えば良いという考え方が共通認識なので、助けられた方はさらなるスキルアップを目指すという環境が生まれます。
「助けを求めるのが恥ずかしい」「自分で考えろと突き放される」という職場環境は、お互いを助け合うこともしません。また、助けを求めることが評価の低下につながる職場も、助け合い因子が満たされているとは言えません。
助け合い因子がある職場は、個々の業務を持っていても、同じチームという考えなので「自分ごと」として協力しあいます。
3-3. 挑戦
挑戦因子とは、新しいことに挑戦したい意見を気兼ねなく発言できる状態があるかどうかをいいます。
「挑戦」というと攻撃的に感じるかもしれませんが、常に成長を求めて挑戦する人の意見も受け入れるというのも、心理的安全性が高い職場の特徴です。「前例がないから無理だ」と切り捨てるのではなく、「やる価値があるか考えよう」「まずはチャレンジしてみよう」とチームが柔軟に受け止められれば、そこから成長が生まれます。
加えて、失敗を責めず次に活かす視点があれば、挑戦的な意見は生まれやすいです。失敗をしても、お互いにダメだった点や改善点を意見交換することで、より良いチームに成長していきます。
3-4. 新奇歓迎
新奇歓迎因子とは、奇抜なアイデアや斬新な発想が自由に発言できる状態があるかを指します。
例えば「その意見は現実的ではない」と否定するのではなく、「何か活かせる部分はないか」と受け止める姿勢がチームにあるかどうかです。個性的な人や斬新なアイデアを受け止められない環境では、従業員は意見を言えなくなってしまいます。
心理的安全性がある会社というのは、「ありのままの自分でいられる場所」であり、個性を尊重しあいます。
本人が奇抜だと思っていた発想が、大きな価値を持つことも少なくありません。既存の枠にとらわれず多様な価値観を受け入れることで、チームに新たな可能性をもたらします。
4. 心理的安全性を高めるメリット


続いて心理的安全性を高めるメリットは、以下の3つが挙げられます。
- 組織の成長を促すアイデアが生まれやすくなる
- 情報共有が円滑になり生産性が上がる
- 離職率の低下につながる
ここでは、それぞれのメリットを解説していきます。
4-1. 組織の成長を促すアイデアが生まれやすくなる
心理的安全性を高めると、新たな発想や工夫が生まれやすくなるというメリットがあります。
プロジェクトや業務に関して、アイデアや意見を自由に出しやすくなることで、新商品の開発やサービスの改善が進みやすくなります。商品だけでなく、社内でも業務の進め方や制度のあり方を見直す発想が生まれやすくなります。
従業員の意見が受け入れられたり認められたりすると、それに触発されて他の従業員も仕事に対して積極的になっていく効果も期待できるでしょう。
その結果として競争力が向上し、市場での優位性や売上の拡大につながるというメリットも得られます。
4-2. 情報共有が円滑になり生産性が上がる
心理的安全性が高まると、情報共有が円滑になり、業務効率が上がることで生産性が向上するというメリットがあります。
心理的安全性が確保された職場では、意見や質問がしやすくなるので、必要な情報を迅速に共有することが可能です。また、ミスや課題をお互いに指摘しやすくなったり、ミスしたことを隠したりする必要もないので、トラブルが発生しても迅速に対応できます。
意見を出しやすい環境が整うということは、業務改善提案もしやすくなります。業務のムダが減ることで効率が上がり、結果として企業の生産性向上につながるメリットも得られるでしょう。
4-3. 離職率の低下につながる
心理的安全性が高い職場にすると、人材の定着につながるメリットもあります。
人材が定着しない職場というのは、従業員の意見を聞き入れない、否定する、圧力をかけるなどの風土があります。そのため、従業員はやる気をなくしたり不満を持ったりするため、エンゲージメントが低下し離職率が高くなるのです。
しかし、心理的安全性が高い職場は、意見や悩みを話しやすい、受け入れてもらえる環境が整っているので、職場への不満が溜まりにくく、安心して働き続けらることができます。
また、意見やアイデアを言いやすい環境が、やりたいことに挑戦できる機会を増やす効果も期待できます。このような環境が働きがいを高め、離職率の低下につながるのです。
5. 心理的安全性の作り方


心理的安全性が欠けている職場では、4つの不安が生まれます。
- 無知だと思われる不安
- 無能だと思われる不安
- 邪魔な存在だと思われる不安
- 否定的な人だと思われる不安
これらの不安が生じることで発言や行動が制限され、組織に多くの悪影響をもたらします。意思決定の質や業務の効率も悪くなるため、心理的安全性をしっかり構築していきましょう。
5-1. 心理的安全性が体感できる仕組みを構築する
心理的安全性が確保されている環境というのは、「誰でも自由に発言できる」というのが特徴です。しかし、性格にもよりますが、日本人は自ら発言するのが苦手な人が多く、発言すること自体に慣れていない人も少なくありません。
そのため、「発言することに慣れる」ことが重要になります。そこで活用できるのが、「1on1」というツールです。
1on1というのは、同僚や先輩、上司と2人だけで話す時間やディスカッションの場を設定し、リラックスして雑談できる機会をつくるという手法です。業務とは離れた場所で心理的安全性を体感できれば、「自分の意見を言う」ことへの不安を取り除くことができます。
5-2. チームの明確な目的・目標を持つ
心理的安全性を作るには、チームの明確な目的や目標を持つことが重要です。
目的が共有されていれば、意見はチームの成果を高めるためのものだと認識しやすくなりますし、意見の衝突があっても感情的になりにくくなります。また、意見を言うことで嫌われるかもしれないと感じている人も、目的が明確なら発言しやすいでしょう。
チーム内での目標が明確で共通認識になっていれば一体感があり、発言のぶれや認識の違いを心配する必要もありません。そのため、上下関係という壁がなくなり、全員がチームの一員という立場で意見を交わすことができるようになります。
5-3. 発言の失敗が許される文化をつくる
どんな人でも、間違った発言をしてしまうことはあります。それを受け入れるのが、心理的安全性の高い職場です。
発言の失敗は、周りの対応が判断材料となります。失敗に対して、責めたり蔑んだりすれば、その人は発言を控えるようになってしまいます。しかし、「失敗は誰にでもあること」「発言をしたこと自体が大事」という対応をすれば、「次は失敗しないようにしよう」「もっと知識をつけよう」と前向きに捉えることができるでしょう。
ネガティブな状況をさらにネガティブにするのは、心理的安全性の妨げになります。会社の損失や大きなトラブルにならない発言であれば、寛容に受け止めて従業員の成長にフォーカスするのが正解です。
5-4. コミュニケーションが取りやすい環境を整える
心理的安全性を作るには、従業員のコミュニケーションを活発にすることが重要です。しかし、近年は飲み会やレクリエーションをおこなう会社は減少しているのが現状かもしれません。
仮に飲み会を実施しても、昨今の風潮では従業員を無理に参加させるのは難しいでしょう。こういった状況の場合、コミュニケーションが取りやすい環境を整えて、従業員が利用しやすいツールでコミュニケーションが取れるように促すのがベストです。
コミュニケーションが取りやすい環境はいろいろありますが、下記のようなものが挙げられます。
- フリーアドレスの導入
- 従業員の休憩時間を統一する
- サークル活動の支援
- 従業員が利用できる休憩スペースの確保
- メンター制度の導入
従業員同士のコミュニケーションが少ないと感じる場合は、状況に合わせて自然に会話ができる環境を作っていきましょう。
6. 従業員の心理的安全性を高める方法


従業員の心理的安全性を高めるには、上司の接し方も重要になってきます。上司の接し方次第で心理的安全性は確保されることもあるので、以下の3つの方法を試してみましょう。
- 頭ごなしに否定せず受け入れる
- 指示を出すときには具体的にする
- 親しみやすい雰囲気を作る
ここでは、これらの方法を詳しく解説していきます。
6-1. 頭ごなしに否定せず受け入れる
従業員の心理的安全性を高めるために重要なのが、頭ごなしに否定をせず受け入れるということです。
忙しいときや急ぎの業務があるときに、部下がミスをしたり認識違いの対応をしたりすると、頭ごなしに否定したくなるかもしれません。しかし、部下の事情や意見を考慮せずに否定してしまうと、そこから信頼を取り戻すのはかなり難しくなります。
部下を甘やかす必要はありませんが、まずは事情や意見を聞いて受け入れましょう。その上で、必要であれば注意や反対意見を言うというスタンスを取れば、部下も納得してくれます。
頭ごなしの否定というのは単なる圧力と捉えられてしまうので、心理的安全性を確保するには、相手を受け入れてからアドバイスをするのがベストです。
6-2. 指示を出すときには具体的にする
心理的安全性を高めるために上司が意識したいのは、指示を出すときには具体的にするということです。
上司が一方的に、「この言い方でわかるだろう」「この程度のことなら理解できるだろう」と決めつけてしまうと、従業員に正確に伝わらないことがあります。自分の認識で理解度を判断するというのは、上司に多い間違った指示の1つです。
人間はそれぞれ認識が違うことがある、というのを前提としておかないと、逆に業務効率を下げてしまう可能性があります。さらに、「なんで理解できないんだ」と怒ったり、「何年働いているんだ」などと無能を指摘したりすると、心理的安全性を低下させてしまうことになります。
まずは、具体的に指示を出し、従業員が的確に指示を把握できるようになったら、細かい説明を省いていきましょう。
6-3. 親しみやすい雰囲気を作る
多くの場合、従業員というのは上司に対して壁を作ってしまいます。また、潜在的に「上司は怖い」「関わらない方がいい」という意識を持っている人もいるので、親しみやすい雰囲気を作りましょう。
従業員に気さくに話しかけたり、失敗したメンバーをフォローしたりすると、「この上司は怖くない」「普通に接することができる」という印象を持ってもらえるようになります。
上司に限ったことではありませんが、「いつも機嫌が悪そう」「偉そうにしている」というような人は、近寄りがたく到底心理的安全性を感じられません。
しかし、上司がオープンな印象を与えたり、偉ぶらず溶け込んだりする様子を見せれば、心理的安全性は格段に高まるでしょう。
7. 心理的安全性を高めて職場の生産性を高めよう


心理的安全性が高い職場というのは、従業員同士が意見を交わしやすくなったり、自分のアイデアを積極的に出しあったりできるのでチーム全体の成長につながります。また、自分の意見が採用されたり議論されたりするというのは、従業員のモチベーションを高め、エンゲージメントの向上効果も期待できます。
ただし、本当に大切なのは単に発言しやすいことではなく、意見が活かされ仕事の前進につながることです。
安心して意見を出せる環境が整えば、課題の解決や新たな挑戦も生まれやすくなりますし、従業員も積極的に仕事に取り組むようになるかもしれません。旧態依然としたままでは心理的安全性を高めるのは難しいかもしれませんが、組織をより良くするためにできることから取り組みを進めていきましょう。



従業員の定着率の低さが課題の企業の場合、考えられる要因のひとつに従業員満足度の低さがあげられます。
従業員満足度を向上させることで、従業員の定着率向上や働くモチベーションを上げることにもつながります。
しかし、従業員満足度をどのように測定すれば良いのか、従業員満足度を知った後どのような活用をすべきなのかわからないという人事担当者様もいらっしゃるのではないでしょうか。
そのような方に向けて当サイトでは、「従業員満足度のハンドブック」を無料でお配りしています。
従業員満足度調査の方法や調査ツール、調査結果の活用方法まで解説しているので、従業員のモチベーション向上や社内制度の改善を図りたい方は、ぜひこちらから資料をダウンロードしてご活用ください。
人事・労務管理のピックアップ
-


【採用担当者必読】入社手続きのフロー完全マニュアルを公開
人事・労務管理公開日:2020.12.09更新日:2026.01.30
-


人事総務担当がおこなう退職手続きの流れや注意すべきトラブルとは
人事・労務管理公開日:2022.03.12更新日:2025.09.25
-


雇用契約を更新しない場合の正当な理由とは?伝え方・通知方法も紹介!
人事・労務管理公開日:2020.11.18更新日:2025.10.09
-


社会保険適用拡大とは?2024年10月の法改正や今後の動向、50人以下の企業の対応を解説
人事・労務管理公開日:2022.04.14更新日:2025.10.09
-


健康保険厚生年金保険被保険者資格取得届とは?手続きの流れや注意点
人事・労務管理公開日:2022.01.17更新日:2025.11.21
-


同一労働同一賃金で中小企業が受ける影響や対応しない場合のリスクを解説
人事・労務管理公開日:2022.01.22更新日:2025.08.26
タレントマネジメントの関連記事
-



プレゼンティーイズムとは?原因と企業に与える損失額・対策をわかりやすく解説
人事・労務管理公開日:2026.01.19更新日:2026.01.19
-



メンタルヘルスサーベイとは?ほかのサーベイとの違い、実施の目的や流れを解説!
人事・労務管理公開日:2026.01.16更新日:2026.01.14
-


企業におけるメンタルヘルスケアとは?4つのケアや事例を紹介
人事・労務管理公開日:2025.11.18更新日:2025.12.19




















