役割等級制度のメリット・デメリットや導入方法を詳しく解説
更新日: 2025.4.17 公開日: 2023.5.17 jinjer Blog 編集部

人事評価制度の公平性を高めるには、従来の年功序列や成果主義ではなく、社員の役割(ミッション)に着目した役割等級制度を取り入れることが大切です。本記事では、役割等級制度のメリットやデメリット、制度設計の流れをわかりやすく解説します。
目次

人事評価制度は、健全な組織体制を作り上げるうえで必要不可欠なものです。
制度を適切に運用することで、従業員のモチベーションや生産性が向上するため、最終的には企業全体の成長にもつながります。
しかし、「しっかりとした人事評価制度を作りたいが、やり方が分からない…」という方もいらっしゃるでしょう。そのような企業のご担当者にご覧いただきたいのが、「人事評価の手引き」です。
本資料では、制度の種類や導入手順、注意点まで詳しくご紹介しています。
組織マネジメントに課題感をお持ちの方は、ぜひこちらから資料をダウンロードの上、お役立てください。
1. 役割等級制度とは?組織における「役割」ごとに等級を分ける制度

役割等級制度はミッショングレード制度とも呼ばれ、社員が組織内で果たす役割(ミッション)に着目した評価制度です。社員の役割のレベルに応じて等級(グレード)を分け、賃金などの待遇を決める点に特徴があります。
役割等級制度における役割は、単に職務を遂行することを意味するわけではありません。ここでいう役割とは、役職×職責を組み合わせたもので、企業が社員に期待する行動全般のことを指します。そのため、厚生労働省によると、役割等級制度には、「企業の経営戦略や組織方針を、各人の役割や職責にダイレクトに設定できる」点に強みがあるとされます。
1-1. 職能資格制度との違い
役割等級制度は、これまで多くの企業で採用されてきた職能資格制度とは異なる制度です。職能資格制度は、社員の職業遂行能力に基づいて待遇を決める制度です。職業遂行能力は、勤続年数とともに上昇していくという前提があるため、年功序列制度や終身雇用制度と強い結びつきがあります。
一方、役割等級制度は年齢や勤続年数にかかわらず、求められる役割をこなしたかどうかをフラットに評価する制度です。
1-2. 職務等級制度との違い
職務等級制度は、社員の職務内容に着目し、等級を分けて評価する制度です。役割等級制度と職務等級制度はよく似ていますが、職務等級制度は社員の全職務に対して「職務記述書」を作成し、業務の責任や難しさを網羅的に記述する点に特徴があります。
一方、役割等級制度では、社員に求められる役割を定義した「役割定義書」を作成し、社員の等級付けをおこないます。
関連記事:職務等級制度の意味や職能資格制度との違いをわかりやすく解説
2. 役割等級制度のメリット

役割等級制度を採用するメリットは2点あります。
- 社員の主体性が高まる
- 社員の貢献度を公平に評価できる
役割等級制度では、企業が期待する役割を積極的に果たした社員が高く評価されるため、社員の主体性を高める効果があります。また、従来の年功序列制度と違い、役割等級制度は年齢や勤続年数にかかわらず、役割を果たせば見合う評価が得られる制度です。そのため、人事評価制度や賃金制度の公平性を高めることができます。
2-1. 社員の主体性が高まる
役割等級制度を導入することで、社員の主体性を高め、組織の活性化につながる場合があります。従来の年功序列制度では、社員の年齢や勤続年数が人事評価の基準となり、社員の主体的な努力や挑戦が評価される仕組みになっていませんでした。
役割等級制度を取り入れれば、人事評価が社員一人ひとりの貢献度とリンクするため、社員が主体的に役割の遂行に取り組む風土が生まれます。
2-2. 社員の貢献度を公平に評価できる
役割等級制度では、社員の年齢や勤続年数にかかわらず、公平に賃金などの待遇を決めます。新入社員や若手社員でも、役割定義書の等級を満たせば、高い評価を得ることが可能です。役割等級制度を取り入れることで、より納得感のある人事評価制度を構築できます。
3. 役割等級制度のデメリット
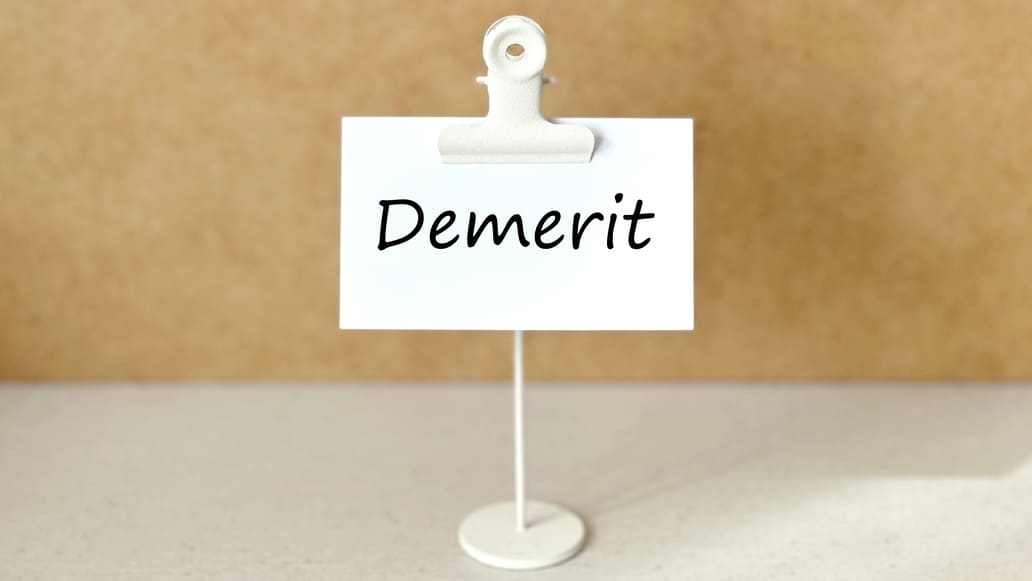
一方、役割等級制度にはデメリットも2点あります。
- 制度設計に時間がかかる
- 社員の理解を得る必要がある
役割等級制度は制度設計に時間がかかるため、人事担当者の負担が増加します。また、年功序列制度をはじめとした従来の評価制度とは大きく異なるため、社員に制度導入の理由を説明し、理解を得ることが大切です。
3-1. 制度設計に時間がかかる
役割等級制度を新たに導入する場合、企業にとって望ましい役割の洗い出しや、役割ごとのグレード分け、評価基準の設定など、制度設計に時間がかかります。また、賃金制度と結びつけ、賃金テーブルの改定などの作業も必要です。そのため、人事担当者の負担が増加する可能性があります。
3-2. 社員の理解を得る必要がある
役割等級制度は比較的新しく普及した制度です。年功序列制度に慣れたベテラン社員などを中心に、役割等級制度の導入が給与の低下につながるとして、反発を招く可能性があります。役割等級制度の導入に当たっては、社員に説明する機会を設け、制度の目的や導入理由を丁寧に伝えることが大切です。
4. 役割等級制度の導入方法
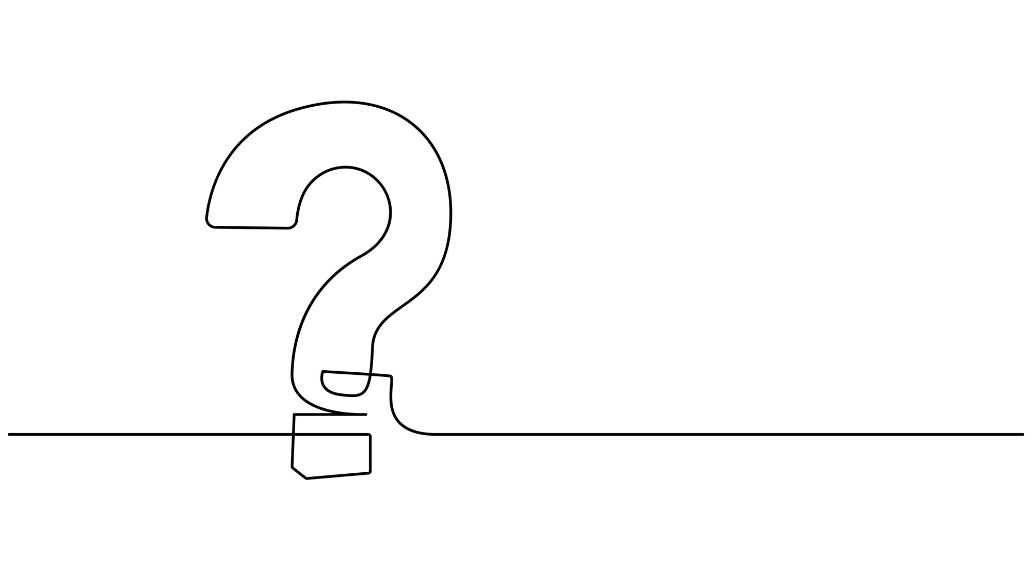
前項で述べたとおり、役割等級制度は導入に時間がかかる制度です。役割等級制度を導入する流れを確認し、スムーズに準備を進めることが大切です。次に、役割等級制度の導入の手順についてご紹介します。
4-1. 制度導入の方向性を固める
役割等級制度を導入するにあたり、まず始めに導入の目的を明確にしておくことが重要です。ここを曖昧なままにしておくと、せっかく制度を導入しても形骸化してしまう可能性が生じます。自社が直面している課題や、どういう人材を必要としているのかなどを洗い出し、経営理念や事業戦略と照らし合せながら、役割等級制度の導入方針を固めておきましょう。
4-2. 等級数と役割を定める
制度導入の方向性が固まったら、職務分析を実施して職務や役割を洗い出し、結果に基づいて等級と役割を決定します。等級数を決める際は適切なバランスが重要です。等級数が多すぎると役割の差が曖昧になり、逆に少なすぎると役割の振り分けが難しくなってしまいます。管理職層で2~3、それ以外の層で3~5とするのが一般的です。
等級数が決まったら、各グレードごとに役割を定義して、役割定義書を作成します。基準は明確かつ簡潔に、誰が読んでも理解できるように作成しましょう。
4-3. 評価プロセスを検討する
等級や役割の定義づけに加えて、評価プロセスも検討しなくてはいけません。役割ごとの評価項目やスケール、ウエイトも決めておきましょう。例えば、厚生労働省が取り上げた事例では、十数個の評価項目を設定し、各項目に5段階のスケール(点数を決めるための基準)とウェイトを設け、社員一人ひとりの「職務(役割)ポイント」を計算しています。
最終的には、役割等級制度と賃金制度を結びつけ、役割や貢献度に応じて賃金が決まる仕組みにする必要があります。賃金テーブルの改定など、賃金制度の見直しもおこなうことが大切です。
参照:厚生労働省 | パートタイム労働者の納得度を高め能力発揮を促進するために
4-4. 導入時期を決める
事前通告なしに導入してしまうと現場の混乱を招くため、予め導入スケジュールを組み、社員に告知するタイミングを決めておきます。
書面だけの告知では従業員からの理解が得られない可能性もあるので、社員向けに説明会を実施するのが望ましいでしょう。また、公正な評価を実現するために、管理職向けの研修を実施するのもおすすめです。
5. 役割等級制度の導入企業の事例

最後に、役割等級制度を導入し事業の成長につながる大きな効果を得た事例を一つご紹介します。
電気機器を製造する企業では、事業環境が厳しくなる中、年功序列による人事制度が企業の成長を阻害する要因となっていました。そこで、企業が求める役割に社員が挑戦できる環境を構築すべく役割等級制度を導入しました。
この際、職務評価を実施した上で、役割定義書の作成がおこなわれています。各ポジションに求められる役割が明確になったことで、人材抜擢がしやすくなり、若手でも管理職に登用できる環境が構築され、組織の活性化につながっています。
参照:「役割定義書」を基に職務評価を実施し、役割等級制度を確立した事例|厚生労働省
6. 役割等級制度のメリット・デメリットを比較し、自社に合った制度を導入しよう

役割等級制度は、企業が社員に期待する行動を「役割(ミッション)」として定義し、役割の等級(グレード)に応じて待遇を決める制度です。役割等級制度の強みは、年齢や勤続年数にかかわらず、求められる役割を果たした社員が評価される点にあります。
役割等級制度を取り入れれば、より公平で社員が納得できる人事評価制度を構築することが可能です。役割等級制度のメリット・デメリットを比較して、自社に合った制度を導入しましょう。
関連記事:等級制度とは?制度の種類や活用するときのポイントを詳しく解説

人事評価制度は、健全な組織体制を作り上げるうえで必要不可欠なものです。
制度を適切に運用することで、従業員のモチベーションや生産性が向上するため、最終的には企業全体の成長にもつながります。
しかし、「しっかりとした人事評価制度を作りたいが、やり方が分からない…」という方もいらっしゃるでしょう。そのような企業のご担当者にご覧いただきたいのが、「人事評価の手引き」です。
本資料では、制度の種類や導入手順、注意点まで詳しくご紹介しています。
組織マネジメントに課題感をお持ちの方は、ぜひこちらから資料をダウンロードの上、お役立てください。
人事・労務管理のピックアップ
-

【採用担当者必読】入社手続きのフロー完全マニュアルを公開
人事・労務管理公開日:2020.12.09更新日:2026.01.30
-

人事総務担当がおこなう退職手続きの流れや注意すべきトラブルとは
人事・労務管理公開日:2022.03.12更新日:2025.09.25
-

雇用契約を更新しない場合の正当な理由とは?伝え方・通知方法も紹介!
人事・労務管理公開日:2020.11.18更新日:2025.10.09
-

社会保険適用拡大とは?2024年10月の法改正や今後の動向、50人以下の企業の対応を解説
人事・労務管理公開日:2022.04.14更新日:2025.10.09
-

健康保険厚生年金保険被保険者資格取得届とは?手続きの流れや注意点
人事・労務管理公開日:2022.01.17更新日:2025.11.21
-

同一労働同一賃金で中小企業が受ける影響や対応しない場合のリスクを解説
人事・労務管理公開日:2022.01.22更新日:2025.08.26
人事評価の関連記事
-

派遣でも部署異動はさせられる?人事が知っておくべき条件・注意点・手順を解説
人事・労務管理公開日:2025.06.03更新日:2025.12.18
-

賞与の決め方とは?種類と支給基準・計算方法・留意すべきポイントを解説
人事・労務管理公開日:2025.05.26更新日:2025.05.27
-

賞与の査定期間とは?算定期間との違いや設定する際の注意点を解説
人事・労務管理公開日:2025.05.25更新日:2025.12.18































