国民年金第3号被保険者関係届とは?定義や提出が必要なケース・手続きを解説

従業員に被扶養者ができた場合や、被扶養者が扶養から外れたとき、人事担当者が行わなければならない労務手続きが「国民年金第3号被保険者関係届」の届け出です。国民年金第3号被保険者関係届とは、従業員の被扶養者が「第3号被保険者」に該当するとき、事業所を通じて日本年金機構に提出する必要がある書類を指します。
この記事では、国民年金第3号被保険者関係届の対象となる第3号被保険者の定義や、第3号被保険者の労務手続きが必要になるケース、国民年金第3号被保険者関係届を提出するまでの流れについて解説します。
目次
社会保険料の支払いは従業員の給与から控除するため、従業員が入退社した際の社会保険の手続きはミスなく対応しなければなりませんが、対象者や申請期限、必要書類など大変複雑で漏れやミスが発生しやすい業務です。
当サイトでは社会保険の手続きをミスや遅滞なく完了させたい方に向け、「社会保険の手続きガイド」を無料配布しております。
ガイドブックでは社会保険の対象者から資格取得・喪失時の手続き方法までを網羅的にわかりやすくまとめているため、「社会保険の手続きに関していつでも確認できるガイドブックが欲しい」という方は、こちらから資料をダウンロードしてご覧ください。
1. 国民年金第3号被保険者関係届とは?


国民年金第3号被保険者関係届とは、厚生年金保険に加入している被保険者が、扶養配偶者を年金制度に加入させる際に必要な書類です。この書類は、日本年金機構に提出され、扶養配偶者が年金保険に加入していることを証明します。この書類を適切に提出することで、国民年金制度への加入状況が正確に管理され、将来的な年金受給にも影響します。
1-1. 国民年金の「第3号被保険者」の定義
国民年金第3号被保険者とは、第2号被保険者である70歳未満の会社員・公務員などに扶養されている20歳以上60歳未満の配偶者を指します(事実婚関係にある人も含む)。
なお、「扶養」の状態になるには、以下の年収要件を二つとも満たす必要があります。
- 年収が130万円未満(障がい者の場合は180万円未満)
- 年収が配偶者の1/2未満(別居の場合は仕送り額未満)
そもそも公的年金制度である国民年金の対象者は、「第1号被保険者」「第2号被保険者」「第3号被保険者」の3種類に分けられます。
被保険者の種類ごとに加入する年金制度や保険料負担、加入方法が異なり、下表の通りになります。
| 第1号被保険者 | 第2号被保険者 | 第3号被保険者 | |
| 定義(対象者) |
日本国内に住む20歳以上60歳未満の人で、自営業、学生、無職など第2・第3被保険者に該当しない人 |
70歳未満の会社員、国家・地方公務員、私立学校教員 | 20歳以上60歳未満で第2号被保険者に扶養される人 |
| 加入する年金制度 | 国民年金 | 国民年金と厚生年金 | 国民年金 |
| 保険料負担 | 月額16,520円(令和5年度)で、加入者が全額負担 | 定められた保険料率を給与にかけた金額を労使で折半 | 負担なし |
| 納付方法 | 加入者自身で納付 | 給与からの天引き | 負担なし |
| 加入手続き | 加入者自身で役所に届け出る | 勤め先が届け出る | 配偶者(扶養者)の勤め先が届け出る |
つまり、第2号被保険者である会社員や公務員の配偶者で、年収が130万円未満の20歳以上60歳未満の方が「第3号被保険者」に該当します。
国民年金の第3号被保険者は保険料を納める義務がありませんが、第3号被保険者になった際に「国民年金第3号被保険者関係届」を届け出る必要があります。
そのため、結婚などにより従業員の被扶養者が増えたために「被扶養者(異動)届」を提出する際、「国民年金第3号被保険者関係届」もあわせて提出することが一般的です。
参考:[年金制度の仕組みと考え方]第3 公的年金制度の体系(被保険者、保険料)|厚生労働省
2. 国民年金第3号被保険者関係届の提出が必要な3つのケース


国民年金第3号被保険者関係届の提出が必要になるケースは、被扶養者が「第3号被保険者になったとき」と「第3号被保険者でなくなったとき」、「海外に転居するとき」の3つのケースです。
注意したいのが、「被扶養者が第3号被保険者ではなくなった場合」も国民年金第3号被保険者関係届を提出しなければならない点です。
それぞれ、詳しく条件を見ていきましょう。
2-1. 被扶養者が新たに第3号被保険者になった場合
国民年金第3号被保険者関係届の提出が必要なのは、従業員の配偶者が扶養に入り、新たに第3号被保険者になった場合です。
たとえば、従業員が結婚した際や、出産や育児など配偶者の年収が減った際などが挙げられます。
また、新しく入社した従業員に被扶養者がいた場合も、事業所を通じて国民年金第3号被保険者関係届を提出する必要があります。
2-2. 被扶養者が第3号被保険者ではなくなった場合
新たに第3号被保険者になった場合だけでなく、被扶養者が第3号被保険者ではなくなった場合も、国民年金第3号被保険者関係届の提出が必要です。具体的なケースとして、以下のような例が想定されます。
- 第2号被保険者である従業員(扶養者)の死亡・退職により、厚生年金の加入者ではなくなった
- 第2号被保険者である従業員(扶養者)が70歳以上になったため、第3号被保険者の資格を喪失し、第1号被保険者になった
- 被扶養者の年間収入が130万円以上になったため、第3号被保険者の資格を喪失し、第1号被保険者または第2号被保険者になった
- 第2号被保険者である従業員(扶養者)と被扶養者が離婚し、被扶養者が第1号被保険者または第2号被保険者になった
被扶養者が第3号被保険者の資格を喪失した場合、第1号被保険者または第2号被保険者への切り替え手続きが必要になります。被保険者の資格変更を行う場合は、第1号被保険者の場合には市区町村の国民年金の窓口、第2号被保険者の場合には勤務先で手続きが必要となります。
2-3. 海外に転居する場合
令和2年(2020年)4月1日以降、被扶養者の認定には年収のほか、「日本国内に居住していること」が要件として追加されました。
したがって、海外に転居し日本国内に居住していない場合は、国民年金第3号被保険者でなくなるため届出が必要となります。
ただし、以下の条件を満たし「日本国内に生活の基礎がある」と認められた場合は、特例として引き続き国民年金第3号被保険者でいることができます。
- 留学をする学生
- 被保険者の海外赴任に同行する者
- 観光やボランティアなどで一時的に海外に渡航する者
- 被保険者が海外赴任している間に婚姻・出産などで親族の関係になった者で2と同じ状況の者
- 1~4以外で個別の事情を考慮し日本国内に生活の基礎があると認められる者
上記の特例を適用する場合でも、被扶養者(異動)届もしくは国民年金第3号被保険者関係届を添付書類とともに届け出る必要があるため、注意しましょう。
参考:健康保険法等の一部改正に伴う国内居住要件の追加(令和2年4月1日施行)|日本年金機構
3. 国民年金第3号被保険者関係届の手続き方法
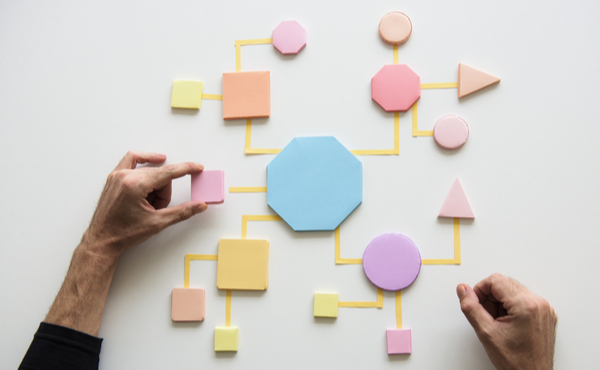
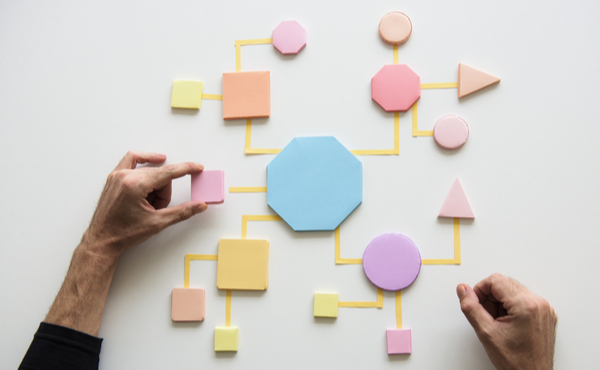
国民年金第3号被保険者関係届は従業員ではなく、扶養者の事業者を通じて届け出る必要があります。手続きの流れは以下の通りです。
- 日本年金機構のホームページなどから、「国民年金第3号被保険者関係届」の書式をダウンロードする
- 被保険者となる従業員に「国民年金第3号被保険者関係届」へ記入してもらう
- 郵送・窓口持参・電子申請により、所轄の年金事務所へ「国民年金第3号被保険者関係届」を提出する
書き方と添付書類、提出方法にわけて、より詳しく解説します。
3-1. 国民年金第3号被保険者関係届の書き方と記入例
まずは日本年金機構のホームページから国民年金第3号被保険者関係届の書式をダウンロードし、従業員に必要な情報を記入してもらいましょう。以下の書式では、書き方の解説資料も一緒にダウンロードすることができます。
日本年金機構の以下のページでは、記入例や被扶養者(異動)届と国民年金第3号被保険者関係届を同時に提出する際などの書式をダウンロードすることができます。
参考:家族を被扶養者にするとき、被扶養者となっている家族に異動があったとき、被扶養者の届出事項に変更があったとき|日本年金機構
国民年金第3号被保険者関係届には「提出者情報」「配偶者欄」「第3号被保険者欄」がありますが、事業所側で「提出者情報」を記入し、従業員に「配偶者欄」と「第3号被保険者欄」を記入してもらうとよいでしょう。
第3号被保険者になった場合は「第3号被保険者欄」で「該当」に丸を付け「第3号被保険者になった日」「理由」「配偶者の加入制度」に記入し、第3号被保険者でなくなった場合は「非該当(変更)」に丸を付け「理由」と「第3号被保険者でなくなった日」に記入をします。
3-2. 必要な添付書類
国民年金第3号被保険者関係届に添付が必要な書類は「続柄確認のための書類」と「収入要件確認のための書類」の2種類です。配偶者と別居している場合と、事実婚(内縁)関係である場合は、別途添付書類が必要になります。
続柄確認のための書類
以下のいずれかを添付する必要があります。
- 被扶養者の戸籍謄(抄)本
- 住民票の写し(同居している場合)
収入要件確認のための書類
扶養には収入要件があるため、要件を満たしているかどうか確認するために、添付が必要な書類があります。
被扶養者が所得税法における控除対象配偶者となっている場合は、事業主の証明があれば添付書類は不要ですが、それ以外の場合は要件を満たした条件に応じて以下の書類を添付しましょう。
-
被扶養者が退職したことにより収入要件を満たす場合:退職証明書または雇用保険被保険者離職票の写し
-
雇用保険失業給付受給、または雇用保険失業給付の受給終了で収入要件を満たす場合:雇用保険受給資格者証または雇用保険受給資格通知の写し
-
被扶養者が年金受給中の場合:現在の年金受取額がわかる年金額の改定通知書などの写し
-
自営業(農業等含む)による収入、不動産収入等がある場合:直近の確定申告書の写し
-
上記以外に他の収入がある場合:上記に応じた書類と課税(非課税)証明書
-
上記以外:課税(非課税)証明書
仕送りについて確認できる書類(被扶養者と別居している場合)
被扶養者と別居している場合、扶養の年収要件に仕送り額が含まれるため、仕送りの事実と金額を確認できる書類を添付する必要があります。
送金者名と受取人名、金額が確認できる以下の書類を用意してもらいましょう。
- 振り込みの場合:「預金通帳等の写し(通帳の名義と振込日と金額が確認できるページ)」「振込明細書」など
- 送金の場合:「現金書留の控え(写し)」
内縁関係を確認するための書類
第3号被保険者は事実婚(内縁)関係でも適用されるため、婚姻関係にない場合は以下の書類を提出する必要があります。
- 内縁関係にある両人の戸籍謄(抄)本
- 被保険者の世帯全員の住民票
3-3. 国民年金第3号被保険者関係届の提出先と提出方法
国民年金第3号被保険者関係届は、所轄の年金事務所へ届け出ます。提出方法としては、郵送・窓口持参・電子申請の3つがあります。
人事部門の業務効率化を目指す場合は、総務省が運営する「e-Gov」を通じた電子申請がおすすめです。電子申請なら24時間365日いつでもどこでも手続き可能なため、テレワークやリモートワークの導入企業に向いています。ジンジャー人事労務であれば、書類の収集から提出までを一気通貫でおこなうことが可能です。詳しくは当サイトで無料配布している「1分でわかるジンジャー人事労務|社保手続き」の資料で紹介しているので、興味がある方はぜひこちらからご覧ください。実際の画面キャプチャを交えて紹介しているので「電子申請のイメージがわいていない」という方にもおすすめです。
4. 手続きが行われないとどうなる?「不整合期間」とは


被扶養者の年収が130万円を上回るなど、第3号被保険者としての資格を喪失した場合、第1号被保険者または第2号被保険者への切り替え手続きを行う必要があります。
もし切り替え手続きが発生しなかった場合、「不整合期間」が発生し、将来の年金が少なくなるリスクが存在します。
4-1. 不整合期間が発生すると、将来の年金が少なくなる!
被扶養者が第3号被保険者としての資格を喪失したにもかかわらず、第1号被保険者または第2号被保険者への切り替え手続きを行わなかった場合、「不整合期間(第3号不整合期間)」が発生します。
第3号被保険者は、年金保険料の支払いが免除されます。第3号被保険者の資格喪失者が、もし年金保険料を支払わなかった場合、不整合期間の長さに応じて、将来的な年金金額が少なくなります。
4-2. 保険料の未納分をさかのぼって納付できるのは2年間まで
第3号被保険者の切り替え手続きを行っていなかった場合でも、最大2年間までなら、未納分をさかのぼって年金保険料や健康保険料を支払うことができます。
もし2年以上の不整合期間が生じた場合は、「時効消滅不整合期間にかかる特定期間該当届」の手続きを行う方法もあります。「時効消滅不整合期間にかかる特定期間該当届」 を提出すれば、保険料の未納期間を年金の受給資格期間に算入できる可能性があります。
ただし、未納期間を受給資格期間として算入できるのは、2013年6月までの期間に限られます。
5. 扶養の出入りがあった際には速やかに国民年金第3号被保険者関係届を提出しよう


従業員の被扶養者が「第3号被保険者」に該当する場合、国民年金第3号被保険者関係届の提出が必要です。企業の労務担当者や人事担当者は、日本年金機構のホームページなどを確認し、「第3号被保険者」の条件を確認しておきましょう。被扶養者の年収が130万円を上回るなど、被扶養者が第3号被保険者としての資格を喪失した場合、切り替え手続きを行う必要があります。
もし切り替え手続きを行わなかった場合、「不整合期間」の発生により、被扶養者が受け取る将来の年金が少なくなる可能性があります。
社会保険料の支払いは従業員の給与から控除するため、従業員が入退社した際の社会保険の手続きはミスなく対応しなければなりませんが、対象者や申請期限、必要書類など大変複雑で漏れやミスが発生しやすい業務です。
当サイトでは社会保険の手続きをミスや遅滞なく完了させたい方に向け、「社会保険の手続きガイド」を無料配布しております。
ガイドブックでは社会保険の対象者から資格取得・喪失時の手続き方法までを網羅的にわかりやすくまとめているため、「社会保険の手続きに関していつでも確認できるガイドブックが欲しい」という方は、こちらから資料をダウンロードしてご覧ください。
人事・労務管理のピックアップ
-


【採用担当者必読】入社手続きのフロー完全マニュアルを公開
人事・労務管理公開日:2020.12.09更新日:2024.03.08
-


人事総務担当が行う退職手続きの流れや注意すべきトラブルとは
人事・労務管理公開日:2022.03.12更新日:2024.07.31
-


雇用契約を更新しない場合の正当な理由とは?通達方法も解説!
人事・労務管理公開日:2020.11.18更新日:2024.08.05
-


法改正による社会保険適用拡大とは?対象や対応方法をわかりやすく解説
人事・労務管理公開日:2022.04.14更新日:2024.08.22
-


健康保険厚生年金保険被保険者資格取得届とは?手続きの流れや注意点
人事・労務管理公開日:2022.01.17更新日:2024.07.02
-


同一労働同一賃金で中小企業が受ける影響や対応しない場合のリスクを解説
人事・労務管理公開日:2022.01.22更新日:2024.10.16
労務管理の関連記事
-


【2024年最新】労務管理システムとは?自社に最も適した選び方や導入するメリットを解説!
人事・労務管理公開日:2024.08.22更新日:2024.08.22
-


【2024年4月】労働条件明示のルール改正の内容は?企業の対応や注意点を解説
人事・労務管理公開日:2023.10.27更新日:2024.10.18
-


社員の離職防止の施策とは?原因や成功事例を詳しく解説
人事・労務管理公開日:2023.10.27更新日:2024.09.03




















