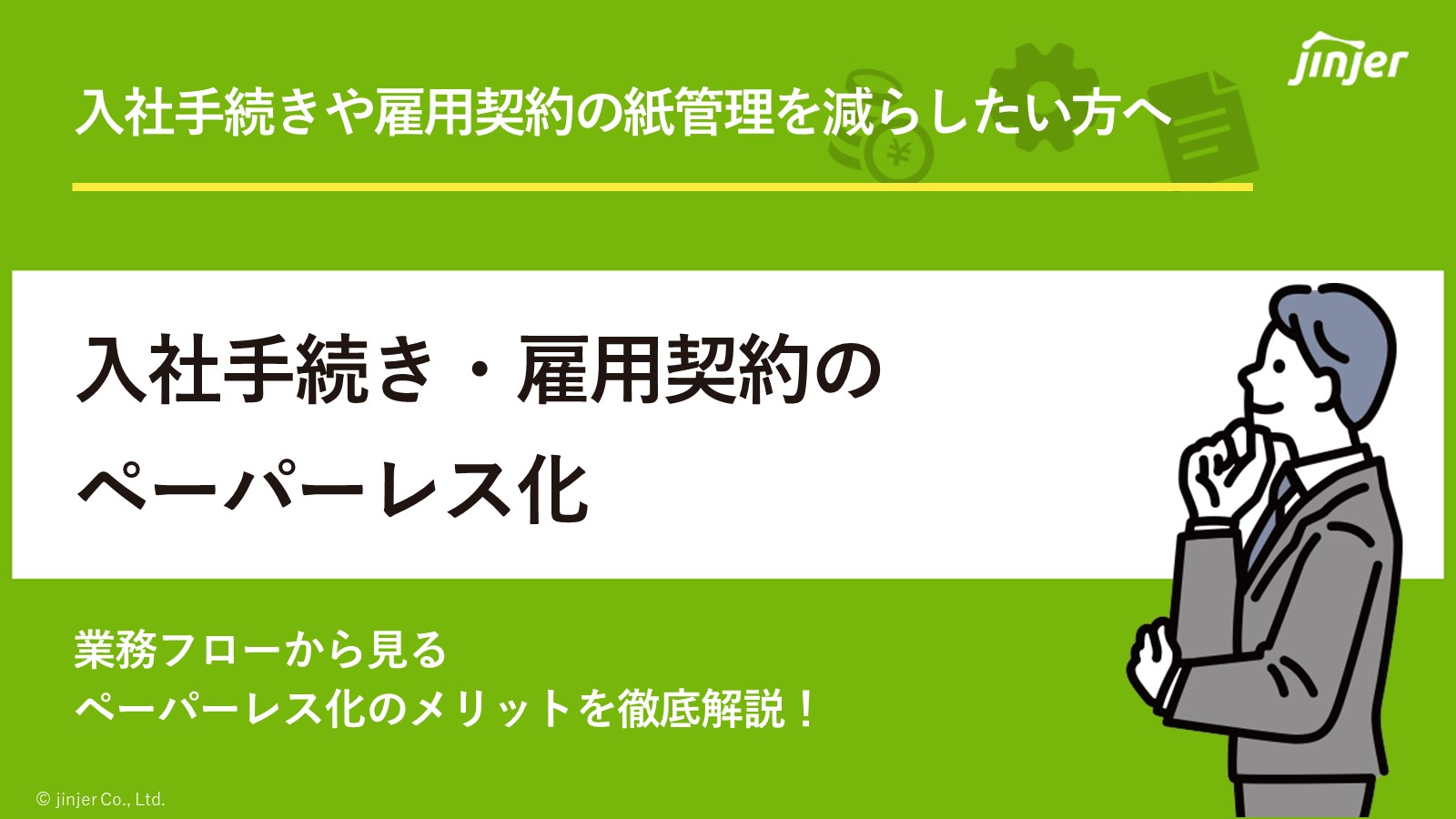退職金制度の基本や計算方法・金額相場・税金を詳しく紹介

退職従業員に対して金銭を支給する「退職金制度」は多くの企業が導入しています。しかし、この退職金制度を根本から理解している人はあまり多くありません。
そこで本記事では、退職金制度の基本や計算方法、金額相場、税金などについて解説します。自社に最適な退職金制度を導入するためにも、ぜひ最後までご覧ください。
▼退職金そのものの知識についてまずは抑えたい方はこちら
労働基準法に退職金の規定はある?金額の決め方を詳しく解説
デジタル化に拍車がかかり、「入社手続き・雇用契約の書類作成や管理を減らすために、どうしたらいいかわからない・・」とお困りの人事担当者様も多いでしょう。
そのような課題解決の一手として検討していきたいのが、入社手続き・雇用契約のペーパーレス化です。
システムで管理すると、雇用契約の書類を作成するときに、わざわざ履歴書を見ながら書類作成する必要がありません。書類作成に必要な項目は自動で入力されます。
また、紙の書類を郵送する必要がないので、従業員とのコミュニケーションが円滑に進み、管理者・従業員ともに”ラク”になります。
入社手続き・雇用契約のペーパーレス化を成功させるため、ぜひ「3分でわかる入社手続き・雇用契約のペーパーレス化」をこちらからダウンロードしてお役立てください。
目次
1. 退職金制度の基本

退職金制度について理解を深めるためには、まず基本的な知識を身につけておくことが必要です。ここでは、退職金制度の概要や法律との関係など、基礎知識について解説します。
1-1. 退職金制度とは退職従業員に対して金銭を支給する制度
退職金制度とは、企業側の雇い主が退職従業員に対して金銭を支給する制度のことを指します。
退職金制度が一般的な言葉ですが、正式名称は「退職給付制度」です。
この退職金制度の支給方法については、退職時に1度だけ支給する「退職一時金制度」と、一定金額を定期的に支給する「退職年金制度」の2種類があります。
また、退職金が支給されるタイミングは定年退職時のみではなく、自己都合による中途退職や解雇、死亡などのケースもあります。
1-2. 退職金制度の導入率
厚生労働省が公表した「中小企業の賃金・退職金事情(令和2年版)」の調査によると、従業員10〜299人の都内中小企業における退職金制度について「制度あり」と回答した企業は65.9%、「制度なし」と回答した企業は20.9%でした。
また、「制度あり」と回答した企業のうち、71.8%が「退職一時金のみ」と回答しています。
一方、「退職一時金と退職年金の併用」と回答した企業は23.3%でした。
これらのことから、多くの企業が退職金制度を実施してはいるものの、ほとんどの企業が退職一時金のみを採用していることがわかります。
1-3. 退職金制度は法律上における義務はない
多くの企業が実施している退職金制度ですが、実は法律上における支払い義務はありません。
退職金を支払うかどうかは就業規則や労働協約で定めることができるため、すべては企業側の裁量次第なのです。
さらに、支給内容も企業ごとに設定できることから、一律の決まりや義務は設けられていません。
2. 退職金制度の種類

退職金制度には、多くの企業で採用している「退職金一時金制度」のほかにも種類があります。それぞれ、運用の仕方や支給方法などが異なるため、違いについてもここでしっかり押さえておきましょう。
2-1. 退職一時金制度
退職金制度の種類1つ目は、「退職一時金制度」です。
退職時に一括で金銭を支給する制度であり、最も一般的な退職金制度となります。
ただし、この「退職一時金制度」を実施するためには、一括で支払うだけの金銭的な余裕が必要です。
また、現金での積み立てとなることから、積立金が課税されてしまう点にも注意しましょう。
2-2. 確定給付企業年金制度
退職金制度の種類2つ目は、「確定給付企業年金制度」です。
「確定給付企業年金制度」は確定した退職金が給付される制度であり、生命保険などを活用して年金資金の管理・運用をおこないます。
そのため、掛金を損金扱いにできる税制上のメリットが見込めますが、資金運用の失敗や金額が不足するなど一定のリスクが伴います。
2-3. 中小企業退職金共済
3つ目の退職金制度として、「中小企業退職金共済」を解説します。
「中小企業退職金共済」は従業員ごとに掛金の設定が可能です。
この際の掛金は全額非課税になるため、金銭的に余裕がない企業でも退職金制度を導入できます。
ただし、掛金の設定・変更は従業員からの同意が必要なので、経営状況に合わせて掛金を自由に変動させることができないという難点があります。
なお、本制度は「自社単独で退職金制度を設けることが困難である中小企業」しか加入できないことから、大企業は導入できません。
2-4. 企業型確定拠出年金制度(企業型DC)
退職金制度の種類4つ目は、「企業型確定拠出年金制度(企業型DC)」です。
この「企業型DC」は企業側が毎月掛金を積み立てていき、従業員自らが年金資金を運用します。
従業員自らが資金運用を実施する点から、企業側が全責任を負わなくても良いというメリットがあります。
資金運用まで手が回らない中小企業が導入しやすい退職金制度です。
3. 退職金の計算方法

退職金の計算方法は、会社が採用している制度によってそれぞれ異なります。
ここでは、「退職金一時金制度」の代表的な4つの計算方法について解説します。
3-1. 定額制
定額制は、基本給には関係なく勤続年数に応じて退職金の支給額を決定する方法です。支給額については、あらかじめ就業規則や退職金規定などで決められているのが一般的です。
3-2. 基本給連動型
基本給連動型では、勤続年数に加えて退職時の基本給や退職理由などを加味して計算をおこないます。
支給係数は会社によって異なりますが、一般的には勤続年数と連動する形となっています。また、退職理由の係数は、自己都合8割、会社都合10割としているケースが多いようです。
【計算例】勤続年数10年の支給係数10、自己都合退職の係数0.8、退職時の基本給30万円の場合
30万円×10×0.8=240万円
3-3. ポイント制
ポイント制は、基本給や勤続年数、役職、退職理由などに基づいてポイント換算し、退職時の累計ポイントに応じて支給額を決定する方法です。
【計算例】
勤続1年につき10ポイント付与、課長クラスはさらに役職1年につき10ポイント加算、自己都合退職は8割、1ポイントあたりの単価は1万円と規定。
勤続年数20年(うち課長としての在職期間10年)の場合。
(10ポイント×20年+役職10ポイント×10年)×0.8×1万円=240万円
3-4. 別テーブル制
別テーブル制は、勤続年数に応じた基準額に役職や退職理由などをかけ合わせた表(テーブル)を作成し、その表に基づいて計算する方法です。ベースとなるのが基本給ではなく、勤続年数に応じて別設定された基準額である点がポイントとなります。
【計算例】勤続年数20年の基準額200万円、課長クラスの係数1.1、退職事由係数0.8の場合
基準額200万円×1.1×0.8(自己都合)=176万円
4. 退職金の金額相場

退職金制度の基本や種類、計算方法がわかったところで、退職金の金額相場をみていきましょう。
厚生労働省が発表した令和5年度の「退職給付(一時金・年金)の支給実態」によると、退職金の金額は最終学歴や勤続年数によって平均額が異なっています。
条件ごとに1つずつみていきましょう。
4-1. 大学・大学院卒の平均退職給付額(勤続20年以上かつ45歳以上が対象)
大学・大学院卒の平均退職給付額は下記のとおりです。
| 定年退職 | 1,896万円 |
| 会社都合 | 1,738万円 |
| 自己都合 | 1,441万円 |
| 早期優遇 | 2,286万円 |
4-2. 高校卒の平均退職給付額(勤続20年以上かつ45歳以上が対象)
高校卒の平均退職給付額は職種によっても異なります。
■管理・事務・技術職
| 定年退職 | 1,682万円 |
| 会社都合 | 1,385万円 |
| 自己都合 | 1,280万円 |
| 早期優遇 | 2,432万円 |
■それ以外の職業
| 定年退職 | 1,183万円 |
| 会社都合 | 737万円 |
| 自己都合 | 921万円 |
| 早期優遇 | 2,146万円 |
このように、職種や退職理由によって退職金は異なるので、注意しましょう。
5. 退職金を支給する勤続年数は?

平成30年の就労条件総合調査によると、退職手当のある企業のうち、退職手当受給に必要な最適勤続年数「3年以上4年未満」である企業が全体の56.4%となっています。次いで多いのが、「1年以上2年未満」で全体の15.0%です(いずれも自己都合の場合)。
退職金支給に必要な所要年数は企業側で自由に決めることができますが、一般的には3年以上としている企業が多い傾向にあるようです。
自社の退職金制度を見直す際に、参考にしてみると良いでしょう。
6. 退職金にかかる税金の計算方法

退職金には所得税と住民税がかかります。会社が源泉徴収をし、支給した月の翌月10日までに税金を納付しなくてはいけません。ここでは、退職金の所得税と住民税の計算について解説します。
6-1. 所得税
退職金は退職所得に該当するため、従業員に「退職所得の受給に関する申告書」を提出してもらいます。この「退職所得の受給に関する申告書」の有無によって、所得税の計算方法や税額が変わってくるため、必ず提出してもらうようにしましょう。
「退職所得の受給に関する申告書」のある場合とない場合、それぞれの計算方法については次のとおりです。
「退職所得の受給に関する申告書」がある場合
退職所得控除の適用を受けることができます。所得税を計算する前にまず「課税退職所得金額」を求めます。勤続年数によって退職所得控除額が変わるため、計算の際は注意しましょう。
〈課税退職所得金額の計算方法〉
課税退職所得金額=(退職金額-退職所得控除額)÷2
〈退職所得控除額の計算方法〉
勤続年数20年以下:40万円×勤続年数
勤続年数20年超:800万円+70万円×(勤続年数-20年)
勤続年数に1年未満の端数がある場合は、切り上げて計算します。計算の結果、金額が80万円以下であった場合は、80万円が退職所得控除額となります。
課税退職所得金額が算出できたら、次に所得税と復興特別所得税を計算します。
<退職金の所得税額の計算方法>
退職金の所得税額=課税退職所得金額×所得税率-控除額
所得税率と控除額に関しては、国税庁のホームページに掲載されている「所得税の税額表」を用いて計算をおこないます。
<退職金の復興特別所得税の計算方法>
退職金の復興特別所得税額=退職金の所得税額×2.1%
参考:退職金と税|国税庁
「退職所得の受給に関する申告書」がない場合
退職所得控除の適用を受けることができません。退職金の額に対して一律20.42%の税率で所得税を計算して源泉徴収をおこないます。
6-2. 住民税
退職金の住民税の計算方法は次のとおりです。
<退職金の住民税の計算方法>
課税退職所得金額=(退職金額-退職所得控除額)÷2
退職金の住民税=課税退職所得金額×住民税率
住民税率は市町村民税(特別区民税)6%、道府県民税(都民税)4%となっています。それぞれ計算し合算額を納税します。住民税に100円未満の端数がでる場合は、切り捨てて計算しましょう。
なお、課税退職所得金額は、所得税の計算と同じ方法によって求めます。
ここで注意したいのが、課税退職所得金額を求める際に、2分の1の乗率が適用にならないケースがある点です。勤続年数5年以内の法人役員は、2分の1の乗率が適用されません。
また、勤続年数5年以内の従業員は、退職金から退職所得控除額を引いたあとの金額が300万円を超える場合、その超えた金額には2分の1の乗率が適用となりません。
退職金の住民税を計算する際は、上記の点に注意しましょう。
7. 自社にとって最適な退職金制度を導入しよう

退職金制度は、企業側の雇い主が退職従業員に対して支給する制度であり、企業側が退職金を支払うかどうかを自由に決めることができます。
ただし、退職金制度を導入している企業は多く、優秀な従業員を雇用したいのであれば検討する必要があります。
ぜひ本記事で解説した退職金制度を理解し、自社にとって最適な退職金制度を導入しましょう。
人事・労務管理のピックアップ
-

【採用担当者必読】入社手続きのフロー完全マニュアルを公開
人事・労務管理
公開日:2020.12.09更新日:2024.03.08
-

人事総務担当が行う退職手続きの流れや注意すべきトラブルとは
人事・労務管理
公開日:2022.03.12更新日:2024.06.11
-

雇用契約を更新しない場合の正当な理由とは?通達方法も解説!
人事・労務管理
公開日:2020.11.18更新日:2024.07.10
-

法改正による社会保険適用拡大とは?対象や対応方法をわかりやすく解説
人事・労務管理
公開日:2022.04.14更新日:2024.06.12
-

健康保険厚生年金保険被保険者資格取得届とは?手続きの流れや注意点
人事・労務管理
公開日:2022.01.17更新日:2024.07.02
-

同一労働同一賃金で中小企業が受ける影響や対応しない場合のリスクを解説
人事・労務管理
公開日:2022.01.22更新日:2024.05.08