社会保険料は賞与(ボーナス)から控除される?保険料の計算方法や注意点を解説
更新日: 2025.9.29 公開日: 2025.2.24 jinjer Blog 編集部

賞与は給与の一部とみなされるので、社会保険料が控除されます。
給料から控除する社会保険料は標準報酬月額を使って計算しますが、賞与から控除する社会保険料の計算で使われるのは標準賞与額です。そのため、賞与から社会保険料を控除する場合は、担当者の方は間違えないようにしなければなりません。
控除の額を間違えたり社会保険料控除に関する正しい知識がなかったりすると、計算ミスをしてしまう可能性があります。賞与は従業員にとって大切な臨時収入となるので、ささいなミスで信頼失わないよう注意が必要です。
この記事では、賞与にかかる社会保険料の種類や計算方法、注意点について解説します。
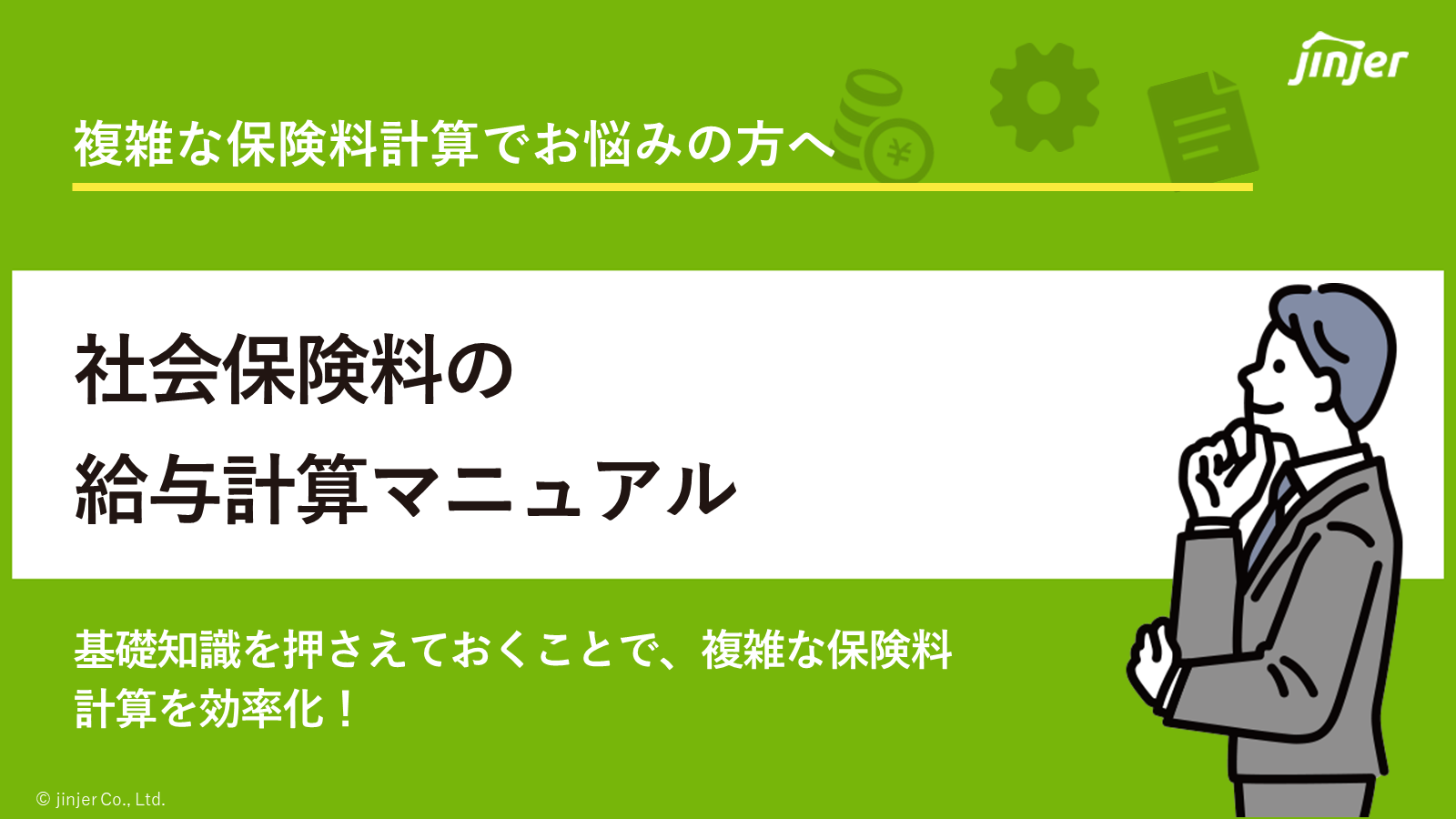
給与計算業務でミスが起きやすい社会保険料。保険料率の見直しが毎年あるため、更新をし損ねてしまうと支払いの過不足が生じ、従業員の信頼を損なうことにもつながります。
当サイトでは、社会保険4種類の概要や計算方法から、ミス低減と効率化が期待できる方法までを解説した資料を、無料で配布しております。
「保険料率変更の対応を自動化したい」「保険料の計算が合っているか不安」「給与計算をミスする不安から解放されたい」という担当の方は、ぜひこちらから資料をダウンロードしてご活用ください。
1. 会保険料は賞与(ボーナス)からも控除される?


社会保険料は、毎月の給与と同様に、賞与(ボーナス)からも控除されます。
従業員からすると「賞与と給与は違うもの」というイメージになっているかもしれませんが、経理の視点でいうと賞与も給与の一部と見なされます。そのため、賞与にも健康保険料や厚生年金保険料、雇用保険料などの社会保険料が適用され、実際の手取り額は控除後の金額となります。
また、所得税は年間所得に基づいて計算されるため、賞与も課税対象です。
ただし、住民税は賞与から控除されません。住民税は前年の所得に基づいて年間の税額が確定し、毎月の給与からあらかじめ決まった額を控除する仕組みが採用されているためです。
1-1. 「賞与」の定義
賞与というと、夏や冬に支給される「ボーナス」をイメージするのが一般的です。
しかし、賞与の定義は「被保険者が労働の対償として受けるもののうち年3回以下で支給されるもの」です。つまり名称は関係なく、極端な例を出すと、例え「給料」や「手当」という名称で支給されるものであっても、支給が年3回以下であれば「賞与」となるのです。
ただし、年4回以上支給されるものに関しては、名称が「賞与」であっても標準報酬月額の対象となります。
ちなみに、結婚祝い金やお見舞い金など、労働の対償とみなされないものは、支給が年3回以下であっても賞与や給与にならないので社会保険料控除の対象にはなりません。
1-2. 「標準報酬月額」の決め方とは?
給料というのは、昇給などによって変動するため、社会保険料の計算をする場合は「標準報酬月額」を使います。
標準報酬月額の決め方は、下記の4つがあります。
a. 月給・週給など一定の期間によって定められている報酬については、その報酬の額を月額に換算した額
b. 日給・時間給・出来高給・請負給などの報酬については、その事業所で前月に同じような業務に従事し、同じような報酬を受けた人の報酬の平均額
c. aまたはbの方法で計算することのできないときは、資格取得の月前1か月間に同じ地方で同じような業務に従事し、同じような報酬を受けた人の報酬の額
d. aまたはbまでの2つ以上に該当する報酬を受けている場合には、それぞれの方法により算定した額の合計額
(関係条文 健康保険法 第42条 )
標準報酬月額は、年に1回決まった時期に見直す「定時決定」がおこなわれます。
賞与から控除する社会保険料は、税引前の賞与総額から千円未満を切り捨てた「標準賞与額」用いて計算しますが、これは全国保険協会などが設定します。
1-3. 社会保険料の控除対象となる賞与の上限
賞与は、社会保険料の控除対象です。しかし、すべての賞与が控除対象となるわけではなく、上限が定められています。
標準賞与額の上限は、健康保険は年間累計額573万円(毎年4月1日から翌年3月31日までの累計額)となり、厚生年金保険については1ヶ月あたり150万円が上限となります。
育児休業を利用している従業員は保険料が免除されますが、賞与が支払われた場合は標準賞与額として決定するので、年間累計額に加算されます。
ただし、年度の途中で被保険者の資格を喪失したり、逆に取得したりした場合の標準賞与額の累計は保険者単位となります。つまり、同一年度内で複数の保険者から賞与を支払われたとしても、標準賞与額の累計は同一の保険者から支払われた賞与だけになるので間違えないようにしましょう。
2. 社会保険料が賞与から控除される背景
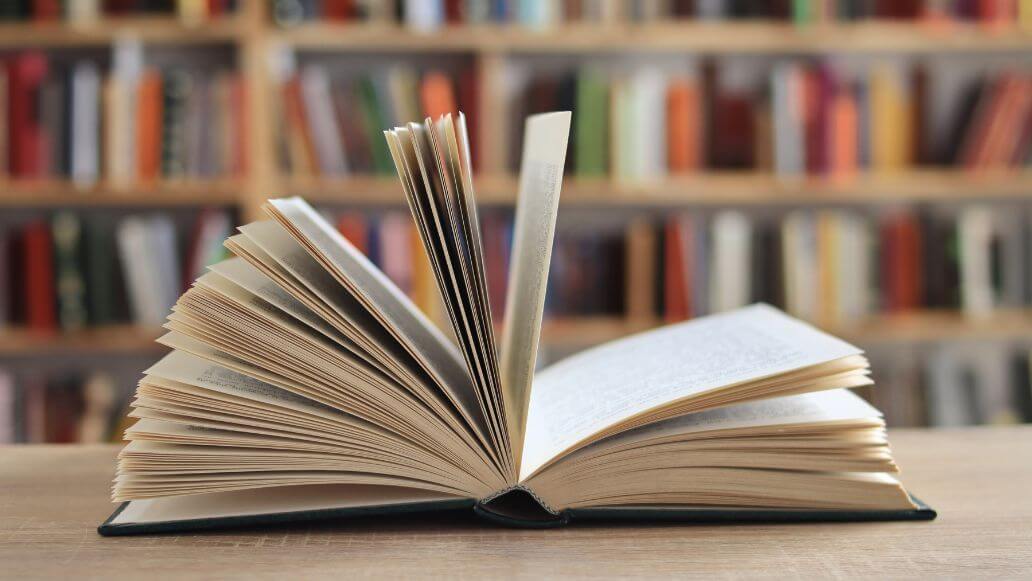
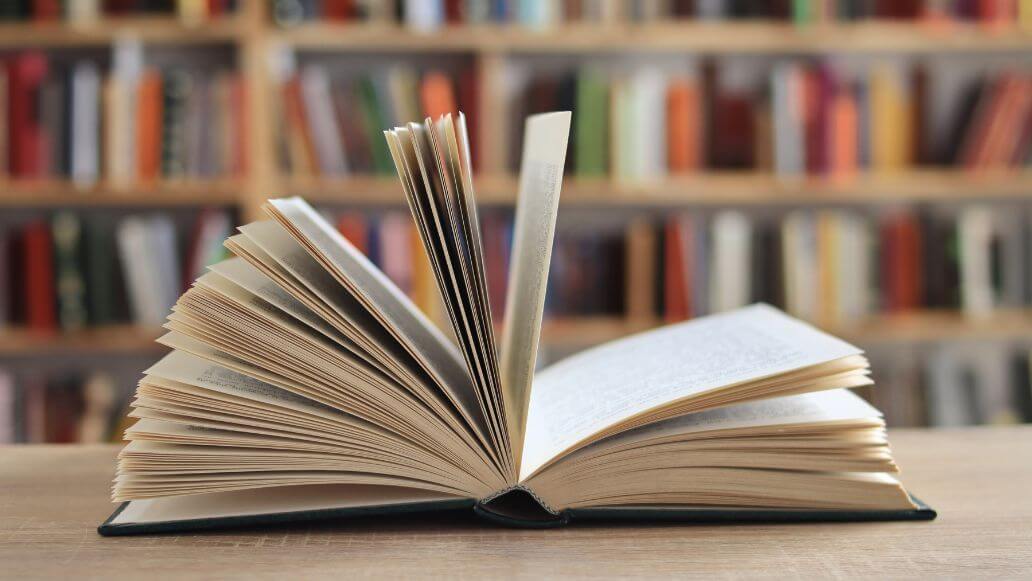
賞与から社会保険料が控除されるようになったのは、「特別保険料」の廃止と「総報酬制」の導入によるものです。
以前は、社会保険料は給与からのみ控除され、賞与については「特別保険料」として別途1%が徴収されていました。
しかし、特別保険料は従業員の年金には反映されず、当時の高齢者への年金給付に充てられていたため、不満の声が多かったのです。また、社会保険料負担を軽減するために給与を減らし、賞与を多くする方法をとる企業も少なくありませんでした。
このような問題を解決するために、2003年4月から給与と賞与を合計した額から計算する「総報酬制」が導入された経緯があります。
総報酬制の導入により、従業員や企業の両者ともに社会保険料負担が増加しましたが、その一方で年金制度全体の安定性が向上しました。
3. 賞与にかかる社会保険料の4つの種類と計算方法


賞与にかかる社会保険料は以下の4種類があります。
- 健康保険料
- 介護保険料
- 厚生年金保険料
- 雇用保険料
ここでは、これらの計算方法や注意点について解説します。
3-1. 健康保険料の計算方法
健康保険料は、事業主と従業員が半分ずつ負担するため、計算式は以下のようになります。
| 健康保険料 = 標準賞与額 × 健康保険料率 ÷ 2
※標準賞与額:賞与から1,000円未満切り捨てした額 |
注意点は、健康保険料率は加入する健康保険組合や事業所の所在都道府県により異なるということです。また、毎年改定されるということも忘れないようにしましょう。改定前の健康保険料率で計算してしまうと、未納分が発生してしまうこともあるため、計算をする際には必ず最新情報を確認することが重要です。
ちなみに、標準賞与額の上限金額は、4月1日~3月31日までの年間累計で573万円となります。
3-2. 介護保険料の計算方法
介護保険料も、健康保険料と同じく事業主と従業員が折半で負担するため、計算式は以下のとおりです。
| 介護保険料 = 標準賞与額 × 介護保険料率 ÷ 2
※標準賞与額:賞与から1,000円未満切り捨てした額 |
介護保険料率は全国健康保険協会(協会けんぽ)の場合全国一律で、2025年度は16.0%となっています。ただし、協会けんぽ以外の組合に加入している場合は、保険者に確認が必要です。
また、介護保険料は、対象者が40歳以上65歳未満の従業員と定められているので、対象外の従業員から徴収しないように注意しましょう。
標準賞与額の上限金額は健康保険料と同じく、年間累計で573万円となります。
3-3. 厚生年金保険料の計算方法
厚生年金保険料は、標準報酬月額(毎月の給与)と標準賞与額(賞与)に共通の保険料率をかけることで算出できます。厚生年金保険料も事業主と従業員が半分ずつ負担するので、計算式は以下のとおりです。
| 厚生年金保険料 = 標準賞与額 × 厚生年金保険料率 ÷ 2
※標準賞与額:賞与から1,000円未満切り捨てした額 |
厚生年金保険の保険料率というのは、年金制度改正によって2004年から段階的に引き上げられてきました。しかし、2017年9月には引上げが終了したため、現時点での厚生年金保険料率は18.3%で固定されています。
厚生年金保険料が控除される標準賞与額の上限金額は、1ヵ月あたり150万円となります。
3-4. 雇用保険料の計算方法
雇用保険料の計算式は以下のとおりです。
| 雇用保険料 = 賞与支給額 × 雇用保険料率 |
雇用保険料はほかの社会保険料とは異なり、賞与支給額を基準に計算されます。1,000円未満を切り捨てないことに注意しましょう。
雇用保険料率は、業種によって異なります。2024年度の業種ごとの雇用保険料率は以下の通りです。
| 業種 | 雇用保険料率(合計) | 労働者負担分 | 事業主負担分 |
|---|---|---|---|
| 一般の事業 | 15.5/1,000 | 6/1,000 | 9.5/1,000 |
| 農林水産・清酒製造 | 17.5/1,000 | 7/1,000 | 10.5/1,000 |
| 建設の事業 | 18.5/1,000 | 7/1,000 | 11.5/1,000 |
なお、雇用保険料は上限がないため、賞与が高額であるほど控除額が大きくなります。
4. 賞与から社会保険料が控除されないケース


賞与から社会保険料が控除されない主なケースは、以下のとおりです。
- 産前産後休業・育児休業中の場合
- 退職する月が賞与支給月の場合
ここでは、それぞれのケースについて、詳しく解説します。
4-1. 産前産後休業・育児休業中の場合
産前産後休業や育児休業中の従業員は、賞与から社会保険料(雇用保険料を除く)が控除されません。
控除されない理由は、産前産後休業・育児休業中は、社会保険料免除が適用されるからです。
ただし、雇用保険料と所得税に関しては、産前産後休業・育児休業中に賞与が支給される場合でも控除されます。
また、以下の場合は社会保険料免除の対象外です。
- 育児休業期間が1ヵ月未満の場合
- 育児休業の期間が月末を含まない場合
賞与への控除も、給与と同じく1ヵ月単位が基準となります。そのため、産前産後、育児休業中に賞与を支給して、月末までに復帰した場合は賞与に対して保険料を徴収しなければなりません。
育児休暇を取得している従業員に関しては、育児休暇の期間をもとに、社会保険料が控除されるかを確認しましょう。
4-2. 退職する月が賞与支給月の場合
従業員の退職月に賞与を支給する場合、退職日が月末か否かで、社会保険料が控除されるかどうかが決まります。
社会保険料の徴収は、被保険者資格喪失日の前月分までが対象となっているので、「月末時点で会社に在籍しているかどうか」で発生が決まる仕組みです。
そのため、退職日が月末の場合は「資格喪失日」が翌月の1日になるので、退職月の社会保険料が発生します。つまり7月10日に賞与が支給された場合、7月31日に退職したとしても8月1日が資格喪失日となるので賞与から社会保険料が控除されます。
しかし、7月11日に退職した場合は7月12日が資格喪失日となるので、月の途中で退職した場合はその月の社会保険料は発生しないため、賞与からは控除されません。
5. 賞与から社会保険料を控除する際の注意点


賞与から社会保険料を控除する際の注意点は、以下のとおりです。
- 同月に2回以上賞与を支給する場合は支給額を合算する
- 年4回以上賞与を支給する場合は「報酬」として扱われる
- 臨時の賞与も年3回以下の支給であれば対象となる
- 役員の賞与も社会保険料の対象となる
- 社会保険料率は定期的に見直される
ここでは、これらの注意点について解説していきます。
5-1. 同月に2回以上賞与を支給する場合は支給額を合算する
同じ月に賞与を2回以上支給する場合、支給額を合算して1,000円未満を切り捨てた金額(標準賞与額)を基に社会保険料を計算します。合算して計算するのは、社会保険料は賞与ごとではなく、同一月に支給された賞与の合計金額から標準賞与額を算出するルールとなっているからです。
例えば、1回目に100,500円、2回目に111,000円を賞与として支払った場合の計算式は次のようになります。
100,000円(1回目の賞与)+111,000円(2回目の賞与)=211,000円(標準賞与額)
211,000円(標準賞与額)×各保険料率-1回目に控除した社会保険料
支給額を合算せず別々に計算すると、本来より控除額が少なくなる可能性があるため注意しましょう。
5-2. 年4回以上賞与を支給する場合は「報酬」として扱われる
賞与が年4回以上支給される場合は、社会保険料の計算方法が変わります。年4回以上支給される賞与は、実質的に定期的な給与の一部(報酬)とみなされるためです。
賞与が報酬扱いとなった場合、年間賞与額から1ヵ月あたりの平均額を算出し、月々の給与に加算して社会保険料を計算します。
例えば、年間の賞与額が240万円の場合は、20万円が月々の給与に加算され、標準報酬月額として社会保険料の計算に反映される仕組みです。
従業員は月々の手取り額が減少するため、この仕組みを従業員が理解していないと不満や混乱を招く可能性があります。
賞与を年4回以上支給する場合は、事前に従業員に対して制度変更の内容や影響をしっかり説明し、納得を得ることが重要です。
5-3. 臨時の賞与も年3回以下の支給であれば対象となる
賞与は、夏と冬に支給する企業が多いですが、決算期などで黒字だった場合は臨時の賞与を支給することがあるかもしれません。
臨時の賞与は、就業規則の賃金規定に記載していないという企業もあるでしょう。しかし、年2回の賞与以外に支給した場合、それが3回以下であれば社会保険料の控除対象となります。
年4回支給した場合は「報酬」として扱いますが、年3回以下の場合は「賞与」の扱いになるため、標準賞与額で控除額を算出してください。
ちなみに、臨時であっても賞与を支給した場合、事業主は年金事務所と健康尾保険組合に対して、賞与支給日を起算日として5日以内に賞与支払届を提出しなければならないので忘れないようにしましょう。
5-4. 役員の賞与も社会保険料の対象となる
役員報酬が0円であっても、賞与を支給する場合は社会保険料の対象になるため、必ず社会保険に加入しなければなりません。加入は、役員賞与を実際に支給する月からなので、例えば12月に支給するのであれば12月中に加入するということになります。
ただし、役員賞与だけの支給であっても、保険料の算出には「標準報酬月額」を使います。そのため、賞与を12分割して計算するようにしてください。
また、保険料の上限額は役員賞与にも適用されるので、上限額を超える場合は「事前確定届出給与に関する届出書」を提出しなければなりません。例えば、役員賞与が年間600万円の場合は、健康保険料であれば573万円、厚生年金保険料は150万円を上限額として計算するということも忘れないようにしましょう。
5-5. 社会保険料は定期的に見直される
社会保険料は毎年2月を基準に、標準月額報酬も定期的に見直しをおこなうため、社会保険料であれば3月分(4月納付分)から改定される場合があります。また、見直しだけでなく、下記の条件によって改定がおこなわれることもあるので、社会保険料を算出する場合は注意が必要です。
| 定時決定 | 毎年7月に実施される標準報酬月額の改定 |
| 資格取得時決定 | 社会保険の被保険者資格者になった段階でおこなわれる標準報酬月額の決定 |
| 随時改定 | 定時改定を待たずにおこなわれる標準報酬額の改定 |
| 育児休業等終了時改定 | 育児休業から復職した従業員に対する標準報酬月額の見直し |
社会保険料控除の額は、給与や賞与によって計算方法が異なるだけでなく、このように定期的もしくは不定期に見直し(改定)されることがあるので、担当者の方は随時確認をするようにしましょう。
6. 社会保険料の計算は給与計算システムが便利


社会保険料は、保険によって保険料率が異なります。また、毎年同じ保険料率ではない保険もあるので、控除額を算出する業務はかなりの負担になるでしょう。
また、控除額の算出をするだけでなく、計算ミスをしないようにするため、精神的な負担が大きいと感じる担当者もいるかもしれません。そのせいで、他の業務が滞ると仕事の効率も悪くなります。
このような状況を改善するには、給与計算システムを導入するのがベストです。給与計算システムには、賞与の計算機能が搭載されているものも多く、保険料を自動計算することが可能です。
また、法改正があった場合でも自動更新されるので、保険料率などを間違えることもありません。
コストはかかりますが、業務負担の大幅な軽減やミスをなくせるというメリットがあるので、導入を検討してみることをおすすめします。
7. 賞与の社会保険料を理解しミスなく支払いをおこなおう


賞与には、健康保険料や介護保険料、厚生年金保険料、雇用保険料などの社会保険料が課されます。賞与から控除される社会保険料は大きな金額になるため、従業員にはかなりの負担がかかります。
当然ですが、企業にも保険料負担がかかるので、正確な計算と処理をおこなうことは、事業主の重要な責任です。
控除額に誤りがあると、従業員からの信頼を損なうだけでなく、事業主にとっても信頼性や運営の透明性に影響を及ぼします。そのため、担当者の方は、賞与にかかる社会保険料の仕組みや計算方法に関して、正しく理解しておくことが重要です。
近年は、社会保険料の負担に対して敏感になっている従業員も増えているので、ミスなく対応することが大切です。
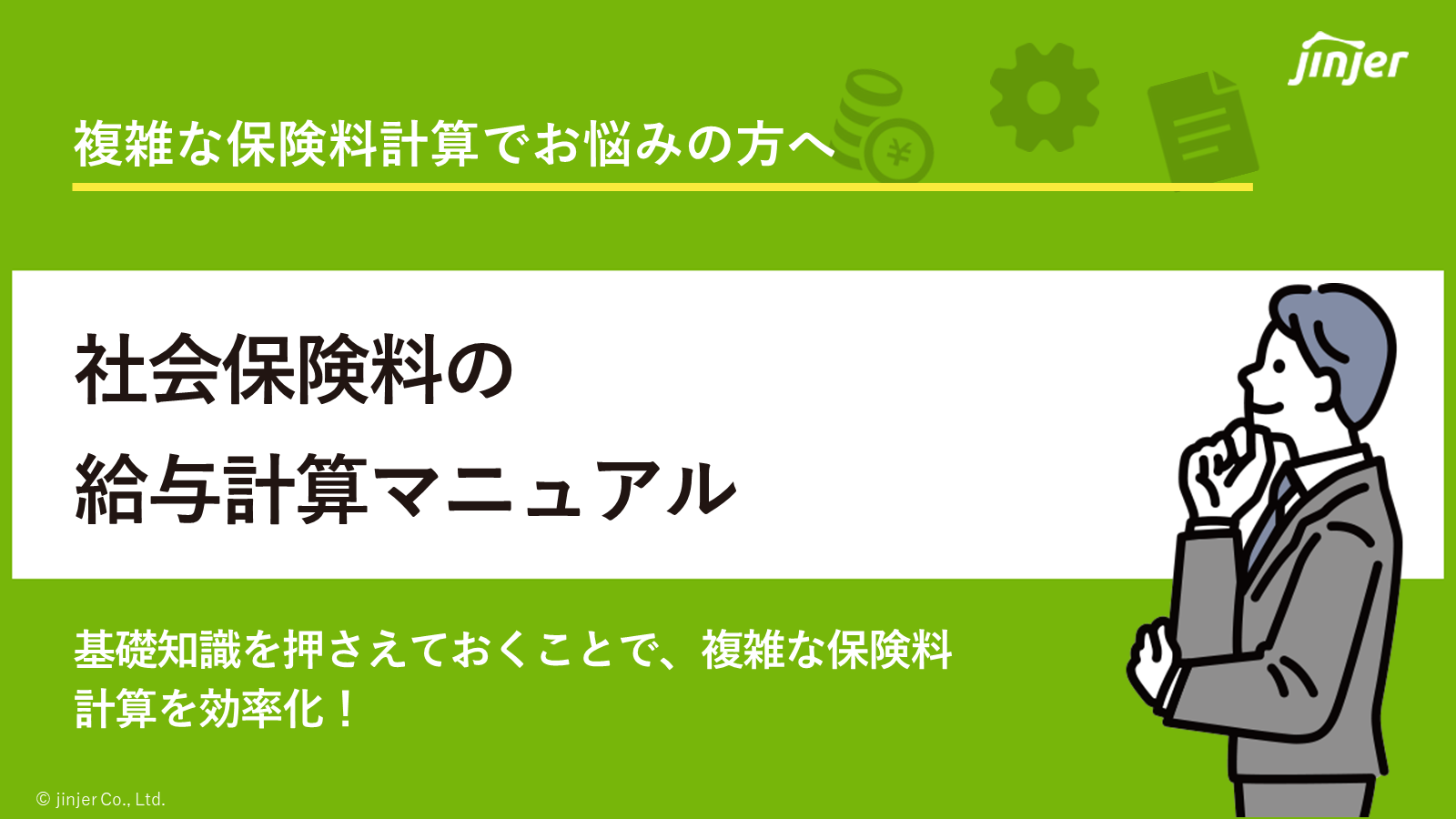
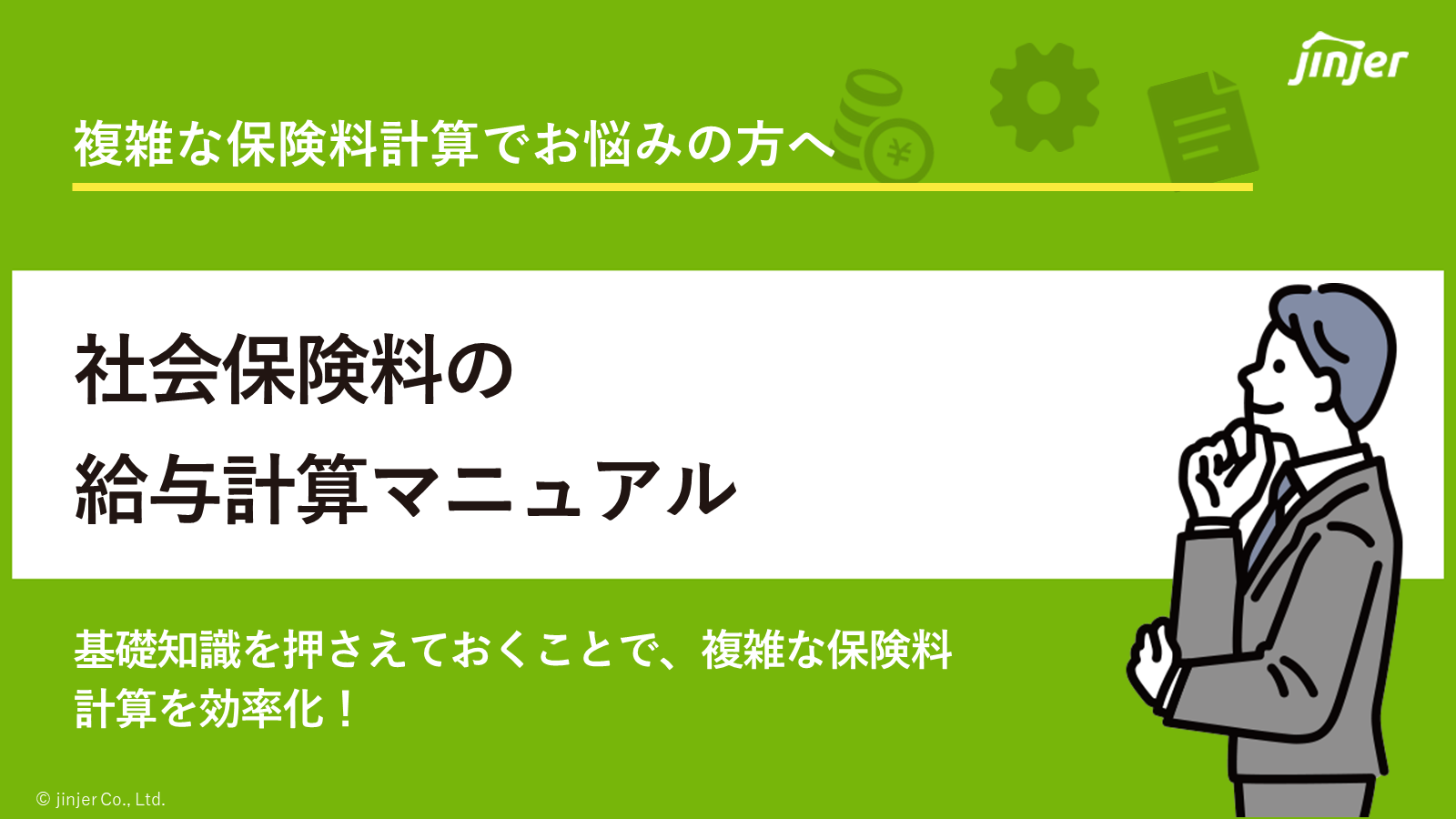
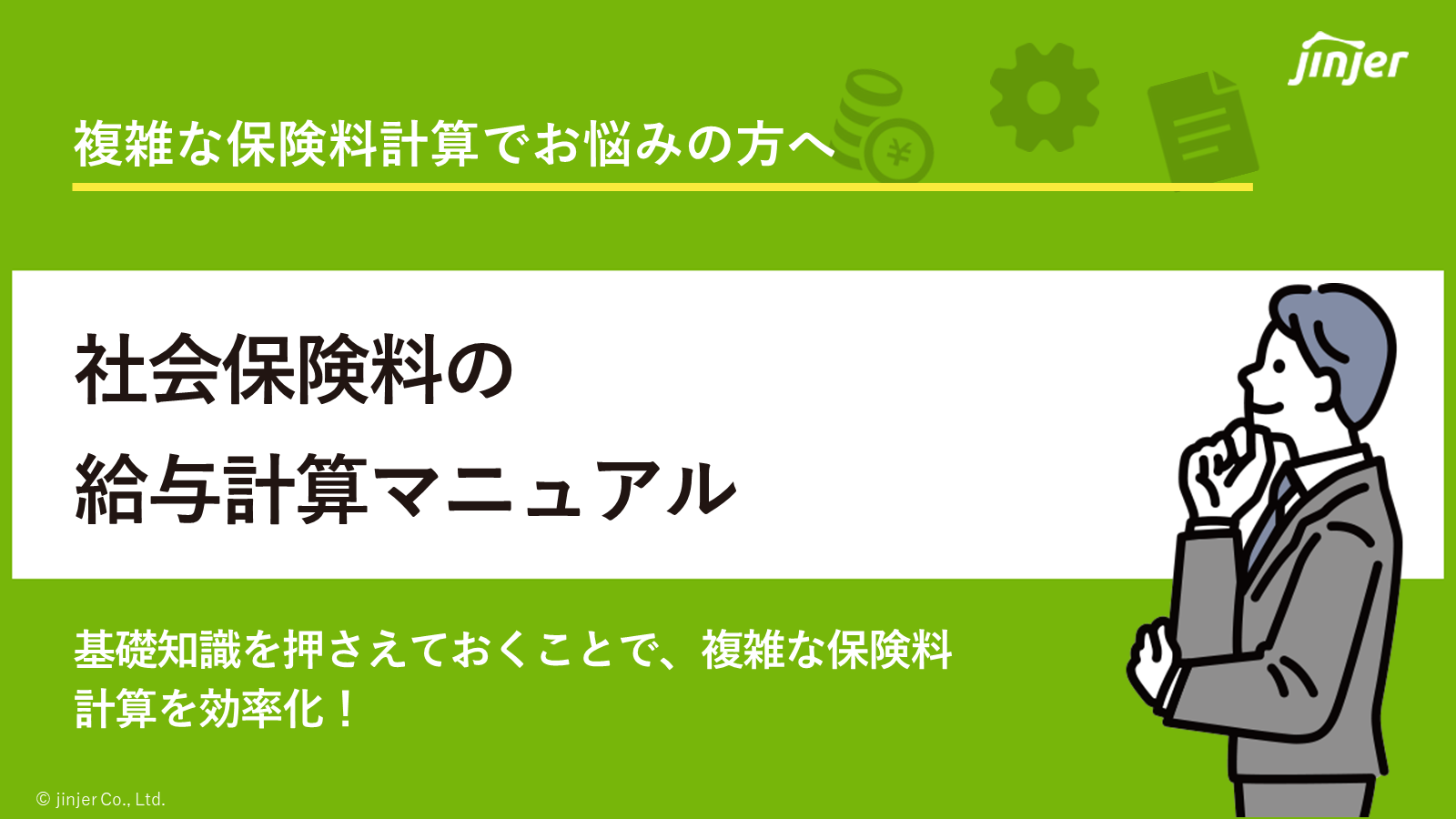
給与計算業務でミスが起きやすい社会保険料。保険料率の見直しが毎年あるため、更新をし損ねてしまうと支払いの過不足が生じ、従業員の信頼を損なうことにもつながります。
当サイトでは、社会保険4種類の概要や計算方法から、ミス低減と効率化が期待できる方法までを解説した資料を、無料で配布しております。
「保険料率変更の対応を自動化したい」「保険料の計算が合っているか不安」「給与計算をミスする不安から解放されたい」という担当の方は、ぜひこちらから資料をダウンロードしてご活用ください。
人事・労務管理のピックアップ
-


【採用担当者必読】入社手続きのフロー完全マニュアルを公開
人事・労務管理公開日:2020.12.09更新日:2026.01.30
-


人事総務担当がおこなう退職手続きの流れや注意すべきトラブルとは
人事・労務管理公開日:2022.03.12更新日:2025.09.25
-


雇用契約を更新しない場合の正当な理由とは?伝え方・通知方法も紹介!
人事・労務管理公開日:2020.11.18更新日:2025.10.09
-


社会保険適用拡大とは?2024年10月の法改正や今後の動向、50人以下の企業の対応を解説
人事・労務管理公開日:2022.04.14更新日:2025.10.09
-


健康保険厚生年金保険被保険者資格取得届とは?手続きの流れや注意点
人事・労務管理公開日:2022.01.17更新日:2025.11.21
-


同一労働同一賃金で中小企業が受ける影響や対応しない場合のリスクを解説
人事・労務管理公開日:2022.01.22更新日:2025.08.26





















