時差出勤の法律上のルールは?違法なケースや注意点を解説
更新日: 2025.2.23 公開日: 2025.2.23 jinjer Blog 編集部

「時差出勤の法律上のルールは?」
「時差出勤の導入手順は?」
働き方の多様化が進むなか、時差出勤を検討している企業も多いのではないでしょうか。柔軟な働き方が求められる現代において、時差出勤は従業員のニーズに応える方法の一つとして注目されています。
企業が時差出勤を導入する際は、法令違反にならないようルールを守りながら適切に運用しなければなりません。
本記事では、時差出勤の法律上のルールや違法になるケース、導入手順を解説します。時差出勤を効率的に取り入れて、柔軟な働き方を実現させましょう。

人事労務担当者の実務の中で、従業員情報の管理は入退社をはじめスムーズな情報の回収・更新が求められる一方で、管理する書類が多くミスや抜け漏れが発生しやすい業務です。
さらに、人事異動の履歴や評価・査定結果をはじめ、管理すべき従業員情報は多岐に渡り、管理方法とメンテナンスの工数にお困りの担当者の方もいらっしゃるのではないでしょうか。
そんな人事労務担当者の方には、Excel・紙管理から脱却し定型業務を自動化できるシステムの導入がおすすめです。
◆解決できること
- 入社手続きがオンラインで完結し、差し戻し等やりとりにかかる時間を削減できる
- システム上で年末調整の書類提出ができ、提出漏れや確認にかかる工数を削減できる
- 入社から退職まで人事情報がひとつにまとまり、紙やExcel・別システムで複数管理する必要がなくなる
システムを利用したペーパーレス化に興味のある方は、ぜひこちらから資料をダウンロードの上、業務改善にお役立てください。
1. 時差出勤の法律上のルール


時差出勤に関連する法律上のルールとして、労働基準法などで明確な規定はありません。ただし、以下の2つのポイントを押さえておく必要があります。
- 男女雇用機会均等法第13条の遵守
- 就業規則の改定と従業員への周知
男女雇用均等法の第13条では、妊娠中および出産後の女性が保健指導や健康診査を受けられるよう、勤務時間の変更や勤務の軽減などの必要な措置を講じることを定めています。
また、企業が新たに時差出勤を導入する際は、労働条件が変更されるため、就業規則に明記して従業員に周知しなければなりません。
時差出勤は、ルールを守り、適切に運用することで従業員のニーズに柔軟に対応できます。従業員のワークライフバランスの充実につながるため、離職率の低下や休職の防止につながるでしょう。
なお、時差出勤は従業員が自由に就業時間を決められるわけではありません。企業が提示したいくつかの勤務パターンのなかから、従業員が選択することが一般的です。
参考:雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律 | e-Gov 法令検索
2. 時差出勤が違法になるケース


時差出勤が違法とみなされるケースは、以下のとおりです。
- 労働基準法に違反する場合
- 企業が一方的に導入した場合
2-1. 労働基準法に違反する場合
労働基準法に違反する場合、違法とみなされます。労働基準法違反の例は以下のとおりです。
| 労働基準違反の例 | 詳細 |
| 法定労働時間を超過している | 1日8時間、1週間40時間を超える労働をさせる(36協定を締結していない場合) |
| 休憩時間を与えない | 労働時間が6時間を超える場合45分、8時間を超える場合1時間の休憩時間を与えていない |
| 休日を与えない | 週に1回以上の休日を与えていない |
| 残業代や深夜割増賃金の未払い | 該当者に所定の割増賃金を支払わない |
一般的に時差出勤は、始業・終業の時間の変更のみで、1日の労働時間が変わるわけではありません。時差出勤を取り入れた際は、従業員一人ひとりの勤務時間が変わるため、就労時間をしっかり管理することが求められます。
2-2. 企業が一方的に導入した場合
従業員の合意を得ずに、企業が一方的に時差出勤を取り入れた場合も違法となる可能性があります。労働契約法第9条で、変更内容が従業員にとって不利益となる場合は従業員の合意が必要であると規定されているためです。
始業・終業時間は、雇用契約の内容に含まれているため、従業員の合意なしに雇用契約の変更はできません。
時差出勤を導入する目的や重要性を、明確かつ合理的に説明できれば、従業員の合意を得やすくなるでしょう。
3. 時差出勤を適法に導入する手順
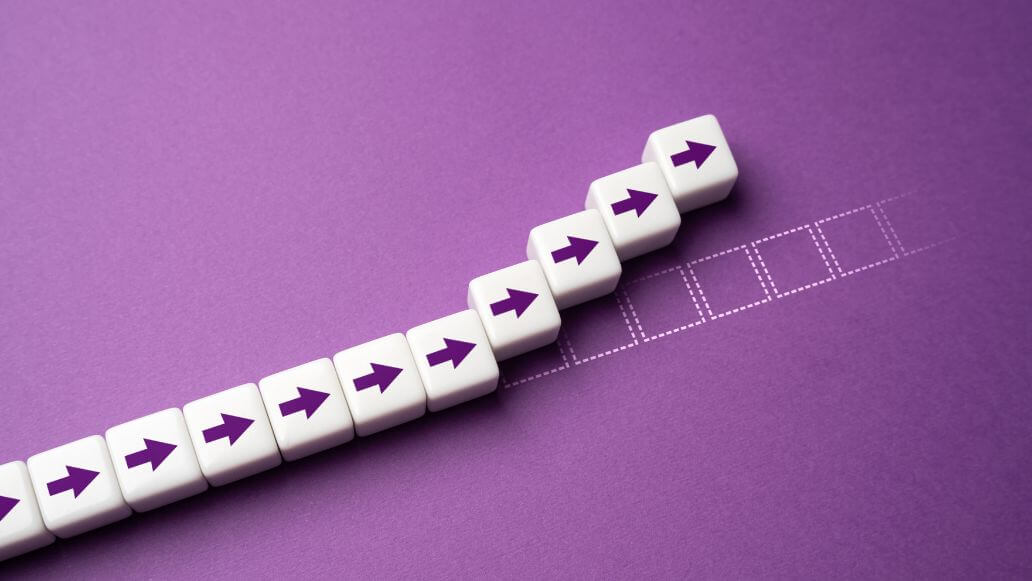
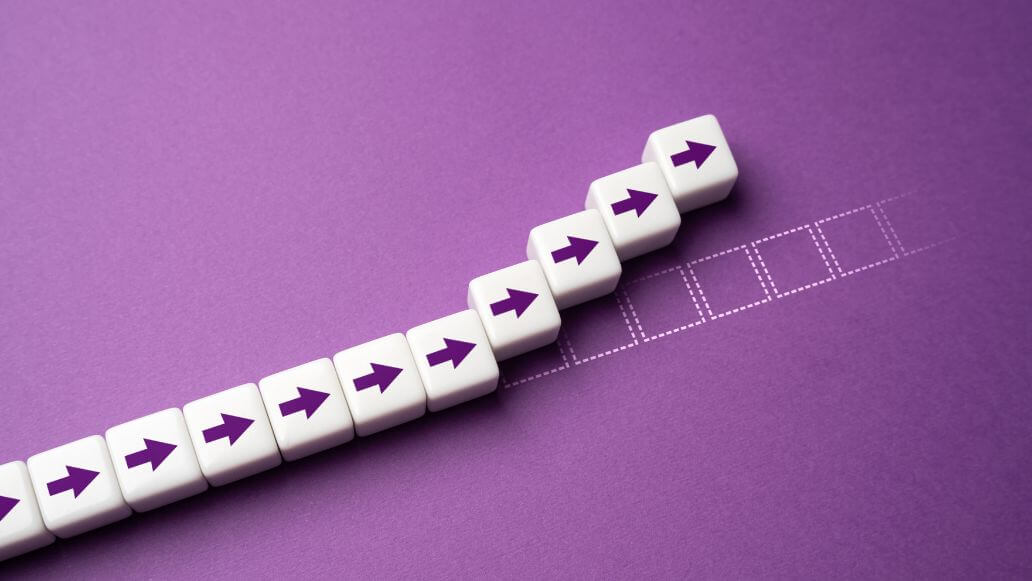
時差出勤を適法に導入する手順は、以下のとおりです。
- 導入目的の明確化
- 制度内容の決定
- 就業規則の改定
- 休憩時間に関する労使協定の締結
- 従業員への周知
- 試用期間の導入
3-1. 導入目的の明確化
まず、時差出勤を導入する目的を明確にしましょう。以下の観点から、時差出勤の必要性を洗い出します。
- 通勤ラッシュによる従業員のストレスの緩和
- 従業員のワークライフバランスの充実
- 企業全体の業務パフォーマンスの向上
時差出勤を導入する際は、必ずしもすべての従業員を対象にする必要はありません。とはいえ、従業員のニーズを考慮しながら現状を分析することは、目的を明確化するうえで重要なフェーズです。
社内アンケートなどを実施し、従業員の意見を直接取り入れてもよいでしょう。
3-2. 制度内容の決定
目的を明確にしたら、具体的な制度内容を決定します。主に、以下の項目を検討しましょう。
- 対象者の決定
- 始業・終業時間のパターン
- 申請・承認方法
- 勤怠の管理方法
一般的に時差出勤は、所定労働時間の変更はされません。制度内容を決定する際は、法定労働時間を守ることを念頭に置いておくことが重要です。
対象者のニーズを考慮しながら、いくつかの始業・終業時間を設定しておくとよいでしょう。
3-3. 就業規則の改定
すべての項目を決定したら、就業規則を改定します。始業・終業時間は、就業規則の絶対的必要記載事項と定められているため、変更手続きをしなければなりません。
9時~18時、10時~19時など勤務パターンが複数ある場合は、すべてを記載する必要があります。
3-4. 休憩時間に関する労使協定の締結
就業規則を改定したら、休憩時間に関する労使協定の締結を結び直します。休憩時間は、事業場単位で一斉に与えることが労働基準法第34条で定められているためです。
労使協定を再締結する場合、労働基準監督署への届出は必要ありません。なお、時差出勤を導入しても一斉休憩を与えられる場合は、労使協定の再締結は不要です。
3-5. 従業員への周知
時差出勤制度を円滑に運用するために、導入したことをすべての従業員に周知します。従業員に周知する際は、変更した就業規則をいつでも見られる状態にしておくことが重要です。
申請方法などを説明するために、すべての従業員を対象に説明会の開催を検討してもよいでしょう。
3-6. 試用期間の導入
試用期間は必須ではありませんが、時差出勤を本格導入する前に設けることを推奨します。試用期間は、主に以下の点を確認しておきましょう。
- 従業員同士のコミュニケーション不足はないか
- 勤怠システムに問題はないか
- 適切な労働時間が守られているか
- 従業員の利用状況はどのくらいか
特に、異なる時間に出勤することで従業員同士の情報共有が難しくなり、コミュニケーション不足に陥るケースがあります。オンラインツールの活用や、定期的なミーティングの主催など、必要に応じて調整をおこないましょう。
4. 時差出勤を導入する際の注意点


時差出勤を導入する際の注意点は、以下のとおりです。
- 実務労働時間の把握
- 従業員の体調面の配慮
4-1. 実務労働時間の把握
時差出勤を導入した際は、従業員一人ひとりの実務労働時間を正確に把握しなければなりません。時差出勤は、従業員ごとに始業・終業時間が異なり、労働時間の管理が煩雑になるためです。
例として、勤務時間が変わったことにより深夜割増賃金が発生する可能性があります。深夜割増賃金は、22時から5時の間に就労した従業員に支払う賃金で、割増率は25%以上です。該当する時間に労働した従業員には、深夜割増賃金を支払わなければなりません。
企業は、管理を徹底するため勤怠管理システムを導入するなど、勤怠記録や給与計算のミスを防止するための体制を整える必要があります。
4-2. 従業員の体調面の配慮
企業は、時差出勤に慣れるまで従業員の体調面に配慮する必要があります。生活リズムが変わることで、体調を崩す可能性があるためです。
生活リズムの崩れは、身体の健康だけではなく、精神面にも影響します。心身の体調を崩せば、業務効率が悪化する可能性も考えられるでしょう。
企業には、従業員の健康や安全を守る安全配慮義務があります。時差出勤の導入によって従業員が不調に陥った場合、企業の安全配慮義務違反とみなされる可能性があるため、従業員への配慮が不可欠です。
5. 時差出勤を取り入れて柔軟な働き方を実現させよう


時差出勤は、従業員のワークライフバランスを向上させ、柔軟な働き方を実現できる一つの手段です。企業にとっても、従業員の生産性向上や離職率低下などのメリットがあります。
しかし、適切に運用しなければ法的リスクを伴う可能性があるため、導入する際は必要な段階を踏まなければなりません。また、従業員の意見を反映したり、勤怠管理システムを導入したりと、想定されるトラブルを防ぐための工夫が必要です。
時差出勤を効果的に取り入れ、柔軟な働き方を実現させましょう。



人事労務担当者の実務の中で、従業員情報の管理は入退社をはじめスムーズな情報の回収・更新が求められる一方で、管理する書類が多くミスや抜け漏れが発生しやすい業務です。
さらに、人事異動の履歴や評価・査定結果をはじめ、管理すべき従業員情報は多岐に渡り、管理方法とメンテナンスの工数にお困りの担当者の方もいらっしゃるのではないでしょうか。
そんな人事労務担当者の方には、Excel・紙管理から脱却し定型業務を自動化できるシステムの導入がおすすめです。
◆解決できること
- 入社手続きがオンラインで完結し、差し戻し等やりとりにかかる時間を削減できる
- システム上で年末調整の書類提出ができ、提出漏れや確認にかかる工数を削減できる
- 入社から退職まで人事情報がひとつにまとまり、紙やExcel・別システムで複数管理する必要がなくなる
システムを利用したペーパーレス化に興味のある方は、ぜひこちらから資料をダウンロードの上、業務改善にお役立てください。
人事・労務管理のピックアップ
-


【採用担当者必読】入社手続きのフロー完全マニュアルを公開
人事・労務管理公開日:2020.12.09更新日:2026.01.30
-


人事総務担当がおこなう退職手続きの流れや注意すべきトラブルとは
人事・労務管理公開日:2022.03.12更新日:2025.09.25
-


雇用契約を更新しない場合の正当な理由とは?伝え方・通知方法も紹介!
人事・労務管理公開日:2020.11.18更新日:2025.10.09
-


社会保険適用拡大とは?2024年10月の法改正や今後の動向、50人以下の企業の対応を解説
人事・労務管理公開日:2022.04.14更新日:2025.10.09
-


健康保険厚生年金保険被保険者資格取得届とは?手続きの流れや注意点
人事・労務管理公開日:2022.01.17更新日:2025.11.21
-


同一労働同一賃金で中小企業が受ける影響や対応しない場合のリスクを解説
人事・労務管理公開日:2022.01.22更新日:2025.08.26






















