ストレス耐性とは?6つの要素・低い人や高い人の特徴・高める方法を解説
更新日: 2025.9.8 公開日: 2025.3.26 jinjer Blog 編集部

ストレス耐性とは、各人が備えるストレスに耐えるための強さのことです。
本記事では、ストレス耐性の概要や6要素、ストレス耐性診断・テストの概要やストレス耐性の低い人・高い人の主な特徴について解説しています。
従業員のストレス耐性を企業が高める方法やストレス耐性を採用面接で見定める企業が増加中であることも解説しているため、ぜひ参考にしてください。

従業員の定着率の低さが課題の企業の場合、考えられる要因のひとつに従業員満足度の低さがあげられます。
従業員満足度を向上させることで、従業員の定着率向上や働くモチベーションを上げることにもつながります。
しかし、従業員満足度をどのように測定すれば良いのか、従業員満足度を知った後どのような活用をすべきなのかわからないという人事担当者様もいらっしゃるのではないでしょうか。
そのような方に向けて当サイトでは、「従業員満足度のハンドブック」を無料でお配りしています。
従業員満足度調査の方法や調査ツール、調査結果の活用方法まで解説しているので、従業員のモチベーション向上や社内制度の改善を図りたい方は、ぜひこちらから資料をダウンロードしてご活用ください。
1. ストレス耐性とは


ストレス耐性とは、一人ひとりが備えているストレスに耐える強さのことです。生まれつきの要因と、経験や環境によって培われる要因から成り立っています。同じストレスを受けても、耐えられる程度は人それぞれです。したがって、ストレス耐性が高い人、低い人が存在します。
会社にストレス耐性が高い従業員が多いと、生産性や定着率、組織としての一体感の向上が期待できます。ストレス耐性は鍛えることが可能です。調査やテストで多くの従業員のストレス耐性が低いとわかった場合は、組織全体で対策を検討し、研修や職場環境の改善などを実施することで、社員全体のパフォーマンス向上と健康維持につなげることができます。
2. ストレス耐性の6要素


- 感知能力
- 回避能力
- 処理能力
- 転換能力
- 経験
- 容量
各要素について詳しく見ていきましょう。
2-1. 感知能力
ストレス耐性の6要素の一つは、感知能力です。ストレスの原因(ストレッサー)を感じ取る能力を指します。
例えば、感知能力の高い人は上司や同僚の機嫌が悪いことに気づきやすいため、険悪な雰囲気や態度からストレスを感じるでしょう。また、機嫌が悪い原因が自分にあるのではないかと考え、ストレスを強める場合もあります。
一方、感知能力の低い人は、そもそも他人の不機嫌に気づかなかったり、意に介さなかったりするため、ストレスを感じにくいです。
周囲によく気がつく繊細な性格の人ほど、感知能力が高くストレスを感じやすいといえます。
2-2. 回避能力
回避能力も、ストレス耐性の6要素の一つです。ストレスを受ける状況や人物から距離を置き、ストレスを避ける能力のことを指します。
回避能力が高い人は人や物事へ過度な期待をせず、考えや行動に個人的な感情を交えない人が多いです。
一方で回避能力が低い人は、原因を避けることが難しいためストレスを受けやすいでしょう。
2-3. 処理能力
ストレス耐性の6要素の一つには、処理能力もあります。ストレスの原因をなくす・減らす能力のことです。
例えば、仕事量の多さがストレス原因の場合は、効率的な方法を見つけ出したり無駄な業務を見つけて省略したりする能力を指します。
処理能力が高い人は、問題解決能力が高いためストレスを受けにくく溜め込むこともないでしょう。
一方、処理能力が低い人は原因を取り除けないため、ストレスを受けがちで溜め込みやすいです。
2-4. 転換能力
転換能力も、ストレス耐性の6要素の一つに挙げられます。ストレス原因になりうる状況に対して、前向きにとらえたり楽観的に見たりする能力のことです。
転換能力が高い人は、失敗に対して貴重な学びだったと考えたり、失礼な態度に接して自分の悪い態度の予防に役立ったと考えたりします。
一方で転換能力が低い人は、失敗を引きずったり物事をネガティブにとらえたりしがちであるため、ストレスを抱えやすいでしょう。
2-5. 経験
ストレス耐性の6要素の一つは、経験です。内容・頻度・対処方法・反省点など、過去に受けたストレスに関する経験全般を指します。
同じストレスを何度も受けて都度対応していると、次第にストレスを感じにくくなりがちです。
例えば、初期においてはストレスを感じていた業務の遂行について見ていきましょう。業務を何度かこなすうちに、慣れによりストレスを感じることなく処理できるようになります。
一般的には、経験が多いとストレスに強く、少ないと弱いです。ただし、同じストレスの経験が多い場合でも、慣れずにストレスが強まるケースもあります。
2-6. 容量
容量も、ストレス耐性の6要素の一つです。各人が抱えられるストレスの総量を指します。
一般的に、容量が小さい人はストレスを感じやすく、ストレスによる心身への悪影響も生じやすいです。
一方、容量が大きい人は一般的にストレスを感じにくく、容量が小さい人に比べてストレスによる心身への悪影響も生じにくいでしょう。
3. ストレス耐性診断・テストとは
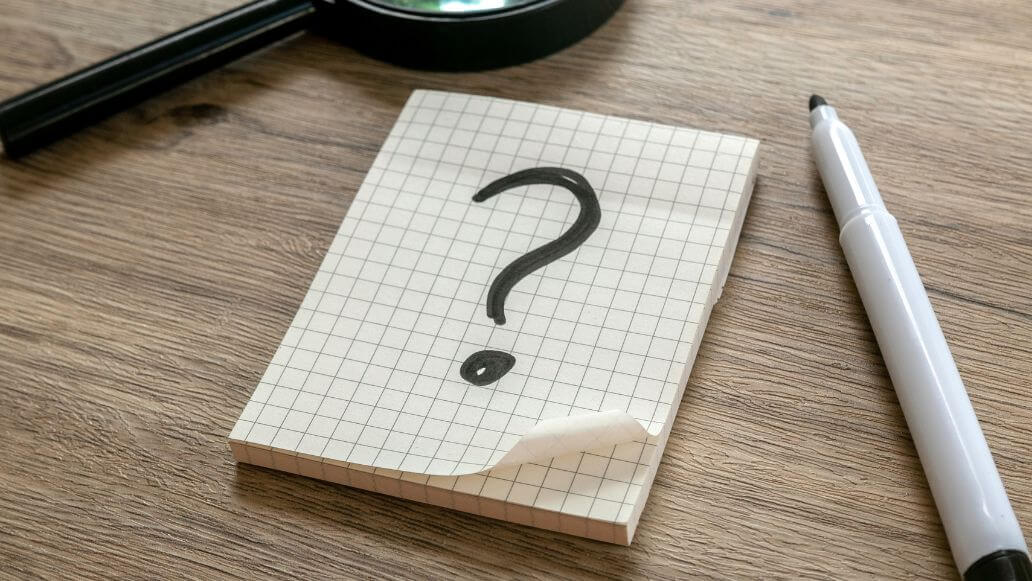
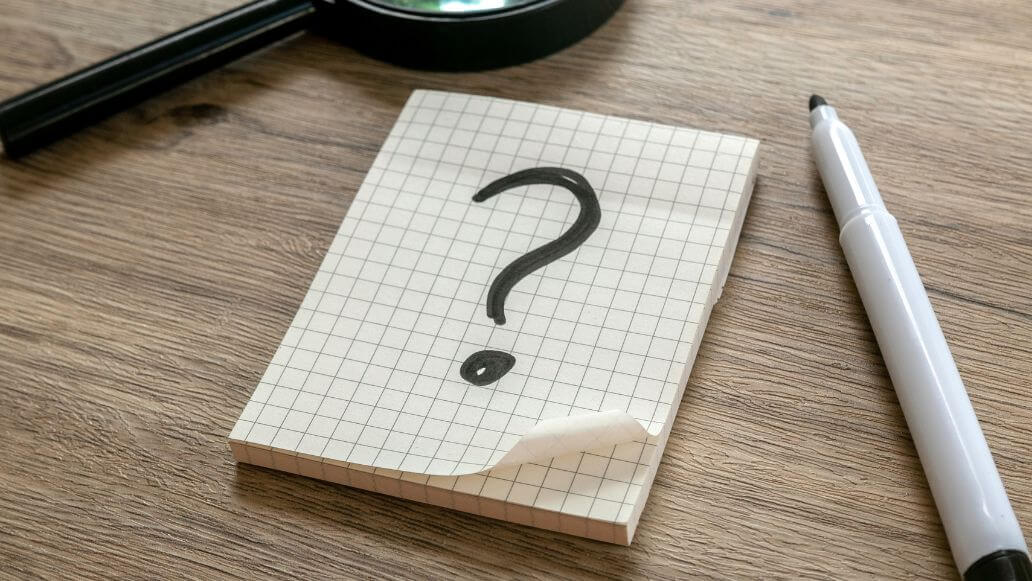
| 目的 | 回答者がストレスを受けやすい人物かどうかを判断すること |
| 回答形式 | 質問回答方式 |
| 評価方法 | 質問への回答内容を数値化し、各人のストレス耐性について評価する |
| 診断方式 |
|
| 設問数 | 100問程度 |
| 所要時間 | 10分程度 |
| 一般的な実施場面 |
|
| 一般的な調査内容 |
|
また、各人がストレスを解消する際の特徴から、各人の行動・判断の根本となる考え方や傾向などについても調べられます。
4. ストレス耐性が低い人の主な特徴


- 責任感が強い
- 完璧主義
- 周囲に合わせる
- 気持ちの切り替えが苦手
それぞれの特徴について解説します。
4-1. 責任感が強い
ストレス耐性が低い人は、責任感が非常に強いことがあります。自分の仕事や役割に対して過度な責任を感じるあまり、プレッシャーを過剰に受けてしまいます。責任感が強いこと自体は良い点でもありますが、それが過度になると、完璧を求めるあまり失敗を恐れ、ストレスが増加しかねません。
4-2. 完璧主義
完璧主義はストレス耐性が低い人に見られる特徴のひとつです。完璧を追い求めるあまり、些細なミスでも自分を責めたり、他人に対して厳しい評価を下すことが多くなります。完璧主義者は「完璧でないと失敗だ」と感じ、常に高い基準を自分に課すため、少しでも期待に応えられなかった場合に大きなストレスを感じてしまうでしょう。
4-3. 周囲に合わせる
ストレス耐性が低い人は、周囲に合わせることに過剰に意識を向けるケースがあります。他人の期待に応えようとするあまり、自分の意見や感情を抑え込むことが多くなるでしょう。人間関係を円滑に保つために自分を犠牲にすることで、後々そのストレスが蓄積し、精神的な負担になりかねません。
4-4. 気持ちの切り替えが苦手
気持ちの切り替えが苦手な人は、過去の失敗やトラブルを引きずりがちです。仕事でミスをしたり、予期しないトラブルが発生したりすると、そのことを長時間引きずってしまいます。一度感じたストレスや不安を引きずることで、次の仕事に対する意欲や集中力が欠けてしまうでしょう。
5. ストレス耐性が高い人の主な特徴


- 自己肯定感が高い
- 自分の価値観がはっきりしている
- ポジティブ
- 集中力がある
それぞれの特徴について解説します。
5-1. 自己肯定感が高い
ストレス耐性が高い人は、自己肯定感が高い傾向があります。自己肯定感とは、自分の価値や能力を適切に認識し、自信を持つことです。自己肯定感が高い人は、困難な状況に直面しても、自分の力で問題を解決できると感じることができ、ストレスを感じることなく冷静に対処することができるでしょう。自己肯定感を高めるためには、日々の小さな成功を積み重ね、自分を肯定する習慣作りがポイントです。
5-2. 自分の価値観がはっきりしている
ストレス耐性が高い人は、自分の価値観が明確であり、物事の優先順位をしっかりとつけることができます。自分にとって何が重要であるかを理解しているため、他人の期待や社会的なプレッシャーに左右されることなく、自分の道を進んでいけるでしょう。このような人は、仕事やプライベートで直面する困難に対しても、自分の価値観に基づいて判断し、柔軟に対応します。
5-3. ポジティブ
ポジティブな思考を持つことは、ストレス耐性を高めるために非常に重要です。ストレス耐性が高い人は、困難な状況や予期しない問題が発生したときでも、前向きに捉え、解決策を見出すことができます。ポジティブな思考は、ストレスを軽減するだけでなく、問題解決能力を高める効果も期待できます。
5-4. 集中力がある
ストレス耐性が高い人は、高い集中力を持っています。集中力が高いと、目の前の課題に集中でき、他のことに気を取られることが少なくなります。その結果、仕事の効率が上がり、ストレスの原因となる時間のプレッシャーや未解決の問題が減少するでしょう。集中力を高めるためには、環境を整えることや、優先順位をつけて計画的に行動することが効果的です。
6. 従業員のストレス耐性を高める


- ストレスの考え方を改める
- ストレスコーピングを試してみる
6-1. ストレスの考え方を改める
ストレス耐性を高めるためには、ストレスそのものに対する考え方を見直すことが重要です。多くの人がストレスを「悪いもの」として捉えがちですが、ストレスを適切に管理することで、逆に自己成長や問題解決のための原動力にすることができます。まずは、ストレスが必ずしも悪いものではなく、避けられないものであることを理解しましょう。
6-2. ストレスコーピングを試してみる方法
ストレスコーピングとは、ストレスに対して適切に対処するための方法を指します。従業員のストレス耐性を高めるためには、ストレスコーピング技術を向上させることが効果的です。具体的には、以下の方法が挙げられます。
- リラクゼーション法の活用
- タイムマネジメントのスキル向上
- 感情のコントロール技術
7. 企業のストレス耐性を高める方法


企業のストレス耐性を高めるためには、従業員個々のストレス耐性をサポートするだけでなく、組織全体の環境を整えることも必要です。企業文化や働き方を改善することで、全体としてストレス耐性を強化することができます。企業のストレス耐性を高める方法は次のとおりです。
- ワークライフバランスを整える
- 1on1でコミュニケーションを促進させる
7-1. ワークライフバランスを整える
ワークライフバランスを整えることは、企業のストレス耐性を高めるための基本です。過度な労働時間や不規則な働き方は、従業員のストレスを増加させる原因となります。企業は、従業員が十分に休息を取れるよう、柔軟な勤務時間や休暇制度の導入が重要です。適切なワークライフバランスを維持することで、従業員は精神的にも身体的にも健康を保ち、仕事のパフォーマンスを向上させることができます。
7-2. 1on1でコミュニケーションを促進させる
定期的な1on1のミーティングは、従業員のストレス耐性を高めるために有効な手段です。上司と従業員が直接コミュニケーションを取ることで、業務に関する不安やストレスを早期に把握し、解消可能です。また、1on1は従業員が自分の意見を安心して話せる場を提供するため、心理的安全性を高め、ストレス耐性の向上にもつながります。
8. ストレス耐性が低い・高いを採用面接で見定める企業も増加中


近年、応募者のストレス耐性を採用面接で見極める企業が増加しています。これは、ストレス耐性が高い人が、前向きで主体性があり、高い定着率を示す傾向にあるためです。一方、ストレス耐性が低い人は、メンタルヘルス不調による休職や離職のリスクにつながる可能性があるため注意が必要です。
面接では、過去に経験した困難な出来事や、それをどのように乗り越えたかについて質問することで、応募者の考え方や行動特性を探ります。また、採用選考の一環としてストレス耐性診断や適性テストを導入する企業も増加しており、客観的なデータに基づいた判断を重視する傾向にあります。これにより、入社後のミスマッチを防ぎ、社員の定着率向上を目指せるでしょう。
9. ストレス耐性について理解を深めよう


近年、採用応募者や従業員のストレス耐性を見定めるために、ストレス耐性診断を実施する企業も増えています。
ストレス耐性が高い従業員が多い場合、生産性や定着率、組織としての一体感の向上などが期待できるためです。
なお、さまざまな取り組みにより、従業員のストレス耐性を鍛えることもできます。具体的にはストレスの考え方を改める、ストレスコーピングを試してみるなどに取り組むことで、従業員のストレス耐性向上が期待できます。さらに、ワークライフバランスを整える、1on1でコミュニケーションの促進で企業のストレス耐性を高められるでしょう。
ストレス耐性に対する理解を深めつつ、従業員のストレス耐性を組織的な取り組みにより高めていきましょう。



従業員の定着率の低さが課題の企業の場合、考えられる要因のひとつに従業員満足度の低さがあげられます。
従業員満足度を向上させることで、従業員の定着率向上や働くモチベーションを上げることにもつながります。
しかし、従業員満足度をどのように測定すれば良いのか、従業員満足度を知った後どのような活用をすべきなのかわからないという人事担当者様もいらっしゃるのではないでしょうか。
そのような方に向けて当サイトでは、「従業員満足度のハンドブック」を無料でお配りしています。
従業員満足度調査の方法や調査ツール、調査結果の活用方法まで解説しているので、従業員のモチベーション向上や社内制度の改善を図りたい方は、ぜひこちらから資料をダウンロードしてご活用ください。
人事・労務管理のピックアップ
-


【採用担当者必読】入社手続きのフロー完全マニュアルを公開
人事・労務管理公開日:2020.12.09更新日:2026.01.30
-


人事総務担当がおこなう退職手続きの流れや注意すべきトラブルとは
人事・労務管理公開日:2022.03.12更新日:2025.09.25
-


雇用契約を更新しない場合の正当な理由とは?伝え方・通知方法も紹介!
人事・労務管理公開日:2020.11.18更新日:2025.10.09
-


社会保険適用拡大とは?2024年10月の法改正や今後の動向、50人以下の企業の対応を解説
人事・労務管理公開日:2022.04.14更新日:2025.10.09
-


健康保険厚生年金保険被保険者資格取得届とは?手続きの流れや注意点
人事・労務管理公開日:2022.01.17更新日:2025.11.21
-


同一労働同一賃金で中小企業が受ける影響や対応しない場合のリスクを解説
人事・労務管理公開日:2022.01.22更新日:2025.08.26
タレントマネジメントの関連記事
-



プレゼンティーイズムとは?原因と企業に与える損失額・対策をわかりやすく解説
人事・労務管理公開日:2026.01.19更新日:2026.01.19
-



メンタルヘルスサーベイとは?ほかのサーベイとの違い、実施の目的や流れを解説!
人事・労務管理公開日:2026.01.16更新日:2026.01.14
-


企業におけるメンタルヘルスケアとは?4つのケアや事例を紹介
人事・労務管理公開日:2025.11.18更新日:2025.12.19




















