ストレス耐性を高める方法は?重要性や低いリスクを解説
更新日: 2025.8.4 公開日: 2025.3.27 jinjer Blog 編集部
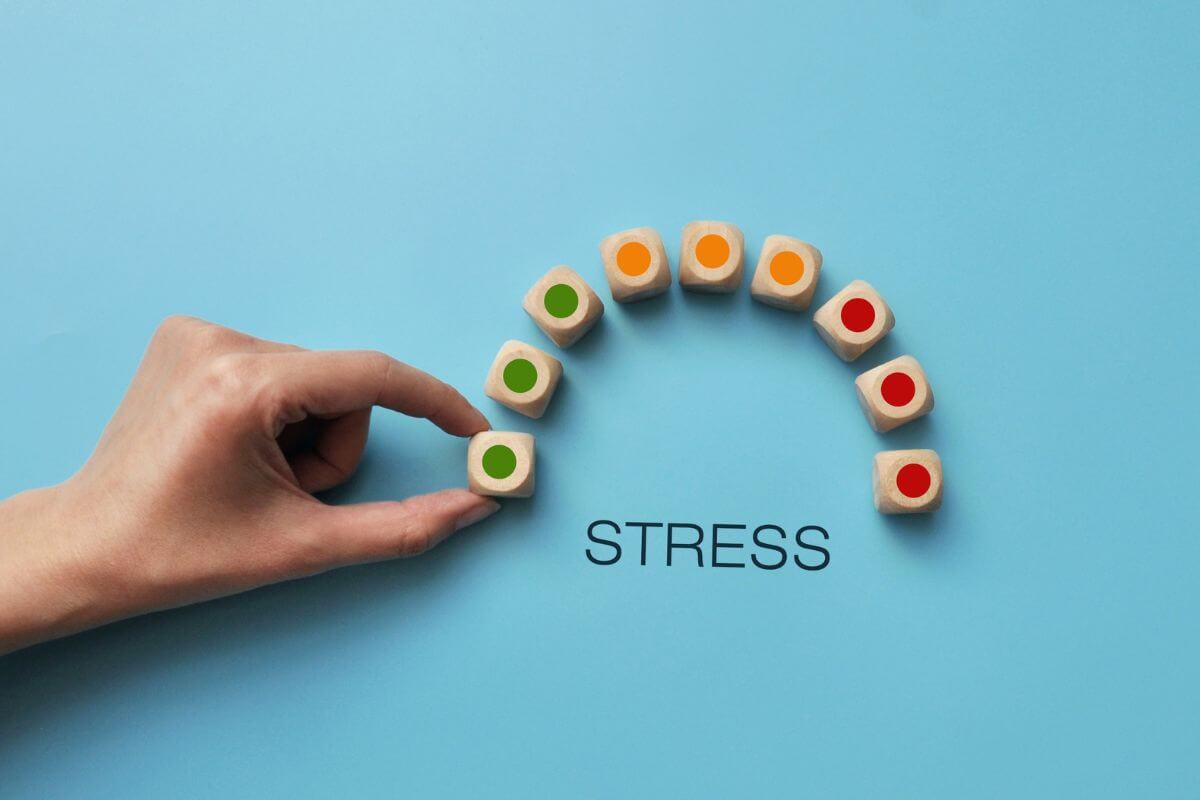
ストレス耐性とは、ストレスを凌ぐ力やストレスに適応する能力のことです。
ストレス耐性が低いと、業務効率の低下やメンタルヘルスの問題が発生しやすくなるため、企業側の対策は欠かせません。
本記事では、ストレス耐性を向上させる重要性や方法、低いことによる企業のリスクを解説します。従業員が安定したパフォーマンスを発揮できるよう、ストレス耐性を高めるための対策をおこないましょう。

従業員の定着率の低さが課題の企業の場合、考えられる要因のひとつに従業員満足度の低さがあげられます。
従業員満足度を向上させることで、従業員の定着率向上や働くモチベーションを上げることにもつながります。
しかし、従業員満足度をどのように測定すれば良いのか、従業員満足度を知った後どのような活用をすべきなのかわからないという人事担当者様もいらっしゃるのではないでしょうか。
そのような方に向けて当サイトでは、「従業員満足度のハンドブック」を無料でお配りしています。
従業員満足度調査の方法や調査ツール、調査結果の活用方法まで解説しているので、従業員のモチベーション向上や社内制度の改善を図りたい方は、ぜひこちらから資料をダウンロードしてご活用ください。
1. ストレス耐性を高める重要性


ストレス耐性を高めることは、従業員の心身の健康を維持し、組織全体のパフォーマンスを向上させるために重要です。従業員個々のストレス耐性の高さは、企業の生産性に直結します。
2022年度の厚生労働省の調査によると、職場において強いストレスや不安を抱えている人の割合は82.2%でした。人間関係やプレッシャー、環境の変化など、さまざまな要素がストレスの原因となっています。
メンタルヘルス対策を実施すると同時に、ストレス耐性を強化することは企業にとって重要な課題です。
ストレス耐性が高い従業員は、プレッシャーのかかる場面でも冷静に対応でき、安定した業務を遂行できます。
一方、ストレス耐性が低い従業員はプレッシャーに押しつぶされやすいため、業務効率の低下やメンタルヘルスの問題が発生しやすくなるでしょう。
従業員のストレス耐性を高めることは、長期的な組織の安定と成長に寄与します。
参考:厚生労働省 | 職場におけるメンタルヘルス対策等の現状
2. ストレスの要因となる4つの要素


ストレスの原因となる要素は次のとおりです。
- 物理的要因
- 化学的要因
- 生物的要因
- 心理的・社会的要因
2-1. 物理的要因
長時間労働や温度・照度の不適切さ、騒音や振動などの物理的な要因は体へ負荷をかけ、疲労を蓄積させます。例えばオフィスのエアコン温度が適切でない、照明の照度が低いなどはストレスにつながりかねません。物理的要因によるストレスは、勤怠データと環境センサーを連携し、作業計画と休憩の最適化につながります。
2-2. 化学的要因
化学的要因とは、化学物質が引き起こす刺激のことです。具体的には、以下のようなものが化学的要因です。
- 公害物質や特定の金属
- アルコールやタバコ
- 食品添加物
例えば、職場での喫煙や、匂いの強い食べ物の摂取なども、周囲の人にとっては化学的要因になります。
2-3. 生物的要因
生物的要因とは、生体の免疫反応の要因となる刺激で、具体的には、以下のようなものが挙げられます。
- 花粉
- ウイルスや細菌
- ダニ
生物的要因によるストレスを避けるには、花粉をオフィス内に持ち込ませないルールの整備や、エアコンフィルターの入念な清掃などが挙げられます。
2-4. 心理的・社会的要因
心理的・社会的要因は、人間が社会生活を営む中で生じるストレス要因を指します。具体的には次のようなケースです。
- 職場での人間関係
- 仕事の量や質
- 自身の社会的立場
一般的にストレスと呼ばれているのは、心理的・社会的要因を指します。
3. ストレス耐性を左右する6つの要素


ストレス耐性を左右する6つの要素は次のとおりです。
- キャパシティ
- 処理
- 経験
- 感知
- 回避
- 転換
3-1. キャパシティ
個人がどれだけのストレスを受け止められるかの許容量を指すのがキャパシティです。一般的に、キャパシティが大きい人は、より多くのストレス刺激を一度に受け止めることができるとされています。
キャパシティは、生まれつきの特性や、過去の経験、現在の心身の状態によって変動します。そのため、キャパシティが大きい人であっても、ストレス過多な状態が続くと、このストレス刺激の許容量が低下することもあります。
3-2. 処理
処理とはストレスを感じた際に、そのストレスに対してどのように対処するかという能力です。ストレス処理の能力は次のとおり多岐にわたります。
- ストレスの原因そのものを取り除く問題解決型
- ストレスに対する考え方を変える情動焦点型の対処
適切な処理能力を持つ従業員は、ストレス状況下でもパフォーマンスを維持しやすくなります。
3-3. 経験
経験は、過去のストレス体験を通じて得られた学習や知識を指します。過去にストレスを乗り越えた経験は、従業員にとって自信となり、新たなストレスに直面した際の乗り越える力となります。また、失敗体験から学び、次回の対処に活かすことも可能です。
3-4. 感知
ストレスの原因や状況をどのように捉えるかという認知の仕方を指すのが感知です。同じ状況に直面しても、ある人はそれを大きなストレスと感じ、別の人は成長の機会と捉えることがあります。
ストレスに対する感知は個人の価値観、信念、思考パターンに大きく左右されます。ストレスを早期に、そして客観的に感知できる能力は、適切な対処を早期に開始するうえで重要です。
3-5. 回避
回避とは、ストレスの原因となる状況や刺激を避けるもしくは距離を置く行動を指します。回避はネガティブな意味だけでなく、自分にとって過度な負担となる状況から身を守るための有効な手段となり得ます。
例えば、休憩を積極的にとる、人間関係の摩擦を避ける、業務量を適切に調整するなど、ストレスが蓄積する前の予防的な行動が回避です。
3-6. 転換
転換とは、ストレスによって生じた心身の不調や疲労を、ポジティブな状態に切り替える能力です。例えば趣味に没頭する、運動をする、十分な睡眠をとるなど、ストレスによって消費されたエネルギーを回復させる行動が含まれます。転換能力が高い従業員は、一時的にストレスを感じても、影響を抑えられる傾向にあります。
4. ストレス耐性を高める4つの方法
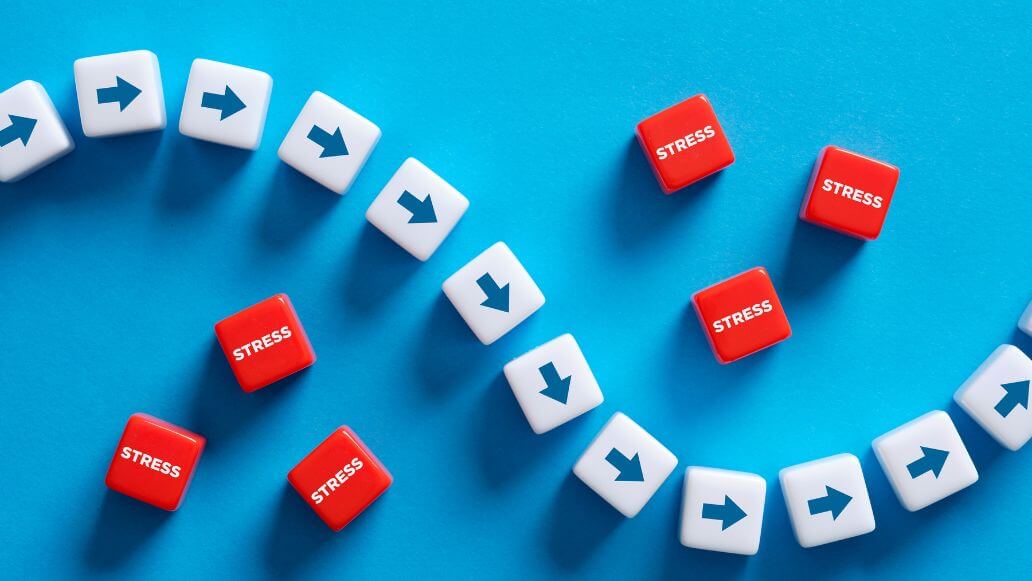
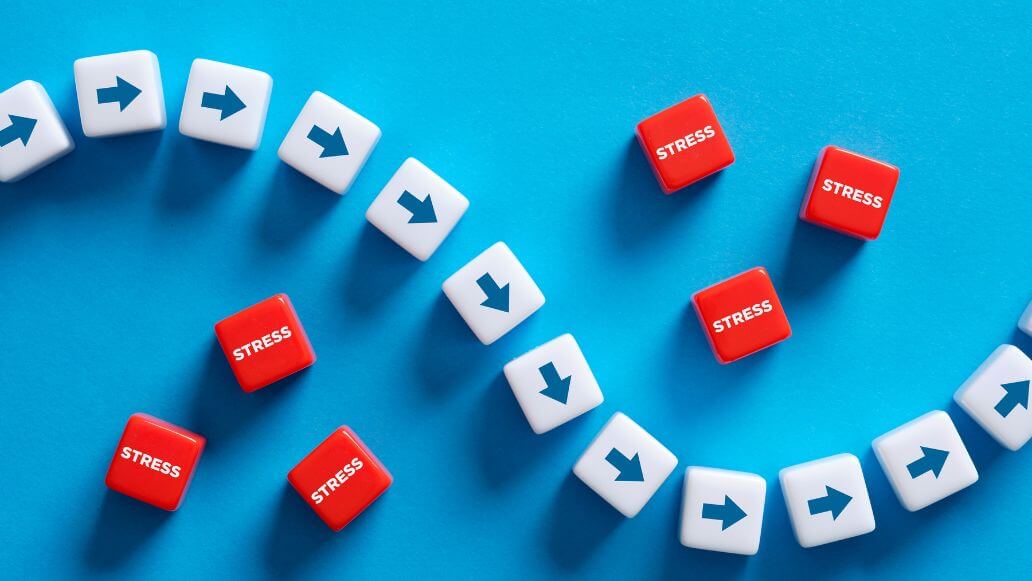
従業員のストレス耐性を高める方法は、以下のとおりです。
- 社内コミュニケーションの促進
- ワークライフバランスの促進
- メンタルヘルスのサポート体制の整備
- ABC理論の活用
4-1. 社内コミュニケーションの促進
社内コミュニケーションを促進することで、従業員のストレス耐性を高められます。社内のコミュニケーションが円滑になると、業務に関する問題点や不安点を共有しやすくなるためです。
円滑なコミュニケーションは、従業員同士の信頼関係を築きながら、ストレスの原因を早期発見するために役立ちます。
具体的には、以下のような取り組みを実施するとよいでしょう。
- 定期的な1on1ミーティング
- オープンな意見交換の場の提供
- 社内SNSの導入
従業員同士の円滑なコミュニケーションは、生産性の向上にもつながります。
4-2. ワークライフバランスの促進
従業員のワークライフバランスを促進することも、ストレス耐性を高めるために役立ちます。
休養をしっかり与え、従業員の心身の健康を守ることは、ストレス耐性の向上につながるためです。
具体的には、以下のような対策を検討するとよいでしょう。
- フレックスタイム制度の導入
- リモートワークの促進
- 有給休暇の取得促進
特に、長時間労働が続くとストレスが蓄積し、心身の不調を引き起こすリスクが高まります。柔軟な働き方を提供し、従業員の健康管理に努めることが重要です。
4-3. メンタルヘルスのサポート体制の整備
従業員のストレス耐性を高めるには、メンタルヘルスのサポート体制の整備も欠かせません。ストレス耐性は、思考・感情・行動などの要素が影響しているため、メンタル面を気にすることが必要です。
具体的には、以下のような対策をおこなえます。
- ストレスチェックの実施
- 定期的な面談の実施
- メンタルヘルス研修の実施
- 相談窓口の設置
企業は、従業員のストレス状態を定期的に把握することが大切です。
研修やセミナーを実施して、ストレスへの対処法を学ぶ機会を与えましょう。思考を柔軟にして、感情をコントロールできる力を身につけさせることが重要です。
ストレスが高い従業員には、産業医など専門家のカウンセリングを促すなど、メンタルヘルスケアも怠らないようにしましょう。
4-4. ABC理論の活用
ABC理論の活用もストレス耐性を高めるために活用できます。具体的には、出来事(A:Activating Event)が直接ストレスを生むのではなく、その出来事への信念・解釈(B::Belief)が感情・行動(C: Consequence)を引き起こすと考えることで、ストレスの捉え方を変えます。
例えば、上司の?責(A)によって落ち込む(C)という流れは、自分に自信がないという信念・解釈(B)が原因と考えるからです。信念や解釈を変えることで、ストレス反応をコントロールし、個人のストレス耐性を高めることが可能です。
5. ストレス耐性が高い従業員の特徴


ストレス耐性が高い従業員の特徴は、以下のとおりです。
- ポジティブ思考で自己肯定感が高い
- 適応力が高い
- マイペース
5-1. ポジティブ思考で自己肯定感が高い
ストレス耐性の高い従業員は、ポジティブ思考で自己肯定感が高い傾向があります。物事を前向きに捉えられるスキルがあるため、トラブルが発生したときや叱責されたときも、必要以上に自分を責めません。
困難な状況も成長の機会と捉え、積極的に挑戦する姿勢を持っているでしょう。ポジティブで自己肯定感が高い従業員は、失敗を過度に恐れず前向きに行動できます。
5-2. 適応力が高い
適応力が高い従業員も、ストレス耐性が高い傾向にあります。環境の変化や、新たな課題に対して柔軟に対応できるため、ストレスを溜め込みにくいといえるでしょう。
適応力の高い従業員は、問題に直面したときの対処法を理解しています。また、スルースキルも高いため、気持ちの切り替えがうまくできるでしょう。
ストレスを溜め込まず、仕事とプライベートのオン・オフの切り替えもしっかりできる人が多いといえます。
5-3. マイペース
マイペースな従業員も、ストレス耐性が高い傾向にあります。評価基準が自分軸であるため、他人からの評価が悪くてもストレスになることが少ないためです。
自分の価値観を大切にしているため、周りの評価や批判に振り回されることも少ないでしょう。ストレスを感じやすい状況でも、自分のペースを維持できるため冷静に対応できます。
加えて自己分析ができており、得手不得手を理解していれば、周りに流されることも少ないでしょう。
6. ストレス耐性が低い従業員の特徴


ストレス耐性が低い従業員の特徴は、以下のとおりです。
- ネガティブで自己肯定感が低い
- 問題解決能力が低い
- 完璧にこだわる
6-1. ネガティブ思考で自己肯定感が低い
ストレス耐性が低い従業員は、ネガティブ思考で自己肯定感が低い傾向にあります。物事を悲観的に捉えがちで、仕事の失敗や困難な状況に直面したときに必要以上に不安を感じやすいことが特徴です。
また、自己評価が低く、他者と比較して劣等感を抱きやすいためストレスを感じやすくなります。自信が無いため自分の意見を言えずに、感情を抑え込むことも少なくないでしょう。
失敗に対して自責の念を抱きやすいため、メンタルヘルスにも悪影響を及ぼします。
6-2. 問題解決能力が低い
ストレス耐性が低い従業員は、問題解決能力が低い傾向にあります。問題に直面したときに適切な対処ができないと、不安や焦りを感じ、ストレスを溜め込みやすくなるためです。
また、問題解決能力がないと周囲に依存しやすく、他人の意見に流されやすくなります。業務を押し付けられるなど、自分にとってマイナスな状況でも断れずに問題を抱え込むことも少なくありません。
6-3. 完璧主義
完璧主義な従業員も、ストレス耐性が低い場合があります。自他問わず評価基準が高いため、目標を達成できなかった場合などに過剰なストレスを感じやすいためです。
完璧主義の従業員は、責任感が強く、仕事や人間関係において高い倫理観を持っている傾向にあります。自分だけではなく、他人に対しても高いレベルの期待を抱くことがあるでしょう。
また、失敗したことを引きずり、気持ちの切り替えができない場合もストレスを抱えやすくなります。
7. ストレス耐性が低いことによる企業のリスク


従業員のストレス耐性が低いことによる企業のリスクは、以下のとおりです。
- メンタルヘルス問題の増加
- パフォーマンスの低下
- 離職率の上昇
7-1. メンタルヘルス問題の増加
ストレス耐性が低い従業員が多いと、メンタルヘルス問題の増加が懸念されます。うつ病や適応障害などの精神疾患を発症するリスクが高まると、休職者が増えることが予想されるでしょう。
休職者が増えると、業務が停滞したり人員不足を招いたりする可能性があります。周りの従業員の負担が大きくなり、職場全体のモチベーションが下がるリスクも考慮しなければなりません。
7-2. パフォーマンスの低下
ストレス耐性が低い従業員が多いと、パフォーマンスが低下するおそれがあります。ストレスを抱えていると、集中力が欠けたり判断力が鈍ったりすることがあるためです。
ミスも増え、仕事に対する意欲が低下するリスクも懸念されます。生産性が低下すれば、企業の業績にも悪影響を及ぼす可能性が考えられるでしょう。
7-3. 離職率の上昇
ストレス耐性が低い従業員が多いと、離職率が上昇するリスクがあります。業務のプレッシャーや人間関係の悩みを解決できず、心身に不調をきたしやすくなるためです。
特に、優秀な人材の離職は、企業にとって大きな損失となります。退職者が増えると新たに人員を確保する必要があるため、採用コストも増加するでしょう。
また、離職率が高い企業と認知されると、求職者が敬遠する可能性も否めません。離職率の上昇は企業にとって損失が大きいため、喫緊なストレス耐性の強化が求められます。
8. ストレス耐性を高めて安定したパフォーマンスを発揮させよう


ストレス耐性を向上させることは、従業員個人の健康維持だけではなく、企業の生産性向上にも寄与する重要な要素です。社内コミュニケーションの促進やワークライフバランスの促進、メンタルヘルスのサポートなど、具体的な対策を講じることでストレス耐性を高められます。
従業員一人ひとりがストレスに適切に対処し、安定したパフォーマンスを発揮できるよう、ストレス耐性を高めるための取り組みを積極的におこないましょう。



従業員の定着率の低さが課題の企業の場合、考えられる要因のひとつに従業員満足度の低さがあげられます。
従業員満足度を向上させることで、従業員の定着率向上や働くモチベーションを上げることにもつながります。
しかし、従業員満足度をどのように測定すれば良いのか、従業員満足度を知った後どのような活用をすべきなのかわからないという人事担当者様もいらっしゃるのではないでしょうか。
そのような方に向けて当サイトでは、「従業員満足度のハンドブック」を無料でお配りしています。
従業員満足度調査の方法や調査ツール、調査結果の活用方法まで解説しているので、従業員のモチベーション向上や社内制度の改善を図りたい方は、ぜひこちらから資料をダウンロードしてご活用ください。
人事・労務管理のピックアップ
-


【採用担当者必読】入社手続きのフロー完全マニュアルを公開
人事・労務管理公開日:2020.12.09更新日:2026.01.30
-


人事総務担当がおこなう退職手続きの流れや注意すべきトラブルとは
人事・労務管理公開日:2022.03.12更新日:2025.09.25
-


雇用契約を更新しない場合の正当な理由とは?伝え方・通知方法も紹介!
人事・労務管理公開日:2020.11.18更新日:2025.10.09
-


社会保険適用拡大とは?2024年10月の法改正や今後の動向、50人以下の企業の対応を解説
人事・労務管理公開日:2022.04.14更新日:2025.10.09
-


健康保険厚生年金保険被保険者資格取得届とは?手続きの流れや注意点
人事・労務管理公開日:2022.01.17更新日:2025.11.21
-


同一労働同一賃金で中小企業が受ける影響や対応しない場合のリスクを解説
人事・労務管理公開日:2022.01.22更新日:2025.08.26
タレントマネジメントの関連記事
-



プレゼンティーイズムとは?原因と企業に与える損失額・対策をわかりやすく解説
人事・労務管理公開日:2026.01.19更新日:2026.01.19
-



メンタルヘルスサーベイとは?ほかのサーベイとの違い、実施の目的や流れを解説!
人事・労務管理公開日:2026.01.16更新日:2026.01.14
-


企業におけるメンタルヘルスケアとは?4つのケアや事例を紹介
人事・労務管理公開日:2025.11.18更新日:2025.12.19




















