試用期間満了で解雇するときの手続きをわかりやすく解説
更新日: 2024.7.9
公開日: 2022.9.27
OHSUGI

試用期間を設け、本採用前に従業員の適性を判断している企業は多いでしょう。試用期間満了時に「本採用はできない」として解雇することはできるのでしょうか。
この記事では、試用期間満了での解雇について詳しく解説するとともに、手続きの流れや注意点をあわせて解説しています。
試用期間においては、法律上で雇用契約締結の義務はありませんが、本採用前のトラブルを避けるため締結しておく方が安心でしょう。
とくに期間や待遇、さらには解雇については企業側は法規則に則って、雇用契約書を作成しなければなりません。
「正当な解雇と認められる要件が知りたい」「解雇を進める手順がわからない」
「解雇予告はいつまでにするべきなのか知りたい」
このようなお悩みをお持ちの方に向けて、当サイトでは雇用契約手続きマニュアルとして、雇入れから雇止め・解雇までを徹底解説した資料を配布しています。
「不当解雇にならないように雇用契約の手続きを確認しておきたい」という方は、こちらから資料をダウンロードしてご覧ください。
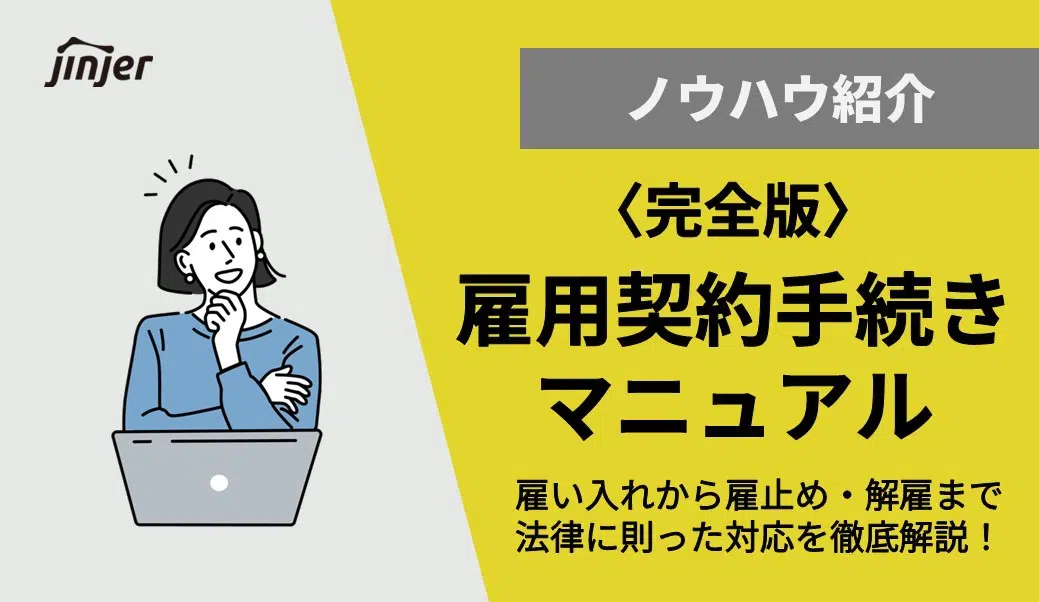
目次
1. 試用期間満了で解雇できる?

「試用期間」という言葉から、お試し期間という気軽なイメージを持つ方もいるかもしれません。しかし、試用期間での雇用契約と本採用後の契約に違いはなく、同じ労働契約であることを理解しておく必要があります。
試用期間だからといって、会社が自由に本採用するかしないかを決められるわけではありません。理由があって試用期間満了時に本採用を見送る場合、それは「解雇」として取り扱われます。
通常、雇用している正社員を解雇することは容易ではなく、よほどの理由がない限りは難しいでしょう。試用期間満了時に解雇する場合は、通常の正社員と比べると解雇しやすいですが、客観的で合理的な理由があり、なおかつ社会通念上相当である必要があります。
合理的な解雇事由には、無断欠勤が多いことや、著しく協調性が欠けている場合などが挙げられますが、指導により改善の見込みがあるのであれば、解雇は認められません。
「仕事の成果を出していない」「効率が悪くミスが多い」などの理由だけで本採用を拒否した場合は、不当解雇と判断される可能性が高いでしょう。
2. 試用期間満了で解雇するときの手続き

試用期間満了で解雇をする場合、通常解雇の流れと基本は同じです。しかし、本採用拒否の理由明示が必要になるなど少し異なる点もありますので、確認しておきましょう。
2-1. 就業規則の解雇事由を確認する
試用期間が終了して、本採用を拒否することができるのは、就業規則に解雇事由が明示されている場合です。そのため、まずは就業規則に試用期間での解雇について記載があるかどうか確認する必要があります。
就業規則に記載されている解雇事由を確認したら、解雇する従業員がその内容に該当するかどうかを見極めなければなりません。
解雇するにあたっての正当な理由には、「勤務態度が著しく悪い」「業務遂行能力がない」なども含まれますが、これらは繰り返しの指導や注意をおこなっても改善が見られない場合のみ、認められるものです。
就業規則で定めていた内容に該当していても、客観的な判断がなければ不当解雇になってしまうため注意しましょう。
2-2. 解雇予告をおこなう
試用期間開始から14日が経過している場合は、30日以上前に解雇予告をおこなう必要があります。予告をしない場合や、30日より前に解雇する場合は、不足分の手当を支払わなければなりません。
例えば、10日前に解雇予告をした場合、20日分は平均賃金から計算した手当を支払う必要があります。
なお、14日以内であれば解雇予告と手当は必要ありません。即日解雇が可能であるため、14日以内なら簡単に解雇しても良いと勘違いされがちですが、通常の解雇と同じように正当な理由が必要です。
極めて短い期間で適性がないと判断することは難しく、解雇権濫用とみなされるケースもあることに注意しましょう。
2-3. 解雇理由証明書を交付する
解雇理由証明書とは、解雇理由が記載された書類です。これは、会社が必ずしも発行しなければならないものではありません。しかし、従業員から請求された場合は発行義務が生じるため、2~3日以内を目安に速やかに交付する必要があります。
内容は従業員が希望する項目のみ記載するので、本人に確認を取った方が良いでしょう。解雇理由は、就業規則の規定に該当する具体的な理由を記載します。
書式は自由なので必要項目に合わせて作成しましょう。
2-4. 社会保険などの手続きをおこなう
試用期間の従業員が社会保険や雇用保険の被保険者となっていた場合、本採用拒否により退職した後に、各種保険の手続きもおこなわなくてはいけません。
手続きの流れについては、通常の社員の退職時と同じです。社会保険については退職日から5日以内、雇用保険については退職日から10日以内に、それぞれ必要書類を揃えて脱退手続きをおこないます。
雇用保険に関しては1つ注意が必要で、離職票を作成する際に離職理由欄を「5.その他(1~4のいずれにも該当しない場合」にチェックし、具体的な理由を記載しなくてはいけません。
試用期間満了による解雇であれば、「試用期間満了による本採用拒否」といったように理由を明記しましょう。
とくに試用期間満了による解雇の場合でも、退職と同様に資格喪失の手続きが必要です。
しかし申請には期限や必要書類が細かく指示されており、大変複雑で漏れやミスが発生しやすい業務です。当サイトでは社会保険の手続きをミスや遅滞なく完了させたい方に向け、最新の法改正に対応した「社会保険の手続きガイド」を無料配布しております。ガイドブックでは喪失時の手続き方法をわかりやすくまとめているため、漏れなく遅滞なく手続きを済ませいたい方はこちらから資料をダウンロードしてご覧ください。
 3. 試用期間満了で解雇するときの4つの注意点
3. 試用期間満了で解雇するときの4つの注意点

試用期間であるとはいえ、解雇は労使トラブルが起きやすい問題のひとつです。紹介する4つの注意点を把握し、不当解雇や法律違反にならないよう、適切に対応しましょう。
3-1. 試用期間中に指導や改善の機会を与えること
解雇の理由として、能力不足が挙げられることがありますが、短期間で能力がないと判断して解雇することは簡単ではありません。
経験者の中途採用では、能力に期待して採用することが多いかもしれませんが、適切な指導をおこなっていない状態で業務遂行能力がないと決めつけた場合、解雇が無効になる可能性があります。
たとえ、無断欠勤が多い場合でも注意や指導をおこない、改善の機会を与えなければなりません。繰り返し指導や注意をしても全く改善されない場合において、はじめて解雇の有効性が高くなるのです。
3-2. 解雇前に面談をおこない事前に伝えること
試用期間終了まで、本採用拒否についての会社側の意思表示が何もなく、突然解雇を言い渡した場合は、無効になるケースがあります。
解雇予告をおこなわず手当を支払ったとしても、解雇前には一度本採用が難しい可能性があることを面談などで伝えることが望ましいでしょう。
話し合いを一切せずに解雇すると、万が一裁判になったときに、強引な不当解雇であったと主張されるかもしれません。
なぜ試用期間満了で解雇をするのか、その理由を具体的に説明し、本人の気持ちや言い分を聞くことが大切です。
3-3. 就業規則に解雇についての規定があること
先ほど述べた通り、本採用を拒否するためには、解雇について就業規則で規定しておく必要があります。就業規則は労働契約の内容でもあるので、規定がない場合は解雇が無効になる可能性が高いでしょう。
どのような理由で解雇するのかを記載し、解雇できる基準を明確にしておくことが重要です。解雇できるかどうかの判断は就業規則に沿っておこなうため、トラブル防止のためにも必ず規定しておきましょう。
3-4. 新卒者の場合は要注意
新卒者は社会経験が少なく、即戦力を期待して採用するわけではないため、能力面や勤務態度などを理由とした解雇は注意が必要です。
裁判において新卒者は「できなくてあたり前」という考えが前提にあるので、解雇した場合、会社側の指導が足りていないことが問題視される可能性があります。
社会人としての一般常識やビジネスマナーなどから教え、会社が新卒者を育てていくことが求められるため、試用期間満了での解雇は難しいケースが多いでしょう。
4. 試用期間の途中で解雇する場合

試用期間の途中であっても通常の解雇と同様に、合理的な理由がある場合は解雇できます。しかし、満了時に本採用を拒否することと比べると、途中での解雇はよりハードルが高くなるでしょう。
満了時であっても、短期間で適性があるかどうかの判断は難しいものです。さらに早い試用期間の途中での解雇は、よほどのことがない限り正当な理由として認められないことがあります。
「試用期間中に重大なトラブルを起こした」「経歴詐称があった」など、途中で解雇するほどの問題があった場合は、それを証明できる書類や証拠を集めておく必要があるでしょう。
5. 試用期間満了での解雇は合理的な理由が必要

客観的に正当な理由であり、社会一般に見ても相当であることが証明できる場合は、試用期間満了で解雇可能です。
手続き方法は基本的に通常の解雇と同じですが、就業規則で規定した解雇事由に沿って判断されるため、規定する内容は重要になります。
しかし、短期間で適性がないと判断して解雇することは容易ではありません。会社は、従業員への指導を十分におこなった上で、改善の見込みがない合理的な理由を証明する必要があるのです。
トラブルを防ぐためにも、今回紹介した注意点をしっかり把握して、適切に対処していきましょう。
試用期間においては、法律上で雇用契約締結の義務はありませんが、本採用前のトラブルを避けるため締結しておく方が安心でしょう。
とくに期間や待遇、さらには解雇については企業側は法規則に則って、雇用契約書を作成しなければなりません。
「正当な解雇と認められる要件が知りたい」「解雇を進める手順がわからない」
「解雇予告はいつまでにするべきなのか知りたい」
このようなお悩みをお持ちの方に向けて、当サイトでは雇用契約手続きマニュアルとして、雇入れから雇止め・解雇までを徹底解説した資料を配布しています。
「不当解雇にならないように雇用契約の手続きを確認しておきたい」という方は、こちらから資料をダウンロードしてご覧ください。
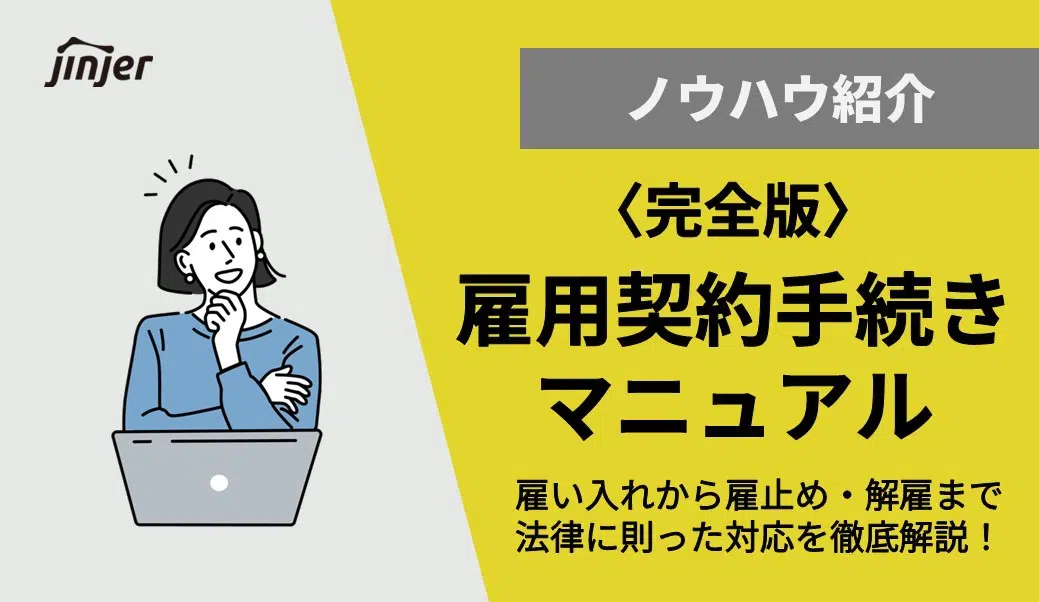
人事・労務管理のピックアップ
-

【採用担当者必読】入社手続きのフロー完全マニュアルを公開
人事・労務管理
公開日:2020.12.09更新日:2024.03.08
-

人事総務担当が行う退職手続きの流れや注意すべきトラブルとは
人事・労務管理
公開日:2022.03.12更新日:2024.06.11
-

雇用契約を更新しない場合の正当な理由とは?通達方法も解説!
人事・労務管理
公開日:2020.11.18更新日:2024.07.10
-

法改正による社会保険適用拡大とは?対象や対応方法をわかりやすく解説
人事・労務管理
公開日:2022.04.14更新日:2024.06.12
-

健康保険厚生年金保険被保険者資格取得届とは?手続きの流れや注意点
人事・労務管理
公開日:2022.01.17更新日:2024.07.02
-

同一労働同一賃金で中小企業が受ける影響や対応しない場合のリスクを解説
人事・労務管理
公開日:2022.01.22更新日:2024.05.08


























