試用期間の延長に違法性はある?要件や手続き・本採用拒否や解雇についても解説
更新日: 2024.7.11
公開日: 2022.9.27
OHSUGI

試用期間を設けている会社は少なくありませんが、設定した期間を途中で延長することは可能なのでしょうか。試用期間中に適性を判断できなかった場合や、もう少し様子を見たいと思うこともあるでしょう。
今回は試用期間の延長についてと、その条件や注意点について解説します。従業員との間でトラブルが発生しないよう、しっかり理解しておきましょう。
目次
「雇用契約手続きマニュアル」無料配布中!
従業員を雇い入れる際は、雇用(労働)契約を締結し、労働条件通知書を交付する必要がありますが、法規定に沿って正しく進めなくてはなりません。
当サイトでは、雇用契約の手順や労働条件通知書に必要な項目などをまとめた資料「雇用契約手続きマニュアル」を無料で配布しておりますので、「雇用契約のルールをいつでも確認できるようにしたい」「適切に雇用契約の対応を進めたい」という方は、是非こちらから資料をダウンロードしてご覧ください。
2024年4月に改正された「労働条件明示ルール」についても解説しており、変更点を確認したい方にもおすすめです。
1. 試用期間とは
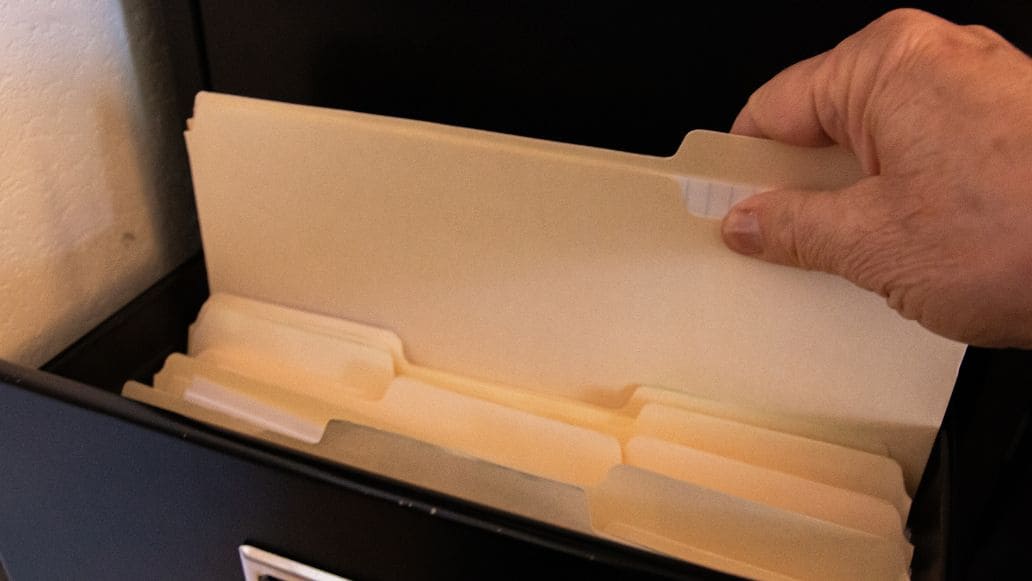
まずは試用期間とは、どのような目的で設けられる期間なのか、試用期間に関するルールはどのようなものがあるのか、概要を説明します。
1-1. 会社が試用期間を設ける目的
労働者を採用する際、書類選考や面接は労働者の能力や適性を見極める手段として重要ですが、実際の業務においてそれらが適切かどうかを正確に判断するには限界があります。そうした背景から、企業は試用期間を設け、労働者の実際の能力や適性を業務を通じて見極めることを目的としています。
この試用期間中には、労働者が会社の業務に適応するかどうか、また会社の文化や価値観に合致するかどうかが評価されます。さらに、試用期間満了後に本採用を拒否する場合でも、この期間中であれば解雇の有効性が通常の解雇よりもやや緩やかに判断されるため、企業にとってもリスクを低減する機会ともなります。
1-2. 試用期間の流れは法律上のルールがない
試用期間の長さには法律上の具体的なルールは存在しないため、企業はその期間を自由に設定することができます。
通常、試用期間は3か月から6か月程度が一般的ですが、これは企業の方針や業界の慣例によって異なることがあります。しかし、ここで重要なのは、試用期間の趣旨が労働者の適性を判断するためのものであるという点です。このため、試用期間が必要以上に長くなることは認められません。
労働基準法を始めとする関連法令は、企業が労働者に対して不当な待遇を行うことを防ぐための枠組みを提供しています。したがって、無制限に試用期間を延長することは不適切であり、法的にも問題となり得るため注意が必要です。企業の採用担当者や人事部のスタッフは、試用期間の設定や延長を行う際には、法的なガイドラインを遵守し、公正なプロセスを重視することが重要です。
2. 試用期間は延長できる?違法性は?

試用期間は、自社の従業員としての適性があるかどうかを見極める期間です。基本的には本採用後の勤務と同じように労働をおこない、その働きを見て会社は適正チェックをおこないます。
期間の上限は法律で決められているわけではありませんが、何年も自由に設定できるものではなく、3~6か月程度が一般的でしょう。試用期間中に遅刻や欠勤が多いなど何かしら問題があり、適性を判断するのにもう少し時間が欲しい場合もあるかもしれません。
そのようなとき、試用期間を延長することは可能です。延長することは法的に制限されておらず、条件をクリアしていれば違法にはなりません。試用期間を延長するには、「試用期間延長通知書」を書面で交付します。内容は、延長期間や延長の理由、根拠となる就業規則について記載しましょう。
3. 試用期間を延長できる要件
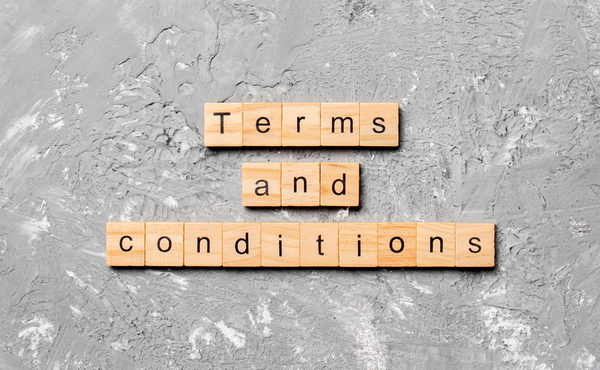
試用期間の延長そのものは違法ではないことを説明しましたが、無条件で延長できるわけではありません。ここでは、試用期間を延長できる条件を紹介します。
3-1. 就業規則・雇用契約上に規定が明記してあること
試用期間を延長するのであれば、就業規則にその可能性があることについて規定されている必要があります。延長の可能性だけでなく、延長期間についても記載しておかなければなりません。
会社によっては試用期間中の賃金を低く設定しているので、試用期間を延ばすことは労働者側からすると不利益な内容です。そのため、仮に試用期間の延長について本人と口頭で同意を得ていたとしても、就業規則で規定されていなければ、無効になる可能性があります。
また、勤務態度に問題がなく業務を遂行している場合は、就業規則で延長について規定していたとしても、正当な理由がないため認められません。
3-2. 延長するに値する合理的な理由や事情があること
試用期間を本来の期間よりも延ばすためには、合理的な理由や事情が必要となります。以下は、延長が認められる合理的な理由の例です。
- 無断欠勤が多い
- 病気や怪我などにより勤務日数が少ない
- 勤務態度が著しく悪く、指導や注意をしても改善されない
- 法律違反があり会社の信用や秩序に影響を与える場合
- 経歴詐称があった場合
「仕事の覚えが悪い」「ミスが多い」などは、試用期間中は当然であると判断される可能性が高いため、合理的な理由としては認められないケースが多いでしょう。採否の判断が困難であったり、労働者の適格性等に問題はあるものの、労働者に相当期間の猶予を与える場合であるなどといったケースが認められるようです。
就業規則に規定があり、採用時に従業員へ延長の可能性を伝えていたとしても、合理的な理由なしに会社が一方的に延長することはできません。
3-3. 常識的・妥当な長さであること
試用期間の延長を検討する際には、その期間が常識的であり妥当であることが重要です。
試用期間が延長されることにより、労働者は不安定な地位に置かれ、不利益を被る可能性があるため、延長期間は社会通念上妥当な範囲内でなければなりません。具体的には、必要以上に長期間の延長や何度も延長を繰り返すことは避けるべきです。
そのような場合、労働者に不当な扱いを与えていると見なされ、延長自体が無効とされる可能性があります。したがって、企業の採用担当者や人事部のスタッフは、雇用契約の法的な枠組みを理解し、試用期間の延長が妥当かどうかを慎重に判断することが求められます。
4. 試用期間の延長を検討すべきケース
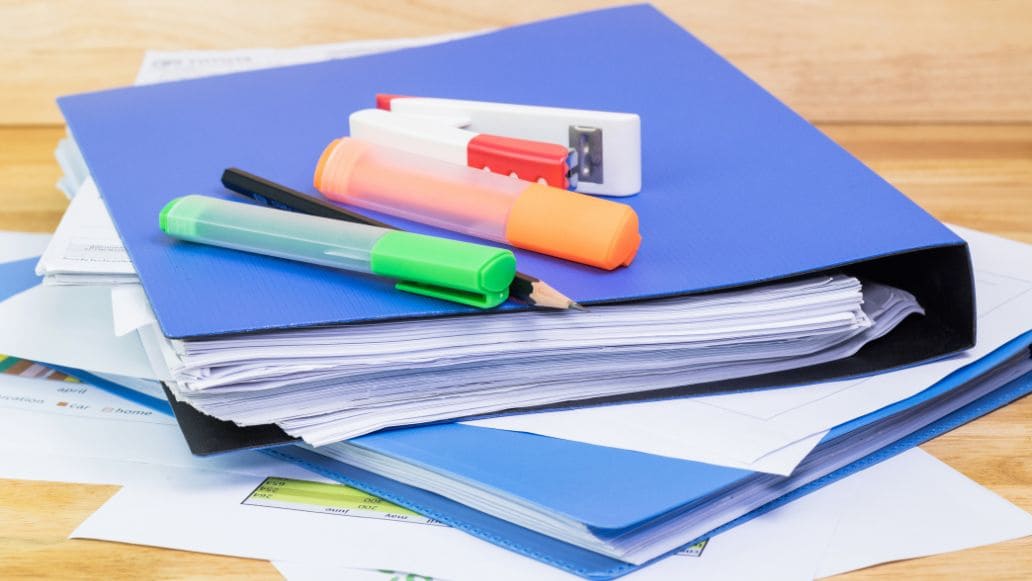
試用期間の延長を検討すべきケースは、多岐にわたります。第一に、従業員の能力がまだ十分に評価されていない場合があります。特に技術的な職種や責任の重いポジションでは、試用期間内に十分な評価を行うことが難しいことがあります。
また、企業環境や業務の理解が遅れている新入社員に対しても、延長を検討する価値があります。さらに、業務の特殊性や未経験の業務に挑戦する場合も、適応期間をさらに確保するために延長が必要です。しかし、試用期間を延長する際には、労働基準法や社内規定を遵守することが重要です。不適切な延長は労働法違反となる可能性があるため、法的な手続きについても十分に確認する必要があります。
4-1. もう少し仕事ぶりを見て検討したい場合
仮採用された労働者が新しい職場にすぐにはなじまず、本来の能力を発揮できないことは珍しくありません。
このような場合、労働者の本来の適性を見極めるために、会社が試用期間を延長することが考えられます。試用期間の延長は、労働者の能力や適性をさらにじっくりと評価するための重要な手段となります。特に、書類選考や面接を経て仮採用されたものの、試用期間中に評価が難しい場合には、延長を検討すべきケースです。適法な手続きを踏まえ、目的を明確にした上で延長を行うことが求められます。
これにより、労働者が職場に適応しやすくなり、最終的には組織全体の成果向上にも寄与するでしょう。
4-2. 病気・怪我により使用期間中休みが多かった場合
試用期間中に病気や怪我により休みが多かった場合、企業は労働者の能力や適性を適切に評価するのが難しくなります。
このような状況では、企業は試用期間を延長することを検討することが一般的です。これは、労働者が通常どおり働ける状態に回復した後に、真の能力や適性を見極めるための手段として有効です。試用期間の延長は法的にも許容されており、適切な手続きを踏むことで、企業と労働者の双方にとって公平な評価を行うことができます。したがって、試用期間の延長を検討することが重要です。
4-3. 遅刻や欠勤が続いていて従業員に問題がある場合
遅刻や欠勤が続いていて従業員に問題がある場合、試用期間の延長を検討することが重要です。
遅刻や欠勤などの問題行動は企業の運営に大きな影響を与えるため、これを無視するわけにはいきません。試用期間中にこのような行動が頻発する場合、本採用を躊躇するケースが多いでしょう。試用期間の延長により、労働者が改善の機会を得て、問題行動の解消を図ることができます。
また、試用期間の延長手続きには法的な知識が求められます。適切な手続きを踏むことで、企業としての対処がより明確になります。ただし、指導を尽くしてもなお労働者の問題行動が改善されない場合は、本採用を拒否することを検討することも必要です。法的手続きを遵守しつつ、試用期間の延長をうまく活用することで、最適な人材を見極める手段となります。
4-4. 他の部署・ポジションでの適性を確認したい場合
企業が書類選考や面接を経て適切と判断した部署への配属後、その働きが期待に達しない場合は、他の部署やポジションでの適性を確認するために試用期間の延長を検討することがあります。これは、試用期間満了時に本採用を拒否できる事案であっても、解雇を猶予しつつ、別の職場での適合性を再判断するための措置です。この延長は、労働者の生活や雇用の安定に寄与するため、法的にも許容されるケースがあります。
さらに、当初の部署での仕事内容が途中で変更された場合も、変更後の業務への適性を判断するために試用期間の延長が行われることがあります。試用期間が延長された場合、その延長が法的に妥当であるかは、後述する基準によって判断されます。このように、試用期間の延長は企業と労働者双方の利益を考慮した柔軟な対応策といえます。
5. 試用期間の延長をおこなう際の手続き

では実際に使用期間の延長を行う際の手続きの流れを紹介します。トラブルを防ぐためにも正しい手順で進めるようにしましょう。
5-1. まずは従業員に改善指導をおこなう
試用期間の延長を行う際には、まず従業員に対して十分な改善指導を行うことが非常に重要です。
特に、能力不足や問題行動が見られる場合には、企業側が具体的な指導を積極的に行う必要があります。この段階での改善指導は、従業員自身に改善の機会を与えるとともに、企業としても労働者に対する適切な支援を提供していることを示す重要な証拠となります。
改善指導の際には、具体的な問題点を明確にし、改善のための具体的なアクションステップを示すことが求められます。例えば、業務スキルの向上や社内ルールの遵守など、具体的な目標を設定し、それに向けた進捗を定期的に確認することで、従業員の成長をサポートします。また、改善指導の内容とその経過を文書化しておくことも重要です。これにより、後日、改善のための努力を企業が適切に行ったことを証明することができます。
このように、試用期間の延長を行う前に従業員に対して改善指導を行っておくことで、不当解雇と判断されるリスクを減少させることができます。試用期間内にしっかりとした改善指導を行い、企業と従業員の双方にとって最適な結果を導く努力を怠らないようにしましょう。
5-2. 試用期間の延長を提案する
試用期間の延長をおこなう際の手続きとしてまずは従業員に改善指導をおこなうことが重要です。
試用期間の延長がやむを得ないと判断した場合には、労働者に対して試用期間の延長を提案しましょう。改善指導では、具体的な改善点や目標を明示し、従業員が改善するためのサポートを行います。この段階での適切なフィードバックが、労働者の成長を促進し、最終的な評価を公正に行うための基盤となります。
試用期間の延長について労働者に伝える際には、労働者に対して何らかの圧力をかけていると解釈され得るような言動を行わないことが大切です。同意を強制するような言動は避け、あくまで労働者の納得を得ることを目指しましょう。例えば、「同意しなければ解雇する」といった圧力的な発言は絶対に避けるべきです。これにより、試用期間の延長が無効と判断されるリスクを回避できます。誠実な対応を心掛け、透明性を持って手続きを進めることが、企業と労働者双方にとって最良の結果をもたらします。
5-3. 試用期間の延長に関する同意書を締結する
試用期間の延長を行う際には、まず労働者から正式な同意を得る必要があります。
試用期間の延長に関する同意が得られたら、次に進むべきステップは「試用期間の延長に関する同意書」を締結することです。具体的には、同意書に延長期間や具体的な理由が明示されていることが重要です。この同意書を労働者に提示し、署名と押印を行ってもらいましょう。
さらに、企業側も同意書に署名・押印を行い、対等な合意を示す合意書として締結します。この署名・押印された同意書や合意書は、後で労働者との間でトラブルが生じることを防ぐためにも、慎重に保管しておくことが推奨されます。こうした手続きは、採用担当者や人事部のスタッフにとって、法的に正当な方法で試用期間を延長するために欠かせない重要な役割を果たします。
5-4. 改めて企業側から改善指導を行う
試用期間の延長をおこなう際は、労働者に対して適切な改善指導を行うことが重要です。
試用期間の目的は労働者の能力や適性を見極めることにありますが、延長後も企業側は労働者に必要なサポートを提供し、十分なパフォーマンスを発揮できる環境を整える必要があります。改善指導を怠ると、最終的に本採用拒否を決定する際に、不当解雇と見なされるリスクがあります。
そのため、延長後の試用期間中に労働者の能力や行動に関する具体的なフィードバックを提供し、改善のための具体的な手段を講じることが求められます。これには、定期的な評価ミーティングや、改善点に関する明確な目標設定を含むべきです。
企業としては、そうした改善指導を通じて労働者の成長を支援し、最終的には適切な判断材料を得ることができます。本採用拒否を考慮する場合でも、十分な改善指導を行ったという証拠を残すことで、後のトラブルを避けることができます。
6. 試用期間を延長するときの注意点

試用期間を延ばすことは違法ではありませんが、適切な方法でおこなわないと、従業員と会社との間で信頼関係が崩れてしまう恐れもあります。
ここでは、試用期間を延長するときの注意点を3つ紹介しますので、延長を実施する前に一度確認しておきましょう。
6-1. 延長期間も一般的な範囲内で設定すること
試用期間の延長は無期限にできるわけではありません。しかし、延長期間に関しても法律では定められていないため、3か月程度の範囲で決めると良いでしょう。
期限を定めない延長は、裁判において無効とされた事例もあります。延長の回数についても、何回もおこなうのであれば無期限とほとんど変わらないため、無効となる可能性が高いでしょう。
元の試用期間と延長分の合計が、1年以内に収まる程の期間が妥当だと考えられています。延長期間についても就業規則や雇用契約書に記載しておきましょう。
6-2. 延長する場合は従業員に丁寧な説明をすること
採用時に試用期間延長の可能性について説明していたとしても、実際に延長するときは改めて本人に十分な説明をおこなう必要があります。
従業員側からすると、試用期間の延長は「本採用されないのでは?」などの不安要素になるため、面談を通してその理由を丁寧に伝えましょう。
従業員が納得していない状態で延長をしてしまうと、モチベーションが低下してしまう原因にもなるため、延長の際は十分な配慮が必要です。
6-3. 延長の理由は明確に示すこと
先ほど述べた通り、ただ単に「仕事ができないから」では、正当な理由にはなりません。
試用期間中に成果が出せなくても本採用した後に能力を発揮する可能性もあり、また別部署であれば違う結果になる場合もあるでしょう。
万が一、延長が不当だとして従業員から訴えられたとき、会社は合理的な理由があったことを証明できなければ、裁判で負けてしまう可能性もあります。
延長をする場合は、必ず合理的な理由を書面で明確に示した上で、従業員の署名捺印をもらっておきましょう。
7. 試用期間延長後に本採用拒否・解雇することは可能?

会社は客観的かつ合理的な理由があり、社会通念上相当である場合に限り、使用期間終了に伴い、従業員を解雇することが可能です。
「適性がないと判断するにはまだ早い」と試用期間を延長した後、「やっぱり問題があるため解雇したい」と考えるケースもあるかもしれません。
しかし、試用期間を延ばしたということは、本採用する可能性があることを意味するため、延長後の解雇が難しくなる可能性があることに注意が必要です。
ただし、使用期間延長後に解雇できるケースも存在します。例えば、試用期間の延長中に新たに発生したトラブルが解雇に相当すると認められる場合です。
改善の期待を込めて試用期間を延長したけれどトラブルが絶えない場合や、どれだけ指導や注意をしても勤務態度が改善されないなどの場合は、解雇できる可能性があります。
とはいえ、試用期間中でも通常の雇用と同じように、簡単に解雇したり期間を延長したりできるわけではないことを覚えておきましょう。
7-1. 通常よりも労働基準監督署の審査が厳しくなる
「適性がないと判断するにはまだ早い」と試用期間を延長した後、「やっぱり問題があるため解雇したい」と考えるケースもあるかもしれません。
しかし、試用期間を延ばしたということは、本採用する可能性があることを意味するため、延長後の解雇が難しくなる可能性があることに注意が必要です。
7-2. 本採用拒否・解雇する場合は解雇予告が必要
試用期間延長後に解雇する場合であっても、労働基準法上のルールが適用されるため、解雇予告をおこなう必要があります。
やむなく解雇するという判断に至った場合、30日前に解雇予告をおこなうか、30日分の解雇予告手当を支払って解雇しなくてはいけません。
ただし、試用を開始してから14日以内であれば、解雇予告をおこなわずに解雇することが可能です。
「試用期間だからいつでも解雇できる」と誤解している方も少なくないため、注意しましょう。
8. 試用期間を延長する際は適法要件を確認した対応が重要

試用期間終了時に解雇するのではなく、もう少し様子をみたいという場合、正当な理由があれば延長は可能です。
しかし、延長するには就業規則で試用期間延長の規定について詳細に定められている必要があり、従業員には採用時に延長の可能性があることを伝えなければなりません。
延長は法的に問題ありませんが、従業員からすると不利益な内容であり、このまま解雇になるのではという不安を抱かせる原因にもなります。
そのため、延長をするときは元々の使用期間と合わせて1年以内になるように設定し、なおかつ延長の理由を本人にしっかり説明することが大切です。
「雇用契約手続きマニュアル」無料配布中!
従業員を雇い入れる際は、雇用(労働)契約を締結し、労働条件通知書を交付する必要がありますが、法規定に沿って正しく進めなくてはなりません。
当サイトでは、雇用契約の手順や労働条件通知書に必要な項目などをまとめた資料「雇用契約手続きマニュアル」を無料で配布しておりますので、「雇用契約のルールをいつでも確認できるようにしたい」「適切に雇用契約の対応を進めたい」という方は、是非こちらから資料をダウンロードしてご覧ください。
2024年4月に改正された「労働条件明示ルール」についても解説しており、変更点を確認したい方にもおすすめです。
人事・労務管理のピックアップ
-

【採用担当者必読】入社手続きのフロー完全マニュアルを公開
人事・労務管理
公開日:2020.12.09更新日:2024.03.08
-

人事総務担当が行う退職手続きの流れや注意すべきトラブルとは
人事・労務管理
公開日:2022.03.12更新日:2024.06.11
-

雇用契約を更新しない場合の正当な理由とは?通達方法も解説!
人事・労務管理
公開日:2020.11.18更新日:2024.07.10
-

法改正による社会保険適用拡大とは?対象や対応方法をわかりやすく解説
人事・労務管理
公開日:2022.04.14更新日:2024.06.12
-

健康保険厚生年金保険被保険者資格取得届とは?手続きの流れや注意点
人事・労務管理
公開日:2022.01.17更新日:2024.07.02
-

同一労働同一賃金で中小企業が受ける影響や対応しない場合のリスクを解説
人事・労務管理
公開日:2022.01.22更新日:2024.05.08



























