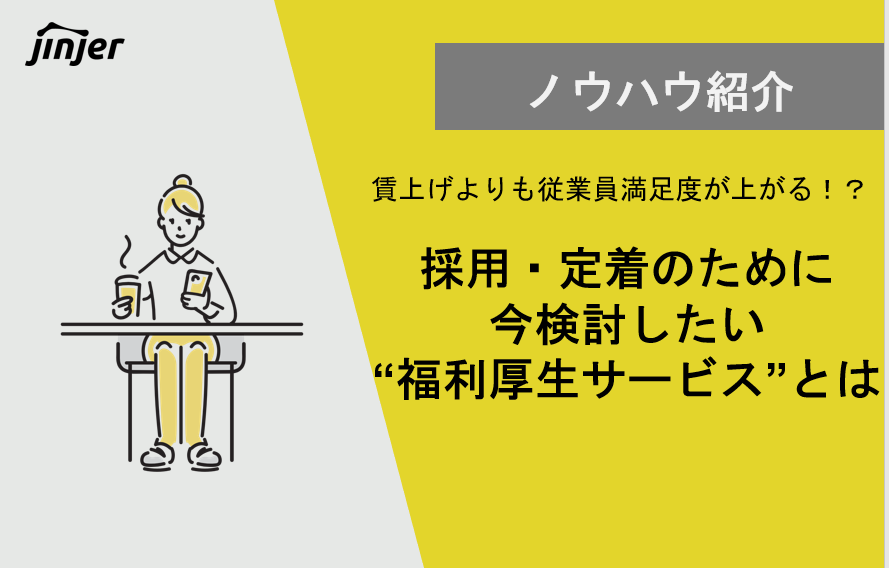福利厚生とは?目的や種類、メリットを簡単に解説
更新日: 2025.9.19 公開日: 2025.1.31 jinjer Blog 編集部

福利厚生とは、従業員の生活や働きやすさを支える制度やサービスの総称です。たとえば、健康保険や年金などの社会保険制度から、住宅手当、育児支援、リフレッシュ休暇といった独自の取り組みまで、その種類は多岐にわたります。
少子高齢化や働き方の多様化が進む中で、福利厚生は従業員のエンゲージメント向上などさまざまな効果が期待できることから、その重要性は年々高まっています。福利厚生の導入によって期待される効果を知り、自社の課題に合わせて上手く活用しましょう。
この記事では、福利厚生の基本的な概要をはじめ、代表的な種類や導入によって期待できる効果やメリット、注意点などを、わかりやすく解説します。
目次
賃上げを実施しても、税負担で手取りは増えず、従業員の反応は今ひとつ…。そんなお悩みはありませんか?
企業の負担を抑えつつ、採用強化や人材定着に繋がる「福利厚生サービス」という選択肢があります。
本資料では、その具体的な仕組みと活用法を分かりやすく解説します。
◆この資料でわかること
- なぜ、賃上げだけでは従業員満足度が上がりにくいのか
- 企業のコストを抑えつつ満足度向上を目指す「福利厚生サービス」の仕組み
- 数あるサービスの中から自社に合ったものを選ぶ、3つの着眼点
これらの疑問に一つでも不安を感じた方へ。企業の成長につなげる具体的な方法として参考になりますので、ぜひこちらから資料をダウンロードしてご活用ください。
1. 福利厚生とは


福利厚生とは、企業が従業員やその家族の健康および生活を向上させるための施策です。英語では、「Employee Benefits」や「Employee Welfare」などとも呼ばれます。給与や賞与以外の報酬を指す言葉でもあり、さまざまな種類があります。
提供する内容は企業により異なり、一般的ではない独自の施策を導入している企業も増えているのが現状です。
少子高齢化による労働人口の減少や働き方改革の促進により、多くの企業で福利厚生が強化されています。
福利厚生は、従業員の生活を安定させたり向上させたりするサービスが多く、充実化することにより満足度やエンゲージメントの向上を図れることが利点です。
ライフスタイルに合った働き方や健康経営を促進することで、企業イメージの向上にもつながります。福利厚生が採用活動のアピール材料になるケースも多く、充実するほど優秀な人材を獲得しやすくなるのも魅力です。
2. 福利厚生の主な種類


福利厚生の主な種類は、次のとおりです。
- 法定福利厚生
- 法定外福利厚生
それぞれ詳しく解説します。
2-1. 法定福利厚生
法定福利厚生とは、法律によって企業への導入が義務づけられているものです。
主に次のような種類があります。
| 種類 | 概要 | 会社の負担 |
| 健康保険 | 病気やケガなどに際して、医療給付や手当金などを受けられる制度。 | 半額 |
| 介護保険 | 介護が必要となった際に、介護サービスを受けるための給付金を支給。 | 半額 |
| 厚生年金保険 | 65歳以上から一定額を受け取れる公的年年金制度。障害を負った際や扶養者を失くした場合にも支給される。 | 半額 |
| 雇用保険 | 失業中や育児・介護休業中に給付金が受け取れる制度。この他に、教育訓練給付金や就職支援などがある。 | 費用の2分の3 |
| 労災保険 | 業務上または通勤中の負傷や疾病、障害、死亡などに対し労働者や遺族に対して給付金を支給する制度。 | 全額 |
| 子ども・子育て拠出金 | 企業から徴収し、児童手当や仕事・子育て両立支援事業などに充当される。 | 全額 |
法定福利厚生では、企業が費用の一部もしくは全額を負担することになっています。労使の費用負担の割合は、上記のとおり種類により異なることが特徴です。
2-2. 法定外福利厚生
法定外福利厚生とは、企業が自らの判断で導入できるものです。企業が任意で導入できる福利厚生であるため、ほかでは見られない企業独自の施策を導入することが可能です。どのような内容でも、従業員サービスを充実させる目的で導入されます。
一般的な法定外福利厚生は、以下が挙げられます。
2-2-1. 住宅・通勤関連
住宅に関する福利厚生では、毎月の住居費用の一部を負担する家賃補助や住宅手当、住宅ローン補助などがあります。また、社員寮や借り上げ社宅の提供など、住居そのものの提供によっておこなう福利厚生もあります。
通勤関連の福利厚生では、代表的なのが通勤手当です。この他にも、ガソリン補助などが挙げられます。
2-2-2. 子育・介護関連
子育・介護関連の福利厚生では、法律で定められた育児・介護休暇以外に取得できる休暇を設定するケースが挙げられます。また、保育所やベビーシッター、介護施設の利用料金の一部補助、短時間勤務の拡大などもあります。
近年では、企業内保育所を設置する企業も増えており、仕事と育児の両立を図れるのが従業員にとっては大きなメリットです。
2-2-3. 慶弔・災害関連
従業員本人や従業員の身内に慶事や不幸があった際の福利厚生です。結婚祝い金や出産祝い金、傷病見舞金、災害見舞金、死亡弔慰金など、現金支給によっておこなうケースが挙げられます。また、休暇で設定するケースもあり、代表的なのが結婚休暇や忌引き休暇などです。
2-2-4. 働き方・余暇関連
仕事とプライベートを両立するワークライフバランスが注目される中、働き方や余暇に関する福利厚生を充実させる企業も増えています。リフレッシュ休暇やボランティア休暇などが代表です。この他にも、宿泊施設の利用補助や社員旅行、社内レクリエーションの実施などが挙げらます。
2-2-5. 健康・食事関連
健康関連の福利厚生では、人間ドックやスポーツジムの費用補助、インフルエンザなどの予防接種の費用補助などが挙げられます。
また、食事関連では、社員食堂の設置や食事補助チケットの提供、無料コーヒーマシーンの設置などがあります。また、最近では置き型の社食やお菓子ボックスの設置などユニークなものも登場しています。
2-2-6. 自己啓発関連
自己啓発関連の福利厚生は、従業員のスキルアップや労働意欲の向上につながるのがメリットです。主に、研修やeラーニングの実施、資格取得費用の負担、通信教育の費用補助などが挙げられます。また、従業員が業務に必要な資格を取得した際に支給する資格手当も福利厚生の一つです。
2-2-7. 財産形成関連
ライフイベントへの備えとして、財産形成関連の福利厚生にも注目が集まっています。代表的なのが、企業が拠出した掛金を従業員自ら運用する企業型確定拠出年金(企業型DC)や将来の受け取り額が確定している確定給付年金(DB)です。
この他にも、社内預金制度や財形貯蓄制度、持ち株制度といった福利厚生もあります。
3. 福利厚生の運用形態


福利厚生の運用形態は、次のとおりです。
- カフェテリアプラン
- パッケージプラン
それぞれ詳しく解説します。
3-1. カフェテリアプラン
カフェテリアプランとは、従業員が利用する福利厚生を選択できる運用形態です。
一例として、従業員にポイントを付与し、ポイントを使って自由に福利厚生のサービスを利用させる方法が挙げられます。
従業員のニーズに対応できる形で運用できるのがメリットです。デメリットとして、パッケージプランと比較するとコストが高くなりやすい点が挙げられます。
3-2. パッケージプラン
パッケージプランとは、事前に決められた福利厚生をパッケージとして提供する運用形態です。
すでにセットになっている福利厚生を従業員に利用させる点が、カフェテリアプランと異なります。
幅広いサービスを従業員に提供できるのがメリットですが、従業員それぞれのニーズに対応しにくい点がデメリットです。
4. 福利厚生の6つのメリット


福利厚生のメリットは、次のとおりです。
- 節税効果が期待できる
- 従業員の健康を維持できる
- 企業の社会的信頼性を向上できる
- 生産性を向上できる
- 従業員の満足度を向上できる
- 採用力が向上できる
それぞれ詳しく解説します。
4-1. 節税効果が期待できる
福利厚生と認められた場合、福利厚生費として経費計上できるため、節税効果が期待できます。福利厚生費とは、従業員のために給与以外で支出した費用を処理する勘定科目です。
福利厚生費として認められるには、以下の3つを満たす必要があります。
- 社内規定で整備されている
- 従業員全体が対象となっている
- 社会通念上妥当な範囲の支出金額である
上記を満たさないものは、導入したとしても経費にならないため気をつけましょう。
関連記事:福利厚生費とは?福利厚生の種類や計上する際の要件も解説
4-2. 従業員の健康を維持できる
福利厚生の内容によっては、従業員の健康維持を図れます。健康被害を予防する制度や治療に関する制度を設けることで、従業員の健康状態が悪くなることを防げるためです。
健康被害を予防するなら、「無理な業務により体調を崩さないよう休暇を自由に取れるようにする」などの施策が効果的といえます。
「体調を崩した際は医療費を全額負担する」など、従業員が無理なく治療を受けられる施策を取り入れることも大切です。
4-3. 企業の社会的信頼性を向上できる
福利厚生を導入することで、企業の社会的信頼性を向上できます。
福利厚生を導入するだけでも「優良な企業」と認識されたり、従業員からの不満が減ったりする効果が期待できるためです。
従業員からの不満を減らすためには、アンケートなどで意見を確認しつつ、要求に合った施策を導入する工夫が必要です。
4-4. 生産性を向上できる
福利厚生を導入すると、生産性の向上が期待できます。
内容によっては心身共に無理のないライフワークを実現でき、良好なコンディションを維持した状態で仕事に取り組めるためです。
生産性の向上を目的とした福利厚生は、以下が挙げられます。
| 福利厚生 | 効果 |
| 自由に休暇を取得できる制度 | 仕事と休日のメリハリがつく |
| スポーツクラブを安価で利用できる制度 | 休日に利用することで心身ともにスッキリした状態で仕事に取り組める |
| 業務の一環としてヨガを取り入れる制度 | 精神的な不調の解決や健康状態の維持を図れる |
仕事のメリハリをつけたり心身のケアをおこなう制度を設けたりすることで、従業員の意欲を高めつつコンディションの維持にもつながります。
4-5. 従業員の満足度を向上できる
福利厚生の導入により、従業員の満足度を向上させられます。従業員にとって得となる制度が充実することで、職場の居心地が良くなるためです。
「周りを気にせず有給休暇を取得できる制度」を導入すれば、働くときは働き休日は休むといったメリハリもつくでしょう。
結果として生産性や業績向上の効果も期待できます。
4-6. 採用力が向上できる
福利厚生を導入すると、採用力が向上します。企業のアピールポイントとなり、優秀な人材が応募しやすくなるためです。
ただ導入するだけでは、採用力の向上につながりません。
「オフィスから徒歩10分以内に住む従業員に家賃を半分補助する」など、従業員が喜ぶ施策を検討したうえで導入する必要があります。
5. 福利厚生の2つのデメリット


福利厚生のデメリットは、次のとおりです。
- 費用がかかる
- モチベーション低下のおそれがある
それぞれ詳しく解説します。
5-1. 費用がかかる
福利厚生を導入すると、費用がかかります。節税できる経費がある一方で、運営や管理に人的コストが発生するためです。
福利厚生を充実させると従業員の利点が多くなりますが、企業の負担も増えていくことも覚えておく必要があります。
5-2. モチベーション低下のおそれがある
福利厚生を導入すると、結果的に従業員のモチベーションが低下するおそれがあります。
すべての福利厚生を継続できるわけではなく、場合によっては廃止しなければいけない制度も出てくるためです。
今まで活用していた施策がなくなることで、従業員によっては意欲の低下につながります。
福利厚生を廃止する場合は、従業員へしっかりと事情を説明して理解してもらうことが大切です。
6. 福利厚生の4つの注意点


福利厚生の注意点は、次のとおりです。
- 目的を明確にする
- 従業員の意見を確認する
- 社内へ周知する
- 定期的に制度の見直しをおこなう
それぞれ詳しく解説します。
6-1. 目的を明確にする
福利厚生を導入する際は、目的を明確にします。目的が不明瞭なまま導入すると、従業員がどのような場面で活用すべきかわからず、利用されなくなるおそれがあるためです。
事前にどのような目的で導入するのかを説明し、導入することで従業員にもたらす利点をイメージできるようにする必要があります。
6-2. 従業員の意見を確認する
福利厚生を導入する際は、従業員の意見やニーズを確認しましょう。ほかの企業で人気がある施策でも、自社の従業員に合っているかはわからないためです。
事前にアンケートやヒアリングなどを実施し、従業員のニーズを把握してから導入を検討しましょう。
6-3. 社内へ周知する
福利厚生を導入する際は事前に社内全体へ周知しましょう。周知を怠ると、従業員が存在を知らないことで利用できないおそれがあります。
ただ存在を伝えるのではなく、目的や内容、利用方法など詳細に説明することが大切です。導入した制度をしっかり活用してもらうために、説明会を実施するのも効果的といえます。
6-4. 定期的に制度の見直しをおこなう
福利厚生を導入したら、定期的に制度の見直しをおこないます。社内のニーズと福利厚生の内容にギャップがあると、従業員が利用しなかったり不満を覚えたりする原因になるためです。
従業員の利用率が高ければ変更の必要はありません。しかし、低い場合は改善を図り、より良い福利厚生制度となるようにしましょう。
定期的にアンケートなどで従業員の意見を聞き、利用率を高めるために改善することが大切です。
7. 福利厚生を充実させて働きやすい環境を整えよう


福利厚生には、節税効果や社会的信頼の向上、生産性の向上などの効果が期待できます。法定外福利厚生として、独自のユニークな制度を導入している企業も多いです。
福利厚生を導入する際は、目的を明確にしたり定期的に見直したりする必要があります。
従業員が活用できるような制度を取り入れられれば、従業員だけでなく企業も利益を得られるでしょう。
物価高騰が続くいま、従業員の生活を支える施策の重要性が増しています。一方で、企業としては人的資本への投資をいかに最適化するかが問われています。
本資料では、最新の社会情勢を踏まえ、これからの時代に求められる福利厚生のあり方と、具体的なサービス選定のポイントを解説します。
◆この資料でわかること
- なぜ今、福利厚生が「人的資本への投資」として注目されるのか
- 多様化する従業員ニーズに、世代や地域の格差なく応える方法
- 賃上げとは違う、従業員の生活コストを実質的に下げる選択肢
これらの疑問に一つでも不安を感じた方へ。人的資本経営のヒントとして参考になりますので、ぜひこちらから資料をダウンロードしてご活用ください。
人事・労務管理のピックアップ
-


【採用担当者必読】入社手続きのフロー完全マニュアルを公開
人事・労務管理公開日:2020.12.09更新日:2026.01.30
-


人事総務担当がおこなう退職手続きの流れや注意すべきトラブルとは
人事・労務管理公開日:2022.03.12更新日:2025.09.25
-


雇用契約を更新しない場合の正当な理由とは?伝え方・通知方法も紹介!
人事・労務管理公開日:2020.11.18更新日:2025.10.09
-


社会保険適用拡大とは?2024年10月の法改正や今後の動向、50人以下の企業の対応を解説
人事・労務管理公開日:2022.04.14更新日:2025.10.09
-


健康保険厚生年金保険被保険者資格取得届とは?手続きの流れや注意点
人事・労務管理公開日:2022.01.17更新日:2025.11.21
-


同一労働同一賃金で中小企業が受ける影響や対応しない場合のリスクを解説
人事・労務管理公開日:2022.01.22更新日:2025.08.26