源泉徴収票の作成方法や項目別の記載内容をわかりやすく解説
更新日: 2024.4.5
公開日: 2022.8.24
OHSUGI
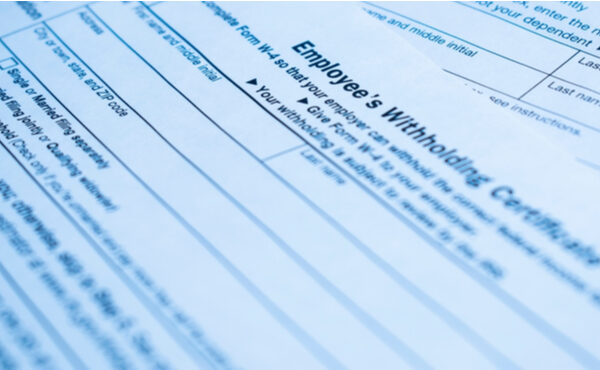
一般的に源泉徴収票は年末に作成されますが、年末はさまざまな業務が重なる忙しい時期です。
そのため、源泉徴収票の作成方法や作成手順を事前にきちんと把握し、スムーズで間違いのない作成ができるように準備をしておきましょう。
本記事では、源泉徴収票の作成方法や作成手順、源泉徴収票を作成するときの注意点について説明します。
「年末調整のガイドブック」を無料配布中!
「年末調整が複雑で、いまいちよく理解できていない」「対応しているが、抜け漏れがないか不安」というお悩みをおもちではありませんか?
当サイトでは、そのような方に向け、年末調整に必要な書類から記載例、計算のやり方・提出方法まで、年末調整業務を図解でわかりやすくまとめた資料を無料で配布しております。
給与支払報告書や法定調書など、年末調整後に人事が対応すべきことも解説しているため、年末調整業務に不安のある方や、抜け漏れなく対応したい方は、こちらから資料をダウンロードしてご活用ください。
1. 源泉徴収票の作成方法

源泉徴収票を作成する方法としては、主に以下のような方法が挙げられます。
- Excel
- 給与計算ソフト
- e-Tax
- 税理士等の専門家に委託
それぞれの方法について、詳しく説明します。
1-1. Excel
Excelを利用して源泉徴収票を作成する場合は、国税庁が公開している源泉徴収票のテンプレートを使うのがおすすめです。インターネット上で公開されている無料のフォーマットを利用できるため、ハードルの低い作成方法です。
無料で利用できる点は便利ですが、Excelに組み込まれている式は本当に正しいか、最新の税制に対応しているかなどは保障されていません。利用する際はそうした確認を自分の目でもおこなうようにしましょう。
1-2. 給与計算ソフト
給与計算ソフトは源泉徴収票の作成に非常に便利です。
源泉徴収で算出した金額をもとにして、従業員ごとに源泉徴収票を自動生成する機能がついている給与計算ソフトもあります。そうした機能を有効活用すると、正確で効率的な作成ができます。
毎月の勤怠管理や給与計算にも利用できるので、そういった部分を効率化できる点と導入コストを天秤にかけて、導入すべきかどうかを判断しましょう。
1-3. e-Tax
国税庁が配布する国税電子報告システム・納税システム「e-Tax」を利用して、源泉徴収票を作成することもできます。
e-Taxで作成した源泉徴収票は、電子データで従業員に配布することが可能です。
「利用者識別番号」および「電子証明書」を事前に取得しておかなければならないことには、注意しておきましょう。
なお、e-Taxの場合、利用できるブラウザに制限があります。会計ソフトのなかにはスマートフォンでそのままデータを閲覧できるものもあるため、社内の状況に応じて選択するのがおすすめです。
1-4. 税理士等の専門家に委託
自分で源泉徴収票を作成せずに、税理士等の専門家に委託するという方法も考えられます。
経理業務についてまだ不慣れだったり、業務で忙しかったりといった場合は、専門家への委託も検討してみましょう。
2. 源泉徴収票に記載する項目
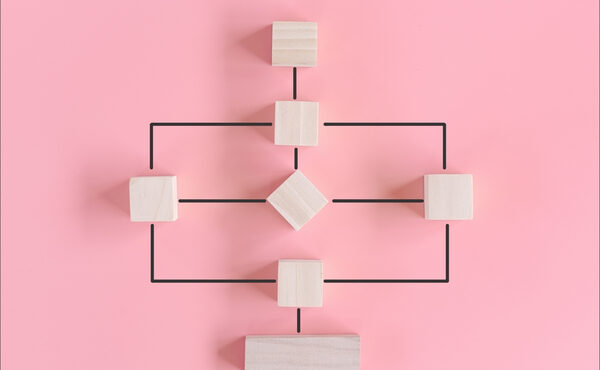
源泉徴収票に記載が必要な項目としては、以下のようなものが挙げられます。
- 支払いを受ける者
- 種別・給与(支払額、税額など)
- 配偶者・扶養親族の有無など
- 社会保険料・生命保険・住宅ローン
- 控除対象者氏名など
- 未成年の各欄、中途就・退職
- 支払者
記載すべき順番が決められているわけではありませんが、今回は上から順に各項目の書き方について説明します。
2-1. ①支払いを受ける者
支払いを受ける者に関しては「住所または居所」「個人番号(マイナンバー)」「氏名」を記載する必要があります。
氏名に関しては会社の役員である場合には役職名を記載して、役員ではない場合は職務の名称(営業部長など)を併記しましょう。
なお、源泉徴収票は会社で保管しておくものと従業員本人に渡すものがありますが、後者には個人番号(マイナンバー)の記載は必要ありません。
2-2. ②種別・給与(支払額、税額など)
給与等の種別(給料、賞与、俸給など)、支払金額、給与所得控除後の金額、所得控除の額の合計額を記載します。
所得控除にはさまざまな種類の控除がありますが、医療費控除・寄附金控除・雑損控除を受けたい場合は、従業員本人に確定申告をしてもらう必要があることには注意しておきましょう。なお、寄附金控除のなかでもふるさと納税ワンストップ特例制度であれば年末調整での対応が可能です。
また、配偶者控除と配偶者特別控除は重複して適用することができません。
2-3. ③配偶者・扶養親族の有無など
配偶者・扶養親族の有無では、「控除対象配偶者」「従有・従無」「老人」「配偶者特別控除」「控除対象扶養者の数」「16歳未満扶養親族の数」「障害者の数」「非居住者である親族の数」を記載します。
配偶者および扶養親族の有無やその構成などによって記載すべき部分、内容が異なるので、正確に記載するよう注意しましょう。
2-4. ④社会保険料・生命保険・住宅ローン
社会保険料・生命保険・住宅ローンでは、各種保険の保険料を記載します。
住宅ローンの初年度は源泉徴収票にも記載されない点に注意しましょう。従業員本人による確定申告が必要になるため、説明しておくと親切かもしれません。
なお、この欄にある項目はすべて記載する必要があるわけではなく、対象者によって記載する欄が異なります。加入している保険の種類や数によっては細かい記載が必要になるため、抜けや間違いが発生しないように注意喚起することも大切です。
2-5. ⑤控除対象者氏名など
控除対象配偶者、控除対象扶養者、16歳未満の扶養親族者それぞれの氏名、フリガナ、個人番号(マイナンバー)を記載します。
控除対象となる配偶者や扶養者がいない場合は、こちらは記載する必要はありません。
2-6. ⑥未成年の各欄、中途就・退職
未成年の各欄には、その受給者について該当する事項がある場合には「○」を付けます。
年の途中で就職や退職をした場合には該当欄に「○」を付けて、就職もしくは退職した日の年月日を記載します。
2-7. ⑦支払者
給与等の支払いをする会社や個人事業主などの住所または所在地、氏名または名称、電話番号、個人番号(マイナンバー)または法人番号を記載します。
3. 源泉徴収票を作成するときの注意点

源泉徴収票の作成は複雑ではありませんが、間違いがあってはならない書類です。以下の点に注意して、計算ミスや記入漏れが発生しないように作成しましょう。
3-1. 金額計算や記載に間違いがないか確認する
源泉徴収票は従業員に配布するだけでなく、税務署や市区町村に提出する重要書類です。
個人情報のほかに、所得税を決定する支払金額や源泉徴収税額は特に重要な項目です。計算間違いがないか確認し、作成したあともチェックするなど二重チェックの体制を取っておくと安心です。
3-2. 通勤手当は支給金額に含めない
給与や賞与など、従業員に対して支払った金額は、基本的に源泉徴収の対象となります。
ただし、通勤手当は非課税扱いになるため、支給金額に含めてはいけません。
3-3. 摘要欄に記入漏れがないように気をつける
源泉徴収票の摘要欄には、扶養親族が5人以上いる場合に関係性の記載をしたり、所得金額調整控除がある場合はその要件に応じて氏名を記載したりする必要があるなど、記載が必須であるケースがあります。
条件に当てはまるケースは多くありませんが、必要な場合に記入漏れをしないように注意しましょう。
3-4. マイナンバーの記載忘れをしない
従業員に配布する源泉徴収票には、マイナンバーの記載は必要ありません。しかし、税務署に提出する源泉徴収票には、マイナンバーの記載が必要です。誤って記載しないまま提出しないように注意しましょう。
その他の会社や個人情報も抜けや記入ミスがないように十分に気をつけてください。
3-5. 従業員の住所は翌年1月1日を想定して書く
従業員の住所を記載する欄には、原則として翌年の1月1日時点での住所を記載します。
従業員の住所は課税のために使われるため、翌年の情報が必要だからです。引っ越し予定がある従業員がいる場合は注意しましょう。
3-6. 電子データで交付する場合は電子証明書の添付が望ましい
源泉徴収票は、紙で発行してもよいですし電子データで交付してもかまいません。
ただし、電子データで交付する場合は正規に交付したものであることを証明するために、電子署名を付した電子証明書を添付することが望ましいです。
電子証明書を取得するためには、法務省が提供する専用ソフトウェアをインストールする必要があります。
4. 源泉徴収票を正しく作成してスムーズかつ正確な納税に役立てよう

源泉徴収票は記載すべき項目が非常に多いですが、税金などに関わる非常に重要な書類です。
記入漏れや計算ミスがないように慎重に作成し、チェックもしっかりする流れを作っておくようにしましょう。
また、源泉徴収票を作成する手間を省きたい、人員が足りないなどの問題がある場合は、効率的に作成・提出ができる給与計算ソフトやe-Taxを活用するとよいかもしれません。
税理士などの専門家に委託する方法も含めて、無理なく正確な書類が作れるようにしましょう。
「年末調整のガイドブック」を無料配布中!
「年末調整が複雑で、いまいちよく理解できていない」「対応しているが、抜け漏れがないか不安」というお悩みをおもちではありませんか?
当サイトでは、そのような方に向け、年末調整に必要な書類から記載例、計算のやり方・提出方法まで、年末調整業務を図解でわかりやすくまとめた資料を無料で配布しております。
給与支払報告書や法定調書など、年末調整後に人事が対応すべきことも解説しているため、年末調整業務に不安のある方や、抜け漏れなく対応したい方は、こちらから資料をダウンロードしてご活用ください。
人事・労務管理のピックアップ
-

【採用担当者必読】入社手続きのフロー完全マニュアルを公開
人事・労務管理
公開日:2020.12.09更新日:2024.03.08
-

人事総務担当が行う退職手続きの流れや注意すべきトラブルとは
人事・労務管理
公開日:2022.03.12更新日:2024.06.11
-

雇用契約を更新しない場合の正当な理由とは?通達方法も解説!
人事・労務管理
公開日:2020.11.18更新日:2024.07.10
-

法改正による社会保険適用拡大とは?対象や対応方法をわかりやすく解説
人事・労務管理
公開日:2022.04.14更新日:2024.06.12
-

健康保険厚生年金保険被保険者資格取得届とは?手続きの流れや注意点
人事・労務管理
公開日:2022.01.17更新日:2024.07.02
-

同一労働同一賃金で中小企業が受ける影響や対応しない場合のリスクを解説
人事・労務管理
公開日:2022.01.22更新日:2024.05.08




























