離婚後の年末調整で気をつけるべき6つのポイント
更新日: 2024.7.16
公開日: 2021.11.5
OHSUGI

離婚すると年末調整で配偶者控除などの所得控除が受けられなくなるなどのデメリットがあるため、配偶者の有無を申請した際に離婚が会社にばれないようにしたいと考える人もいるでしょう。
しかし、年末調整がきっかけで従業員の離婚が発覚するケースも珍しくありません。
離婚したことは、会社に黙っていてもよいのでしょうか。また、従業員が会社に離婚を報告する必要はあるのでしょうか。
今回は離婚をした場合に年末調整で気をつけるべきポイントを解説します。
目次
「年末調整のガイドブック」を無料配布中!
「年末調整が複雑で、いまいちよく理解できていない」「対応しているが、抜け漏れがないか不安」というお悩みをおもちではありませんか?
当サイトでは、そのような方に向け、年末調整に必要な書類から記載例、計算のやり方・提出方法まで、年末調整業務を図解でわかりやすくまとめた資料を無料で配布しております。
給与支払報告書や法定調書など、年末調整後に人事が対応すべきことも解説しているため、年末調整業務に不安のある方や、抜け漏れなく対応したい方は、こちらから資料をダウンロードしてご活用ください。
1. 年末調整で利用する控除の種類によって離婚が発覚する可能性がある

年末調整ではさまざまな控除を受けることで節税になります。しかし、その控除の中には配偶者や扶養親族がいることが利用条件となっているものもあります。
従業員の離婚が発覚するきっかけとなるものは次のようなケースです。
- 苗字が変わった
- 家族手当を受け取っている
- 既婚者用の社宅に住んでいる
- 扶養家族が変更になる
- 転居によって通勤手当に変更がある
一方で次のようなケースは離婚が発覚しづらいでしょう。
- 子どもがいない
- 子どもが16歳未満または子どもが働いていて扶養控除を受けていなかった
- 夫婦が共働きだったが、配偶者控除を受けていなかった
これは年末調整の際に提出が必要な「扶養控除等(異動)申告書」に配偶者や扶養親族の情報を記載するからです。
もともと配偶者控除と扶養控除を受けていなかった場合、離婚しても記載内容に変更がないため、年末調整がきっかけで離婚が発覚することはないでしょう。
1-1. 会社に離婚を報告する義務はないが給与や税金に影響がある場合は必要
会社の就業規則などで報告が義務とされていない限りは離婚を報告する義務はありません。しかし、上にあるように離婚をすると支給されなくなる手当や控除を受けている場合は、給与や税金に影響があるため報告する必要があります。
離婚したことを隠して家族手当を受け取っていたりすると、不当受給などトラブルの原因となる可能性もあるため、注意が必要です。
なお、離婚したことを報告するのは、人事部と経理部など手当や税金に関する手続きをおこなう部署に限定されます。中には「他の従業員にも離婚したことがばれるのでは」と心配する人もいるため、従業員から離婚の報告を受けた際はしっかり考慮して対応しましょう。
2. 離婚後の年末調整で気をつけること

離婚後の年末調整における注意点は書き方だけでなく、以下の6つが挙げられます。
2-1. 離婚した後の年末調整では受けられなくなる控除がある
離婚をした場合、配偶者や扶養する子どもがいることで受けられた所得控除が受けられなくなる可能性があります。
| 受けられなくなる所得控除の種類 | 受けられなくなる所得控除額 |
| 配偶者控除 | 38万円 |
| 配偶者特別控除 | 配偶者の所得額によって異なる |
| 扶養控除(16歳以上の子どもで給与収入103万円以下) | 38万円 |
| 扶養控除(19歳~22歳の子どもを扶養している場合) | 63万円 |
離婚しても16歳以上の子どもの親権をもち、子どもと生計を共にしている場合は扶養控除が受けられます。
また、子どもと別居していても養育を常におこなっている場合は扶養控除の適用となるケースもあります。ただし、その場合も扶養控除が適用されるのは父側・母側どちらか片方だけです。
2-2. 生命保険金の受取人を変更する
生命保険料控除を受けるには全ての保険金受取人が契約者本人か配偶者、その他の親族である必要があります。
保険金受取人が配偶者だった場合、離婚したら保険契約を変更して受取人を6親等以内の血族に変更します。子どもに変更するのが一般的です。
変更せずにそのままにしておくと、離婚後に支払った保険料については生命保険料控除の対象外となります。
2-3. 離婚したことで受けられる控除もある
離婚したことで受けられなくなる控除もある一方で、離婚したから受けられるようになる控除もあります。
- ひとり親控除
- 寡婦控除(女性のみ)
ひとり親控除・寡婦控除(女性のみ)の存在は知っていても、内容まで理解していない方もいらっしゃるのではないでしょうか。
控除金額や必要な申請書を間違えると年末調整にも影響が出るため、しっかり把握しておく必要があります。
当サイトでは、それぞれがどのような控除か具体的な内容を知りたい方に向けて年末調整の控除について金額や条件をまとめた資料を無料でお配りしています。
年末調整の控除に関してミスがないか確認したい方は、こちらの「年末調整ガイドブック」をダウンロードしてご確認ください。
2-4. 扶養控除がなくなることで追徴される可能性がある
離婚して子どもなど扶養親族がいなくなった場合、源泉徴収額が適正な所得税額を下回り、不足分としていくらか追徴される可能性があります。
2-5. 離婚協議中や別居の状態では配偶者控除や扶養控除が受けられる
配偶者控除や扶養控除が受けられなくなる可能性があるのは、法的に離婚が成立した後です。離婚協議中であったり、別居中の場合、12月31日時点で婚姻状態が継続されていて配偶者や子どもを扶養していれば、それぞれの控除が適用されます。
逆にまだ同居をしていても、離婚が成立していれば控除は受けられません。
自分の両親や自身が親権を持つ子どもについては、離婚後も扶養控除が適用されます。
2-6. 控除を最大限適用させるには年明け後に離婚をしたほうがいい
年末調整における控除適用の判断はその年の12月31日の現況によっておこなわれます。
12月31日までに離婚をすると、その年の配偶者控除や子どもの扶養控除が受けられなくなりますが、1月1日以降に離婚をすれば控除が適用される仕組みです。
例えば、2021年分の所得控除は2021年12月31日までに離婚をすれば適用されなくなります。しかし、2022年1月1日以降に離婚すれば2021年分に関しては適用されます。
3. ひとり親控除と寡婦控除について知っておきたいポイント

2020年に従来の寡夫控除が改正されて「ひとり親控除」の制度が新設されました。ひとり親控除は離婚や死別だけではなく、既婚・未婚に関係なく、全てのひとり親家庭に対して控除が適用されるものです。
3-1. ひとり親控除の対象となる人
ひとり親控除の対象になる人は次の要件を全て満たしている人です。
- 事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる一定の相手がいない
- 生計を一にする子がいる
- 合計所得金額が500万円以下(給与収入678万円以下)である
1と2にある人と子は、その年の総所得金額が48万円以下で、他の人の同一生計配偶者または扶養親族になっていない人のみに限られます。
3-2. ひとり親控除は合計65万円の所得控除が受けられる
ひとり親控除の要件に全てあてはまる人は、年末調整時に35万円、住民税で30万円の所得控除が受けられます。
また、女性の場合はひとり親控除で35万円の所得控除が受けられます。
3-3. 子ども以外の扶養親族がいる離婚した女性は寡婦控除が受けられる
離婚した女性に子ども以外の扶養親族がいる場合は、いずれかの条件に該当すれば寡婦控除が適用されます。
- 夫と離婚後に婚姻をしておらず、扶養親族がいて、合計所得金額が500万円以下(給与収入678万円以下)である
- 夫と死別後に婚姻をしていない、または夫が生死不明で合計所得金額が500万円以下(給与収入678万円以下)である
この場合の所得控除額は年末調整で27万円、住民税で26万円です。
3-4. ひとり親控除・寡婦控除を受けるには年末調整で扶養控除申請書を提出する
年末調整でひとり親控除や寡婦控除を受けるには「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を記載し、給与支払者に提出する必要があります。
「C 障害者、寡婦、寡夫または勤労学生」の欄にある「ひとり親」または「寡婦」の所のチェックボックスにチェックを入れます。
4. 年末調整後に離婚した場合の対応
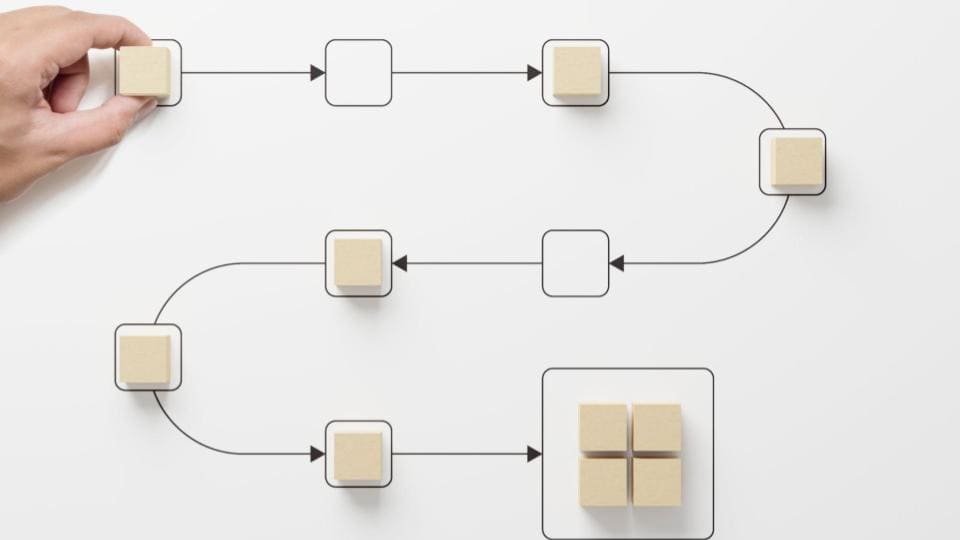
年末調整後に離婚した場合には次のような2つの対応を取りましょう。
- 年末調整をやり直す
- 確定申告をする
源泉徴収票を従業員に発行するまでの翌年の1月31日までであれば、再年調として再度年末調整が可能です。1月31日を過ぎてしまっているのであれば、従業員自らが確定申告をする必要があります。従業員による確定申告は手間がかかるため、担当者は年末調整後に離婚の旨を聞いたら、再年調可能なタイミングであるかを確認しましょう。
5. 離婚後の年末調整では所得控除の変化に注意

離婚後の年末調整では、配偶者や扶養する子どもがいなくなることで、所得控除額に変化が生じる可能性があります。会社に離婚したことを報告せずにそのまま控除を受けたり手当を受け取ると、トラブルに発展する可能性があるため注意が必要です。
離婚した従業員は、ひとり親控除や寡婦控除などの所得控除が受けられる可能性もあります。担当者は年末調整で要件を確認することと、給与所得者の扶養控除等(異動)申告書にしっかり記載して提出するよう、全従業員に周知しましょう。
「年末調整のガイドブック」を無料配布中!
「年末調整が複雑で、いまいちよく理解できていない」「対応しているが、抜け漏れがないか不安」というお悩みをおもちではありませんか?
当サイトでは、そのような方に向け、年末調整に必要な書類から記載例、計算のやり方・提出方法まで、年末調整業務を図解でわかりやすくまとめた資料を無料で配布しております。
給与支払報告書や法定調書など、年末調整後に人事が対応すべきことも解説しているため、年末調整業務に不安のある方や、抜け漏れなく対応したい方は、こちらから資料をダウンロードしてご活用ください。
人事・労務管理のピックアップ
-

【採用担当者必読】入社手続きのフロー完全マニュアルを公開
人事・労務管理
公開日:2020.12.09更新日:2024.03.08
-

人事総務担当が行う退職手続きの流れや注意すべきトラブルとは
人事・労務管理
公開日:2022.03.12更新日:2024.06.11
-

雇用契約を更新しない場合の正当な理由とは?通達方法も解説!
人事・労務管理
公開日:2020.11.18更新日:2024.07.10
-

法改正による社会保険適用拡大とは?対象や対応方法をわかりやすく解説
人事・労務管理
公開日:2022.04.14更新日:2024.06.12
-

健康保険厚生年金保険被保険者資格取得届とは?手続きの流れや注意点
人事・労務管理
公開日:2022.01.17更新日:2024.07.02
-

同一労働同一賃金で中小企業が受ける影響や対応しない場合のリスクを解説
人事・労務管理
公開日:2022.01.22更新日:2024.05.08




























