勘定科目「消耗品費」に仕訳すべき品目や摘要の書き方を解説
更新日: 2024.5.8
公開日: 2022.9.9
MEGURO

経理業務で扱う帳簿には多くの勘定科目があり、状況に応じて適切に使い分けることが重要です。
中でも、消耗品費に振り分ける取引内容は多岐にわたるため、消耗品費に分類する取引の具体的な内容を把握しておきましょう。
消耗品費を計上するときには、摘要欄に具体的な取引内容を記載しておく必要があります。
本記事では、勘定科目のひとつである消耗品費の扱い方について詳しく解説します。
目次
86個の勘定科目と仕訳例をまとめて解説
「経理担当になってまだ日が浅く、会計知識をしっかりつけたい!」
「会計の基礎知識である勘定科目や仕訳がそもそもわからない」
「毎回ネットや本で調べていると時間がかかって困る」
などなど会計の理解を深める際に前提の基礎知識となる勘定科目や仕訳がよくわからない方もいらっしゃるでしょう。
そこで当サイトでは、勘定科目や仕訳に関する基本知識と各科目ごとの仕訳例を網羅的にまとめた資料を無料で配布しております。 会計の理解を深めたい方には必須の知識となりますので、ぜひ資料をダウンロードしてご覧ください。
1. 勘定科目「消耗品費」に仕訳すべき品目
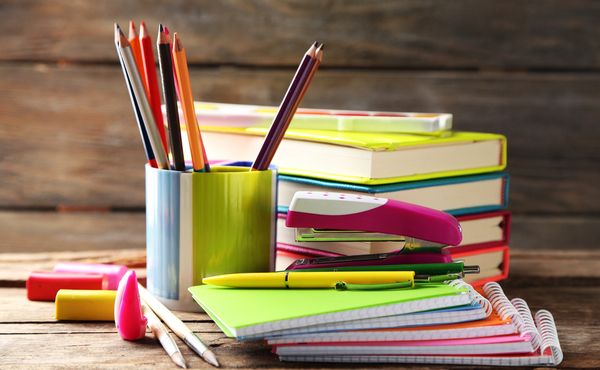
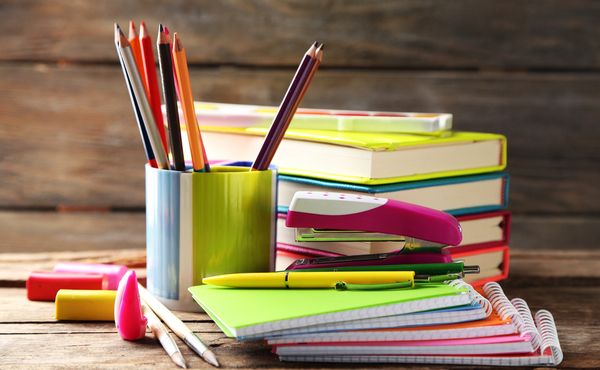
経理上の勘定科目の1つである消耗品費には、オフィスで使用するさまざまな消耗品の取引を記載します。
条件としては、使用可能期間が1年未満であること、または購入金額が10万円未満であることが消耗品費として扱える品目です。[注1]
具体的には、以下のようなものを購入したときに消耗品費として経費に計上できます。
[注1]消耗品費|国税庁
関連記事:消耗品費はいくらまで経費計上できる?上限や雑費との違いを解説
1-1. 事務用品
オフィスの事務用品のほとんどは経理上、消耗品費に分類されます。
事務用品の代表例として、ボールペンやノート、ファイルやバインダーなどが挙げられます。
また、名刺や印鑑類、請求書や領収書などの伝票類、コピー用紙やFAX用紙なども事務用品に分類できます。
オフィスでは事務用品をまとめて購入することもあります。
まとめ買いしたときには「ボールペン等」といったように、最も金額が高いものや量の多いものを摘要欄に記載しておきます。
1-2. 日用品
オフィスで仕事をするにあたっては、ティッシュ類やゴミ袋、洗剤などのこまごまとした日用品も必要になります。
これらの品目も消耗品費として処理できます。
ほかに、社内用のお茶類、電化製品に使用する電池類、電球や蛍光灯なども消耗品費に分類できます。
1-3. パソコン用品
パソコンやその周辺機器なども消耗品費として計上できます。
ただし消耗品費に振り分けられるのは、取得価格が10万円未満の品目に限られます。
例えば、パソコンのキーボードやマウス、ケーブルや記録媒体などのアイテムはパソコン用品に分類できます。
ほかに、パソコンで利用するソフトウェアやライセンスの費用も消耗品費として計上することが可能です。
1-4. 機器類、電化製品
オフィスで使う電話やFAX機器、カメラなどの機器も、取得価格が10万円未満であれば消耗品費として扱えます。
また、湯沸かしポットやアイロンなど業務上必要となる家電製品も消耗品費として計上するのが一般的です。
2. 勘定科目「消耗品費」の摘要欄に記入すべき内容


経理で処理する帳簿には仕訳帳や総勘定元帳、現金出納帳などさまざまな種類があります。
どの帳簿にも、摘要と呼ばれる項目が設けられています。
摘要とは、対象となるものの要点を書き出すことをいいます。
帳簿において勘定科目を使って処理するのみでは、取引の内容が分かりにくくなってしまうことがあります。
摘要欄に具体的な内容を記載することで、取引内容を把握しやすくなります。
消耗品費を計上する際に摘要欄を使用する目的は、どのような消耗品に対していくらの費用を使ったのかを明らかにするという点にあります。
借方を消耗品費、貸方を現金として計上するだけでは、どのような目的で何を購入したのかを把握することができません。
あとあと具体的な取引の内容を思い出したり調べたりするのは大きな手間となってしまいます。
こういった手間を省くために、摘要欄に具体的な取引内容を記載することが求められるのです。
摘要欄に取引内容を記載することは税法にも定められています。
税法では、取引の内容を整然とかつ明瞭に記録するよう指示しています。
摘要欄に具体的な記載がない場合、税務調査などの外部チェックの際に不利益を被る可能性があります。
摘要欄を埋めておけば帳簿の内容が分かりやすくなり、調査をスムーズに進めることができるのです。
消耗品費の摘要欄には税法の定め通り、取引の内容を端的かつ分かりやすく記載します。
多くの場合、領収書には「文具代として」「事務用品代として」と簡略に記載されますが、帳簿の摘要欄の記載内容はこれだけでは不十分です。
消耗品費を計上したときには、支払先の店舗や購入した商品の種類を記載しておけば問題ありません。
必要に応じて購入数やその他の情報についても書き添えておきましょう。
例えば、ボールペンを30本購入したときには「○○商店 ボールペン 30本」といったように摘要欄を埋めておきます。
こまごまとしたものを購入したときには「ティッシュ等」など主な購入品目を書いておくだけでも問題ありません。
その他、日用品であれば「ゴミ袋」「電球」など、機器類であれば「パソコン本体」「カメラ」といったように、品目を具体的に記載することが肝心です。
手書きの帳簿の場合、摘要欄の中で勘定科目と取引の具体的な情報を記載するのが一般的でした。
しかし近年では会計ソフトやクラウドシステムを使って帳簿を作成する企業が増加しています。
電子データの帳簿では、勘定科目と摘要を別々に入力することがほとんどです。
専用ソフトや専用システムでは、各勘定科目を集計したりソートしたりといった処理が可能です。
しかし、摘要欄に情報が記載されていると情報の集計がしにくくなってしまいます。
そのため、デジタル上で勘定科目を処理する際には摘要欄が別の場所に設置されるのです。
使用する帳簿の種類に合わせて、最適な情報を記載するよう心がけましょう。
関連記事:関連記事:消耗品費とは?具体例を挙げてわかりやすく解説
3. 勘定科目「消耗品費」に仕訳するときの注意点


消耗品費の勘定科目はよく使うため、適切な運用を心がけることが大切です。
帳簿の記載内容に不審な点がある場合、税務署の調査の対象となってしまうこともあるので注意しましょう。
ここからは、消耗品費の仕訳をするときに気をつけたいポイントをチェックしていきましょう。
3-1. 取引があったときにはこまめに記載する
消耗品費の取引があったときには、こまめに記載しておきましょう。
あとからまとめて記帳しようとすると詳しい内容が分からなくなってしまうことがあります。
その日の取引が終わったあとには当日の差し引き状況を書き込み、残高に問題がないか確かめておくことが重要です。
3-2. 消耗品費に該当するか否かを都度確かめておく
消耗品費には幅広い項目が該当しますが、消耗品費として計上していいかどうかを確認しておくことも大切です。
例えば、ごみの処分費用や銀行の振込手数料といった取引は雑費に分類されます。
また、消耗品に分類されるものを購入した場合でも、取得費用が10万円を超えるときには消耗品として計上することができません。
消耗品費という勘定科目は使い勝手がいいものですが、さまざまな取引を消耗品費で処理していると消耗品費の金額が膨れ上がってしまいます。
場合によっては税務署の調査で指摘を受けることもあるので十分な注意が必要です。
関連記事:10万円以上の消耗品費を経費計上する方法を徹底解説
4. 消耗品費勘定科目は細かく記載!迷ったらチェックしよう


オフィスの経理では消耗品費の勘定科目を頻繁に使います。
しかし、消耗品に該当しないものを消耗品費として計上すると、あとあと消耗品費が膨れ上がってしまうことがあります。
また、帳簿を適切に記載しなかったために数字が合わなくなるなどの問題が発生するケースもあります。
消耗品の取引一つひとつはこまごまとしたものですが、帳簿に記帳する際には間違いが起きないよう注意深く扱うよう心がけたいものです。
該当するか迷った場合はそのまま記帳せず、チェックするようにしましょう。
86個の勘定科目と仕訳例をまとめて解説
「経理担当になってまだ日が浅く、会計知識をしっかりつけたい!」
「会計の基礎知識である勘定科目や仕訳がそもそもわからない」
「毎回ネットや本で調べていると時間がかかって困る」
などなど会計の理解を深める際に前提の基礎知識となる勘定科目や仕訳がよくわからない方もいらっしゃるでしょう。
そこで当サイトでは、勘定科目や仕訳に関する基本知識と各科目ごとの仕訳例を網羅的にまとめた資料を無料で配布しております。 会計の理解を深めたい方には必須の知識となりますので、ぜひ資料をダウンロードしてご覧ください。
経費管理のピックアップ
-


電子帳簿保存法に対応した領収書の管理・保存方法や注意点について解説
経費管理
公開日:2020.11.09更新日:2024.03.08
-


インボイス制度の登録申請が必要な人や提出期限の手順を解説
経費管理
公開日:2022.01.27更新日:2024.01.17
-


インボイス制度は導入延期されるの?明らかになった問題点
経費管理
公開日:2021.11.20更新日:2024.01.17
-


小口現金とクレジットカードを併用する方法とメリット
経費管理
公開日:2020.12.01更新日:2024.03.08
-

旅費精算や交通費精算を小口現金から振込にする理由
経費管理
公開日:2020.10.07更新日:2024.03.08
-


経費精算とは?今さら聞けない経費精算のやり方と注意点を大公開!
経費管理
公開日:2020.01.28更新日:2024.07.04





















