未払法人税等とは?仕訳方法や未払法人税等の具体例、計上の手順を解説
更新日: 2024.5.28
公開日: 2022.8.17
jinjer Blog 編集部
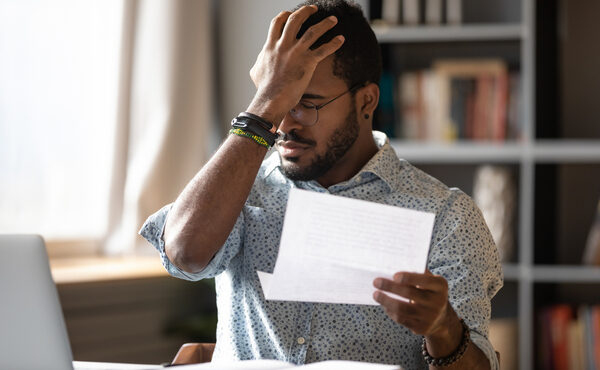
未払法人税等は仮払法人税等の絡みもあり、慣れていないと複雑に感じます。間違いのない処理をおこなうためには、どのような性質を持つものなのか、基本から知っておかなくてはいけません。
本記事では未払法人税等を使う場面や取り扱い方、実際の仕訳例などを分かりやすく解説しています。
経理に不慣れな人でも分かるように説明しますので、肩の力を抜いてぜひお読みください。
86個の勘定科目と仕訳例をまとめて解説
「経理担当になってまだ日が浅く、会計知識をしっかりつけたい!」
「会計の基礎知識である勘定科目や仕訳がそもそもわからない」
「毎回ネットや本で調べていると時間がかかって困る」
などなど会計の理解を深める際に前提の基礎知識となる勘定科目や仕訳がよくわからない方もいらっしゃるでしょう。
そこで当サイトでは、勘定科目や仕訳に関する基本知識と各科目ごとの仕訳例を網羅的にまとめた資料を無料で配布しております。 会計の理解を深めたい方には必須の知識となりますので、ぜひ資料をダウンロードしてご覧ください。
1. 未払法人税等とは?
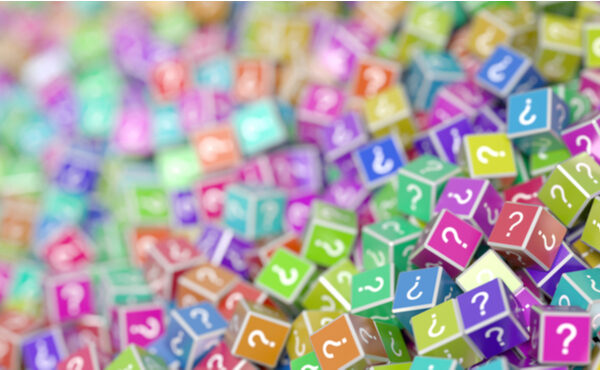
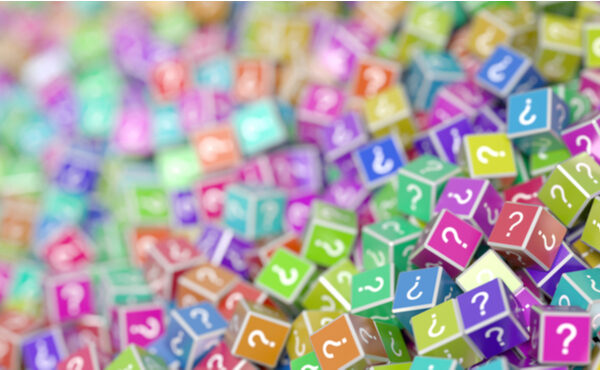
未払法人税等は勘定科目の1つです。取り扱い方法や分類を知っておきましょう。
1-1. 未払いの法人税がある場合に使う
未払いの法人税は名前の通り、未払い状態の法人税が残っている場合に使う勘定科目です。
会社がおこなう確定申告は、会社ごとに自由に決められる事業年度末日(決算日)から2ヵ月以内におこなわなくてはいけません。一方で確定申告をおこなう期間は決められています。そのため、決算により法人税の納税額が決まったあとも、申告・納税ができない期間が発生することが多いです。
その際に使うのが未払法人税等の勘定科目で、中間納付によって納付済みの分を差し引いた、確定法人税額を処理しておきます。
関連記事:法人税中間納付とは何か?納付の方法や計算方法、注意点を確認
1-2. 「負債」に分類される
未払法人税等は確定申告をおこなった後に支払うことが確定しています。そのため、分類は負債(流動負債)になります。
感覚的には「支払う予定のお金を避けておく」だけのように感じるため、負債という認識が薄くなる科目です。
仕訳方法・処理手順については次項以降で詳しく解説していますので、実際の処理を知りたい場合はお読みください。
2. 未払法人税等にあたる税


未払法人税等にあたる税金は次の3種類です。
- 法人税
- 法人住民税
- 法人事業税
同じ法人にかかる税金の中でも、消費税および地方消費税は未払法人税等にはあたりません。それぞれの特徴を解説します。
2-1. 法人税
会社の所得に課される税金で、決められた法人税率によって算出します。
中間申告で予定納税をおこなっている場合は、決算で確定した法人税額から、予定納税額を差し引いた金額が未払法人税等になります。
関連記事:法人税とは?特徴や対象となる法人、種類や計算方法を紹介
2-2. 法人住民税
法人住民税は地方自治体が会社に対して課す税金で、都道府県民税と市町村民税が含まれています。「法人税割」「均等割」どちらの場合も未払い分がある場合は、法人税と同様に未払法人税等として処理します。
2-3. 法人事業税
法人事業税も地方自治体が課す税金で、会社がおこなう事業活動に対して課されています。法人税・法人住民税と違う点は、損金として算入できることです。
取り扱いが特殊な税金ですが、こちらも未払い分がある場合は未払法人税等として処理する必要があります。
3. 未払法人税等の仕訳方法


未払法人税等を仕訳するときに必要な考え方と、実際の仕訳例を解説します。実際に仕訳をすることでより理解を深められます。
3-1. 未払法人税等の仕訳の基本
未払法人税等の仕訳が必要になるのは、決算時です。中間申告では必要ありません。
仕訳をおこなう際には、法人税・法人住民税・法人事業税の確定年税額が必要です。つまり、決算書が出来上がる前は仕訳ができません。
また、中間報告で一部の税金を納付している場合は、仮払法人税のことも考えて計上する必要があります。
通常、仮払法人税と未払法人税等を足した数字は、確定した法人税等の税額になるはずです。
しかし、会社の所得が想定よりも大幅に少ないと、中間納付の予定納税額の方が確定年税額よりも大きくなることがあります。未払法人税等がマイナスになった状態です。
その場合は未払法人税等の科目は使わず、上回っている分の予定納税額を未収金として処理します。
これは確定申告によって、納めすぎている予定納税額が還付されるからです。
3-2. 実際の仕訳例
予定納税額の取り扱いが少し複雑に感じる未払法人税等の仕訳を、実際におこなってみましょう。
未払法人税等がプラスの場合と、マイナスの場合両方の例を解説します。
次のような条件で未払法人税等がプラスだとします。
確定年税額:150万円
中間納付税額:70万円
この条件の場合の仕訳は次のとおりです。
| 借方 | 貸方 | ||
| 法人税等 | 1,500,000円 | 仮払法人税等 | 700,000円 |
| 未払法人税等 | 800,000円 | ||
確定した法人税額150万円を借方に記入し、中間申告で納付した70万円を貸方の仮払法人税等に記入します。
70万円はすでに支払っていることになるため、150万円から70万円を引いた80万円を未払法人税等として仕訳しています。
中間申告が不要でおこなっていない会社の場合は、未払法人税等のみを記載すればOKです。
一方、以下の条件で未払法人税等がマイナスだったケースをみてみましょう。
確定年税額:60万円
中間納付税額:70万円
| 借方 | 貸方 | ||
| 法人税等 | 600,000円 | 仮払法人税等 |
700,000円 |
| 未収金 | 100,000円 | ||
確定した法人税等の金額60万円を記載し、中間申告の納税分で多く支払っている10万円を未収金として処理します。
仮払法人税等は中間納付した金額の70万円をそのまま記載すればOKです。
借方の未収金を「未払法人税等」として処理しないように注意しましょう。未収金とする理由は、払いすぎた中間申告の税金が還付されるからです。
まだ回収できていないけど、将来的に入ってくるお金として仕訳します。
4. 未払法人税等を計上する際の流れ


最後に経理担当者様に向けて、未払法人税等を計上する流れやタイミングを解説します。決算や確定申告の時期は業務が煩雑になりますので、計上漏れが発生しないように注意しましょう。
4-1. 未払法人税等を計上するのは期末決算終了後
未払法人税等を計上するのは、期末決算で法人税等の金額が決まった後です。
未払法人税等は年に1回計上するものですので、中間決算時に計上する必要はありません。
実際に法人税等を納税するのは確定申告のタイミングです。
会社の年度末日によっては、計上と納税の間が長くなりますが、問題ありません。
4-2. 先に税引前当期純利益を確定させる
税引前当期純利(税引前利益)とは、税金を引く前の会社の利益のことをいいます。法人税等を求める際に必要であるため、まずはこの金額を確定させなくてはいけません。
税引前当期純利を求めるには、減価償却費・棚卸在庫・資産の売却費など、さまざまな情報と計算が必要です。
4-3. 未払法人税等を算出する
税引前当期純利益から法人税を算出できれば、未払法人税等も確定します。
仮払法人税等の扱いや税率の計算を間違えないようにしましょう。
関連記事:法人税の計算方法を確認!計算後の仕訳方法や納付書の書き方も紹介
4-4. 仕訳・計上し、申告に備える
未払法人税等が確定したら、あとは仕訳によって計上し、申告に備えます。
確定申告書や決算報告書などもこの情報を元に作成しましょう。
関連記事:法人税の勘定科目とは?ケースごとの仕訳ルールや注意点を解説
5. 未払法人税等や仮払法人税等の計算・仕訳は経理ソフトを活用しよう


未払法人税等は年に1回、期末決算のときに計上するものです。年度末の業務は煩雑で、限られた時間の中でミスなく進めなければいけません。
少しでも時間と労力を減らし、確実な申告をするためには経理ソフトの活用をおすすめします。
経理ソフトなら計算や仕訳も入力するだけで完了します。申告書の作成も簡単になるため、税金の取り扱いもとても楽になるはずです。
人件費の削減にもつながりますので、ぜひご検討ください。
86個の勘定科目と仕訳例をまとめて解説
「経理担当になってまだ日が浅く、会計知識をしっかりつけたい!」
「会計の基礎知識である勘定科目や仕訳がそもそもわからない」
「毎回ネットや本で調べていると時間がかかって困る」
などなど会計の理解を深める際に前提の基礎知識となる勘定科目や仕訳がよくわからない方もいらっしゃるでしょう。
そこで当サイトでは、勘定科目や仕訳に関する基本知識と各科目ごとの仕訳例を網羅的にまとめた資料を無料で配布しております。 会計の理解を深めたい方には必須の知識となりますので、ぜひ資料をダウンロードしてご覧ください。
経費管理のピックアップ
-


電子帳簿保存法に対応した領収書の管理・保存方法や注意点について解説
経費管理
公開日:2020.11.09更新日:2024.03.08
-


インボイス制度の登録申請が必要な人や提出期限の手順を解説
経費管理
公開日:2022.01.27更新日:2024.01.17
-


インボイス制度は導入延期されるの?明らかになった問題点
経費管理
公開日:2021.11.20更新日:2024.01.17
-


小口現金とクレジットカードを併用する方法とメリット
経費管理
公開日:2020.12.01更新日:2024.03.08
-

旅費精算や交通費精算を小口現金から振込にする理由
経費管理
公開日:2020.10.07更新日:2024.03.08
-


経費精算とは?今さら聞けない経費精算のやり方と注意点を大公開!
経費管理
公開日:2020.01.28更新日:2024.07.04





















