棚卸差異はなぜ発生する?発生による影響や改善方法も解説
更新日: 2024.7.2
公開日: 2022.8.19
jinjer Blog 編集部
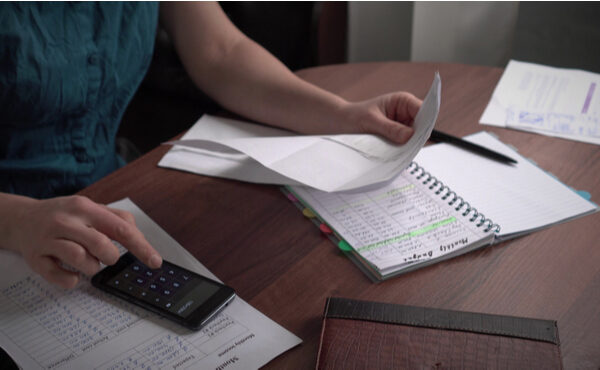
棚卸差異は棚卸時に発生するだけでなく、日々の在庫管理が適切におこなわれていなくても発生します。
これらの差異は発生原因の特定のため通常業務を圧迫するだけでなく、積み重なれば会社の決算書にも誤差を生んでしまいます。
本記事では、棚卸差異が発生する原因や発生による影響、棚卸差異の許容範囲、改善方法を解説します。
関連記事:棚卸とは?棚卸の目的や実施の時期、方法や流れについて解説
86個の勘定科目と仕訳例をまとめて解説
「経理担当になってまだ日が浅く、会計知識をしっかりつけたい!」
「会計の基礎知識である勘定科目や仕訳がそもそもわからない」
「毎回ネットや本で調べていると時間がかかって困る」
などなど会計の理解を深める際に前提の基礎知識となる勘定科目や仕訳がよくわからない方もいらっしゃるでしょう。
そこで当サイトでは、勘定科目や仕訳に関する基本知識と各科目ごとの仕訳例を網羅的にまとめた資料を無料で配布しております。 会計の理解を深めたい方には必須の知識となりますので、ぜひ資料をダウンロードしてご覧ください。
1. 棚卸差異とは?発生する原因


棚卸差異とは、実際に棚卸して数えた商品数(実地棚卸数量)と、帳簿で記録されている商品数(帳簿棚卸数量)に差が生じている状態です。
実地棚卸数量が帳簿よりも多いときは「棚卸差益」、帳簿よりも少ないときは「棚卸差損」と呼び区別します。棚卸差異はプラス、マイナスどちらにも転じることがあります。プラス、マイナスいずれにしても棚卸差異が発生した場合は報告書の作成が必要です。
これらが発生する原因は、日々の倉庫業務でのミス、または、棚卸時のミスが考えられます。それぞれ原因を解説します。
1-1. 受払の間違い
発注した製品は仕入先が商品や数量を間違えて卸す可能性もあります。
倉庫への受入では検品を怠ると上記が原因で差異が発生するケースもあります。発注書通りの商品・数量で納品されているか確認しましょう。
また、払出時もハンディターミナルで処理した商品と、売却した商品が異なれば差異が発生します。
払出と商品確認を別の担当者がおこなうなどの対策が必要です。
1-2. 破損や紛失
商品を運んでいる最中に落として破損させたり、置き場所や納品先を間違えて紛失したりすれば、棚卸差損が発生します。
商品の移動は適正人数でおこなう、倉庫内の整理整頓をする、移動用通路を整えるなど基本を見直しましょう。
1-3. 盗難や持ち出し
従業員以外も出入りできる倉庫では、盗難の恐れもあります。
セキュリティ対策が取られていなければ、従業員による持ち出しなども考えられます。
盗難対策としては、倉庫の施錠や監視カメラの設置、開閉時の記録をつけるなどが有効です。
また、内部犯罪防止のためにも、経理や事務担当者は受払後や納品後の伝票を確認し不審な点がないか確認しましょう。
1-4. 在庫管理システムへのインプット間違い
倉庫管理システムなどを利用している場合、数字自体を打ち間違えたり、別の商品欄に数量を打ち込んだりすると、帳簿が狂う原因となります。また、伝票で商品管理をおこなっているなら、処理漏れも差異の原因です。
これらのケースでは、帳簿残高の方が実際の商品数よりも多くなる可能性があります。ダブルチェックなどでミスを防止しましょう。
1-5. 棚卸時の間違い
棚卸では商品のカウントからデータインプットまで、どこかで間違いがあれば差異が発生してしまいます。
在庫を確認するときは、数え間違いや二重計上のないようにしましょう。
また、インプット時は、数字を打ち間違えない、データがシステムに反映されたか確認するなどチェックを徹底しましょう。
1-6. 災害
人為的ミスによらない場合としては、災害による倉庫在庫の破損が挙げられます。
自然災害や人的災害により多額の損失が発生したときは、「災害損失」や「特別損失」という勘定科目で処理が必要なため注意しましょう。
1-7. 棚卸差異報告書の書き方
棚卸差異が発生した際は報告書を作成します。棚卸差異報告書の書き方は次のとおりです。
- 報告書の概要を記載する
- 棚卸の結果を記載する
- 原因の分析・対策を記載する
- まとめとして結論を記載する
棚卸差異が発生したことだけを記載するのではなく、次回の発生を防ぐための対策を記載しておきましょう。
2. 棚卸差異発生による影響


棚卸差異が発生すると通常業務に影響を及ぼすだけでなく、最終的には決算時の売上総利益にもマイナスの影響がでてしまいます。それぞれ、具体的に解説します。
2-1. 販売機会の損失
帳簿と実際の在庫数量が一致していなければ、注文を受けてもすぐに納品の約束ができません。注文の都度、倉庫担当者に在庫を確認していては迅速な対応は不可能です。
在庫不足で顧客を待たせれば他社商品に乗り換えられる可能性もあり、また欠品などが続けば信頼を失うこともあります。
2-2. 業務効率の悪化
会計上、棚卸差異が発生すればその原因を突き止めなければいけません。
商品数が多ければ、1つ1つ差異発生理由を確認するだけでも多くの時間を要します。これらの時間は、本来、適切に在庫管理がされていれば浪費する必要のない労働時間です。
不要な業務が発生すれば本来の業務は後回しになるなど、業務効率が悪化し、残業にもつながってしまいます。
2-3. 正しい売上総利益が算出できない
売上総利益(粗利)は、売上-売上原価により求められます。
売上原価は、期首商品棚卸高+当期商品仕入高-期末商品棚卸高により計算されます。棚卸が狂うと正確な売上原価が算出できません。
原価が不正確では粗利自体の正確性も保証できません。
営業利益や経常利益も粗利を元に計算するため、結果として正確な決算申告ができず、不必要な税金を納めなければいけない恐れもあります。
3. 棚卸差異の許容範囲


帳簿棚卸数量と実地棚卸数量の差を割合で表したものを棚卸差異率といい、以下の方法で計算できます。
棚卸差異率(%)=在庫差異÷帳簿棚卸数量×100
一般的に棚卸差異は5%までが許容範囲とされており、3%が目標値とされています。
しかし、差異が発生しないに越したことはないため、次に紹介する改善方法により、少しずつ差異を減らすことが大切です。
関連記事:棚卸計算法とは何か?具体的な計算方法やメリット・デメリット、継続記録法との違いも紹介
4. 棚卸差異の改善方法


棚卸差異の改善方法では、まず、現状の棚卸差異がどの程度発生しているのか数値で把握しましょう。その上で適切な対策を検討します。
場合によっては棚卸の方法を変えたり、回数を増やしたりなども必要です。
4-1. 現在の棚卸差異率を確認する
棚卸が終わったら差異率を割り出し、現在どの程度ズレが生じているのか確認しましょう。その上で、なぜ差異が発生したのか、原因を確認します。
帳簿上にミスがあるなら入力時にダブルチェックをおこなう、差異の多い商品があるなら置き方を変えるなど、原因に合わせた対策が必要です。
また、棚卸のときにミスが多いなら、方法を変えたり、回数を増やしたりしてもよいでしょう。
4-2. 棚卸マニュアルを作成する
在庫管理システムへの入力ミスをはじめ、人的なミスを防止するために棚卸マニュアルを作成しましょう。各工程のマニュアルを作成することで人的ミスの防止が期待できます。マニュアルを作成したら、存在を周知しましょう。従業員が存在を認識して作業を進めることが大切です。
4-3. 棚卸方法の変更
棚卸の方法には、「循環棚卸」と「一括棚卸」があります。
循環棚卸では一気に棚卸を進めるのではなく、場所や商品ごとに回数を分けておこないます。作業量を調節しやすいため業務が多忙でも棚卸をしやすい点がメリットです。しかし、二重集計などに注意が必要です。
一括棚卸とは、すべての商品を一度に数える方法です。棚卸回数は減らせるものの、商品数が多いと業務を止めて作業が必要です。
それぞれ、現在おこなっている棚卸方法が業態にあったものか確認しましょう。
4-4. 月次または日次で棚卸を実施する
期末のみの棚卸では差異が大きいなら、月末に一斉棚卸をおこない在庫の状況を把握するとよいでしょう。
また、高単価の商品や、使用期限の短い商品は、日々棚卸をすると正確性を確保できます。その際は、当日動きのあった商品に限定し棚卸を実施します。
4-5. 在庫管理システムの導入
もし、在庫管理を紙やExcelなどでおこなっているなら、在庫管理システムを導入し棚卸を効率化するのもおすすめです。
ハンディターミナルやバーコードなどにより管理でき、適正在庫数の管理にも役立ちます。
これらも活用し、棚卸差異の解消に努めましょう。
5. 棚卸では差異率を確認し誤差が生じないよう管理を徹底しよう


棚卸差異は日常の倉庫業務や、棚卸のときに発生しやすくなります。
多少の誤差であっても、発生すれば会計上の処理が必要となり、最終的には決算額も変わってしまうため注意が必要です。
現場担当者には棚卸差異率を確認し、どのような原因で差異が発生しているか突き止めるように指示しましょう。
そのうえで5%以下に収まるよう具体的な対処方法を検討し、PDCAサイクルを回して改善していくことが必要です。
86個の勘定科目と仕訳例をまとめて解説
「経理担当になってまだ日が浅く、会計知識をしっかりつけたい!」
「会計の基礎知識である勘定科目や仕訳がそもそもわからない」
「毎回ネットや本で調べていると時間がかかって困る」
などなど会計の理解を深める際に前提の基礎知識となる勘定科目や仕訳がよくわからない方もいらっしゃるでしょう。
そこで当サイトでは、勘定科目や仕訳に関する基本知識と各科目ごとの仕訳例を網羅的にまとめた資料を無料で配布しております。 会計の理解を深めたい方には必須の知識となりますので、ぜひ資料をダウンロードしてご覧ください。
経費管理のピックアップ
-


電子帳簿保存法に対応した領収書の管理・保存方法や注意点について解説
経費管理
公開日:2020.11.09更新日:2024.03.08
-


インボイス制度の登録申請が必要な人や提出期限の手順を解説
経費管理
公開日:2022.01.27更新日:2024.01.17
-


インボイス制度は導入延期されるの?明らかになった問題点
経費管理
公開日:2021.11.20更新日:2024.01.17
-


小口現金とクレジットカードを併用する方法とメリット
経費管理
公開日:2020.12.01更新日:2024.03.08
-

旅費精算や交通費精算を小口現金から振込にする理由
経費管理
公開日:2020.10.07更新日:2024.03.08
-


経費精算とは?今さら聞けない経費精算のやり方と注意点を大公開!
経費管理
公開日:2020.01.28更新日:2024.07.04





















