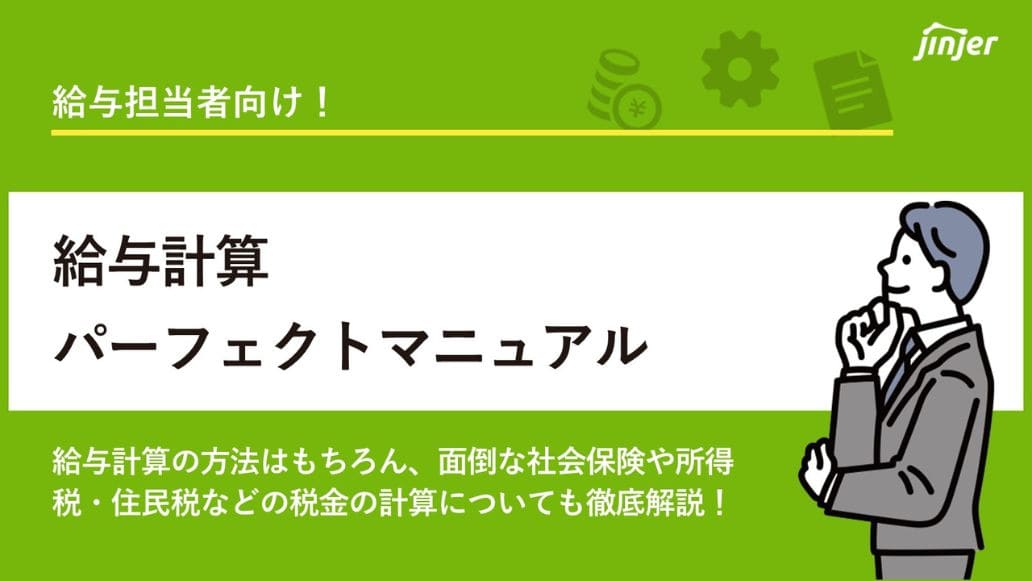賞与計算の基本や注意点・社会保険料が引かれる理由を解説
更新日: 2024.5.10
公開日: 2021.10.20
OHSUGI

「賞与計算」は非常に複雑であり、注意すべき点がいくつもあります。知識がないまま賞与計算を実施してしまうと、大きなトラブルにつながる可能性もあるため気をつけなければなりません。
そこで本記事では、賞与計算の基本的な方法、賞与から社会保険料が引かれる理由、賞与計算をおこなう上での注意点を解説します。賞与計算方法注をしっかりと把握して不要なトラブルを避けましょう。
「自社の給与計算の方法があっているか不安」
「労働時間の集計や残業代の計算があっているか確認したい」
「社会保険や所得税・住民税などの計算方法があっているか不安」
など給与計算に関して不安な方もいらっしゃるのではないでしょうか。
そのような方に向けて当サイトでは「給与計算パーフェクトマニュアル」という資料を無料配布しています。
本資料では労働時間の集計から給与明細の作成まで給与計算の一連の流れを詳細に解説しており、間違えやすい保険料率や計算方法についてもわかりやすく解説しています。
給与計算の担当者の方にとっては大変参考になる資料となっておりますので興味のある方はぜひご覧ください。
目次
1. 賞与とは?給与の違い


賞与と給与の違いは企業が決めた労働への対価か、法律で決められた労働への対価かです。賞与は給与の何ヵ月分と紹介されるため給料と近しく思えます。しかし、給与が法律定められた労働への対価なのに対して、賞与は企業が定めた労働への対価です。
法律では、給与は毎月1回以上、決められた日に、通貨で直接従業員に支払うことを原則としています。一方、賞与は法律に定めがありません。そのため、企業は就業規則をもとに賞与を好きなタイミングで誰にいくら払うのかを決定できます。
1-1. 賞与の種類
賞与には次のとおりさまざまな種類があります。
- 基本給連動型賞与:基本給と連動して賞与の支給額が決定する制度
- 業績連動型賞与:業務の成果に連動して賞与の支給額が決定する制度
- 決算賞与:決算時の業績に応じて賞与の支給額が決定する制度
このうち、日本の企業で一般的に採用されているのが、基本給連動型賞与です。基本給連動型賞与の支給タイミングは一般的に決算期の前後に設定されています。例えば大手企業であれば6~8月に夏季賞与、10~12月に冬季賞与が支払われます。
2. 賞与の平均額


賞与は企業が設定できる労働への対価です。そのため、どれくらいの賞与を支払えばいいのかわからなくなってしまうかもしれません。では賞与の平均額はどれくらいなのでしょうか。
厚生労働省『毎月勤労統計調査 令和3年9月分結果速報等』によれば、令和3年の賞与支給のある事業所の一人当たり平均は380,268円、一方、賞与支給のない事業所を含めた全労働者一人当たりの平均は301,553円でした。
2-1. 賞与の決め方
賞与をどのように支払うかは企業が決められます。一般的に日本での賞与は基本給と連動させる基本給連動型賞与が採用される傾向にあります。基本給連動型賞与の場合、基本給の数ヵ月分を賞与として支払います。なお、基本給連動型賞与は手当などを除く基本給をベースとするので注意しましょう。
具体的な計算方法にいては次の章で解説します。
3. 賞与計算の基本的な方法:賞与総額(賞与原資)


まずは賞与総額(賞与原資)の計算方法について解説します。
賞与総額の計算方法で主流となるのが「業績連動型」と呼ばれる方法です。
この業績連動型は、企業の業績に応じて賞与の総額を決定します。
また、給与の総額を導き出す際には、「業績指標」をベースにして計算します。
業績指標を求める計算式は以下のとおりです。
・営業利益 = 売上高 – 売上原価 – 販売費または一般管理費
・経営利益 = 営業利益 + 営業外利益 – 営業外費用
つまり、営業利益は本業で得た利益のことであり、経営利益は本業を含めた事業全体で得た利益です。
これら業績指標をもとに賞与総額を計算していきます。
なお、給与総額の計算方法は大きく分けて以下の2つがあげられます。
3-1. 利益比率と平均支給月数を連動させる方法
賞与総額の計算方法1つ目は、利益比率と平均支給月数を連動させる方法です。
具体的には、「売上高経常利益比率」は業績指標をベースにして算出し、その後に「平均支給月数」を連動させて総額を求めます。
なお、売上高経常利益比率の計算式は「経常利益 / 売上高 × 100」です。
この計算方法は少し複雑であるのが難点ですが、業績を賞与に反映させやすいという利点があります。
つまり、利益比率と平均支給月数を連動させる方法を用いることで、業績に対して最適な賞与を算出することが可能です。
参考:売上高経常利益率|財務省
3-2. 業績指標に一定の係数を乗じて計算する方法
賞与総額の計算方法2つ目として、業績指標に一定の係数を乗じて計算する方法があげられます。
事前に決めておいた係数に業績指標を乗じるだけなので、簡単に賞与総額を計算することができます。
この計算方法は非常にシンプルで手間がかからない反面、賞与額を柔軟に調整できないため、業績に対して不釣り合いになりやすいのが難点です。
そのことから、1つ目の方法を用いる企業が多い傾向にあります。
4. 賞与計算の基本的な方法:個別賞与額


賞与総額の計算方法がわかったところで、個別賞与額の計算方法もみていきましょう。
個別賞与額の算出は、下記の計算式を一般的に用います。
・個別賞与 = 基準額 × 平均支給月数 × 評価係数
「基準額」については「基本給 + 各種手当」で求めることができます。
ただし、各種手当に含まれる内容は会社ごとに異なるため注意が必要です。
「評価係数」は各会社によって設けられていることが多く、人事評価に基づいて決定されます。
評価係数の具体例として下記をご参考ください。
- 評価ランクS:評価係数1.5
- 評価ランクA:評価係数1.3
- 評価ランクB:評価係数1.1
- 評価ランクC:評価係数0.9
- 評価ランクD:評価係数0.7
この評価係数はあくまで一例であるため、参考程度にとどめておきましょう。
4-1. 個人賞与額の計算方法の一例
先ほどお話した計算式や評価係数の基準を用いて、個人賞与額の計算方法例を1つご紹介します。
計算方法が明確になっていない方は確認してみてください。
個人賞与額の計算方法の一例
基準額(基本給+各種手当)= 30万円、平均支給月数 = 2.5ヵ月、評価係数 = 1.3
個人賞与額 = 30 × 2.5 × 1.3 = 97万5,000円
このように、計算式に当てはめるだけで個人賞与額を算出できます。
5. 賞与の社会保険料の計算方法


次に、賞与における社会保険料の計算方法を解説します。
社会保険料と所得税は、社会保険料(健康保険料・厚生年金保険料・介護保険料・雇用保険料)を計算したあと、所得税(源泉所得税)を差し引きます。
はじめに社会保険料の計算にあたる、「健康保険料」「厚生年金保険料」「介護保険料」「雇用保険料」それぞれの計算方法を紹介します。それぞれの計算方法をもとにシミュレーションをしてみましょう。
5-1. 健康保険料の計算
健康保険料の計算は、賞与額から1,000円未満の端数を切り捨てて、その金額に保険料率を掛け合わせます。
保険料率または保険料額は保険料額表などで算出できるものの、保険料率に関しては毎年改定されるため注意が必要です。
健康保険料の計算方法
健康保険料 = 標準賞与額 × 保険料率
5-2. 厚生年金保険料の計算
厚生年金保険料の計算方法は健康保険料と同様です。
賞与額から1,000円未満の端数を切り捨てた金額に対し、保険料率を掛け合わせます。
なお、厚生年金基金に加入している際の保険料率は、基金ごとに決められている免除保険料率が控除されます。
厚生年金保険料の計算方法
厚生年金保険料 = 標準賞与額 × 保険料率
5-3. 介護保険料の計算
介護保険料の計算方法も健康保険料と同様のやり方を用います。
なお、保険料率は健康保険料率と同じく毎年改定されるため気をつけましょう。
介護保険料の計算方法
介護保険料 = 標準賞与額 × 保険料率
5-4. 雇用保険料の計算
雇用保険料の計算方法は、健康保険料・厚生年金保険料・介護保険料とは異なり、賞与額に保険料率を乗じて計算します。
雇用保険料の計算方法
雇用保険料 = 賞与額 × 保険料率
なお、雇用保険料率は事業主か被保険者であるかによって異なるほか、保険料率の見直しが毎年入ります。
本章で解説したように、社会保険料の計算は、標準賞与額を求めなければいけなかったり、毎年税率の変更や見直しがあったりするため、ミスが起きやすかったり業務を手間に感じることが多いのではないでしょうか。
当サイトでは、「給与計算パーフェクトマニュアル」という資料を無料配布しています。本資料では社会保険料の定義や計算方法はもちろん、間違えやすい所得税・住民税の計算など給与計算に関する基礎を図解つきでわかりやすく解説しています。給与計算の担当者の方にとっては大変参考になる資料ですので興味のある方はこちらから無料でダウンロードしてご覧ください。
6. 賞与の源泉所得税の計算方法


賞与における社会保険料の計算方法が理解できたところで、源泉所得税の計算方法もみていきましょう。
源泉所得税は、前月の給与から社会保険料を差し引いた金額と扶養親族等の人数を確認し、この両者をベースに「賞与に対する源泉徴収額の算出率の表」を用いて税率を算出します。[注1]
源泉所得税の計算方法
賞与の源泉徴収税額 = 賞与から社会保険料を差し引いた金額 × 税率
7. 賞与計算で社会保険料が引かれる理由


続いて、賞与計算で社会保険料が引かれる理由についてみていきましょう。
まずは、賞与から社会保険料がいつから引かれ始めたのかを解説します。
7-1. 賞与から社会保険料はいつから引かれ始めたのか
1994年度から「特別保険料」という名目で賞与から社会保険料が引かれ始めました。
しかし、徴収される比率は一律1%であり、労使折半を考慮すると労働者はわずか0.5%しか徴収されませんでした。
そのため、当時はいまよりも徴収比率が非常に低く、給与を減らして賞与を増やすという手法が横行していたのです。
しかし、2003年度に特別保険料が廃止され、賞与にも社会保険料を大幅に徴収するシステムへと変わりました。
このシステム変更に伴い、「急にボーナスが減った」と感じる方も一定数いたはずです。
7-2. 社会保険料が引かれる理由は保険料逃れの防止
賞与から社会保険料が引かれるのは、主に保険料逃れを防ぐためです。
先ほどお話したように、特別保険料が廃止される前は給与を減らして賞与を増やし、意図的に社会保険料の負担を減らすことが可能でした。
多くの企業が社会保険料の徴収を逃れるため、給与と賞与を意図的に操作する事態が横行していたのです。
それに伴い、保険料逃れをしている企業としていない企業では不公平になることから、総報酬制が導入され、賞与から社会保険料が大幅に引かれるようになりました。
これまでの煩雑な賞与計算も給与計算システムのジンジャー給与を使用することで、正確で楽な計算が実現可能です。資料をご用意しておりますので興味のある方はご覧ください。
8. 賞与計算における3つの注意点


最後に、賞与計算における注意点を3つ解説します。
賞与計算を実施する方はぜひ理解しておきましょう。
8-1. 退職予定者の賞与計算
賞与計算における注意点1つ目は、退職予定者の賞与計算です。
退職予定者の賞与を支払う場合、健康保険料や厚生年金保険料については、資格喪失の前月までに支給された賞与分までが控除の対象です。
つまり、資格喪失の当月に支給された賞与については、保険料控除の対象にはならないため気をつけましょう。
8-2. 賞与支払届・賞与支払届総括表の提出
賞与計算における注意点2つ目として、賞与支払届・賞与支払届総括表の提出があげられます。
会社で従業員に賞与を支払う場合は、従業員ごとの賞与支払額を記入する「賞与支払届」と、賞与の支払人数と合計金額を記入する「賞与支払届総括表」を提出する必要がありました。
しかし、令和3年4月から「賞与支払届総括表」は廃止となったため、提出する必要がなくなりました。
また、新しく「賞与不支給報告書」が設けられ、被保険者および70歳以上被用者に賞与を支給しなかった場合は、この「賞与不支給報告書」を提出する必要があります。
関連記事:賞与支払届とは?手続きの方法や注意点、電子申請についても解説
8-3. 社会保険料が対象となる上限
賞与計算の注意点3つ目は、社会保険料が対象となる上限です。
賞与を支払う際には、健康保険料と厚生年金保険料に異なる上限が設けられています。
また、「支給が年3回以下」の条件を満たした賞与のみが社会保険料の対象となるため、支給が年4回以上の賃金は賞与ではなく給与の扱いとなり、標準報酬月額に基づいて保険料を計算します。
そのため、従業員に賞与を支給するときは、社会保険料が対象となる上限を意識しましょう。
9. 賞与計算を正確におこなってトラブルを避けよう


賞与総額の計算方法には、「利益比率と平均支給月数を連動させる方法」と「業績指標に一定の係数を乗じて計算する方法」があり、計算式や意識すべきことがそれぞれ異なります。
また、個別賞与額の算出方法は企業ごとに評価係数が違うため注意が必要です。
そのほかにも賞与計算に関する多数の計算方法があるため、ぜひ本記事の内容を参考にし、賞与計算を正確におこなってトラブルを避けましょう。
関連記事:給与計算の基礎が初心者でも分かる!基礎知識から全体の流れまで徹底解説!
勤怠・給与計算のピックアップ
-




【図解付き】有給休暇の付与日数とその計算方法とは?金額の計算方法も紹介
勤怠・給与計算公開日:2020.04.17更新日:2024.10.21
-



36協定における残業時間の上限を基本からわかりやすく解説!
勤怠・給与計算公開日:2020.06.01更新日:2024.09.12
-


社会保険料の計算方法とは?給与計算や社会保険料率についても解説
勤怠・給与計算公開日:2020.12.10更新日:2024.08.29
-


在宅勤務における通勤手当の扱いや支給額の目安・計算方法
勤怠・給与計算公開日:2021.11.12更新日:2024.06.19
-


固定残業代の上限は45時間?超過するリスクを徹底解説
勤怠・給与計算公開日:2021.09.07更新日:2024.03.07
-


テレワークでしっかりした残業管理に欠かせない3つのポイント
勤怠・給与計算公開日:2020.07.20更新日:2024.09.17
給与計算の関連記事
-
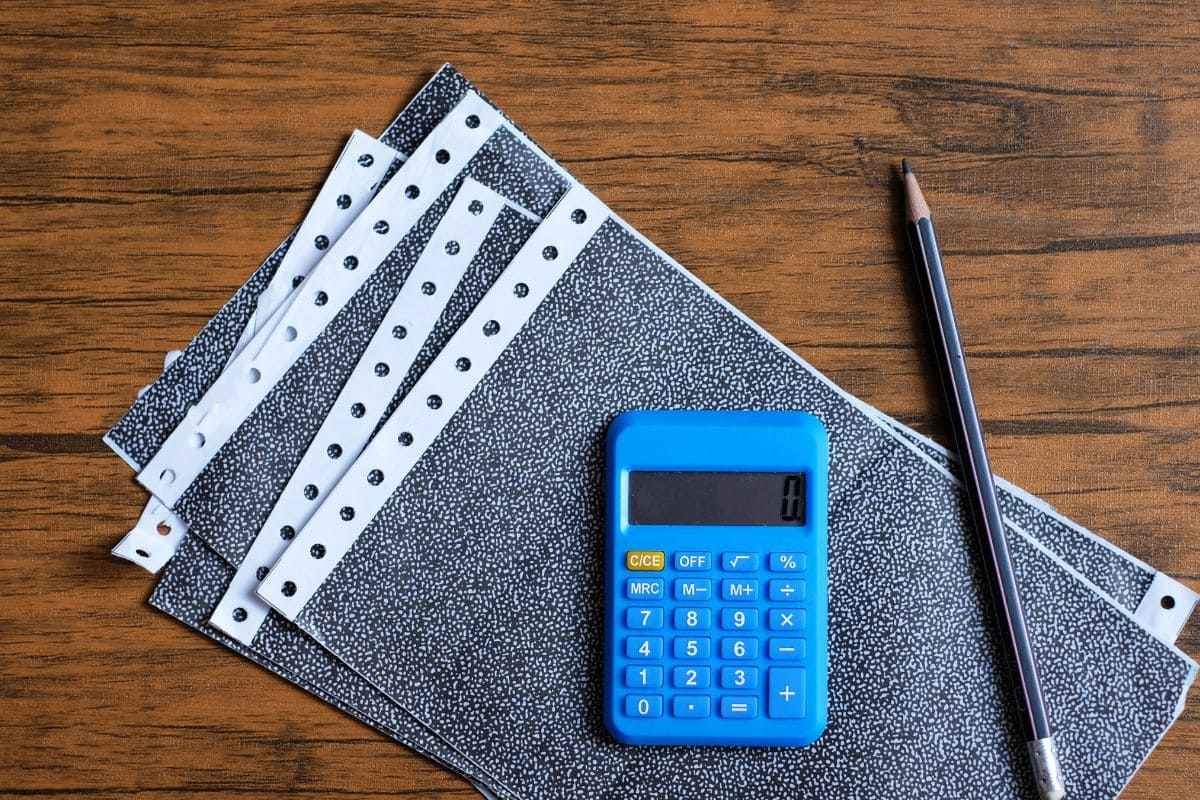
懲戒解雇した社員に退職金を支払う義務はある?不支給の条件や手続きを解説
勤怠・給与計算公開日:2024.07.31更新日:2024.07.31
-


退職金の前払い制度とは?導入のメリット・デメリットやポイントを解説
勤怠・給与計算公開日:2024.07.31更新日:2024.07.31
-


源泉徴収票は電子化OK!メリット・デメリットや方法を解説
勤怠・給与計算公開日:2024.07.31更新日:2024.07.31