半休(半日休暇)とは?時間休との違いや導入方法を解説
更新日: 2025.12.25 公開日: 2024.12.24 jinjer Blog 編集部

半休とは、有給休暇を半日単位で取得できる制度です。この制度に関しては労働基準法の規定がないため、取得条件や方法、制度内容などは企業が自由に決めることができます。
休暇取得の一つの方法であり、導入することで従業員のライフワークバランス向上を図れるだけでなく、生産性やエンゲージメントの向上につながります。企業にとってもメリットがある制度といえるでしょう。
ここでは、半休の概要や時間休との違い、半休を導入する際のポイントや注意点を解説していきます。
目次
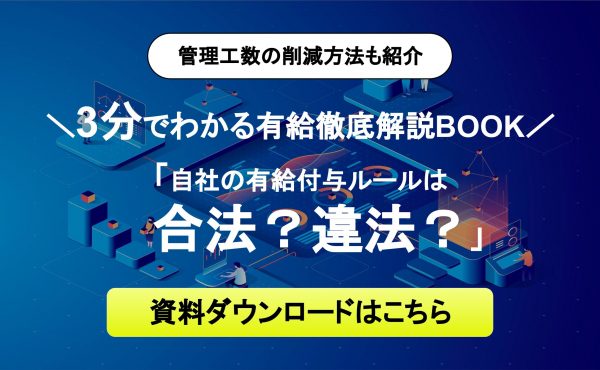
毎月の有給休暇の付与計算、取得状況の確認、法改正への対応…。
「この管理方法で本当に問題ないだろうか?」と不安を抱えながら、煩雑な業務に追われていませんか?
当サイトでは、担当者の方が抱えるそのようなお悩みを解決し、工数を削減しながらミスのない管理体制を構築するための実践的なノウハウを解説した資料を無料配布しています。
◆この資料でわかること
-
年5日の取得義務化で、企業が対応すべき3つのポイント
-
すぐに使える!Excelでの年次有給休暇管理簿の作り方
-
複雑なケース(前倒し付与など)の具体的な対応フロー
最新の法令に対応した、効率的で間違いのない有休管理のために、ぜひこちらから資料をダウンロードの上、ルールの見直しにお役立てください。
1. 半休(半日休暇)とは


半休とは、半日単位で休暇を取得することを指します。労働基準法に定められたものではなく、企業が自主的に取り入れることができる制度です。
そのため、半休の具体的な取得方法や条件は企業ごとに異なります。導入する場合は就業規則に明記したうえで、制度の内容や手続きを従業員に周知しなければなりません。
半休は、社員が仕事と生活のバランスを取りやすくし、心身の負担を軽減するために役立つでしょう。
1-1. 半休における休憩の扱い
「休憩」は、労働時間に応じて必要な時間(休憩時間)が労働基準法において明確に規定されています。
企業は、従業員の労働時間が6時間超えの場合は45分以上、8時間超えの場合は60分以上の休憩を与えなければなりません。この休憩とは「労働から完全に開放され、心身を休められる時間」です。電話番や来客対応などがある場合は休憩として認められません。
これは半休を取得した従業員にも当てはまります。半休を取得している場合でも、労働時間が6時間超えであれば少なくとも45分の休憩を与えなければなりません。「半休で午後から出社してるから」などの理由により、その日の労働時間が6時間を超えているにもかかわらず、正しく休憩を与えない場合は、労働基準法違反に該当するため注意しましょう。
1-2. 半休における残業の扱い
「半休」は、半日だけ休むという状態ですが、半日は出勤となります。出勤していると通常通りの扱いをしてしまいがちですが、「半休」であっても「休暇を取得している状態」に該当するため、残業をさせないようにするというのが原則です。
とはいえ、業務上どうしても残業をしてもらわなければいけないこともあるかもしれません。そのような場合は、半休であっても残業をさせることは可能です。しかし、半休をとった日でも、労働時間が8時間を超えたら残業代を支払う必要があります。
労働基準法では、労働時間は8時間と規定されており、8時間を超える労働時間は「時間外労働」となります。そのため、半休を取っていても、労働時間が8時間を超えた場合は、割増賃金を支払わなければならないのです。
割増賃金は、労働基準法の規定で「通常の賃金×1.25倍」の割合で計算するため、適切に支払いましょう。
2. 半休を取得した場合の給与はどうなる?
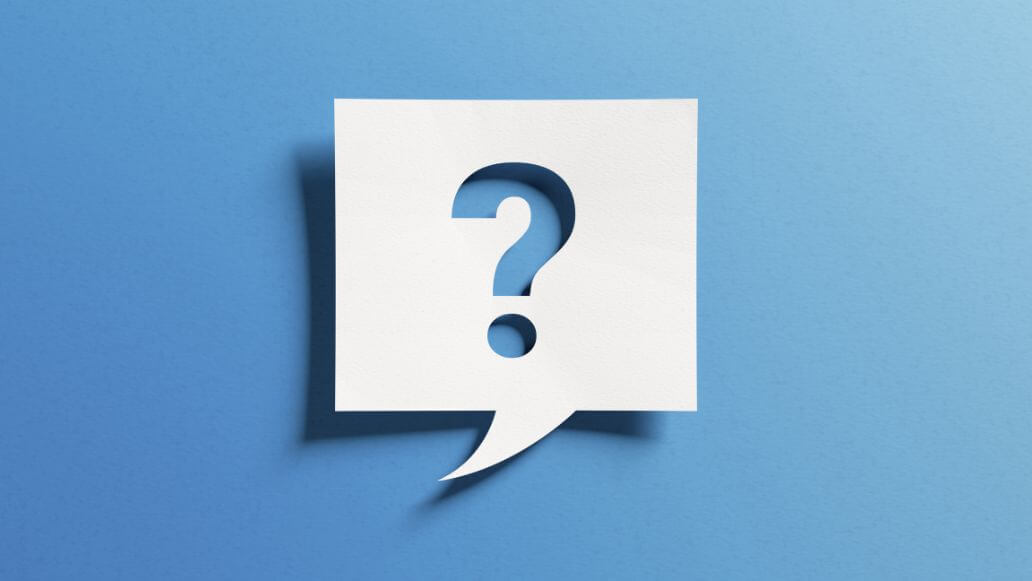
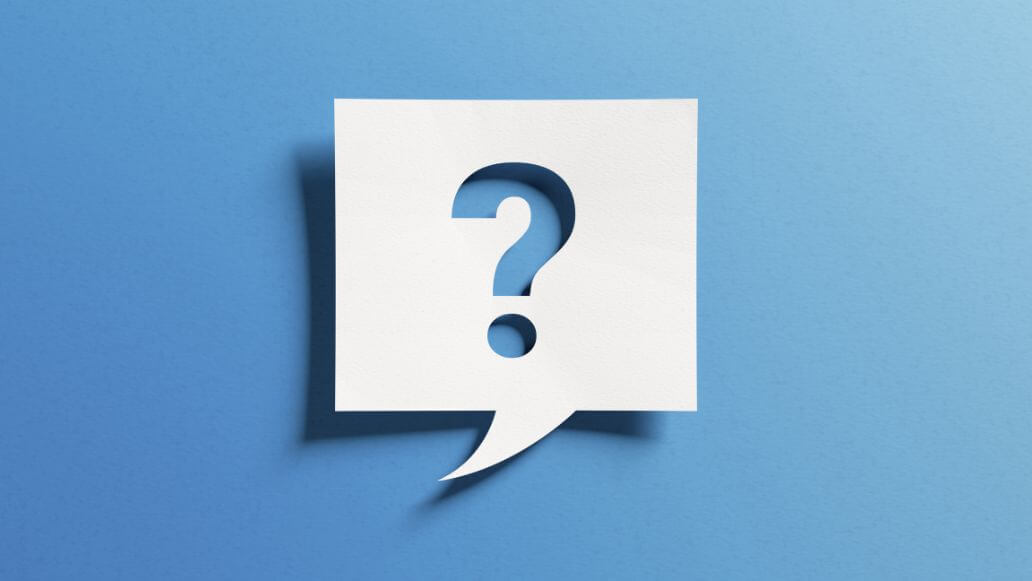
半休を取得した日の労働時間は、通常の労働時間よりも少なくなります。時給制の場合は問題ありませんが、日給制や月給制の場合は賃金をどのように扱うかが1つの問題です。半休をした日の給与計算方法について解説します。
2-1. 計算方法は企業が自由に決められる
半休を取得した日の給与計算方法は、基本的には企業が自由に決められます。ただし、従業員が損をしたり、不利になる計算は認められません。一般的には以下のいずれかの方法で計算します。
通常通りの勤務として扱う
半休を取得しており、午前や午後のみの勤務になっている場合でも、通常の勤務と変わりない給与を支払う方法です。
出勤した際と同じ処理で済むため、特別な計算が不要で事務処理が簡単というメリットがあります。
平均賃金で計算する
平均賃金とは、「算定すべき事由の発生した日以前の3ヶ月間に支払われた賃金総額を元に1日当たりの賃金を計算したもの」です。通常通りの給与を支払うよりも安くなるケースが多いため、半休の日の給与計算方法として利用されることがあります。
平均賃金の計算には以下の式を使います。
平均賃金 = 算定事由発生日以前3ヶ月間の賃金総額 ÷ その期間の総日数(暦日数)
この方式で求めた金額を半休を取得した日の給与とします。ただし、日給・時給・出来高給の場合、平均賃金は賃金の総額を労働日数で割った金額の60%を下回ってはならないと決められています。平均賃金が最低保証額を下回る場合は、最低保証額を給与とします。
最低保証額=賃金の総額 ÷ その期間中に働いた日数 ✕ 60%
健康保険の標準報酬日額で計算する
健康保険の標準報酬日額は、標準報酬月額の30分の1として計算します。この場合も通常通りの勤務として給与を支払うよりも安くなります。
ただし、標準報酬月額による計算では、従業員に不利益が発生することがあります。そのため、半休の給与に標準報酬日額を利用する場合は、労使協定の締結が必要です。
2-2. 就業規則に明記しておく必要がある
前述のように、半休を取得した日の給与計算方法は主に3種類です。どの計算方法を採用するかは、企業が自由に決められます。
決定した半休取得時の給与計算方法は、就業規則に明記しなければなりません。必要に応じて労使協定の締結も必要です。
給与の取り扱いはトラブルを招きやすい部分であるため、明記するとともに十分に周知・理解を促すことも求められます。
また、決定した計算方法は社内で統一する必要があります。部署や時期によって、異なる計算方法を採用することはできず、全従業員がどの時期に取得しても同じ計算方法で給与が支給されなければなりません。
3. 半休と時間休の違い
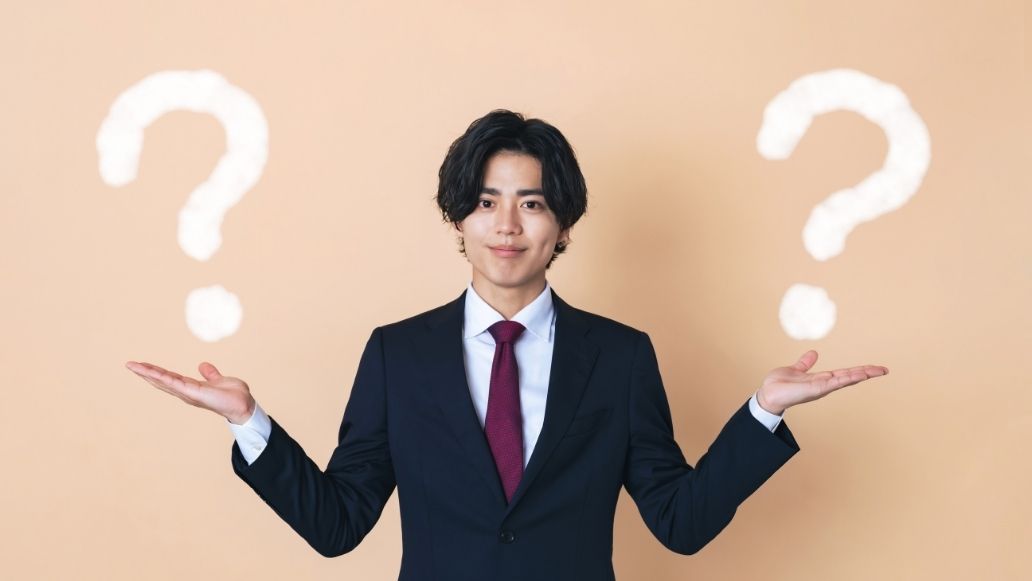
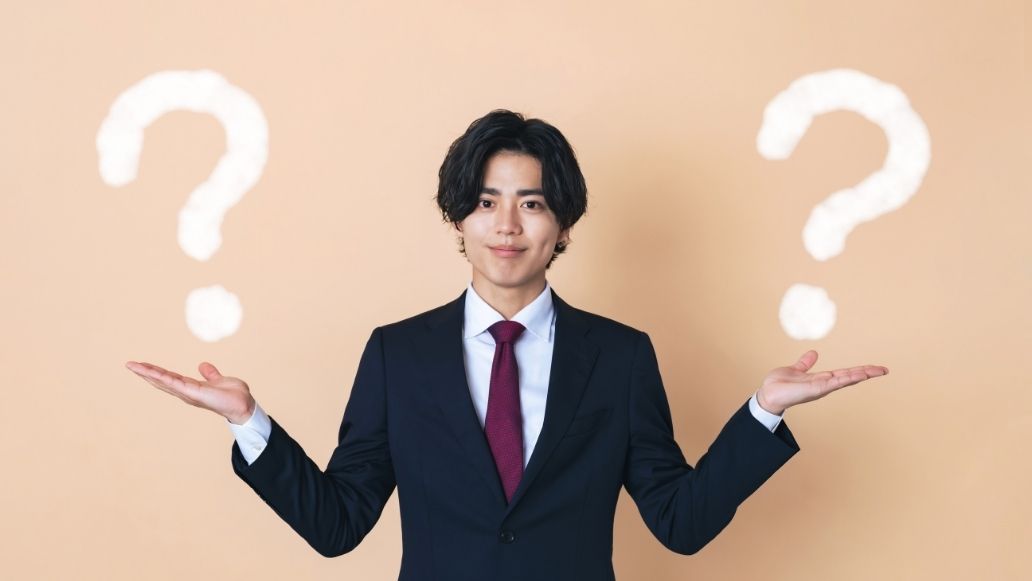
半休と時間休の違いは、以下のとおりです。
| 半休 | ・自主的に導入できる制度
・半日単位で有給休暇を取得できる ・法的な上限がない |
| 時間休 | ・労働基準法に基づく制度
・導入するには労使協定を結ぶ必要がある |
半休と時間休は、どちらも休暇を1日単位以外で取得するための制度ですが、それぞれ異なる特徴があります。
時間休は2010年4月に施行された労働基準法改正により設けられ、1時間単位で有給休暇を取れるようになりました。
ただし年間の上限があり、1日分の年次有給休暇が何時間にあたるかは、企業ごとの所定労働時間により設定されます。時間休の取得は柔軟な働き方を可能にしますが、上限は超えられません。
一方、半休は法的な上限がなく、企業の裁量で利用を許可していることが一般的です。半日単位で取ることができるため、数時間のまとまった休暇が必要な場合に適しています。
4. 従業員が半休を取る理由


「半休を取っても意味がないのでは」と思う担当者もいるかもしれませんが、従業員それぞれに半分だけでも休みを取りたい理由があります。
半休を取る理由は、主に以下の3つが挙げられます。
- 旅行やリフレッシュ
- 葬式や法事
- 体調不良
ここでは、これらの理由について解説します。
4-1. 旅行やリフレッシュ
半休を取る理由としては、旅行やリフレッシュをするときが挙げられます。
例えば、午前中に仕事を終え、午後から旅先へ向かうことで、移動時間を効率的に確保可能です。従業員は、仕事の流れを大きく崩さず、ゆとりのあるスケジュールでリフレッシュできるでしょう。
また、旅行や帰省の際に、週末と半休を組み合わせると、より充実した時間を過ごせます。金曜の午後や月曜の午前に半休を取得すれば、週末に2泊の旅行が可能になります。
特に、月曜の午前中半休は、宿泊料金が高くなりやすい金曜や土曜を避け、日曜の宿泊を選べるため、旅行費用を抑えられるのもメリットといえるでしょう。
4-2. 葬式や法事
半休を取る理由には、家族や親しい人の葬式や法事に参列する場合も挙げられます。
葬式や法事は、平日におこなわれることも多く、仕事を途中で離れる必要が出てくることもあるでしょう。特に葬式は急なことがほとんどであるため、ギリギリまで仕事をしてから参列するケースも多いです。 少しでも落ち着いて参列してもらえるように、上司や同僚はサポートをして、半休に対応する必要があります。
葬儀や法事というのは、大切な人との最後の別れをおこない、遺族や親族への支援や共感を示す重要な行事であるため、企業側は従業員の気持ちを尊重し、柔軟に対応できるよう配慮しましょう。
半休を利用すると、全日の休暇を取らず必要な時間だけを確保し、年次有給休暇を効率的に活用できます。
4-3. 体調不良
半休を取る理由として、体調不良のときが挙げられます。
風邪や頭痛、腹痛、生理痛など「症状は軽いけど業務に集中しづらい」という状態のときは、半休を取得することで無理なく休めます。症状が悪化する前に対処すれば回復も早まるため、業務効率の維持にもつながるでしょう。
また、家族や子どもが急に体調を崩したときや、怪我をしたときなどにも半休を取るケースがあります。家族が急病になった際でも、半休があれば周りに遠慮せず対応することができます。
家庭の事情に柔軟に対応できる半休制度が整っていることは、ワークライフバランスの面でも非常に役立ちます。
5. 半休になるのは何時間から?


半休として取り扱われる時間には厳密な規定がないため、企業が独自に設定可能です。
厚生労働省の「改正労働基準法に係る質疑応答」でも、半休の時間を労働時間の正確な半分にする必要はないと明言しています。そのため、午前と午後で休暇の時間が異なる設定でも問題ありません。
例えば、8時間勤務の場合、午前半休は9時から12時の3時間、午後半休は13時から18時の5時間となり、勤務時間に2時間の差が生まれます。このような場合でも、午前と午後のどちらを休んでも法律的には問題がなく、半休という扱いになります。
ただし、午前・午後で休暇時間に差が生じると、午前半休を取った社員が不公平さを感じる場合もあります。制度に対する社員の納得感を得るためにも、公平に扱う工夫が大切です。
具体的には、所定労働時間を半分に割るなどの対策をおこなうことが望ましいでしょう。
6. 半休制度を導入する方法
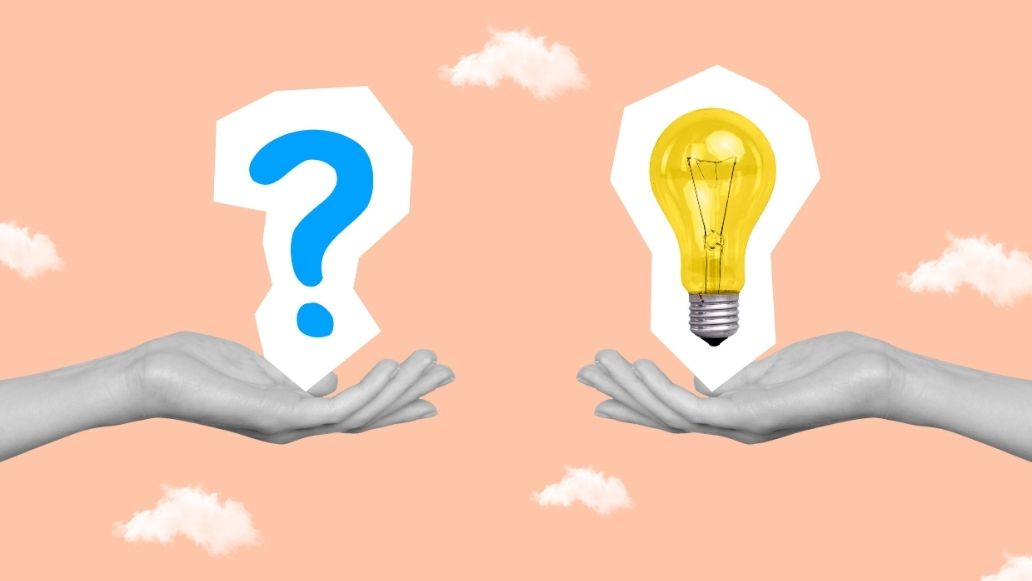
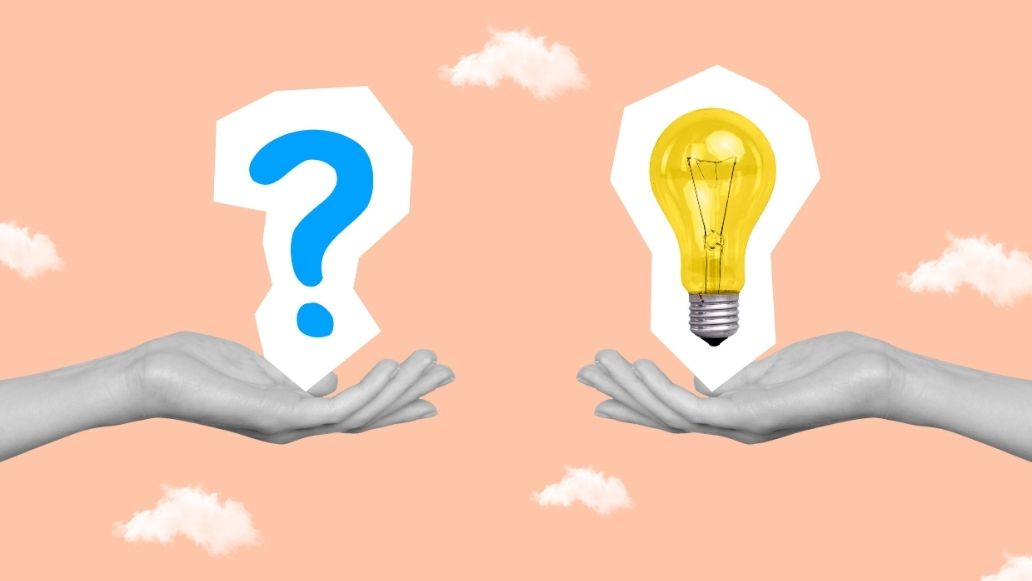
半休制度の導入方法は、以下の4ステップです。
- 半休制度導入における課題を考える
- 半休のルールを決める
- 就業規則を改正する
- ルールを従業員に周知する
ここでは、それぞれのステップについて解説していきます。
6-1. 半休制度導入における課題を考える
半休制度を導入する場合、勤怠管理や給与計算が複雑になります。特に半休をとった日の給与計算を、平均賃金の半日分にする方法や、標準報酬日額を採用する場合などは、計算が複雑になるでしょう。
また、シフト管理も複雑になりやすく、部署内でも休みなのか半休なのかを判断しなければならないため、混乱が生じやすいです。
人事や労務担当者の業務負担や、現場の混乱を踏まえ、対応できるか十分に検討しなければなりません。
担当者の業務量を調整するとともに、勤怠管理システムなどを導入して勤務日数や給与計算の効率化をおこなって対策しましょう。
6-2. 半休のルールを決める
半休は労働基準法で明確に定められていないため、企業ごとに細かなルールを定める必要があります。一例としては以下のような内容が必要です。
- 半休制度を利用できる従業員の範囲
- 半休取得時の給与計算方法
- 半休を取得する際の手続き(届出先・届出方法など)
- 半休の希望を出す期限
- 皆勤手当に対する影響
- 半休取得時の有給休暇の取り扱い
半休制度を利用できる対象者や、半休取得時の給与計算方法は非常に重要な項目です。わかりやすく、具体的な内容でルールを決めて明示することが求められます。また、半休を取得する際に「取得義務となる年5日の有給休暇」を適用するかどうか決めておきましょう。時間区分に関しても、業務やシフトの影響を考慮した上で設定しておくと不公平感が生まれにくいです。
6-3. 就業規則を改正する
半休を導入する際は、就業規則の改正が必要です。
常時雇用する従業員数が10名以上の企業は、改正した就業規則を労働基準監督署に届け出る義務があります。届出をする際には以下の書類が必要です。
- 就業規則
- 意見書
- 就業規則(変更)届出書
意見書は、従業員が過半数を占める労働組合からの意見や、従業員の過半数を代表する者の意見を聴取し、記載した証明書類です。
社内での手続きが完了次第、すみやかに書類を労働基準監督署へ提出し、正式な届出を済ませます。丁寧な合意形成と法的な手続きを踏むことで、半休制度の導入が円滑に進むでしょう。
6-4. ルールを従業員に周知する
新たに半休制度を導入する際には、全従業員にルールをわかりやすく周知することが重要です。
就業規則の改正手続きでは、従業員全員の意見を求める義務はありません。そのため、半休が設けられたことを知らない従業員もいる可能性があります。せっかくの制度でも周知がされていなかったり、誤った認識がされていたりすると活用されません。どのような時に半休をとるとよいのか、具体例もあると取得しやすくなるでしょう。
また、「半休」の定義は会社ごとに異なるため、ルールを説明しないと、従業員の間で認識にずれが生じ、トラブルになるかもしれません。トラブルを防ぐためにも、制度の内容をわかりやすくまとめた説明資料などを作成し、社内メールや掲示板を通じて広く告知しましょう。
7. 半休制度を導入する際の注意点


半休制度を導入する際の注意点は、主に以下の3つです。
- 従業員に対して不利益な扱いは禁止されている
- 半休の取得方法を明文化する
- 半休と時間有給は別のものと考える
ここでは、これらの注意点について解説します。
7-1. 従業員に対して不利益な扱いは禁止されている
半休制度を導入する際、従業員に対して不利益な扱いをしない配慮が必要です。労働基準法でも、有給休暇の取得に関して、従業員が不利になる取り扱いを禁止しています。
半休を取得する場合も、「不利益な扱いをしない」という方針が適用されます。例えば、半休を取得した従業員に対して賃金を減額したり、そのほかの従業員との不公平な扱いをしたりすることは認められていません。
半休時の給与計算で、平均賃金や標準報酬月額を利用する場合も従業員の利益を守るためのルールがあります。十分に確認し、半休制度によって知らずのうちに違法行為をしていることがないように注意しましょう。
7-2. 半休の取得方法を明文化する
半休制度を導入するときは、就業規則や社内規定に取得方法を明文化することが不可欠です。
半休を取得する際の始業時刻や終業時刻をはっきりと定めましょう。また、どのような手続きで取得できるかを社員に理解してもらえるような説明が必要です。一般的には、通常の有給休暇の取得方法と同様のプロセスを適用します。しかし、社員間で誤解を生まないように代休の取得方法として明文化するとよいでしょう。
- 届出方法(メール・書面・口頭など)
- 届出先(担当者・部署など)
- 提出期限(半休を希望する日の〇日前まで、など)
最低でもこの3つは明示するとともに、各部署でも説明するとよいでしょう。
手続き方法や届出先が明確になっていないと、半休を取得しにくく、手続きが遅滞するおそれもあります。半休の届出を受ける立場の人も含めて、取得方法を理解できることが大切です。
7-3. 半休と時間有給は別のものと考える
半休制度と時間単位の有給休暇は、法的には別の制度として考えましょう。
時間単位の有給休暇は、従業員が1時間単位で休暇を取得できる制度であり、労働基準法に基づいて導入されます。
一方、半休は半日だけ休暇を取得する制度で、企業が独自のルールで運用するものです。適用方法や導入の手続きは時間休とは異なるため混同しないように注意してください。
また、半休と時間休は併用することが可能です。午前に3時間の半休を取得し、午後は必要に応じて1時間単位で時間給を取得するということもできます。このような取り方を認めない場合は、併用禁止のルールを設ける必要があります。
8. 半休制度を導入して従業員のワークライフバランスを保とう


半休や時間休は、社員のワークライフバランスを支える重要な制度ですが、導入や運用には慎重な対応が求められます。
そのため、導入する場合は制度の目的を明確にし、就業規則をしっかり整備したうえで、社員への周知や意見を取り入れることが大切です。
また、半休と時間休が異なる制度であることを理解し、それぞれに合った取り扱いをしましょう。柔軟な働き方を実現するためには、社員一人ひとりのライフスタイルに合わせた制度を提供することが求められます。
半休制度を導入するときは、この記事で紹介したポイントを参考に、効果的な運用を目指しましょう。
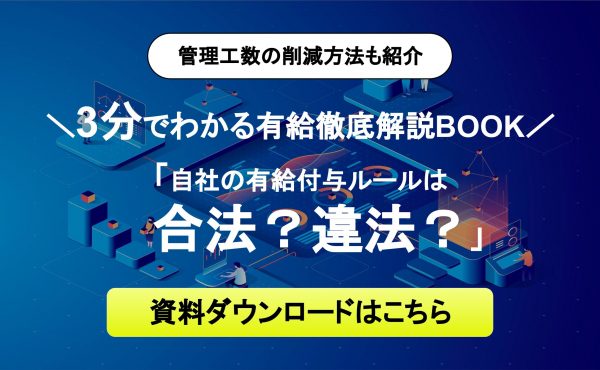
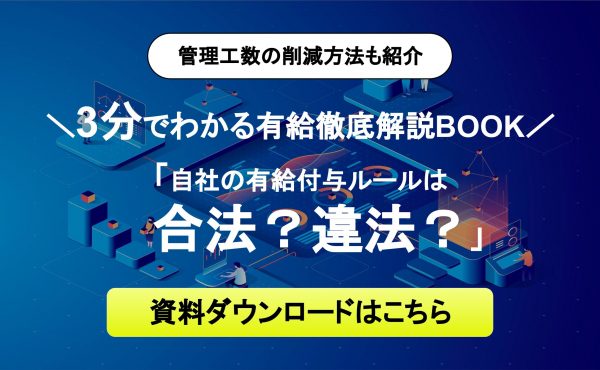
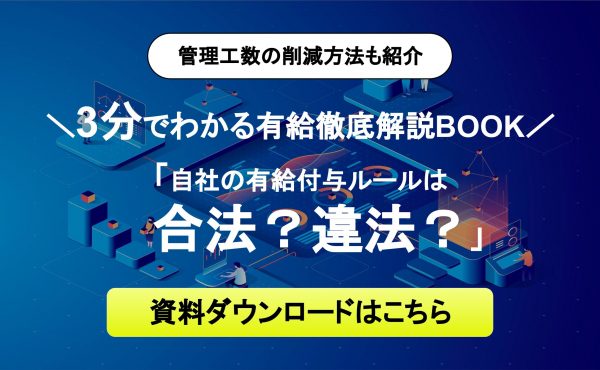
毎月の有給休暇の付与計算、取得状況の確認、法改正への対応…。
「この管理方法で本当に問題ないだろうか?」と不安を抱えながら、煩雑な業務に追われていませんか?
当サイトでは、担当者の方が抱えるそのようなお悩みを解決し、工数を削減しながらミスのない管理体制を構築するための実践的なノウハウを解説した資料を無料配布しています。
◆この資料でわかること
-
年5日の取得義務化で、企業が対応すべき3つのポイント
-
すぐに使える!Excelでの年次有給休暇管理簿の作り方
-
複雑なケース(前倒し付与など)の具体的な対応フロー
最新の法令に対応した、効率的で間違いのない有休管理のために、ぜひこちらから資料をダウンロードの上、ルールの見直しにお役立てください。
勤怠・給与計算のピックアップ
-



有給休暇の計算方法とは?出勤率や付与日数、取得時の賃金をミスなく算出するポイントを解説
勤怠・給与計算公開日:2020.04.17更新日:2026.01.29
-


36協定における残業時間の上限を基本からわかりやすく解説!
勤怠・給与計算公開日:2020.06.01更新日:2026.01.27
-


社会保険料の計算方法とは?計算例を交えて給与計算の注意点や条件を解説
勤怠・給与計算公開日:2020.12.10更新日:2025.12.16
-


在宅勤務における通勤手当の扱いや支給額の目安・計算方法
勤怠・給与計算公開日:2021.11.12更新日:2025.03.10
-


固定残業代の上限は45時間?超過するリスクを徹底解説
勤怠・給与計算公開日:2021.09.07更新日:2025.11.21
-


テレワークでしっかりした残業管理に欠かせない3つのポイント
勤怠・給与計算公開日:2020.07.20更新日:2025.02.07
休日休暇の関連記事
-


休日出勤のルールは?割増賃金が必要な場合や計算方法を解説
勤怠・給与計算公開日:2025.06.23更新日:2025.09.29
-


法定休日とは?労働基準法のルールや特定義務・割増賃金計算のポイントを解説
勤怠・給与計算公開日:2025.06.15更新日:2026.01.21
-


忌引き休暇は何日付与する?給料や土日と重なったときの対応などを解説
勤怠・給与計算公開日:2024.12.24更新日:2026.01.29




















