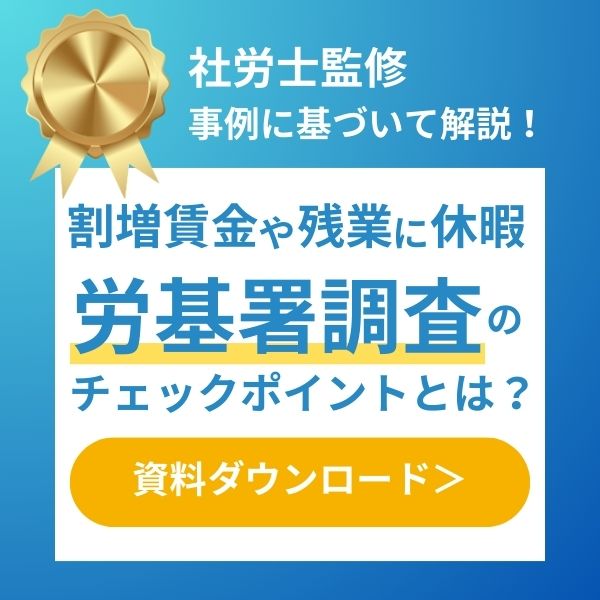副業禁止は就業規則で定められる?トラブルの対処法も解説
更新日: 2025.7.11 公開日: 2022.2.18 jinjer Blog 編集部

近年は副業を認める会社が増えてきていますが、その一方で、未だに就業規則等で副業を禁じている会社も多く、全体の約8割に上っています。
副業を禁止する法律はないものの、従業員が副業をすると労働時間の管理の手間が増えたり、従業員の健康リスクがあったりするため、企業側としては全面禁止にしたいというのが本音かもしれません。
しかし、物価上昇や家族の高齢化などの問題もあるため、副業を希望する従業員はは年々増加傾向にあると言われています。全面的に禁止した場合、離職のリスクが高まることも考えるので、自社で副業に関するルールを決める必要があります。
今回は就業規則で副業を禁止できるのか、副業で懲戒処分を下せるのかなどについて解説します。
参考:労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置 に関するガイドライン|厚生労働省
目次

人事労務担当者の実務の中で、勤怠管理は残業や深夜労働・有休消化など給与計算に直結するため、正確な管理が求められる一方で、計算が複雑でミスや抜け漏れが発生しやすい業務です。
さらに、働き方が多様化したことで管理すべき情報も多く、管理方法と集計にお困りの方もいらっしゃるのではないでしょうか。そんな担当者の方には、集計を自動化できる勤怠システムの導入がおすすめです。
◆解決できること
- 打刻漏れや勤務状況をリアルタイムで確認可能、複雑な労働時間の集計を自動化
- 有給休暇の残日数を従業員自身でいつでも確認可能、台帳の管理が不要に
- PCやスマホ・タブレットなど選べる打刻方法で、直行直帰やリモートワークにも対応
システムを利用したペーパーレス化に興味のある方は、ぜひこちらから資料をダウンロードの上、工数削減にお役立てください。
1. 就業規則で副業禁止は違法?


結論からいうと、就業規則で副業を禁止しても違法ではありません。
日本国憲法第22条では、何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有することができるとして、個人が自由に職業を選択できる権利を持つことが定められています。
そのため、本業とは別に副業をおこなったとしても、法律に抵触することはありません。
しかし、企業と従業員との契約においては、就業規則で副業を禁止することが可能です。労働基準法第2条第2項では、下記のように定められています。
(労働条件の決定)
第二条 労働条件は、労働者と使用者が、対等の立場において決定すべきものである。
② 労働者及び使用者は、労働協約、就業規則及び労働契約を遵守し、誠実に各々その義務を履行しなければならない。
そのため、就業規則に「副業禁止」の規定がある場合、使用者および労働者はそのルールを守る義務があり、違反した際は就業規則の規定に基づき、懲戒処分の対象になります。
就業規則に副業禁止を盛り込む場合は、どこに記載しているかを従業員に周知することが重要です。従業員が就業規則を読まなかった場合、「副業が禁止されていることを知らなかった」とトラブルになる可能性があるため、必ず周知を徹底しましょう。
ただし、従業員にもさまざまな事情があると考えられるので、全面的に禁止するというのは難しいかもしれません。前面禁止にした場合、人材の流出というリスクもあるため、従業員の事情も考慮して禁止事項を決めましょう。
関連記事:労働基準法での副業の規定や取り組むメリットについて
2. 副業を禁止できるケース


原則として企業は従業員の副業を禁止することはできません。しかし、従業員が副業をすることで次のような問題が起きる可能性があります。
- 労務提供上の支障がある
- 企業秘密が漏洩する
- 会社の名誉や信用を損なったり信頼関係を破壊したりする
- 競業により企業の利益を害する
上記のような問題を発生させないためには、それぞれに応じて副業禁止の就業規則を設ける必要があります。
ここでは、副業のリスクを回避するためにおこなう「副業を禁止するケース」について解説します。
2-1. 労務提供上の支障がある場合
副業をすることで本業の業務がおろそかになる、本業の業務中に副業をおこなうなど、労務提供上の支障がある場合は、副業を禁止しましょう。
労務提供に支障がでるかどうかは業種や業務によって異なりますが、例えば出勤時間が早朝だと副業のせいで遅刻をする可能性もあります。他にも、業務時間中にこっそり副業をおこなう従業員もいるかもしれません。
企業は従業員の健康維持だけでなく、業務の円滑な運営をおこなうという責任があるので、副業によってこれらが損なわれる場合、副業禁止は適切といえるでしょう。
2-2. 企業秘密が漏洩する場合
企業機密というのは、会社の財産にもなり得るもので、業務上の機密や顧客情報であれば、その漏洩は企業にとって重大なリスクを伴います。このリスク対策として、競業を避けるための副業制限は企業の正当な権利として位置付けられ、特に機密保持の観点から厳しく取り扱われます。
企業機密にもいろいろなものがありますが、漏洩すると下記のような事態を招く可能性があります。
- 類似商品を安価で作られる
- 営業戦略が他社にばれて先手を打たれる
- 顧客データが流出する
また、企業機密が漏洩すると、原因調査や正常業務への復旧作業、問合せ対応などの業務負担が発生します。このような事態を防ぐには、副業を禁止するのが有効な対策となるでしょう。
2-3. 会社の名誉や信用を損なったり信頼関係を破壊したりする行為がある場合
近年はさまざまな副業があり、中にはグレーゾーンのような業務もあります。このような業務に自社の従業員が関わっていた場合、会社の名誉や信用を損なったり、信頼関係が破壊されたりする可能性もあるので、副業を禁止するのが望ましいでしょう。
例え従業員はホワイトな仕事だと思っていても、「携帯買い付け」や「補助金の申請サポート」、「ネットワークビジネス」などは違法行為になる可能性があります。
企業のブランドイメージが損なわれることで、顧客や取引先からの信頼を失うリスクがあり、その結果、業績に深刻な影響を及ぼすことも考えられます。そのため、企業は就業規則において副業に関する明確な基準を設け、違法性の高い副業は禁止とするルールを定めることが必要です。
2-4. 競業により企業の利益を害する場合
従業員によっては、「自分のスキルを活かしたい」「業務が覚えやすい」などの理由で、競合企業で副業をすることもあり得ます。
業種や業務内容にもよりますが、競業で働いた場合、自社の顧客に競合企業の製品やサービスを提供する可能性があります。これは、自社の利益を害する行為になるため、副業は禁止しましょう。
特に、成果報酬制の場合は、従業員もできるだけ楽にたくさんの成果を上げるため、自社の顧客情報を利用するかもしれません。このような行為は就業規則で禁止しているのが一般的ですが、それでも完全に防げるわけではないので、不要なトラブルを防ぐためにも副業は禁止にするのが望ましいです。
3. 副業禁止の就業規則違反は解雇できる?


無断で副業・兼業をしていたことが発覚した場合、就業規則に副業禁止の規定がある場合のみ、懲戒処分の対象となります。
ただし、解雇などの重い処分が適用されるのは以下の三つのケースに限られるのが一般的です。
- 会社の社会的信用や名誉を侵害する副業・兼業
- 競業会社での副業・兼業
- 労務提供に重大な支障を生じさせる副業・兼業です。
これらの条件に該当する場合、企業は適切な対処を講じることが可能ですが、それでも即刻解雇というのは難しいと言われています。
ここでは、就業規則違反の解雇について、また過去の判例を紹介します。
3-1. 即解雇は難しい場合が多い
社会通念上、客観的に合理的な理由がなければ即解雇は難しいというのが原則的な考え方です。
副業禁止違反だけでなく、業務命令違反や勤務態度に問題があるなどの理由で解雇をすることがありますが、1回の違反で解雇が認められることはほぼありません。
また、例え合理的な理由があるとしても、解雇をおこなう30日前に予告をすることが義務付けられています。予告をしなかった場合は、30日分以上の平均賃金(解雇予告手当)、予告日数が30日に満たない場合は不足日数分の平均賃金を支払わなければなりません。
そのため、例え就業規則で副業を禁止していたとしても、本業の就業時間内に副業していたとしても、それを理由に即日解雇することはできないのが実情です。
3-2. 副業禁止に関する過去の裁判例
副業禁止に違反した従業員の解雇が認められなかったケースは、過去のような裁判例があります。
判例1:東京都私立大学教授事件(東京地判平成20年12月5日)
【概要】
教授が無許可で語学学校講師等の業務に従事し、講義を休講したことを理由として行われた懲戒解雇について、副業は夜間や休日に行われており、本業への支障は認められず、解雇無効とした事案。
【判決抜粋】
兼職(二重就職)は、本来は使用者の労働契約上の権限の及び得ない労働者の私生活における行為であるから、兼職(二重就職)許可制に形式的には違反する場合であっても、職場秩序に影響せず、かつ、使用者に対する労務提供に格別の支障を生ぜしめない程度・態様の二重就職については、兼職(二重就職)を禁止した就業規則の条項には実質的には違反しないものと解するのが相当である。
判例2:○小川建設事件(東京地決昭和57年11月19日)
【概要】
毎日6時間にわたるキャバレーでの無断就労を理由とする解雇について、兼業は深夜に及ぶものであって余暇利用のアルバイトの域を超えるものであり、社会通念上、会社への労務の誠実な提供に何らかの支障を来す蓋然性が高いことから、解雇有効とした事案。
【判決抜粋】
労働者は労働契約を通じて一日のうち一定の限られた時間のみ、労務に服するのを原則とし、就業時間外は本来労働者の自由であることからして、就業規則で兼業を全面的に禁止することは、特別な場合を除き、合理性を欠く。
しかしながら、・・・(中略)・・・兼業の内容によつては企業の経営秩序を害し、または企業の対外的信用、体面が傷つけられる場合もありうるので、従業員の兼業の許否について、労務提供上の支障や企業秩序への影響等を考慮したうえでの会社の承諾にかからしめる旨の規定を就業規則に定めることは不当とはいいがたく、したがつて、同趣旨の債務者就業規則第三一条四項の規定は合理を有するものである。
これらの判例からわかるように、法律においては「就業時間以外は労働者の自由」というのが基本的な考え方で、明らかに本業に支障がでたり企業の信用を貶めたりような副業でなければ、就業規則違反として解雇をすることは認められないという判決になります。
5. 労使間でトラブルになったときの労働審判の流れ


副業禁止について就業規定に定めたにも関わらず副業をおこなった従業員に対しては、就業規則に基づく懲戒処分を科します。しかし、処分を不服とする従業員との間にトラブルが生じることもあります。
労使間のトラブルは、使用者と労働者との話し合いで解決するのが望ましいですが、場合によっては労働審判と呼ばれる法的処置がとられることもあります。
審理は、労働審判官1名と労働審判員2名の計3名で組織される労働審判委員会によっておこなわれ、原則として3回以内の期日で審理が終結します。そのため、労働裁判に比べると短期間で労使間トラブルの解決を目指せますが、実際に労働審判の申立てがおこなわれても慌てることのないよう、大まかな流れを事前に把握しておきましょう。
ここからは、労働審判の基本的な流れを6つに分けて解説します。
参考:労働審判手続|裁判所
5-1. 申立て
労働審判とは、労使間で発生した問題を審理し、迅速な解決を目指すための裁判手続きのことです。労働審判の手続き前には、当事者双方が裁判所に呼び出され、答弁をおこないます。
その後、トラブルの発端となった懲戒処分の内容を不服とする申立者(労働者)が、地方裁判所に申立書を提出します。申立書には、懲戒処分に対する不満の理由や具体的な事案、証拠書類が記載されます。
申立書の内容を確認した後、裁判所は原則として、申立てを受理した際に、相手方となる企業に通知をおこないます。
5-2. 期日指定・呼び出し
申立てされた日から40日以内に、労働審判官より第1回の期日指定および呼び出しがおこなわれます。企業には期日呼出状と共に、申立書の写しなどが送付されますので、手元に届いたら中身を確認しましょう。
申立てがおこなわれてから、期間内にも関わらず、企業が呼び出しに応じなかった場合、裁判所から不利な判断が下されるリスクがあります。特に、労使間のトラブルが複雑化する前に、迅速かつ適切な対応をすることが重要です。
そのため、企業側は期日の通知を受けたら、遅滞なく準備を進め、必ず出席することが求められます。
また、呼び出しにおいては、企業側は自身の主張を正確に伝え、必要に応じて証拠を提示することが重要です。労働者と企業がお互いに期日を守り、しっかりと準備をおこなうことで、スムーズな審理を迎えることができるでしょう。
5-3. 答弁書等の提出
企業は、労働審判官が定めた期限までに、答弁書等を提出する必要があります。
答弁書には、以下6つの事項を記載することとされています。
- 申立の趣旨に対する答弁
- 申立書に記載された事実に対する認否
- 答弁を理由付ける具体的な事実
- 予想される争点及び当該争点に関連する重要な事実
- 予想される争点ごとの証拠
- 当事者間においてされた交渉その他の申立てに至る経緯の概要
答弁書は、労働審判委員会への心証や、証拠調べなどに影響を及ぼす要素のひとつなので、正確な情報や経緯を記載すると共に、反論すべきポイントはきちんと反論することが大切です。
参考:労働審判規則|裁判所
5-4. 期日における審理
労働審判委員会による審理の期日は原則として3回以内で、その期日内に労使双方の言い分を聞き、トラブルの内容や争点を整理します。必要に応じて、申立人や企業の関係者などから直接事情を聴取することもあります。
労働審判の期日における審理は、労働者と企業双方が公平に意見を述べる機会です。ここでは、双方が提出した主張や証拠に基づいて、どのような点が争点となっているのかを明確にするための重要なステップがあります。
また、審理中は証人の出廷を求めることも可能であり、必要に応じて追加の証拠を提出することもあります。これにより、労働審判官はさまざまな角度からの情報を元に、問題の解決に向けた判断を行うことができます。
期日における審理は、速やかに解決を図るための大切な手続きであり、労働者と企業の双方が適切に考えを述べることが求められます。したがって、この機会を最大限に活用し、公平な議論を進めることが重要です。
5-5. 調停成立
3回以内の期日の中で、話し合いによる解決の見込みがあるとみなされた場合、調停を試みます。労使間の話し合いがまとまったら調停成立となり、手続きは完了です。
調停内容は調書に記載され、条項の内容によっては強制執行を申し立てることも可能となります。
この過程で重要なのは、双方が誠意を持って話し合いに臨むことです。調停成立に至るためには、労働者と企業双方が妥協点を見出し、共通の利益を追求する姿勢が求められます。
調停が成立した場合、労働者と企業は今後の関係をより良好に保つための基盤を築くことができるため、この行程は非常に重要です。
5-6. 労働審判
調停成立の見込みがないと判断された場合、労働審判委員会がおこなった審理の結果をもとに、当事者間の権利関係や、これまでの手続きの経過などを踏まえ、実情に即した判断を下します。
労働審判に対して2週間以内に異議申立がおこなわれなければ、労働審判は確定し、内容によっては強制執行を申し立てることが可能となります。
一方、労働審判に不服がある場合は、2週間以内に異議申立をおこなうことが可能です。労働審判の効力が失われると共に、訴訟手続き(労働裁判)へ移行することになります。
6. 副業禁止を就業規則に定めるかどうか慎重に判断しよう


日本の法律では職業選択の自由が認められているため、原則として副業をおこなうことは法に触れるわけではありません。
ただし、企業は就業規則で「副業禁止」を規定することが可能です。就業規則で副業を禁止しているにもかかわらず、副業をおこなった従業員は懲戒処分の対象となりえます。
ただちに重い処分を科すケースはまれですが、会社に著しい損害を与えた場合や、本業に支障を来す場合などは懲戒解雇を科さざるを得ません。
しかし、労働者が懲戒処分を不服とした場合、労使間トラブルに発展し、労働審理に移行する可能性もあります。そもそも、副業は法律で禁止されていることではなく、副業をすることは現代社会で一般的になってきているので、副業を禁止にするかどうかは慎重に判断しましょう。



人事労務担当者の実務の中で、勤怠管理は残業や深夜労働・有休消化など給与計算に直結するため、正確な管理が求められる一方で、計算が複雑でミスや抜け漏れが発生しやすい業務です。
さらに、働き方が多様化したことで管理すべき情報も多く、管理方法と集計にお困りの方もいらっしゃるのではないでしょうか。そんな担当者の方には、集計を自動化できる勤怠システムの導入がおすすめです。
◆解決できること
- 打刻漏れや勤務状況をリアルタイムで確認可能、複雑な労働時間の集計を自動化
- 有給休暇の残日数を従業員自身でいつでも確認可能、台帳の管理が不要に
- PCやスマホ・タブレットなど選べる打刻方法で、直行直帰やリモートワークにも対応
システムを利用したペーパーレス化に興味のある方は、ぜひこちらから資料をダウンロードの上、工数削減にお役立てください。
勤怠・給与計算のピックアップ
-



有給休暇の計算方法とは?出勤率や付与日数、取得時の賃金をミスなく算出するポイントを解説
勤怠・給与計算公開日:2020.04.17更新日:2026.01.29
-


36協定における残業時間の上限を基本からわかりやすく解説!
勤怠・給与計算公開日:2020.06.01更新日:2026.01.27
-


社会保険料の計算方法とは?計算例を交えて給与計算の注意点や条件を解説
勤怠・給与計算公開日:2020.12.10更新日:2025.12.16
-


在宅勤務における通勤手当の扱いや支給額の目安・計算方法
勤怠・給与計算公開日:2021.11.12更新日:2025.03.10
-


固定残業代の上限は45時間?超過するリスクを徹底解説
勤怠・給与計算公開日:2021.09.07更新日:2025.11.21
-


テレワークでしっかりした残業管理に欠かせない3つのポイント
勤怠・給与計算公開日:2020.07.20更新日:2025.02.07
労働時間の関連記事
-


副業の労働時間通算ルールはいつから見直される?改正の最新動向
勤怠・給与計算公開日:2025.12.17更新日:2026.01.15
-


着替えは労働時間に含まれる?具体的なケースや判例を交えながら分かりやすく解説
勤怠・給与計算公開日:2025.04.16更新日:2025.10.06
-


過重労働の基準とは?法的ラインや健康リスク・防止策をわかりやすく解説
勤怠・給与計算公開日:2025.02.16更新日:2026.02.27