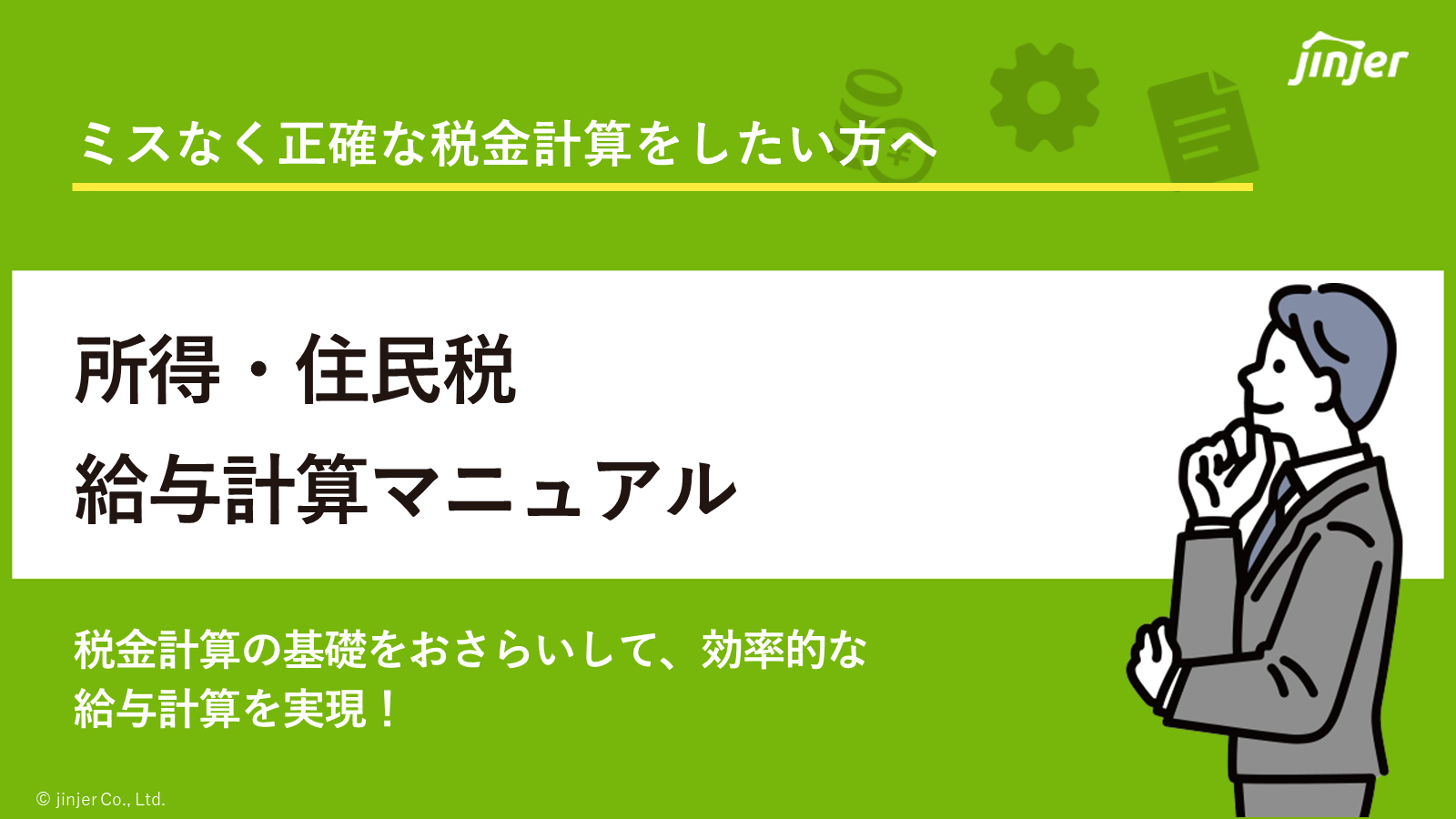賞与から引かれる所得税の基礎知識と計算方法について解説
更新日: 2024.3.12
公開日: 2022.3.22
OHSUGI

会社勤めをしている方にとって、賞与は非常にありがたいものですが、額面金額と手取り金額に大きな差が発生してしまうことがあります。
給与と同様に、賞与でも額面金額からいろいろなものが引かれているため、額面金額を満額もらえるわけではないことは、当然理解しているでしょう。
しかし、「それにしても差がありすぎる、必要な金額以上に会社に持っていかれているのでは…」というような疑いを抱いてしまう従業員もいるかもしれません。そのため、このような従業員から経理担当者に質問がくる可能性があります。経理担当者は適切な計算はもちろん、従業員の質問にも対応できるようにしておきましょう。
本記事では、賞与から引かれるものの内訳や賞与の源泉所得税の計算方法について説明すると同時に、具体的な例を用いて賞与の源泉所得税額のシミュレーションをおこないます。
関連記事:所得税とは?納税方法や確定申告が必要な人・不要な人について解説
給与計算業務は税務リスクや労務リスクと隣り合わせであるため、
・税額が合っているか不安
・税率を正しく計上できているか不安
・自社に合った税金計算方法(システム導入?代行依頼?)がわからない
というような悩みをお持ちのご担当者様は多いと思います。
そのような方に向け、当サイトでは所得税と住民税の正しい計算方法、税金計算時によく起きるミスとその対策をまとめた資料を無料で配布しております。
本資料にて、税金計算のミスを減らしたり、効率化が図れる給与計算システムの解説もあるので、税金計算をミスなく効率的に行いたいという方は、こちらから「所得・住民税 給与計算マニュアル」をダウンロードしてご覧ください。
1. 賞与から引かれる所得税や保険料の種類

賞与は給与と同じく、額面金額をそのまま受け取れるわけではありません。
賞与からは、以下に挙げるようなものが引かれているからです。
- 所得税(源泉徴収)
- 健康保険料
- 介護保険料(40歳以上の場合)
- 厚生年金保険料
- 雇用保険料
所得税の金額は、健康保険料、介護保険料、厚生年金保険料、雇用保険料の金額を用いて算出されます。
そのため以下では、まず先に所得税以外の保険料の算出方法について、簡単に説明します。
1-1. 健康保険料
健康保険料は、「標準賞与額×健康保険料率÷2」という式で算出されます。
標準賞与額とは、賞与の額面金額から1,000円未満を切り捨てた額のことで、額面金額が52万3,600円の場合、標準賞与額は52万3,000円となります。
健康保険料率に関しては、「協会けんぽ」では都道府県ごとに異なっているので、協会けんぽのホームページに載せられている保険料額表で確認するとよいでしょう。
1-2. 介護保険料
40歳以上の方の場合は、健康保険料に加えて介護保険料も支払う必要があります。
上述した協会けんぽの保険料額表には、介護保険料率を加味したものも記載されているので、40歳以上の方はそちらの数値を参照して保険料の算出をおこなってください。
なお、健康保険組合がある企業にお勤めの場合は、健康保険料と介護保険料率が独自に決められています。
保険料を計算したい場合は、健保組合に問い合わせてそれぞれの料率を確認しましょう。
1-3. 厚生年金保険料
厚生年金保険料は、「標準賞与額×厚生年金保険料率÷2」という式で算出されます。
計算に用いられる料率が健康保険料率から厚生年金保険料率に変わった以外は、健康保険料の算出方法と同じです。
厚生年金保険料率は徐々に引き上げられていましたが、平成29年9月に引き上げが終了し、現在では18.3%で固定となっています。
1-4.雇用保険料
雇用保険料は、「賞与額面×雇用保険料率」という式で算出されます。
健康保険料や厚生年金保険料では、標準賞与額を用いて算出していましたが、雇用保険料は賞与の額面金額をそのまま用いることには注意しておきましょう。
また、健康保険料や厚生年金保険料は会社と折半のため「÷2」をしていましたが、雇用保険料は会社と折半ではないため、「÷2」をする必要がありません。
雇用保険料は会社の業態によって異なり、一般事業では0.3%、農林水産や建設事業などでは0.4%となっています。
2. 賞与の源泉所得税の計算方法

賞与の源泉所得税は、上述した4つの保険料を用いて、以下の式で算出されます。
(賞与額面-健康保険料-介護保険料-厚生年金保険料-雇用保険料)×源泉徴収税率
雇用保険料と同じように、標準賞与額ではなく賞与の額面金額をそのまま用いて算出します。
源泉徴収税率は、「前月の給与の総支給額から社会保険料を差し引いた金額」と、「扶養人数」によって決まるため、人によって異なります。
具体的な所得税率は、国税庁のホームページに記載されている「賞与に対する源泉徴収税額の算出率表」に記載されているので、源泉徴収税率を把握したい場合はそちらを確認するとよいでしょう。なお算出率表には甲欄と乙欄があります。給与所得者の扶養控除等申告書を提出している従業員は甲欄を、それ以外の従業員は乙欄を見て所得税等の金額を求めます。
2-1.前月の給与を用いて賞与の所得税の計算をおこなう
では具体的に、賞与にかかる所得税の計算をシミュレーションしてみましょう。
所得税の計算に必要な数値が、以下のようになっていると仮定します(それぞれの数値は簡単のため分かりやすい数値にしています)。
- 賞与額面金額:400,000円
- 健康保険料と介護保険料の合計額::25,000円
- 厚生年金保険料:40,000円
- 雇用保険料:2,000円
- 前月の給与の総支給額:200,000円
- 前月の社会保険料の総額:40,000円
- 扶養人数:2人
まず源泉徴収税率に関してですが、「前月の給与の総支給額から社会保険料を差し引いた金額」は、200,000円-40,000円=160,000円です。
この数値と扶養人数が2人という条件を満たす場合の源泉徴収税率を、「賞与に対する源泉徴収税額の算出率表」で確認すると、「2.042%」という数字になります。
そのため、賞与から引かれる源泉所得税の金額は、以下のようになります。
(400,000円-25,000円-40,000円-2,000円)×0.02042≒6,800円
算出された数値だけ見ても、どのようにしてその金額が弾き出されたかが分からないかもしれませんが、上述したような過程を経ることで、数値の内訳を理解できるでしょう。
当サイトでは、賞与における所得税の計算を考える上で、そもそも必要となる基礎知識や給与にかかる所得税の計算方法をまとめた資料を無料で配布しております。
税金に関する知識で不安な点がある方は、こちらから「所得・住民税 給与計算マニュアル」をダウンロードしてご確認ください。
関連記事:所得税の計算方法は?計算を効率良く行う方法や年収が変わった場合について
3. 所得税や保険料算出に関する知識があれば、容易に算出することができる

賞与であっても所得税が発生するため、適切な計算が求められます。賞与の所得税を計算するには額面から以下を引く必要があります。
- 健康保険料
- 介護保険料
- 厚生年金保険料
- 雇用保険料
上記を引いたのちに、源泉徴収税率を乗じましょう。具体的な源泉所得税率は「賞与に対する源泉徴収税額の算出率表」を参考にするのがおすすめです。源泉所得税率は扶養人数によっても変動します。そのため、従業員が給与所得者の扶養控除等申告書を提出しているのであれば、「賞与に対する源泉徴収税額の算出率表」の甲欄を確認しましょう。
賞与は給与と同じく従業員にとって大切な報酬です。そのため、しっかりと計算方法を把握してミスのない計算につなげることが大切です。
給与計算業務は税務リスクや労務リスクと隣り合わせであるため、
・税額が合っているか不安
・税率を正しく計上できているか不安
・自社に合った税金計算方法(システム導入?代行依頼?)がわからない
というような悩みをお持ちのご担当者様は多いと思います。
そのような方に向け、当サイトでは所得税と住民税の正しい計算方法、税金計算時によく起きるミスとその対策をまとめた資料を無料で配布しております。
本資料にて、税金計算のミスを減らしたり、効率化が図れる給与計算システムの解説もあるので、税金計算をミスなく効率的に行いたいという方は、こちらから「所得・住民税 給与計算マニュアル」をダウンロードしてご覧ください。
勤怠・給与計算のピックアップ
-

【図解付き】有給休暇の付与日数とその計算方法とは?金額の計算方法も紹介
勤怠・給与計算
公開日:2020.04.17更新日:2024.03.07
-


36協定における残業時間の上限を基本からわかりやすく解説!
勤怠・給与計算
公開日:2020.06.01更新日:2024.06.04
-


社会保険料の計算方法とは?給与計算や社会保険料率についても解説
勤怠・給与計算
公開日:2020.12.10更新日:2024.07.08
-


在宅勤務における通勤手当の扱いや支給額の目安・計算方法
勤怠・給与計算
公開日:2021.11.12更新日:2024.06.19
-


固定残業代の上限は45時間?超過するリスクを徹底解説
勤怠・給与計算
公開日:2021.09.07更新日:2024.03.07
-


テレワークでしっかりした残業管理に欠かせない3つのポイント
勤怠・給与計算
公開日:2020.07.20更新日:2024.03.25