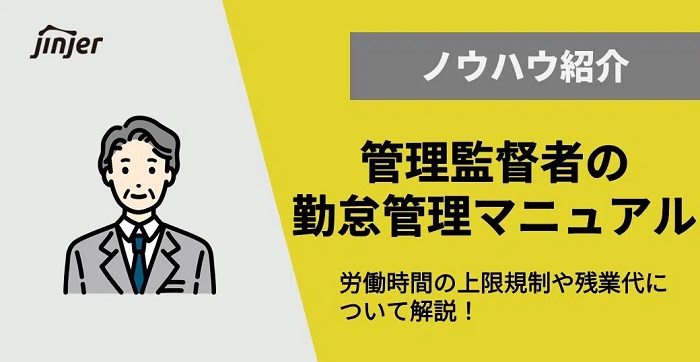管理職の労働時間・休憩時間や休日についての基礎知識を徹底解説!
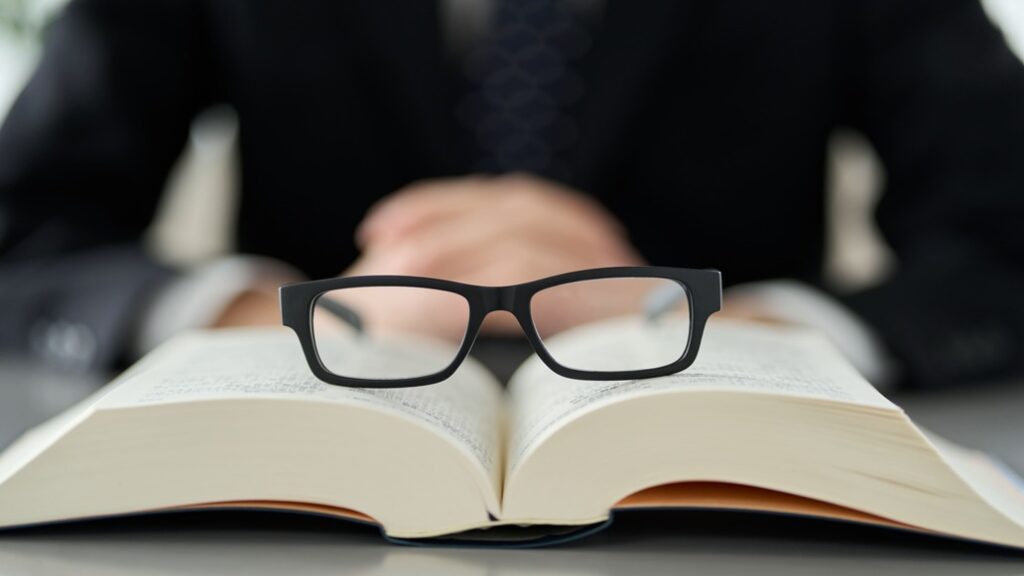
近年では働き方改革の影響で、労働時間を企業がしっかり管理するという意識がさらに高まってきました。しかし、これはあくまで一般従業員に対するもので、管理職従業員の労働時間となるとまだそれほど重要視されていないことが多いようです。
しかし離職者を減らし、管理職従業員も働きやすい環境を整えることは非常に重要です。では管理職従業員の労働時間と休憩時間についてのルールを見ていきましょう。
【関連記事】労働時間について知らないとまずい基礎知識をおさらい!
目次
管理監督者に残業の上限規制は適用されませんが、労働時間の把握は管理監督者であってもしなくてはならないと、法改正で変更になりました。
この他にも、法律の定義にあった管理監督者でなければ、残業の上限超過や残業代未払いとして違法になってしまうなど、管理監督者の勤怠管理は注意すべきポイントがいくつかあります。
当サイトでは、「管理職の勤怠管理を法律に則って行いたい」という方に向け、管理監督者の勤怠管理の方法やポイントについて、本記事の内容に補足事項を加えわかりやすくまとめた資料を無料で配布しております。
管理職の勤怠管理に不安のある方は、こちらから資料をダウンロードしてご覧ください。
1. 管理職の労働時間ルール


管理職の労働時間について考える場合、役職を持たない一般の従業員とは労働時間の上限が異なることを知識として覚えておくことが重要です。
一般の従業員のケースでは、労働基準法によって一日の労働時間が8時間かつ週40時間までと定められています。部長や課長、チーフマネージャーのような管理職の方であっても、この労働基準法に基づいて労働時間が決まります。
労働組合と会社との間で36協定を結んだ場合のみ、この上限を超えて労働をおこなうことが可能です。それでも残業できる時間も細かく定められており、無限に残業させられるわけではありません。当然残業代の支払いも求められます。
1-1. 管理監督者は労働基準法の規制の対象外
管理職であっても、しっかりとルールに則って労働時間を決める必要があります。ただし、管理職従業員のなかでも「管理監督者」に該当する方の場合には、この労働基準法の規制を受けません。
管理監督者は社長や専務のように定時に出勤・退勤するという勤務形態が現実的でないなどのケースで、労働基準法の定める労働時間の規制を受けないということになるのです。
また、管理監督者は労働基準法で定められている「1日8時間、週40時間」の法定労働時間が適用されないため、時間外労働という概念もなく、残業時間にも規制がありません。したがって、管理監督者には残業代が支給されないのです。
ただし、管理監督者であっても深夜時間である22時~翌5時におこなった労働に対しては、割増賃金を上乗せした深夜手当が支給されます。
2. 管理職の休憩時間ルール


管理職従業員の労働時間は労働基準法によって定められていますが、管理職の休憩時間もルールがあるのでしょうか。こちらのケースであっても労働時間と同様、一般企業でいう管理職にも休憩時間は決められています。
労働時間が6時間を超え、8時間以下の場合は少なくとも45分、8時間を超える場合には少なくとも1時間の休憩が与えられなければなりません。
労働時間が6時間以下の場合は、法律上休憩が無くても問題はないとされています。ここで重要なのは休憩時間が何を指すかということです。休憩時間は労働から離れて自由に過ごせる時間であり、誰の指示下にもない時間です。さらに休憩時間は労働時間の途中に取ることと定められています。
たとえば、業務開始時間の1時間前に出社させ、業務開始まで休憩を取らせることはできません。さらに労働から離れていなければならないため、1時間電話番をさせたり顧客対応のために待機させたりしている時間を休憩時間と見なすことも不可です。
また、業務をせずにどこかに待機するよう上司が命じた場合でも、誰の指示下にもないという休憩時間のルールに反するため、同様に休憩時間に含めることができません。休憩時間もこのように細かい規定があるのです。
2-1. 管理監督者は例外
しかし労働時間と同様、管理職社員のなかでも管理監督者にあたる場合には労働基準法の休憩の規制の対象とはなりません。
企業側が管理監督者についてどのくらい働いているのか、どのくらい休憩しているのかを把握しておく必要はありますが、極端にいえばまったく休憩を取らずに働かせることも可能です。
しかし企業は管理監督者として働いている従業員に対して労働時間と休憩時間をしっかり把握し、過重労働させないように注意を払うべきでしょう。
当サイトでは「管理監督者の勤怠管理マニュアル」という資料を無料配布しております。本資料では管理職の残業代や労働時間の上限、そもそも何をもって管理監督者になるのかなどを法律の観点でわかりやすく解説しております。勤怠管理の管理者にとっては大変参考になる内容となっておりますので興味のある方はこちらから無料でダウンロードしてご覧ください。
3. 管理職に休みや休暇はない?


通常であれば、労働基準法によって休日は「1週間のうちに1日、もしくは4週を通じて4日」を与えなくてはならないとされています。このルールは、管理職にも当てはまるのでしょうか?
3-1. 管理職には労働基準法に定められた休みはない
休日についても同様に、労働基準法で取得が定められている法定休日のルールも、管理監督者には適用されません。つまり、管理監督者に休みを取らせなくても、法律違反にはならないのです。
したがって、休日労働への割増賃金を支給する必要はなく、管理監督者には休日手当の支払いも不要です。
しかし、管理監督者にも安全配慮義務はあるため、休みなく働かせ続けるというのはおすすめできません。管理監督者の心身の健康を損ねない範囲の労働時間になるように配慮する義務があります。
3-2. 管理職であっても有給休暇はあり、取得義務化の対象
管理監督者には法定休日や代休、振替休日はありませんが、有給休暇は付与されます。1年に10日以上の年次有給休暇が付与されれば取得義務化の対象となりますが、こちらは管理職も含まれます。
「管理職は休みがない」というイメージから、有給も同じであると考えて管理していると法律違反になってしまうため、気をつけましょう。
4. そもそも管理職とは?管理監督者とみなされる4つの基準


企業の中で「管理職」といわれいても、労働基準法が定める「管理監督者」には当てはまらない可能性があります。管理監督者は役職名ではなく実態に基づいて判断されるため、役職についているからといって必ず管理監督者にあてはまるとは限らないのです。
そもそも、労働基準法における「管理監督者」とは、経営者と一体の立場として事業上の判断をおこなったり、責任をおったりしている従業員のことを指しますが、「職務内容」「責任と権限」「勤務形態」「賃金(待遇)」の4つを基準として管理監督者にあたるかが判断されます。それぞれの基準について、確認していきましょう。
4-1. 重要な職務を担っていること
管理監督者には労働時間の上限や休憩、休日の規定が適用されませんが、その規制を超えて労働しなければならないほどの重要な職務を担っていなければ、管理監督者とみなされません。
たとえば、労働時間の管理や人事考課、従業員の採用・解雇などの業務を担当している場合、重要な職務を担っているといえるでしょう。
4-2. 十分な責任と権限をもっていること
「課長」や「リーダー」などの役職についていたとしても、実際には多くのことについて裁量がなく上司の判断を仰がなければならない状態であったり、上司の指示や命令に基づいて業務をおこなう場合は、管理監督者であるとはみなされません。
4-3. 厳密な管理をされず、労働時間の規制になじまない勤務態様であること
管理監督者は経営者と一体の立場となって経営上の判断をするため、時を選ばずに対応が必要になることがあります。したがって、労働時間が定められており裁量がないなど厳密に管理されている場合は、管理監督者とはいえません。
4-4. 賃金などについて、一般の従業員よりも待遇が良いこと
管理監督者は、一般の従業員よりも重要な職務や重い責任を負っています。したがって、給与や賞与などの待遇も一般の従業員と比較して優遇されていなければなりません。給与を時間単価に換算した際に、一般の従業員の給与や最低賃金よりも下回っている場合、管理監督者とはみなせません。
5. 管理職にも勤怠管理は必要!
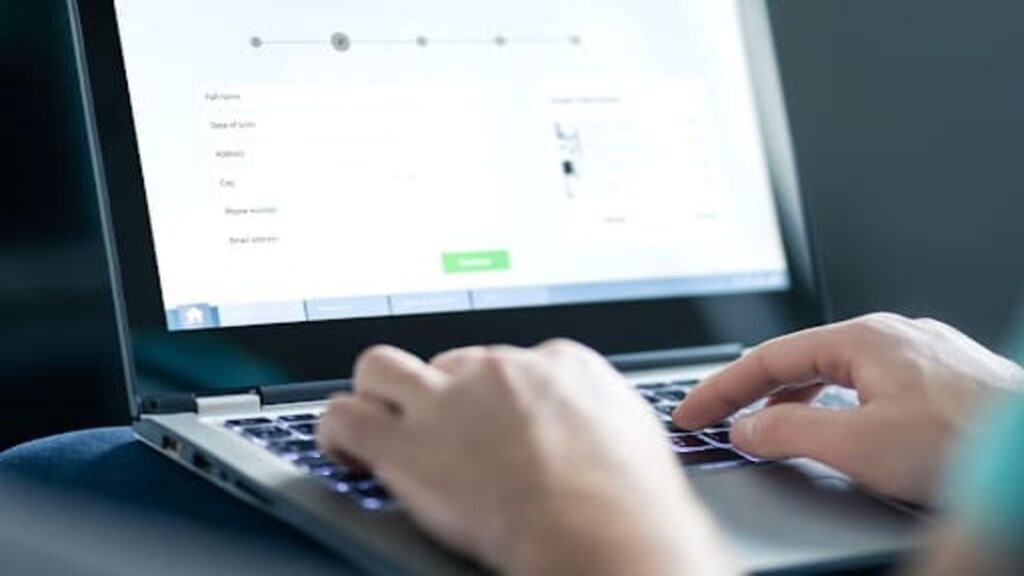
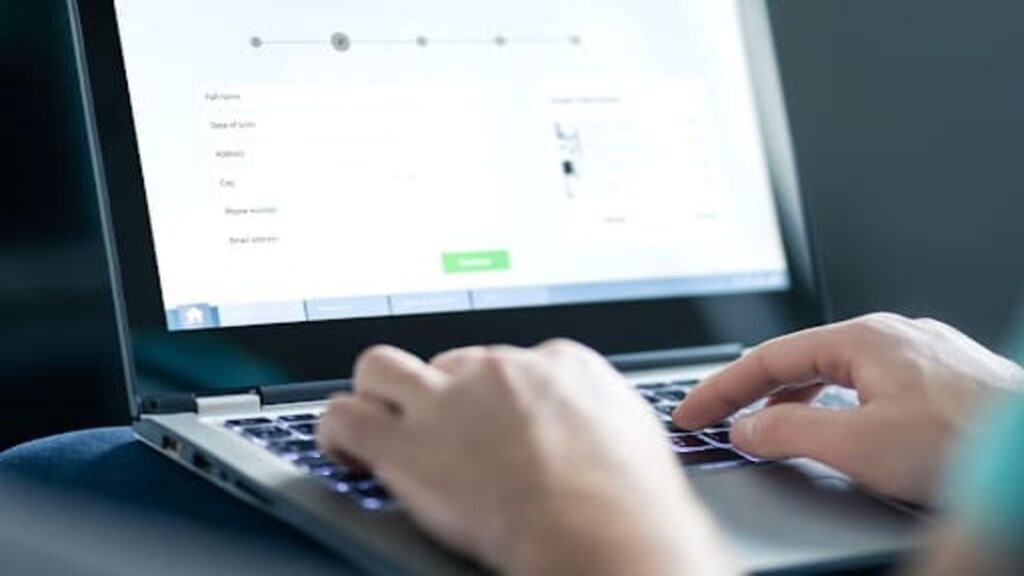
管理監督者には労働時間や残業時間の上限がなく、休憩や休日も労働基準法のルールが適用されないため、勤怠管理は不必要であると考える方もいらっしゃるかもしれません。
たしかに、以前は管理監督者の勤怠管理は「おこなうのが望ましい」というレベルでしたが、2019年にあった働き方改革による労働安全衛生法の改正により、管理監督者であっても勤怠管理をしなければならなくなりました。
これは、労働安全衛生法第66条の8で、過度な長時間労働者に対して医師の面談を受けさなければならないとされており、その対象者を把握するために労働時間の管理が必要になったのです。
外出が多かったり、労働時間が長くなりがちな管理監督者の労働時間を把握するには、勤怠管理システムの導入がおすすめです。勤怠管理システムは多様な打刻方法を取り揃えているため、外出先でも打刻が可能なほか、労働時間をリアルタイムで把握することができるため、一般の従業員の勤怠管理にも役立ちます。
勤怠管理システムで何ができるかを知りたい方は、以下のリンクより勤怠管理システム「ジンジャー勤怠」のサービス紹介ページをご覧ください。
▶クラウド型勤怠管理システム「ジンジャー勤怠」のサービス紹介ページを見る
6. 管理職の労働時間をチェックする方法


上述で解説したとおり、労働者の健康を守るという観点から、管理職であっても適切に労働時間をチェックする必要があります。ここでは、効率良く管理職の労働時間を管理する3つの方法についてご紹介します。
6-1. タイムカードを使用する
出勤時と退勤時にタイムカードをタイムレコーダーへ挿すだけで、自動で出退勤の時間を記録することができる方法です。出勤簿のように手書きする手間が省けるため、多忙を極める管理職にとっては利便性の高い方法だといえるでしょう。
一方で、基本的には出退勤の時間しか記録できないものが多いため、管理者にも取得が義務付けられている有給休暇については別に管理しなくてはなりません。また、テレワークが多い職場においては、タイムカードを使用した労働時間の管理は不向きだといえます。
6-2. エクセルで出勤簿を作成する
エクセルで出勤簿を作成して管理する方法は、エクセルさえあればすぐに導入できるため、3つの方法の中でも一番コストを抑えることが可能です。さらに関数を使えば、残業時間や有給休暇の管理までおこなうこともできます。
ただし、本人の自己申告によって出退勤の時間を入力するため、改ざんが容易にできてしまうことが欠点として挙げられます。また、数式が破損してしまうと、誤って集計されてしまう恐れもあるため注意が必要です。
6-3. 勤怠管理システムを導入する
勤怠管理システムであれば、客観的に労働時間を記録できるため、厚生労働省のガイドライン「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関する基準」に則って運用ができます。不正打刻に関しても、ICカードやGPS機能付きスマートフォン、生体認証などの打刻に対応したシステムがあり、このような機能を活用すれば未然に防げるのでおすすめです。
最近では、テレワークの普及を受けて、パソコンだけでなくスマートフォンやタブレット端末にも対応した勤怠管理システムも登場しています。遠隔操作によって出退勤の打刻がおこなるため、オフィスという場所に縛られない柔軟な働き方にも対応でき、管理職の勤怠時間も適切に管理することができるでしょう。
7. 管理職の労働時間も適切に管理しよう
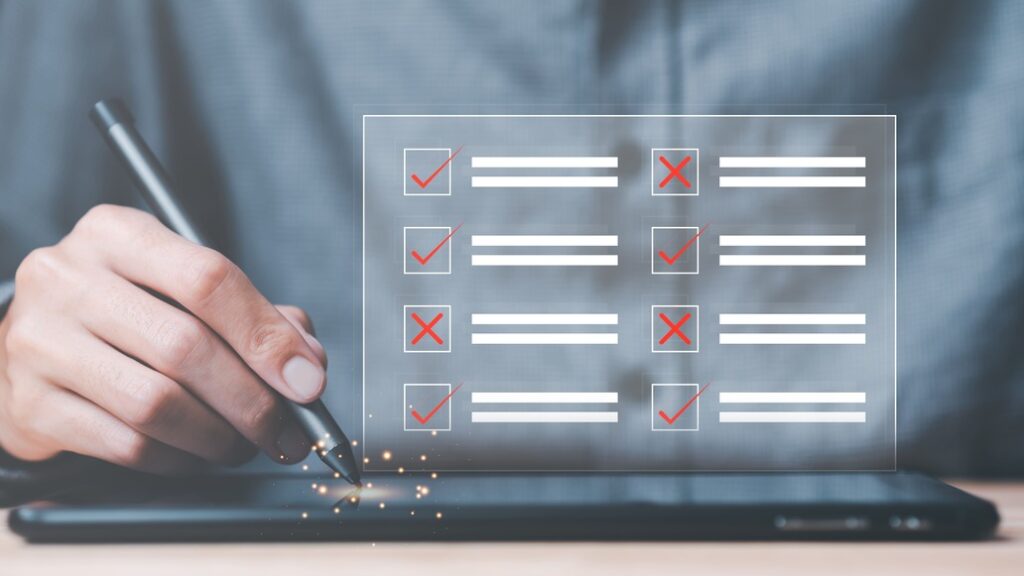
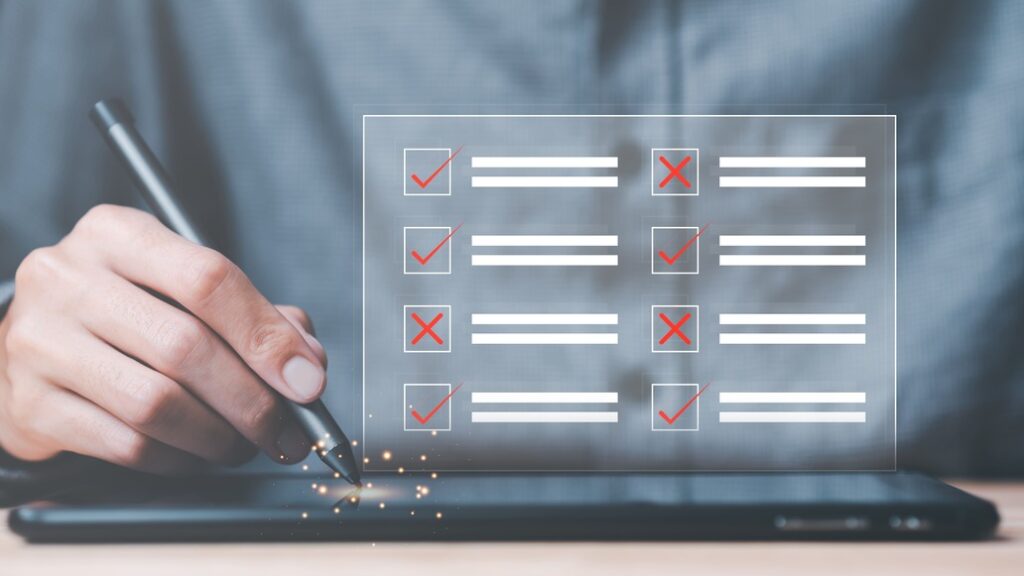
管理職社員の労働時間や休憩時間は、その社員が一般企業の定義する管理職なのか、労働基準法の定める「管理監督者」なのかによって大きく異なります。こうした点を従業員が知識として身につけているかどうかを確認するのも企業の務めの1つです。
したがって労働時間の上限、休憩時間の長さ、さらに労働時間・休憩時間とは何を指すのかを周知することが非常に重要です。
適切な業務がおこなわれ、従業員にとって働きやすい環境を整えるためにも、企業全体として労働基準法を遵守すること、管理監督者の労働時間をしっかり把握することを意識していく必要があるでしょう。
身近な法律情報誌リーガレットというサイトにおいて、管理職の労働時間について解説されています。是非、読んでみてください。
管理職の労働時間は平均177時間!上限規制の有無と把握義務を解説|リーガレット (legalet.net)
管理監督者に残業の上限規制は適用されませんが、労働時間の把握は管理監督者であってもしなくてはならないと、法改正で変更になりました。
この他にも、法律の定義にあった管理監督者でなければ、残業の上限超過や残業代未払いとして違法になってしまうなど、管理監督者の勤怠管理は注意すべきポイントがいくつかあります。
当サイトでは、「管理職の勤怠管理を法律に則って行いたい」という方に向け、管理監督者の勤怠管理の方法やポイントについて、本記事の内容に補足事項を加えわかりやすくまとめた資料を無料で配布しております。
管理職の勤怠管理に不安のある方は、こちらから資料をダウンロードしてご覧ください。
勤怠・給与計算のピックアップ
-




【図解付き】有給休暇の付与日数とその計算方法とは?金額の計算方法も紹介
勤怠・給与計算
公開日:2020.04.17更新日:2024.03.07
-


36協定における残業時間の上限を基本からわかりやすく解説!
勤怠・給与計算
公開日:2020.06.01更新日:2024.06.04
-


社会保険料の計算方法とは?給与計算や社会保険料率についても解説
勤怠・給与計算
公開日:2020.12.10更新日:2024.07.08
-


在宅勤務における通勤手当の扱いや支給額の目安・計算方法
勤怠・給与計算
公開日:2021.11.12更新日:2024.06.19
-


固定残業代の上限は45時間?超過するリスクを徹底解説
勤怠・給与計算
公開日:2021.09.07更新日:2024.03.07
-


テレワークでしっかりした残業管理に欠かせない3つのポイント
勤怠・給与計算
公開日:2020.07.20更新日:2024.03.25