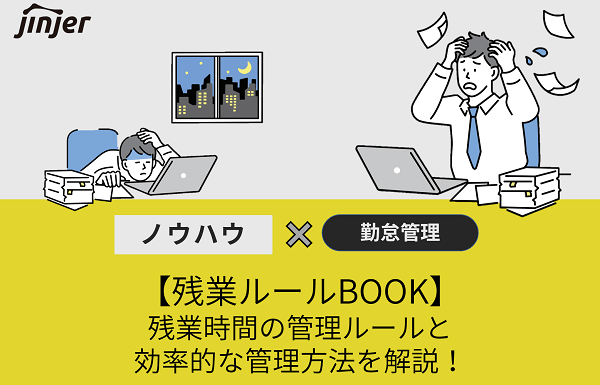労働時間について知っておきたい基礎知識をおさらい!労働時間計算方法も紹介
『不必要な残業を減らして人件費をカットする』『従業員の労働時間を圧縮することで時間あたりの生産性を高める』『従業員のプライベートを確保することによって離職者を減らす』など、企業が勤怠管理を通じて何らかの課題の解決を目指す場合、労働時間の正しい理解が必要です。
従業員の給与計算は、労働時間×時給で金額が決まります。人事の側が労働時間の定義を間違って理解していると、離職率が高くなったり職員の退職時に未払いの残業代を請求されたりするため、今回は人事担当者が把握しておく必要がある労働時間の基礎知識をおさらいしていきましょう。
目次
残業時間は労働基準法によって上限が設けられています。
しかし、法内残業やみなし残業・変形労働時間制などにおける残業時間の数え方など、残業の考え方は複雑であるため、どの部分が労働基準法における「時間外労働」に当てはまるのか分かりにくく、頭を悩ませている勤怠管理の担当者様もいらっしゃるのではないでしょうか。
そのような方に向け、当サイトでは労働基準法で定める時間外労働(残業)の定義から法改正によって設けられた残業時間の上限、労働時間を正確に把握するための方法をまとめた資料を無料で配布しております。
自社の残業時間数や残業の計算・管理に問題がないか確認したい人は、ぜひこちらから資料をダウンロードしてご覧ください。
1. 労働基準法による労働時間・休憩時間・時間外労働の概要
大前提として、労働契約を結んで従業員を雇用する企業は、「労働基準法」を守り、適切な人材管理をすることを義務づけられています。
人事にとっての仕事である勤怠管理も、基本的に労働基準法の内容が基本です。法律違反の状態で従業員を働かせていると、企業が処罰されてしまうため、まずは労働基準法の内容から押さえましょう。
1-1. 労働基準法とは
労働基準法とは、働く際に必要な最低限のルールを定めた法律のことです。
たとえ企業側と従業員との間に同意があっても、労働基準法の基準に満たない労働条件で雇用契約を交わしている場合、労働基準法の基準に満たない部分のみ無効となり、かわりに労働基準法の基準が適用されます。法律には罰則のないものも存在しますが、労働基準法の場合罰金刑も懲役刑もあるため、「知らなかった」ではすまされません。
企業の人事として活動する場合は、労働基準法の正しい理解が必要不可欠です。
1-2. 労働時間の上限は週40時間・1日8時間まで
労働基準法で決められた労働時間の上限、「法定労働時間」は、原則として1日8時間・1週間で40時間までとなっています。
原則として、企業は1日8時間・週40時間以上社員を働かせることができません。ただし、残業や休日などに関するルールを定めた「36協定」を結んで届け出れば、残業手当を出して時間外労働をさせることができます。
なお、社員が1人しかいない企業でも、法定労働時間を越えた時間外労働をしてもらう場合は、36協定の届け出が必要です。
【関連記事】労働時間の上限は週40時間!法律違反にならないための基礎知識
1-3. 6時間越えの勤務する場合は、従業員に休憩を与える必要がある
労働基準法では、休憩時間についても定められています。
具体的には、1日の労働時間が6時間を越える場合は最低45分以上の休憩が必要で、労働時間が8時間を越えると、1時間以上の休憩を取らせる必要があるという規定です。
従業員に適切な休憩を取らせずに、長時間の勤務を強制した場合、労働基準法違反となってしまいます。
労働基準法違反で告発されると、企業のブランドやイメージも傷ついてしまうので、休憩時間の定義や管理も理解しておきましょう。
なお、1日の労働時間が6時間以下なら、従業員に休憩を取らせる必要はありません。同じ職種でも、フルタイム勤務と時短勤務では休憩時間の有無や長さが変わります。
【関連記事】労働時間に対する休憩時間数とその計算方法をわかりやすく解説
1-4. 残業時間が法定労働時間を超えると割増賃金の支払いが必要
労働時間の基本知識として、必ず押さえておきたいのが「残業」の定義です。実は、残業は「法定内残業」と「法定外残業」の2種類にわかれます。
法定内残業とは、「所定労働時間を越えているものの、法定労働時間以内の残業」のことです。
たとえば、10時出勤16時退社という内容で雇用契約を結んでいる場合、1日の労働時間は6時間です。
この社員に1時間の残業を頼むと、総労働時間は7時間です。1時間の残業については別途残業代を支給する必要がありますが、法定労働時間である8時間は越えていないため、「基本給を時給換算した額」が残業代です。
一方、同じ人に3時間の残業を頼んだ場合、1日の労働時間は合計9時間です。法定労働時間にあたる2時間分の給与は、先ほどの計算と同様基本給の時給で求めます。
しかし、法定労働時間である8時間を越えた部分、法定外残業の1時間に対しては、基本給に25%上乗せした割増賃金の支払いが必要です。
つまり、法定内残業には1時間あたりの賃金を残業時間分支払い、法定外残業には1時間あたりの賃金に割増率25%を上乗せした上で残業時間分の残業代が必要になります。
「法定内残業は無給」と考える方もいるかもしれませんが、割増賃金にならないというだけで、法定内残業にも1時間あたりの基礎賃金を残業時間分、支給する必要があるため、注意しましょう。
時間外労働の考え方や割増賃金が必要な時間の考え方はきちんと理解していないと、違法な取り扱いをしてしまう可能性があります。「割増賃金が必要な残業時間の定義や数え方が曖昧」「自社できちんと管理されていないので不安」という方に向け、当サイトでは「残業ルールBOOK」を無料で配布しております。この資料では、法律上の時間外労働の定義や割増賃金の取り扱い、働き方改革で定められた残業の上限規制も含めて確認できるため、不安な方はこちらからダウンロードしてご覧ください。
【関連記事】残業による割増率の考え方と残業代の計算方法をわかりやすく解説
2. 労働時間の定義
じつは、労働基準法を見ても「労働時間」そのものの定義は載っていません。そのため、日本では過去におこなわれた労働裁判の結果、いわゆる判例を基準に「どの時間を労働時間とカウントするのか」を決めています。
判例に従った労働時間の定義は、「使用者の指揮命令下にある」ことです。電話番など、上司から指示を受けて業務を遂行している時間は、休憩中でも実際には労働時間として扱わなければなりません。
「業務で休憩時間にしているから、この時間に作業をさせても給与を支払う必要はない」という考えだと、残業代などの未払い請求につながってしまうので、気をつけましょう。
【関連記事】労働時間とは?社会人が今さら聞けない基本情報を徹底解説!
2-1. 労働時間と勤務時間の違いは休憩を含むかどうか
労働時間と勤務時間の違いは、明確な定義はないのですが一般的には、休憩を含むかどうかです。労働時間は、出社してから退社するまでの時間から休憩を引いた、実質的な作業時間のことを意味します。
一方、勤務時間は会社にいる時間のことを表してます。9時から17時までの勤務で、途中に1時間の休憩がある場合、労働は7時間、勤務時間は8時間です。
【関連記事】労働時間に休憩は含む?含まない?気になるルールと計算方法
3. 電話番や持ち帰り残業にも給与が必要!労働時間にあたるものの例
- 会社での残業
- 自宅へ仕事を持ち帰っておこなう残業
- 「電話番」や「来客対応」が必要な休憩
- 仕事中の仮眠
- 勤務開始前の着替え
- 参加が強制の研修や社員旅行
などは、労働時間として扱われる可能性が高いです。労働時間になるものとそうでないものを混同しないように、労働時間として扱うべきケースをご紹介します。
3-1. 会社に残っておこなう残業は労働時間に含まれる
基本的に、終業後に社内でおこなう残業は労働時間です。いわゆるサービス残業も、従業員の雇用時に交わした労働時間を越えたものであれば残業代を支払う必要があります。
注意したいのは、「社員が個人的にしている残業」の扱いです。たとえば、タイムカードを押さずに会社の業務と関係のない個人的な勉強をしている場合は、労働時間としてカウントする必要はありません。
3-2. 自宅へ仕事を持ち帰っておこなう残業も会社の管理下にあれば労働時間
残業には、「自宅へ持ち帰って行うもの」もあります。こちらも、上司や同僚から渡された仕事をしている場合は労働時間です。
たとえば、上司が「ノー残業デーだから早く帰るように」と伝えていても、帰社前に翌日の朝必要な会議資料の作成を頼んでいる場合は、「上司の指示で自宅仕事をしている」となります。
帰宅を促していても、事実として会社の業務をしている場合は労働時間です。
3-3. 「電話番」や「来客対応」が必要な休憩は労働時間
労働時間が1日6時間以上ある場合、従業員に最低45分以上の休憩を取らせる必要があります。
しかし、休憩中であっても、「取引先の○○さんから連絡がくるから、お昼はデスクで取ってほしい」「電話番を頼む」「来客があったら対応を任せる」といった指示、または暗黙の了解がある場合、厳密には休憩時間になりません。
休憩時間は、出社前や退社後と同じ完全に仕事から切り離された時間にする必要があるため、基本的には休憩前や休憩中に仕事の指示を出さないよう社内に周知しましょう。
なお、どうしても昼休憩時間に対応が必要な場合は、休憩時間をずらしたり、手当をつけたりすることをおすすめします。
3-4. 労働からの解放が保障されていない場合には仮眠時間も労働時間
長距離を移動する車や航空機の運転手、日勤夜勤で働くスタッフなど、勤務時間中に仮眠を取る必要がある場合、仮眠の時間も内容によっては労働時間です。
労働時間になるかどうかは「何かあったときに仮眠から起きて対応する必要があるかどうか」も重要な判断要素の一つです。
たとえば、夜勤の休憩中に仮眠時間があり、来客時に寝ている人が起きて対応する必要がある場合、休憩時間とはみなされません。
仮眠をしていても、実際には仕事中の隙間時間や空き時間といった、待機時間と同じ扱いになるからです。
3-5. 勤務開始前の着替えは労働時間
職場で制服などに着替える必要がある場合、始業前の着替えも労働時間です。タイムカードを押していなくても、企業は着替えにかかる数分から十数分の給与支払いが必要です。
3-6. 参加が実質強制されている研修や社員旅行は労働時間
社員研修や写真旅行も、上司や会社側から参加を実質強制している場合は労働時間です。具体的には、
- 本来休日の日に研修や社員旅行を設定し、参加するよう圧力をかける
- 研修などに参加しないと査定結果に悪影響が出る
- 仕事に最低限必要なスキルの研修なのに「自主参加」になっている
といったケースです。さも強制をしていないように振る舞っていたとしても、不満を持った従業員側が職務の一環であったという証拠を残していれば、後々費用を請求されてしまいます。
長期間、従業員の労働時間をごまかすような勤怠管理は、リスクが大きいです。万が一退職と未払い賃金の請求が立て続けに起これば、企業のキャッシュが尽きて運転資金がなくなってしまう可能性もあります。また、本章を読んで「え、それも労働時間なの?」と感じた内容も少なくないでしょう。今までは良いと思っていた内容であっても、本章で書かれているものが労働基準法に沿った内容となります。当サイトでは、労働時間のFAQをまとめた資料を無料で配布しております。自社が労働基準法違反をしていないか、正しい知識を確認したい方はこちらからご確認ください。
【関連記事】労働時間管理を正確におこなうための7つのポイントを徹底解説
4. 時間外労働(残業)には36協定が必要
労働基準法における残業とは時間外労働、すなわち法定労働時間を越えて労働があった時間をさします。時間外労働をさせる際に必要となる36協定について、確認しておきましょう。
4-1. 36(サブロク)協定とは
36協定とは、正式には「時間外・休日労働に関する協定書(協定届)」といいます。 労働基準法第36条により、会社は法定労働時間(1日8時間、週40時間)を超える時間外労働及び休日勤務などを命じる場合、労組などと書面による協定を結び労働基準監督署に届け出ることが義務付けられているため、一般的に「36協定」という名称で呼ばれています。
法定労働時間を超えて労働する必要がある場合には、労使間で「36(サブロク)協定」を締結し、所轄労働基準監督署に届出をしなければなりません。
ところが、これまでは労使間の合意があれば労働時間を無制限に延長することができるという抜け穴がありましたが、労働基準法の改正により、時間外労働の上限時間が初めて法的に定められました。
違反に対しては罰則も設けられているため、これまでよりも厳密な労働時間の管理が求められます。
4-2. 36協定における残業時間の上限は月45時間、年360時間
36協定を結んだ場合、残業時間の上限は原則として月45時間、年360時間以内になりますが、例外として特別条項を結べばこの原則を超えて労働させることができます。
とはいえ、働き方改革による法改正で特別条項を結んでいた場合でも時間外労働と休⽇労働の合計が⽉100時間以上または年720時間超えるような労働をさせることはできず、法律違反となります。
この他にも、月45時間を超えて労働させられるのは年に6回までであり、2〜6か⽉の平均残業時間は80時間以内にしなければなりません。
【関連記事】36協定における残業時間の上限を基本からわかりやすく解説!
5. 勤務時間・労働時間・休憩・残業を利用!労働時間と給与の計算方法
労働時間の算出方法と、労働時間から給与を求める際の手順は以下の通りになります。
- 勤務時間から休憩時間を引いて実労働時間を出す
- 総労働時間を『労働時間』『法定内残業』『法定外残業』にわける
- 労働時間×時給換算した基本給=A
- 法定内残業×時給換算した基本給=B
- 法定外残業×時給換算した基本給×1.25=C
- A+B+C
という流れです。計算自体は簡単なので、「基本給で働く時間」と「残業手当が必要な時間」の混同に注意しましょう。
【関連記事】労働時間の正しい計算方法についてわかりやすく解説
5-1.労働時間が8時間の場合
時給が1,200円の従業員が8時間労働した場合の給与は、次のとおり算出可能です。
1,200円×8時間=9,600円
8時間労働は法定労働時間の範囲のため、残業代は発生しません。
5-2.労働時間が9時間の場合
労働時間が9時間の場合、8時間を基本給で働き、残り1時間は残業手当が必要です。アルバイトやパートのように時給制の場合は時給の換算は不要です。しかし、固定給の場合は最初に時給換算が求められます。
例えば、月の平均所定労働日数が20日、1日の所定労働時間が8時間で月給24万円の従業員の給与を時給換算すると次のとおりです。
24万÷(8時間×20日)=1,500円
時給換算した給与1,500円に8時間をかけると次のとおり、1万2,000円が1日あたりの給与です。
1,500×8=1万2,000円
一方、1時間の残業分の給与は次のとおりです。
1,500×1.25×1=1,875円
つまり、基本給+残業分で1万3,875円を給与として支払います。
6. 企業は従業員の労働時間を客観的に把握しておく
働きすぎを防いだり、労働量を調整して人員を手配したり、人件費を節約したりするためには、労働時間の把握が必要不可欠です。労働安全衛生法が改正されたことで、従業員の勤務時間の客観的な把握が欠かせません。
中途半端な理解で、本来給与支払いが必要な時間を無給扱いにしてしまうと、最悪の場合退職する社員から裁判を起こされたり、労働基準監督署に通報されたりしてしまいます。
企業にとって、「労働条件が悪い」という評判が広まるメリットはありません。勤怠管理を扱う人事には正確な知識が求められるので、人事担当になったら労働時間の基礎を学びましょう。
参考:客観的な記録による労働時間の把握が法的義務になりました|厚生労働省
残業時間は労働基準法によって上限が設けられています。
しかし、法内残業やみなし残業・変形労働時間制などにおける残業時間の数え方など、残業の考え方は複雑であるため、どの部分が労働基準法における「時間外労働」に当てはまるのか分かりにくく、頭を悩ませている勤怠管理の担当者様もいらっしゃるのではないでしょうか。
そのような方に向け、当サイトでは労働基準法で定める時間外労働(残業)の定義から法改正によって設けられた残業時間の上限、労働時間を正確に把握するための方法をまとめた資料を無料で配布しております。
自社の残業時間数や残業の計算・管理に問題がないか確認したい人は、ぜひこちらから資料をダウンロードしてご覧ください。
勤怠・給与計算のピックアップ
-




【図解付き】有給休暇の付与日数とその計算方法とは?金額の計算方法も紹介
勤怠・給与計算
公開日:2020.04.17更新日:2024.03.07
-


36協定における残業時間の上限を基本からわかりやすく解説!
勤怠・給与計算
公開日:2020.06.01更新日:2024.06.04
-


社会保険料の計算方法とは?給与計算や社会保険料率についても解説
勤怠・給与計算
公開日:2020.12.10更新日:2024.07.08
-


在宅勤務における通勤手当の扱いや支給額の目安・計算方法
勤怠・給与計算
公開日:2021.11.12更新日:2024.06.19
-


固定残業代の上限は45時間?超過するリスクを徹底解説
勤怠・給与計算
公開日:2021.09.07更新日:2024.03.07
-


テレワークでしっかりした残業管理に欠かせない3つのポイント
勤怠・給与計算
公開日:2020.07.20更新日:2024.03.25