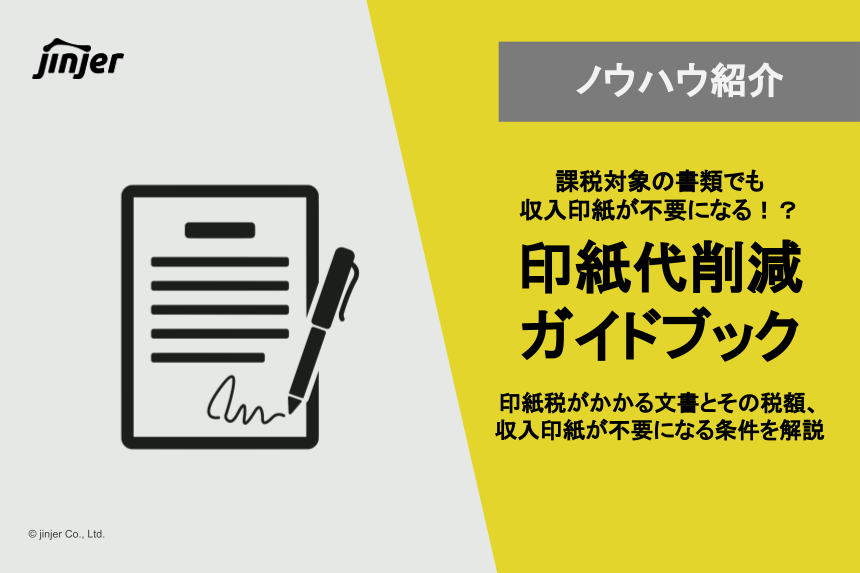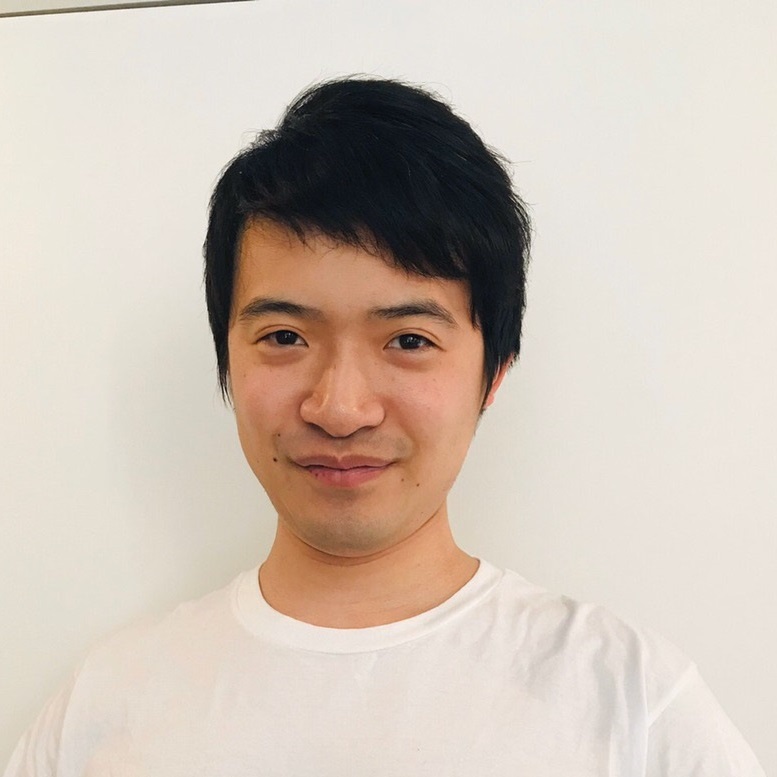契約書には収入印紙を貼るべき?必要となる条件や貼り忘れた場合の罰則について解説
更新日: 2024.5.8
公開日: 2022.2.9
HORIUCHI

契約書や領収書など、ビジネスに関する文書のなかには、作成時に収入印紙を貼り付けなければならない場合があります。
収入印紙を貼ることで印紙税を納めていることは理解していても、どの書類に、いくら分の収入印紙を貼るべきか正確に理解している人は少数ではないでしょうか。
本記事では、収入印紙が必要な書類や、貼り忘れた際の罰則などについて詳しく解説します。
自社で取り扱っている文書が収入印紙を貼るべきか分からない、いくらの収入印紙を貼ればよいか分からないという方はぜひご覧ください。
目次
契約書によっては、印紙税を納めなければなりません。この印紙税の金額は、契約書に記載された取引額によって変動します。そのため、間違えて多く貼ってしまった、という経験があるのではないでしょうか。
また、購入場所も限られているため、買いに行くのが面倒と感じる人も多いでしょう。
そこで今回、印紙代を削減する方法をまとめた資料を用意しました。
印紙税法により課税対象となる書類やその金額についても解説しているので、「毎回、印紙代を確認している」という方にもおすすめです。
無料でダウンロードできるので、ぜひご覧ください。
1. 収入印紙とは


印紙(収入印紙)とは、印紙税を納付する際に使用する切手サイズの証票のことです。印紙税法に基づき、課税対象に指定されている書類(課税文書)には既定金額分の収入印紙の貼り付けが義務付けられています。
課税対象となるのは主に経済取引で作成される書類(契約書や領収書)です。
収入印紙は法務局や郵便局、コンビニ等で販売されていますが、購入しただけでは税金を納めたことにはなりません。課税文書に張り付け、消印をすることで初めて税金を納めたことが証明されます。
また、印紙税は経済取引で用いられる全ての書類を対象とするものではありません。印紙税法で定められた20種類の文書に該当し、かつ所定の要件を満たした文書のみ課税されます。
印紙税を過不足なく納税するためにも、収入印紙の貼り付けが必要な書類、不要な書類をしっかり区別しましょう。
1-1. 収入印紙が必要となる条件
収入印紙の貼り付けが必要となる文書の要件は、以下の3つです。
・印紙税法別表第1に掲げられる20種類(第1号~第20号)の文書に該当すること
・当事者間で課税事項を証明する目的で作成されること
・非課税文書に該当しないこと
次に、課税文書には具体的にどのようなものがあるのかを紹介します。
2. 収入印紙が必要な契約書・その他文書
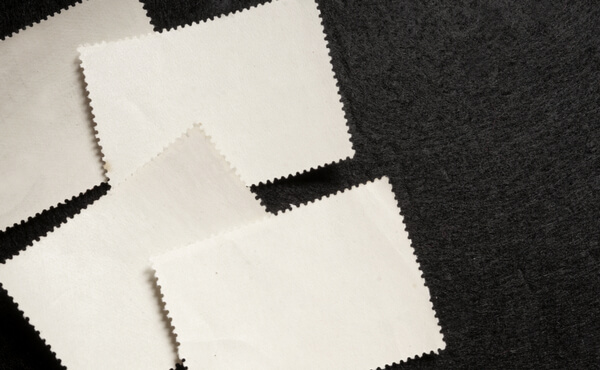
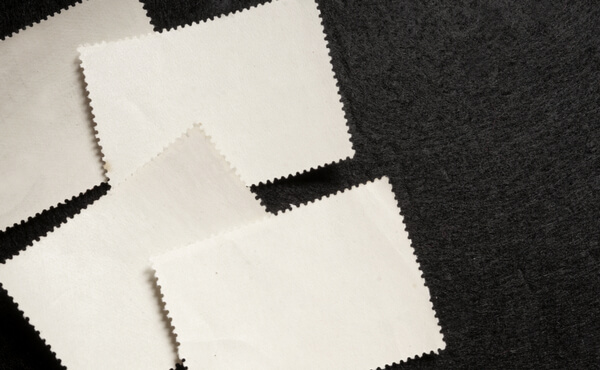
収入印紙の貼り付けが必要な課税文書は、国税庁が発表している印紙税法別表第1(課税物件表)で確認することができます。この表に記載されている文書は、別途非課税文書の規定がない限り、収入印紙を貼付しなければなりません。
ここでは収入印紙が必要な書類について、契約書とその他文書に分けて紹介します。自社が普段取り扱っている文書が課税文書に含まれているかどうか不安な方は、一度確認しておくとよいでしょう。
2-1. 収入印紙が必要な契約書
・第1号
└不動産・鉱業権・無体財産権・船舶・航空機また営業の譲渡に関する契約書
└地上権・土地の貸借権の設定や譲渡に関する契約書
└消費貸借に関する契約書
└運送に関する契約書
・第2号
└請負に関する契約書
・第5号
└合併契約書又は吸収分割契約書若しくは新設分割計画書
・第7号
└継続的取引の基本となる契約書
・第12号
└信託行為に関する契約書
・第13号
└債務の保証に関する契約書
・第14号
└金銭又は有価証券の預託に関する契約書
・第15号
└債権譲渡又は債務引受けに関する契約書
2-2. 収入印紙が必要なその他文書
・第3号
└約束手形、為替手形
・第4号
└株券、出資証券若しくは社債券又は投資信託、貸付信託、特定目的信託若しくは受益証券発行信託の受益証券
・第6号
└定款
・第8号
└預金証書、貯金証書
・第9号
└倉荷証券、船荷証券、複合運送証券
・第10号
└保険証券
・第11号
└信用状
・第16号
└配当金領収書、配当金振込通知書
・第17号
└売上代金に係る金銭又は有価証券の受取書、売上代金以外の金銭又は有価証券の受取書
・第18号
└預金通帳、貯金通帳、信託通帳、掛金通帳、保険料通帳
・第19号
└消費賃借通帳、請負通帳、有価証券の預かり通帳、金銭の受取帳などの通帳
・第20号
└判取帳
参考:印紙税額の一覧表(第1号文書から第20号文書まで)|国税庁
2-3. 該当する文書かどうかは内容に応じて判断される
印紙税法別表第1に記載されている課税文書に該当するかどうかの判断基準は、文書の名称ではなくその内容(課税事項)です。
契約の当事者が文書に適当な名前を付けて「これは契約書ではない」と言い張っても、その内容から契約書であることが明らかな場合は課税文書として扱われます。
そもそも契約書には法律で定められた形式はなく、当事者同士でその契約内容(課税事項)が確認できるものであれば文書の名称やフォーマットは自由です。
そのため、該当書類を確実に課税文書として扱うために、課税条件に「当事者間で課税事項を証明するために作成されること」という条件が含まれています。
■「【ガイドブック】電子契約で印紙税削減」資料でお悩み解決!
・電子契約で印紙税を削減できる法的根拠
・印紙税の課税対象となる書類と税額
・削減額シミュレーションの計算式 など
3. 収入印紙が不要な文書


課税文書の要件に当てはまったとしても、必ずしも収入印紙が必要になるとは限りません。
ここでは印紙税法における非課税文書と、法律の解釈上、収入印紙が不要とされる電子契約について解説します。
3-1. 印紙税法における非課税文書
印紙税法では、『課税文書』の対になる言葉として『非課税文書』が使われます。これは課税文書のなかで特定の要件に該当することで、非課税となる文書のことです。
非課税文書の要件は、以下の4つが挙げられます。
・印紙税法別表第1の非課税物件の欄に掲げる文書
・国、地方公共団体、または印紙税法別表第2に掲げるものが作成した文書
・印紙税法別表第3の擾乱に掲げる文書で、道標の下欄に掲げるものが作成した文書
・特別の法律により非課税とされる文書
実務の上で特に注意すべきポイントは「別表第1の非課税物件」です。
以下、別表第1に掲げられている非課税物件の要件をまとめます。
・第1号、第2号、15号
└記載された契約金額が1万円未満のもの
・第3号
└記載された手形金額が10万円未満のもの
└手形金額の記載がないもの
└手形の複本または謄本
・第4号
└日本銀行その他特定の法人の作成する出資証券
└譲渡が禁止されている特定の受益証券
└一定の要件を満たしている額面株式の株券の向こう手段に伴い新たに作成する書類
・第6号
└株式会社又は相互会社の定款のうち公証人法の規定により公証人の保存するもの以外のもの
・第8号
└信用金庫その他特定の金融機関の作成するもので記載された預入額が1万円未満のもの
・第13号
└身元保証ニ関スル法律に定める身元保証に関する契約書
・第16号
└記載された契約金額が3万円未満のもの
・第17号
└記載された受取金額が5万円以下のもの
└営業に関しないもの
└有価証券
└預貯金証書など特定の文書に追記した領収書
・第18号
└信用金庫など特定の金融機関の作成する預貯金通帳
└所得税が非課税となる普通預金通帳など
└納税準備預金通帳
参考:印紙税額の一覧表(第1号文書から第20号文書まで)|国税庁
3-2. 電子契約の場合は収入印紙が不要
印紙税法における課税文書に該当する文書であっても、電子的に発行されたものや原本を電子データとして保管するものに関しては印紙税が課税されません。
たとえば、電子契約システムで発行された契約書や、電子メールにより送付された領収書などが該当します。
電子データの文書が非課税となる根拠は、印紙税法基本通達第44条における以下の条文です。
“法に規定する課税文書の「作成」とは、単なる課税文書の調製行為をいうのでなく、課税文書となるべき用紙等に課税事項を記載し、これを当該文書の目的に従って行使することをいう。”
引用:第7節 作成者等|国税庁
この条文では、印紙税の課税対象となる文書の作成を「紙の用紙に課税事項を記入し交付すること」と定めています。
電子データは紙ではないため、データの送信はおこなっても交付はしません。これを根拠として、電子データの文書は課税文書に該当しないと判断されています。
4. 収入印紙を貼り忘れた場合の罰則


課税文書を作成した際の納税は、法律で定められた義務です。収入印紙の貼り忘れは脱税とみなされてしまい、罰則が科される点に注意しましょう。
ここからは、収入印紙を貼り忘れた際の罰則についてケース別に解説します。
4-1. 税務調査を受ける前に自主的に申し出た場合
税務調査を受ける前に収入印紙の貼り忘れを自主的に申し出た場合、本来納税すべき印紙税の1.1倍の金額が徴収されます。200円の収入印紙を貼らなければならない契約書であれば、220円の納税が必要となります。
税務調査はいつおこなわれるか分からないため、印紙の貼り忘れに気付いた場合は即座に申し出るようにしましょう。
4-2. 税務調査を受けた際に発覚した場合
税務調査によって収入印紙の貼り忘れを指摘されてしまった場合は、本来納税すべき印紙税の3倍の金額を支払わなければなりません。
1億円を超えるような金額の大きい契約であれば、もともとの印紙税が10万円を超えることもあります。罰則時の負担金額が非常に大きくなるので、契約書を作成する際は収入印紙が適切に貼られているか、細心の注意を払うようにしましょう。
5. 収入印紙に関するよくある疑問


ここからは、収入印紙を取り扱いに関してよくある疑問について紹介します。
5-1. 収入印紙を貼り忘れたら契約は無効になる?
万が一、契約書などの課税文書に収入印紙を貼り忘れても、契約や取引の内容が無効になることはありません。ただし、印紙税法には違反することになってしまい、前項で説明したとおり過怠税が発生する可能性があります。
取引金額が大きければ大きいほど過怠税は高額となるので、契約を取り交わす前に収入印紙が必要か、適した金額の収入印紙が貼られているかを確認するようにしましょう。もし貼り忘れてしまった場合は、過怠税を最小限にするためにも、できる限り早く税務署へ申し出るようにしましょう。
5-2. 契約書の収入印紙代はどちらが負担する?
印紙税法第3条1項では、契約締結において発生する収入印紙代は契約書を作成した方が負担すると定められています。同時に2項では、書面を共同で作成した場合にはお互いに負担するという記載もあります。
そのため、契約書面を2通作成した場合には、1通ずつ収入印紙代を負担して書面に貼付することが多いです。締結時にトラブルを発生させないためには、両者の関係性も踏まえて、収入印紙代の負担割合を事前に決めておくのがよいでしょう。
関連記事:契約書の作成から郵送までの手順・ルールは?押印や保管の方法も詳しく解説! | jinjerBlog
5-3. 収入印紙の貼り方と割印(消印)の押し方は?
収入印紙を貼る位置に関して、厳密に定めている法律やルールはありません。ただし、契約書の左上もしくは右上に貼られるのが一般的です。
また、収入印紙が使用されたことを証明するために、使用する際は割印(消印)を押しましょう。押印は契約書と収入印紙にまたがるようにおこないます。
万が一押印し忘れていた場合、印紙税を納めたとみなされず過怠税が発生してしまう可能性もあります。そのような事態を防ぐために、先方に契約書を送付する前に「収入印紙が貼られているか」「割印(消印)が押されているか」はよく確認するようにしておきましょう。
6. 印紙税の金額


最後に課税文書の種類ごとの印紙税の金額について解説します。
印紙税の課税額は一律ではありません。
印紙税法別表第1における分類ごとに課税額が設定されているため、収入印紙を貼る際は作成した書類がどの文書に該当するのか把握することが大切です。
6-1. 第1号文書(不動産・運送に関する契約書)の印紙税額
第1号文書は建物や土地などの不動産、船舶や航空機など運送に関する契約書です。
これらは契約金額に応じて課税額が決定されます。
● 10万円以下のもの:200円
● 10万円を超え50万円以下のもの:400円
● 50万円を超え100万円以下の:1,000円
● 100万円を超え500万円以下のもの:2,000円
● 500万円を超え1,000万円以下のもの:1万円
● 1,000万円を超え5,000万円以下のもの:2万円
● 5,000万円を超え1億円以下のもの:6万円
● 1億円を超え5億円以下のもの:10万円
● 5億円を超え10億円以下のもの:20万円
● 10億円を超え50億円以下のもの:40万円
● 50億円を超えるもの:60万円
※契約金額の記載がないもの:200円
6-2. 第2号文書(請負に関する契約書)の印紙税額
第2号文書は主に請負に関する契約書です。こちらも契約書の金額に応じて課税額が決められます。
● 100万円以下のもの:200円
● 100万円を超え200万円以下のもの:400円
● 200万円を超え300万円以下の:1,000円
● 300万円を超え500万円以下のもの:2,000円
● 500万円を超え1,000万円以下のもの:1万円
● 1,000万円を超え5,000万円以下のもの:2万円
● 5,000万円を超え1億円以下のもの:6万円
● 1億円を超え5億円以下のもの:10万円
● 5億円を越え10億円以下のもの:20万円
● 10億円を越え50億円以下のもの:40万円
● 50億円を超えるもの:60万円
※契約金額の記載がないもの:200円
6-3. 第3号文書(約束手形・為替手形)の印紙税額
第3号文書に該当するのは約束手形や為替手形です。手形に記載された金額により課税額が決められます。
● 10万円以下100万円以下のもの:200円
● 100万円を超え200万円以下のもの:400円
● 200万円を超え300万円以下のもの:600円
● 300万円を超え500万円以下の:1,000円
● 500万円を超え1,000万円以下のもの:2,000円
● 1,000万円を超え2,000万円以下のもの:4,000円
● 2,000万円を超え3,000万円以下のもの:6,000円
● 3,000万円を超え5,000万円以下のもの:1万円
● 5,000万円を超え1億円以下のもの:2万円
● 1億円を超え2億円以下のもの:4万円
● 2億円を超え3億円以下のもの:6万円
● 3億円を超え5億円以下のもの:10万円
● 5億円を超え10億円以下のもの:15万円
● 10億円を超えるもの:20万円
6-4. 第4号文書(株券・投資信託等の証券)の印紙税額
第4号文書は株券や投資信託等の証券が該当する文書です。証券に記載された金額に応じて印紙税額が決定されます。
● 500万円以下のもの:200円
● 500万円を超え1,000万円以下のもの:1,000円
● 1,000万円を超え5,000万円以下のもの:2,000円
● 5,000万円を超え1億円以下のもの:1万円
● 1億円を超えるもの:2万円
6-5. 第5号文書~第7号文書の印紙税額
第5号、第6号、第7号に該当する文書の印紙税額は一律で4万円です。
なお、第5号は会社の合併・吸収等に関連する書類、第6号文書は会社の定款、第7号文書は取引基本契約書等が該当します。
6-6. 第8号~第16号文書の印紙税額
第8号~第16号文書の印紙税額は一律で200円です。
投資信託に関する契約書や金銭の寄託に関する契約書、債権譲渡に関する契約書等が該当します。
6-7. 第17号文書(領収書)の印紙税額
第17号文書は売上代金の受取書、つまり領収書のことです。受取金額によって印紙税額が決まります。ただし5万円以下の受取書は課税されません。
● 100万円以下のもの:200円
● 100万円を超え200万円以下のもの:400円
● 200万円を超え300万円以下の:600円
● 300万円を超え500万円以下のもの:1,000円
● 500万円を超え1,000万円以下のもの:2,000円
● 1,000万円を超え5,000万円以下のもの:4,000円
● 2,000万円を超え3,000万円以下のもの:6,000円
● 3,000万円を超え5,000万円以下のもの:1万円
● 5,000万円を超え1億円以下のもの:2万円
● 1億円を超え2億円以下のもの:4万円
● 2億円を超え3億円以下のもの:6万円
● 3億円を超え5億円以下のもの:10万円
● 5億円を超え10億円以下のもの:15万円
● 10億円を超えるもの:20万円
※契約金額の記載がないもの:200円
6-8. 第18号文書、第19号文書の印紙税額
第18号文書に該当する文書は預金通帳や信託通帳等です。これらは1年ごとに200円の印紙税が徴収されます。
また第19号文書も消費賃借通帳や金銭・有価証券の受取通帳といった通帳類です(※第18号文書に該当する通帳を除く)。
19号に該当する文書は1年につき400円の印紙税が徴収されます。
6-9. 第20号文書(判取帳)の印紙税額
第20号文書に該当する文書は判取帳です。判取帳とは金銭の支払いをした際に、受取人に金額と名前を記入してもらうための名簿です。
判取帳を運用する際は1年につき4,000円分の収入印紙を張り付けなければなりません。
このように文書によって印紙を貼るかどうか異なります。
また、印紙を貼る文書も取引金額ごとに印紙の金額が変わるため注意が必要です。
当サイトで無料配布している「印紙代削減ガイドブック」では、印紙税の課税対象となる文書や、取引金額ごとに発生する税額をまとめています。
あわせて印紙代を削減する方法についても紹介しているので、「課税対象の文書や税額が覚えられない」「印紙税を削減したい」という方はこちらからダウンロードしてご覧ください。
関連記事:契約書の種類別に貼るべき収入印紙の金額を紹介 | jinjerBlog
7. 収入印紙の使用ルールはマニュアル化しておくのがおすすめ


収入印紙はその書類がどの課税文書に該当するのか、また文書によってはその記載金額によって張るべき金額が異なります。その要件は非常に細かく分かれており、全てのルールを正確に把握することは簡単ではありません。
マニュアルや資料を手元に用意して、頻繁に作成する契約書面はこの金額の収入印紙を利用するなど決めておくと、契約業務が属人化することなくスムーズに締結が進められるようになるでしょう。
また、コスト削減や業務効率化の観点から、電子契約の導入は非常におすすめです。収入印紙の煩わしさに課題を感じている場合には、電子契約サービスの導入を検討してみてはいかがでしょうか。
電子契約のピックアップ
-


電子サインで契約書の法的効力は担保される?電子署名との違いもあわせて解説!
電子契約
公開日:2022.06.22更新日:2022.12.09
-


電子署名とは?電子署名の仕組みや法律などわかりやすく解説
電子契約
公開日:2021.06.18更新日:2024.05.08
-


電子署名の認証局の役割とは?|仕組みと種類をご紹介します!
電子契約
公開日:2021.07.01更新日:2023.01.20
-


電子署名の社内規程のポイントをサンプル付きで解説
電子契約
公開日:2021.10.05更新日:2022.12.08
-


脱ハンコとは?メリット・デメリットや政府の動きについて解説!
電子契約
公開日:2022.06.14更新日:2023.01.25
-


BCP(事業継続計画)対策とは?重要性やマニュアル策定の手順をわかりやすく解説
電子契約
公開日:2022.09.15更新日:2022.12.13