年俸制とは?月給制との違いやメリット・デメリット、残業代・賞与の有無について解説
更新日: 2025.6.10 公開日: 2025.2.3 jinjer Blog 編集部

「年俸制とは何?」
「年俸制を導入する際の注意点は?」
年俸制は、成果主義を基盤に1年単位で給与を決定する特徴的な制度です。従業員の能力や業績が直接給与に反映されるため、高度な専門性を持つ職業、外資系企業などで広く採用されています。
本記事では、年俸制の基本的な仕組みやメリット・デメリットを詳しく解説します。導入を検討する際のポイントも紹介するので、ぜひ参考にしてみてください。

人事労務担当者の実務の中で、従業員情報の管理は入退社をはじめスムーズな情報の回収・更新が求められる一方で、管理する書類が多くミスや抜け漏れが発生しやすい業務です。
さらに、人事異動の履歴や評価・査定結果をはじめ、管理すべき従業員情報は多岐に渡り、管理方法とメンテナンスの工数にお困りの担当者の方もいらっしゃるのではないでしょうか。
そんな人事労務担当者の方には、Excel・紙管理から脱却し定型業務を自動化できるシステムの導入がおすすめです。
◆解決できること
- 入社手続きがオンラインで完結し、差し戻し等やりとりにかかる時間を削減できる
- システム上で年末調整の書類提出ができ、提出漏れや確認にかかる工数を削減できる
- 入社から退職まで人事情報がひとつにまとまり、紙やExcel・別システムで複数管理する必要がなくなる
システムを利用したペーパーレス化に興味のある方は、ぜひこちらから資料をダウンロードの上、業務改善にお役立てください。
1. 年俸制とは


年俸制(ねんぽうせい)とは、従業員の給与を1年間単位で決定・更新する賃金体系のことです。
年俸制の最大の特徴は、成果主義にもとづいており、従業員の能力や業績が給与に直接反映される点です。スポーツ選手や高度な専門性を持つ職業など、成果や能力が重視される分野で主に採用されています。
1-1. 年俸額の決め方
年俸額の決め方は企業によって様々ですが、一般的には賃金規定に年俸額の決め方に関するルールや計算方法をあらかじめ規定しているケースが多いです。中には、前年度の業績や成果に基づいて事業主が年俸額を提示し、従業員との合意によって決めるケースもあります。
いずれにしても、年俸額の決め方は、就業規則や雇用契約書に明記しておくことが必要です。
1-2. 年俸制の給与の支払い方法
年俸制であっても、毎月給与を支給しなくてはいけません。なぜなら、労働基準法24条において「毎月1回以上、支払期日を定めて賃金の支払いをする」ことを事業主に義務づけているからです。そのため、1年後に年俸額をまとめて支払うことは法律上では認められないため、注意しましょう。
一般的には、年俸額を12か月で均等割りして支払期日を決めて支払うケースが多いですが、賞与の支給も踏まえて14等割、16等割にするなど、企業により支払い方法には多少の違いがあります。
1-3. 年俸制を採用する目的
年俸制を採用する主な目的は、企業の経営効率を図ることです。
1年間の給与総額が事前に決定されるため、企業は年間の人件費を正確に把握できます。長期的な経営計画や予算編成が容易になり、不測の人件費増加による経営リスクを軽減可能です。
また、従業員のモチベーション向上も目的の一つとされています。
従業員の成果や業績が直接給与に反映されることで、個々の努力や能力が評価されやすい特徴があるためです。従業員に「来年度はさらに高い評価を得よう」との意識を芽生えさせられると期待されています。
2. 年俸制と月給制・日給制の違い


ここからは、年俸制と月給制・日給制の違いについて解説します。
- 年俸制と月給制の違い
- 年俸制と日給制の違い
それぞれの違いを確認して、年俸制への理解をより深めましょう。
2-1. 年俸制と月給制の違い
年俸制と月給制の大きな違いは、月ごとに給与の変動があるかどうかです。
年俸制は、1年間の給与額をあらかじめ決定し、各月に当分して支払います。原則として、あらかじめ決定した額のみを支払うため、1年間を通して給与額の変更はありません。
一方で月給制は、1ヶ月ごとに給与額を決定します。企業が業績不振に陥れば、ボーナスの増減などで収入が途中で変動する可能性があるでしょう。
また、年俸制と月給制とでは、給与額に成果や業績が影響するかどうかも異なります。
年俸制は従業員の業績や能力が評価基準となるのに対し、月給制は勤続年数や年齢などが影響したり、企業の業績が関係したりするのが特徴です。
年俸制は、優秀な従業員は高い報酬が期待できる反面、成果が出ない場合は翌年度の給与が減少するリスクもあります。一方で月給制は、安定した収入が得られる反面、大きな成果を上げても急激な昇給は難しい可能性が高いでしょう。
2-2. 年俸制と日給制の違い
年俸制と日給制の主な違いは、給与の計算方法や支払い基準です。
年俸制は1年間の給与総額を分割して毎月支給されるのに対して、日給制は1日あたりの給与額を基準に月々の給与が決まります。
年俸制は年間の給与総額が固定されているため、月々の収入は安定しており、勤務日数や残業時間による変動が少ない点が特徴です。
一方、日給制は出勤日数に応じて給与が変動するため、月ごとの収入は安定しません。主に派遣社員やアルバイトなどで採用されることが多いです。
3. 年俸制では賞与や残業代の支払いがない?


年俸制では、「賞与(ボーナス)なし」とすることはできますが、「残業代なし」とすることはできません。年俸制における、賞与や残業代の取り扱いについて、退職金の取り扱いと合わせて詳しくご紹介します。
3-1. 賞与の支払いは企業側で決めることができる
そもそも賞与の支払いは法律で義務づけられたものではないため、年俸制に限らず月給制であっても必ず支給する必要はありません。そのため、企業側で賞与を支給するかどうかの判断はもちろん、賞与額も自由に決めることができます。
年俸制で賞与を支給する方法としては、以下2つの方法が一般的です。
- 年俸額に賞与を含める場合
- 年俸額とは別に賞与を支給する場合
年俸額に賞与を含める際は、例えば年俸を14等分して12回分を毎月支払い、残り2回分を夏と冬に「賞与」として支給します。支給額が年間を通じて安定しているため、人件費の計画が立てやすい点が特徴です。
年俸額とは別に賞与を支給する際は、年俸額を12等分して毎月支払い、そのうえで業績などに応じた賞与を別途支給します。業績に応じた報酬が得られるため、従業員のモチベーション向上が期待できるでしょう。
3-2. 年俸制でも残業代の支払いは必要
労働基準法では「1日8時間・週40時間」を超える時間労働時間に対して、所定の割増賃金の支払いを企業に義務付けています。これは年俸制でも適用されるため、時間外労働に対して25%を乗じた割増賃金を支給しなくてはいけません。成果によって年俸額が決まることから「残業代の支給は不要」と誤解されがちですが、割増賃金を支給しないと処罰の対象となる可能性があります。
ただし、固定残業制を採用している場合はこの限りではありません。年俸に固定残業代が含まれている場合は、固定残業時間を超えた場合にのみ支給が必要となります。
残業だけに限らず、休日労働や深夜労働に対しても、それぞれ割増賃金の支給が必要である点にも注意しましょう。
3-3. 退職金の支払いも義務ではない
賞与と同様に、退職金の支払いも法律で義務づけされているものではありません。そのため、退職金の支払いに関しても、企業が自由に決めることができます。
なお、年俸制で退職金を支給する際は、あらかじめ制度として設計しておき、就業規則にも退職金を支給する労働者の範囲や支給要件、金額の計算方法や支給時期など退職金の支払いルールを明記しておく必要があります。
関連記事:退職金制度の基本や計算方法・金額相場・税金を詳しく紹介
4. 年俸制の社会保険料や税金はどう計算する?


年俸制であっても、月給制と同様に毎月の給与から所得税や住民税、社会保険料を控除しなくてはいけません。ただし、計算方法に関しては、年俸の支給の仕方によって変わってきます。
年俸額を12等分して毎月給与として支給する場合は、標準報酬月額に基づいて社会保険料が計算されます。一方、年俸額を14等分や16等分して一部を賞与として支給する場合は、賞与部分に関しては標準賞与額に基づいて計算しなくてはなりません。
そのため、前者と後者が同じ年俸額であったとしても、支給方法に違いによって徴収する社会保険料額が変わることがあります。
5. 年俸制を導入するメリット


年俸制を導入するメリットは、以下の3つです。
- 経営計画が立てやすい
- 成果主義的な評価制度を導入しやすい
- 外部から優秀な人材を集めやすい
それぞれ、具体的に解説します。
5-1. 経営計画が立てやすい
年俸制を導入する最大のメリットの一つは、企業が経営計画を立てやすくなる点です。年俸制では1年間の給与額が事前に確定されるため、人件費を正確に予測できます。
例えば月給制の場合、賞与や業績連動型の給与変動などによって人件費が増減するリスクがあるでしょう。
しかし年俸制は、月給制のような変動を抑えられるため、経営資源の配分や投資計画などの年間のコスト管理がしやすい点が特徴です。
長期的な経営戦略を立案しやすく、大規模なプロジェクトや新規事業を開始したい企業に適しています。
5-2. 成果主義的な評価制度を導入しやすい
年俸制のメリットとして、従業員の業績や貢献度を直接的に評価する仕組みを取り入れやすい点も挙げられます。労働時間や年齢、勤続年数ではなく、個々の成果や能力をもとに1年間の給与を決定するためです。
成果が給与に直結することで、従業員は自身の目標達成に向けて積極的に取り組む姿勢を持ちやすくなるでしょう。また、「来年はさらに高い評価を得たい」などの意識も目覚めるため、組織全体の生産性向上にもつながります。
5-3. 外部から優秀な人材を集めやすい
年俸制を導入するメリットとして、外部から優秀な人材を集められる点も考えられます。
年俸制は成果主義にもとづいており、高いパフォーマンスを発揮できる従業員ほど高い報酬を得られるためです。スキルや経験に自信のある人材にとっては、大きな魅力となるでしょう。
優秀な人材の確保は企業の競争力向上につながり、生産性や業績の向上が期待できます。新たなプロジェクトや市場拡大への取り組みも可能となり、企業全体の成長を促進できるでしょう。
6. 年俸制を導入するデメリット
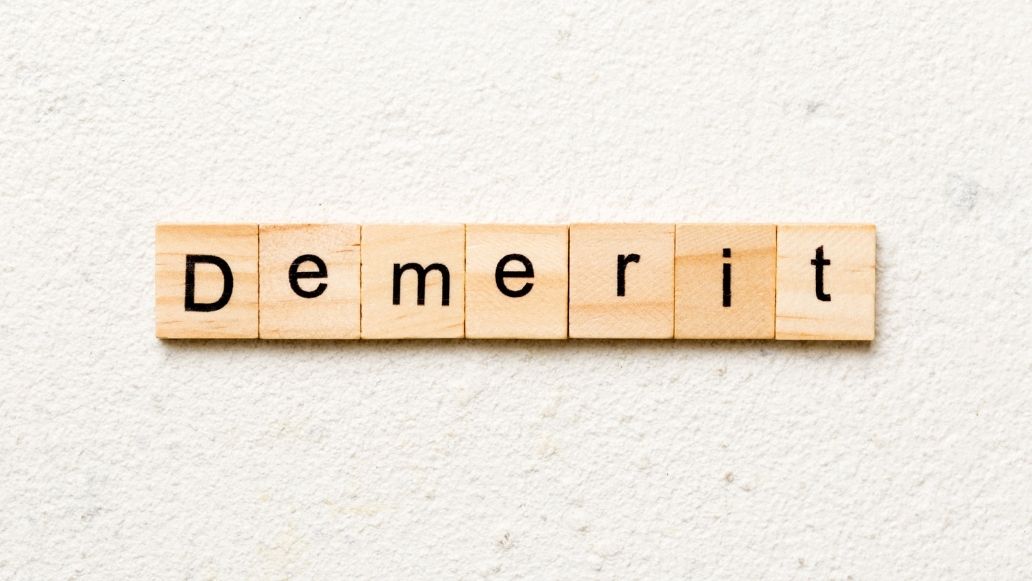
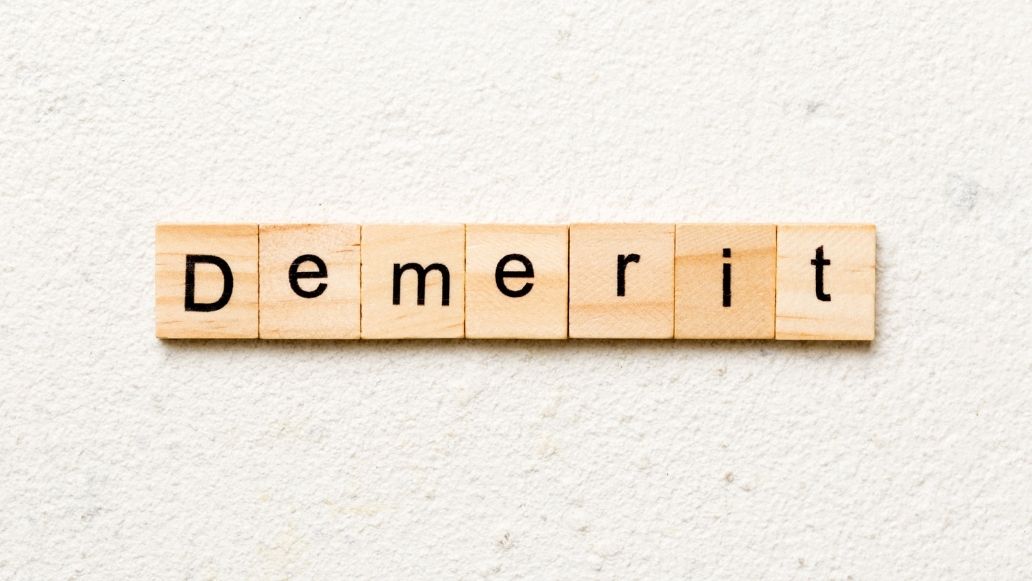
年俸制を導入するデメリットは、主に以下の2つです。
- 年度中の賃金制度の変更が難しい
- 残業代や賞与が複雑になる
それぞれ、順に解説します。
6-1. 年度中の賃金制度の変更が難しい
年俸制のデメリットとして、年度中の賃金制度の変更が難しい点が挙げられます。なぜなら、1年間の給与額が事前に確定されるためです。
もし企業の業績が急激に悪化した場合でも、年度途中で給与を減額したり、月給制などほかの賃金制度へ移行したりできません。経営状況が予測通りに進まなければ、人件費が大きな負担となる可能性があるでしょう。
さらに、従業員個人の成績や能力が途中で大幅に変化したとしても、年度中は給与に反映できません。従業員の短期的なモチベーション向上につながりにくいといえるでしょう。
6-2. 残業代や賞与が複雑になる
年俸制を導入する際のデメリットとして、残業代や賞与の計算が複雑化する点も考えられます。
先で解説したとおり、年俸制であっても労働基準法にもとづき、時間外労働に対する残業代の支払いは必須です。固定残業代として支払うことが一般的ですが、実際の残業時間が固定残業代を超えた場合は差額も支払う必要があります。結果、残業代の計算は煩雑になりがちです。
さらに賞与は、年俸額に含める場合と年俸額とは別に支給する場合の2種類が存在し、それぞれ異なる計算が求められます。企業側の計算負担が増えるだけでなく、従業員との間で誤解やトラブルが生じるリスクも高まるでしょう。
7. 年俸制を導入する企業が多い業種


年俸制を導入する企業が多い業種は、主に以下の通りです。
- IT業界
- 外資系企業
それぞれ、詳細に解説します。
7-1. IT業界
IT業界は、年俸制が採用されている企業が多い業種の代表例です。とくにシステムエンジニアやプログラマーなどでは、成果を給与に反映させることでモチベーション向上を期待できます。
また、IT分野では従業員に高度なスキルや専門知識が求められることも理由の一つです。競争力のある報酬体系として年俸制を提示することで、優秀な人材を獲得するための戦略として活用されています。
7-2. 外資系企業
外資系企業では、年俸制が給与体系の主流となっています。終身雇用制度や年功序列型の昇給システムではなく、個人の成果や能力に応じて報酬を支払う文化が根付いているためです。
また外資系企業は、グローバル競争で勝つために優秀な人材を確保する必要があることも、年俸制を採用する理由として考えられます。とくにコンサルティングや金融など、専門性が高く競争が激しい分野では欠かせない制度といえるでしょう。
8. 年俸制で注意するポイント


年俸制で注意するべきポイントは、以下の2つです。
- 導入前に労使間で合意を得る
- 公正で透明性の高い評価制度を構築する
それぞれ、具体的に解説します。
8-1. 導入前に労使間で合意を得る
年俸制を導入する際には、労働者と企業の間での合意が不可欠です。労働基準法第89条では、賃金の決定方法を就業規則に明記することが義務づけられています。
まず、年俸制を適用する従業員を明確にし、給与の支払い方法や評価基準などを詳細に説明しましょう。次に、給与額や条件について双方が納得できる形で合意を形成します。
最後に、年俸制の導入について就業規則に明記し、従業員全員に周知することも大切です。適切な手続きと十分な合意形成をおこなうことで、年俸制の円滑な導入が可能になるでしょう。
8-2. 公正で透明性の高い評価制度を構築する
年俸制を導入する際は、公正で透明性の高い評価制度の構築も欠かせません。
年俸制は、従業員の成果や貢献度に基づいて給与が決定されるためです。評価制度が不透明であったり、公平性を欠いたりすると、従業員が不信感を抱き、組織全体の士気低下につながる恐れがあるでしょう。
評価基準や運用ルールを就業規則などに明示して全従業員に周知することで、納得感の高い制度を実現できます。労働者が評価に対して異議申し立てできる仕組みを設けることも、公正性の担保につながるでしょう。
9. 年俸制について理解して適切に雇用契約を締結しよう
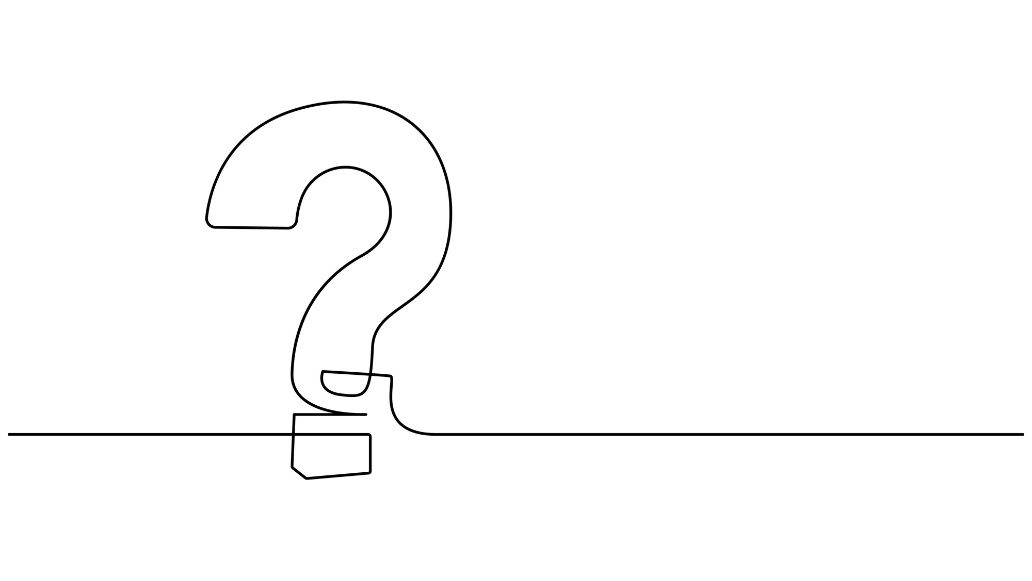
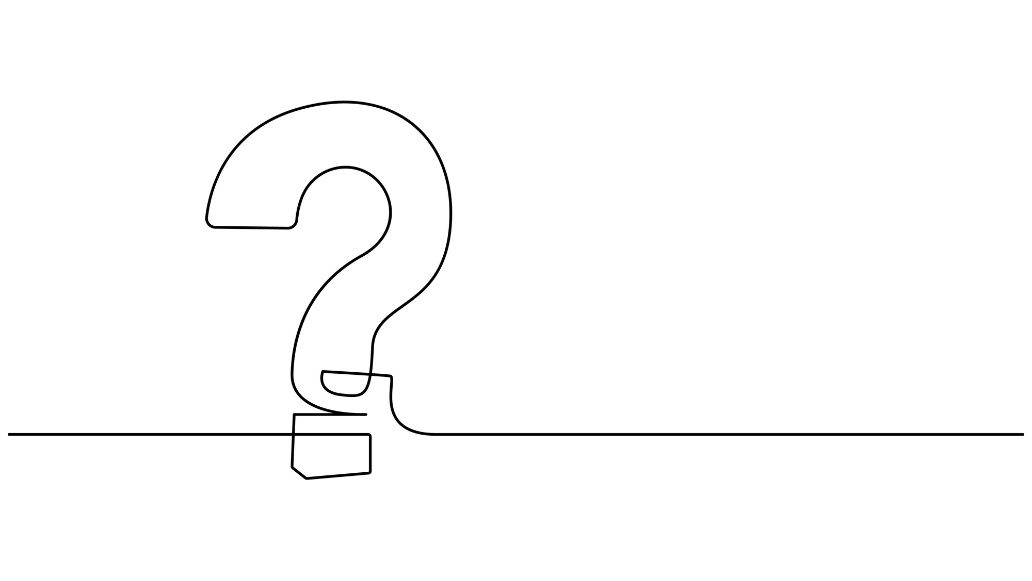
本記事では、年俸制の基本的な仕組みやメリット・デメリット、導入時の注意点について詳しく解説しました。
年俸制は、経営計画の立案が容易になるなどの利点がある一方、残業代や賞与の計算が複雑になるなどの課題も存在します。
企業として年俸制を検討する際は、メリットとデメリットを十分に理解し、適切な運用体制を整えることが大切です。従業員との信頼関係を築きながら、効果的な制度設計を目指しましょう。



人事労務担当者の実務の中で、従業員情報の管理は入退社をはじめスムーズな情報の回収・更新が求められる一方で、管理する書類が多くミスや抜け漏れが発生しやすい業務です。
さらに、人事異動の履歴や評価・査定結果をはじめ、管理すべき従業員情報は多岐に渡り、管理方法とメンテナンスの工数にお困りの担当者の方もいらっしゃるのではないでしょうか。
そんな人事労務担当者の方には、Excel・紙管理から脱却し定型業務を自動化できるシステムの導入がおすすめです。
◆解決できること
- 入社手続きがオンラインで完結し、差し戻し等やりとりにかかる時間を削減できる
- システム上で年末調整の書類提出ができ、提出漏れや確認にかかる工数を削減できる
- 入社から退職まで人事情報がひとつにまとまり、紙やExcel・別システムで複数管理する必要がなくなる
システムを利用したペーパーレス化に興味のある方は、ぜひこちらから資料をダウンロードの上、業務改善にお役立てください。
人事・労務管理のピックアップ
-


【採用担当者必読】入社手続きのフロー完全マニュアルを公開
人事・労務管理公開日:2020.12.09更新日:2026.01.30
-


人事総務担当がおこなう退職手続きの流れや注意すべきトラブルとは
人事・労務管理公開日:2022.03.12更新日:2025.09.25
-


雇用契約を更新しない場合の正当な理由とは?伝え方・通知方法も紹介!
人事・労務管理公開日:2020.11.18更新日:2025.10.09
-


社会保険適用拡大とは?2024年10月の法改正や今後の動向、50人以下の企業の対応を解説
人事・労務管理公開日:2022.04.14更新日:2025.10.09
-


健康保険厚生年金保険被保険者資格取得届とは?手続きの流れや注意点
人事・労務管理公開日:2022.01.17更新日:2025.11.21
-


同一労働同一賃金で中小企業が受ける影響や対応しない場合のリスクを解説
人事・労務管理公開日:2022.01.22更新日:2025.08.26
労務の関連記事
-


年収の壁はどうなった?2025年最新動向と人事が押さえるポイント
勤怠・給与計算公開日:2025.11.20更新日:2025.11.17
-


2025年最新・年収の壁を一覧!人事がおさえたい社会保険・税金の基準まとめ
勤怠・給与計算公開日:2025.11.19更新日:2025.12.22
-


人事担当者必見!労働保険の対象・手続き・年度更新と計算方法をわかりやすく解説
人事・労務管理公開日:2025.09.05更新日:2026.01.30






















