アセスメントとは?ビジネスにおける意味や種類を解説
更新日: 2025.4.24 公開日: 2024.12.28 jinjer Blog 編集部

「アセスメントの意味は?」
「アセスメントにはどのような種類がある?」
上記のような疑問をお持ちではないでしょうか。アセスメントとは、組織の人材や物事に対する評価や分析を客観的におこなうことです。
ビジネスシーンだけではなく、さまざまな分野で活用されていますが、正しく活用しなければ本来の目的を見失う可能性があるため注意が必要です。
本記事では、アセスメントの種類やプロセス、導入時の注意点などを詳しく解説します。アセスメントについて正しく理解し、従業員個人や組織全体の成長を促しましょう。

人事評価制度は、従業員のモチベーションに直結するため、適切に設計・見直し・改善をおこなわなければ、最悪の場合、従業員の退職に繋がるリスクもあります。
しかし「改善したいが、いまの組織に合わせてどう変えるべきか悩んでいる」「前任者が設計した評価制度が古く、見直したいけど何から始めたらいいのかわからない」という方もいらっしゃるでしょう。
当サイトではそのような企業のご担当者に向けて「人事評価の手引き」を無料配布しています。
資料では、人事評価制度の基本となる種類の解説や、導入手順、注意点まで詳しくご紹介しています。自社の人事評価に課題感をお持ちの方は、ぜひこちらから資料をダウンロードしてご活用ください。
1. アセスメントの意味とは

まずはアセスメントがどのような意味を持つ言葉なのか知っておきましょう。ビジネスだけでなく、さまざまな分野で活用されています。
1-1. 評価や分析を客観的にすること
アセスメントとは、組織の人材や物事に対する評価や分析を客観的におこなうことです。英語の「assessment」を由来としており、直訳すると「査定」や「評価」などの意味があります。
アセスメントはビジネスシーンだけではなく、医療や教育など、幅広い分野で活用されています。ビジネスシーンにおけるアセスメントの目的は、従業員のスキル・能力・知識などを客観的に評価し、個人や組織の成長に取り組むことです。
アセスメントは、企業の現状を把握し、次のステップに進むための基盤を築く重要な役割を果たします。問題点の早期発見と改善策の策定が可能となり、企業の持続的な成長を促します。
1-2. アセスメントが活用されている分野
アセスメントはビジネスシーンだけでなく、さまざまな業種や分野で活用されています。
| 看護・福祉アセスメント | 病院や介護施設、訪問診療など医療や介護に関連する業種で利用者の状態把握や問題の把握や解析などに活用されています |
| 保育アセスメント | 保育園や幼稚園などで子供の発達や行動を分析し、サービスの向上や適正化に向けたプログラムの作成などで活用されています |
| 心理アセスメント | 会社や学校などさまざまな場所で個人が抱える問題や特性などを評価し、適した対応をするために活用されています |
| 政策アセスメント | あらゆる企画や政策をたてるさいの目標設定やコストパフォーマンスなどの評価・分析に活用されています |
| 環境アセスメント | 特定の範囲におけるプロジェクトや政策を分析し、該当する範囲の環境への影響を特定し評価するために活用されています |
アセスメントはビジネスに加えて医療や教育、製造業や建設業など幅広い業種でもおこなわれています。
業種や分野によってどのような目的で評価をするのかが異なりますが、いずれも分析した結果を問題への対処やリスクへの事前対処、効率化やなどにつなげるために活用します。
2. ビジネスで使用されるアセスメントの種類

ビジネスで使用されるアセスメントの種類は、主に以下の3つです。
- 人材アセスメント
- 組織アセスメント
- リスクアセスメント
従業員のスキルや知識、特性などを客観的に分析し評価して、人材配置や問題への対応などに使われます。
2-1. 人材アセスメント
人材アセスメントとは、従業員個人や組織のスキル・能力・知識などの評価や分析を客観的におこなうことです。採用や昇格の対象となる従業員に対して、シミュレーションや適性検査、心理テストなどを実施し、適性を見極めます。
人材アセスメントは、人事分野でよく実施されるアセスメントの一つです。企業内での評価だけではなく、外部の第三者機関が実施するケースもあります。外部に委託すれば、企業内の主観や見解を排除し、より公平で客観的な評価がおこなえます。
第三者による客観的な評価は、とくに採用や昇進、人事評価など、重要なシーンにおいて非常に有効です。主観や先入観がないため、適材適所の人材配置をする際に役立ちます。
さらに、採用や人事異動におけるミスマッチを防ぐことが期待できます。結果として、従業員の働きやすさや生産性向上につながるでしょう。
関連記事:コンピテンシーアセスメントとは?ビジネスでの意味や導入手順・活用方法を紹介
2-2. 組織アセスメント
組織アセスメントとは、組織全体の現状を客観的に評価することを指します。組織のビジョンやシステムなどを分析し、課題や強みを明確にすることが目的です。
人材アセスメントが個人の評価に焦点をあてるのに対し、組織アセスメントは企業全体の機能やパフォーマンスを評価することが特徴です。組織アセスメントは、組織文化や業務プロセスの効率性など、さまざまな要素を対象に評価をおこないます。
企業全体の現状を分析し評価することで、組織改革や改善活動のための具体的なプランを立てられます。
2-3. リスクアセスメント
リスクアセスメントとは、事業におけるリスクを特定し、評価することです。主に、事故やトラブルが発生しやすい場所や状況を事前に把握し、安全管理をおこなうために活用されます。
リスクアセスメントは、事業やプロジェクトの計画段階で実施されることが一般的です。事前にリスクの低減や発生確率、影響度などを分析することで、リスク管理や対策を構築する際に役立ちます。
リスクアセスメントは、予期せぬ事故を防ぐために有効な手段です。組織の安全性を構築するうえで、非常に重要な役割を担っています。
3. アセスメントが必要とされる理由
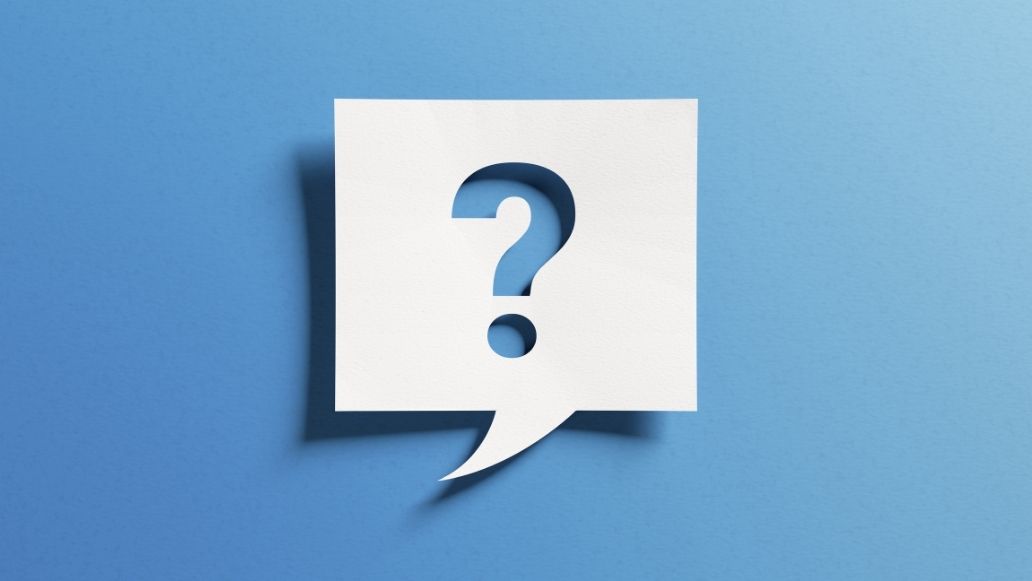
ビジネスでアセスメントが必要とされる理由は、主に人材の選抜や配置に有用だからです。人的資源を有効に活用するために、アセスメントは欠かせません。
3-1. 適材適所の人材配置がしやすくなる
アセスメントでは従業員の能力や特性を客観的に評価し、得意分野や経験を活かせる分野などを分析できます。
個人の能力を発揮しやすい環境が見えてくるため、適材適所の配置がしやすくなるという大きなメリットがあります。
アセスメントを活用できれば、新規採用後の配属先の決定や人材が不足している部署への異動、メンタルの問題が浮上した場合の対応などさまざまな場面での人材配置の適正化がしやすくなるでしょう。
3-2. 自社に適した人材を採用できる
アセスメントは新規採用の際にも活用できます。応募者の能力や人柄、価値観などを分析すれば、自社の企業理念や方針に適した人材を発掘しやすくなります。
もちろん会社が求めているスキルや経験を持つ人物も見つけやすくなるため、採用活動のミスマッチを防げるでしょう。
また、効率的な採用活動ができるようになることで採用にかかるコストも削減できます。
3-3. 管理者候補が選びやすい
管理職になる人には、経験だけでなく判断力や管理能力、リーダーシップなどが求められます。
経験が豊富な人や、実績がある人でもこうした能力をもっているかどうかはなかなかわかりません。管理職にした結果、本人の負担になってしまったり、部下のモチベーションを下げてしまったりするケースもあります。
アセスメントでリーダーや管理職に向いている人物を見つけることができれば、そのような問題が発生するリスクを下げられます。
4. アセスメントのプロセス
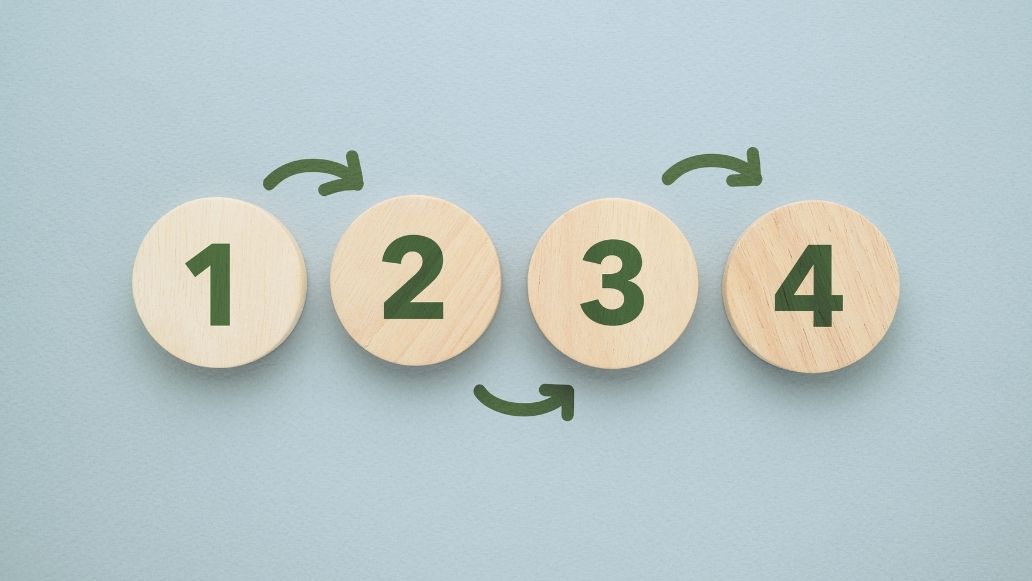
アセスメントを利用する際は、PDCAサイクルを継続することが重要です。
- Plan(計画)
- Do(実行)
- Check(評価)
- Action(改善)
PDCAサイクルは、アセスメントの結果を最大限に活用するために有効なフレームワークです。それぞれの内容を詳しく見ていきましょう。
4-1. Plan(計画)
まず、アセスメントの目的を明確にします。目的を明確にすることで、方向性がしっかりと定まるためです。
目的を明確にしたら、必要な情報を集めながら行動計画を立てます。具体的には、数値や客観的なデータの収集、適性検査などのツールを活用して現状を分析します。
現状を把握しながら、収集した情報をベースに原因を分析して、仮説を立てましょう。
「どのように問題を解決できるのか」また「どうすれば目標達成できるのか」、具体的な計画を立てます。明確かつ、達成度を測定しやすいゴールを決めることが重要です。
4-2. Do(実行)
収集した情報をもとに計画を立てたら、設定した目的や目標に向けて行動します。現状を細かく分析・把握しながら、客観的な視点で計画を堅実に進めることが大切です。
進捗状況をチェックすることで、目標に向かって正しい方向に進んでいるのかどうかを確認できるためです。必要に応じて調整が必要な場合は、柔軟に対応し、計画を改善しましょう。
計画実行の際には、「いつ・どこで・だれが・何を・なぜ・どのように」おこなうのか、5W1Hのフレームワークを活用すると効果的です。各従業員の役割と責任を明確にし、全員が共通認識をもって行動できます。
4-3. Check(評価)
計画を実行した後は、結果を評価します。例えば、「従業員のスキルが向上しているかどうか」「業務プロセスの効率化が実現しているかどうか」などを検証します。
計画時に設定した目標と実際の結果を比較し、達成度や問題点を確認しましょう。単に結果を評価するだけではなく、浮き彫りになった問題点なども丁寧に分析することが大切です。
評価と分析をしっかりおこなうことで、より効果的なアセスメントにつながるでしょう。
4-4. Action(改善)
最後のステップである「Action(改善)」では、評価をもとに改善策の実施計画を立てます。アセスメントで問題となった課題を解決するために、もう一度計画を立て、次のサイクルに生かすことが重要です。
アセスメントのプロセスをPDCAサイクルにもとづいて実施することで、継続的に課題を改善する仕組みを構築できます。継続的な取り組みが、組織や個人の成長をサポートします。
5. アセスメントを導入する際の注意点

アセスメントは従業員の能力やスキルを分析し、生産性や効率の改善に役立てられます。しかし、実施方法やアセスメントへの理解度によっては十分な効果を得られません。3つの注意点に気を付けましょう。
5-1. 能力やスキルではなく適性を評価する
アセスメントは、能力やスキルの評価ではなく「適性を評価すること」と認識しておかなければなりません。アセスメント本来の目的を見失わないよう注意しましょう。
また、アセスメントを実施する際は、対象者にも目的や意図を説明しておくことが重要です。対象者が、「アセスメント=自身の能力やスキルを評価される」と捉えると、萎縮する可能性があり、本来の目的である適性を評価できなくなるためです。
アセスメントは、個人の人間性やスキルを推し量るものではなく、適性を評価するためのツールであることを、評価担当者と対象者の両者が理解しておくことが大切です。
5-2. 客観的なフィードバックをおこなう
アセスメントの結果は、客観的にフィードバックすることが重要です。アセスメント本来の目的である客観的な評価・分析を、対象者も受け入れやすくなるためです。
評価担当者が主観や感情に左右されず、明確な基準にもとづいてフィードバックをおこなうことで、信頼性と透明性のある評価がおこなえます。
具体的には、数値データや測定結果を用いてフィードバックすることで、対象者は納得感をもって評価結果を受け入れられるでしょう。客観的で透明性のある評価は、対象者が新たな目標設定をする際にも役立ちます。
また、批判的な口調や一方的な指摘にならないよう、丁寧なフィードバックを心がけることも大切です。ポジティブな要素もあわせて伝えることで、対象者は改善点を前向きに捉えやすくなり、自主的に課題に取り組む可能性が高まるでしょう。
5-3. 氷山モデルを理解しておく
氷山モデルとは「海面に突き出て目に見えている氷山は、巨大な氷山の一角でしかない」という考え方です。
人材アセスメントでは、この水上に見えている氷山の一角は履歴書や職務経歴書から読み取れる部分だと考えます。この見えている部分は、行動特性の2割ほどでしかないといわれており、正確な評価の材料には足りません。
水面下にある8割以上の巨大な氷の塊は、書類だけでは見えない性格や自己像、モチベーション、社会的な役割などです。人材アセスメントは、この見えていない部分を評価し、より深く個人を分析することで意味をなします。
この点を理解して表面に出ていない部分を分析することを心がければ、より正確で有用なアセスメントをおこなうことができます。
6. アセスメントの必要性がわかれば人的資源の有効活用や企業成長が望める

アセスメントは、組織の人材や物事を客観的に評価や分析をすることを指します。アセスメントを取り入れることで、適材適所の人材配置や、採用時のミスマッチを防ぐ効果などが期待できます。
正しく活用することによって、組織全体の成長や生産性向上に大きく寄与します。アセスメントの必要性を理解し、組織の成長を促しましょう。

人事評価制度は、従業員のモチベーションに直結するため、適切に設計・見直し・改善をおこなわなければ、最悪の場合、従業員の退職に繋がるリスクもあります。
しかし「改善したいが、いまの組織に合わせてどう変えるべきか悩んでいる」「前任者が設計した評価制度が古く、見直したいけど何から始めたらいいのかわからない」という方もいらっしゃるでしょう。
当サイトではそのような企業のご担当者に向けて「人事評価の手引き」を無料配布しています。
資料では、人事評価制度の基本となる種類の解説や、導入手順、注意点まで詳しくご紹介しています。自社の人事評価に課題感をお持ちの方は、ぜひこちらから資料をダウンロードしてご活用ください。
人事・労務管理のピックアップ
-

【採用担当者必読】入社手続きのフロー完全マニュアルを公開
人事・労務管理公開日:2020.12.09更新日:2026.01.30
-

人事総務担当がおこなう退職手続きの流れや注意すべきトラブルとは
人事・労務管理公開日:2022.03.12更新日:2025.09.25
-

雇用契約を更新しない場合の正当な理由とは?伝え方・通知方法も紹介!
人事・労務管理公開日:2020.11.18更新日:2025.10.09
-

社会保険適用拡大とは?2024年10月の法改正や今後の動向、50人以下の企業の対応を解説
人事・労務管理公開日:2022.04.14更新日:2025.10.09
-

健康保険厚生年金保険被保険者資格取得届とは?手続きの流れや注意点
人事・労務管理公開日:2022.01.17更新日:2025.11.21
-

同一労働同一賃金で中小企業が受ける影響や対応しない場合のリスクを解説
人事・労務管理公開日:2022.01.22更新日:2025.08.26
人事評価の関連記事
-

派遣でも部署異動はさせられる?人事が知っておくべき条件・注意点・手順を解説
人事・労務管理公開日:2025.06.03更新日:2025.12.18
-

賞与の決め方とは?種類と支給基準・計算方法・留意すべきポイントを解説
人事・労務管理公開日:2025.05.26更新日:2025.05.27
-

賞与の査定期間とは?算定期間との違いや設定する際の注意点を解説
人事・労務管理公開日:2025.05.25更新日:2025.12.18































