完全歩合制とは?仕組み・違法性・最低賃金との関係を徹底解説
更新日: 2025.7.11 公開日: 2025.2.4 jinjer Blog 編集部

「完全歩合制って、どのような仕組みなのだろう?」
「最低賃金や法律との関係は大丈夫?」
上記のような疑問を感じている方も多いのではないでしょうか。
完全歩合制とは、仕事の成果に応じて報酬が決まる給与形態の一つです。固定給がなく、努力がそのまま収入に反映される一方、収入が不安定になるリスクもあります。
また、通常の雇用契約では違法となるため、業務委託契約の形で導入されることが一般的です。
本記事では、完全歩合制の基本的な仕組みや法律上の注意点、導入時のポイントを解説します。完全歩合制を検討している企業の方や、働き方を見直したい方に役立つ内容です。
目次

人事労務担当者の実務の中で、従業員情報の管理は入退社をはじめスムーズな情報の回収・更新が求められる一方で、管理する書類が多くミスや抜け漏れが発生しやすい業務です。
さらに、人事異動の履歴や評価・査定結果をはじめ、管理すべき従業員情報は多岐に渡り、管理方法とメンテナンスの工数にお困りの担当者の方もいらっしゃるのではないでしょうか。
そんな人事労務担当者の方には、Excel・紙管理から脱却し定型業務を自動化できるシステムの導入がおすすめです。
◆解決できること
- 入社手続きがオンラインで完結し、差し戻し等やりとりにかかる時間を削減できる
- システム上で年末調整の書類提出ができ、提出漏れや確認にかかる工数を削減できる
- 入社から退職まで人事情報がひとつにまとまり、紙やExcel・別システムで複数管理する必要がなくなる
システムを利用したペーパーレス化に興味のある方は、ぜひこちらから資料をダウンロードの上、業務改善にお役立てください。
1. 完全歩合制とは
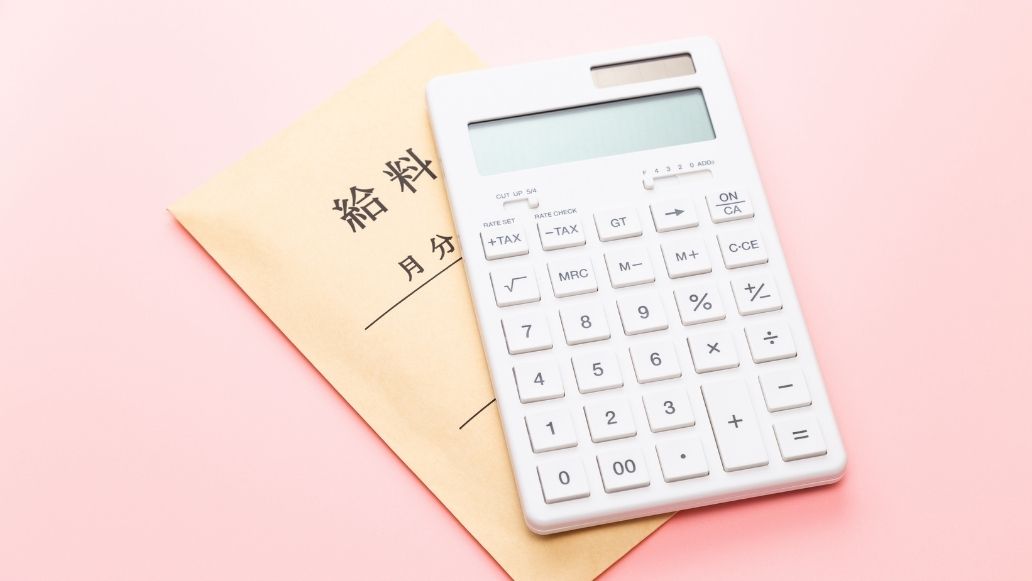
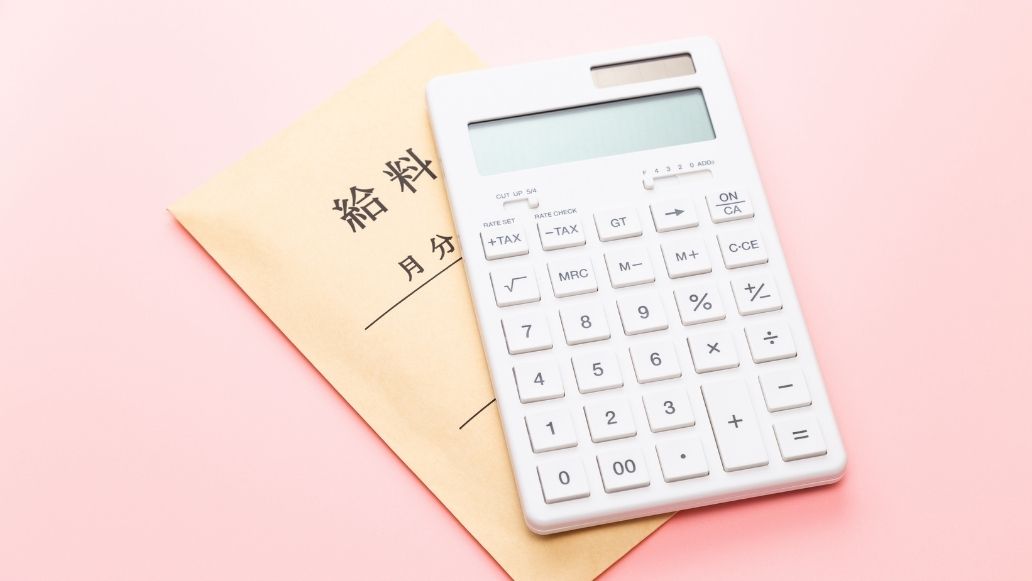
完全歩合制(フルコミッション制)とは、成果に応じて報酬が支払われる給与体系のことです。
歩合制は、固定給と歩合給を組み合わせた形が一般的ですが、完全歩合制は成果報酬のみで支払われる点が異なります。
例えば営業職の場合、契約1件につき報酬1万円と設定されていれば、50件契約すると50万円の収入です。
完全歩合制は働き方によっては高収入も可能ですが、基本給がなく、成果が出ない場合は収入がゼロになるリスクもあります。
2. 完全歩合制の3つのメリット


完全歩合制のメリットは以下の3つです。
- 高収入を目指しやすい
- 働く時間や場所を選ばないことが多い
- 自己成長につながる
それぞれのメリットについて、詳しく見ていきましょう。
2-1. 高収入を目指しやすい
完全歩合制は、成果を出した分だけ報酬が増えるため、高収入を目指しやすい仕組みです。
固定給の場合、昇給や昇進を待たなければ収入を増やすことは難しいですが、完全歩合制なら成果を出せば短期間で収入アップが期待できます。
年齢や勤続年数に関係なく、実力で評価される点も、収入を増やしたい方にとって大きなメリットです。
成果に応じた収入が得られる完全歩合制は、努力で収入を大きく伸ばしたい人に適しています。
2-2. 働く時間や場所を選ばないことが多い
完全歩合制では、オフィスへの出社を求められることが少なく、自分のスケジュールに合わせた柔軟な働き方が可能です。
通勤時間や拘束時間が最小限に抑えられ、残りの時間を趣味やスキルアップに充てることもできます。
ラッシュアワーを避けて仕事を開始したり、カフェや自宅でリラックスしながら業務をおこなったりすることも可能です。
完全歩合制は、効率的かつストレスフリーな環境を求める人に最適な働き方と言えるでしょう。
2-3. 自己成長につながる
完全歩合制は努力が報酬に直結する仕組みのため、業務の効率化やスキル向上に自然と取り組むようになります。
例えば、フリーランスのプロカメラマンの場合、撮影技術や画像編集スキルだけでなく、顧客獲得のためマーケティングを学習する人も少なくありません。結果として、収入アップと自己成長を同時に実現できます。
完全歩合制は、自分の成長を楽しみながら収入を得たい人に最適な働き方です。
3. 完全歩合制の3つのデメリット
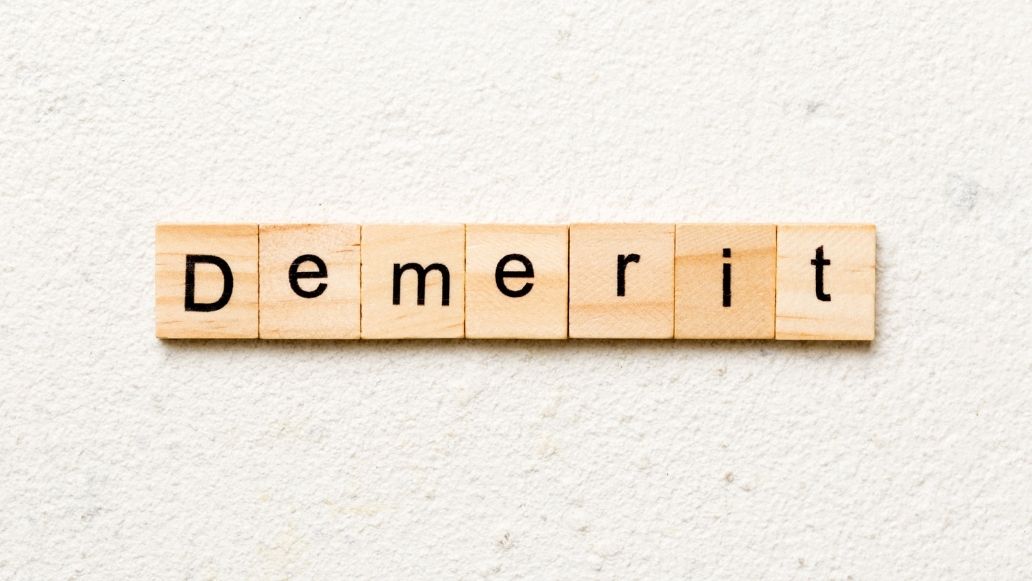
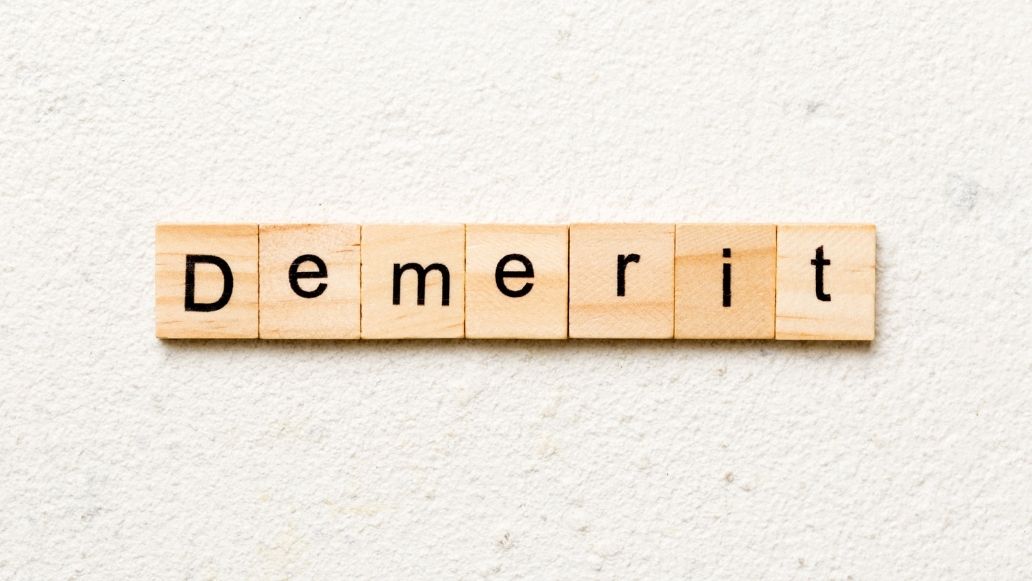
完全歩合制のデメリットは以下の3つです。
- 収入の不安定さに備える必要がある
- 時間対効果が低くなるリスクがある
- 業務にかかるコストが自己負担になる
それぞれのデメリットについて、詳しく見ていきましょう。
3-1. 収入の不安定さに備える必要がある
完全歩合制では基本給がないため、成果が出なかった場合の収入はゼロになります。体調不良や市場の変化など、外部要因によって収入が左右されやすい点にも注意が必要です。
収入の不安定さに備え、日常生活費の3〜6ヵ月分を目安に貯蓄を用意しておきましょう。
副業や投資など、複数の収入源を確保しておくことも一つの方法です。
3-2. 時間対効果が低くなるリスクがある
完全歩合制は成果主義のため、契約や売上が成立しなければどれだけ時間をかけても評価されません。
特に業務開始当初は効率が悪く、労働時間が長くなる傾向にあります。
しかし、業務の優先順位を見直したり、スキルを磨いたりすることで、時間対効果を高めることは十分に可能です。工夫を積み重ね、無駄の少ない働き方を目指しましょう。
3-3. 業務にかかるコストが自己負担になる
完全歩合制では、業務に必要な経費を自分で負担する場合が多く、収入に対する手取りが減る可能性があります。
例えば、交通費や道具、通信費などの経費は、すべて個人持ちとなることが一般的です。そこに税金が加わると、手取りはさらに減少します。
手取りを増やすには、回数券や定期券を活用したり、格安SIMに切り替えたりするなど、経費の節約を心がける必要があります。
4. 完全歩合制は違法?適切に運用するためのポイント


雇用契約を結んでいる従業員(正社員・契約社員・アルバイト)に完全歩合制を適用することは違法です。労働基準法第27条「出来高払制の保障給」により、成果報酬型の賃金体系であっても、労働時間に応じた一定額の賃金を保障する義務があります。
そのため、成果がゼロでも最低賃金を下回る給与はNGです。これらの雇用形態で完全歩合制を採用することは法律違反となり、30万円以下の罰則が科される恐れがあります。
完全歩合制を合法的に適用するには、雇用契約ではなく業務委託契約を採用する必要があります。
業務委託契約は、個人事業主が企業と対等な立場で契約を結び、成果に応じた報酬を支払う契約形態です。不動産営業や保険代理業、タクシードライバーなどで一般的に採用されています。
5. 完全歩合制と最低賃金の関係


完全歩合制と最低賃金の関係はどうなっているのでしょうか。
まず、業務委託契約で働く場合、労働者ではなく個人事業主として扱われるため、労働基準法や最低賃金法の適用対象外となります。そのため、業務委託契約で完全歩合制を採用する場合、最低賃金を下回っても違法性を問われることはありません。
一方、雇用契約のもとで歩合制を導入する場合には、最低賃金法が適用され、実際に支払われる賃金が地域別の最低賃金を下回ることは違法です。歩合給であっても、労働時間に応じた保障給を支払う義務があり、これを怠ると法律違反となります。さらに、所定労働時間を超える残業が発生した場合には、割増賃金の支払いも必要です。
業務委託契約と雇用契約では、最低賃金の取り扱いが異なるため注意しましょう。
6. 完全歩合制を導入する際の注意点


完全歩合制を導入する際の注意点は、以下の2つです。
- 実態が雇用契約と判断されないようにする
- 報酬基準を明確にする
それぞれの注意点について、詳しく見ていきましょう。
6-1. 実態が雇用契約と判断されないようにする
完全歩合制を適切に運用するためには、業務委託契約としての独立性を保つことが重要です。
労働条件や働き方の実態が企業の指揮監督下にあると判断される場合、業務委託契約であっても雇用契約とみなされる可能性があります。
具体的には、以下の条件がある場合、雇用契約と判断されるリスクがあるため注意しましょう。
| 条件 | 内容 |
| 勤務時間の拘束 | 特定の時間帯に勤務を強制している |
| 業務命令の存在 | 業務内容や作業手順を詳細に指示している |
| 就業規則の適用 | 企業の規則に従わせている |
| 業務場所の指定 | オフィスなど特定の場所での業務を義務付けている |
例えば、営業活動をおこなう個人事業主に対して勤務時間を指定したり、成果が出ない場合にペナルティを課したりした場合は、雇用契約とみなされる可能性があります。
6-2. 報酬基準を明確にする
完全歩合制を導入する際には、報酬基準を明確に設定することが不可欠です。基準が曖昧だと労働者とのトラブルを招き、企業の信頼を失うリスクがあります。
以下のような基準を事前に設定し、労働者に周知することが大切です。
| 報酬形態 | 報酬基準の例 |
| 売上連動型 | 売上金額の◯%を支給 |
| 契約件数型 | 契約1件につき◯円を支給 |
| 目標達成型 | 一定の目標達成時に追加報酬を支給 |
透明性を確保した公平な制度運用が、企業と労働者双方の信頼関係を築くカギとなります。
7. 完全歩合制を適切に活用して公平な働き方を実現しよう


完全歩合制は、成果を上げた分だけ報酬を支払う給与形態です。企業と働き手の双方にメリットがある一方で、運用方法を誤るとトラブルにつながる可能性もあります。
適切に運用するためには、業務委託契約としての独立性を確保し、業務委託契約者が雇用契約者とみなされないようにすることが大切です。
働く時間や業務の進め方に関して自由度を与えることで、労働基準法の適用を避けつつ、完全歩合制を導入できます。
完全歩合制を適切に活用し、企業と労働者がともにメリットを享受できる働き方を実現しましょう。



人事労務担当者の実務の中で、従業員情報の管理は入退社をはじめスムーズな情報の回収・更新が求められる一方で、管理する書類が多くミスや抜け漏れが発生しやすい業務です。
さらに、人事異動の履歴や評価・査定結果をはじめ、管理すべき従業員情報は多岐に渡り、管理方法とメンテナンスの工数にお困りの担当者の方もいらっしゃるのではないでしょうか。
そんな人事労務担当者の方には、Excel・紙管理から脱却し定型業務を自動化できるシステムの導入がおすすめです。
◆解決できること
- 入社手続きがオンラインで完結し、差し戻し等やりとりにかかる時間を削減できる
- システム上で年末調整の書類提出ができ、提出漏れや確認にかかる工数を削減できる
- 入社から退職まで人事情報がひとつにまとまり、紙やExcel・別システムで複数管理する必要がなくなる
システムを利用したペーパーレス化に興味のある方は、ぜひこちらから資料をダウンロードの上、業務改善にお役立てください。
人事・労務管理のピックアップ
-


【採用担当者必読】入社手続きのフロー完全マニュアルを公開
人事・労務管理公開日:2020.12.09更新日:2026.01.30
-


人事総務担当がおこなう退職手続きの流れや注意すべきトラブルとは
人事・労務管理公開日:2022.03.12更新日:2025.09.25
-


雇用契約を更新しない場合の正当な理由とは?伝え方・通知方法も紹介!
人事・労務管理公開日:2020.11.18更新日:2025.10.09
-


社会保険適用拡大とは?2024年10月の法改正や今後の動向、50人以下の企業の対応を解説
人事・労務管理公開日:2022.04.14更新日:2025.10.09
-


健康保険厚生年金保険被保険者資格取得届とは?手続きの流れや注意点
人事・労務管理公開日:2022.01.17更新日:2025.11.21
-


同一労働同一賃金で中小企業が受ける影響や対応しない場合のリスクを解説
人事・労務管理公開日:2022.01.22更新日:2025.08.26
労務の関連記事
-


年収の壁はどうなった?2025年最新動向と人事が押さえるポイント
勤怠・給与計算公開日:2025.11.20更新日:2025.11.17
-


2025年最新・年収の壁を一覧!人事がおさえたい社会保険・税金の基準まとめ
勤怠・給与計算公開日:2025.11.19更新日:2025.12.22
-


人事担当者必見!労働保険の対象・手続き・年度更新と計算方法をわかりやすく解説
人事・労務管理公開日:2025.09.05更新日:2026.01.30






















