雇用保険法とは?制度の基本や改正内容、適用範囲を分かりやすく解説
更新日: 2025.9.29 公開日: 2024.10.22 jinjer Blog 編集部

雇用保険法とは、雇用保険の加入義務・条件や給付内容などを定めた法律のことです。2024年に雇用保険法の一部が改正され、最近では2025年4月に施行された改正もあります。
本記事では、雇用保険法の基本や適用範囲、2025年4月から施行された改正法の概要を紹介します。最後まで読むことで、雇用保険法への理解を深められるため、ぜひご一読ください。
目次
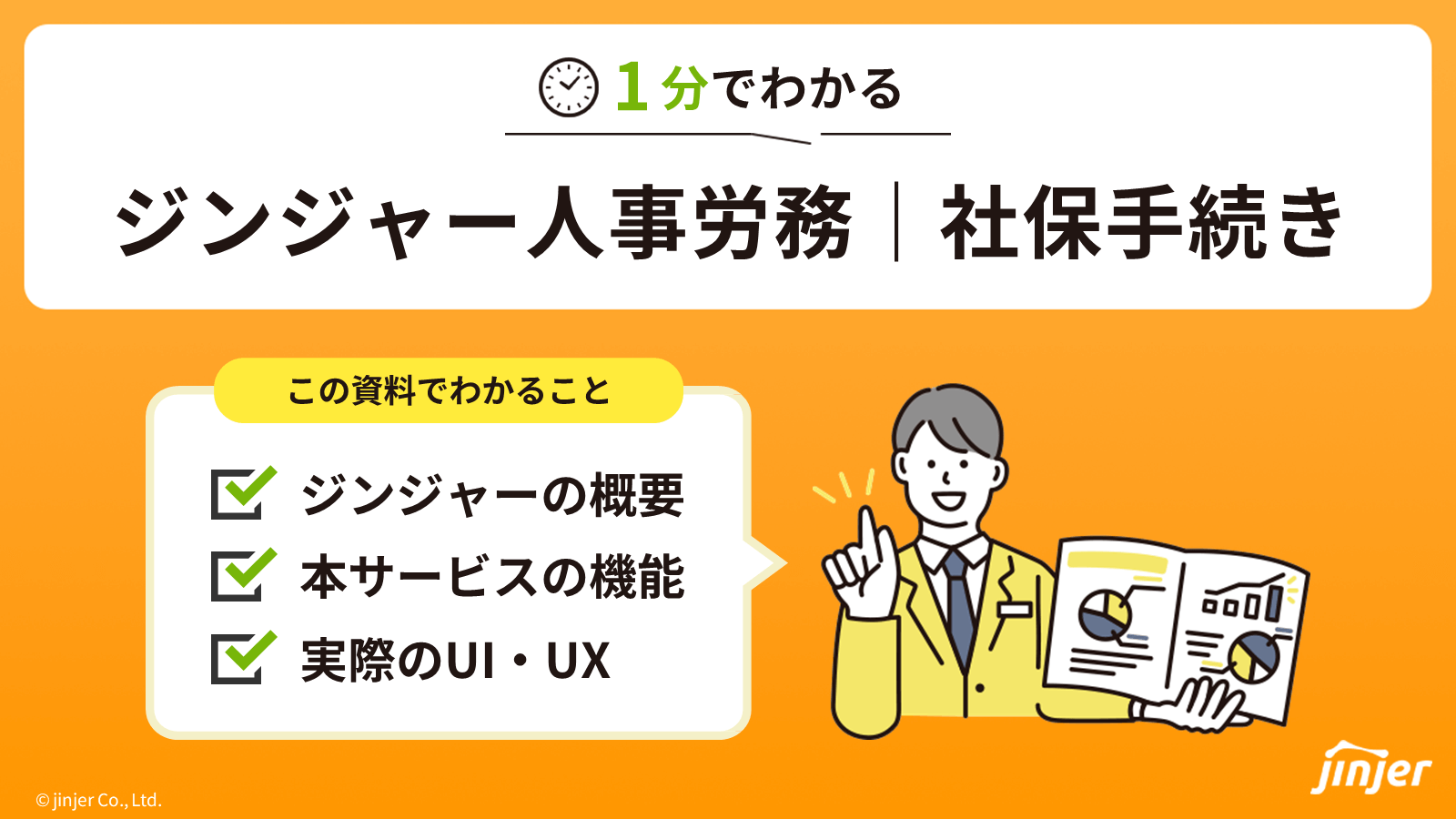
入退社のたびに発生する書類作成、行政機関への提出…。
書き損じや、手続きの度にキャビネットを埋め尽くしていく大量のファイル管理に時間を費やしていませんか?
その手間、電子申請で一気に解決できるかもしれません。
◆紙の書類管理から解放される3つのポイント
- 探す手間からの解放: 保管書類はデータで管理。検索すればいつでもすぐに検索可能。
- 手書き・転記からの解放: 人事データをもとに、面倒な申請書類を自動作成。
- 提出・保管からの解放: 作成した書類はオフィスから一括電子申請、物理的な保管場所も不要。
ペーパーレス化で実現する、新しい働き方の第一歩を提案していますので、ぜひこちらから資料をダウンロードしてご活用ください。
1. 雇用保険法とは?
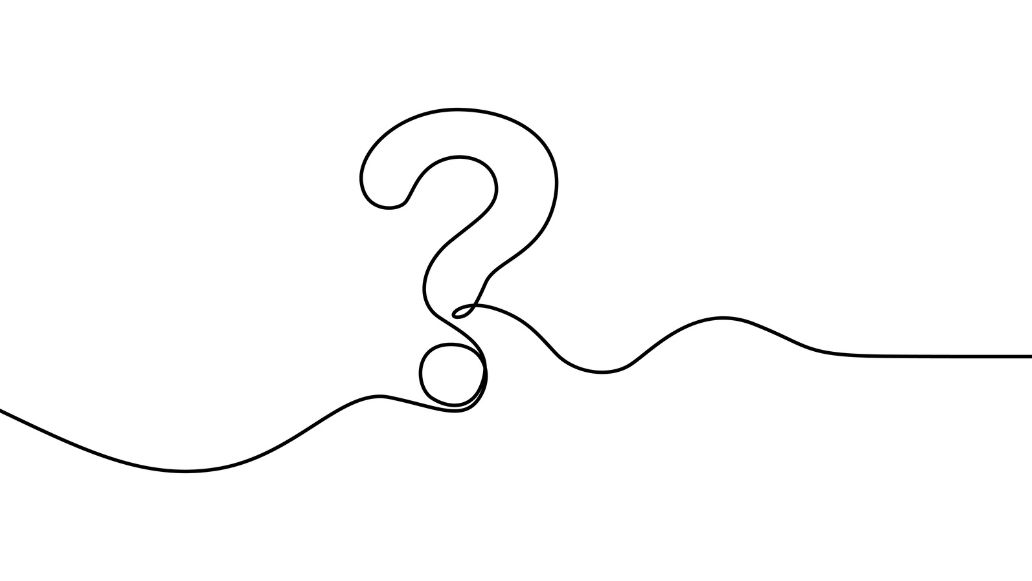
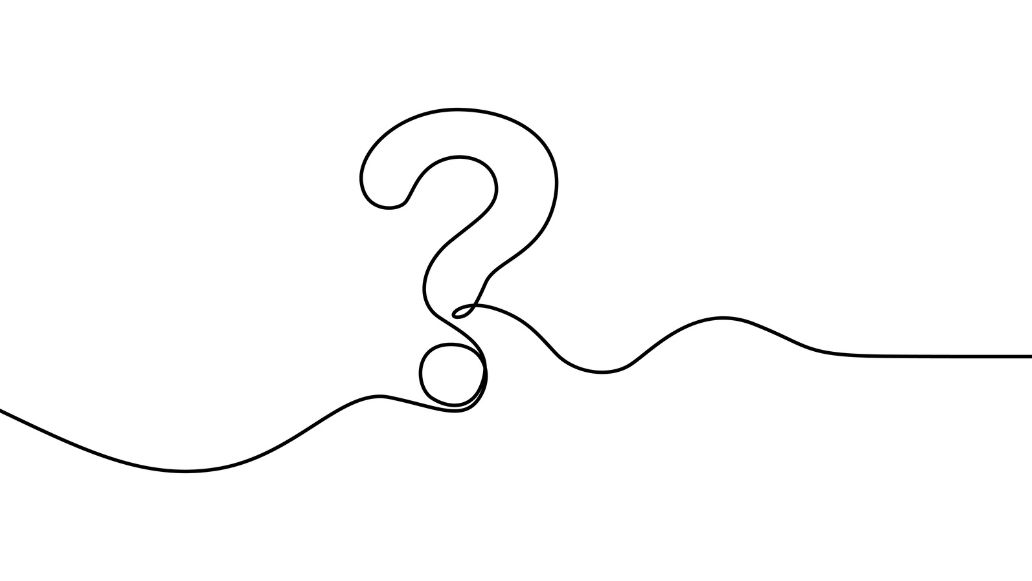
雇用保険法とは、雇用保険の加入条件や給付手続きなど、雇用保険制度のことをまとめた法律です。以下を目的として定められました。
- 労働者の生活および雇用の安定と就職の促進
- 失業の予防、雇用状態の是正および雇用機会の増大、労働者の能力開発および向上、労働者の福祉の増進
この法律に基づき、原則として労働者が1人でも存在する事業所は、ハローワークに事業所設置届や雇用保険被保険者資格取得届を提出する義務があります。
雇用保険制度は、失業や休業で収入が減少した際に必要な給付をおこなう公的保険です。適用事業所は、雇用保険料の納付が求められ、この費用は労働者と事業主の双方によって負担されます。なお、雇用保険法には罰則規定も定められているので、遵守しなければ、懲役や罰金などのペナルティが課せられる恐れもあるので注意しましょう。
2. 雇用保険法の適用範囲


雇用保険の適用範囲は、1人でも労働者がいる事業所であり、一部農林水産業を除くすべての業種や規模が対象です。
被保険者とは、加入条件を満たした労働者のことで、企業の代表や役員、個人事業主は労働者性がないため、原則として被保険者にはなりません。ただし、企業の役員が同時に従業員の地位を持つ場合、雇用関係が認められれば加入が可能です。
雇用保険の加入条件は、以下の条件を満たしていれば正規・非正規を問いません。
- 1週間の所定労働時間が20時間以上
- 同一の事業主に継続して31日以上の雇用が見込まれている
ただし、季節的に雇用される労働者や昼間学生など、一部は被保険者とならないこともあります。
2-1. 65歳以上労働者の雇用保険加入手続きに注意!
65歳以上労働者は、かつて雇用保険への加入や、雇用保険料の支払いが免除されていました。しかし、雇用保険法の改正により、2017年1月から65歳以上労働者も雇用保険の適用対象(この段階では雇用保険料免除)となり、2020年4月から65歳以上労働者も雇用保険料の支払い義務が生じるようになりました。つまり、現状は年齢に関係なく、雇用保険の加入条件を満たす労働者は、雇用保険に加入させなければなりません。
また、雇用保険法の改正によって、2022年1月からマルチジョブホルダー制度が開始され、65歳以上労働者は、1つの事業所で雇用保険の加入条件を満たせない場合でも、次のいずれもの要件を満たせば、マルチ高年齢被保険者として雇用保険に加入することが可能です。
- 複数の事業所に雇用される65歳以上労働者である
- 2つの事業所(1つの事業所の週所定労働時間が5時間以上20時間未満)の週の所定労働時間の合計が20時間以上である
- 2つの事業所それぞれの雇用見込みが31日以上である
参考:【重要】雇用保険マルチジョブホルダー制度について|厚生労働省
マルチジョブホルダー制度に関する手続きは、基本的に従業員がおこないますが、会社に証明書類などの作成を依頼されることもあります。また、マルチジョブホルダー制度の適用を受けると、会社にも雇用保険料の納付義務が生じます。今一度、65歳以上労働者の雇用保険の手続きについても見直しておきましょう。
関連記事:マルチジョブホルダー制度とは?対象要件や手続きの流れについて
3. 雇用保険の給付金・助成金一覧


雇用保険法に則り、雇用保険に加入することで、従業員は必要に応じて失業等給付や育児休業給付が受けられます。また、会社側も一定の要件を満たせば、雇用関係助成金を受給することが可能です。
ここでは、雇用保険法に基づく給付金や助成金の内容について詳しく紹介します。
3-1. 失業等給付
失業等給付とは、雇用保険に加入する労働者が失業した場合や、雇用の継続が困難となった場合に一定の要件を満たすことで受けられる給付制度です。失業等給付は、次の4種類に大別できます。
- 求職者給付:失業者の生活を安定させ、求職活動をしやすくするための給付(基本手当や高年齢求職者給付金など)
- 就職促進給付:失業者が再び就職することを支援・促進するための給付(就業手当や再就職手当など)
- 教育訓練給付:就労者の主体的なスキルアップ・能力開発を支援し、雇用の安定や再就職の促進を図るための給付(一般教育訓練給付金や専門実践教育訓練給付金など)
- 雇用継続給付:就労者が職業生活を円滑に続けられるよう支援・促進するための給付(高年齢雇用継続給付など)
失業者だけでなく、現在職に就いている人であっても受けられる給付があるので、正しく失業等給付制度を理解しておきましょう。
3-2. 育児休業給付
育児休業給付とは、復職を前提に育児のために休業している労働者の生活を支援するための給付制度です。育児休業給付にも、受給要件があり、子育てに従事するすべての労働者が給付を受けられるわけではありません。
また、育児休業給付は、原則として被保険者の代わりに事業主が手続きをします。また、新しく給付制度が創設されるなど、改正も繰り返しおこなわれているので、常に最新の情報を把握し、正確に対応することが大切です。
3-3. 雇用関係助成金(事業主向け)
雇用関係助成金とは、企業が労働者の雇用維持や職場環境の改善に取り組むための支援を目的とした助成金制度です。雇用関係助成金は、次のようにさまざまな種類があります(2025年4月現在)。
- 雇用調整助成金
- 産業雇用安定助成金
- 早期再就職支援助成金
- 特定求職者雇用開発助成金 など
雇用保険適用事業所に該当し、雇用保険に加入する労働者が1人でもいれば、助成金の受給対象となる可能性があります。ただし、それぞれの助成金の種類によって受給要件は変わってきます。また、雇用保険法の改正などで、新しく助成金制度が創設されることもあるので、最新情報を定期的にチェックするようにしましょう。
4. 雇用保険法の2024年の改正の動き


2024年5月10日には「雇用保険法等の一部を改正する法律」、同年の6月5日には「子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律」が可決されました。
2024年の雇用保険法の改正の目的は以下のとおりです。
- 多種多様な働き方を効果的に支えるセーフティネットの構築
- 労働者の学び直しを支援
- 共働きや共育ての推進
改正内容を以下にまとめました。
| 雇用保険法等改正 | 子ども・子育て支援法等改正 |
| 雇用保険の適用範囲の拡大
教育訓練やリスキリング支援の充実 育児休業給付に係る安定的な財政運営の確保 |
こども未来戦略の「加速化プラン」の施策を実行するため、共働き・共育ての推進に関わる施策を実施するのに必要な措置 |
雇用保険法が改正されることになった要因には、高齢者や女性などの人材が労働に参加したこと、労働に対する考え方やライフスタイルが多様になったことが影響しています。
また、少子化が進行していることから、社会全体で子育てを支援するために、男女が働きながら育児できる環境を整えることもねらいです。
5. 2025年4月に施行される雇用保険法等改正法の概要


2025年4月に施行される雇用保険法等改正法の概要を以下の2つに分けて紹介します。
- 雇用保険法等改正法(令和6年法律第26号)
- 子ども・子育て支援法等改正法(令和6年法律第47号)
5-1. 雇用保険法等改正法(令和6年法律第26号)
雇用保険法等改正法の改正事項は、以下の4つに分けられます。
- 雇用保険の適用拡大
- 教育訓練やリスキリング支援
- 育児休業給付に係る安定的な財政運営の確保
- そのほか雇用保険制度の見直し
5-1-1. 雇用保険の適用拡大
2025年4月の改正では、セーフティネットを拡大するために、1週間の所定労働時間が「20時間以上」から「10時間以上」に拡大されました(2028年10月1日施行予定)。
参考:雇用保険法等の一部を改正する法律(令和6年法律第26号)の概要|厚生労働省
ただし、1週間の所定労働時間は通常の週に勤務する時間のことで、祝日や夏季休暇などの特別な休暇は含まれません。
この変更により、パートタイムや短時間労働者の雇用保険への加入が可能となり、より多くの人々が保険の恩恵を受けられるようになります。
さらに、企業は労働力をより多様に受け入れやすくなり、高齢者や子育て中の女性など、多様な働き方を希望する人々にとって働きやすい環境が整備されることも期待されています。この改正は、雇用保険制度の目的である「労働者の生活及び雇用の安定」に寄与し、長期的な労働力確保を促進する重要なステップといえます。
参考:雇用保険法等の一部を改正する法律(令和6年法律第26号)の概要|厚生労働省
5-1-2. 教育訓練やリスキリング支援
労働者が安心して再就職活動をしたり主体的にリスキリングしたりするために、給付制限期間の見直しや教育訓練給付の拡充がおこなわれます。
主な施行内容は以下のとおりです。
| 自己都合退職者の給付制限期間の短縮 | 自己都合退職であっても給付制限が撤廃
給付制限期間が2ヵ月から1ヵ月に短縮(※ただし、自己都合による退職が5年以内に3回以上ある場合は給付制限3か月) 2025年4月1日から施行 |
| 教育訓練給付金 | 教育訓練給付金の給付率の上限が70%から80%に引き上げ
2024年10月1日から施行 |
| 教育訓練休暇給付金の創設 | 被保険者期間が5年以上で教育訓練のために休暇を取得
離職した際に支給される基本手当と同額が給付 給付日数は被保険者期間に応じて90日・120日・150日のいずれかになる 2025年10月1日から施行 |
施行内容によって、施行日が異なるため、内容と合わせて把握しておきましょう。
参考:雇用保険法等の一部を改正する法律(令和6年法律第26号)の概要|厚生労働省
5-1-3. 育児休業給付に係る安定的な財政運営の確保
育児休業給付に係る安定的な財政運営の確保のために、以下の改正がおこなわれます。
- 育児休業給付に関する国庫負担割合が8分の1に引き上げ
- 当面の保険料率は0.4%に据え置きつつ、本則両立を0.5%に引き上げ、実際の両立は保険財政の状況に応じて弾力的に調整する仕組みを導入
国庫に係る点は2024年5月17日から施行、保険料率に係る点は2025年4月1日からの施行です。
参考:財政運営|厚生労働省
5-1-4. そのほか雇用保険制度の見直し
教育訓練支援給付金の暫定措置が2年間延長し、給付率が80%から60%に引き下げられます。
また、介護休業給付の国庫負担割合を80分の1にする暫定措置も2年間延長や、支援実績が少ない就業手当の廃止、就業促進定着手当の上限を支給残日数の20%へ引き下げが決まりました。
これらは2025年4月1日から施行されています。
参考:雇用保険法等の一部を改正する法律(令和6年法律第26号)の概要|厚生労働省
5-2. 子ども・子育て支援法等改正法(令和6年法律第47号)
子ども・子育て支援法等改正法の雇用保険制度に関する改正は以下の2つです。
- 出生後休業支援給付の創設
- 育児時短就業給付の創設
5-2-1. 出生後休業支援給付の創設
子どもの出生直後に、両親が共に育児休業を取得することを促進するため、出生後休業支援給付が創設されました。これにより、出生後8週間以内に、両親がそれぞれ14日以上の育児休業を取得した場合、最大28日間、休業開始前の賃金の13%相当額が支給されます。
従来の育児休業給付は通算180日で67%の支給ですが、今回の改正により、これと併せて給付率は実質的に80%に引き上げられました。なお、配偶者が専業主婦やひとり親家庭の場合、育児休業の取得がなくとも支給される制度も導入されました。
支給は非課税で、社会保険料も免除されるため、実質的な給付率は手取りで見ても10割相当となります。施行日は2025年4月1日からです。
参考:子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律(令和6年法律第47号)の概要|厚生労働省
5-2-2. 育児時短就業給付の創設
従来、育児のために短時間勤務を選択した結果、賃金が低下した労働者に対する給付はありませんでした。
今回の改正により、共働き・共育ての促進を図り、育児とキャリア形成の両立を支援するための「育児時短就業給付」が創設されました。この給付は、被保険者が2歳未満の子を養育するために時短勤務をする際に適用され、給付率は時短勤務中に支払われた賃金の10%相当となります。これは、時短勤務よりも従前の所定労働時間での勤務を推進する観点で設計されています。
なお、育児時短就業給付の制度は、2025年4月1日から施行されています。
参考:子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律(令和6年法律第47号)の概要|厚生労働省
6. 雇用保険法の改正による企業への影響と対応方法


2025年の雇用保険法の改正では、各制度の施行日に注意して準備していく必要があります。また、法改正によって、企業にどのような影響があるのか正しく理解しておきましょう。
6-1. 押さえておくべき法改正への対応ポイント
パート労働者は平成21年時点で約1,431万人にものぼり、雇用保険の適用拡大による影響は大きく、自社でも対応が必要になる可能性が高いです。
加入対象となる労働者の数や保険料負担が増加するかなどを事前に把握しておきましょう。
さらに、育児時短就業給付や教育訓練給付の改正により、社員の能力開発や多様な働き方に対応することも企業にとって重要な課題となります。
これによって、労働者が育児と仕事を両立しながら、スキルを向上させる機会が増えることは、企業の生産性向上にも寄与します。
そのため、社内の人事制度や育児支援政策の見直しをおこない、積極的に労働者に寄り添った柔軟な勤務環境を提供することが求められます。
妊娠や出産などの申し出があった場合は、従来の育児休業給付に加えて、新設された出生後休業支援給付の2つの事項を把握しておかなければいけません。育児休業の取得の有無や日数などをサポートできるとスムーズに手続きできるため、事前に確認しておきましょう。
7. 雇用保険法についてきちんと把握しておこう


本記事では雇用保険法とは何か、適用範囲、改正法の概要について紹介してきました。
雇用保険法はこれまで何度も改正がおこなわれており、2025年4月から施行された改正もあります。今後も引き続きさまざまな法改正がおこなわれる予定であるため、どのような対応をしなければならないのか、事前に確認しておくことが大切です。
人事労務担当者は本記事を参考に定められた期限までに準備や手続きをおこないましょう。
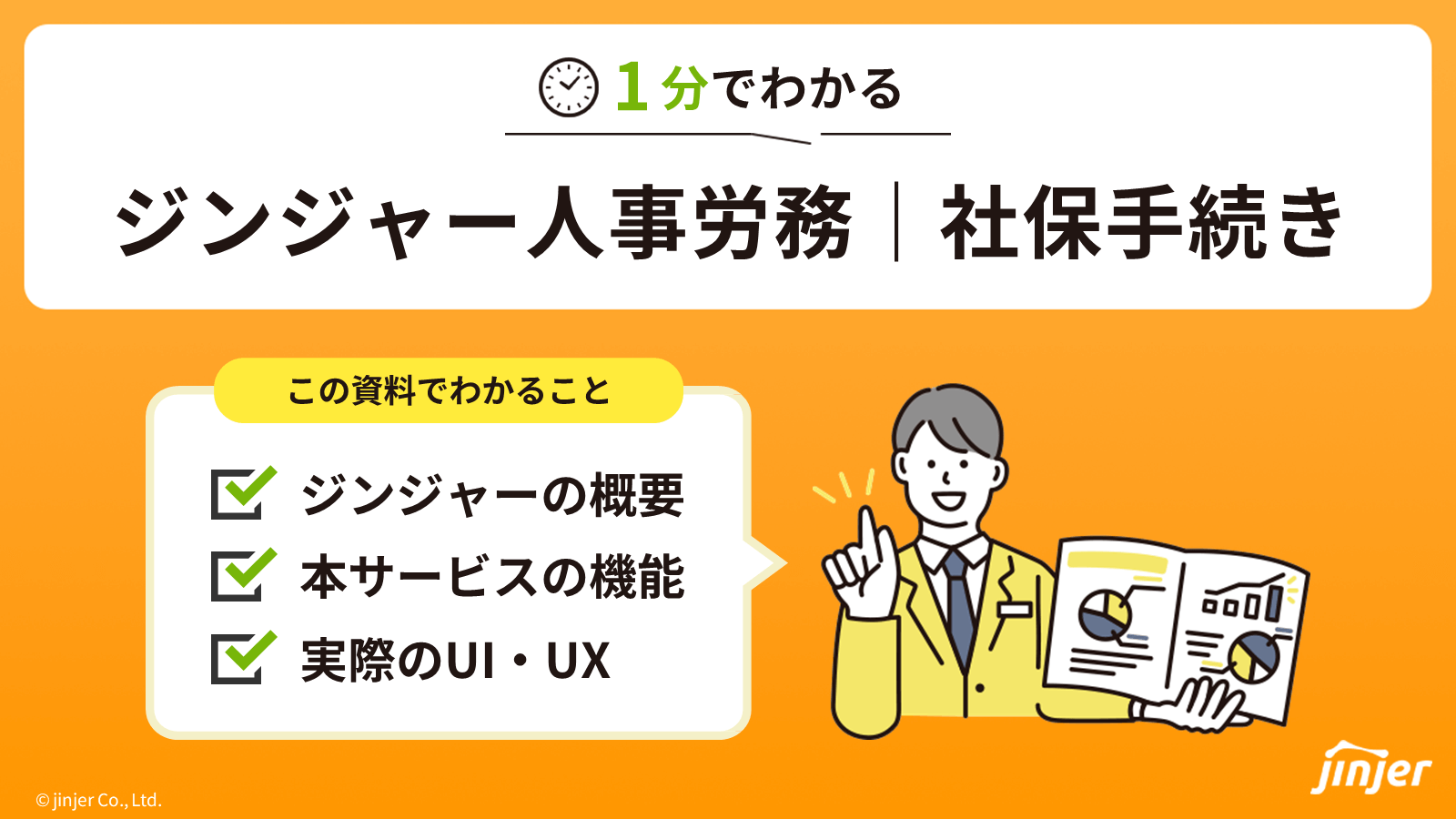
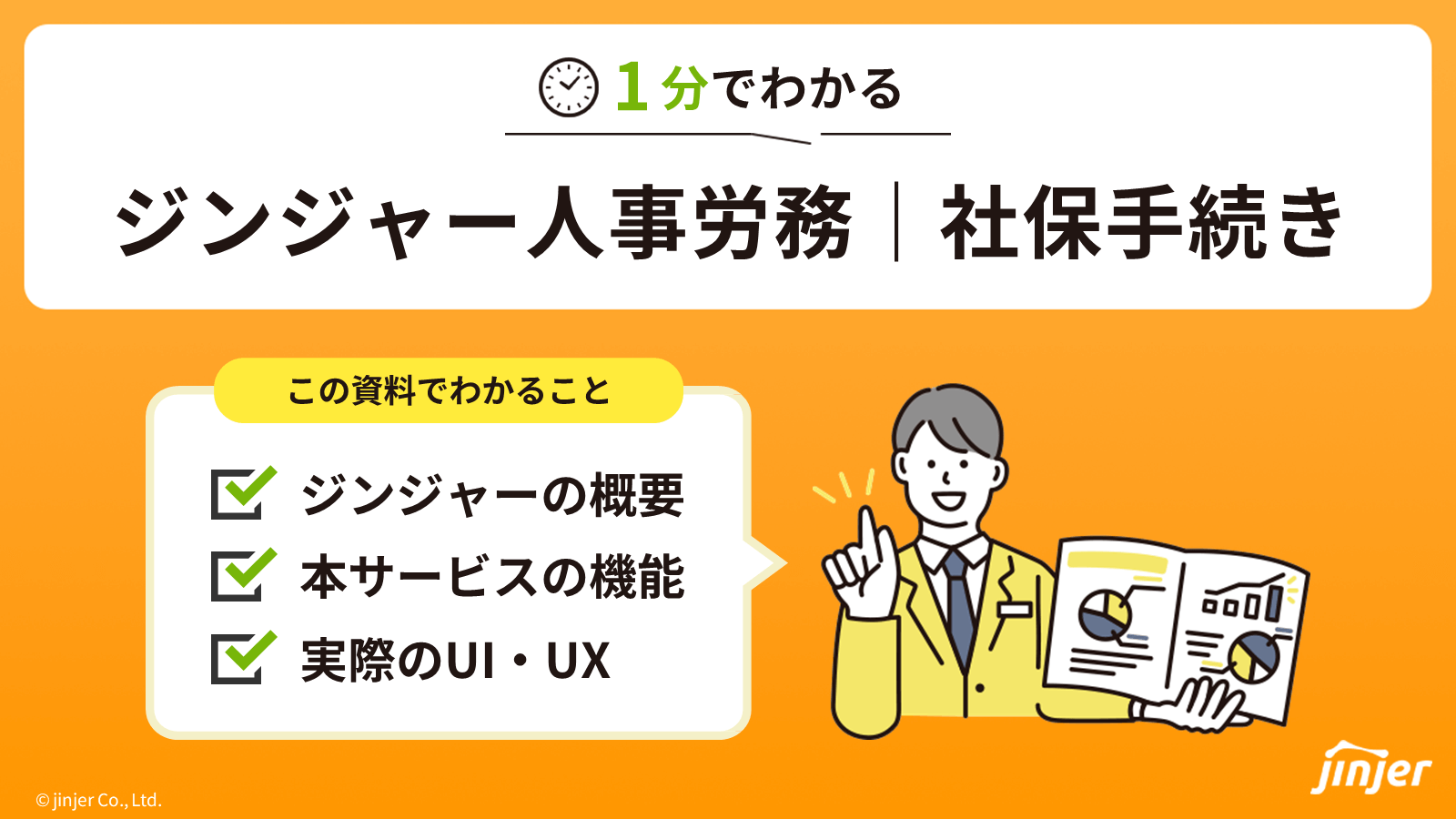
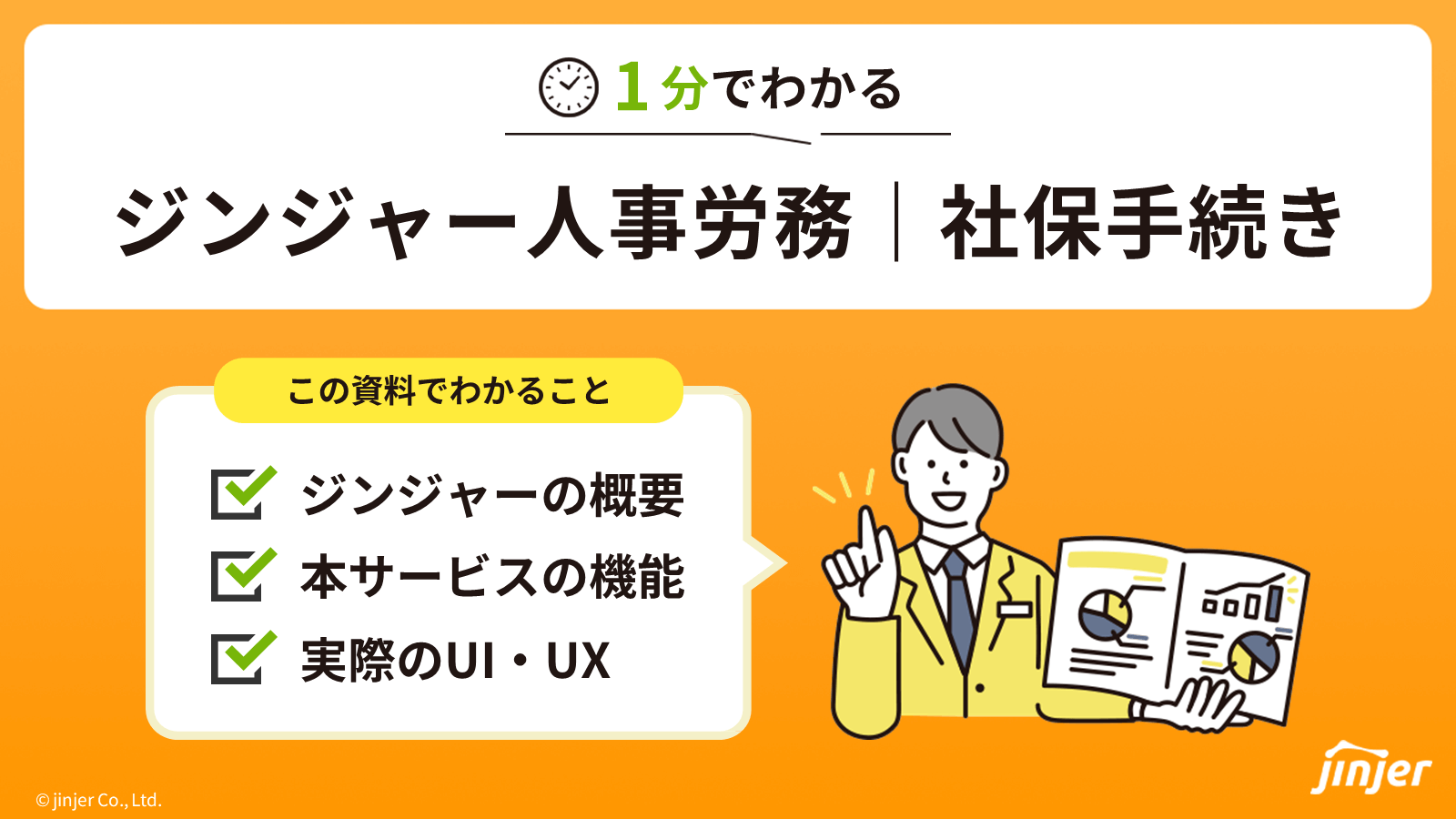
入退社のたびに発生する書類作成、行政機関への提出…。
書き損じや、手続きの度にキャビネットを埋め尽くしていく大量のファイル管理に時間を費やしていませんか?
その手間、電子申請で一気に解決できるかもしれません。
◆紙の書類管理から解放される3つのポイント
- 探す手間からの解放: 保管書類はデータで管理。検索すればいつでもすぐに検索可能。
- 手書き・転記からの解放: 人事データをもとに、面倒な申請書類を自動作成。
- 提出・保管からの解放: 作成した書類はオフィスから一括電子申請、物理的な保管場所も不要。
ペーパーレス化で実現する、新しい働き方の第一歩を提案していますので、ぜひこちらから資料をダウンロードしてご活用ください。
人事・労務管理のピックアップ
-


【採用担当者必読】入社手続きのフロー完全マニュアルを公開
人事・労務管理公開日:2020.12.09更新日:2026.01.30
-


人事総務担当がおこなう退職手続きの流れや注意すべきトラブルとは
人事・労務管理公開日:2022.03.12更新日:2025.09.25
-



雇用契約を更新しない場合の正当な理由とは?伝え方・通知方法も紹介!
人事・労務管理公開日:2020.11.18更新日:2025.10.09
-


社会保険適用拡大とは?2024年10月の法改正や今後の動向、50人以下の企業の対応を解説
人事・労務管理公開日:2022.04.14更新日:2025.10.09
-


健康保険厚生年金保険被保険者資格取得届とは?手続きの流れや注意点
人事・労務管理公開日:2022.01.17更新日:2025.11.21
-


同一労働同一賃金で中小企業が受ける影響や対応しない場合のリスクを解説
人事・労務管理公開日:2022.01.22更新日:2025.08.26
労務の関連記事
-


年収の壁はどうなった?2025年最新動向と人事が押さえるポイント
勤怠・給与計算公開日:2025.11.20更新日:2025.11.17
-


2025年最新・年収の壁を一覧!人事がおさえたい社会保険・税金の基準まとめ
勤怠・給与計算公開日:2025.11.19更新日:2025.12.22
-


人事担当者必見!労働保険の対象・手続き・年度更新と計算方法をわかりやすく解説
人事・労務管理公開日:2025.09.05更新日:2026.01.30




















