マルチジョブホルダー制度とは?対象要件や手続きの流れについて
更新日: 2024.7.11
公開日: 2022.4.12
OHSUGI

雇用保険法の改正にともない、2022年1月より雇用保険マルチジョブホルダー制度が導入されることになりました。
要件を満たす労働者が希望した場合、事業者は手続きに必要な証明などに対応しなければならないため、マルチジョブホルダーに関する基本的な知識をしっかり押さえておきましょう。
今回は、マルチジョブホルダー制度の概要や、対象要件、手続きの流れ、注意点について解説します。
目次
社会保険の手続きガイドを無料配布中!
社会保険料は従業員の給与から控除するため、ミスなく対応しなければなりません。
しかし、一定の加入条件があったり、従業員が入退社するたびに行う手続きには、申請期限や必要書類が細かく指示されており、大変複雑で漏れやミスが発生しやすい業務です。
さらに昨今では法改正によって適用範囲が変更されている背景もあり、対応に追われている労務担当者の方も多いのではないでしょうか。
当サイトでは社会保険の手続きをミスや遅滞なく完了させたい方に向け、最新の法改正に対応した「社会保険の手続きガイド」を無料配布しております。
ガイドブックでは社会保険の対象者から資格取得・喪失時の手続き方法までを網羅的にわかりやすくまとめているため、「最新の法改正に対応した社会保険の手続きを確認しておきたい」という方は、こちらから資料をダウンロードしてご覧ください。
1. マルチジョブホルダー制度とは?


マルチジョブホルダー制度とは、雇用保険法の改正にともなって新設された新たな雇用保険制度のことです。
複数の事業所で働く65歳以上の高齢労働者が一定の要件を満たした場合、本人からハローワークに申し出ることで、特例的に雇用保険に加入することが可能となります。
なお、マルチジョブホルダー制度によって雇用保険に加入した高齢労働者は、制度を利用していない高齢労働者と区別するため、「マルチ高年齢被保険者」と呼ばれます。
マルチジョブホルダー制度は2022年1月1日より試行実施され、5年後を目途にその効果を検証する予定となっています。
1-1. マルチジョブホルダー制度導入の目的
日本では少子高齢化が急速に進展しており、労働生産人口が年々減少していることから、慢性的に働き手が不足しています。そこで近年では、定年退職を迎えた高齢者を積極的に雇用する事例が増えてきていますが、パートやアルバイトなどの非正規社員として雇い入れるケースが多く、雇用保険の加入要件を満たせる人は決して多くありません。
雇用保険に加入していないと、万一失業してしまった場合に保障を受けられず、生活に困窮してしまうおそれがあります。マルチジョブホルダー制度はこうした問題を解決するために導入された制度で、高齢労働者が安心して働ける環境の整備を目的としています。
1-2. マルチジョブホルダーで受けられる給付内容
マルチジョブホルダーでは、会社を退職した際に支給される⾼年齢求職者給付(失業給付)を受けることができます。ただし、離職日以前の1年間に基礎賃金の支払いが11日以上あった月が6か月以上(11日に満たない場合は80時間以上)あるという条件を満たすことが必要です。
条件を満たしていれば、被保険者であった期間に応じて30日分または50日分の⾼年齢求職者給付が一時金で支払われます。
このほかにも通常の雇用保険と同様に、教育給付や育児給付、介護給付なども受けることができます。
2. マルチジョブホルダーの対象要件


マルチジョブホルダー制度は誰でも利用できるわけではなく、一定の要件を満たす必要があります。
マルチジョブホルダー制度の対象要件は以下の通りです。[注1]
- 複数の事業所に雇用される65歳以上の労働者であること
- 1週間における2つの事業所の所定労働時間の合計が20時間以上であること
- 2つの事業所それぞれの雇用見込みが31日以上であること
2に関しては、1つの事業所における1週間の所定労働時間が5時間以上20時間未満である必要があります。
たとえば、Aの事業所で18時間、Bの事業所で3時間働いている場合、1週間の所定労働時間は20時間を超えますが、Bの事業所の所定労働時間が5時間を超えていないので、マルチジョブホルダー制度の対象にはなりません。
[注1]「雇用保険マルチジョブホルダー制度」を新設します|厚生労働省
2-1. 従来の雇用保険の対象要件との違い
従来の雇用保険では、以下の1および2のいずれにも該当することが加入要件となっています。[注2]
- 31日以上引き続き雇用されることが見込まれる者(以下いずれかに該当)
a. 期間の定めがなく雇用される場合
b. 雇用期間が31日以上の場合
c. 雇用契約に更新規定があり、31日未満での雇い止めの明示がない場合
d. 雇用契約に更新規定はないものの、同様の雇用契約によって31日以上雇用された実績がある場合 - 1週間の所定労働時間が20時間以上であること
つまり、特定の事業所で31日以上かつ週の所定労働時間が20時間以上でなければ、雇用保険に加入できない仕組みになっています。
一方、マルチジョブホルダー制度では、週の所定労働時間が複数の勤務先で通算されるため、パートやアルバイトなどの短時間勤務であっても、制度の適用対象者となることが可能です。
ただ、年齢に定めのない雇用保険に対し、マルチジョブホルダー制度は65歳以上の高齢労働者であることが要件のひとつとなっています。
[注2]雇用保険の加入手続はきちんとなされていますか!|厚生労働省
関連記事:雇用保険とは?給付内容や適用される適用事業所について
3. マルチジョブホルダーを利用する際の手続きの流れ


マルチジョブホルダー制度を利用するためには、被保険者となる労働者本人が手続きをおこなう必要があります。
ただ、手続きの過程には事業主が関わる項目もありますので、労働者から求められた場合は、速やかに対応しましょう。
ここでは、マルチジョブホルダーを利用する際の手続きの流れを4つのステップに分けて解説します。
3-1. ステップ①必要書類を入手する
労働者は最寄りのハローワークまたは厚生労働省のHPから、以下の書類を入手します。[注3]
- 雇用保険マルチジョブホルダー雇入・資格取得届(マルチ雇入届)
- 個人番号登録・変更届
- 被保険者資格取得時アンケート
マルチ雇入届は、選択した2社分必要となります。3社以上で勤務している場合には、労働者が選択した2社分が必要となります。
労働者は、自分の被保険者番号、氏名、性別、生年月日、就職経路などを記載します。
被保険者番号は雇用保険被保険者証に記載されていますが、入社時に会社に預けている場合は番号を調べる術がありませんので、空欄でもOKです。
一方、個人番号登録・変更届には、個人番号や被保険者番号、氏名、生年月日などを記載します。
被保険者資格取得時アンケートは、マルチジョブホルダーの試行実施の効果などを検証するための情報のひとつとして活用されるものです。なぜマルチジョブホルダー制度を利用しようと思ったのか、退職する時期は決まっているかなどの質問がいくつか掲載されていますので、自分の状況に合った回答を選択しましょう。
[注3]雇用保険マルチジョブホルダー制度の申請パンフレット|厚生労働省
3-2. ステップ②事業主がマルチ雇入届に必要事項を記載する
マルチ雇入届には、被保険者だけでなく、事業者が記入する項目もあります。
具体的な記載項目は以下の通りです。
- 事業所番号
- マルチジョブの被保険者となったことの原因
- 賃金
- 雇入年月日
- 雇用形態
- 職種
- 1週間の所定労働時間
- 契約期間の定め
3には、賞与や臨時の賃金を除く、採用時に定められた賃金のうち、毎月決まって支払われるべき金額を記載します。7と8についてはマルチジョブホルダーの対象要件に関わる項目ですので、間違いのないよう記載しましょう。
マルチ雇入届に必要事項を記入したら、以下の確認書類を添付し、労働者に交付します。
- 賃金台帳、出勤簿
- 労働者名簿
- 雇用契約書
- 労働条件通知書、雇入通知書
「賃金台帳、出勤簿」は原則として、記載年月日の直近1ヵ月分のものを用意します。
これらの確認書類はすべてコピーの提出が可能で、原本を添付する必要はありません。
なお、労働者が会社の役員・事業主と同居している親族および在宅勤務者の場合は、別途確認書類が必要になることもあるため、あらかじめハローワークに問い合わせておきましょう。
3-3. ステップ③ハローワークに書類を提出する
労働者の住まいを管轄するハローワークに、窓口または郵送で必要書類を提出します。なお、マルチジョブホルダー制度は申し出をおこなった日から特例的に高年齢被保険者となるため、書類を郵送する場合は送達記録が残る簡易書留などの方法で送付する必要があります。
3-4. ステップ④ハローワークから書類が交付される
ハローワークは提出された書類を確認した後、労働者と事業主それぞれに必要書類を交付します。
労働者宛に交付される書類は以下の通りです。
- 雇用保険マルチジョブホルダー雇入・資格取得確認
- 雇用保険マルチジョブホルダー喪失・資格喪失届
- 雇用保険被保険者証
- 被保険者資格喪失時アンケート
1と2は勤め先の数だけ交付されます。
なお、2・3・4の書類は離職する際に使用するため、きちんと保管しておく必要があります。
一方、事業主宛には、雇用保険マルチジョブホルダー雇入・資格取得確認通知書(事業主通知用)が交付されますので、会社で保管しておきましょう。
3-5. 資格を喪失したときも手続きが必要
離職や週の労働時間が20時間未満になるなどして、マルチジョブホルダーの資格を喪失した際にも所定の手続きがです。資格取得時と同様、資格喪失時においても基本的には労働者本人が手続きをおこないます。
ただし、「雇用保険マルチジョブホルダー喪失・資格喪失届」の事業主記載事項には、事業主が記載をおこない、必要な確認書類を労働者へ交付しなくてはいけません。
手続きが終わると、ハローワークより「雇用保険マルチジョブホルダー喪失・資格喪失確認通知書(事業主通知用)」と「離職証明書(事業主控)」が送られてくるので大切に保管しましょう。通知書に記載されている離職年月日から雇用保険料の納付義務が消滅となります。
4. マルチジョブホルダー制度のメリットは


マルチジョブホルダー制度は、事業主と労働者双方にメリットがあります。
事業主側のメリットは、手続きの負担が少ないことです。基本的には労働者本人がほとんどの手続きをおこなうので、事業主は必要な証明や確認書類の交付だけで済みます。
一方、労働者側のメリットは、短時間労働であっても雇用保険の補償を受けやすくなることです。マルチジョブホルダー制度では2事業所の週の労働時間を通算することができるため、所定の条件を満たすことで、失業給付や教育給付などの補償を受けることができます。
5. マルチジョブホルダー制度の注意点


マルチジョブホルダー制度は、労働者の自己申告によって加入する雇用保険です。通常の雇用保険制度とは運用方法が異なるため、注意しておきたいポイントがいくつかあります。
ここでは、マルチジョブホルダー制度で特に注意しておきたいポイントを3つご紹介します。
5-1. 労働者に求められた場合、企業は必ず対応しなければならない
雇用保険の適用事業者は、労働者からマルチジョブホルダー制度の利用手続きを求められた場合、これを拒否することはできません。
労働者から証明を求められた場合はすみやかに対応しなければなりませんし、マルチジョブホルダーが申し出をおこなったことを理由に、不利益な取り扱いをおこなうことは禁じられています。
事業主がマルチジョブホルダーの手続きを拒否し続けた場合、ハローワークから事業主に対して指導が入る可能性があるため注意しましょう。
5-2. 申し出日から雇用保険料の納付義務が発生する
マルチジョブホルダー制度を利用して特例的に雇用保険に加入する場合、申し出をおこなったその日から雇用保険料の納付義務が発生します。
雇用保険料は、原則として事業者が労働者の給与から天引きする形で納付するので、マルチジョブホルダー制度を利用する申し出を受けたら、雇用保険料の計算や納付に必要な準備をあらかじめおこなっておきましょう。
なお、マルチジョブホルダーでも通常の雇用保険と計算方法は同じです。
5-3. 3つ以上の事業所で勤務の場合は申請できるのは2事業所まで
マルチジョブホルダー制度で申請できるのは、2事業所までです。例えば、3つの事業所で働いている場合、このうち2つの事業所を労働者が選択して手続きをしなければなりません。労働者がこのことを知らずに、3つ以上の事業所で手続きしようとしている場合は注意が必要です。
もし申請後に、どちから一方の事業所を退職して週の労働時間が20時間未満となっても、申請をしなかった事業所と通算して20時間を超えていれば、引き続きマルチジョブホルダーの適用が受けられます。
この場合にも、退職する事業所で資格喪失手続きをおこない、新たに適用する事業所で資格取得の手続きをおこなう必要があります。
6. マルチジョブホルダー制度を正しく理解し、すみやかな対応に努めよう
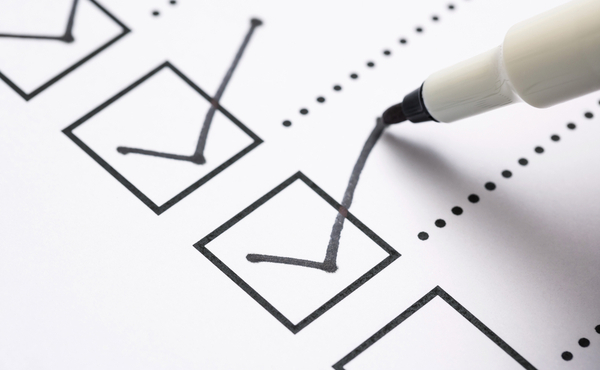
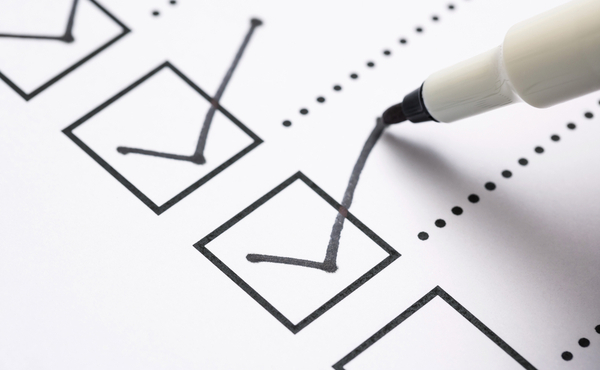
マルチジョブホルダー制度は、一定の要件を満たした65歳以上の労働者が特例的に雇用保険に加入できる制度です。
手続きそのものは原則として労働者本人がおこないますが、事業者も書類に必要事項を記載したり、書類を用意したりしなければなりません。必要な手続きや大まかな流れをしっかり把握しておきましょう。
社会保険の手続きガイドを無料配布中!
社会保険料は従業員の給与から控除するため、ミスなく対応しなければなりません。
しかし、一定の加入条件があったり、従業員が入退社するたびに行う手続きには、申請期限や必要書類が細かく指示されており、大変複雑で漏れやミスが発生しやすい業務です。
さらに昨今では法改正によって適用範囲が変更されている背景もあり、対応に追われている労務担当者の方も多いのではないでしょうか。
当サイトでは社会保険の手続きをミスや遅滞なく完了させたい方に向け、最新の法改正に対応した「社会保険の手続きガイド」を無料配布しております。
ガイドブックでは社会保険の対象者から資格取得・喪失時の手続き方法までを網羅的にわかりやすくまとめているため、「最新の法改正に対応した社会保険の手続きを確認しておきたい」という方は、こちらから資料をダウンロードしてご覧ください。
人事・労務管理のピックアップ
-


【採用担当者必読】入社手続きのフロー完全マニュアルを公開
人事・労務管理
公開日:2020.12.09更新日:2024.03.08
-


人事総務担当が行う退職手続きの流れや注意すべきトラブルとは
人事・労務管理
公開日:2022.03.12更新日:2024.06.11
-


雇用契約を更新しない場合の正当な理由とは?通達方法も解説!
人事・労務管理
公開日:2020.11.18更新日:2024.07.10
-


法改正による社会保険適用拡大とは?対象や対応方法をわかりやすく解説
人事・労務管理
公開日:2022.04.14更新日:2024.06.12
-


健康保険厚生年金保険被保険者資格取得届とは?手続きの流れや注意点
人事・労務管理
公開日:2022.01.17更新日:2024.07.02
-


同一労働同一賃金で中小企業が受ける影響や対応しない場合のリスクを解説
人事・労務管理
公開日:2022.01.22更新日:2024.05.08





















