男女雇用機会均等法のセクシャルハラスメントとは?事業主がとるべき防止策を解説
更新日: 2025.10.30 公開日: 2025.2.28 jinjer Blog 編集部

「男女雇用機会均等法のセクシャルハラスメントとは?」
「セクシャルハラスメントの防止策を知りたい」
上記のような疑問や悩みをお持ちの方もいるでしょう。
男女雇用機会均等法におけるセクシャルハラスメントとは、職場において労働者の意に反し、性的な言動をする行為です。
男女雇用機会均等法は、従業員が安心して能力を発揮できる職場環境を整えるために制定されました。セクシャルハラスメントの防止策についても定められており、企業は適切な措置をおこなうよう義務付けられています。
本記事では、男女雇用機会均等法におけるセクシャルハラスメントや事業主がとるべき防止策について解説します。男女雇用機会均等法に違反した場合のリスクや罰則についても触れているので、ぜひ参考にしてください。

人事労務担当者の実務の中で、従業員情報の管理は入退社をはじめスムーズな情報の回収・更新が求められる一方で、管理する書類が多くミスや抜け漏れが発生しやすい業務です。
さらに、人事異動の履歴や評価・査定結果をはじめ、管理すべき従業員情報は多岐に渡り、管理方法とメンテナンスの工数にお困りの担当者の方もいらっしゃるのではないでしょうか。
そんな人事労務担当者の方には、Excel・紙管理から脱却し定型業務を自動化できるシステムの導入がおすすめです。
◆解決できること
- 入社手続きがオンラインで完結し、差し戻し等やりとりにかかる時間を削減できる
- システム上で年末調整の書類提出ができ、提出漏れや確認にかかる工数を削減できる
- 入社から退職まで人事情報がひとつにまとまり、紙やExcel・別システムで複数管理する必要がなくなる
システムを利用したペーパーレス化に興味のある方は、ぜひこちらから資料をダウンロードの上、業務改善にお役立てください。
1. 男女雇用機会均等法におけるセクシャルハラスメントとは


男女雇用機会均等法におけるセクシャルハラスメントは、以下の条件をすべて満たす行為が対象となります。
- 職場においておこなわれていること
- 労働者の意に反していること
- 性的な言動がおこなわれていること
1-1. 職場においておこなわれていること
男女雇用機会均等法におけるセクシャルハラスメントは、職場においておこなわれている行為が対象です。
職場とは、従業員が業務を遂行する場所であり、通常就業する場所以外であっても職場に該当します。取引先の事務所や顧客の自宅、移動に利用する車中なども対象です。
また、勤務時間外の宴会の場も実質上業務の延長とみなされ、職場に該当します。社員旅行や社内レクリエーションなどの場も同様です。
このように、職場の定義は単に就業場所だけを指すものではない点に注意が必要です。職場であるかどうかの判断は、職務との関連性や参加者、参加や対応が強制的か任意であるかなどを踏まえて、個別に考慮する必要があるとされています。
1-2. 労働者の意に反していること
男女雇用機会均等法におけるセクシャルハラスメントは、労働者の意に反している行為が対象となります。
労働者は性別や雇用形態にかかわらず、雇用する従業員全員が対象です。正社員はもちろん、契約社員や派遣社員、アルバイトなどの非正社員も含まれます。
なお、労働施策総合推進法の改正が令和7年6月に公布されたことで、求職者に対するセクハラ防止措置も事業主に義務付けられます。そのため今後は、労働者だけでなく求職者に対しても、定められた措置を講じる必要がでてくるでしょう。
参考:ハラスメント対策・女性活躍推進に関する改正ポイントのご案内|厚生労働省
1-3. 性的な言動がおこなわれていること
男女雇用機会均等法におけるセクシャルハラスメントは、性的な言動がおこなわれていることを指します。
性的な言動は、性的な内容の発言だけではなく性的な行動も対象です。性的な言動にあたる可能性が高い内容を以下にまとめました。
| 性的な発言 |
|
| 性的な行動 |
|
異性に対してだけではなく、同性におこなう行為もセクシャルハラスメントと定義されます。
参考:職男女雇用機会均等法におけるセクシュアルハラスメント防止対策 | 香川労働局
参考:職場におけるセクシュアルハラスメントとは | 岐阜労働局
1-4. セクシャルハラスメントの判断基準
セクシャルハラスメントの状況は多様であることから、厚生労働省では個別に状況を考慮した上で判断されるべきという見解を示しています。
この判断の際に重視されるのが、「労働者の意に反する性的な言動」と「労働者の就業環境を害している」の2点です。この2点の判断にあたっては、被害者の主張を尊重しつつも、以下のような客観性のある判断も必要としています。
・一回の身体的接触でも強い精神的苦痛を与える場合は、就業環境を害していると判断され得る
・明確な抗議があったにもかかわらず放置された場合や、心身に重大な影響があることが明らかな場合には、少ない回数であっても就業環境を害していると判断され得る
・被害者が女性の場合は「平均的な女性労働者の感じ方」、男性の場合は「平均的な男性労働者の感じ方」を判断の要素として考慮することが適当
身体的な接触がある場合や、セクハラ行為が繰り返しおこなわれていた場合は、上記のとおり厳しい基準が適用されるため注意が必要です。
1-5. セクシャルハラスメントの現状
厚生労働省が公表している令和5年度の「職場のハラスメントに関する実態調査」によると、セクハラに関して過去3年間に相談があったと回答した企業割合は39.5%でした。令和2年度の調査より9.7%増加しています。
また、相談があった事例のうち、企業がセクハラと判断した事例の有無については80.9%となっています。
男女雇用機会均等法によってセクハラ対策が義務化されたものの、依然として被害の報告は後を絶ちません。この状況からも、企業におけるセクハラ対策の重要性は変わらず高く、組織としての取り組みを一層強化する必要があると言えるでしょう。
2. 男女雇用機会均等法の歴史


男女雇用機会均等法は1986年に施行されました。当初は募集や採用、配置・昇進について女性を男性と均等に取り扱う努力義務を定めるとともに、教育訓練や福利厚生、定年、退職、解雇などでの女性に対する差別的取り扱いを禁止していました。その後、次のとおり改正が繰り返されています。
| 年 | 主な改正内容 |
| 1999年 | ・募集や採用、配置・昇進について女性を男性と均等に取り扱う努力義務を義務化
・事業主に対するセクハラ防止措置の義務化 ・行政指導に背いた際の企業名公表制度の導入 |
| 2007年 | ・男女双方への差別禁止
・妊娠や出産などを理由にした不利益な取り扱いの禁止 |
| 2017年 | ・妊娠や出産などを理由にした不利益な取り扱いを防止する措置の義務化 |
| 2020年 | ・セクハラ防止対策の強化 |
3. 男女雇用機会均等法で想定される2種類のセクシャルハラスメント


男女雇用機会均等法におけるセクシャルハラスメントは、以下の2つに分類されます。
- 対価型セクシャルハラスメント
- 環境型セクシャルハラスメント
3-1. 対価型セクシャルハラスメント
対価型セクシャルハラスメントとは、セクシャルハラスメントにあたる行為を拒否した影響で不利益を受けることです。
不利益の具体例としては、解雇や降格、減給などが挙げられます。
例えば以下のようなケースが、対価型セクシャルハラスメントとみなされます。
- 経営者から性的な関係を求められたが、拒否したところ解雇された
- 出張中に上司に何度も体を触られたため抗議したら、遠方の部署に配置転換された
参考:職場におけるハラスメントの防止のために(セクシュアルハラスメント/妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメント/パワーハラスメント|厚生労働省
3-2. 環境型セクシャルハラスメント
環境型セクシャルハラスメントとは、セクシャルハラスメントにあたる行為により、就業環境が害されることです。
具体的には、業務に対するモチベーションや集中力の低下が挙げられます。
環境型セクシャルハラスメントには、以下のようなケースが該当します。
- 上司がたびたび腰を触ってくるため、事務所内にいることを苦痛に感じている
- 同僚が勤務中に性的な話を頻繁にしているため、就業意欲が低下している
対価型セクシャルハラスメントと比較すると判断が難しく、セクシャルハラスメントであることに気づかないケースも少なくありません。環境型セクシャルハラスメントは、行為がエスカレートしやすいので注意が必要です。
参考:職場におけるハラスメントの防止のために(セクシュアルハラスメント/妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメント/パワーハラスメント|厚生労働省
4. 職場のセクシャルハラスメント防止対策は企業の義務


男女雇用機会均等法では、企業に対してセクシャルハラスメントの防止対策を講じるよう義務付けています。
企業として実施すべき防止策は以下のとおりです。
- 事業主の方針を明確化にして周知・啓発する
- 相談や苦情に対応できる体制を整備する
- 事後に迅速かつ適切な対応をおこなう
- 相談者や行為者のプライバシーを保護する
4-1. 事業主の方針を明確にして周知・啓発する
事業主は、セクシャルハラスメントを禁止する方針を就業規則等に定め、従業員に周知・啓発する必要があります。
従業員に周知・啓発するための方法を以下にまとめました。
| 具体例 | |
| 周知する方法 |
|
| 啓発する方法 |
|
セクシャルハラスメントについての方針は性別や雇用形態にかかわらず、全従業員に対して周知・啓発するようにしましょう。
4-2. 相談や苦情に対応できる体制を整備する
セクシャルハラスメントの被害にあった従業員の相談や苦情に対応できる体制を整備しておくことも重要です。具体的には、相談窓口の設置が挙げられます。
相談窓口は面談に限らず、電話やメールなどのツールも利用できるようにして従業員が相談しやすい仕組みにしましょう。
また、セクシャルハラスメントの相談や苦情に適切な対応をするためには、専門的な知識とスキルが必要です。社内で相談担当者を任命できない場合は、社外相談窓口の設置を検討してみてもよいでしょう。
4-3. 事後に迅速かつ適切な対応をおこなう
セクシャルハラスメントの相談や苦情を受けたら、担当者には迅速かつ適切な対応が求められます。
まずは、被害者と加害者を隔離しましょう。同じ環境のままにしておくと、さらなるトラブルに発展するおそれがあるためです。配置換えが理想的ですが、難しい場合は自宅待機などの方法を検討しましょう。
つぎに、被害者と加害者の双方からヒアリングを実施します。事実関係について調査するためです。必要に応じて、周囲の同僚などからもヒアリングを実施しましょう。
調査の結果、セクシャルハラスメントに該当する行為があったと認められたら、加害者に妥当な処罰を下し再発防止策を立てます。
4-4. 相談者や行為者のプライバシーを保護する
セクシャルハラスメントの相談や苦情を受けた場合、相談者のプライバシーを保護しなければいけません。プライバシーの保護が不十分だと、被害者が安心して相談できないためです。
また、行為者のプライバシーについても保護する必要があります。とくに事実関係が明らかになるまでは冤罪の可能性もあるので、慎重に対応しましょう。
参考:職場におけるハラスメントの防止のために(セクシュアルハラスメント/妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメント/パワーハラスメント|厚生労働省
5. 男女雇用機会均等法に違反した場合のリスク・罰則


男女雇用機会均等法に違反すると、次のような罰則やリスクにつながりかねません。
- 事業主への報告要求や勧告
- 勧告に応じない事業主の公表
- 訴訟に発展する恐れがある
5-1. 事業主への報告要求や勧告
男女雇用機会均等法に違反した場合、厚生労働大臣は事業主に対して報告を求めることが認められています。また、対象の事業主へ助言、指導、勧告をおこなうことも可能です。
報告を求められているにも関わらず、対応しなかった場合や虚偽の報告をした場合、20万円以下の過料が科せられる可能性があります。
男女雇用機会均等法に違反しないことが最も重要ですが、万が一違反してしまい、厚生労働大臣から報告を求められた際は、速やかに対応しましょう。
5-2. 勧告に応じない事業主の公表
先述のとおり、厚生労働大臣は男女雇用機会均等法に違反した事業主に対して、勧告ができます。助言や指導、勧告は行政指導にあたるため、法的な拘束力はありません。
しかし、勧告に応じなかった事業主は厚生労働省のサイトにて公表されてしまいます。厚生労働省のサイトで公表されてしまうと、自社のイメージが大幅に低下しかねません。
違反内容が悪質な場合は、マスコミによって報道される恐れもあるでしょう。これにより、顧客からの信頼低下も免れません。さらに、採用活動にまで影響が及ぶ恐れもあります。
5-3. 訴訟に発展する恐れがある
訴訟に発展した場合、訴えられるのは行為者だけではありません。セクハラに対して適切な対応や措置をおこなわなければ、使用者責任や債務不履行責任を問われて会社側も訴えられる可能性があります。
過去には、上司からのセクハラ行為を会社に訴えたにもかかわらず、調査もせずに相談者に降格や減給の処分をしたとして、行為者と会社に対して約3,000万円の損害賠償を連帯して支払うよう命じられた判例もあります。
このように悪質なケースでは、報道され社会的に広く認知される可能性もあり、会社に与える損害ははかりしれません。セクハラを放置することは、行為者だけでなく会社側にとっても大きなリスクであることを認識する必要があります。
6. セクシャルハラスメント防止の取り組み事例
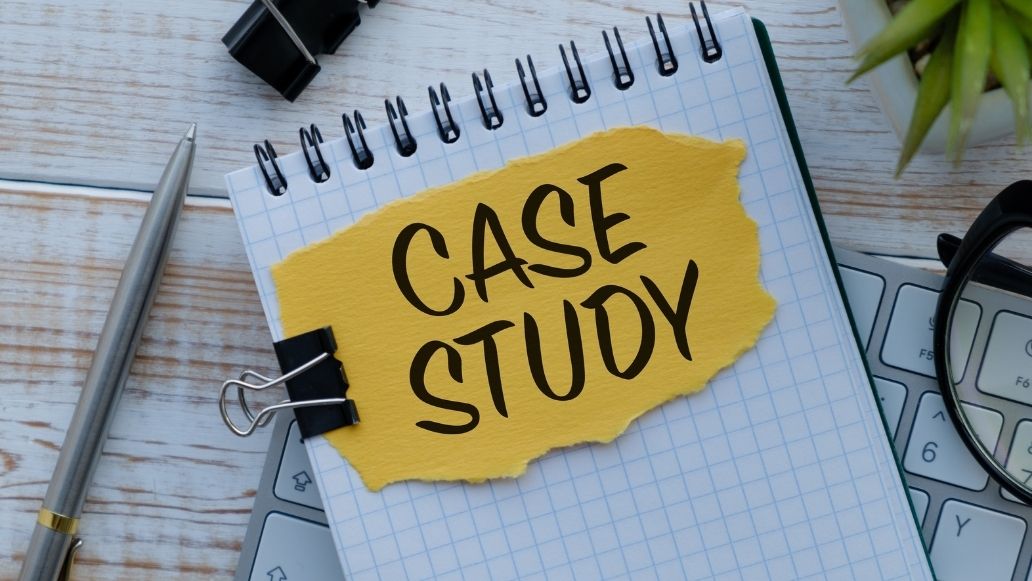
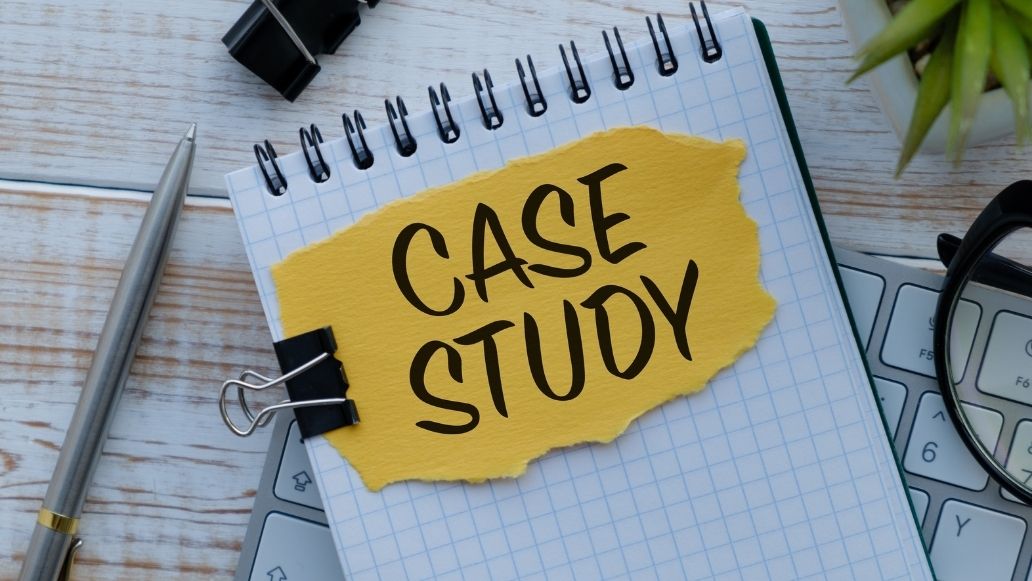
セクシャルハラスメントを防止するための施策を検討するにあたっては、他社の取り組み事例が参考になります。ここでは、株式会社アドウェイズの取り組みを紹介します。
同社では、セクハラを含むハラスメントの防止のために、eラーニングの実施などさまざまな取り組みを実施していますが、中でも目を引くのが相談窓口です。
窓口の種類を「相談」と「通報」で分け、さらに内容に応じて計6つの窓口を設けています。匿名で相談できる「目安箱」や、外部カウンセラーが対応する「なんでも相談室」など、相談内容に合わせて従業員が選べるようになっているのが特徴です。
これには、ハラスメントの早期把握や、従業員の心理的ハードルの低下などの効果が現れています。取り組みを実施してからは、従業員同士の会話や接し方に変化が現れ、安心した距離感で働ける職場環境に変わりつつあるようです。
7. ハラスメント以外の男女雇用機会均等法のポイント
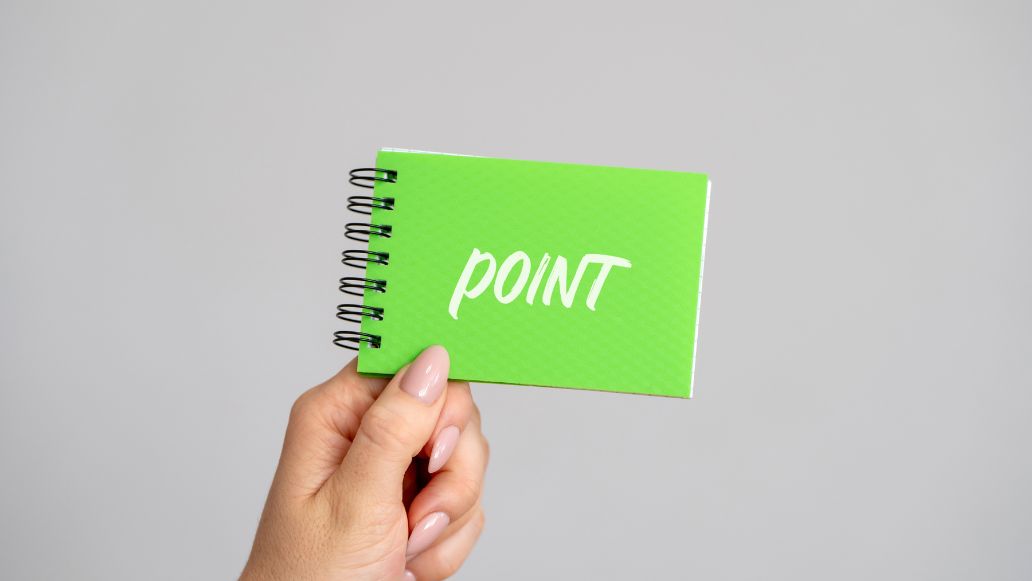
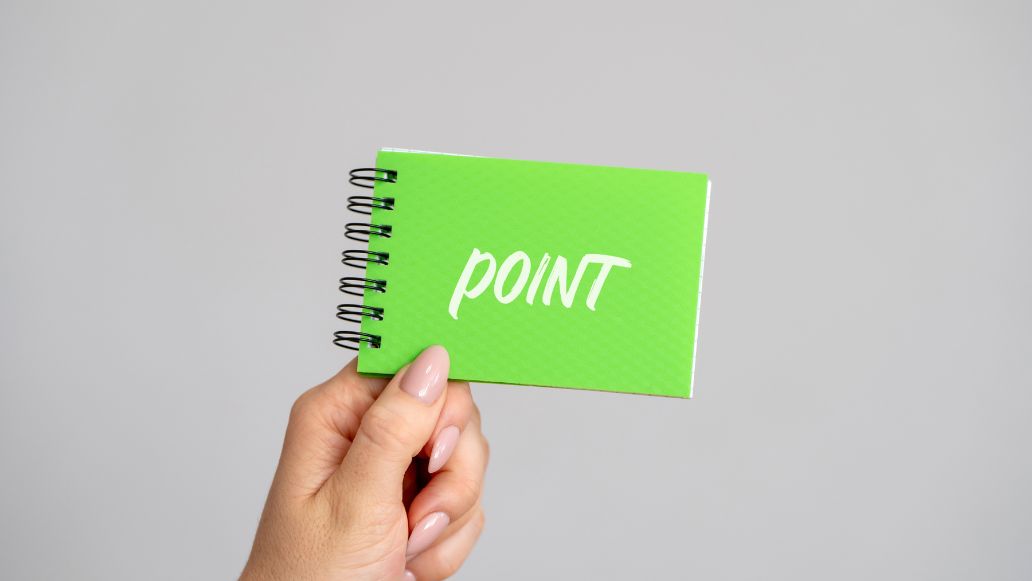
男女雇用機会均等法を遵守するうえでは、ハラスメントだけでなく以下のポイントも押さえておきましょう。
性別を理由とする不合理な差別の禁止
労働者と事業主との間に紛争が生じた場合の救済措置
7-1. 性別を理由とする不合理な差別の禁止
男女雇用機会均等法では性別を理由とした不合理な差別を禁止しています。性別を理由とする不合理な差別は次の2通りです。
直接差別:募集・採用時や配置・昇進、教育訓練、福利厚生、定年・退職・解雇などにおいて、性別を理由に取り扱いを変えること
間接差別:中立に見えても実際は性別によって実質的に不利益を生じさせる措置を合理的理由なしに講じること
間接差別の例として、身長や体力、体重を募集の要件にするケースがあります。身長、体力などは性別によって異なるにも関わらず、募集要件とすると不合理な差別に該当しかねません。
7-2. 労働者と事業主との間に紛争が生じた場合の救済措置
男女雇用機会均等法上の差別や不利益取扱いについては、まず労働者と事業主との間で自主的に解決を図ることが原則とされています。当事者間で解決しない場合、都道府県労働局長に対して以下の手続きが利用可能です。
- 援助請求
- 調停申し立て
救済措置では、労働局長が当事者双方から事情聴取や必要に応じて調査をおこない、助言や指導、勧告をおこなって紛争解決の援助をおこないます。なお、労働者が紛争解決の援助を求めたことを理由に、事業主が解雇や配置転換など不利益な取り扱いをすることは禁じられているため注意しましょう。
8. 男女雇用機会均等法を理解しセクシャルハラスメントを防止しよう


男女雇用機会均等法は、従業員が安心して能力を発揮できる職場環境を整備するための法律です。セクシャルハラスメントに対する防止対策についても定められているので、企業は適切な措置をおこなう必要があります。
男女雇用機会均等法に違反した場合、過料が科せられたり企業名が公表されたりするため、企業にとって大きなリスクとなります。
男女雇用機会均等法を正しく理解し、セクシャルハラスメントを防止しましょう。



人事労務担当者の実務の中で、従業員情報の管理は入退社をはじめスムーズな情報の回収・更新が求められる一方で、管理する書類が多くミスや抜け漏れが発生しやすい業務です。
さらに、人事異動の履歴や評価・査定結果をはじめ、管理すべき従業員情報は多岐に渡り、管理方法とメンテナンスの工数にお困りの担当者の方もいらっしゃるのではないでしょうか。
そんな人事労務担当者の方には、Excel・紙管理から脱却し定型業務を自動化できるシステムの導入がおすすめです。
◆解決できること
- 入社手続きがオンラインで完結し、差し戻し等やりとりにかかる時間を削減できる
- システム上で年末調整の書類提出ができ、提出漏れや確認にかかる工数を削減できる
- 入社から退職まで人事情報がひとつにまとまり、紙やExcel・別システムで複数管理する必要がなくなる
システムを利用したペーパーレス化に興味のある方は、ぜひこちらから資料をダウンロードの上、業務改善にお役立てください。
人事・労務管理のピックアップ
-


【採用担当者必読】入社手続きのフロー完全マニュアルを公開
人事・労務管理公開日:2020.12.09更新日:2026.01.30
-


人事総務担当がおこなう退職手続きの流れや注意すべきトラブルとは
人事・労務管理公開日:2022.03.12更新日:2025.09.25
-



雇用契約を更新しない場合の正当な理由とは?伝え方・通知方法も紹介!
人事・労務管理公開日:2020.11.18更新日:2025.10.09
-


社会保険適用拡大とは?2025年6月改正法成立後の動向や必要な対応を解説
人事・労務管理公開日:2022.04.14更新日:2026.02.27
-


健康保険厚生年金保険被保険者資格取得届とは?手続きの流れや注意点
人事・労務管理公開日:2022.01.17更新日:2025.11.21
-


同一労働同一賃金で中小企業が受ける影響や対応しない場合のリスクを解説
人事・労務管理公開日:2022.01.22更新日:2025.08.26





















