ハラスメント相談窓口の義務化とは?企業が実施すべき措置や注意点を解説
更新日: 2025.7.11 公開日: 2025.3.17 jinjer Blog 編集部

職場におけるパワハラやセクハラなどのハラスメントは、深刻な社会問題となっています。
ハラスメントを放置すると、従業員のメンタルヘルスの悪化だけでなく、離職をしてしまう確率が高くなります。また、ハラスメントの内容によっては、提訴や告訴など訴訟問題が起こる可能性もあるので、企業側は適切な対応をしなければなりません。
そもそも、ハラスメントに対しては、2022年4月から「パワーハラスメント防止措置の義務化」が施行されています。そのため、従業員が安全かつ働きやすい場を提供できるよう、企業はハラスメント相談窓口を設置し、適切な措置を取ることが求められます。
本記事では、ハラスメント相談窓口の義務化の背景や種類、企業が実施すべき措置について解説します。
目次
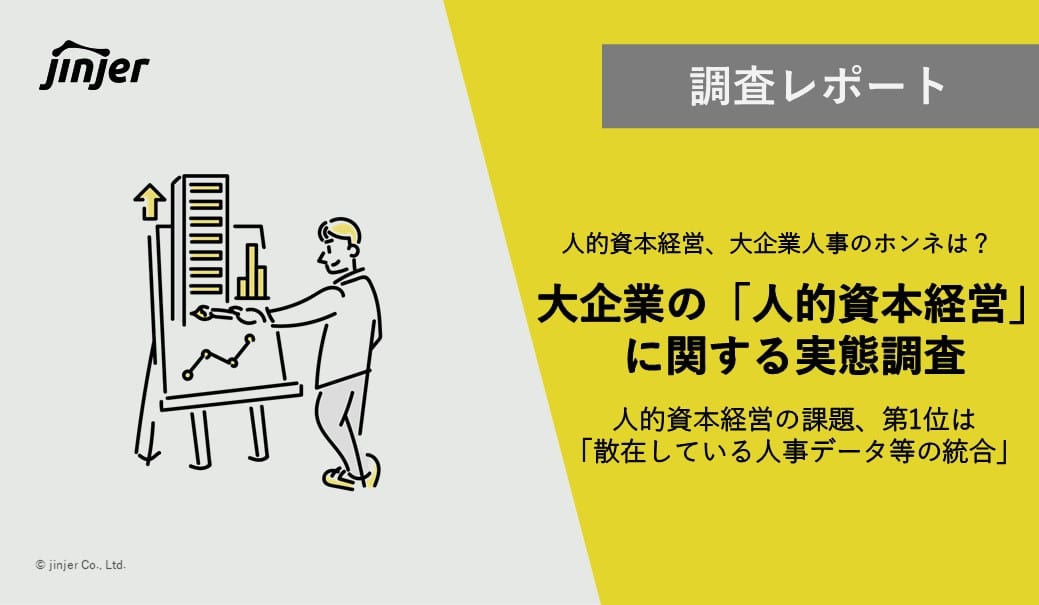
人的資本の情報開示が義務化されたことで人的資本経営への注目が高まっており、今後はより一層、人的資本への投資が必要になるでしょう。
こういった背景の一方で、「人的資本投資にはどんな効果があるのかわからない」「実際に人的資本経営を取り入れるために何をしたらいいの?」とお悩みの方も、多くいらっしゃるのが事実です。
そのような方に向けて、当サイトでは人的資本経営に関する実際調査の調査レポートを無料配布しています。
資料では、実際に人事担当者にインタビューした現状の人的資本経営のための取り組みから、現在抱えている課題までわかりやすくレポートしています。
自社運用の参考にしたいという方は、ぜひこちらから資料をダウンロードの上、お役立てください。
1. ハラスメントの現状|ハラスメントは増加している

ハラスメント相談窓口が義務化された背景には、以下の点が挙げられます。
- 職場のハラスメントに関する相談件数の増加
- ハラスメントを受けた従業員の精神的・肉体的な負担
労働施策総合推進法制定後も、労働局へのハラスメントに関する相談件数は年々増加傾向にあります。
厚生労働省の「職場におけるハラスメントの実態調査(令和5年度)」によると、過去3年間に相談があった事例のうち、「企業がハラスメントに該当すると判断した事例の有無」はセクハラが80.9%、パワハラが73.0%、妊娠・出産・育児休業等ハラスメントは50.1%といずれも高い数値であり、この事態の深刻さから、国は企業に対しハラスメントを未然に防ぐための取り組みを強く求めるようになりました。
ハラスメント相談窓口の設置は、職場のハラスメントを防止し、健全な労働環境を確保するための重要な措置といえるでしょう。
参考:職場のハラスメントに関する実態調査 結果概要|厚生労働省
2. ハラスメントの種類

近年は、カスタマーハラスメントやスメルハラスメントなどたくさんのハラスメントがありますが、企業で問題視されるハラスメントは主に下記の3種類が挙げられます。
- パワーハラスメント
- セクシャルハラスメント
- 妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメント
ここでは、これらのハラスメントについて解説していきます。
参考:職場におけるパワーハラスメント対策が事業主の義務になりました!|厚生労働省
2-1. パワーハラスメント
パワーハラスメントと定義されるのは、下記のような要素です。
- 優越的な関係を背景とした言動
- 業務上必要かつ相当な範囲を超えたもの
- 労働者の就業環境が害される
これら3つの要素すべてを満たす言動や行動があった場合、パワーハラスメントと認定されることがあります。
「優越的な関係を背景とした言動」とは、業務をおこなう従業員にとって、上司や先輩など拒否や抵抗できない関係性を背景におこなわれる言動です。「業務上必要かつ相当な範囲を超えたもの」とは、一般的な常識を基準として、業務上必要性のない言動や指示、または対応が相当ではないことを指します。
これらの行動や言動によって、従業員が精神的もしくは肉体的な苦痛を感じ、就業ができなくなるのが「労働者の就業環境が害される」に該当します。
2-2. セクシャルハラスメント
セクシャルハラスメントとは、1人の従業員の気持ちに反して、他の従業員が性的な言動を発したり行動をしたりすることで、その職場で働くことが難しくなってしまうことです。
「性的な言動」というのは、従業員個人の性的な関係を尋ねたり、自分の性的体験談を話したり、執拗に食事やデートに誘ったりすることが挙げられます。「性的な行動」とは、性的な関係を求めるだけでなく、理由もないのに従業員の身体を触ったり接触したりすること、性的な動画や画像を見せたりすることなども該当します。
ちなみに、性的な言動・行動というのは男性から女性に対するものだけでなく、女性から男性、同性であっても該当するということを覚えておきましょう。
2-3. 妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメント
妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメントとは、上司や同僚などが「育児休業すると周りに迷惑がかかる」「出産ぎりぎりまで働くべき」などの言動によって、育児休業の利用や妊娠・出産した従業員が働きづらくなる、仕事が続けづらい環境になってしまうことです。
また、配置転換や人事異動などが、妊娠や育児休業制度の利用と因果関係がある場合も、妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメントに該当します。
ただし、出産・育児をする従業員の安全性や働きやすさを配慮した配置転換や、業務上必要がある言動の場合はハラスメントには該当しません。
3. ハラスメントが起こりやすい企業の特徴

ハラスメントが起こりやすい企業の特徴として、コミュニケーション不足が挙げられます。
近年は、個人の意思が重視されるようになったため、飲み会やサークルなどへ参加しない従業員が増えています。また、人手不足による業務負担の増加で、雑談をしたり助け合ったりするという環境が減っている職場も多いようです。
従業員間でのコミュニケーションが取れていない場合、相手への理解や思いやりがなくなり、さまざまなハラスメントが引き起こされる可能性が高まります。
また、業務過多になったり業績が低下したりするとストレスが溜まり、ハラスメントをフラストレーションのはけ口にしてしまうことがあります。
このような特徴がある会社は、リスクチェックをおこなって早急にハラスメント対策を実施する必要があるといえるでしょう。
4. ハラスメント相談窓口の義務化とは

2020年6月に「労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律」略称「労働施策総合推進法」が施行され、ハラスメント相談窓口を設けることが企業の義務となりました。
労働施策総合推進法は「パワハラ防止法」とも呼ばれています。ハラスメント相談窓口の設置義務は、施行時は大企業のみを対象としていましたが、2022年4月から中小企業まで拡大されました。
企業は、従業員がハラスメントの被害に遭った際に相談できるよう、社内や社外に相談窓口を設けなければなりません。相談窓口を設置したことを、従業員に周知しておくことも義務に含まれます。
参考:労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律 | e-Gov 法令検索
5. ハラスメント相談窓口の種類

ハラスメント相談窓口の種類は、以下のとおりです。
- 社内の相談窓口
- 有料の外部相談窓口
- 無料の外部相談窓口
ここでは、これらの窓口について解説します。
5-1.社内の相談窓口
社内の相談窓口は、企業内で選任された担当者が対応する窓口で、人事部や総務部などに設置するケースが多く見られます。
担当者は男性社員1名と女性社員1名を設置し、上長には責任が明確になるよう課長もしくは部長レベルの人材を置くことが基本となります。社内の相談窓口なので、人員が不足している場合は、コンプライアンス相談窓口と一体化することも可能です。
社内相談窓口は、社内に設置されているため、従業員が気軽に相談しやすい点がメリットです。一方で、担当者が社内の人間というのは相談しにくいというデメリットがあり、そのせいで適切な対応が出来ない可能性があることを頭に入れておきましょう。
5-2. 有料の外部相談窓口
有料の相談窓口は、企業が社会保険労務士や法律事務所など外部の専門機関に委託し、設置する窓口です。
専門機関というのは、ハラスメントに関する専門知識を保有しているので、第三者として中立的かつ的確な立ち回りをしてくれます。また、従業員にとっては、社内の担当者に相談するよりも気軽に利用できますし、少々相談しづらいデリケートな内容でも話しやすくなるでしょう。
有料の相談窓口は、社内の相談窓口だけでは対応できない場合や、自社に相談窓口を設置できない場合に活用できます。ただしコストがかかるため、中小企業には利用ハードルが高い場合もあるでしょう。
5-3. 無料の外部相談窓口
無料の相談窓口というのは、厚生労働省が設置している「ハラスメント悩み相談室」や労働局の総合労働相談、労働基準監督署など行政が運営している窓口です。行政機関の窓口を利用すれば、企業が独自に相談窓口を設置しなくても、従業員に適切なサポートを提供できます。
ただし、無料の相談窓口は、あくまでも個人的な事案に対して相談できる公的窓口です。そのため、従業員個人が自由に使用する窓口であり、企業が外部ハラスメント相談窓口として利用することはできません。つまり、社内でハラスメントが起こっても把握できない可能性があります。
6. ハラスメント相談窓口の義務化にあたり企業が実施すべき措置

ハラスメント相談窓口の設置義務にあたり、企業が実施すべき措置は以下のとおりです。
- ハラスメントに関する企業の方針を明確にする
- 相談内容に応じて適切に対応できる体制を整える
- ハラスメントが発生した場合は迅速に対応する
ここでは、これらの措置について解説していきます。
6-1. ハラスメントに関する企業の方針を明確にする
ハラスメントは相談を受けた担当者の感情や、独自の見解で判断すれば良いというものではありません。
基本として、ハラスメントに関する企業の方針を決め、それに沿って対応する必要があります。そのため、企業は以下の方針を明確にし、管理監督者を含むすべての従業員に周知しなければなりません。
- ハラスメントに該当する行為
- ハラスメントをおこなってはならない旨の方針
ハラスメントにはある程度定義が決まっているものの、ケースごとに言動や行動が異なります。そのため、場当たり的な対応をしてしまうと、判断がばらばらになってしまいます。公平に判断するためにも、ハラスメントに該当する行為とハラスメントをした場合に会社が取る方針を明確にしておきましょう。
ハラスメント相談窓口があることを従業員に周知・啓発する
上記の方針をすべての従業員に周知することは、企業の義務です。周知することで、従業員のハラスメントに対する意識の向上と予防につながります。
周知の義務を怠ると、適切なハラスメント防止策をおこなっていないとみなされる可能性があるため注意が必要です。
また、職場の秩序が乱れ、ハラスメントが横行することも考えられます。ハラスメントが横行する職場環境は、従業員のモチベーションを下げ、結果として生産性が低下するリスクもあるでしょう。
就業規則などに明示し、従業員に周知・啓発することが重要です。行為者に対しては、厳正な対処をすることも記載しておきましょう。
6-2. 相談内容に応じて適切に対応できる体制を整える
企業は、従業員の相談内容に応じて適切に対応できる体制を整えておく必要があります。
相談窓口の担当者が、以下のような内容や状況に応じて臨機応変に対応できるようにしておきましょう。
- ハラスメントの相談が寄せられたときの対応
- ハラスメントが発生するおそれがある場合の対応
- ハラスメントに該当するのかどうか判断に迷う場合の対応
ハラスメントというのは、ケースによっては証明が難しいことがあります。そのため、確実に起こったハラスメントだけではなく、発生する恐れがある場合、判断に迷う場合にもしっかり対応しなければなりません。「証拠がないから対応できない」ではなく従業員の相談内容に耳を傾け、些細なことでも寛容に対応することが重要です。
6-3. ハラスメントが発生した場合は迅速に対応する
ハラスメントが発生した場合は、迅速な対応が求められます。
事案が発生してから、措置を検討すると対応が遅れるため、対応者や手順などを事前に明確にしておくことが大切です。
ハラスメント対応で優先しなければならないことは、ハラスメントの有無を明確にすることではありません。問題行動がただちに中止され、良好な職場環境を回復させることです。
「確たる証拠」を求めようとすると、その間にハラスメントが助長される恐れがあります。もちろん、一方の話だけで判断することは厳禁ですが、ハラスメント相談があったことを周知し、間接的に注意喚起をして問題行動を止めるようにしましょう。
7. ハラスメント相談を受けた場合の対応

ハラスメント相談を受けた場合の対応は、以下のとおりです。
- 被害者へ事実確認をヒアリングする
- 関係部署で対応策を検討する
- 相談者と行為者への対応・説明
- 再発防止の策定
ここでは、これらの対応について詳しく解説します。
7-1. 被害者へ事実確認をヒアリングする
まずは、被害者と行為者の双方から事実関係を確認します。ハラスメントの性質や実際の状況をみて、臨機応変に対応することが重要です。
例えば、パワーハラスメントで暴力などがおこなわれたり、セクシャルハラスメントで性的行為を強要したりするというような事案の場合、訴訟問題が起こる可能性があります。ここで対応を間違えてしまうと、会社の信用を落とすようなことになるので慎重に対応しましょう。
また、両者の主張が対立し、事実が不明瞭な場合は、第三者からも聴取するなどの措置をとる必要があります。片方だけの意見に耳を傾けるのではなく、中立な立場として公平な視点で調査を進めることが大切です。
7-2. 関係部署で対応策を検討する
被害者と行為者に事実確認をおこない、行為者がハラスメントを認めた場合は、ハラスメント窓口だけでなく人事部や被害者・行為者が所属する部署なども含め、対応策を検討しましょう。
この場合、関係部署で対応策を決めることが重要です。一部の部署だけで対応を決めてしまうと、忖度が働いてしまう可能性があります。特に、行為者が被害者よりも上位の地位にいる場合、被害者が納得できない対応になってしまうことが多いので、公平性を保てるようにしましょう。
ただし、被害者にも指導が必要な場合は、臆せずにしっかりとした対応を取ってください。
7-3. 相談者と行為者への対応・説明
ハラスメントが認められた場合は、状況や内容に応じて以下のような措置を被害者へ速やかにおこないましょう。
- 行為者との距離を離すための配置転換
- 行為者から被害者への謝罪
- 産業医などによるメンタルヘルス不調の相談
- 被害者の労働条件上の不利益の是正
悩みを抱えている相談者に対して対応が遅れてしまうと、企業への不信感から離職に繋がる可能性もあるので、問題の調査をしっかりとおこなった上で、迅速な対応を心がけましょう。また、ハラスメントが原因で被害者が休職した場合は、本人の希望に応じて復職へ向けた積極的な支援も必要です。
行為者に対しても、以下のような適切な措置をとる必要があります。
- 就業規則に明示した減給・降格・懲戒処分などの措置
- 被害者への謝罪
- 被害者と距離を離すための配置転換
ハラスメントの問題を軽く考えたり、話が広がることを避けるために内密に処理したりする行為は、問題をこじらせ解決を困難にするケースがあります。
企業は、ハラスメント問題に真摯に取り組み、公正なルールにもとづき判断することが重要です。行為者の言動がハラスメントに該当する理由や、どのような点が問題だったのかを根底から理解させることが求められます。
7-4. 再発防止の対策を実施する
ハラスメント問題が発生した場合、再発防止に向けての措置を改めて講じなければなりません。行為者は厳正に処分する方針などを、社内報やパンフレットなど資料にまとめて掲載し配布します。
企業内のハラスメントに対する意識を高めるために、研修や講習などを実施してもよいでしょう。
また、ハラスメントに関する相談があった場合は、事実確認ができなくても防止策を再検討し、必要に応じて改善することが望まれます。「相談だけだから」「確証がないから」といって放置してしまうと、防止することができません。
ハラスメントは「起こってから対処をすればいい」というものではなく、ハラスメントが起こらない職場を目指すことが重要です。
8. ハラスメント相談窓口を設置する際の注意点

ハラスメント相談窓口を設置する際の注意点は、以下のとおりです。
- ハラスメントの相談を理由に不利益となる扱いをしない
- 相談窓口担当者の教育とフォローを怠らない
- 相談内容が深刻な場合は産業医などの専門家に相談する
ここでは、これらの注意点について解説します。
8-1. ハラスメントの相談を理由に不利益となる扱いをしない
ハラスメントの相談を理由に、従業員が不利益となる扱いをしてはなりません。不利益となる扱いとは、以下のようなことが挙げられます。
- 解雇、退職願の提出の強要、労働契約の終了・更新拒否、本採用・再採用の拒否など
- 降格や不利益な配転・出向・転籍・長期出張等の命令、昇進・昇格における不利益な取扱い、懲戒処分など
- 減給その他給与・一時金・退職金等における不利益な取扱い、損害賠償請求など
- 事実上の嫌がらせなど
不利益な扱いをすることは、労働施策総合推進法、男女雇用機会均等法、育児・介護休業法によって禁止されています。そのため、扱いの内容によっては罰則が科せられることもあるので注意してください。
8-2.相談窓口担当者の教育とフォローを怠らない
ハラスメントの相談窓口というのは、事案によっては、担当者が直接対応しなければならないこともありますし、ハラスメントに関する知識や被害者と行為者へヒアリングをするスキルも求められます。そのため、相談窓口担当者には適切な研修を受けさせるなどの教育をおこなう必要があります。
また、ハラスメントの相談を受けるというのは、担当者の精神的にも大きな負担がかかる業務です。基本的に、ハラスメントというのはネガティブな内容となるため、聞き取りをする担当者にはストレスが溜まってしまう可能性もあります。
担当者のメンタルヘルスに不調が起こってしまうと、適切な対応ができなくなるので、上長などがしっかりフォローをしてストレスを溜め込ませないようにしましょう。
8-3. 相談内容が深刻な場合は産業医などの専門家に相談する
相談内容が深刻な場合は、窓口担当者だけで解決しようとせず、産業医などの専門家に相談することが大切です。
深刻な相談内容というのは、相談者がすでにメンタルヘルスの不調に陥っていたり、命の危険を感じたりしている場合などが挙げられます。
特に、ハラスメント相談窓口を企業内に設置する場合、いざというときにすぐに対応できるように、事前に産業医と対応方法を相談しておくことが重要です。
ハラスメント相談窓口設置の段階から産業医の意見を仰ぐなどの対応策を決めて、連携体制を整えておくことで問題の早期発見・解決につながります。
9. ハラスメント相談窓口を設置して働きやすい職場を目指そう

ハラスメント相談窓口設置は、企業の義務となっているので、社内もしくは外部に必ず窓口を設けましょう。
ただし、相談窓口は設置して終わりではありません。ハラスメントによる職場環境の悪化や人材流出を防げるよう、相談窓口の設置を従業員に周知し、適切な対応ができる体制を整えておくことが求められます。
また、ハラスメントの相談を受けた場合は、公正な立場から迅速に対応しなければなりません。場合によっては産業医などの専門家に相談し、問題の早期発見・解決に努めることが重要です。
企業は相談窓口の設置義務を遵守し、従業員が働きやすい職場環境の構築を目指しましょう。
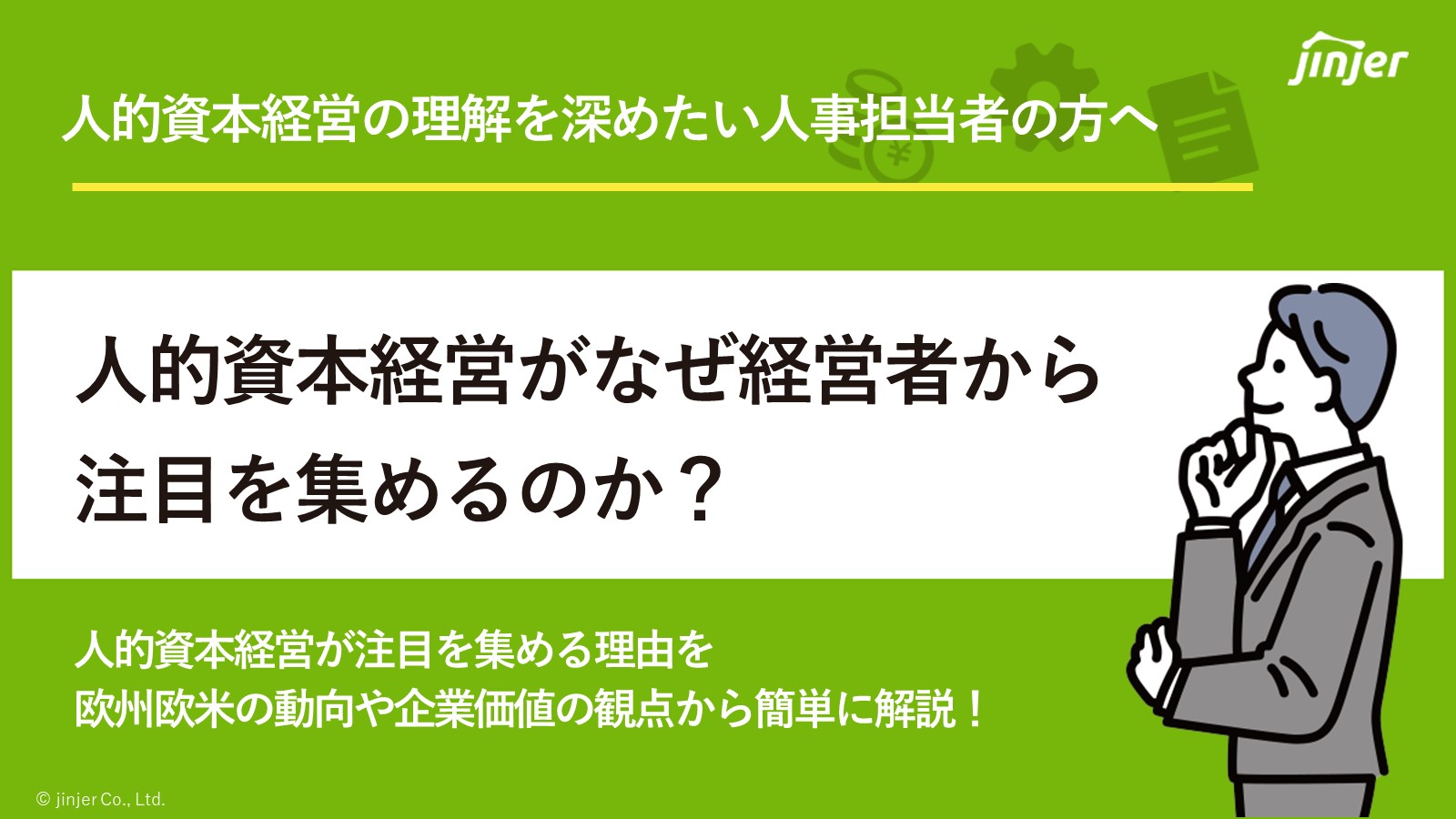
企業価値を持続的に向上させるため、いま経営者はじめ多くの企業から注目されている「人的資本経営」。
今後より一層、人的資本への投資が必要になることが想定される一方で、「そもそもなぜ人的資本経営が注目されているのか、その背景が知りたい」「人的資本投資でどんな効果が得られるのか知りたい」という方もいらっしゃるのではないでしょうか。
そのような方に向けて、当サイトでは「人的資本経営はなぜ経営者から注目を集めるのか?」というテーマで、人的資本経営が注目を集める理由を解説した資料を無料配布しています。
資料では、欧州欧米の動向や企業価値を高める観点から、人的資本経営が注目される理由を簡単に解説しています。「人的資本経営への理解を深めたい」という方は、ぜひこちらから資料をダウンロードの上、お役立てください。
人事・労務管理のピックアップ
-

【採用担当者必読】入社手続きのフロー完全マニュアルを公開
人事・労務管理公開日:2020.12.09更新日:2026.01.30
-

人事総務担当がおこなう退職手続きの流れや注意すべきトラブルとは
人事・労務管理公開日:2022.03.12更新日:2025.09.25
-

雇用契約を更新しない場合の正当な理由とは?伝え方・通知方法も紹介!
人事・労務管理公開日:2020.11.18更新日:2025.10.09
-


社会保険適用拡大とは?2024年10月の法改正や今後の動向、50人以下の企業の対応を解説
人事・労務管理公開日:2022.04.14更新日:2025.10.09
-


健康保険厚生年金保険被保険者資格取得届とは?手続きの流れや注意点
人事・労務管理公開日:2022.01.17更新日:2025.11.21
-


同一労働同一賃金で中小企業が受ける影響や対応しない場合のリスクを解説
人事・労務管理公開日:2022.01.22更新日:2025.08.26
労務の関連記事
-


年収の壁はどうなった?2025年最新動向と人事が押さえるポイント
勤怠・給与計算公開日:2025.11.20更新日:2025.11.17
-


2025年最新・年収の壁を一覧!人事がおさえたい社会保険・税金の基準まとめ
勤怠・給与計算公開日:2025.11.19更新日:2025.12.22
-


人事担当者必見!労働保険の対象・手続き・年度更新と計算方法をわかりやすく解説
人事・労務管理公開日:2025.09.05更新日:2026.01.30
























